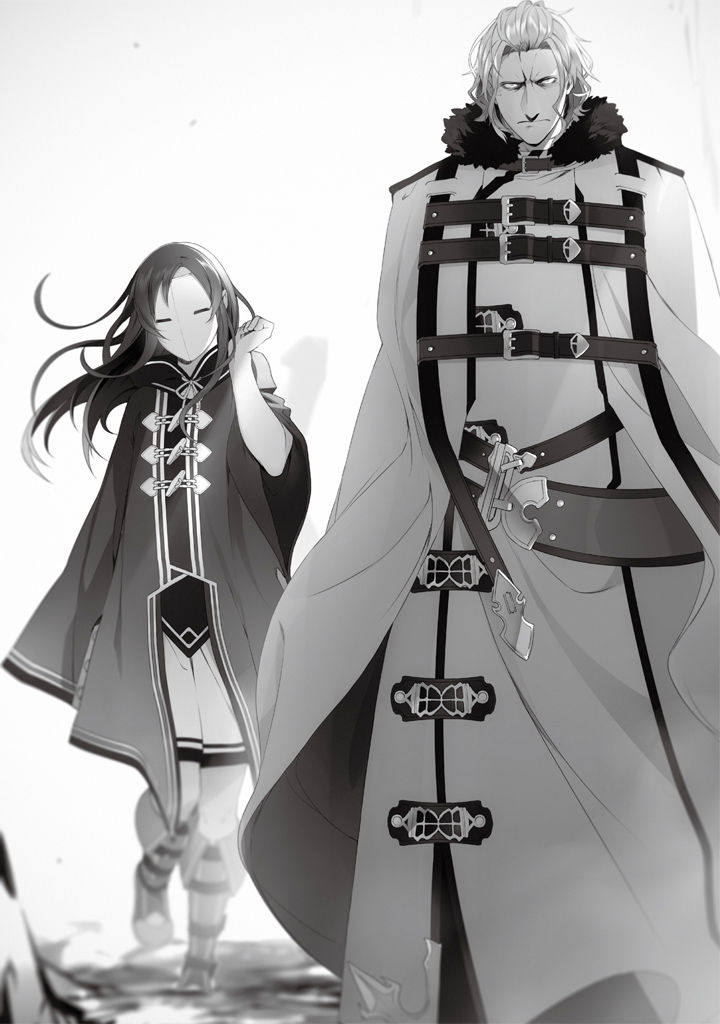制作信息
简介
简介
徐々に明らかになる家族の行方。やがて近づく仲間との別れ!?
パウロとの波乱の親子喧嘩を乗り越え、一路アスラ王国を目指す『デッドエンド』一行。
アスラ王国へのルート選択も決まったかに思えた矢先、人神から告げられたのは、侍女リーリャと異母妹アイシャがシーローン王国に抑留されているという情報だった?
真偽を確かめるべく向かった先で、ルーデウスが目にしたのは、リーリャの面影を持つ少女が泣き叫ぶ姿で……!?
やり直し型転生ファンタジー、急展開の第六弾!
目录
CONTENTS
第六章 少年期 帰郷編
「人が皆、自由に生きられるわけではない」
──The moment hope could be seen, it is the easiest to be thrust down into hell.
著:ルーデウス・グレイラット
译:ジーン・RF・マゴット
第一話 「ルート選択」
十二歳になった。
ふと冒険者カードを見た時、年齢の欄が十二になっていたのだ。
いったいいつ誕生日が過ぎたのだろうか。
旅をしていると、日付の感覚が狂いがちだ。
それにしても、転移から二年か。
二年で魔大陸とミリス大陸を踏破したと言えば早いものだが、逆に言えば二年も掛かっているともいえる。
二年も掛けて、ようやく中央大陸へと戻ってくることができたのだ。
だが、ここまで来ればアスラ王国は目前と言っても過言ではないだろう。
ミリス大陸での道中を考えるに、ここから先も苦労することはなさそうだ。
金もある、移動手段もある。懸念としては、家族の行方がわからないことだが……。
パウロが組織だって動いているのに、誰も見つかっていない。
ゼニス、リーリャ、アイシャ。それにシルフィ。
全員が生きていると信じてはいる。
だが、今更俺がやる気になったところで、そうそう見つかるものではないだろう。
ゆっくりと時間を掛けて探していくしかない。
★ ★ ★
現在位置は王竜王国の最東端、港町イーストポート。
ウェストポートと同じく、水産業者や輸送業者が幅をきかせている町である。
俺たちは宿を取り、作戦会議を開いた。いつも通り地図を囲んで三人で顔を突き合わせる。
「では、これからのことについて話しましょう」
二人は真面目な顔で地図を覗き込んでいる。
何度も繰り返していることで飽きがきそうなものだが、難しい話の苦手なエリスでも、この時だけは真剣な顔で聞いている。
「ここからアスラ王国へと向かうルートは三つあります」
と、俺は買ったばかりの地図を指さしつつ、説明する。
大まかな村の場所や森の位置が載っているだけの簡易的な地図である。詳しい地図を作ったり販売したりするのは、この国の法律で固く禁止されていた。他国に渡るのを恐れているのだろう。
まあ、大体がわかればいい。
「まず一つは、通常の交易に使われる街道を使うルートです」
と、俺は地図上の王竜山脈を東回りに迂回するルートを、指でなぞった。
「最も安全なルートですね。僕らの移動速度を考えると、到着まで一〇ヶ月程度でしょうか」
最も時間が掛かるが、整備された街道を通るため、最も安全である。
「なんで遠回りしないといけないのよ」
と、エリスが当然の疑問を投げかけてくる。彼女はいつだって当然の疑問を投げてくれる。
素直なので説明がしやすい。
「西回りのルートは、森が広がっているからです」
俺は王竜山脈の西側を指さし、その疑問に答える。
王竜山脈の西には、広大な密林地帯が広がっているため、馬車では通れない。
一応、道に詳しいのなら数ヶ月は移動時間を短縮できるそうだが、前提条件に乗馬の腕も入ってくる。俺とエリスは乗馬ができない。ルイジェルドは馬ぐらい乗れるだろうが、いくら俺たちが小さいとはいえ、一つの馬に三人で乗るのは無理だろう。
なので、このルートを通る場合は徒歩となる。
徒歩の場合にどれだけ日数が掛かるのかを調べることはできなかったが、その代わり、基本的に誰もが安全な東回りのルートを選ぶらしいことはわかった。
それほど日数に差はないか、あるいは東の方が早いのだろう。急がばまわれってやつだ。
ということをかいつまんで説明する。
「そう、じゃあ西はダメね」
エリスも納得してくれた。
「で、三つ目のルートなのですが」
最後のルートを指で示す。船でベガリット大陸へ渡り、捜索しつつアスラへと抜けるルートだが、こちらは何日かかるかわからない。
「もっとも、こちらのルートは却下です」
「なんでよ」
「危険だからです」
ベガリット大陸は魔大陸以上に魔力が濃いとされている。
平均で見れば魔物の強さは魔大陸と同程度だが、地下には大量の迷宮が存在しており、地上では異常気象が巻き起こる。
その風土は一言で説明できる。砂漠だ。あの大陸は砂で覆われているのだ。
さらに大王陸亀と同等の大きさを持つ巨大なサソリや、そのサソリを主食とするような巨大なワームが跋扈する。昼は灼熱、夜は極寒。オアシスの類はほとんどなく、休憩することはできない。また、さらに中央に進むと砂が消失し、なぜか雪が降り積もる極寒の地となる。砂漠から、いきなり氷に閉ざされた土地になるのだ。そこまで行くと、食える魔物はほとんど出てこなくなるとか。
そんな所を捜索しながら通り抜けるのは、現実的ではない。
「というわけで、我々は東回りのルートを通ります」
「ルーデウスは相変わらず臆病ね」
「怖がり屋なもので」
「私たちなら大丈夫だと思うけど?」
エリスはベガリット大陸にちょっと行ってみたいようだ。
目がキラキラしている。
だが、ベガリット大陸との距離は、ミリス──中央大陸間とは比べ物にならないほどある。
「長いこと船に乗りますけど、エリスは大丈夫なんですか?」
「…………ベガリットはなしね」
ということで、俺たちは東ルートを通ることとなった。
★ ★ ★
気づくと白い部屋にいた。
身体の奥底から湧き上がる情動。
何度体験してもなれないこの感覚を、一言で表そう。
クソが。
「いきなりクソなんて、相変わらず下品だね、君は」
モザイク。人神だ。
チッ、何が相変わらずだ。ようやく忘れかけてた頃に現れやがって。
「一年ぶりだね」
ああ、一年ぶりだ。ずいぶんと久しぶりだ。
もしかしてお前、一年に一度しか顔を出せないのか?
だとすりゃあ、俺としても心休まるんだがな。
「そんなことはないよ」
だろうな。最初の時は一週間も経たずに顔出したもんな。
「それにしても、君は相変わらず僕に冷たいね。僕のおかげで魔眼も手に入ったっていうのに」
いやまぁ、そりゃ感謝はしてる……けど、もっとうまいこと教えてくれりゃあ、牢屋に入ることもなかったし、情報のスレ違いでパウロと喧嘩することもなかったんじゃねえか?
ああ、くそ、さぞ面白かったんだろうな。俺が情報を得られずにパウロと仲たがいして、落ち込んで、慰めてもらって、なんとか話し合って仲直りするのを見るのはよ!
「そりゃもう楽しかったさ。でも、いいのかい?」
いい? なにがだよ。
「全部、僕のせいにして、さ」
チッ………………くそ。この部屋にいると、昔に戻るな。
何でもかんでも他人になすりつけていたあの頃に。
俺は反省したんだ。反省……ああ、くそ、どんな反省したのか思い出せねえ……。
なんでだよ、クソ……ちくしょう……。
「ま、それも君の味だよ。ちょっと反省したぐらいじゃ、ちっとも前に進めないのさ」
チッ、いいさ。今だけだ。目が覚めれば思い出せる。反省できる。
だから開き直らせてもらおう。開き直ってお前に聞くことにする。
「聞く? へえ、今回は珍しく助言を素直に聞くのかい?」
ああそうさ。けどな、俺の知りたい助言は一つだ。
「何かな? 僕が知っていることなら、答えてあげてもいいよ」
家族の居場所を教えてくれ。
「君の家族は異世界にいるんじゃあ、ないのかい?」
茶化すなよ、ゼニス、リーリャ、アイシャの三人だ。
できればシルフィとギレーヌ、フィリップとサウロスも頼む。
「んー」
なんだよ。人がこうやって頭下げて頼んでんだ。さっさと教えろよ。
「どうしよっかなぁ~」
なんでお前はそう上から目線なんだ?
人の人生を覗き見してるだけのデバガメ野郎の分際でよ。
お前はなにか? 自分に都合のいいことしか教えられないのか?
魔界大帝には会わせても、家族には会わせられないのか?
「あーあー、ごめんごめん。調子に乗ってたよ」
わかりゃいいんだよ。
「けどいいのかい? 今回、僕は嘘をつくかもしれないよ?」
へえ、嘘!
ようやくお前からそういう話が聞けたよ。そうだな、お前は嘘をつくタイプだよな。
「僕が嘘をつくかどうかじゃなくて、君は僕の言葉が信じられるのかって聞いているんだよ」
いや、信じねえよ。今は非常事態だからその通りには動いてやるけど、もし一度でも嘘をついたら、二度と助言は聞かねえよ?
「じゃあ約束してほしいんだ」
何をだよ。
「もし、次の助言で家族と再会することができたら、今後は僕のことを信じてほしいんだ」
…………お前を信じて、操り人形みたいになれってか?
お前の言うことをハイハイ聞いて、下僕みたいに仕えろってか?
「いいや、そこまでは言わないさ。ただ毎回毎回こうやって喧嘩腰ってのも、疲れるじゃないか」
別に喧嘩腰じゃなくたって疲れるんだよ。
お前にわかるか?
できれば忘れたい、直したいと思っている過去の感覚を引きずりだされて、反省した、成長したと思ってる記憶を薄れさせられて、朝起きた瞬間にすげぇ卑屈な気分になって凹む気持ちがよ。
「そりゃあ悪いことをしたね。じゃあ、ルールでも決めるかい? 次はこの日に助言する、とか」
ああ、それは名案だな!
次に現れるのは百年後ってのはどうだ?
「それじゃ、君が死んでるじゃないか」
二度と出てくんなつってんだよ。
「はぁ……まぁ、そう言うと思ったよ。で、いいのかい? 今回は、助言はなしで」
……いや、ちょいまった。
悪かった。俺も妥協しよう。もし、今回の助言でうまいこと家族の誰かと再会できたなら、俺も喧嘩腰でお前と話をするのはやめにする。
「信用してくれるのかい?」
いや、そこまでは行かない。だが、少なくとも、聞く聞かないの意味のない問答を繰り返すのはやめにしよう。
「前向きだね」
だからお前も妥協しろ。今回みたいに、いきなり顔を出すのはやめろ。
心の準備をさせろ。もしくは別の奴の夢に出て、そいつを通して手紙をよこせ。
「それは難しいね。夢に現れるのには、実は条件があるんだ」
条件? つまり、いつでも顔を出せるってわけじゃないってことか?
「そういうこと。夢に出るにも波長が合う相手じゃないとダメだからね。なかなかいないんだよ。僕の助言をタイミングよく受けられる人物ってのは。君は幸運だね」
ああ、幸せすぎて涙が出そうだぜ。この幸せをおすそ分けしてやりたいぐらいだ。
そこらのゴミムシあたりにでもよ。
……でも、ふうん、そうなのか。条件があるのか。
ちなみに、その条件ってのは?
「さぁ、僕もよくわかってないんだよ。ただ、あ、こいつはイケるな、この日はイケるな、って思ったらつながっているのさ」
へぇ。つまり、お前にもコントロールしきれてないってことか。
じゃあ、それは諦めよう。別のことにするか。そうだな……。もう少し、助言の内容を詳しくしてほしい。あっちにいけ、こっちに行けじゃあ、何をすればいいのかわからなくて混乱するんだ。
手のひらの上で遊ばれている感じもしてイラつくし。
「オッケー、詳細にね。わかった、それでいこう」
よし、じゃあ、頼む。
「ごほん。では、今回の助言を授けます」
次の瞬間、俺の魔眼に、ビジョンが流れこんできた。
[そこは、どこかの国の裏路地で]
[一人の少女が乱暴に手を掴まれていた]
[手を掴んでいるのは兵士]
[兵士は二人]
[手を掴んでいないほうは少女から取り上げた紙をビリビリに破いている]
[少女はそれを見て、何かを叫んでいた]
ビジョンはそこまでだった。
「ルーデウスよ。よくお聞きなさい。彼女の名はアイシャ・グレイラット。現在、シーローン王国にて抑留されています。あなたは今の場面に出くわし、助けることになるでしょう。しかし、決して名前を名乗ってはいけません。『デッドエンドの飼主』を名乗り、彼女に事情を聞いてください。それから、シーローンの王宮にいる知り合いへと手紙を出すのです。さすれば、リーリャ、アイシャの二人を、シーローン王宮から救い出すことができるでしょう」
えっ、ちょ、なに。いや、まった、なんで。
知り合い? 手紙?
「ちょっと詳細すぎたかな? あんまり詳しいと面白みに欠けるから、こんなもんかな。さて、君はどっちと仲良くなるかなぁ……」
え? リーリャとアイシャは二人ともシーローン王国にいるの?
なんで? そんなところにいるなら見つからないはずないじゃん。
仲良くなるってなんだ? リーリャとアイシャのどっちかと仲たがいするってことか?
「それではルーデウスよ。頑張りなさい……」
なさい……なさい……なさい……。
エコーを聞きながら、俺の意識は沈んでいった。
★ ★ ★
跳ね起きた。
「うっ……」
ガンガンと頭が痛む。圧倒的なめまい。そして吐き気。
俺はベッドを降りて、小走りで部屋の出口へと向かった。部屋を出てトイレに入り、便器を覗き込み、即座にゲーゲーと吐いた。
頭が痛い。凄まじい頭痛と吐き気で、足がフラフラする。
トイレから出るが、部屋が随分と遠く感じた。
壁に手を付くと足から力が抜け、ズルズルと床にへたり込んだ。
暗い宿屋に、ヒューヒューという音がする。
何だと目だけで周囲を見渡して、すぐに気づいた。俺の呼吸音だ。
「どうした、大丈夫か……?」
気づけば、真っ暗闇に白い顔が浮かんでいた。
ルイジェルドだ。彼は俺の顔を心配そうに見ている。
「ええ……大丈夫です」
「何を食った? 解毒は使えるか?」
ルイジェルドはポケットから布を取り出し、俺の口元を拭いてくれた。
自分の出した吐瀉物の匂いでさらに吐き気が強くなるが、吐くまでには至らず、胸にムカムカしたものが残った。
「大丈夫です……」
なんとか喉の奥から、そんな言葉を絞り出した。
「本当か?」
心配そうな声に、俺は頷く。
この頭痛には覚えがあった。ウェンポートで味わったことがある。
「ええ、寝ぼけて予見眼の調整に失敗しただけですから」
予見眼を使い、数秒以上先の未来を見た時、こんな頭痛がした。
あの時は、頭痛がした時点でそれ以上先の未来は見なかったが、あれが悪化するとこうなるのだと、直感的に理解できた。
なぜこんなことになっているのかも予想できる。
あの夢、あの助言だ。あそこで見せられたビジョン、あれのせいだ。
人神は俺に未来を見せた。恐らく、予見眼を通して。
「このためか……」
ぽつりと呟くと、ルイジェルドが怪訝そうな顔をする。
港町で魔界大帝に出会い、魔眼を手に入れた経緯を思い出す。
唐突に出会い、何のためか魔眼を手に入れた。
その後、ガルスと出会ったわけだが、魔眼自体は渡航するにはまったく意味のないモノだった。
魔眼のおかげでガルスに勝利できたのは確かだが、それにしたって、なくてもなんとかなったかもという感じはする。
俺にとっては大きな意味はなかったが、人神にとっては意味があったということだ。
ああやって俺に未来を見せるために、俺を魔界大帝に会わせたのかもしれない。
何かの準備が着々と整っている気がする。
不安が鎌首をもたげ、俺の中に初めて人神への恐怖が生まれた。
強大な力を持つ不定形の存在が、俺に何かをさせようとしている予感に、身震いした。
「ルーデウス、顔色が悪いぞ。本当に大丈夫なのか?」
ルイジェルドの心配そうな顔に、俺はそのまま自分の不安を吐露しそうになった。
実は俺はあなたと出会った頃から人神に監視されていて、奴の言いなりになって物事を進めているのです、と。
しかし、その瞬間、俺は一つの事実に気づいた。
『ルイジェルドと出会った頃から』
そうだ。人神が初めて俺に接触したのは、ルイジェルドと出会う直前だ。そして、奴はルイジェルドの手伝いをするようにと助言してきた。
おかしな話だ。
なぜ、今まで接触してこなかったのか。なぜ、魔力災害の直後に声を掛けてきたのか。なぜ、ルイジェルドを頼るだけでなく「助けろ」と助言したのか。
全てにつながりがある気がしてくる。奴が何かを企んでいるように思えてくる。
確証はなく、邪推の類であるが、そんな邪推の中でこんな考えが浮かんだ。
『人神はルイジェルドに何かをさせるつもりなのではないか』
人神は、夢に出るには条件があると言っていた。
その条件に引っかかり、直接ルイジェルドを操れない。だから、条件に合う俺を魔力災害で転移させ、ルイジェルドを助けるように誘導し、中央大陸まで護衛させたのではないか……。
いや。なら、俺に魔眼を与えたり、アイシャを助けるように助言する意味がわからない。
わからない。奴が何を考えているのかわからない……。
奴にとっては全てがつながっていることなのかもしれないが、俺にはそのつながりが見えない。
そして、人神のことをルイジェルドに言うべきか、否か。
迷った。
「……」
この不安を誰かに話して解消したかった。
だが、この男にこれ以上負担をかけるべきではないとも思った。
俺が人神のことをルイジェルドに話したことで何らかの条件が整い、人神がルイジェルドに接触できるようになるかもしれない。
実直なこの男は、きっと、あっさりと人神に騙されるだろう。
俺自身、騙されていないとは到底思えないが、少なくとも俺が喧嘩腰の態度をとることで、人神はやりにくそうにしている。
やりにくそうにしているうちは酷いことにはなっていない……と思いたい。
「ルイジェルドさん。もし辛い時、誰かから甘い言葉を囁かれても、決して信用しないでください。辛い時こそ、騙そうとしてくる奴は寄ってきますから」
結局、俺は言わなかった。人神のことを口にはしなかった。
「…………何の話かわからんが、了解した」
真面目な顔で頷くルイジェルドに、複雑な感情を抱いた。
彼は俺のことを信用してくれているのに、俺は隠し事をしている。隠しておいたほうがいいと判断したからだが、それでも心は晴れない。
気づけば頭痛と吐き気は収まっていた。だが、頭は別の意味でモヤモヤした。
部屋に戻り、ベッドに横になっても、眠れる気がしなかった。
冴える眼、考えの渦巻く頭。眼をつぶると、次々と思考が浮かんできた。
意味のある思考ではなかった。理論的な考えでもなかった。
出口のない迷路のように、益体もない考えが浮かんでは消えた。
「にゃによ……」
ふと、そんな寝言が聞こえて、目線を横へと動かした。
隣のベッドでエリスが大の字になって寝ていた。
相変わらず寝相が悪い。大きく足を広げて寝ている。
寝間着代わりにしている短パンから伸びる健康的な足。裾から奥が覗けそうな危うい隙間。
めくれた服と、そこから覗く可愛らしいおへそ。
真上を向いていても起伏がわかるようになってきた胸。
寝ている時はブラジャーをつけていないのか、目を凝らせば浮かび上がるぽっち。
そして、よだれを垂らしながらニマニマと笑う顔。
「んふふ……」
俺はそんな寝言に苦笑しつつ起き上がった。
彼女の服の裾を下ろし、毛布を掛けてやる。
「るーでうすはえっちね……」
だらしのない顔だ。
人があれこれと悩んでいるのに、こともあろうにエッチとは。
言葉通り胸でも揉んでやろうかなどと考えていると、急に眠気が戻ってきた。
俺はあくびをしつつ、ベッドに倒れこむ。
エリスはさすがだ……。
そう思った直後、俺はすぐに眠りに落ちた。
第二話 「米」
翌日。酒場にて朝食を取りつつ、俺は二人に宣言した。
「道中での捜索を短めに終わらせて、シーローン王国に立ち寄ります」
二人は、首をかしげつつも頷いた。
「わかったわ」
「了解した」
どうして、とか、なんで、などとは聞いてこない。
理由を聞かれないのは、俺としてもありがたい。人神のことはなるべく喋らない方向でいくと決めてはみたものの、人神のことを喋らずどうやって説明したものか、頭を悩ませていたのだ。
ルイジェルドは、昨晩の俺の様子を見て、何か思うところがあるようだ。
恐らく、隠し事をしていることに気づいているだろう。
病気を隠しているとか見当違いの方向かもしれないが。いや、人神は病魔のようなものだ、あながち間違ってはいない。
「シーローンってあそこよね、ルーデウスの師匠がいるっていう」
エリスのそんな言葉で、俺は一人の少女の姿を思い浮かべた。
ロキシー・ミグルディア。
そう。シーローンには彼女がいるはずだ。
人神も知り合いに手紙を出せと言っていた。
最初は「知り合いって誰だっけ」と思ったが、俺が手紙を出す相手と言えば一人しかいない。彼女に助力を願え、ということだろう。
人神もたまには粋な提案をする。
「はい。僕の尊敬する……先生です」
師匠です、と言おうとして言葉を変えた。
そういえば、師匠と呼ぶことは禁止されていたのだった。
最近は師匠が凄い、師匠が凄いといろんな人に言っていたが……まあいいか。
「そう、ルーデウスの尊敬する人なら、立ち寄って会っておくべきよね。何か力になってくれるかもしれないし」
エリスはそう言って、一人でうんうんと納得していた。
ロキシー。優秀な彼女なら、強い力になってくれる。それは間違いない。
とはいえ、ロキシーも宮廷魔術師だ。忙しいだろうから、あまり世話を掛けたくない。
ただでさえ、世話になりっぱなしだし、生徒として情けないところも見せたくない。
もっとも災害や捜索という建前を抜きにしても、会いたいという気持ちは変わらない。
魔族辞典のお礼も言いたい。あれがなければ、俺はまだ魔大陸にいたかもしれない。転移で失われてしまったのが悔やまれる。あれは写本して全世界にて販売すべきものだった。
「ルーデウスの先生、会ってみたいわね」
「ふむ、俺も興味があるな」
エリスとルイジェルドも興味を示したらしい。
旅の最中でも、時折ロキシーの名前を出して絶賛していたからだろうか。
ロキシーはどこに出しても恥ずかしくない自慢の先生だ。当然だろう。
「では、シーローン王国に到着したら紹介しますよ」
そんな約束をしつつ、俺たちは旅立った。
★ ★ ★
まずは街道沿いに進み、王竜王国の首都ワイバーンを経由する。
この首都から、王竜山を迂回するように道が分かれている。
まっすぐに北へと伸びていくルートと、西へと伸びていくルート。
俺たちは計画通り、シーローンへと通じる北ルートを選択する。
首都ワイバーンには、期せずして七日ほど滞在することになった。
当初の予定では三日ほどで発つ予定だったのだが、買ったばかりの馬車の調子が悪く、修理に時間を要したのだ。
石や鉄で作られたものなら俺でも多少は修理できるが、木材を魔力でどうこうすることはできない。修理工にはやや多めに金を渡し、早めに直してもらうことにした。
その期間が、七日程度だ。
焦りはない。
人神に見せられた光景では、アイシャが二人の男に絡まれていた。
心配はしているが、人神は俺があの場に居合わせると言っていた。
なら、あるいは馬車が壊れたこの事件は、運命操作的な何かの結果なのかもしれない。
恐らく、急ぎすぎても、あの場面には遭遇できないのだ。
心はなるべく平常心に。
そう思いつつ、首都ワイバーンを見て回った。
王竜王国はこの世界で三番目にでかい国だ。中央大陸南部の雄で、四つの属国を従えている。
かつては、この国も中央大陸南部に多数存在する国の一つだったが、北西にある王竜山の王者、王竜王カジャクトを倒し、その縄張りにある膨大な鉱物資源を手に入れたことで、一気に強国へとのし上がったらしい。
世界に散らばる四十八魔剣の発祥の地であり、北神英雄譚の一節にも語られる場所。
数々の逸話がありつつも、伝統をそれほど重要視している感じはせず、アメリカのような雑多な感じのする国だ。
また、この町には鍛冶場や剣術道場が多い。
流派はまちまちだが、北神流と水神流が多いように見える。
道場をチラリと覗いてみたが、子供相手に教えているところが多かった。
道場主ですら上級剣士というケースが多いようで、エリスは一目見ただけで大したことないわねと鼻で笑い、ルイジェルドにたしなめられていた。
さて、そんな町にて行方不明者に関する情報収集をする。
冒険者ギルドにはパウロの手先がいて、この国に大した情報がないことを教えてくれた。
やはり、もうこの時期になると、そうそう行方不明者が見つかるものではないらしい。
その後、いつも通りの市場調査だ。
ワイバーンは、中央大陸の特産物とミリス大陸の特産物の両方が売られている町だった。
その幅広い種類の食材が売られている市場で、俺はあるものを発見した。
米である。
やや黄色がかっているが、確かに米である。
無論、この国に米があることは知っていた。イーストポートでも白米を食った。
それでこの国の食事を楽しみにしていたのだが、残念なことに、この国の店で出てくるのはスプーンで食べやすいように作られたパエリアや粥ばかりだった。
俺の求めるものとは少々違う。
俺は白い飯が食いたい。そう願いつつも、叶いはしなかった。
だが、売られている米を見た瞬間、俺の中に電撃が走った。
何も悩むことなどはなかったのだ。
白米がないのなら、自分で作ればいいのだ。
そう考えた俺は、咄嗟に米を購入した。
数時間後、俺は宿の庭にて料理の準備をしていた。
購入した三合程度の米、土魔術で丁寧に作ったはんごう、かまど、店の人に教わったレシピに加え、塩と卵も用意した。
レシピを片手にはんごうで米を研ぎ、かまどに火を入れた。
米を炊くのに大切なのは火加減だ。
「何をしているのよ?」
真剣な顔ではんごうを火に掛けていると、エリスが寄ってきた。
「実験です」
「ふうん?」
エリスは興味なさそうに鼻息を吐くと、俺のすぐ脇で素振りを始めた。
チラチラとこちらを見ているところをみると、興味はあるらしい。
俺は酒場の主人に借りてきた砂時計をひっくり返し、火力を強める。少しずつ火力を上げるのがコツだと店の男は言っていた。それに従いつつ火力を上げていく。
砂時計を三回ほどひっくり返し、そこで火を弱める。更に砂時計を二回。
最後には火を止め、砂時計を二回。
「できた」
「ほんと?」
ぽつりと呟くと、エリスが素振りをやめて、俺のすぐ隣にしゃがみ込んだ。
ふわりとエリスの匂いが漂う。いい匂いだ。
だが、今は性欲より食欲だ。彼女はわくわくした表情ではんごうを見ている。俺もわくわくしながら、はんごうの蓋を開けた。
むわりと香るゴハンの匂い。
「いい匂いね。さすがルーデウスだわ」
「いや、まずは味を見てみないと」
俺はそう呟き、米を指でつまんで口に入れた。
「…………ふむ。四五点」
記憶にあるコシ○カリやササ○シキには遠く及ばない。
現代日本でランク付けをしたとしても、Cランクにも及ぶまい。
ボソボソとしていて、雑味が強い。色もやや黄色っぽい。俺の炊き方がヘタクソだったのもあるだろうが、素材も悪いのだ。やはりこの国は米が主食ではないからだろうか。銀シャリなどとはとても呼べない。
本当なら三〇点で赤点だが、米を食べていると懐かしさで胸が一杯になる。
それを加味して、一五点プラスだ。甘いね俺も。
「これって、前にも食べたわよね? どういう実験なの?」
「ここからが本番です」
俺は土魔術で作ったどんぶりにご飯を盛る。
そして、念入りに解毒魔術を掛けた卵を溶く、そしてご飯の真ん中に穴を開け投入。
その上から塩をパラパラとまぶす。土魔術で作った箸を構え、両手を合わせて。
「いただきます」
「え? ちょ、ルーデウス、その卵……生……」
大きく口を開けて、黄色く染まった米をバクリ。
うむ、生臭い。一応塩をかけてみたものの、あまり変化はないようだ。
しかし、こうして食べてみると、卵自体も若干ながら味が違う。日本で食える生食用の新鮮なものとは違うのだろう。あとで、解毒魔術を掛けておかないと危ないだろうな……。
あと、やはり醤油が必要だな。醤油がないと、どうにも生っぽさが際立ってしまう。
この世界に醤油はあるのだろうか。ないのであれば代用品を見つけたい……。
などと思いつつ、一心不乱に飯をかっこむ。
「ハムッ、ハフハフ、ハフッ!!」
「おいしいの?」
エリスの問いに、俺は土魔術で二つ目の丼をつくりだした。
そこにご飯をよそい、塩をパラパラとかけてエリスに突き出す。
ついでに、スプーンを作り、手渡す。まずは初心者用だ。
「……ねえ、これってこれだけなの?」
…………こくり。
俺は静かに頷いた。
ご飯はご飯だけで食べることができる。だからこそ主食なのだ。
自慢ではないが、生前の俺の全盛期には、山盛りご飯が主食で握り飯がオカズだった頃がある。
白米さえあれば、どれだけでも食べることができた時代だ。
「んー……」
エリスはもそもそと微妙そうな顔で食べていた。彼女はまだまだ子供だな。
だが、卵をかけると「うん、さっきよりはいいわね」と、頬をもちゅもちゅさせながら、食べきってしまった。
やはり卵かけご飯は最強だ。完全食だからな。
俺たちはそう言いつつご飯を完食し、最後におこげをパリパリと食って食事を終了した。
一人、卵かけご飯にありつけなかったルイジェルドは何の文句も言わなかった。
仲間はずれにされてもただ苦笑するだけだった彼は、実に大人だ思う。
だが、申し訳ないことをした。次回は彼にも食べさせてやろう。
★ ★ ★
王竜王国から出立し、街道を北上する。
シーローン王国にたどり着くまでにまたがっている国は二つ。
サナキア王国とキッカ王国。どちらも王竜王国の属国のような立場である国だ。
サナキア王国では米の栽培が盛んだった。
そういう風土なのか、街道を移動していると一面の水田があった。
この辺りは川が多く、気候も日本や東アジアに近いのかもしれない。
米は王竜王国で食べたものと同じだった。どうやら、ここで作られたものが王竜王国の市場に輸出されているらしい。なので、ここの米はサナキア米と呼ぶことにした。
宿の食事は魚介系の炊き込みご飯が多く出てきた。この世界では節制を心がけている俺であったが、やはり米の魅力には逆らえない。
今日もお腹は一杯。俺の一日はハッピーエンドである。
最近、食事時になると、エリスがたまにポカンとした眼で俺を見ている。
いつも食事時でもそれなりに小うるさい俺が黙って食べ続けているので、何か思うところがあるのかもしれない。
「どうしました?」
「ルーデウスって、あんまり食べないほうだと思ってたわ」
生前には小食なんて言われたことはない。あればあるだけ食べておかわりを要求するスタイルだった。この世界に来てから節制できていたのは、食生活が合わなかったからだ。
魔大陸における硬い肉中心の食事はさておき、アスラ王国におけるパン中心の食事も、少々もの足りないものだった。
ゼニスの料理が悪いわけではないが、米の味というのは俺の求めてやまないものなのだ。
うむ。やはり米はいい。
食の探求だけでなく、冒険者ギルドにも顔を出す。
さすが中央大陸というべきか。デッドエンドという名前を出しても、誰も驚きやしなかった。
しいて言うなれば、アメリカで有名だからって日本にまで名前が知れ渡っているわけではないという感じだろうか。スー○ーマンを知っていても、キャプテンア○リカを知らない子供が多いようなものだ。
とはいえ、彼らも冒険者だ。
デッドエンドという単語を聞いたことぐらいはあるだろう。ただ、外国の有名人が日本に来たところで、コアなファン以外は誰も騒がないってことだ。
スペルド族と知っても、それほど騒ぐ気配はない。
結局、大事なのは髪の色なのだろうか。
この世界の差別は、現代日本のオタクに通じるところがある。スペルド族は緑髪じゃなきゃスペルド族じゃない、陸上部女子は黒髪ポニテじゃなきゃ陸上部じゃない、ってなもんだ。
しかし、Aランクとなると、そこそこ注目されるらしい。
「よう、おめえら、見ない顔だな、Aランクたぁな。最近結成したのかい?」
俺たちに話しかけてきたのは、ノコパラによく似た雰囲気をもつ男だった。
経験上、こういう男とは仲良くしたくない。
けど、邪険にしたら絡まれて面倒なので、適当にあしらうに限る。
「結成したのは二年前ですよ」
「へぇ、ここらじゃ聞かねえな。『デッドエンド』。確か、魔大陸の悪魔の名前だっけか?」
「ええ、魔大陸から旅してきたもので」
「ヘヘッ、またまた。そっちの男がその悪魔かい?」
「そうですが、あまり彼のことを悪魔と言わないでくれませんか?」
「なんでだ? そういう触れ込みじゃねえのか?」
「騒ぎになるので髪は剃ってますけど、本物ですから」
またまた、と男は笑ったが、俺は真顔だったし、エリスは若干キレそうだったし、ルイジェルドも不快そうだ。
それを見て、男も冷や汗をかいていた。
「おい、まじなのか?」
「なんだったら、額の宝石も見せましょうか?」
「いや、いや、いい。悪かった。本物だとは思わなかった。いるとこにはいるんだな、スペルド族ってのは……」
魔大陸にいるうちにAランクに上がれたのは良かった。
ルイジェルドが本物のスペルド族だという信憑性につながっている。
中央大陸は魔族への風当たりが強いのに、なぜか魔大陸よりスペルド族を恐れてはいない。
危険が身近にあるかどうかってことだ。
羆を安全だなどと言う人は、実際に山で羆に遭遇したことのない人なのだ。
ネームバリューは使えなくなったが、しかし恐れられていないのであれば、人気回復の難易度も下がるだろう。先の見通しは明るい。
とはいえ、なかなかいい案が浮かばないのも確かだ。
ルイジェルドフィギュアも、ミリスの宗教圏にいるうちは受け取ってもらえないしな。
などと考えていると、エリスが先ほどの男を睨みつけていた。
「エリス。喧嘩はやめてくださいね」
「わかってるわよ」
「ならいいです」
エリスは最近、あまり絡まれなくなった。
彼女はこの一年ぐらいで物腰がかなり鋭くなって、素人臭さが抜けてきたのだろう。
パッと見ただけで危険だとわかる相手に、どうして絡む奴がいようか。
また、彼女自身も、冒険者流の冗談がなんとなくわかるようになってきたらしい。何かを言われても、それが前に聞いたことのあるようなフレーズだと気づけば、不機嫌な顔をしつつも、それに対応したフレーズで返すだけの余裕が出てきた。
それで相手が笑えば、エリスもドヤ顔で応じる。
冒険者らしくなってきた。
もっとも、売られた喧嘩を買わないというわけではない。
エリスが若いのにAランクと見て、わりと本気で絡んでくる奴もいるのだ。
そういうのは、Cランク程度の若い奴が多い。「実力もないのに、男に引っ張ってもらったんだろ?」というような感じで絡んできて、ワンパンで沈む。
そういう奴は、大抵どこの冒険者ギルドにもいるらしい。バカな奴らだ。
ちなみに、俺もよく絡まれるが「そーなんすよー、うちのダンナのおかげでウハウハっすよー」などと言って適当にあしらっている。プライドはない。実際、Aランクまで上がれたのはルイジェルドに頼った部分も大きいからな。
エリスは俺の態度が気に食わないようだが、一人でAランクになどなれなかっただろう。
謙虚になろうぜ。
キッカ王国では、アブラナのような植物の栽培が盛んだった。
街道からも、白っぽい花が一面に咲いている花畑が見える。
盛んなのは盛んだが、このアブラナの栽培は王竜王国がキッカ王国相手に強制してさせている事業だそうだ。サナキア王国で水田が盛んなのも、王竜王国の指示だとか。属国も大変だな。
ちなみに、この国でも米が主食だ。
食べ比べてわかったが、どうやら北にいくほど米の質が上がっているようだ。
これは、俺が一目惚れする米と出合う日も近いかもしれない。
だが、残念ながら、現在中央大陸の北のほうでは小国同士の小競り合いが続いている。
そんな状態ではおいしい米を作ることなどできないだろう。実に残念だ。
そういえば、この王竜王国からキッカ王国に至る界隈では、『ナナホシ焼き』と呼ばれる料理が流行していた。肉に麦粉や米粉で衣をつけて、高温の油で揚げる──要するに唐揚げだ。
最近になって、アスラ王国の方で開発されて大流行し、その煽りが流れてきたらしい。
食用油が大量に取れる国以外では作りにくいらしいが、この近隣の国は油の生産量が多いから、食べる機会が多くなった。
ちなみにこの唐揚げも、少々味が悪い。肉にしても羊や豚、馬だったりすることが多いし、油の温度が適切ではないのか、硬かったりベチャっとしていたりする。
下味もきちんとつけていない。もちろん、岩塩や乾燥ハーブ、この土地に伝わるソース等で味に変化をつけられてはいる。ゆえに、イーストポートで食ったモノほどまずくはない。
むしろ、よくできていると褒めてもいい。
食べる専門の俺でも工夫の程がわかるのだ。この国の料理人は頑張っている。
だが、俺の渇望する味とはやや違う。やはり醤油がないのがよくないのだ。
下味には醤油とにんにく、生姜などを使い、甘辛く仕上げねば……。
「ルーデウス、最近食事の時間に難しい顔してるわね」
「奴は味にうるさいからな。思うところがあるんだろう」
「十分おいしいと思うんだけど……」
テーブルを囲む二人はそう言いつつ、むしゃむしゃと食べている。
彼らは食に関してはうるさくない。俺だって、こんなところに来てまで美食な倶楽部の主宰者みたいなことは言わないけれど、あと少し、あと少し醤油味があればと思わざるをえない。
「でも不思議な食感よね、カリカリしてて、噛んだらジュワッって溢れてきて」
「ああ、うまいな」
おかわりを頼んでバクバクと食べる二人。
彼らは幸せだ。初めて食べた料理を、うまいと思って食べられるのだから。
俺はこれ以上の味を知っているがゆえ、素直に喜ぶことができない。
白米と醤油味の唐揚げ。そこに豆腐とワカメの味噌汁があれば、と渇望せざるをえないのだ。
飽くなき食への探求。もちろんその合間にも当然のように行方不明者の捜索をし、当然のように何の情報も得られない日々が続いていた。
そんな旅を続けつつ、四ヶ月。
俺たちはシーローン王国へとたどり着いた。
第三話 「シーローン王国」
シーローン王国は小国だが、二〇〇年程度の歴史を持つ古い国だ。
千年単位で歴史の動いているこの世界で二〇〇年というと、それほど古くないようにも思えるが、四〇〇年前の戦争において、人族の国はアスラ王国とミリス神聖国以外、全滅している。
中央大陸南部は豊かな土地だが、三〇〇年前に王竜王国が最南端の一帯を支配するまで、激しい紛争地域だった。今でも、北に行けば紛争地帯が広がっている。
シーローン王国は、そんな紛争地帯に近い場所にある国だ。
そんな場所で、シーローン王国がなぜ二〇〇年も国を保っていられたのか。
建国後、早い段階で王竜王国と同盟を結んだからだ。もっとも同盟とはいえ、国力の差は歴然としている。シーローン王国は、途中で立ち寄った二国同様、王竜王国の属国みたいなものだ。
とはいえ、正直そのへんに興味はない。
俺が興味があるのは、この国にロキシーがいるということだ。
あの幼くも……いや幼くはないんだっけか。
可愛らしく、ちょいドジな師匠は、まだこの国で宮廷魔術師をしているのだろうか。
王子に手を焼いているということだったが、きっとなんとか頑張っていることだろう。
久しぶりに会いたい。会って無事を伝えたい。ロキシーの故郷に行った話をしたい。王級の魔術というのも見せてもらいたい。
ワクワクとそう思いつつ、首都への道を移動していく。
街道沿いに続くのは、統一感のない田畑や放し飼いにされている家畜、あるいは休耕しているのかクローバーのような牧草の植えられた区画だ。
俺に農業に関する知識はないが、この世界の住人も、何も考えずに作物を作っているわけではないらしい。
ここも王竜王国の属国みたいなものだそうだが、途中で立ち寄った二国と違い、植民地のような印象は受けない。位置的に離れているためか、それとも紛争地帯の防波堤として役だっているためか、そのへんはよくわからない。
そんな風景を横目で見ながら移動して、シーローン王国王都ラタキアへとたどり着いた。
この世界では、主要な都市は大抵城壁に囲まれている。
ロアもミリシオンもそうだった。キッカ王国やサナキア王国でも、大きな町には城壁があった。
シーローン王国の首都ラタキアもまた、見るからにファンタジーといった感じの、頼もしい城壁に囲まれていた。
そういえば、城壁の存在は魔大陸でも変わらなかった。
むしろ、魔物の強い魔大陸の方が徹底していたと言える。
リカリスの町ほど巨大な自然防壁を持つ町はなかったが、それぞれの町では近くに住む各種族の特殊能力を使い、堅牢な壁を作って町を守っていた。
また小さな集落でも、村周辺の魔物駆除は日常的に行っていたようだ。
それにくらべれば、中央大陸の城壁は、あくまで格好をつけるためのものに思えてくる。
そんな城壁をくぐって町中に入り、いつも通り馬車を馬屋へと預ける。
この国の周辺には迷宮がやや多く存在しているためか、物腰の鋭い冒険者が多いな。
迷宮探索を主とする冒険者は数多く存在している。パウロやギレーヌもそうだったし、ロキシーも一時期は迷宮に潜っていたようだ。
迷宮探索者には凄腕が多いのだとパウロが言っていたような気がする。
シーローン周辺には迷宮が多い。
その一つでも最初に踏破できれば、莫大な資金が手元に転がり込んでくる。
そこらを歩いている冒険者の中にも、一攫千金を狙うSランク冒険者が何人もいるのだろう。
彼らに交じって大通りを移動し、適当な宿をとった。
いつもと同じ、Dランク冒険者向けの宿だ。
この町ではランクの高い冒険者が多いからか、低ランクの宿でも値段が少々割高だ。
とはいえ中央大陸の宿はDランク向けでも、魔大陸のDランク部屋より質が上である。
ゆえに、さらに部屋のグレードを落としてもいいのだが、値段を気にしなくていいぐらいの金は持っている。逆に言えば、もっと高いグレードの部屋をとることもできた。
かつては「もう少しいい部屋に泊まりたい」と思っていたものだったが、金に余裕があっても、もったいないと思ってしまう。
案外、俺は貧乏性なのかもしれない。
「さて、では、シーローン王国に到着しましたので、作戦会議を行います」
部屋にて待機する二人を前に、俺はいつも通り宣言する。
パチパチとおざなりな拍手は、すっかりと手馴れてきた証拠だろう。
「さて、では、何から決めましょうか……」
「ルーデウスの先生に会うのよね?」
エリスの言葉に、人神の言葉を思い出す。
『彼女の名はアイシャ・グレイラット。現在、シーローン王国にて抑留されています。あなたは今の場面に出くわし、助けることになるでしょう。しかし、決して名前を名乗ってはいけません。『デッドエンドの飼主』を名乗り、彼女に事情を聞いてください。それから、シーローンの王宮にいる知り合いへと手紙を出すのです。さすれば、リーリャ、アイシャの二人を、シーローン王宮から救い出すことができるでしょう』
そんな感じだったはずだ。
これを全面的に信用するのであれば……つまり俺は、夢で見た路地を探して歩きまわればいい。
エリスとルイジェルドは一緒に連れていくべきだろうか。
今回は一人で、とは指定されなかったから、三人で行くべきだろうか。
少し考えてみよう。
人神の言葉を信じるなら、リーリャとアイシャの二人はシーローン王宮に抑留されている。
でも、アイシャとは外で会う。ということは、彼女はどうやってか王宮から逃げ出してくるってことだ。夢で見たあの光景、そこに出てきた兵士二人。彼らの格好は町中でも何度か見たが、この国の正規兵の服装だ。
つまりアイシャは王宮の兵士に追いかけられ……しかし追いつかれるわけだ。
俺がそこにかち合う、と。
それを真正面から助けるとなると、王宮と真正面から事を構える形になる。
ゆえに、決して名前を名乗ってはいけないと言った。
ここで偽名を名乗る必要性が出てくると……顔も隠したほうがいいかもしれないな。
騎士たちが偽名の俺を探している間に、俺はシーローン王宮の知り合い──ロキシーに手紙を送り、助けを求める。ロキシーも宮廷魔術師なら、それなりに発言力はあるだろう。
きっと力になってくれるはずだ。
また世話になることになるな。本当にロキシーには足を向けて寝られない。逆に足を向けて寝てもらえれば、寝ている間にその足を綺麗に掃除してしまうだろう。
うん、簡単に考えれば、この助言はそういう流れだろう。
だが、人神のことだ、何か企んでいる可能性もある。
この助言の後に、『あんまり詳しいと面白みに欠ける』と発言していた。
つまり、奴にとって面白い出来事が起こるというわけだ。
恐らく、それは避けられないことだろう。とはいえ、奴は『次回は信用してほしい』と言っていた。
なら、多少きつい展開が待っていたとしても、俺が大怪我を負ったり、身内の誰かが死んだりするような事態にはならないと予想できる。
あくまで奴を信用するなら、だ。
今回、確実に騙すためにあんな嘘をついただけで、次回など考えていないかもしれない。
しかし、だからといって、無駄に逆らって事態が悪化したら目も当てられない。
また手のひらで弄ばれている感じがしてイヤだが、言うことを聞くしかあるまい。
何にせよ『アイシャを探す』、『名前を隠す』、『ロキシーに手紙を出す』、この三つは鉄板だろう。
しかしさて、どうやって二人を説得するか。
手紙はいいとして、路地裏を探す理由、名前を隠す理由、二つ同時に考えなきゃいけない。
ミリシオンを出立してからというもの、一日を休日に指定してもエリスかルイジェルドのどちらかが、必ず俺に付いてまわるようになった。
パウロの一件で俺が落ち込んでいたのが、よほど心に残っているらしい。
それだけ心配を掛けたということだ。申し訳ない。
とはいえ、今回は兵士と事を構える可能性が高いし、演技のヘタな二人を連れていくと、藪から野生の蛇が飛び出してきそうだ。スネークはどこにだって潜伏しているのだ。
さて、どうしたものか。
「ルーデウス、何を悩んでいるの?」
長時間言葉を止めた俺に、エリスが小首をかしげて聞いてくる。
ふむ……。案ずるより産むが易しというし、言ってみるか。
「実は、この町では名前を隠したいと思いまして」
「また演技をするの? どうして?」
「ええと……」
人神のことは伏せておくにしても、二人のことを伏せておく必要はないか。
「実はある筋からの情報なのですが、この国のどこかに、僕の家族が囚われているそうなのです」
「そうなの?」
「ほう」
どこで、誰から聞いたなどと、二人は聞かなかった。
そもそも、情報収集もこの二人のどちらかと行っていたのだが……。
まあ、突っ込んで聞かれないのは俺としても都合がいい。
「なるほど、グレイラットって名乗ったら警戒されるもんね!」
「そういうことです」
「で、誰がいるの?」
「リーリャとアイシャ……元メイドと妹ですね」
そういえば、俺から見てリーリャは何と呼べばいいのだろうか。継母ではないだろうし……。
「ルーデウスの妹? ミリシオンにもいたわよね、生意気そうなのが」
「もう一人いるんですよ」
「ふうん……」
エリスはつまらなさそうに口を尖らせた。
ノルンは生意気そうか。俺はそう思わなかったが、エリスにしてみればあの態度も生意気に見えるのだろうか。もし妹が殴られたら、俺はどっちの味方をするんだろう……。
「そういうことなら、文句はないわ! さすがルーデウスね、よく考えてる」
エリスはフフンと鼻を鳴らした。
考えているといっても、人神の甘言に乗っているだけなのだが。
「名前を隠すのよね。偽名を名乗るの?」
「よくある名前の方がいいだろうな」
「どうして?」
「偽名は憶えられないほうがいいときく」
悩ましく思う俺を尻目に、二人はあれこれと偽名を考えだした。
「このへんで有名な名前ってどういうのがあったかしら」
「旅の最中では、シャイナやレイダルという名前をよく聞いたな」
死神騎士シャイナは北神英雄譚に出てくる女騎士の名前だ。
北神三剣士の一人で、かつ北神の伴侶の一人。
どんな過酷な戦場からでも必ず帰還するという、異能○存体みたいな人物だ。
恐らくフィクションだろうが、ここいらの人々の間では、我が子が不慮の事故で死なないようにと、シャイナという名前をつけることが多いと聞く。
レイダルは水神だ。カウンターの天才で、海を凍らせながら足場を造り、海竜王を倒した英雄である。その偉大なる人物の名前をもらい、水神流の宗主は代々、男ならレイダル、女ならレイダを名乗る。こちらも、名前としては結構多い。
名前を隠すと言っただけで、二人はちゃんと考えてくれている。
ありがたい話だ。よし、俺も真剣に考えよう。
「ルーデウス、どうするの?」
「そうですね、この場合は、いっそ完全に偽名だとわかったほうがいいかもしれません」
「どうして?」
「僕らは顔も名前も知られていませんし、あえて派手な名前を名乗れば、目的がわからず、相手方も混乱するかもしれません」
と、昔どこかのアニメで見たようなことを言ってみる。
ぶっちゃけ、偽名なんてなんでもいいのだが……。
「じゃあ、カッコイイのがいいわね」
カッコイイのか。
「わかりましたよ、じゃあ僕は影月の騎士とでも名乗りますよ」
「シャドームーンナイト!?」
エリスが頬を染めて眼をキラキラさせていた。
とっさに出た名前だが、給食当番みたいな格好をしてキザったらしい川柳を吐く人物だ。
エリスだったら見た瞬間ぶん殴るんじゃなかろうか。
「私もそれにする! あ、でも同じだと困るわね、ええと……」
そんなに気に入ったのか。よし、じゃあナイツな名前を授けよう。
「では、エリスは影月の剣士と、それで、ルイジェルドが影月の槍士にしておけばいいですね。そうすればお揃いです」
「いいわね、お揃い! それでいきましょう」
ルイジェルドはそんなので恥ずかしくないのかと思ったが、まんざらでもないようだ。
パウロも『傲慢なる水竜王』をかっこいいとか言っていた。
この世界には中二病とかなさそうだ。
「でもルーデウスが騎士って感じじゃないわよね」
決まりかけてから、エリスがぽつりと呟いた。
騎士じゃないって。じゃあ俺は魔術師か司令官とでも名乗るか? ……まぁ実際に名乗るかどうかわからんし、なんでもいいんだが。
状況で判断して、ダメそうなら飼主と名乗ればいいわけだしな。
「では、偽名はそんな感じで」
「そうね、それからどうするの?」
「とりあえず、王宮にいるロキシーに手紙を出して……返事が来るまでは情報収集ですかね」
俺はそう宣言した。自由時間に探し回れば、例の場面に遭遇するだろう。
うまく事が運ぶように頑張るとしよう。
★ ★ ★
翌日。
市場で便箋と封筒を購入し、ロキシー宛の手紙を書く。
まずは時節の挨拶などを書きつつ、転移しても無事だったという旨を書く。それから、元気にやっていたので心配ない。とりあえずシーローンの首都まで来ているので会いたいと書く。
ブエナ村での面々が行方不明であることにさりげなく触れ、捜索中で誰も見つかっていなくて心配だと不安を煽り、それから、メイドのリーリャのことにさりげなく触れ、大事なことなのでもう一度家族が心配だと締めくくる。
さらに、それらの文面の頭文字に「助けてください」と縦読みを配置。
これだけ書いておけばロキシーでも気づいてくれるだろう。
これを蝋で封印をして、ロキシーペンダントの模様を形どった印鑑(自作)をペタリ。
差し出し名は偽名にしようか迷ったが、名前を見て「知らん誰そいつ」と捨てられたら困るし、実名にしておいた。
『貴方の生活を見守りたい愛弟子ルーデウス・グレイラットより』と。
おそらく偽名で書いても、ロキシーなら俺の字を見ただけでピンときてくれるだろうが、肝心なところでおっちょこちょいっと失敗するのがロキシーだ。手紙の行方はロキシーの手にわたってみるまでわからない。
シュレディンガーのロキシーだ。
拾ってくださいという箱に入ったロキシーが脳裏に思い浮かぶ。
おお、神よ、ダンボールは逆さにして隠れるものですぞ。
ま、それはともかく、中身を読んでもらえる可能性を高めるに越したことはない。
「では、手紙を出してきます」
「ああ」
「はい、いってらっしゃい」
エリスたちは満面の笑みで俺を見送った。
てっきり付いてくるものと思ったが、拍子抜けである。
「あれ? 二人はどうするんですか?」
「町でルーデウスの妹の情報を探ってみるつもりよ」
ああ、そういえば情報収集をするって言ってたか。
まあ情報は力だ、集めておいて損はないだろう。
むしろ、情報を集めずに事に当たろうとしていた自分の迂闊さに呆れる。
「僕も手紙を出したら、少し情報収集をしてみるつもりです」
そう言って、二人と別れた。
それから冒険者ギルドで手紙を出し、情報収集を開始したわけだが……。
数分後、俺は尾行されていることに気づいた。
最初はルイジェルドが俺を監視しているのかと思った。俺は一人にすると何かしら問題を起こすので、問題が起きた時のためにスタンバっているのかと。
しかし、この数ヶ月、ルイジェルドはわざわざ尾行などせず、俺と行動を共にしていた。
そもそも、ルイジェルドの尾行能力は極めて優秀だ。俺が気づけるわけもない。
今、俺の後ろにいる奴の尾行はお粗末だからルイジェルドではあるまい。
恐らくエリスでもないだろう。エリスは尾行がヘタだ。宿を出た時から気配がしていてもおかしくないし、彼女ならわざわざつけ回さず、無言で付いてくるだろう。尾行する理由も思いつかない。
では誰か。
この国において俺に恨みを持つ者……?
心当たりはない。なにせ、この国には昨日来たばかりだ。これから国と事を起こす可能性は高いが、今のところは誰にも迷惑をかけていない。
それとも、魔大陸でやらかした事件関係だろうか。
魔大陸からわざわざ俺たちを追ってきて、復讐しようというのだろうか。バカな。
でも、ザントポートの密輸組織の生き残りという可能性もある。偶然見かけた俺を、この機会に始末しようという腹づもりかもしれない。
もっとも、何の関係もない可能性も高いが。
曲がり角を曲がる際、チラリと後ろを見てみると、小さな影がサッと物陰に隠れるのが見えた。
子供だ。
何のために、などとは思わない。突発的にそういう遊びをする子供もいるだろう。
近所の子供が、なんとなく生意気そうな俺を悪人に見立てて尾行ごっこしているのかもしれない。あるいは孤児が俺のサイフをスリ取ろうと狙っているとか……。
どこかに隠れて、慌てて追っかけてきたところを「ワッ」と脅かしてやろうか……。
いや、この世界には小人族なんていう背の低い種族もいる。
油断は禁物だ。どこかで撒くことにしよう。
そう考えて、二つほど十字路を右折し、やや狭い路地へと入っていく。
「……ん?」
ふと、何か違和感を覚えた。
何かが喉元まで出かかっているような雰囲気。
「……」
だが、俺はさして気にせず、魔術で土壁を作った。俺の魔力によって三メートルほどの壁が唐突に地面からせり上がり、路地を袋小路へと変えた。
壁の向こうから、タタッと慌てて走ってくる音が聞こえた。
そして、力なく壁を叩く音。魔術や剣術を使い、壁を破ろうとする気配はない。
もしかするとエリスが追いかけてきたのかとも思っていたが、彼女ならこのぐらいの壁は飛び越えられる。
やはり近所の子供のイタズラだったのだろう。
俺は自分の考えに満足し、その場を後にした。
さて、子供を撒くために少々路地の奥まで来てしまった。大通りはどっちだったか。やや迷子気味だ。でもまあ、大きめの通りが見つかればすぐわかるだろう。
そう思いつつ、曲がりくねった路地を歩くのだが、思った方向に行けず、四苦八苦する。
この町は大通りですら曲がりくねっている。
碁盤目のミリシオンとは大違いだ。迷子属性のない俺ですら、今まさに迷子になろうとしている。
いざとなれば魔術を使って屋根の上にでも登ればいいのだが。
そういえば、人神に見せられた光景も、こんな路地だったか。
「あっ!」
と、そこで俺は先ほどの違和感に思い至った。
あれは違和感ではない。
既視感だ。
即座に踵を返し、曲がりくねった路地を走った。
ト型になった三叉路で迷いつつも、背後を振り返りつつ、先ほどの道を戻る。
「やだ、やめてぇ!」
少女の悲鳴が聞こえた。
俺の視界にも、自分で作り上げた土壁が見えた。
「返してよぉ!」
俺は土壁に手を当てると、魔力を集中した。
土魔術によって壁を操作して亀裂を入れ、同時に風魔術を使い、壁の中心に衝撃波を発生させると、ボゴンと大きな音がして土壁は粉々に砕け散った。
俺の視界にその光景が入ってくる。
一人の少女が乱暴に手を掴まれている。手を掴んでいるのは兵士。
兵士の数は二人。手を掴んでいないほうは少女から取り上げた紙をビリビリに破いていた。
「お父さんに出す手紙を破らないで!」
少女の叫びが響き渡る中、二人の兵士は唖然とした顔で俺の方を見ていた。
「な、何者だ……?」
少女。リーリャに似た面影を持ち、パウロによく似た茶髪をポニーテールにまとめ、ダボッとした小さなメイド服を着ている。普段は飄々として活発そうな印象を受けるだろうその顔は、クシャクシャに歪み、涙と鼻水で濡れていた。
それを見下ろす、下卑た顔をした兵士!
あ、いや、兵士二人は下卑た顔はしていなかった。どちらかというと、申し訳なさそうな顔だ。あくまで仕事でやっているだけで、本意ではないのかもしれない。
「何者だ! 名を名乗れ!」
「僕はその子の……」
兄と名乗ろうとして、思いとどまった。
名前を名乗ってはいけないんだったな。えっと。
「我が名は影月の騎士!」
「なにが騎士だ、どうみても魔術師ではないか」
「うぐっ……」
的確にツッコまれてしまった。
くそう。次回があったら、魔術師と名乗ることにしよう。
「いいか坊主。正義の味方ごっこをするのはいいが、おじさんたちはこれでも王宮の兵士なんだ。彼女が迷子になってたから、迎えに来ただけなんだよ」
挙句、ヤンチャな子供を見るような眼で、優しく諭された。この言葉には少々の嘘が混じっているのだろうが、脇の兵士も泣きじゃくるアイシャを見て、やや困った顔をしている。
悪い奴らではないのだろう。王宮に何かしら問題があってリーリャとアイシャが抑留されているのだとしても、末端の兵士まで悪いというわけではないのだ。
もしかすると、この兵士たちとは敵対してはいけないのではないだろうか。
戦うのではなく、話し合いで解決したほうがいいのではないだろうか。
「彼女の持っていた手紙を破いていたようですが?」
「あ~……あれは、まぁ、なんだ。いろいろあるんだよ、大人には」
そうだな、大人には色々あるよな……。
「あっ!」
と、その時アイシャが一瞬の隙を衝き、兵士の手を振り払った。
「だっ、だずげでください!」
まっすぐに俺の元へと走り、俺の後ろに隠れ、涙と鼻水で顔をぐしゃぐしゃにしたまま、すがりついてくる。
その顔と必死さを見れば、王国と敵対とか、どうでもいい気分になった。
「あ、あのびどだりが、ぶりやりあだぢのでがびぼやぶびで……」
何いってんだかわからないが、必死さだけは伝わってきた。
やめだやめだ。俺のようなアダルトな中年にはヤングな正義の味方ごっこはできん。
いつも通りやらせてもらおう。
「……ふん!」
唐突に手を上げ、無詠唱からの岩砲弾。
「むっ!」
騎士は唐突に飛来した岩砲弾を、咄嗟に抜き放った剣で脇へと逸らした。
うおお、反応はええ!
水神流か。やりにくいな。でも俺が使えるのは岩砲弾だけじゃない。この距離なら余裕だ。
ふふ、俺の岩砲弾を避けたのは、お前で四人目だぜ。
「無詠唱魔術だと!?」
「じゃあこいつ、もしや!?」
「応援を呼べ!」
「わかっ、うおおぉぉ!」
俺は駆け出そうとする兵士の足元に、落とし穴を設置した。没シュート。
同時に岩砲弾を連発しながらもう片方の兵士を牽制しつつ、アイシャに問いかける。
「逃げますよ、大丈夫ですか?」
「えぐっ、ぐすっ、うん……!」
アイシャは泣きじゃくりながらも、コクリと頷いた。
よしよし。あとはもう一人を気絶させて離脱するだけだな。
そう思った時だ。
ピイィィィ────!
唐突に鳥の鳴き声にも似た、甲高い音が響き渡った。
音は穴の底から響いていた。
笛だ。兵士が警笛を鳴らしたのだ。
そして、やや間を置いて遠くから、あるいはすぐ近くの路地から、次々と笛の音が響いてきた。
ピィィピッピッピィィ────!!
それぞれ、鳴らし方や響きが微妙に違う。
おそらく、音の響きで位置を伝え合っているのだ。俺の岩砲弾の手が止まるのを見て、兵士が口を開いた。
「この辺りの道は全て封鎖した! もうすぐここにも兵が来る。無駄な抵抗はやめて、その娘を離せ! 悪いようにはしない!」
「…………」
恐らく、すぐにでもここに兵士だか騎士だかが殺到するだろう。
だが、俺にはまだ手がある。
「アイシャ! 僕にしっかり捕まってください!」
「えっ!?」
「絶対に手を離してはいけませんよ!」
アイシャは戸惑いつつも、俺の腰のあたりに手を回し、ガシリと掴んでくる。
俺は左手で彼女の服を掴み、右手に魔力を集中させる。
自らの足元に、先端を平たくした土槍を発生させる。
その勢いで人間砲弾のように中空へとぶっとんだ。
「な、なにぃ!?」
「キャァァァァァァ!」
兵の狼狽する声とアイシャの悲鳴を聞きつつ、俺はその場から華麗に脱出した。
わはは、さらばだ明痴くん!
ちなみに、着地時に両足がボッキリ折れました。
もう二度とやらない。
第四話 「神の不在」
魔術でカタパルト脱出した後、アイシャはしばらく泣いていた。
エグエグと泣きながらガタガタと震えて、おしっこまで漏らしていた。
気持ちはわかる。俺だって強面の男に腕を掴まれて恫喝されたら、漏らしはしないまでも足をガクガクと震わせてしまうだろう。漏らしはしないまでも。
あの兵士二人は紳士的なほうだろうが、五~六歳の子供には少々刺激が強かったのだ。
年齢差というのは、小さい頃は顕著に表れる。
例えば、小中学生にとって高校生は妙に大人に見えるものだ。高校生が道端に立っているだけで、その高校生がとっぽい格好をしていなくても、妙に怖いものだ。
まして相手は二人。さぞ恐ろしかっただろう。
決して、すぐ近くで両足が折れる音を聞いたせいじゃないと思いたい。
すぐに治癒魔術で治したが、あれは痛かった。
現在、俺は彼女がおもらししたことには言及せず、粛々とパンツを洗濯している。
場所は宿屋である。帰ってきた時には、エリスもルイジェルドもいなかった。情報収集に赴くと言っていたので、帰るのは恐らく夜になるだろう。
さて、俺はここで、また不思議な体験をしている。
先ほど、アイシャのダボついた小さなメイド服を脱がせ、ぐっしょりと濡れたパンツを剥ぎ取り、彼女の未発達な小文字のIとその周辺を、即席オシボリで拭いてやり、俺が普段着としているシャツを着せてやった。
手元には洗濯用の木桶と石鹸、そして女児用のパンツである。
生前の俺であれば、このシチュエーションとアイテムに興奮状態に陥ったであろう。
考えても見てほしい。
すぐ近くのベッドに、おもらしをして泣きじゃくり、一度全裸に剥かれてから、だぼだぼの俺の服を着せられた幼女がいるのである。もちろんノーパンだ。
紳士なら、誰しもこんな状況に陥れば興奮してしまうだろう。
え? なぜパンツを履かせないのかって?
そりゃもちろん、履かせるパンツがないからだ。
エリスのパンツを履かせるわけにいかない。彼女のパンツにはノータッチ。それはこの『デッドエンド』における重要なルールの一つだ。いくら非常事態だったとしても、彼女のいない間に荷物をあさりパンツを取り出すなど……考えるだに恐ろしい。
ルールを破るとルイジェルドが助けてくれないし、魔眼を使って逃げればエリスは三日ぐらいは不機嫌になる。かといって無防備に殴られれば、三日ぐらい飯の味がわからなくなるほど顔が変形する。無論、三日も待たず治癒魔術で治すんだが……。
話を戻そう。
現在、俺の野獣が遠吠えを始めてもおかしくない状況だ。
しかし、俺の心は穏やかな湖面の如く静かであった。
興奮どころか、波一つ立っていない。明鏡止水だ。
不思議なことだ。
泣きじゃくるアイシャに「困った子だな」という感情は抱くというのに、それ以上の性的な興奮は覚えないのだ。知らないうちに聖人男性にでもなってしまったのだろうか。それとも、知らぬ間に俺はエリスの逆鱗に触れ、ポケットなモンスターを戦闘不能にされてしまったのだろうか。
俺はその時の恐怖を忘れるため、記憶に封印を施したのだろうか。
いや、まさか、そんな、大丈夫だよね、マイサン?
などと考えていると、あっという間に洗濯が終わった。
色気のない麻のパンツに、そこそこ高級そうな生地でできた小さなメイド服。
それらをアイシャに渡すと、いつしか泣きやんでいた彼女は、いそいそと着替え始めた。
俺はじっとそれを見るも、やはり興奮しない。
そういえば、ゼニスの生パイにも興奮しなかったな……この体は、家族には興奮しないのだろうか。生前では老若男女お構いなしだったが……。
生命とは不思議なものである。
★ ★ ★
「あたしはアイシャ・グレイラットといいます! どうもありがとうございました!」
アイシャはだぼついたメイド服姿でペコリと頭を下げた。
それに合わせて、ポニーテールもピコンと揺れた。
やはりポニテはいいな。エリスもたまにポニテにしているが、彼女のポニテは運動部女子という感じだ。アイシャのとはまた少し趣が違う。
アイシャはお人形さんみたいで大変かわいらしい。
目が充血しているので呪いの人形みたいだが。
彼女は顔を上げると、ずいっと一歩近づいてきた。近い。
「ナイトさまに助けてもらわなければ、連れ戻されているところでした!」
ナイトさまという単語を聞いて、
俺は彼女の前で『影月の騎士』と名乗ったことを思い出した。
背中に一筋の冷や汗が流れる。
エリスとの会話でのことで、ちょっと調子に乗りすぎてしまったかもしれない。この歳で痒いものを感じて転げまわったりはしないが、十年後ぐらいにこのことをネタに強請られたりするかもしれないと考えると、ちょっと後悔。
「本当にありがとうございました」
再度、アイシャは深々と頭を下げた。
彼女、いま何歳だったっけか、六歳かな? まだ幼いのに礼儀正しい子じゃないか。
「助けてもらった上、一つ図々しいお願いをしたいのですが!」
「おう」
図々しいなんて難しい言葉を知ってるんだな。
パウロの話でアイシャがリーリャから英才教育を受けていたのは知っているが、それにしても賢いなぁ。
「手紙を書く道具をください! あと冒険者ギルドの場所を教えてください! よろしくおねがいします!」
そう言って、ぺこりと頭を下げた。
人にものを頼むときの「お願いします」ができている。
うん、いい子だ。
「その二つだけでいいんですか? お金はあるんですか?」
「……お金は無いです!」
「手紙を書く道具も、手紙を届けてもらうのも、お金が必要だって、教わらなかったのですか?」
小さな頃からお金の大切さを学ばせるのは大事だ。
リーリャならそのへんも抜かりないかと思ったが、物心ついてから数年では、教えられることと教えられないこと、理解できることとできないことがあるんだろう。
「お母さんは、あたしみたいな子が上目遣いで「おとうさんにおてがみおくりたいの」って言えば、お金を払わなくてもなんとかしてくれるって教えてくれました」
あらやだリーリャさんたらお茶目さん。
自分の娘に何を教えてんだ……女としての武器の使い方か?
そう思うと、この喋り方や仕草も演技っぽく見えてくる。いや本当に、何を教えてるんだ。
「ずっとお父さんに連絡を取ろうとしてるんですけど、お城の人がダメって言って、手紙を出させてくれないんです!」
リーリャは抑留されていると聞いている。
手紙も出させてもらえないらしい。もしかして、わりと酷いことになっているんだろうか。
人神も「救い出す」なんて単語を使っていたから、もしかするとこれは、パウロにとって面白くないNTR展開かもしれない。
「お父さん以外に……その、他に頼れそうな人はいないんですか?」
「いません!」
「例えばそう、お母さんの知り合いの青い髪のお姉さんとか……そう、どこかにいるはずのお兄さんとか」
さりげなくそう言うと、アイシャは眉根を寄せた。
不愉快そうな顔だ。なんでだ。
「兄はいますけど……」
「いますけど?」
「頼りにはなりません」
なんでや! 今さっきあんたのことを華麗に助けたやないか!
「り、理由を聞いてもいいですか?」
「理由! いいですよ! お母さんは、兄のことを事細かに話してくれました」
「ほう」
「しかし、どれも信じられないことばかりです! 三歳で中級魔術が使えただとか、五歳で水聖級魔術師になっただとか。あげくの果てには、七歳で領主の娘の家庭教師ですよ? とてもじゃないけど、信じられないです! 絶対に嘘です!」
信じられないか。そうか。そうだろうな。
「でも、実際に会ってみると、いいお兄ちゃんかもしれないし……」
「ありえません!」
「な、なんで?」
「家には、お母さんが大事にしている小箱があるんです。触るな、中身を見るなというので、なぜかと聞いたのです。なんでも、兄の大切なものなのだからだそうです」
小箱……そういえばそんな話をパウロから聞いたような気もする。
「お母さんがいない時に、こっそり開けてみました。すると中に何が入ってたと思います!?」
「さ、さあ、なんだろう」
「パンツです。女物のパンツです。それも、サイズ的には結構小さい。あたしの計算によると、十四歳ぐらいの子のパンツです。ありえませんですよ。そんな歳の人なんて、あの家にはいませんでした。兄が実は姉という可能性も考えましたが、ちょっと大きい。該当する人物はただ一人。兄の家庭教師だった人物です。兄は、四、五歳という年齢で、明らかに年上な女性のパンツを後生大事にしていたのです」
計算て。
ちょ、ちょっとこの子、賢すぎやしませんか? え? まだ五歳か六歳ですよね?
なんか、こんな小さな子からこんな、すごいギャップが、あれぇ?
「でも、誤解という可能性もありますよね?」
「いいえ、さりげなくお母さんに裏を取りました。兄はその女性の水浴びを覗いたり、父と奥方様の情事を覗いたりと、やりたい放題だったみたいです。お母さんは隠しているようですが、間違いありません。兄は紛うことなき変態です!」
変態です! 変態です! 変態です! 紛うことなき変態です!
もひとつついでに変態です!
もうやめたげてよお、ルーデウスの精神力はゼロよお!
「そ、そうか、お兄さんは変態か。そりゃ大変だね、ハハハ……」
自業自得とはいえ、なんてこった……。
まさか、こんな……くそう。なるほど、こういうことか。だから人神は名前を名乗るなと言ったのか。今、心で理解できたよ。さすが人神さんだぜ。パネェ。
「ところで、ナイトさん、本当のお名前はなんていうんですか?」
「ナイショです。巷では『デッドエンドの飼主』と呼ばれていますがね」
キリっとした顔で答える。
お兄ちゃんだと伝えるのは、もう少し後にしたほうがいいだろう。変態扱いだしな。
「へぇ……カイヌシさんですか。カッコイイですね! やっぱり召喚術とか使えるんですか?」
「いいえ、二匹の凶暴な犬を使役できるだけですよ」
「そうなんですか、すごいですね!」
アイシャは目をキラキラさせて俺を見ていた。
子犬みたいだ。しかも騙されている子犬だ。ああ、ちょっと心が痛いぜ。
しかし、とりあえず結果オーライだ。
ここで俺が兄だと明かしていれば、アイシャは俺の言うことを聞かなかったかもしれない。
だが、この調子なら、カイヌシの言うことなら素直に聞いてくれそうだ。
正体を隠したままリーリャをカッコよく助ける。そうすれば、アイシャはカイヌシを尊敬の目で見てくるだろう。そして、後で俺がお兄ちゃんだと知れた時に評価が鰻登りという寸法だ。
「よし。では僕が君のお母さんを助け出してきます」
「えっ?」
そう宣言すると、アイシャはポカンとした目で俺を見ていた。
「で、でも」
「任せてください」
こうして、俺はアイシャと出会った。
最悪な印象を持たれているようだが、父親をぶん殴ったのを目の前で見られたノルンほどではない。
ロキシーのパンツを持っていたことを変態などと言っていたが、なに、彼女にもいずれわかる日が来る。人には縋るべき物が必要なときもあるんだってな。
しかし、この歳でパンツ=変態という認識があるのか。
性的な欲求と下着を結びつけるような年齢ではないし、そもそも性欲というものを理解しているのかどうかも怪しい年齢だというのに……。
誰かに何かを吹きこまれたのかな?
うちの妹に変なことを教える奴にはキツイお仕置きをしてやらないといけないな。
「ところでカイヌシさん」
「なんですか?」
「なんで私の名前、知ってたんですか!?」
その後、メイド服の端に「アイシャ」と書かれた刺繍を見つけるまで俺の必死な言い訳が続いたが、割愛しよう。
それから、しばらくアイシャと話をした。
アイシャからは、ここ二年のことを聞かせてもらった。舌足らずで説明不足だったが、大体のことは把握できた。
なんでも、彼女らはこの国の王宮に転移したらしい。
当然不審者として捕まったが、リーリャがあれこれと話をした結果、王宮に軟禁されるくだりとなったそうだ。その前後関係については、アイシャは理解できていないようだったが、手紙すら出させてもらえないのには、何かしら理由があるらしい。
リーリャも酷いことはされていないようだ。
体が目当てというわけではないらしい。
アイシャが知らないだけで、夜な夜な何かされている可能性もあるが、リーリャはいい歳だし、王宮に住む人物がわざわざ監禁して手篭めにするほどの美貌というわけでもないし、可能性は低いだろう。
怪しい人物であることには変わりないから、抑留されているのか……。
それにしては、少々おかしな部分もある。
転移から二年半。ずっと誤解を解くことができず、抑留されっぱなしだったのだろうか。
俺の知らない何らかの事情が関与しているのかもしれない。
ちなみに、アイシャはそんな状況において、パウロに助けを求める手紙を出そうとしたそうだ。しかし道に迷い、冒険者を追いかければギルドに行けると考えたんだと。それが俺だったんだと。まさか俺も、アイシャ側から接触してくるとは、思いもしなかったな。
アイシャの口からロキシーの名前は出てこなかった。彼女はリーリャを助けてはくれなかったのだろうか……いや、陰ながら助けてくれたからこそ、今の状況で済んでいる可能性もある。
何はともあれ、今はロキシーの返信待ちだ。人神は、手紙を送れと言った。なら、その結果でパズルのピースがハマるように、全ての疑問が氷解するだろう。
「へぇー、カイヌシさんは魔大陸から旅してきたんですね」
「ああ、フィットア領の転移事件に巻き込まれましてね」
また、アイシャは俺のことを聞きたがった。
「その前は何をしていたんですか?」
「家庭教師ですよ。貴族のお嬢さんに魔術を教える」
「そうなんですか、どこで教えていたんですか?」
「ロアですよ」
「じゃあうちの兄と一緒ですね! もしかしたら町中でスレ違ったりしてたかもしれませんね!」
「そ、そうですね、その可能性も微粒子レベルで存在するかな……」
それにしても、アイシャはリーリャからいろんなことを学んでいるようだ。
一般常識や礼儀作法、生活で役立つ知恵、メイドの極意、エトセトラ。
この幼さで理解できるのかと俺ですら不思議に思うのだが、少なくとも、俺に理解できる程度には説明できるようだ。話し方も歳相応とは思えない。あえて大人っぽく振る舞っているのかもしれないが、それにしても賢いのだ、この子は。マジで。
小さな頃から、教えられたことをスポンジのように吸収できる力がある。
将来的にはどうなるだろうか。俺は、兄としての威厳が保てるのだろうか。
「貴族のお嬢さんってことは、うちの兄の雇い主とも接点があったかもしれませんし、聞いたことはありませんか?」
「い、いや、寡聞にして、そのような人物のことは……」
「そうですかー。カイヌシさんから見た兄の印象を聞いておきたかったんですが」
「ええと、領主様のところのお嬢様が乱暴で手に負えないという噂しか聞いたことはないですね」
ここで自分の情報を流したい気持ちが芽生えたが、グッと我慢。
どのみち後でバレるんだ。その時に自作自演したなんて知られたら評価が下がるだろうからな。
その後、魔大陸のことをあれこれと聞かれたので、詳しく話した。
この年齢の子と何を話せばいいかと思っていたのだが、不思議と話題は尽きなかった。
アイシャの会話能力が高いせいかもしれない。
そう思いつつ、俺は純粋に、ほぼ初対面となる妹との会話を楽しんだ。
数時間後、アイシャは疲れたのか眠ってしまった。
エリスとルイジェルドは日が落ちきってから戻ってきた。
若干疲れた表情をした二人に事情を聞いてみると、裏町の方まで情報収集に出かけたら、色々あって喧嘩になったらしい。
また喧嘩だそうだ。
申し訳なさそうにする二人だが、いつものことだ。詳しくは聞くまい。
誰だって失敗はする。俺だってする。何かあったら助け合えばいい。
俺は町中でアイシャと出会ったことと、リーリャが城に捕らわれていることを話した。
どうやら色々キナ臭いらしいと。
あとついでに、名前を伏せていることも話しておく。
特にアイシャには俺の正体がルーデウスだと知られないようにと念を押す。
「どうしてそんな回りくどいことをするのよ?」
「どうやら、兄に対して間違った知識を教えこまれているようなので、カッコいいところを見せて、その認識を正そうかと」
「ふーん、私はそのままでもカッコイイと思うけど?」
「エリス……」
嬉しいこと言ってくれるじゃないのと『いい男』な笑みを浮かべる。
するとエリスはたじろいで一歩後ろに下がった。
「うっ……どうして褒めるとそういうニチャっとした顔するのよ!」
俺のキメ顔はニチャっとした顔らしい。
ちょっとショック。誰か新しい顔をください。
「でも、そういうことなら今から襲撃ね!」
「城攻めは久しぶりだな……」
エリスがやる気満々でそんなことを言い出した。
ルイジェルドまで槍を持ち上げていたため、俺は慌てて二人を止めた。
「いえ、とりあえずは手紙の返事を待ちましょう」
と言うと、エリスはつまらなさそうな顔をした。
相変わらず、彼女は暴れるのがお好きなようだ。
難しく考えるより、城に襲撃してリーリャを攫ったほうが確かに簡単だろうが、それでロキシーに迷惑をかけたら目も当てられないからな。
まずは細かい状況を確認しなくては。
けっしてロキシーに会いたいからとかいう理由ではないですよ。
などと考えつつ、その日が終わった。
★ ★ ★
翌日。そろそろ昼時という時刻になって、宿に騎士がやってきた。
昨日アイシャを捕まえようとしていたのと似た、しかしより高級そうな格好をした人物だ。
三人には部屋にいてもらい、宿のロビーにて単独で対応することにした。
「ルーデウス殿でございますか?」
「はい」
「自分はシーローン第七皇子親衛隊に所属しているジンジャー・ヨークと申します」
なぜ親衛隊が、と思わなくもないが、ロキシーは王子の家庭教師をしているという話だし、別におかしくはないか。
「これはどうもご丁寧に。ルーデウス・グレイラットです」
騎士は一人で、女だった。
彼女は俺の顔を見ても顔色一つ変えず、騎士風の挨拶で一礼した。
俺も貴族風の挨拶で返礼する。どういった挨拶を返せばいいのかは実はわかってないのだが、とにかく誠意が伝われば大丈夫だろう。
「ロキシー殿がお呼びです。王宮までご同行願えますか?」
先日の一件については、特に何も言われなかった。
特に顔を隠してはいなかったのだが、面は割れていないらしい。
「……」
同行しろと言われ、迷う。
アイシャをどうするべきか。彼女を連れていけば、兵士に攻撃したことがバレるだろう。
やはり、岩砲弾を放ったのは失敗だったかもしれない。
……よし、ここは、アイシャには留守番をしていてもらおう。
ロキシーに緩衝材になってもらって話をつけた上で、きちんと謝罪すればいいはずだ。
俺はそう決めると、アイシャに絶対に部屋から出るなと伝え、エリスとルイジェルドに彼女の護衛を頼んでおいた。
そして、ロキシーに会うための身だしなみチェック。
髪の乱れはない。服装はいつものローブでいいだろう。あ、そうだ、菓子折りとかも必要だろうか。ご無沙汰していた師匠に会うのに何を持っていけばいいのか。
と、そこで道具袋の端に、不人気ナンバーワンのルイジェルド人形を発見。
そういえば、以前手紙でロキシー人形が本人のところに届いたって書いてあった。
この人形を見せて、実は俺の作品でしたー、ってのも面白いかもしれない。
「随分と念入りね」
「久しぶりに師匠と会いますからね」
「……ちゃんと紹介してくれるのよね?」
「ええ、もちろん。事が終わった後にゆっくりと」
エリスとそんなやり取りをしつつ、準備完了。
「一人で大丈夫なのか?」
ルイジェルドのやや心配そうな声。
俺も一人になると問題を起こすことが多いから、心配する気持ちはわかる。
「問題ありません。何かあったら飛んで逃げてきますので」
もちろん、比喩表現だ。もう二度と両足を折るようなムチャはしないよ。
「カイヌシさん……」
「大丈夫です。任せておいてください」
不安そうなアイシャの頭をポンポンと撫でると、彼女は口元をキュっと結んで、頷いた。
よし、いい子だ。
騎士ジンジャーに連れられ、王宮への道を歩く。
馬車の行き交う大通りの隅を二人で、やや足早に。
大通りは曲がりくねっていて、時折馬車がすれ違えないほど狭い通路がある。
敵国に攻められた時の対策なのだろう。
生前の日本でも、美濃地方の町はこうして曲がりくねっていたと聞き及んでいる。
「……」
ジンジャーは寡黙な人物のようで、余計なことは一切喋らなかった。
ただ、何かを聞けば口を開いてくれたし、物腰は常に丁寧だった。
「よーし、次はこいつだ!」
ふと、威勢のいい声が聞こえたので、そちらを見てみる。
「こいつは元ワシャワ国の騎士! 戦闘用の奴隷だ! ちとばかし生意気だが、腕は立つ! 金貨三枚からだ!」
大通りに面した場所に、奴隷市場があった。
お立ち台のような一際高い台の上に、奴隷が並んでいる。
人族が三人と、ウサギの耳をした獣族が一人。
男二人、女二人。男も女も上半身は裸で、遠目からでも肌がテカっているのが見えた。見栄えを良くするため、油が塗られているのかもしれない。
あの獣族は、大森林から連れ去られてきたのだろうか。
助ける余裕も義理もないとはいえ、少々眉根が寄ってしまう。
眉根を寄せつつも、彼女の胸を見ていると股間の方が少々反応してしまう。
アイシャに反応しなかったので不思議に思っていたが、やはり俺もまだまだ現役のようだ。
奴隷の脇に立った商人があれこれと説明しているのが聞こえてくる。内容は聞き取れなかったが、おおかた奴隷の出自や能力といったセールスポイントを挙げているのだろう。
しばらくして、聴衆の方から声が上がり始める。オークション方式なのだ。
リーリャやアイシャも、運が悪ければあそこに並べられていたのかもしれない。
そう考えれば、今の状況は決して悪いものではないと言えるかもしれない。断言はできないが。
ふと見ると、ジンジャーは奴隷市場を見て眉をひそめていた。
彼女はこの国の治安を守る者だ。ああいうことを堂々とされるのは気に障るのかもしれない。
「奴隷市場というのは、もっと町の奥の方にあると思っていました」
これも話題の一つだろうと思って、言葉を投げかける。
他の町では奴隷市場というのは、もっと奥まったところにあった。
この世界では別に奴隷自体は悪事ではないそうだが、大通りに面したところで堂々とやっているのを見たのはこれが初めてだ。
「そうですね。ああした競りも、いつもはもっと奥の方で行われています」
憎々しげに何かを言うかと思えばジンジャーは平坦な声音で返してきた。
「今日は何かイベントデーだったりするんですかね」
「いいえ。先日、元々奴隷市場がある辺りで冒険者同士の喧嘩があったそうです。それで市場が使用できなくなったので、一時的にこちらに奴隷市場を移しました」
奴隷市場で喧嘩、か。
エリスとルイジェルドも、喧嘩を起こしてきたらしい。
つながりがありそうな気がしてならないが、言えばきっと藪蛇だろう。
「失礼」
唐突にジンジャーは俺の脇を掴み、持ち上げてくれた。
「どうぞ」
「あ、どうも」
どうやら、高いところから見せてくれるらしい。よく気がつく人だ。
顔は平凡で、決して美女という感じではないが、細かいところに気がつくなら、きっといいお婿さんをもらえるだろう。
「ロキシー殿も、人混みがあるとピョンピョンと飛び跳ねていました」
「そうなんですか」
「はい、しかしこうして持ち上げると複雑そうな顔をされました」
その光景が目に浮かぶ。
よく見えませんね、などといいつつピョンピョンと飛び跳ねるロキシー。それを見かねて善意で持ち上げるジンジャー。憮然として下ろしてくださいと言うロキシー。
「ロキシー先生を持ち上げたことがあるんですか?」
「はい、すぐに下ろせと怒られましたが」
やはりか。
「どこを掴んで、ですか?」
「どこと言われても、今のようにですが」
今の俺は、ちょうど脇の下あたりを持たれて、持ち上げられている。
「どんな感じでしたか?」
「ですから、複雑そうな顔をしてすぐに下ろせと」
俺が聞きたいのは、ロキシーの脇の下の感触についてなのだが……まあいい。
「下ろしてください。先を急ぎましょう」
特に面白いものもなかった。これから売られるであろう奴隷が鉄格子の中にいるだけだ。
さっさと先を急ごうと、王宮へと足を向ける。
「ロキシー先生は、王宮ではどんなことをしているんですか?」
共通の話題を見つけたと思った俺は、ジンジャーにそう訪ねてみる。
「普段は王子に勉強を教えていましたが、暇なときは兵士の演習に参加していました」
ロアにいた頃にロキシーから送られてきた手紙にも、そんなことが書いてあった気がする。
「確か、魔術師との戦いを想定した演習を行っていた、という話でしたか?」
手紙によると、乱戦の最中にロキシーが魔術を放ち、それを受け流すという訓練だ。
咄嗟に意識の外から放たれる魔術を受け流せるようになれば、戦場で九死に一生を得ることも難しくないのだとか。
「その通りです。我々は皆、水神流の中級剣士なのですが、ロキシー殿のおかげで咄嗟に魔術を掛けられても剣で受け流せるまでになりました」
なるほど、だから昨日の騎士は俺の岩砲弾を受け流せたのか。
木っ端な騎士にまで受け流されてちとショックだったが、ロキシーの教えの結果なら納得だ。
それから、しばらくロキシーについて話をした。
魔術の授業中にじゅうたんを焦がして真っ青になったロキシーを見て兵士みんなでほっこりしたことやら、食事に出てきたピーマンを、ロキシーが真っ青な顔で噛まずに飲み込んでいたことやら。
「ルーデウス殿の話も聞き及んでいます」
「ほう。な、なんて言ってました?」
「若くして無詠唱で魔術を操る天才だと」
「先生がそんなことを?」
「ロキシー殿はよく自慢していました。本当ならわたしが教えられるような存在ではなかった、と」
「でへへ、それは言いすぎですよぉ」
そんな会話をしているうちに、城へとたどり着いた。
なかなかに大きな城だが、リカリスのキシリス城やミリシオンのホワイトパレスほどではない。
エリスの実家と同じぐらいの大きさである。要するに、アスラの辺境領土とこの国は同じぐらいということだ。さすがアスラ王国はすごいね。
「……」
「お勤めご苦労様です!」
ジンジャーが門番に軽く会釈すると、門番が直立不動になった。
彼女は親衛隊とか言ってし、普通の兵士より偉いのだろうな。
「こちらです」
そのまままっすぐ進もうとすると、ジンジャーは横へとそれた。
城の周りをぐるりと回り、勝手口のようなところから中へと入る。
「申し訳ありません。正面門は貴族用なのです」
「そうですか」
勝手口の中は、兵士の詰所のような場所だった。
部屋の隅に長机が二つ並び、数名の兵士が座って、カードのようなものに興じていた。
彼らはジンジャーを見るとすぐに立ち上がり、直立不動の姿勢をとった。
「……」
「お勤めご苦労様です!」
ジンジャーは会釈を一つして、部屋の奥へと入っていく。
俺は彼らを横目で見ながら、彼女に続く。
「ジンジャーさんは、偉い人なんですね」
「騎士の中では十二番目ぐらいでしょうか……」
十二番目、高いのか低いのか判別しにくいな。
この国の騎士とて百人単位でいるだろうし、そう考えると低くはないだろうな。
「こちらです」
ジンジャーはどんどん奥へと入っていく。その足取りは、やや慎重になったように思う。
彼女は階段は上らず、廊下の突き当たり、最奥の部屋の前にて足を止めた。
ここがロキシーの部屋なのだろうか。随分と閑散とした場所だ。ロキシーらしいとも言えるが。
「……」
ジンジャーはふと俺の格好を見て、手を出す。
「失礼、杖と荷物をお預かりします」
「あ、はい」
ドアボーイの真似までしてくれるとは、親切だな。
ジンジャーは俺の荷物を受け取ると、コンコンとノック。
「ジンジャーです。ルーデウス殿をお連れしました」
「入れ」
返事は男の声だった。
俺がそのことを疑問に思う前に、ジンジャーはすぐに扉を開け、俺に中に入るように手で示した。
俺は促されるまま、部屋の中に入る。
「ほう……こいつがルーデウスか」
そこには、偉そうに座った男がいた。小さい樽みたいな男だ。
男は偉そうにふんぞり返っているが、背がやけに小さい。背だけでなく、手足も短い。
小人族と炭鉱族を合わせたような感じがする。だが、顔だけはやけにでかく、人族の成人男性のものだった。顔も俺にとっては親近感を覚える類の顔であり、イケメンとはいえない。
その両脇には二人のメイドの姿。見覚えのあるメイドと、ないメイド。
見覚えのないほうをメイドAとしよう。二十代後半ぐらいの普通の女だ。
メイドBはリーリャにそっくりな顔をしている。
ていうか、リーリャだ。
五年も経つと少々老けたように見える。お肌の曲がり角な時期が重なっていたことに加え、転移などというものに巻き込まれたのだから、仕方ないだろう。
「もごっ!?」
そして、彼女は椅子に座らされていた。
なぜか椅子ごとロープでぐるぐる巻きにされ、口には猿轡。
ロキシーの姿はどこにもない。
「えっ? なにこれ……」
俺は混乱しつつ、周囲を見渡した。
俺はここにロキシーがいて、事情を説明してくれるものだと思っていた。
「落とせ」
男の声で、俺の足元の床が消失した。
★ ★ ★
気づけば、俺は魔法陣の中にいた。
合図と同時に足元の床が崩され、落とし穴のように落とされたのだ。
そうとわかるのに、数秒の時間を要した。小さな部屋だ。六畳間ぐらいだろうか。
地面には魔法陣が描かれており、ぼんやりと光を放っている。
俺は咄嗟に魔術を使おうとした。
落とされたのだから上に戻らなければと、土槍で己の体を持ち上げようとした。
「…………あれ?」
しかし、魔術は発動しなかった。
もう一度、少し強めに魔力を込めて、足元に土柱を発生させようとするも、発動しない。
おかしい。魔力は確かに出ているはずなのに……。
いや、おかしくはないか。周囲を囲むこの魔法陣。これのせいだろう。
「結界……か」
魔法陣の縁の方に向かって手を伸ばしてみると、壁のようなものに触った。
ドンと殴りつけてみるが、ビクともしない。
出られない。が、危機感がやってこない。まだ状況に理解が追いついていない。
「ギャハハハハ! 無駄だ! 無駄だ! その魔法陣はロキシーを捕まえるために作らせた王級の結界だ! お前ごときではどうしようもないわ!」
先ほどの丸っこい男が、部屋の隅にある階段を降りてきた。
そして、俺の前で立ち止まると、ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべつつ、勝ち誇った感じでふんぞり返っている。
「あなたは?」
「余の名はパックス。パックス・シーローンだ!」
パックス。ああ、第七王子か。
それにしてもこの男、魔術の使えなくなる結界にロキシーを捕らえて、一体何をするつもりだったのだろうか。
いや、手紙には俺に似ていると書いてあった。
俺は紳士的な男だ。
なら、きっと紳士的な振る舞いをするに違いない。紳士的な狼藉を働くのだ。
「くくく、いい顔だな。ルーデウス・グレイラット」
俺の悔しげな顔を見たのか、男はニヤニヤと笑う。
俺はポーカーフェイスを作りつつ、深呼吸する。落ち着け。とにかく落ち着け。
「僕は罠にハメられたわけですか。わかりました。昨日兵士さんを攻撃したことは正式に謝罪しましょう。そのまえに、まずはロキシーを呼んでください。僕は彼女の元生徒です、身元の証明をしてもらいます。それから、弁護士を呼んでもらい、正式な裁判の後──」
「ロキシーはいない」
ロキシーがいない。
「なん……だと……」
その言葉に、俺は自分でも驚くほど衝撃を受けた。
ロキシーがいない。それはつまり神の不在を意味する。
神はいないのか。
いや、そんな馬鹿な。かの偉大なる数学者オイラーも神は存在すると言っていたではないか。エカチェリーナ二世の命を受け、見事に神の存在を証明してみせたではないか。
神はいる。俺もまた、神の存在は身をもって証明することができる。
「いや、神はいます」
「……なに? 神?」
パックスはポカンとした顔になった。
そうさ。神はいる。間違いなくな。いないというなら宗教戦争だ。ミリス教団だかなんだか知らんが、死にたい奴からかかってこい。勝てそうな奴だけ相手になってやる。
「ふん、神に祈るか。正しい選択だな。こんな状況ではもはや助かることもないだろうからな」
「そうですね」
さて、落ち着いてきたことだし冗談はそろそろ終わりにしよう。
「それで、先ほどの発言はこの国にロキシーがいないということでよろしいのですか?」
「そうだ! 貴様はロキシーをおびき寄せるための餌になるのだ!」
「ロキシーにパックリと咥えてもらえるなら、それは本望ですが……」
適当に返事をしつつ、考える。
つまりロキシーはこの国にいなくて。この人はロキシーを捕らえようとしている。
なんでだ? 何かをやらかしてロキシーが出奔したってことか?
考える俺に、パックスは次の言葉を言い放った。
「手紙を見て驚いたぞ。まさか、ロキシーの恋人がこの国に来ていようとはな!」
「えっ! ロキシーに恋人がいるんですか!」
まじで!
手紙にはそんなことは書いていなかったのに……。
「む? 貴様は違うのか?」
あ、俺がロキシーの恋人に間違われていたのか。
「滅相もない! そんな恐れ多い! 至るところの一切ない不肖の弟子でございます!」
俺はブンブンと首を振った。
本当は嬉しさの余り、クネクネしたい。トナカイの珍獣のようにクネクネしたい。メタルモンスターの中の人のようにクネクネしたい。
しかし、ぐっと我慢。
「ふん、恋人でなくとも、弟子ならばロキシーは来る」
「来るでしょうか」
「来るとも。リーリャでは餌として弱かったようだが、あれだけ褒めちぎっていたお前なら、ロキシーは来る! そして、来た時がロキシーの女としての最後だ。余の性奴隷として一生飼ってやる。五人は世継ぎを産ませてやる」
性奴隷云々の前に、第七王子に政権取れるのかってところが突っ込みどころだろうか。
あ、一つ疑問が。
「あの。一ついいですか?」
「なんだ。おお、そうだ。最初の一回はお前の目の前で犯してやろう! そして、お前の首をたたき落とした後、絶望の顔に染まるロキシーと二回目だ!」
随分と妄想たくましいな。
「僕はここに来るまで、リーリャの情報を一切聞かなかったのですが……。その、どうやってロキシーは僕が捕らわれていることを感知できるのでしょうか」
パックスはピタリと止まった。
「ふん、優秀なロキシーならば、どこからか聞きつけてくる!」
なるほど、ロキシーは優秀だからな。
俺が見つけられなかった情報でも見つけられるかもしれない。
けど、その確率は低いだろう。
「その、せめて情報を流すとか、そういうことをしたほうがいいのではないでしょうか」
ロキシーが犯されてほしいわけではない。
ないのだが、せめてそうしてくれれば、あるいはパウロがもうちょっと早くリーリャのことを知ることができるかもしれない。
「ふん、その手には乗らんぞ! 貴様らはアスラの上級貴族の庇護下にあるのだろう! リーリャやお前を捕らえたことを知られれば、ボレアスとかいうのが敵に回るのだろう?」
「まわる……のかな?」
んん? なにかおかしいな。まあ、俺が捕らえられたと知れれば、あるいはサウロス爺さんなら助けてくれるかもしれないが……。
でもなんでリーリャが関係してるんだ?
「リーリャも何度も手紙を出そうとしていたからな! 誰が助けなど呼ばせるものか!」
なぜ助けを呼ばせずにターゲットだけが釣れると思うのか。
ああそうか。こいつ馬鹿なのか。
「いや、情報も流さない、助けも呼ばせないだと、誰も来ないと思うのですが」
「フン! 現にお前はノコノコと現れたではないか!」
いや、その理屈はおかしい。
「大体、情報などロキシーに直接渡せばいいのだ!」
「渡せたんですか?」
「二年探し続けているが見つからん! だがいずれ見つかるだろう! あの女は目立つからな!」
目立つからって見つかるとは限らんと思うんだが……。
おかしいな、手紙には俺に似て優秀だって書いてあった気がしたんだが。
それとも、もしかして、ロキシーの俺への評価ってこんなもんなのか?
だとしたら凹む。
「ふふん、どうやら諦めたようだな。無詠唱魔術だかなんだか知らんが、所詮余の権力には勝てんということだ」
ふん、絶対に権力なんかに負けないんだから。キッ!
「おお、いい目だ。ゾクゾクするな。最後までその目をしていてくれよ? ああ、楽しみだ、楽しみだ。ロキシー、早くこないかなぁ……」
パックスは恋焦がれる少年のように言いながら、階段を上っていった。
来るわけねえだろ……。
「おい、誰がリーリャの猿轡をはずせと言った?」
「申し訳ありません、一言ぐらい話すかと思いまして」
「余計なことをするな!」
「お願いします殿下、私ならなんでもしますので、ルーデウス様だけは……!」
「うるさい、余は年増には用はないのだ!」
「ああっ!」
階上からそんな声と共に、パンと乾いた音が響いた。
天井が開いているので丸聞こえなのか。
てか、もしかして今、リーリャを叩いたのか?
「それにしても、アイシャはまだ見つからんのか!」
「現在捜索中です、殿下!」
「くっ、攫った奴の特徴は!?」
パックスの苛立つ声が聞こえてくる。
どうやら、昨日のことを話しているようだ。
しかしさて、困ったな。俺も顔は隠していなかったし、すぐにバレそうだ。
宿の場所は手紙に書いてあったし……。
だが、バレてもいいのか。宿にはルイジェルドとエリスがいる。ルイジェルドなら、ルイジェルドならなんとかしてくれるはずだ。オフェンスに定評のあるエリスもいることだし。
「報告によると、シャドームーンナイトと名乗る、筋骨隆々とした大男だそうです。高笑いをしながら屋根を飛び回る変態だと」
「そんな目立つ奴がなぜ捕まえられんのだ! クソッ、どいつもこいつも役立たずめ!」
「ハッ、申し訳ありません」
おおい! 兵士、兵士さん、ちゃんと報告しようぜ!
俺のどこが筋骨隆々だよ!
いや、でも実際のところ、善意なのかもしれないな。善意でアイシャを逃がそうとしてくれているのかもしれない。よさそうな人だったしな。
グッジョブ兵士。
「ですが、手紙はすでに破り捨てたと報告にございます」
「手紙など何度でも書けるだろうが!」
「子供の手紙では上級貴族も動きますまい。放っておかれては?」
「ダメだダメだ! 探せ。家族がどうなってもいいのか!」
「……クッ! 直ちに捜索隊を出します」
バタバタと走る音。
ジンジャーは家族を人質に取られているのか。
「ふん、リーリャはいつもの所に放り込んでおけ!」
「ハッ!」
「ルーデウス様! 必ず助けに!」
「黙れ! 行かせるわけがなかろうが!」
「ああっ!」
「ふん、お前もロキシーを知っているのだったな。あの小生意気な女の前で首を刎ねてやる!」
バシンと、もう一度乾いた音が響き、何かがズルズルと引きずられる音が聞こえる。
「ふん、ルーデウス! 貴様は絶対に出してやらんからな!」
そんな声に上を見ると、パックスのいやらしい笑みが見えた。彼は俺に一瞥をくれると、穴から見えない位置に移動する。
しばらくして、俺の落ちてきた穴にバタンと何かが載せられた。蓋をされたのだ。
魔法陣のボンヤリとした明かりと、シンとした静寂だけが残った。
「ふぅ……」
なんか呆然としてしまった。
リーリャが殴られ、怒るべきところなのだろうが、不思議と怒りが湧いてこない。
今のやり取りが、あまりに喜劇じみていたからだろうか。それとも、すでに人神にリーリャが助かることを聞かされているからだろうか。
あるいは、歪んでいるとはいえ、彼がロキシーを求めているからだろうか。
俺だってロキシーに見捨てられていれば、彼のようになっていたかもしれない。
いや、違うな。少し似てるからだ、生前の俺に。
だから怒りというより、戸惑いの方が大きいのだろう。
「さて……」
何にせよ、大まかな状況はわかった。
要するに、やっぱりリーリャはパックスに捕まっていたわけだ。
拘留する名目はなんでもいいのだろう。他国のスパイとか。
で、話を聞いているうちに、どうやらロキシーの関係者であると考えた王子は、一計を案じる。
リーリャを餌に、ロキシーに連絡を取り、おびき出そうとした。
グレイラットという名前が怖いから、あくまで極秘裏に。
アスラ王国に見つかってもリーリャは所詮メイドだし、いくらでも揉み消せるだろう。
ロキシーは見つからず、リーリャは長いこと抑留されるハメになる。
パウロに助けを求めるリーリャだが、当然ながら王子はそれを許さない。
そんな状況で、アイシャは城を脱出、手紙を届けようとしたが失敗。手紙は破かれてしまう。
不思議なのはその後、なぜか兵士は彼女の動きを助ける報告をしていることだ。単に王子が嫌いなのか、それとも何か別の理由があるのか……。ジンジャーは人質を取られているようだし、他の兵士も似たような感じになってるのかもしれない。
そんな状況の中、まんまと俺が蜘蛛の巣に掛かったわけだが、人神はロキシーに手紙を出せと言ったわけだし、こうやって俺が捕まるのは想定の範囲内というところか。
慌てることはない。
今のところは指示通りにやれている。
………………いや、まて。
俺は本当に指示通りやれていたのか?
例えば、兵士には影月の騎士と名乗った。
人神の助言はアイシャに『デッドエンドの飼主』と名乗ればいいのだと思った。
だが、本当は兵士にも飼主と名乗らなければいけなかったのではないか?
それだけじゃない。
手紙だってそうだ。てっきり、本名を『名乗らなければいい』と思っていたが、手紙の差出人にルーデウスと書かなければ、こうなることはなかったんじゃないのか? ただのロキシーの知り合いとして王子と対面すれば、もう少し穏便に話を進められたはずじゃないのか?
まずい、なんか失敗した気がしてきた。
いや、まだ、まだ大丈夫だよな? これぐらいは想定内だよな?
心配だ。
とりあえず、脱出ルートだけはこっそりと確保しておくことにするか。
第五話 「第三王子」
こんにちは。元ヒキニートのルーデウスです。
本日はシーローン王国の無料アパートへと来ています。
敷金礼金ゼロ。家賃ゼロ。零食昼寝付きのワンルーム。
建材は堅牢なる石材、ガッチリと硬く組まれています。
ちょっと日当たりが悪くて、ベッドが無いのが難点で、トイレは少々古めの垂れ流し型、長く暮らせば病気になること間違いなしですが、それを差し引いても家賃が安い!
なにしろ、タダですからね。
しかもなんと、安心のセキュリティ構造。
見てください、この堅牢な結界。なんとこの中にいると魔術を無効化し、外に出ることができなくなるんです!
Aランク冒険者である私が本気で殴ってもビクともしません。
いかに脱獄脱走の名人だったとしても、ここを出入りすることは容易ではないでしょう。
うん、まあそのネタは二回目だからいいとして。
出られない。誰か助けて。ルイジェルド早く助けに来て、ルスケテ!
と、囚われの桃姫さまのような感じに陥っています。
あれから丸一日、俺は結界の解除を試みた。
結果はというと、ひどいものであった。魔術が使えないということは俺にできることはほとんどないということ。見えない壁を叩いてみたり、床の魔法陣を擦ってみたり四メートル近くある天井に届かないかピョンピョン跳んでみたり。
やれることはやったが、何もできなかった。
せめて杖があれば天井を叩くぐらいはできたかもしれないが、荷物は全てジンジャーに預けてしまった。大したものを持ってきているわけではないが、何か使えるものもあったかもしれない。
魔術に関しては色々と試してみたが、どれも不発に終わった。
魔力が吸収されているなら、できる限り最大限の魔力で壊してやるぜ、などと少年漫画のように試してみもしたが、どうにかなるような気配はない。
魔力は出る、しかし、なぜか形にならない。
現象へと変化させることができない。できそうだが、できない。
なんというか、ライターが強風でつかない時と似ているのかもしれない。火花は出るし、ガスも出るのだが、しかし火はつかない。あるいは、火がついてもすぐに吹き消される感じだ。
王級の結界魔術と言っていたか。凄いものだ。
「……」
自力で出られないと認識した時点で、じわじわと焦燥感が湧いてきた。
いま俺は、いざというときに何もできない状況に置かれている。
例えば、運悪くここにロキシーが来たとして、彼女が俺を助けようと尽力してパックスのいいなりになったとしても、俺は彼女を助けることができない。
見捨ててくれと喚くだけだろう。
例えば、何かの拍子にエリスが捕まったとして、俺は彼女を助けることができない。その場合は、きっと俺を人質に取られてのことだろうから、ルイジェルドになんとかしてもらうしかない。
これまた、見捨ててくれと喚くだけだろう。
例えば、パックスの気が変わって、俺がいれば人質は十分だからと言って、リーリャを殺そうとしたら……やはり、喚くしかないだろう。
大丈夫だとは思いたいが、人神の助言を完全になぞれてはいない。
もしかすると、すでに助言から外れているのかもしれない。
人神のことだから、それも想定していそうだが。しかし、あの助言は、アイシャとリーリャが助かるとしか言っていない。その他の人物が助かるとは言っていない。
いや、俺の信用を得ようという助言だ。裏の意味で何かをもたせるとは思いにくい。
でも、だが、しかしと、イヤな考えがグルグルと回る。
くそっ。はやく脱出しないとな……。
あれこれと試している間にどれぐらいの時間が経過したのだろうか。
疲れた。久しぶりにこんなに魔力を使った気がする。
結界はびくともしない。
ロキシーを捕まえようという結界だもんな。そう簡単に解除できるわけがないか……。
「ふぅ……少し、休むか……」
時計もないし、太陽も見えないので、時間の感覚が曖昧だ。
腹が減った。先ほどからグウグウと腹が鳴っている。あの王子、もしかして飯のことを忘れてるんじゃないだろうな。
いや違うか。食事の量を減らし、ガリガリにやせ細った華奢リンみたいな身体にするつもりなのだ。その方が、ロキシーを連れてきた時に興奮するだろう。
一日に一食か。育ち盛りの身体を持つ身としては、少々辛いな。
どうしたもんか……。力任せでは脱出できない。少しひねったほうがいい。生前、牢屋に捕まった人物はどうやって脱出していたっけか。
例えばそう、病気や死んだフリ。
医者か治癒術師を入れるために、一時的に結界を解除するかもしれない。
いや、単に見殺しにされる可能性もあるな。人質は二人いるわけだし。
ハリウッドスターなら、門番が近寄ってきたところを鉄格子の間から手を伸ばし、一瞬で気絶させて鍵束を奪い取ったりするんだろうが、ここではできない。
……あと、どんな方法があったかな。
要は、ここから出てしまえばいいのだ。魔術さえ使えれば、どうにでもなるからな。
だからいっそ、恭順するふりをするのもいいかもしれない。
『実はロキシーのことは前々から気に入らなかったんですぜ兄貴、グヘヘ。実はロキシーの家族の居場所を知っていやしてね。父親と母親の目の前で、なーんてのはどうでゲスか?』
てな感じでいけば、引っかかるんじゃなかろうか。
あいつ馬鹿そうだし……いや、やめとこう。
いくら俺でも、ロキシーを悪く言うことはできない。
自身のプライドはいくらでも捨てるが、ロキシーを悪く言うことだけはできない。
────コツ……コツ……。
悩んでいる俺の耳に、ふと音が届いた。
足音である。
段々と近づいてくる。パックスが様子を見に来たのだろうか。
────コッ……。
足音が、ちょうど真上で止まった。
そして、足音はすぐに部屋を横切り、階段から聞こえてくるようになる。
「ほう、ジンジャーの言う通りだな」
階段を降りてきたのは見知らぬ男だった。
だが、恐らく王族であろうことは一目でわかった。
まず、服装が実に偉そうな感じである。黒を基調にしており、金色の刺繍がそこらに施され、一目で高いとわかる。年齢は二十歳ぐらいだろうか。顔はパックスにやや似ているがパックスよりもヒョロっとした印象を受ける。面長で、頬骨が浮かんでいて、メガネを付けている。
キューピッドの存在が科学的に証明された世界のニートがこんな顔をしていただろうか。
「シーローン王国第三王子、ザノバ・シーローンである」
やたらと渋い声で、そいつは言った。
第三王子てことは、パックスの兄貴か。
「どうもご丁寧に。ルーデウス・グレイラットです」
「うむ」
「本日は、どのようなご用件で?」
「うむ」
ザノバは大仰に頷くと、手に持った袋を掲げた。
どこかで見た袋だ。ていうか、俺のだ。
ザノバは袋を地面に置くと、慎重な手付きで、その中から一つのものを取り出した。
槍を構えた戦士の人形──ルイジェルド人形だ。
「この魔族の人形をどこで手に入れた?」
ザノバは人形を結界のすぐ外に置いて、そう質問してきた。
「言え。ジンジャーから、貴様が持ってきたと聞いておる」
詰問口調だった。
魔族の人形。あまり難しく考えずに持ってきたが、やはり魔族の人形はこの辺りでも邪神像になるのだろうか。ロキシー人形は魔族の特徴がない人形だが、ルイジェルドのは額に宝石があるから一目で魔族だとわかる。
なんと答えるべきか……少なくとも、俺が作ったとは言わないほうがいいだろう。
「……魔大陸を旅している時に、偶然入手したものです」
「ほう! やはり魔族の手によって作られたか! して、どこら辺りで手に入れた? 売っていた商人はどんなナリだった? 製作者は誰かわかるか!?」
なんかすごい食いつきがいい。目が輝いている。
「さ、さて、なにぶん、僕も一目見て気に入ったから購入しただけで詳しいことは……」
「なにぃ?」
ザノバの眼鏡がギラリと光った。
すげぇ威圧感だ。間違いない、これは人を殺したことのある奴の目だ。
「ああそうだ。その人形を売るときに、商人が言っていました。その人形を持っていれば、スペルド族に襲われても大丈夫。人形を見せてルイジェルドハコドモズキ、ルイジェルドハコドモズキという呪文を唱えるだけで、たちまちスペルド族は十年来の旧友のようにフレンドリーになり、馴れ馴れしく肩に手を回してヘイブラザーと言ってくるようになるとか」
「ほうほう! そんなことを! 他には!? 他には!?」
「えっと、無病息災で子宝に恵まれて、あ、あと剣術がうまくなるとか?」
「ええい、そういうことではない! 要するに、スペルド族と関わり深い者が作ったということなのだな!?」
そういうことになるのかな。
俺はルイジェルド一人しかスペルド族を知らないが。
それでも、関わり深いといえば、深いだろう。この世界では、スペルド族とはあまり関わりあいになりたくない人が多いようだしな。
「ふーむ、やはりこれは同じ製作者の可能性が高くなってきたな……」
ザノバはふむふむと言いつつ、人形を手に持って、グリグリと回して見ている。
それとトンと地面に置くと、また袋の中へと手を伸ばした。
はて、あれ以外に入れてるものといえば、緊急用の着替えとかだけだが……。
「では、この人形には見覚えがあるか?」
袋から出てきたのは、ロキシーのフィギュアだった。
ロキシー人形が床へと置かれ、ザノバがその前にどっかりと座り込む。
「この魔族の像は五年ほど前、市場で発見されたものだ……」
彼は顎に手をやり、慈しむ目で人形を見ている。
ルイジェルドフィギュアを布教させようとした時にわかったのだが、ミリス教団の影響下では、魔族の人形はご法度である。やはりそのことを糾弾するのだろうか。
怒っている感じはしないが。
「我が弟が発見したものでな、当時宮廷魔術師だったロキシーによく似ていると、手ずから市場で行商人から購入したものだという」
「……『当時』宮廷魔術師『だった』、ですか?」
「うん? そうだ。お前は知らないようだが、ロキシー・ミグルディアはすでにこの国にはいない。我が弟の性的嫌がらせに耐えかねて、出奔した」
いや、一応、パックスから聞いたんだがね。
そうか、セクハラで出奔したのか。
「具体的にはどんなセクハラを?」
「セク……? 下着を盗んだり、水浴びを覗いたりだな」
マジか。許せんな。そういう奴にはキツイお仕置きをすべきだ。
そうだな、例えばパソコンをバットで壊すとか。事あるごとに命を刈り取る形をしたパンチを放つお嬢様と一つ屋根の下で暮らさせるとか。全裸にして牢屋にぶちこんで冷水を浴びせるとか。
なんだったら、俺が直々にぶっとい土槍を明日に向かって撃ち込んでやってもいい。
カラーコーン並みのぶっといやつだ。
それにしてもまったく。ロキシーのパンツを盗むだとか、そんなことをしていいと思っているのだろうか……いやない。いいわけがない。許されざる行為だ。いくら王子といっても、やっていいことと悪いことがある。ロキシーが出奔して当然だ。
……あれ?
その論法でいくと、もしかして、ロキシーが俺の家庭教師をやめた理由って、俺のせい?
「そんなことより、この人形の話だ」
ザノバはそう言って、ロキシー人形の肩のあたりをツイっと撫でた。
そうだな、こういう鬱な話題は変えるべきだ。
そう思い、俺は真面目な顔で頷いた。
「余は人形には目がなくてな。世界各地の人形を集めているのだが……」
と、前置きをして、彼は語りだした。
「この人形だけは製作者も、どこで作られたのかもわからんのだ。岩を削り出して作られていることはわかるが、ドワーフの使う石細工の材質よりも硬く、重い。この硬度の石をここまで精巧に削り出す技術は、今の世には存在しない……。例えばだ……見ろ、この杖の部分を。器用なドワーフであっても、硬い石材をここまで細く削り出すのは至難の業だろう」
ザノバはそう言って、人形の持つ杖を指さした。
杖などの細い部分は折れやすい。
その欠点を補うため、かなり試行錯誤した。
そのかいあって、高い剛性と靭性を得ている。
ルイジェルド人形の槍の柄の部分も同じ材質であるが、しかしこの部分は作るのにかなりの魔力と集中力、そして時間を要する。具体的に言うと、一センチ作るのに丸一日かかる。
その甲斐あって、俺の製造技術の結晶ともいえるような折れず曲がらないものに仕上がった。
工夫した部分の一つだから、褒められると嬉しいね。
「こんな素晴らしいものが、アスラ金貨にして五枚程度で売っていたというのだ。余ならアスラ金貨一〇〇枚は出すところだ。市井に住む者はまったく目利きのできん無骨ものばかりで困る。もっとも、安いのは魔族の像であるということを考慮しての値段だろう。こんな像を持っているところをミリス教団の神殿騎士団に知られれば、シーローンの王子であっても異端審問に掛けられ、魔神崇拝者の一人として殺されるであろうからな。安値で投げ売りにすれば、いくらでも言い訳ができる」
ザノバは額を押さえ、やれやれと肩をすくめた。
殺されるのか……神殿騎士団は狂信者ばかりだそうだしな。
「だが、余はかねてよりこの像の製作者を探しておった。魔神崇拝者とは関わりあいになりたくはないが、しかし、この像を作ったものとは話をしてみたいとな。そんな折、リーリャがいきなり余の部屋に現れた。ロキシーが出奔した翌日であった」
ふむ。偶然すれ違いになってしまっていたのか。
「リーリャは兵に捕らわれ、色々あってパックスが管理することとなったのだが、リーリャの持ち物にこんなものがあった」
ザノバはそう言いつつ、袋より小さな箱を取り出した。拳大の見覚えのない箱である。
「なぜこんなものを大事そうに持ち歩いていたのか不思議でならんのだが、よく見るがいい」
ザノバは俺によく見えるように箱を開けた。
柔らかそうな布に包まれたそれを取り出すと、ザノバは丁寧に布を開いていく。
中に入っていたのは、木彫りのペンダントだった。
どこかで見たことのあるような木だ。
当然ながら手彫りで、作り手の不器用さが伝わってくる。
「そのペンダントが……何か?」
「うむ、このペンダントはどうでもいい」
ザノバはそう言うと、ペンダントを摘んで、袋の上に置いた。
動作がいちいち丁寧で、好感が持てる。
しかし、箱の中身がどうでもいいとはどういうことだろうか。
と、そこで俺も気づいた。ペンダントを包んでいた布に、見覚えがあった。
「さて、このパンツだが」
ザノバはそう言って、布を摘んで広げた。
ホームベースのような形をした白い布、間違いない……あれは……
御神体だ。
「リーリャは貴様の十歳の誕生日にこれを贈ろうとしていたそうだ」
つまり、そういうことか。ペンダントはカモフラージュ。包んだ布こそが、俺の大切なものだとハッキリわかっているのだ。
もしかすると、当初はそのまま贈ろうとしたのかもしれないが、誕生日にパンツを贈ることの異常性を考慮して、わざわざこんなことをしてくれたのだ。
しかし、残念でならない。
御神体は綺麗に洗濯をされていた。
ロキシーのエクストラバージンオリーブオイルは流れ落ち、神性は失われた。すでに、このパンツに神は宿っていない。代わりに、リーリャの真心が詰まっているといえるだろうが……。
「そ、それで、そのパンツがどうしたというのですか?」
震える声を隠しつつ、俺は尋ねる。
ザノバはうむと頷くと、四つん這いになった。
「パンツについて話す前に、この人形について説明してやろう」
ロキシー人形をこわれものでも扱うように指で触れる。
そして、語りだした。
そう、語りだしたのだ……滔々と、長々と、恍惚とした表情で。
「まずはこう正面から見てみろ。
一見すると、これは杖を構えた普通の魔術師だ。
しかし躍動感がある。
このローブの波打ち具合を見ろ。
片足をバッと前に出し、杖をグッと突き出す、その瞬間がありありとわかる。
そして、ローブの袖と裾から覗く、手首と足首!
露出している肌はほんの少しだ。
ほんの少しだが、そこはかとないエロスがある。
このほんの少しの部分だけで、この魔術師の少女が痩せぎすで、
決して豊満ではない体がローブの中に隠されているとわかる。
こんなダブダブなのに、わかるのだ!
そして、今度はこうして……後ろから見てみろ。
ダブダブなローブは本来、体の線が出ない。
しかし、足を前に出したことで布が引っ張られ、
ほんの少しだけ尻の線が浮かび上がっている。
小さな尻だ。恐らく実物を見ても、そうエロいとは思わないだろう。
だが、こうして、ダブついたローブに浮き出るからこそ、エロいのだ!
ぜひ見たいと、脱がしてみたいと、そう思わせる尻なのだ。
そう思えば、なんと、このローブは脱がすことができる。
ローブをつなぎ止める部分を丁寧にはずしてやると、
あどけない少女の下着姿が露わになるのだ。
しかも、この少女は胸下着を付けてはいない。
ロキシーという人物の胸の大きさ的に、この選択は正解だ。
そうして表を向けてみると、なんと、左手が胸を隠している。
おかしい、先ほどまで左手は杖を持っていたはずなのに。
そう思い、ローブを見てみると、なんと左手がくっついたままだ。
そう。この像には腕が三つあるのだ。
ローブを着た姿と、下着姿。このギミックで二つの像が一体化しているのだ。
まさに天才だ。
ローブを脱がすことができるということは、すなわち体のポーズを固定化させてしまう。
しかし、こうして腕の位置を中と外で変えることで、ポーズの自由度を上げているのだ。
それだけじゃないぞ、今度は横から見てみよう。
ローブを着ている時は背筋を張り、前足を突き出したようなポーズだった。
しかし、ローブを脱がすと、なぜか前かがみになっているのだ。
まるで、胸を、体を隠すように。
それを確認した上で、顔を見てみろ。
ローブをつけている時は凛々しかった顔が、
今は恥じらいを必死にこらえているようではないか。
これを作ったものはわかっているのだ。わかっていて、表情を同じにしたのだ。
誰も真似しえない、『至高』がここにはある。
確かに、要所要所は炭鉱族の細やかな技術には遠く及ばない。
素人もいいところだ。
だが、粗野な炭鉱族などでは到底及びもつかない領域に、この人形はある!」
俺はそれを一言一句、聞き逃さなかった。
普通ならポカンとするところかもしれないが、俺はこの人形の製作者だ。
噛み締めるように聞き、そして満足げな気分になっていた。だってそうだろう、自分が作ったものが、これほどまでに熱く語られているのだ。嬉しくないわけがない。
そうだ。そうとも、その通りだ。このロキシー人形には、当時俺の持てる全ての技術を注ぎ込んだ。まだまだ素人の出来とはいえ、見る者が見ればわかるのだ。
嬉しいものだ。細かいところに施した工夫まで気づいてもらえるなんて……。
でもひとつ足りないな。俺がなぜ手で胸を隠すようにしたのかを……。
「あれ?」
と、そこで俺は気づいた。
「脇下のホクロが消えてるのですが」
「ん?」
ザノバはそう言うと、ロキシー人形を再度裏返した。
「ああ、脇にあった黒い点のことか? だが、それは像の美観を損ねると思って削った」
ザノバは、こともなげにいった。
俺はその言葉でフリーズした。凍りついた。目を見開いて、動きを止めた。
「け、削った……?」
「ふむ、ここに点があったことを知っているということは、やはり貴様はこの像のことを何か知っているのだな?」
「……ちょっと、その像を回してみてください」
「その前に余の質問に答えよ」
「いいから回せよ」
自分でも驚くほど冷たい声が出た。
ザノバは「うっ」とたじろぐと、俺に言われるがまま、像を回した。
「そこで止めて、その角度で見てみてください」
ほくろがあった位置がザノバにギリギリ見える位置で、止めさせる。
「手の位置を見てみてください」
「なんだというのだ」
「いいから、見てみてください」
俺のやや強い口調に、ザノバがムッとしているのがわかる。
しかし、律儀に人形を見ていた。真面目なヤツだな。
「隠しきれていないのがわかりますか?」
「……ふむ?」
「手が届いていないのがわかりますか?」
「…………あっ」
ザノバが小さな声を上げる。
ようやく、彼にもわかったらしい。そう、俺が手で胸を隠すようにした理由。
十八禁という概念が存在しない世界において、なぜロキシーの可愛らしく慎ましい胸を露出させなかったのか。
「胸は隠せているのに、ホクロが隠せていないことが、わかりますか?」
「……そん……な……馬鹿な……」
ザノバがわなわなと震えていた。
そうだ。俺がホクロに目をつけたのは、まさにそこだ。ホクロを第二の乳首に見立て、それを隠せていないことに対する恥じらいを表現したのだ。すなわち、あのホクロはこの人形の中で一番エロい場所なのだ。
「よ、余は……何も、わかっていない……。なのに、作品を……汚して……」
ザノバの目はうつろで、身体を痙攣させ始めた。
口から泡が吹き出ている。ちょっと反応が過敏すぎやしないだろうか。
「まぁ、ホクロなんてまた付け直せばいいんですが、それで、パンツがどうしたんですか?」
「ぱ、パンツは……それと……同じで……」
と、パンツと像を見比べてみると、人形の履いているパンツと、元御神体は同じものだった。
なるほど。俺は自分の最も見慣れたものを人形に装着させた。このパンツをリーリャが俺に贈ろうとしているのなら、関係性があると考えるのが普通だろう。
ちなみにロキシーは、当時あと四枚のパンツを持っていたが、細部が少しずつ違った。
ああ見えて、ロキシーはオシャレなのだ。
「そういうことでしたか。それで、僕はこの人形の何を喋ればいいんですか?」
まあ、いいだろう。ザノバはこの人形を大切に扱ってくれているらしいし、いきなり神殿騎士団に突き出されたりはしないはずだ。
「ぬううおおおお!」
ザノバは、唐突に五体投地をした。床にダンと己の全身を叩きつけたのだ。
びっくり。
「あなた様がこの像の製作者であらせられましたか!」
なぜこいつはいきなり這いつくばっているのだ。
わからない。俺にわかるのはロキシーが偉大だってことぐらいだ。
「さすがは『水王級魔術師』ロキシーの弟子! この人形は魔術にて作り上げたのですね!」
ロキシーの名前を呼び捨てにするなよ。
さんを付けろよ。
「あなた様の作品を毎日見ていました。見る度に発見があり、尊敬の念を募らせていました。ぜひ、師匠と、そう呼ばせてください」
そう言って、彼は四つん這いでカサカサと動き、俺の靴にキスをしようとして、しかし結界に阻まれて「うおおぉ」と雄叫びを上げて結界を叩いた。
その姿は、まるで夏の三日目に新刊に群がる亡者のようであった。
人としてのプライドや尊厳をかなぐりすて、欲望のままに生きる者の姿がそこにあった。
「うおおお! なんだこの結界は! 誰がこんなものをぉ! 師匠! ぜひともその神の手を拝ませてくださああああぐおおああぁぁ!」
こうして、俺にちょっと気持ち悪い弟子ができた。
こういう奴は生前にもいた。
主にネット上での付き合いで、友人とも言えない関係だったが、いた。
そうか、あいつ、こういう顔をしていたのか。ここまで心酔されたのは初めてだが……しかし好都合。きっと、人神はこのことを予見していたのだ。城で捕まることで彼と仲良くなり、そして手を貸してもらって脱出するのだ。
よし。エンディングが見えた!
俺は仏のような顔で、彼に言った。
「弟子よ。部屋のどこかにこの結界を維持する魔力結晶があるはずです。それを見つけ出し、叩き壊すのです!」
「わかりました師匠! それを実行したら、ぜひとも、ぜひとも人形製作の極意を我が身にぃ!」
「見つけ出せなければ破門です。今後二度と僕を師匠と呼ぶことは許しません」
「もちろんですとも!」
ザノバはその言葉に奮起した。
奮起して部屋の中を調べて回り、上の部屋も探しまわり、ガサガサとゴキブリのように周囲を這いまわった。
そんなこんなで小一時間。
発見したものといえば、天井にA4サイズぐらいの穴が開けられるということぐらいだった。
パックスはどうやら、そこから食事を投げ入れるつもりだったようだ。
食事はそれでいいとして、排泄物とか病気とかはどうするつもりだったのだろうか。
上から催眠ガスでも吹きつけて、俺を眠らせてからこっそり結界を解除するのだろうか。
いや、どうせ考えてないだろう。
あのパックスという男は、ペットには餌さえ与えておけばいいと思っていそうだ。
とりあえず、蓋さえどけることができれば脱出できるだろう。
天井は高いが、ロープでも垂らしてもらえばなんとか登れるだろうし。
しかし、重そうな石版が溶接されたマンホールのようにガッチリと固定されていて、外すことは難しいらしい。
蓋の上にも魔法陣が描かれているんだそうだ。
ワンセットなのかな。壊すことも難しそうだ。
「殿下の配下には、結界に詳しい人はいないんですか?」
「余に配下はおりませんゆえ!」
「そうなんですか? あのパックスですら親衛隊がいるのに……」
「最後の一人はロキシーの人形とトレード致しました! いやあ、いい取引でした!」
こいつもバカか。しかも、親衛隊をトレードって、この国はどうなってんだ。
とにかく、一つ判明したことがある。
「よし……わかりました」
「おお、わかりましたか、さすが師匠!」
「はい、このままだと、どうやら君は破門になりそうです」
「なんとぉ!?」
俺のちょっと気持ち悪い弟子は、異例のスピード破門──とは、ならない。
せっかくの協力者を失うつもりはない。
「条件を変えましょう。ここから出るのを手伝ってくれれば、出られた時に弟子としましょう」
「おお! そんなことでいいのですか! しばし、しばしお待ちを!! 今すぐ拳で天井をぶち破りますゆえ!」
「無茶はやめなさい」
拳を握りしめて天井を睨むザノバを、俺は慌てて止めた。
本気の顔だった。手骨が砕け散ってもなお蓋を殴り続けそうな顔をしていた。危うい奴だ。
ザノバはしばらくそわそわしていたが、ふと、何かに気づいたように顔を上げた。
「師匠、この結界を作り上げたのは誰ですか?」
「ええと、確か第七王子のパックス殿下という話です」
「ふむ、そういえばジンジャーがそんなことを言っていたな……」
「詳しい事情は聞いてないんですか?」
「なにぶん、余の頭は人形で一杯ですゆえ」
「ああ、そう」
とりあえず、この王子はジンジャーにツテがあるらしい。
ジンジャーも裏で動いているのだろうか……なら、あの人もパックスには思うところがあるようだし、その方面で手伝ってもらったほうがいいかもしれない。
いや逆か。ザノバはジンジャーに言われてここに来たと言っていた。ということは、ジンジャーは俺とザノバを会わせたかったということだ。ルイジェルド人形を見て、趣味が一緒だとでも思われたのだろうか。
しかし、ジンジャーはこの頼りない王子を仲間に引き入れて、どうするつもりなのだろうか。
イマイチ動きが見えない。
「つまり師匠、パックスをどうにかすればいいわけですね?」
「ん? ええ、そうなりますね」
ザノバはそこで少しだけ考えた後、今まではしゃいでいたのが嘘のような静かな声で言った。
「わかりました、しばしのご辛抱を」
何かを思いついたらしいけど、この王子もあんまり頭よくなさそうだし、変な動きをすると藪蛇になるんじゃなかろうか。
「ええと、行動を起こす前に誰かにきちんと相談してくださいよ。そう、例えばジンジャーさんとか。僕でもいいですけど」
「ははは、師匠は心配性ですね。ご安心を、全て任せておいてください」
「おい、ちょっとまて。どこに行く。話を聞け。何をするつもりだ!」
ザノバは笑いながら、階段を上っていった。
「まじかよ……」
俺はこの時、やっちまったという気持ちになっていた。
配下のいないダメ王子をその気にさせて、蛇のいる藪をつついてしまったと、思っていた。
事態は非常に悪い方向に転がってしまうと思っていた。
イヤな予感がひしひしと伝わってきた。
ああ、こんなことなら、せめて飯を持ってきてもらう程度の頼み事にしておけばよかった。
なんて考えていた。
だが、それは間違いだと、知ることになる。
俺はザノバ・シーローンという人物を完全に見誤っていたのだ。
後になって考えてみれば、人形の製作者だとザノバに知られた時点でこの事件は全て終わっていたのかもしれない。
第六話 「スピード解決」
俺はこの時、やっちまったという気持ちになっていた。
配下のいないダメ王子をその気にさせて、蛇のいる藪をつついてしまったと、思っていた。
事態は非常に悪い方向に転がってしまうと思っていた。
イヤな予感がひしひしと伝わってきた。
ああ、こんなことなら、せめて飯を持ってきてもらう程度の頼み事にしておけばよかった。
なんて考えていた。
だが、それは間違いだと、知ることになる。
俺はザノバ・シーローンという人物を完全に見誤っていたのだ。
後になって考えてみれば、人形の製作者だとザノバに知られた時点でこの事件は全て終わっていたのかもしれない。
第六話「スピード解決」
事件の結末を話す前に、一つの要素について触れておこう。
この世界には、生まれつき異常を持って生まれてくる子供がいる。
異常というと奇形児を思い浮かべるかもしれないが、見た目は普通であることが多い。
逆に言えば、見た目が普通なだけである。
その子供は、生まれつき特殊な能力を持っているのだ。
異常に足が速かったり、怪力だったり、耳が他人よりよく聞こえたり、体重が羽のように軽かったり、逆に重かったり、触ったものを全て凍らせたり、口から炎が吐けたり、指先から毒を出せたり、短い距離を瞬間移動できたり、目から光線を出せたり、あらゆる毒を無効化したり、一日中眠らなくても疲れなかったり、何百という女を同時に抱いていても萎えなかったり……。
そうした超常的な能力を生まれつき持つ子供のことを、この世界では『神子』と呼ぶそうだ。
あるいは役に立たない、あるいは生きていく上で不都合な能力を持った子のことは『呪子』と呼ばれるらしいが、それは置いておこう。
さて、『神子』という存在を踏まえた上で、シーローン王宮の話をしよう。
現在この王宮には、七人の王子がいる。
一番上が三十二歳で、一番下が……まあ、年齢はどうでもいい。
この国においては、王子が生まれると直属の親衛隊が与えられる。
幼い頃から自分の手足となるものを与えることで、人を動かすことを学ばせようという魂胆である。
親衛隊の数は決まっておらず、良いことをすれば増え、悪いことをすれば数が減る。
王が崩御した時に最も親衛隊の数が多いものを次代の王にする。
というのがこの国の習わしである。
親衛隊の数が多ければ多いほど、権力を持つというわけだ。
そんな中で最も多くの親衛隊を持つのが第一王子。
長男であることに自覚を持ち、少々傲慢ではあるものの、王族として相応しい振る舞いをしている。ゆえに三〇人近い親衛隊を持っている。
では、最も数が少ないのは誰か。
兵士たちに蔑まれている第七王子パックス・シーローンか。
たしかに彼の親衛隊の数は少ない。
現在のところ、三名のみである。一時期は一名まで減ったのだが、無法地帯だった奴隷市場にツテを作ったことで一人増えた。もう一人は後述する。
パックスの親衛隊は少ない。
だがさらに下がいる。
それが第三王子ザノバ・シーローンである。
彼の親衛隊数はゼロ。自身に動かせる兵はただの一人も存在しないのだ。
ごく数年前までは、ジンジャーという、この国で十二番目に腕の立つ者が親衛隊だった。
だが、とうとうその最後の一人も、とある人形とトレードされ、パックスのものとなった。
ジンジャーはその時点で辞職を願い出ようとしたらしいが、慌てたパックスに家族を人質に取られ、嫌々彼の親衛隊になったそうな。
さて、この第三王子ザノバ・シーローン。
実は彼、神子であった。
生まれつきの怪力で、非常に頑丈な身体を持っている。異能者なのだ。
大した能力ではないが、生まれた時、国王は歓喜した。
神子は将来、必ず国の役に立つ人物になる。
特に、紛争地帯が北に近いこの国では、戦力になりうる存在の誕生は両手を上げて喜ぶべき事柄だった。ザノバを生んだのは妾の女だったが、彼女もこれで役割が果たせたと、ほっと胸を撫でおろした。
国王の上げられた両手が下がったのは、三年が経過した時だ。
ザノバが三歳の時、第四王子が生まれた。
第四王子ではあるが、正妃にとって初めての子供だった。玉のような子供だと周囲は喜び、国をあげてのをパーティが行われた。
ザノバはそのパーティの中、とてとてと歩き、己の弟の居場所に向かったそうだ。
そして、ベッドに横たわる弟に触りながら、可愛いね、お人形さんみたいだねと言った。
誰もがその言葉を聞いて、にこやかに笑った。ザノバは三歳にして人形が好きだったから、弟を自分の好きなものにたとえて言うのは、実に微笑ましい光景だったという。
──だが次の瞬間、ザノバは弟の首を引きちぎった。
人形のように。
パーティは阿鼻叫喚の地獄となった。
国王と正妃は発狂し、ザノバの母を国外追放に処した。
しかし、ザノバは国に残った。まだ幼いということもあったが、神子でもあったからだ。
この世界における神子とは、それほど重要な人物であるのだ。
ザノバの親衛隊は、その事件で三人にまで減らされた。
八人だったのが、三人だ。その上、これ以上増やすことはない、と王に宣言された。
次に事件が起こったのは、彼が十五歳の時だ。
この頃になると、ザノバは人形狂いとはいえ、分別もついていた。
なので嫁を迎え入れることになった。
幾度となく北の紛争地帯にあるビスタ国からの侵攻を食い止めてきた豪族の娘で、国王としてはビスタ国と戦争となった時、ザノバを矢面に立たせるつもりだったのだろう。
結婚式はつつがなく終了した。
結婚式は、だ。
初夜を終えた翌日。花嫁がベッドの中で、首なし死体となって発見された。
ザノバが引きちぎったのだ。
豪族は娘が殺されたことで怒り狂い内乱を起こしたが、鎮圧された。
国王はザノバから二人の親衛隊を取り上げ、戦争が起こるまで城内に軟禁することを決めた。
その際、ザノバが偏愛していた人形を取り上げようとしたが、その任に赴いた兵士は、全て首を引っこ抜かれて死んだ。
『首取り王子』ザノバ・シーローン。
この事件から、ザノバはそう呼ばれるようになった。
さすがに正嫡を殺し己の妻も殺すような狂人は、いかに神子とはいえ目に余る。国王も処刑も視野にいれていたという。
だが、ザノバには人形があればよかった。
人形さえ定期的に与えておけばザノバは害がなかった。
ゆえに王も、あれは人の形をした危険な兵器だと、そう思うことにしたのだ。
それ以後、ザノバは腫れ物のように扱われ、現在に至る。
と、偉そうに事情を語ってみたが、俺がこの話を聞いたのは、後になってからだ。
あの時、俺はザノバがシーローン王宮の最大戦力の一つだとは知らなかったのだ。
★ ★ ★
ザノバが任せろといって立ち去ってから数時間後。
彼はニコニコした顔で戻ってきた。
対する俺は引きつった顔をしていたと思う。
ザノバはにこやかな顔をしながら、手に、あるものを持っていた。
「師匠、どうでしょう、これで弟子にしてくださいますね!」
「いだいいだいいだいいだい! やめろ! やめてくれ兄上!」
「うるさいぞパックス」
「あああぁぁぁがああああぁぁぁ!」
それは顔面を掴まれているパックス・シーローンだった。
掴まれているところからボタボタと血が垂れている。
パックスが血を流しているのではない、ザノバの全身が血にまみれているのだ。
「っ……」
俺は言葉を失っていた。
意味がわからなかった。弟子だのなんだのと軽い話をしていると思ったら、いつのまにかスプラッタホラーになっていた。いやほんと、ワケがわからないよ。
ザノバはニコニコしている。
無邪気な笑顔だ。血塗れの笑顔というものは、美女がしてこそ艷がでるものだ。こんなオタクっぽいヒョロい兄ちゃんがしても猟奇的なだけだ。怖い。
「……」
ザノバの後を追うように、何人かの人物が付いてきた。
まず剣を抜いたジンジャーと、彼女と同じ格好をした騎士三人。
「やめろザノバ! 手を離せ!」
「そ、そうだぞザノバ、気を確かに……!」
それから騎士の後ろに隠れる、高価そうな服を着た二人の王子。両方とも王子というには、片方は少々歳を食いすぎているが……。
それにしても、この狭い部屋に俺を含めて九人では、ちと手狭だ。
「兄上。パックスは兵士の家族を人質に取り、己が意のままに操っていたことをご存知ですか?」
「い、いや……」
「親衛隊ではない、父上のものである国の兵士を、です」
ザノバはニコニコしていた。
ニコニコしながら語っていた。
「そこなジンジャーも、家族を人質に取られていたようです」
「……そうなのか?」
「ハッ」
ジンジャーは剣を抜いたまま、王子に対し答える。
ザノバは変わらずにこやかな表情のままだ。
「兄上たちは、ロキシーを覚えていますか?」
「あ、ああ。パックスの家庭教師の……」
「水王級魔術師にして、我がシーローンの兵に対魔術師戦の極意を教えてくれた、大恩のあるお方です。父上もロキシーを正式に王宮に招こうとおっしゃっていたではありませんか。このパックスの浅はかな行動でそれも灰燼に帰しましたが」
「う、うむ……そうだな、確かにパックスは悪い、だがお前が……」
「だというのに……ご覧ください。その弟子である師しょ……ルーデウス様がこのような辱めを受けている。パックスの手によってです。ロキシー師曰く、自分よりも才能のある弟子と豪語する、素晴らしい人材であるはずのルーデウス様が、です」
ザノバは笑顔を崩さない。ある意味、あれもポーカーフェイスといえるのだろうか。
「お、お前、議会の時はつまらなそうにしているが、聞いているのだな。兄として安心したぞ。てっきりお前は国のことなどどうでもいいと……」
「兄上、余は人形にしか興味はありません。ただ、パックスをこうする正当性を説いていただけです。余がこうしている理由は、ただひとつ」
ザノバはハッキリとそう宣言し、パックスを持ち上げた。
「イダダダ!」
「ルーデウス様は、この世界に二つとない素晴らしい人形を作るお方。そんなお方が、パックスのくだらぬ復讐に利用されるなど、あってはならぬこと!」
「アアアアァァァ! 割れる、割れる、割れるぅぅ!」
パックスの悲痛な悲鳴が部屋に響き渡る。
「兄上、パックスの肩を持つのでしたら、余は暴れます」
騎士三人と王子二人が見るまに青ざめた。
もうすでに暴れてるじゃねえかと俺は思うのだが……場の空気が凍りついたところを見ると、この程度では暴れたうちに入らないらしい。
「余は難しいことは言っておりません。人形の製作者を助けたいが、パックスの悪事が邪魔だと申しておるのです」
「しかし、パックスは奴隷市場を……」
「兄上、何度も言わせないでください。弟の首を引っこ抜きそうです」
ザノバはもう笑っていなかった。
俺はワケがわからなかった。引っこ抜くってどういう比喩表現なんだと戸惑っていただけだ。
ただ、ザノバがこの場の主導権を持っているのはわかっていた。
頑張れ我が弟子よ。ちょい怖いけど。
「ィィィィ、イヤダ! やめろ! 離せ、ジンジャァァ! 助けろ! 家族が、家族がどうなってもいいのか!」
「自分の家族でしたら、昨晩ルイジェルド殿が助けてくださいました」
「なにぃ!?」
パックスが暴れ、ジンジャーが冷徹に答える。
ルイジェルドが誰を助けたというのだろうか。あいつはいつも誰かを助けている。
わからないが、やはり俺の知らないところで何かが進行していたらしい。
「この通りです兄上。余は王子の中で最も権力が無いゆえ、兄上に頼むという形になりましたが、断るというのならば、余も力の限り暴れましょう。なに、この距離ならば兄上のどちらか、あるいは両方の首をねじ切ってさしあげることができるでしょう。その後は、宮廷魔術師にでも焼かれて死ぬでしょうが……」
その言葉で、おそらく第一王子と第二王子と思われる二人は、折れた。
「わ、わかった! お前の言う通りにしよう!」
「兄上、きちんと調べてくださいよ? それから、城のどこかに二年前に騒ぎを起こしたリーリャが囚われているはずです。その身柄も確保していただきたい」
「無論だ。父上の耳にも入れよう……」
この時、俺はザノバが神子だと知らず、お前みたいなヒョロい男が大した自信だな、と本気で思っていた。自分を強いと思い込むのは危険だぞとか、なぜこの王子二人はパックスのようなクズを擁護しているのだろうとか、真面目にそんな疑問を持っていた。
しかし、違うのだ。
彼らはザノバを恐れていたのだ。爆発寸前の爆弾に恐れを抱いていたのだ。
それがわからないまま、俺は結界から出された。
パックスは捕らえられ、リーリャは解放され、あれよあれよという間に事件は終了した。
★ ★ ★
ここからは後日談というか、事件の種明かしとなる。
まず、リーリャが抑留されることになった流れからだ。
彼女は当初、他国のスパイだと疑われていたらしい。尋問された時に、ロキシーやパウロの名前を出したことで投獄は免れたが、疑いは晴れず監禁。転移事件の情報が流れてきた時に解放されそうになったらしいが、パックスが横槍を入れ、情報規制を敷いて城の中に閉じ込めたそうだ。
パックスはロキシーが出奔した後、奴隷市場にツテを作っていた。
で、その奴隷市場のツテで私兵を雇い、兵士の家族を拉致監禁。
命が惜しければ言うことを聞けと脅したのだそうだ。
兵士たちもなんとかしたいと思いつつ、裏町を探り人質の場所を見つけ出したりはしたものの、屈強な護衛も多く救出は困難で、もどかしい日々が続いていた。
そんな中、アイシャが脱走し、王子より追跡命令が下った。
兵士たちは嫌々ながら動いてアイシャを発見。
と、そこに俺が現れ、華麗にアイシャを攫う。
兵士たちはアイシャを助けるという行動に加え、無詠唱魔術という高度な術を見た時点で、俺がロキシーの弟子だと気づいたのだそうだ。
そこで、兵士たちは計画を練った。
まず、奴隷市場にて喧嘩を起こし、市場を使えなくする。アイシャが謎の男に攫われたことにして、私兵を追跡に出してもらう。それから俺に事情を話し、人質救出に参加してもらう。警備の手薄になった人質の保管場所に襲撃を掛けるのを助けてもらい、見返りにリーリャの身柄をなんとかしてくれる、とそういう流れだったそうだ。
まぁ、その計画が実行される前に、俺はロキシーがいると思い込んで王宮に手紙を出し、それを見たパックス王子に監禁されていたわけだ。
せめて、あと一日手紙を出すのを遅らせれば、俺は彼らから事情を聞き、パックスを逆に罠にハメることもできただろう。やっぱり人神の助言は、アイシャを助けた後に手紙を書けという意味だったのだろう。
で、救出計画だが、頓挫するかと思われたが実行された。
俺のいる宿に行ったら、ルイジェルドがいたからだ。
彼は兵士から事情を聞き、奮起してあっという間に人質を助け出したらしい。
人質を無事家に送り返した後、ルイジェルドは城に突撃をかまそうとしたそうだが、そこは兵士たちが自分たちでやると言って聞かなかったそうだ。いわばプライドだね。
兵士たちの計画では、人質が帰ってきたという報告はせず、のこのこと裏町にきた王子を、そのまま殺害する予定だったのだとか。
裏町での殺人なら、発見も遅れるし、死体も隠せるんだそうだ。
やや無謀な作戦に思えたが、勝算はあったらしく、ルイジェルドは折れた。
ちなみに、これらの作戦、終了するまでジンジャーは知らなかったらしい。
ハブられてたっていうか、親衛隊だから危険と思われていたそうだ。かわいそうにね。
ただ、人質を解放した時、ジンジャーの家族も発見され、無事に保護されたという。
一方、ジンジャーはジンジャーで今回の一件を好機と考え、ザノバに人形を渡したりとかしていたそうだ。
この王国で最強の戦闘力を持つザノバ。彼に人形を渡せば俺に興味を持つ。俺がその人形のことを喋れば、ザノバが貴重な情報源として、自分の側についてくれるかもしれない。
という打算もあったそうだが、ジンジャーは単純にザノバに忠誠を誓っているのも理由の一つだそうだ。この一件でパックスから解放され、ザノバの元に戻りたかったらしい。
人形のカタに売られたというのに、なぜまだ忠誠を誓うのかと思うが、彼女にもお涙頂戴のエピソードがあるのだろう。
で、翌日。ザノバがパックスの親衛隊二人を殺害し、身柄を確保した。
兵士たちの計画は最後まで実行されることはなく、事件は驚きの結末を迎えたというわけだ。
全てが明るみに出た後、国王より沙汰があった。
まずパックスだが、国外追放に処された。
奴隷市場のツテはもったいなかったらしいが、兵士の家族を、あまつさえ親衛隊の家族を人質に取り、本来なら懐柔して引き入れるべき魔術師である俺を捕らえ、その上にロキシーをおびき出して犯し殺そうとまでしたとなれば、いくらなんでも示しがつかない。
体裁が悪いので、表向きは留学。
実際には殺されてもいい人質として、王竜王国あたりに送られるようだ。
ザノバもまた、国外追放となった。
こちらも表向きは留学という形である。
これを提案したのは第一と第二の王子だ。やり方がスマートでなかっただの、ザノバにも非はあるだのと第一、第二王子が言っていたそうだが、実際には、どんなことで爆発するかわからない核弾頭が自分に被害を与えるのが怖いようだ。
国王もザノバを手放すのは嫌なようだが、操れる手綱が頼りない上、問題ばかり起こすザノバに対し、さすがに疲れたのだろう。
リーリャの身柄は解放された。だが、この後に及んで、まだ他国のスパイ云々と言い出す者がいた。リーリャはパックスに取りいって、裏ではシーローンの情報を盗んでいたんだと。
監禁されながらそんなことまでできるとは、うちのリーリャはすごいな。
で、そいつらを黙らせるために、リーリャはパウロのところまで『護送』されることとなった。
アスラ王国ではなく。パウロのところに。
まあ、アスラ王国に送られても、彼女の身元を証明できる人はいないしな。
あ、一応アスラ王国に故郷があるんだったか。仕送りしてるって言ってたもんな。
でも、夫妻という間柄なのでパウロのところに送るらしい。今のパウロはどちらかというとミリス神聖国とのつながりの方が強いようだし、アスラ王国に変な勘ぐりをされるよりマシというところだろう。
まあ、これも建前上の問題だって話だ。
俺としては、移動の最中に口封じに殺されたりするんじゃないかと心配だったが、護衛にはジンジャーが参加してくれるらしい。
師匠の家族を守れという、ザノバの命令だそうだ。
他にも、ルイジェルドに助けられた兵士も参加するのだというので、安心できる。
で、俺に対しては、国王様から直々に、宮廷魔術師の地位を用意するがこの地にとどまらぬか? という提案があった。
声
こわ
音
ね
からしてため息交じりという感じで、ダメ元という感じの聞き方だった。
俺も当然のように断った。
すると王様はハッキリとため息をつきつつ、ならば下がってよいぞと言った。
それだけだった。特に謝罪とかはなかった。相手は王族だし、謝る頭を持ち合わせていないのだろう。そういう部分、獣族の方が潔かった。
けど、慰謝料を払えとか言わないよ、俺は。
全てが終わり、俺が王宮を出ようとすると、ザノバが泣きついてきた。
「師匠ぉぉ! 行ってしまわれるのですか! 弟子を置いて行ってしまわれるのですか!」
「申し訳ありません。旅を急ぐ身なので……」
「では人形は、人形は作ってはもらえぬのですか!」
「あれを作るのには結構時間が掛かるので、ちょっと……」
「なんとぉぉ!」
ザノバは俺に人形を作ってもらえなかったことが悲しいらしく、俺の手にすがりついてさめざめと泣いていた。
この時には、こいつが神子ってことを聞いていた。
他人の手足をバラバラにして首を引っこ抜く殺戮の王子だと。
正直、かなり怖い。いきなり頭を引っこ抜かれるんじゃないかとビクビクしてしまう。
キレるスイッチがわからない奴は怖いのだ。
いや、感謝はしているんだけどな。怖いものは怖い
「もし、次回会えたら、僕の人形の作り方を一から教えますよ」
「ええ! そんな、でも、余は、その、いいんですか? 秘伝の極意ではないのですか?」
「弟子に作り方を教えなくてどうするんですか」
「うおおおぉぉ、師匠ぉぉぉ!」
ザノバは泣きながら俺の身体を胴上げした。
俺は天井に叩きつけられた。
「し、しまった!! ジンジャー! 治癒魔術を!」
「ハッ!」
ジンジャーが治癒魔術を詠唱し、すぐに俺の傷が塞がれる。ザノバは危うく俺を殺しかけたことで真っ青になってわたわたしていたが、俺が無事に起き上がると、ほっとした顔をしていた。
こいつ、破門にしてやろうかという考えが浮かぶ。
いや、やめとこう。首を引っこ抜かれるのは勘弁だ。
「では師匠、達者で! 余はどこに留学処分となるのかわかりませぬが、なに、師匠とならいずれまた出会える気がします!」
「ゲホッ…………はい、達者で」
ザノバは泣きながらうんうんと頷いて、俺を見送った。
ジンジャーもそれを見て、ホロリと涙をこぼしていた。
こうして、シーローンにおける事件は終了した。
リーリャとアイシャは救い出され、パウロの元へと送られる。
パックスは国外追放。
俺にはザノバとかいう弟子ができる、と。
俺としては人神の助言に完璧に従えたわけでもなく、至らない部分もあったのだが……結果は最上とも言える形に落ち着いた。
なんていうか、人神の手のひらの上で踊らされていた感じだ。
俺がどんな動きをしようとも、大まかに助言に従えば、似たような結果に収まっていたように思える。茶番を見ていたような気分だ。
けど、確かに全てがいい方向に行った。
リーリャもアイシャも五体満足。ザノバはよくわからんが、悪感情は持たれていない。
パックスには悪感情を持たれたままだろうが、完全に手駒のない状態で国外に。
過程はともかく、少なくとも俺にとっては都合のいい結末だ。
思えば、今までの助言も、最終的に俺の都合の悪い形には収まらなかったように思う。
もしかすると、人神をもっと信じたほうがいいのだろうか……いや、詐欺師ってのは一度成功体験をさせてから搾取するからな。もう少し慎重に見極めよう。
でもまあ、約束は約束だ。次に出てきたら喧嘩腰はやめておこう。
第七話 「妹侍女の生まれた日」
ここはシーローン王国にある小さな町の宿。
アスラ王国とミリス神聖国への道は、ここで分かれる。
ゆえに、俺はここでリーリャたちと別れることとなる。
俺はテーブルを挟んで、リーリャと向かい合って座っていた。
「そうよ! ルー……カイヌシは凄いんだから! 本気だせば雨がザーザー降る森もカッチカチに凍らせたりできるしね!」
「それは魔術なんですか! 凄いです!」
「もちろんよ! それよりもっと凄い話もあるんだから、聞く?」
「聞かせてください!」
窓の外からは、エリスとアイシャの声が聞こえる。エリスがカイヌシさんの偉業について自慢げに語っているようだ。
俺は苦笑しつつ、テーブルを挟んだ向かい側に座っているリーリャに意識を向けた。
彼女とは、昔からポツポツと話をした程度だが……さて、こういう時は何を話すべきなのか。
迷っていると、リーリャの方から話しかけてきた。
「改めて、お礼を申し上げます、ルーデウス様。一度ならず二度までも命をお救いいただき、感激の念にたえません」
「やめてください。今回、僕は何もしてません」
「いいえ、ルーデウス様がかすかな筋から情報を得て、わざわざシーローンへと足を運んでくださったと聞き及んでいます」
リーリャはそう言って、深々と頭を下げた。
俺は人神の言う通りにしただけだ。その後は、本当に何もできなかった。無様に罠に嵌り、助け出されただけだ。これで感謝しろなんて言えるなら、生前の俺はもっと大物になれたはずだ。
「ルイジェルドとエリスに感謝してください。彼らがうまい具合に動いてくれたから、スムーズに事が終わったんです」
「彼らとも少し話をしましたが、全てはルーデウス様の策略だと……」
「そんなわけないでしょう」
「…………ルーデウス様がそうおっしゃるのであれば」
不満そうだが、俺は黒を白と言えなんて言ってないはずだ。
そのまま、しばらく沈黙が流れた。
「時に」
リーリャは窓の外をチラリと見て、ポツリと聞いてきた。
「アイシャは何か失礼なことはしませんでしたか?」
「まさか……優秀な子ですね。六歳であそこまで考えて行動できるなんて普通はできませんよ」
まあ、ちょっとツメが甘かったようだけど。
黙っておこう。俺も人のことは言えないしな。
「ルーデウス様ほどではありません……。この数年で、できる限りのことは教えたつもりですが。未だにルーデウス様の素晴らしさを理解できぬ愚鈍な娘です」
「愚鈍は言いすぎでしょう」
大体、俺は例外だ。生前の記憶を持っているからな。
妹であるアイシャにもその可能性はあるのかと思って、試しにテレビやら携帯やらの存在について聞いてみても、きょとんとされるだけだった。
妹は単に天才なだけなのだ。パウロの遺伝子ってのは案外凄いね。
「ルーデウス様。アイシャをどう思いますか?」
ふとリーリャが、思いついたように聞いてくる。
「え? だから、優秀ですと」
「そうではなく、見た目です」
「可愛いと思いますが」
「私の娘です、成長すれば胸も大きくなるでしょう」
ほう、胸が……?
いやいや。妹の胸になんざ興味はない……ていうか、なんの話をしているんだ。
「ルーデウス様。アスラへと旅を続けるのなら、ぜひともアイシャを連れていってください。私は旦那様のところに行かなければなりませんが、アイシャはそちらに付いていっても大丈夫でしょう?」
「理由を聞いても?」
俺は反射的に聞き返した。
「ルーデウス様。アイシャには常日頃から、将来はルーデウス様に仕えるのだ、と教えています」
「らしいですね」
「娘には、私の知るありとあらゆることを教えてきました。今はまだ幼いですが、四年もすれば男好きのするいい体になるでしょう」
男好きて。
「ちょっと待ってください。彼女は妹ですよ?」
「ルーデウス様が女好きなのは、存じております」
存じておりますか、そうですか。
でもな。どうやら、生前と違って、血のつながった相手にはあんまり欲情しないみたいなんだ。だから、アイシャが育ったよさぁ食べちゃってね、と言われても困るのだ。
と、まあ、それも本心だが、本音はもう一つ。
「あの子は、まだ六歳でしょう? 親と一緒にいるべき年齢です」
「…………ルーデウス様がそうおっしゃるのであれば」
リーリャはガッカリしていたが、俺は間違ったことは言ってないはずだ。
アイシャは幼い。親と一緒にいたほうがいいだろ?
あくまで日本人としての感覚だが、小さい頃は父と母、両方と一緒にいるのが望ましい。
どちらかだけでもいいとは思うが、どちらもいないのはダメだろう。
「承知いたしました。確かにまだアイシャは未熟。未熟な者をルーデウス様の供にするわけにはいきませんね」
「あの、あんまり変なこと教えないでくださいよ? その、変態がどうとか」
「私はルーデウス様が素晴らしいお方だとしか伝えておりません」
「そのせいで、やや反発しているようですが……」
「そうですね。まあ、今だけですよ」
リーリャはふふっと笑い、顔を上げた。
晴れやかな顔だ。
アイシャは連れていけないが、俺はもう大切なものをリーリャから受け取っている。
その片方は革紐を通して俺の首にぶら下がり、もう片方は箱に入れて大切に保管されている。
二度と手放したりはしない。
「このペンダント(とパンツ)、ありがとうございます」
「いいえ、ルーデウス様にとって大切なものであるとは、知っておりますので」
口に出していない部分も汲んでくれた。
リーリャには本当に世話になる。
「……あの、やっぱりパンツを持っていると変態と思われるでしょうか?」
「変態? それはアイシャに言われたのですか?」
リーリャがガタッと立ち上がった。
どうどう、ストップストップと座らせると、リーリャは小さくため息をついた。
「あの子は比較的自由に城内を動けたので、誰かに変なことを吹きこまれたのでしょう」
変なことか、うん。そうだな、変なことだ。
「パンツぐらいで変態などと言っていては、アスラ王宮に勤めたらどうなってしまうのか……」
「アスラ王宮、ですか? そういえば、昔後宮に勤めていたそうですね」
「はい。あそこに比べれば、旦那様やルーデウス様など変態のうちに入りません」
「そう、ですか……」
俺は自分のことはそれなりにアレだと自覚しているが、そうか……アスラ王宮ってのは、それ以上の紳士が集うところなのか。考えてみれば、辺境貴族ですらケモナーだったりするもんな。いや、グレイラット家に限らず、シーローン王家もひどいもんだったが。
「中には女性のおりも──」
「いえ、具体的な描写はいいです」
これ以上はいけない。
「とにかく、王侯貴族の方は倒錯した趣味を持つ方が多いのです。それに比べれば、憧れの方の下着に興味を持つことなど普通です」
リーリャは遠い目をしていた。
きっと、嫌なことを思い出しているのだろう。
「父様には、よろしく言っておいてください」
「承知いたしました」
「路銀は渡しておきますが、足りなくなりそうなら冒険者ギルドで父様の部下を探してください」
「承知いたしました」
「護衛の兵士は信用できると思いますけど、知らない相手なのでくれぐれも気をつけてください」
「問題ありません。皆顔見知りでした」
「あ、そうですか、ええと……」
「ルーデウス様」
あれこれ考えていると、リーリャがふと立ち上がり、こちらに歩いてきた。
そして、俺の頭を胸に抱いた。
彼女の豊満な胸が俺の顔に押し付けられ、思わず鼻息が荒くなった。
「あの、リーリャさん、当たってますよ?」
「ルーデウス様は、昔から変わりませんね」
リーリャはそう言って、くすりと笑った。
翌日。出発直前に、俺はエリスやルイジェルドと、馬車に不備がないかの最終点検をしていた。
リーリャたちは先に出るようで、すでに別の馬車に乗り込んでいる。
「カイヌシさん、カイヌシさん!」
そこでアイシャが馬車から飛び出して、小走りでやってきた。
「なんですか?」
「ちょっと」
と、俺の裾を引っ張って、どこかへと連れていこうとする。
とりあえず、ルイジェルドに目配せをして、付いていくことにした。
連れていかれたのは、道端の茂み。アイシャはしゃがみ、俺にも座るようにとジェスチャー。
しゃがんで顔を突き合わせると、まるで内緒話だ。いや、まるでもなにも内緒話なのか。
「カイヌシさん、実は内密にお願いがあるのですが」
「お願いですか? 僕にできることなら」
可愛い妹の頼みなら、なるべく叶えてやりたい。
ノルンには嫌われたが、アイシャには嫌われたくないからな。
今のところは好感触だが、しかしそれは俺がカイヌシさんだからだ。兄と打ち明ければゴミを見るような目で見てくるだろう。
「どうか、あたしを旅の仲間に加えてください……!」
そんなことを言われ、俺は目が点になった。
…………リーリャか。
「それ、お母さんに言われたんですか?」
自分が頼んでダメだと思えば、今度は娘の泣き落とし作戦にきたか。
意外とやるね、あの人も。
「いいえ、お母さんがいいって言うわけないです」
「ん?」
あれ。先日の話だとリーリャは俺に付いていかせたいという話だが……どういうことだ?
「お母さんは、日頃から言っているんです。あたしは将来、腹違いの兄に仕えることになるのだと」
「言ってましたね」
「ですが!」
アイシャは、ドンと拳を地面に叩きつけた。
「あたしはゴメンです!」
よほど俺のことがゴメンらしい。
パンツに興奮するからだろうか。ゴメンなさい。
「先日も話しましたよね。兄は変態なんです。カイヌシさんの言うことはわかりますが、あたしはそんな人に仕えるなんて絶対に嫌です」
「そうですか……」
そこまで言うことはないと思うんだがなぁ。
「ぜひとも、あたしを救ってください。先日、救ってくれたように変態の魔の手から、颯爽と!」
「お断りします」
冗談じゃない。一緒に旅なんかしたら、名前がバレるじゃないか。バレた時に嘘をついてたなんて知れたら……あれ? でも家族だし、いつかはバレるよな?
「なんでですか! 変態なんですよ!」
「それは、君の想像であって、真実ではありません」
よし。ここで、少し誤解を解いておくことにしよう。
リーリャにまかせておいたら、きっといつまで経っても変態のままだからな。
いくら王宮にはもっと凄いのがいたといっても、兄の評価は変わらんのだ。
「実際に会ったことはないんでしょう?」
「でも、パンツは確かにあったんです!」
「何か、理由があったのかもしれません」
「パンツを大事にする理由ってなんですか!?」
なんで? なんでって言われてもな。
ほら、例えば某宗教だと、聖人の身に着けていたものは御神体として崇めるだろ?
ましてロキシーがソロプレイに使った時のパンツだぜ? 一流のプレイヤーのアイテムだぜ?
シーンに注目するリスナーなら、どうする?
そりゃ後生大事にとっておくさ!
うちの宗派のモットーは「性欲も勉強も大事!」。エロスタディのダブルスタンダードだ。
ま、それはさておき。
「その、ロキシーという人は、お兄さんの家庭教師なんですよね?」
「はい」
「ということは、お兄さんに多大な影響を与えたはずです」
「そうでしょうか……」
そうとも、俺が言うんだから間違いない。
二十年近くできなかったことを、できるようにしてくれた人だもん。
俺がこうして生きているのは、彼女のおかげだもん。
「そんな人の身に着けていたものなら、なるべく持っておきたい、と思うのではないでしょうか」
「うーん……」
納得いってないようだな。
では、先ほど命を助けてくれたカイヌシさんの所持品をあげてみよう。
俺は懐から、一つのものを取り出す。
「この鉢金は、僕がずっと使っているものです」
「なんですか、いきなり」
「これを差し上げましょう」
俺は荷物から鉢金を取り出し、彼女に手渡した。
昔、リカリスの町で購入したものだ。洗濯はしているが、結構使っているため俺の汗が染み込んでいると言えよう。
それを手にすると、彼女は少しハッとした顔になった。
「あ! なんか、わかります」
「言葉ではなく、心で理解できましたか?」
「はい、できました! 兄は変態じゃなかったんですね!」
というわけで。
俺は古くなった鉢金を、手放すことにした。にしても、この子チョロイな。
「カイヌシさんは本当に良い人ですね!」
「それほどでもないですよ」
キラッと、ルーデウスマイル。
アイシャは俺をきらきらした目で見ていたが、ふと気づいたように「あ、そうだ」と呟いた。
「現在、兄は行方不明なんですが。もし死んでたら、カイヌシさんに仕えさせてくれませんか?」
「いや、それは、どうでしょう」
「ダメですか? お母さんを見ればわかると思いますけど、あたし、結構育つと思いますよ! 男好きのする体に!」
「男好きって、意味わかって言ってます?」
「子作りをしたくなる体ってことですよね!」
「子供が子作りとか言っちゃいけません」
大きなお友達に攫われて、お赤飯の日すら消滅させられますよ。
まったく、誰だそんなことを教えたのは。
「どうしてもダメですか……? あたしのこと、嫌いですか?」
目をうるませる妹。うーむ、可愛い。もちろん嫌いじゃない。
「わかりました。お兄さんが見つからなかったら、いいですよ」
「ほんとうですか?」
騙すようで心苦しい。
彼女が成長する頃には旅も終わり、また家族で仲良く暮らせるようになっているだろう。
「じゃあ、変態って言ったことは怒ってないんですね?」
「ええ、もちろ…………え?」
なんつった、今。
「ありがとうお兄ちゃん!」
最後に彼女はそう言ってバッと立ち上がり、三人の護衛の待つ馬車へと走っていった。
俺が呆然としているうちにアイシャが馬車に飛び乗り、馬車が進みだす。
アイシャは手を振り、リーリャもぺこりと頭を下げる。
そして、最後に。
「じゃあね、お兄ちゃん! また会おうね! 約束だよ!」
馬車が行く。
それを見届けて、俺も自分の馬車に戻った。
呆然としていると、エリスがしらけた顔で言った。
「なによ、やっぱりバレバレじゃないのよ」
「あ、あれぇ……?」
ルイジェルドが馬の手綱を引くと、俺たちの馬車も動きだした。
そもそも、考えてみれば、気づかれる場面は多かった。最初に名前を呼んでしまったし、その後もエリスやルイジェルドと話している時、彼らがふとルーデウスと洩らした時もあったはずだ。
すでにバレていたのだ。
では……なぜ知らないフリを?
考え、考え。すぐに答えが出た。
おそらく彼女は、兄を信頼できる人物か、見極めようとしたのだろう。俺があそこでカイヌシと偽ったまま彼女を連れていこうとすれば、彼女は俺を見限っていたに違いない。
「ははっ」
それに気づいて、俺は笑った。
アイシャは本当に賢く、聡い子だ。
将来が楽しみである。
第八話 「一人前」
俺たちはシーローン王国から西へ、西へと進んでいく。
目指すはアスラ王国。
かの国への道は平坦で、ついうつらうつらとしてしまいそうな陽気が周囲を包んでいる。
街道の左右は見渡す限りの草原、正面にうっすらと見えるのは赤竜山脈だ。
山脈の上を、三匹の影がゆっくりと旋回しているのが見える。
のどかだ。
たまに空気を読まない盗賊が金目のものを置いていきな、などと言ってくることもあるが、お望み通りエリスが鉄拳をくれてやると、這々の体で逃げ出していく。
最初はルイジェルドが皆殺しにしようとしたが、事情を聞いてみると単に食うに困ってのことだそうなので、とりあえず見逃してやる。一度はね。
中央大陸とはいえ、この辺りの街道はやや治安が悪い。
魔大陸を見習ってほしいものだ。
あそこは盗賊なんて出てこなかった。盗賊の一〇倍ぐらい、魔物が出てきたんだけどな。
人が好き勝手できるってのは、平和な証拠なのかね。
もうちょっと北の方に行くと、たくさんの小国が入り乱れて戦争してるらしく、盗賊もその戦争の煽りで増えてきているそうだが……。
何にせよ、のどかなもんだ。
少しだけ、このへんの地形について説明しておこう。
赤竜山脈とは、中央大陸にある長大な山脈のことだ。
中央大陸を三分割するように山が連なり、その全土には赤竜が生息している。
赤竜とは、中央大陸で最強と言われている魔物だ。
絶対強者とでも言うべきか。
単体でも相当の強さを持ちながら、数百匹という単位で群れを作る。
特筆すべきは、その探知能力である。彼らは縄張りに入ってきた生物を絶対に見逃さない。
犬程度のサイズの生物すら逃すことはなく、どれだけ強力な魔物であっても、その縄張りに入ってしまえば赤竜に群がられ、骨も残さずに食いつくされてしまう。
どうやって縄張りに入ってきたものを探知しているのかという点についてはわかっていない。
竜の縄張りに入れば死ぬ。それがこの世界の常識だ。
この世界には何種類もの竜がいる。
そのどれもが単体でAランク以上。中でも最も危険で獰猛だと言われているのが赤竜だ。単体ではせいぜいSランク下位と言われているものの、なにせ群れの単位、縄張りの規模が大きすぎる。
赤竜という種が住み着いたがゆえに、山脈は赤竜山脈と名付けられたのだ。
通行不能の死の山脈……それが赤竜山脈である。
赤竜は危険な生物であるが、実はひとつの弱点が存在する。
彼らは戦闘能力は高いが飛行能力はお粗末であるがゆえ、平地から飛び立つことができない。
飛ぶためには高い崖から飛び降りるか、もしくはある程度長い斜面を滑走する必要があるのだ。
中央大陸は山こそ高いものの、基本的にはなだらかな平野や森ばかりである。
ゆえに、平地に住む人々が赤竜に襲われることは滅多にない。
もっとも、たまにマヌケな個体もいるらしく、乱気流か何かに巻き込まれてきて平地に落ちるヤツもいる。
そうした竜ははぐれ竜と認定される。
天空の覇王は地に落ちれば力を失う……が、全ての力をなくすわけもなく、Aランク上位に位置する力を残している。
人里の近くに落ちた赤竜は圧倒的な力で暴れ回り、甚大な被害をもたらし始める。
そうなれば国を挙げての討伐騒動だ。緊急依頼が発生し、蜂の巣をつついたような騒ぎになる。
もっとも、大抵は人里から離れたところに落ちる。
依頼のランクはSランクとはいえ、安全を期して一〇近いパーティが組んで罠に嵌めるため、案外簡単に狩られてしまうそうだ。
ちなみに、竜の肉や骨は武具の素材として最上級に近く、竜の皮は芸術品としての価値も高い。
もちろん、皮だけじゃない。竜は全身余すことなく、何かに使える。
一匹を一〇人で討伐して報酬を山分けしたとしても、一年は豪遊できる金が手に入るそうだ。
具体的にいうと、一匹でアスラ金貨一〇〇枚ぐらいになるらしい。
高額素材であるため、依頼を受けられないCランクに上がりたてのペーペーが無謀にも挑むことがあるそうだが、大抵は焼肉にされてペロリと平らげられてしまうらしい。
そんな赤竜が大量に生息する赤竜山脈には二ヶ所だけ通行できる場所がある。
『赤竜の下顎』、『赤竜の上顎』と呼ばれる断崖絶壁の渓谷だ。
これは第二次人魔大戦時から存在している渓谷で、当時でも唯一軍が通行できる広さを持つ道だったそうだ。ラプラスはそういうことも見越して、赤竜山脈に赤竜を放ったらしい。
ルイジェルドが言うのだから、間違いあるまい。
俺たちは、中央大陸南部と西部をつなぐ『赤竜の下顎』へと馬車を進めている。
そこを抜ければ、アスラ王国だ。
しかし、迂回するということは、すなわち遠回りということだ。
遠回りが嫌なお嬢様が、ここに一人。
「迂回なんてしなくても、ルイジェルドがいるなら赤竜山脈ぐらい通過できるわよね!」
とは、赤竜山脈の上を小さく旋回する赤竜を見たエリスのムチャぶりである。
「無茶を言うな」
ルイジェルドが苦笑しつつ、そう答えた。
俺ももしかするとルイジェルドなら、と思っていたが、さすがの彼でも赤竜山脈を徒歩で通過するのは無理らしい。なら俺も無理だろう。ルイジェルドには勝てないしな。
「でもルーデウスなら行けるわよね!」
「いや、無理ですよ。なに言ってるんですか」
どうやらエリスは、竜退治というものを体験してみたいらしい。
気持ちはわからなくもないが、ちょっと待てと言いたい。
さすがにできることとできないことがある。
「でも、ギレーヌは前にはぐれの赤竜を倒したって言ってたわ!」
「本当ですか?」
俺はその話は聞いていない。
冒険者時代の話ではないのかもしれない。
もし冒険者時代の話であれば、パウロが一度ぐらい自慢げに話してきただろうしな。
「なんでも、剣聖になる前に赤竜と戦ったんですって!」
「へぇー、一人でですか?」
「えっと、同じぐらいの上級剣士五人ぐらいで、って言ってたわね」
「それ、何人死んだんですか?」
「二人だって」
馬鹿野郎。
四〇パーセントも損失してるじゃねえか。なんでそれで俺が赤竜に勝てると思うんだ。
「大体、はぐれ竜と山にいる竜じゃ強さが全然違いますよ。だって、空飛んでるんですよ?」
空飛ぶってのは、人に対して大きなアドバンテージがあるということだ。
飛行属性を持っていれば弓に弱いとかはないのだ。
しかも、群れ。この世界で群れを作っている魔物は、大抵は群れでの狩りの仕方も心得ている。
群れを作りつつも、せいぜい数匹でしか行動しない王竜や、そもそも群れを作らない黒竜ならまだしも、百匹単位で襲い掛かってくる赤竜をちぎって投げるなどできるはずもない。
「ですよね、ルイジェルドさん」
「ああ、赤竜の群れをどうにかできる奴などいない。いるとすれば、『七大列強』の上位陣だけだ。恐らく、北神や剣神であっても、道半ばで引き返すことになるだろうな」
「そうなんですか?」
へぇ、『七大列強』なら、ドラゴンぐらいは簡単に相手にできると思ったのだが……。
「ああ、恐らく、途中で体力が尽きるだろう。眠ることもできんだろうからな」
なるほど。数百匹の竜が夜も寝ないで攻撃し続けるのか。
戦闘力云々以前に、物量で押しつぶされるのだろうな。
「もっとも、ラプラスはそんな赤竜の王をも従えていた。ゆえに『七大列強』の上位なら、通過ぐらいはできるだろう。もっとも、昔の『七大列強』であれば、七位でも赤竜の縄張りを通過するぐらいはできただろうがな」
封印中の四位『魔神』と、現在五位『死神』の間には越えられない壁ってやつがあるらしい。
「でも、いつか一匹ぐらい狩りたいわよね……」
今日もエリスはいつも通り物騒だった。
そのいつかに、きっと俺も巻き込まれるんだろうな。
いずれ来るであろう時のために、赤竜戦の予習ぐらいはしておきたいものだ。
★ ★ ★
のどかな一日。
赤竜の下顎まであと数日で到着するという日。
俺は飯を作りながら、人神について考えていた。
先日のシーローン王国でのことだ。
正直、ザノバに出会った後の流れは、さすがにおかしいと俺も考えている。
俺に都合よく事が進みすぎた。
もしかすると人神は、未来予知以外にも、未来を変える力も持っているのだろうか。
いや、どうにせよザノバはあの場にいた。
ザノバの性格が唐突に変わったわけでもない。仮に人形を持っていかなくとも、ジンジャーはなんらかの形で俺とザノバを引きあわせたような気がする。ザノバはロキシー人形を持ってくるだろうし、語るだろうし、俺はやっぱりホクロのことを指摘しただろう。
偽名はどうだろうか。
少なくとも本名を名乗らなかったおかげでアイシャとは仲良くなれた。
だが、それ自体は事件には関係ないしな……。
逆に、もしあそこで本名を名乗っていたら、どうなっていたのだろうか。アイシャは俺のことを変態だと思っていたようだが、最終的に誤解は解けた。
だが、少なくとも宿についた時点では、まだ俺を兄だと確信はしていなかったはずだ。
変態な兄と、宿に二人きり……。
俺なら貞操の危機を感じるな。トイレに行ってる隙に逃げるかもしれない。
逃げる先はどこだろうか。
彼女は手紙を出そうとしていたから、金を盗んでいくかもしれない。
金があれば、手紙を出すことができると俺は教えた。
賢い彼女なら、その金で便箋を買い、人に道を聞いて冒険者ギルドに行き、そこで手紙を出そうとするだろう。
いや、兵士には一度見つかっている。普通に考えれば、冒険者ギルドに行けば兵士に見つかるから、別の人物に頼もうとするだろう。でも彼女の知り合いはいない。兵士に見つからなかったとしても危ない状況で、うろうろと町中を歩くことになる。
俺は探すだろう。
アイシャがいなくなったと知れば、きっと俺は取り乱し、後先考えずに空に向かって爆裂魔法を使い、ルイジェルドに連絡を取るだろう。そして、妹を見つけたが逃げられたと言って、探してもらったはずだ。そして、迷子のアイシャはルイジェルドに保護される。
ルイジェルドは子供にやさしい。アイシャもきっと彼を信用するだろう。
うん、やはり問題ない。
考えれば考えるほど、人神の助言は『大まかに行動したとしても、一つの結果に向かうようにできている』ように思えてくる。
今までも、おそらくそうだったのだろう。
ルイジェルドに助けてもらっても助けなくてもらわなくても、最終的にはルイジェルドと一緒に旅をすることになるし、キシリカに会ってどの魔眼をもらっても、やはり俺は大森林でドルディア族に捕まることになったのだ。
奴は、色々と考えて助言をくれている。
もしかすると、信用してもいいのかもしれない。
しかし、相変わらず目的だけは見えないんだよなぁ。そこさえきちんと語ってくれれば、俺だってもう少し素直になれるんだけどなぁ……。
「それにしても、二人は元気だな」
俺が人神について考える脇で、エリスとルイジェルドは今日もかかさず訓練をしていた。
最初は俺も混じっていたのだが、基礎体力の差なのか、半分ぐらいでギブアップだ。
ここ最近、エリスの強さは目を見張るほどに上がった。
一年前は魔眼を使えば余裕で勝てた。あの頃のエリスなら、戦闘中にパンツを引きずり下ろすこともできたかもしれない。
けど今は無理だ。魔眼と魔力を全開にすれば最後に立っているのは俺だろうが、恐らくギリギリの勝負になるはずだ。
もちろん、距離をおいての戦いであれば、簡単に俺に軍配が上がるだろう。
だが、それはどさくさまぎれにおっぱいを触る可能性をも摘み取ってしまう。
それでは勝ったとはいえない。
しかしまあ、才能ってやつなのかね。
俺だってそれなりに努力はしているつもりなのだが、エリスはその上をいっている。
努力の質も量も俺より上だ。俺も頑張らなければとは思うのだが、体はついていかない。
もしかして、この体はあまり体力がないのだろうか。生前の基準ではそこそこだと考えていたが、この世界の基準では、平均を下回るのだろうか。
エリスぐらいしか同年代の子がいないのでわかりにくい。
などと考えていると、今日のお稽古は終了したようだ。
「終わりだ」
「ハァ……ハァ……ええ……」
ここ最近、ルイジェルドはエリスに対し、「わかったか?」と聞かない。
言わなくてもわかるからだろう。
エリスはよく吸収している。
「エリス」
俺の傍まで戻ってきた時、ふとルイジェルドがエリスに声を掛ける。
「なに?」
エリスは俺からよく絞った布を受け取り、服の中に手を入れて汗を拭いている。以前は上半身ブラジャーのみになって汗を拭いていたのだが、俺が興奮するので今の形になった。
彼女も汗とか気持ちわるいだろうに。すまないねえ。
「お前は、今日から戦士を名乗ってもいい」
ルイジェルドは地面にどっかりと腰を下ろしつつ、言った。
戦士か。
剣士ではなく戦士。この世界における戦士は、単純に剣士ではないというだけで、戦闘能力に大きな違いがあるわけではない。だから……ん?
と、そこで俺は、ルイジェルドの言葉の意味に気づいた。
エリスもまた、脇の下に手を差しこみつつ、動きを止めていた。
「…………それって」
「一人前だ」
ルイジェルドは静かにそう言った。
エリスはぎくしゃくした動きで、布を俺の方へと放ってきた。
俺はそれを受け取り、水魔術で再度濡らしてから、ジャッと絞ってパンと叩く。
エリスが隣に座ってきた。
この表情は見覚えがある。嬉しくてニマニマしたいのだが、神妙な顔をしなくちゃと思っている時の顔だ。
「で、でもルイジェルド、まだ全然あなたに勝てないのだけど?」
「問題ない。お前はすでに戦士としては申し分ない力を持っている」
これは言ってみれば、認可のようなものなのかもしれない。
ギレーヌに剣神流上級と名乗ってもいいと許可されたように、ルイジェルドに戦士と名乗ってもいいと許可されたのだ。
「エリス、おめでとうございます」
エリスは目を白黒させていた。
そんなつもりで稽古をしていたつもりはなかったのかもしれない。
「る、ルーデウス、夢じゃないかしら、ちょっとつねってみて?」
「つねっても殴りませんか?」
「殴らないわよ」
言質を取ったので、彼女の乳首をきゅっとつねってみた。
もちろん、優しくだ。おっと、この場合はやらしく、かな?
エリスの拳は優しくなかった。
「どこつまんでるのよ!」
「失礼……でも夢じゃないですよ。夢ならこんなに痛くないはず」
真っ赤な顔をして胸元を押さえるエリスに、真っ青な顔をして顎を押さえる俺は告げる。
「そう、戦士……」
エリスは何かを実感するように、自分の手のひらを見ていた。
「だが、自惚れるな。もう子供扱いはしないという意味だ、わかったな」
まるで、子供に言い聞かせる親のような言い方だ。
「…………はい!」
エリスは神妙な顔を作りつつ、そう言った。
まあ、頬のあたりがニマニマしそうになってぴくぴくしていたが。
何にせよ、今日の飯はいつもよりうまそうだ。
その夜、エリスが寝静まった頃、ふと気になることがあって目が覚めた。
目を閉じながら見張りをしているルイジェルドに話しかける。
「なんで、エリスにあんなことを?」
ルイジェルドは薄目を開けて、俺を見る。
「お前が、いつまで経ってもあの子を子供扱いしているからだ」
……はて。エリスは子供かどうか。
子供だろう。生前の俺とくらべても二十歳は年下だ。
まして、俺は彼女がもっと小さい頃から、手取り足取り、殴られつつもいろいろと教えてきたのだ。子供と見て、何が悪い。
確かにエリスは最近大人びてきた。
体つきの話だけじゃない。少しずつ、分別というものをわきまえるようになってきた。
昔のように、後先考えずに暴れることも少なくなってきた。
まだまだ似たようなことはしているが、しかし、頻度は減ってきた。
言ってみればそう……彼女は子供から大人になる過程にいるのだろう。
なんて偉そうに言ってみたが、俺も立派な大人とはお世辞にも言えないか……。
「うーん……」
俺が考えていると、ルイジェルドは静かに目を閉じた。
「まあ、仕方がないか……」
何が仕方ないのだろうか。俺はその意味を深く考えることはなかった。
わからないが、何かイヤな予感を感じた。
「ルイジェルドさん」
「なんだ」
「胸ポケットに、この銀貨を一枚入れておいてください」
そう言って、懐から銀貨を一枚取り出し、ルイジェルドに投げ渡す。
彼は戸惑っていた。上着にポケットがなかったからだ。
それでも彼は、胸近くの縫い目に銀貨を挟み込むことに成功したらしい。
「で、これはなんなんだ?」
「おまじないです」
俺はそれに満足し、眠りについた。
★ ★ ★
それから数日後。
シーローン出発から四ヶ月。
俺たちはアスラ王国の入り口である『赤竜の下顎』へとたどり着く。
そして、思い知ることになる。
物事ってのは、唐突に起きるものだと。
悪いことは、予測も予防もできない時があるのだと。
唐突に親が死ぬこともある。唐突に兄弟がぶん殴ってくることもある。唐突にトラックが突っ込んでくることもある。唐突に異世界に転生することもある。唐突に父親に襲い掛かられてお嬢様の家庭教師をさせられることもあれば、別の大陸にいきなり飛ばされることもある。
恐らく全ては偶然の産物である。
さらに、思い知ることとなる。
この世界の厳しさを。
人が簡単に死ぬということを。
どんな人物であっても、いともあっさりと死ぬということを。
例外などないということを。
自分だけ、あるいは自分の周囲だけ都合よく生き延びることはないのだと。
今更になって、ようやく、実感として、思い知ることとなる。
死という現象を原因にして、身近な人が唐突にいなくなってしまうこともあるのだ、と……。
そして、愚かなことに、この時の俺は、それを真実と結びつけることができなかった。
もしこの時、俺が事実をきちんと理解し、何者にも負けない力というものを得ようと考えていればと、そう後悔せずにはいられない。
もしここで、この出来事で、もう少し別の道を歩んでいれば。
そう後悔せずにはいられない。
ただひとつだけ言えることがある。
エリスは、さすがだった。
第九話 「ターニングポイント二」
赤竜の下顎。ただ一本道が続く渓谷。
聖剣街道のようにまっすぐではないが、分かれ道のない一本の道。
国境と国境の間にある、どこの国のものでもない領域。
ここを抜ければ、アスラ王国である。
俺たちは長い旅路の終わりを予感してウキウキとしていた。
故郷がどうなっているかわからないという不安もあったが、それでも達成感のようなものを感じ始めていた。
油断していた、と言ってもいいかもしれない。
そんな中、そいつは、普通に歩いてきた。
一本道の向こうから、ゆっくりと。馬に乗るでもなく、馬車に乗るでもなく、ただ歩いてきた。
銀髪、金色の瞳、特に防具はなく、何かの皮で作られた無骨な白いコートを着た、男だ。
俺の印象としては、せいぜい「目つきの悪い奴だな」という程度だ。
酷
ひど
い三白眼だったのだ、この男は。
それよりも、目に留まったのは、彼の脇にいる人物だ。
黒髪の少女が一人、付き従っていた。どこかで会ったような気がするが、思い出せない。
この世界は純粋な黒髪が少ない。黒に見えても、よく見ると焦げ茶だったり、やや灰色に近かったりする。髪の色で他人を覚えているつもりは毛頭ないが、純粋な黒髪なら覚えていてもおかしくはない気がする……だというのに、思い出せない。
また、この少女がことさら目に入ったのには理由がある。
その顔だ。
彼女の顔に、仮面がつけられていたのだ。
真っ白で、何も描いていないし、何の装飾もされていない仮面だ。特徴がないと言えばないが、しかし一目見たら忘れることのない仮面だ。
例えるならば、ダーティマスクのような仮面である。
この世界において、こんな仮面をつけている奴はいなかった。
酷く悪目立ちしているため、ファッションではないだろう。
「……!」
少女に見とれていたから、というわけではないが、この時の俺は、御者台に座るルイジェルドの顔が蒼白になっていることに気づかなかった。エリスもそうだ。男が一歩近づいてくるたびに、その表情を険しくし、剣の柄を握る手が真っ白になるほど力を込めていた。
男は俺たちの姿を認めると、おや、と首をかしげた。
「うん……? お前は、もしかしてスペルド族か?」
男の三白眼が細められるのを見て、俺は疑問に思った。
今のルイジェルドは髪はなく、額の宝石も隠している。どうしてわかったのだろうか。にじみ出るスペルド臭でも発しているのだろうか、などと思いつつ、ルイジェルドを振り返る。
「知り合いです……か……?」
俺の問いかけは、途中で途切れかけた。
ルイジェルドの顔が違った。いつもとあまりにも違った。
元々白い肌から一切の血の気が引いており、冷や汗をだらだらと流し、槍を掴む手がブルブルと震えている。
これは……この表情には見覚えがある。
恐怖だ。
「ルーデウス、絶対に動くな。エリスもだ」
ルイジェルドの声は震えていた。
俺はわけがわからないまま、無言で頷いた。
エリスは顔を真っ赤にして、今にも飛び出しそうだ。手も足も、ブルブルと震えている。怯えているのもあるが、それ以上に、エリスは彼に敵意を持っているのだ。
しかし、俺は知らない相手だ。俺が知らない間に、二人はこの男に出会っていたのだろうか。
俺はとりあえずなりゆきを見守る。
「ん? その声、ルイジェルド・スペルディアか。髪がないから一瞬わからなかったぞ。なぜこんなところにいる?」
男は無造作に近づいてくる。
ルイジェルドが槍を構えた。
俺にはわからない。なぜルイジェルドがこの男をこれほどまでに警戒しているのか。
とりあえず二人が恐れているので、魔眼を開眼する。
はっきり言って、軽い気持ちだった。
[男の姿が何重にもブレている]
ブレすぎて輪郭すらハッキリしない。
なんだこりゃ。
「ん? そっちの赤毛はエリス・ボレアス・グレイラットか。もう一人は……誰だ? 知らない顔だが……まあいい……なるほど、読めたぞルイジェルド・スペルディア。子供好きの貴様は、例の転移によって魔大陸に飛ばされたこの二人を、ここまで送り届けたということだな」
訳知り顔で頷く男に、エリスがびっくりした声で叫ぶ。
「な、なんで私の名前を知ってるのよ!」
エリスの言葉に、俺はさらに混乱した。
初対面なのか?
エリスのことだから、忘れていてもおかしくはないとはいえ、この世界でほとんど見かけない銀髪と、特徴的な三白眼と、エリスとルイジェルドだけが感じているらしい、何か異様な感覚。
一度会えば、さすがに覚えているはずだ。
「貴様は何者だ! なぜ俺の名前を知っている!」
ルイジェルドが男に槍を突きつけた。
彼の知り合いでもないらしい。
エリスとルイジェルド、二人は男を知らないという。
俺も男を知らない。男も俺を知らない。だが、男はエリスとルイジェルドを知っている。
どういうことだろうか……。俺たちは常に一緒に行動してきたはずなのに……。
ルイジェルドは有名だ。
中央大陸ではそれほど名前が売れていないが、魔大陸に行けば、彼の名前と顔を知っている人物は大勢いる。エリスについてはわからないが、赤毛の少女剣士となれば、当てずっぽうで言って当たることもあろう。
が、おかしいのはそこではない。
あからさまにおかしいのは、そんなところではない。
態度だ。温度差とでもいうべきか。
男の態度はフレンドリーだ。声音も平坦ではあるが、どちらかというと思わぬところで旧友に出会ったかのような嬉しさが滲み出ている気がする。
対するルイジェルドは、今にも襲いかかりそうだ。
しかし、手を出していない。明らかに敵としてみているのに、攻撃を仕掛けていない。
常に先手を取ろうとするエリスだって、動けないでいる。
ルイジェルドに動くなと言われたから……というだけではあるまい。
「奇妙なところで会ったが……元気そうだな。ならいい」
男は槍を突きつけるルイジェルドをまじまじと見ていたが、やがて、自嘲気味に笑い、一歩後ろへと下がった。
それを見て、仮面の少女がぽつりと呟く。
「いいの?」
「今の時点では仕方がない」
俺には理解できない、主語の抜けた会話をした後、
「邪魔したな」
男は、俺たちのすぐ脇をゆっくりと歩いて去ろうとする。
黒髪の少女がその後を追う。
ルイジェルドは視線を外していない。もちろん、エリスもだ。
「俺のことは……そのうちわかる」
最後に、ぽつりとそう言った。
意味深だ。
俺は直感的に思った。この男は何かを知っている。この男からは人神と同じような何かを感じる。それを聞き出さなければいけない。
「待ってください!」
気づけば、呼び止めていた。
男は振り返る。意外そうな顔だ。
そして、ルイジェルドとエリスも、びっくりした顔で俺を見ている。
「どうした。なんだ、お前は?」
「あ、どうも。ルーデウス・グレイラットです」
「聞いたことがないな」
初対面だしな。
「いや、グレイラットか。親の名は?」
「それより、ええと、お名前は?」
「ふむ……まあ、構わんか。俺はオルステッドだ」
オルステッド。聞き覚えのない名前だ。
死んであの世で詫び続ける人と同じということしかわからない。
ルイジェルドを見ると、やはり知らないようだ。
「あの、二人とは知り合いなんですか?」
「いいや、まだ知り合ってはいない」
「まだ? どういう意味ですか?」
「お前は知らなくてもいい。で、親は?」
突き放したような言葉だった。
こちらの質問には答えてくれないくせに、質問には答えろというのか。
まあいい。俺はその程度のことで腹は立てないのだ。
「パウロ・グレイラットです」
「……ふむ? パウロに息子はいないはずだ。娘が二人きりのはず」
なんと失礼な。いるんですよ、父親によく似た息子が一人。
魔大陸まで出稼ぎに出てた馬鹿息子が。
「……うん?」
そこでオルステッドは何かに気づいたように首をかしげた。
ゆっくりと俺に歩み寄ってくる。
「それ以上近づくな!」
「ああ、わかっている」
しかしルイジェルドに威嚇されて、距離を保つ。やや距離を置きつつ、まじまじと俺の顔を見てきた。俺はその視線を正面から受け止める。
「お前、目を逸らさないな」
「あなたの目つきは怖いので、今にも逸らしたいところです」
「ふむ、つまり、恐怖は覚えていないのか」
男の眉根が寄った。
「ふーむ。おかしいな。お前と出会った記憶がない」
俺もない。初対面だ。オルステッドなんて名前も知らない。容姿にも見覚えがない。
だから何もおかしくないはずなのに。
「それで、何の用だ?」
「えっと、もしかして、あの転移のことについて、何か知ってるんじゃないかな、とか思って」
「……知らん」
オルステッドは首を振るでもなく、ただ拒絶するように言い放った。
あれ、なんか、俺に対する態度がおかしいな。警戒心があるというか……エリスやルイジェルドに対する口調より、余所余所しいというか……。いや、やはり初対面の相手に不躾に呼び止められて、あれこれと誰何されるのは誰だって嫌だろう。
これでは、知っていても教えてもらえないかもしれない。
「そうですか、呼び止めて申し訳──」
俺が頭を下げようとした次の瞬間、
「お前、もしかして、人神という単語に聞き覚えがあるんじゃないのか?」
彼はようやく、俺の理解できる単語を吐いた。
これはそう、ようやくだ。ようやくなのだ。ようやくわかる単語が出てしまった。
これで会話は終わりだという段で、油断していたのもある。
今まで誰にも言わないようにしていたのに、ふと他人の口から、しかもワケのわからない男の口から出てしまったせいで、会話をつなげる共通言語になると思って、あ、それなら俺でもわかる、と反応してしまったのだ。
だから、軽い気持ちで言ってしまった。
「あります。夢にヒトガミってのが出てき……」
唐突にビジョンが見えた。
[オルステッドの貫手が俺の胸を貫く]
まるで瞬間移動のようなスピードで、俺の胸を貫く。
回避できない。
一秒では、短すぎる。
「ルーデウス!」
貫くビジョンは一瞬にして消え、ルイジェルドが俺の目の前に割り込んだ。貫手はルイジェルドによって止められ、俺は仰け反って後ろに倒れた。
ルイジェルドの肩越しに、男が見下ろしてくる。
冷たい眼だった。
「そうか、人神の使徒だったか」
冤罪だと思った次の瞬間、ルイジェルドが叫んだ。
「逃げろ! ルーデウス!」
「邪魔だ、ルイジェルド・スペルディア」
ルイジェルドが槍を振るった。
俺は動けなかった。逃げようとしなかったわけじゃない、逃げる時間はなかったのだ。
ルイジェルドがやられるまで秒数。
俺は彼が赤子のようにひねられるのを、ただ黙って見ているしかなかった。
ルイジェルドは強い。強いはずなのだ。
エリスは結局、この旅の間、彼から一本も取れなかった。五〇〇年分の戦闘経験が、彼を無敵たらしめているはずなのだ。王級以上の強さを持つ男のはずなのだ。
そのルイジェルドが負けるのは、俺の眼にもハッキリとわかった。
魔眼で見ながら、その一部始終を見届けた。
時間にすれば、せいぜい十秒といったところだろうか。
オルステッドは決して、ルイジェルドより速いわけではなかった。
ただ、一手ルイジェルドが動く度に、ほんの少しだけルイジェルドが劣勢になった。それが一秒間に三回から四回、繰り返された。
ルイジェルドは動く度に墓穴を掘った。
少し、また少しと追い詰められていく。
攻撃を受ける度に少しだけ体勢が崩れ、攻撃を仕掛ける度に少しだけ後手に回った。
技量。まさに技量の差としか言いようがない。
オルステッドが圧倒的に上回っているのだ。俺の眼から見ても、ハッキリとわかるほどに。
その圧倒的差をもって、オルステッドはルイジェルドを切り崩していた。
鮮やかな手管だった。
できうる限り最小限の動き、かつ最速でルイジェルドを無力化する。
そんな理想を実現できるとすれば、あんな動きになるだろう。
ルイジェルドの間合いを完全に見切り、槍の有効射程内より常に内側に身を置く。
得意な距離へと熟達の連携で押し出そうとするルイジェルドをあざ笑うかのように崩し、よろめかせ、隙を作り出し、決して食らってはいけない攻撃をガードさせた。
そして、ルイジェルドはどうしようもなくなった。
何の手立てもなくなった。
一発、ルイジェルドの鳩尾に深々と拳が刺さり、次いで二発目、顎先に拳が掠めた。三発、ルイジェルドの意識を刈り取る拳が、こめかみを撃ちぬいた。
ルイジェルドは二回転して地面に落ち、動かなくなった。
おそらく、三発目で殺そうと思えばできただろうが、奴はそれをしなかった。
気絶させたのだ。あのルイジェルド相手に、加減していたのだ。
オルステッドは、一発だけならいつでも打ち込めた。二発でも、恐らくは打ち込めた。しかし、ルイジェルドの意識を刈り取るには三発必要だったのだろう。
それがルイジェルドを無力化するのに、最速であると言わんばかりの手際だった。
「さて」
「う、うあぁぁぁ!」
叫んだのは俺ではない。
エリスだった。彼女は俺の前に躍り出ると、抜刀からの一閃をオルステッドに向け、放った。
「……奥義『流』」
エリスに対して、オルステッドは手間を掛けなかった。
ただ、剣を手のひらで優しく受け止めただけだ。少なくとも、俺にはそう見えた。
それだけで、エリスの体は竜巻のように回転し、吹っ飛んだ。
まるでセ○ントの必殺技をくらった時のような吹っ飛び方だった。
エリスは奴の視界の外にいた。
ルイジェルドがやられた瞬間、エリスが死角から放った斬撃は、俺の眼から見ても申し分ない一撃だったと思う。
防御を考えない、思い切りのいい斬撃。
それに対し、奴は返し技を一つだけ。
具体的に何をしたのかは、わからない。俺の眼には、ただエリスの剣の横腹に手を添えただけに見えた。だというのに、次の瞬間エリスはキリモミだ。意味がわからない。
いや、似たようなものを見たことがある。
パウロが見せてくれたことがある。
水神流の技だ。あれをもっと、研ぎ澄ませたような感じの動きだった。
エリスは全ての運動エネルギーを自分へと返されたのだ。
「がはっ……!」
エリスは岩壁へと激突する。
岩肌をパラパラと落としつつ、どさりと落ちる。
彼女も鍛えているし死ぬことはないと思うが、もしかすると骨折ぐらいはしたかもしれない。
「エリス・ボレアス・グレイラット。随分と剣の腕が上達しているな。素質はあると思っていたが……まだ荒い」
「う……うぅ………」
エリスはうめき声をあげながら、起き上がろうとしている。
いつもの俺なら、彼女に早く治癒魔術を、と思っただろうか。
しかし、俺はそれどころではなかった。なにせ、奴の目が俺を向いていたから。
「……!」
あっという間に、二人がやられてしまった。
その間、俺はずっと魔眼を開眼していたが、一秒先に見えたのは絶望だ。
俺はここまでの、どのタイミングで行動しても、返り討ちにあっていた。
一秒先の俺は、あらゆる急所を潰されていた。
頭、喉、心臓、肺……それぞれを潰すビジョンが見えつつも、さらに奴はその場にいるというビジョンも見えた。意味がわからなかった。
これが本当なら、一秒後、奴は五人いるということになる。
動けなかった。何をしても、無駄であるとわかってしまった。
何もできないまま、一秒が経過した。
奴は目の前にいた。動けない俺の目の前に。
物理法則を完全に無視したのかと思えるようなスライド移動で、瞬間移動したかのように目の前に来ていた。中割りの足りないアニメのように、唐突に。
そして、目の前に来た時には、すでに攻撃の動作を終えていた。
こんな動きを、昔どこかの格ゲーで見たことがあった。全てのキャラが永久コンボか即死コンボを持っている、世紀末なゲームだ。気づいた時には、俺は奴の双掌打をモロに受けていた。
肋骨が八本ぐらい同時に折れた。
衝撃はあったが、俺の身体は決して後ろに吹っ飛ぶことはなかった。背中からも同時に攻撃を受けたかのような圧迫感を覚えた。
ダメージは全て内部へと集約。
肺が潰れた。
「ごはっ!」
一瞬にして血が喉を駆け上がり、血反吐を吐いた。
「魔術師は肺を潰すに限るな……」
膝をついた俺に、奴は何事もないように、そう言った。
俺は地面に広がる自分の血を見ながら、心のどこかでなるほどと納得していた。
魔術師は肺を潰せばいい。詠唱ができなくなる。事実、俺はこの時点で治癒魔術を封じられた。もちろん、肺を潰されれば生命活動だって維持できなくなる。
つまり、どのみち致命傷だ。
「死んで人神に伝えるがいい。龍神オルステッドは、必ずお前を殺す、とな」
龍神。『七大列強』第二位。
オルステッドは胸を押さえてうずくまる俺に一瞥し、踵を返した。
俺は、それを油断と見た。
すでに致命傷を受け、敗北どころか死亡も目前。
その状態でなぜまだ戦おうと考えたのか、わからない。
視界の端でエリスが立ち上がろうとしていたからだろうか。この男が、俺が死んだのを見届けた後、わざわざ二人にトドメをさすと思ったからだろうか。
とにかく、俺は岩砲弾を奴に向かってぶちかました。
なぜもっと強い魔術を使わなかったのか、俺にはもっと上級の魔術も使えたのに。後になってもそれはわからない。ただ、おそらく一番使い慣れた魔術を使っただけなのだ。
できる限り硬い岩を、できる限り速い速度で、できる限りの回転を加えて。自分でも驚くほど、その岩砲弾は高威力だったと思う。
男と俺との極めて短い距離を、岩砲弾は赤熱しながら飛んだ。
[オルステッドは振り返り、岩砲弾を拳で粉砕する]
そして、砕かれた。
パラパラと落ちる岩は地面に落ちると、チリンチリンと金属音を立てた。
オルステッドは自分の拳を見ている。
「今のは岩砲弾か……凄まじい威力だな。こんな魔術で俺の体に傷をつけるとはな……」
オルステッドの手の甲は皮がベロンと剥がれていた。
かすり傷だ。
だめだ、岩砲弾ではこの男にダメージを与えることはできない。
「肺は潰したはずだが、無詠唱魔術か? それは人神から得た力か? 他には、どんな力を得た?」
オルステッドは俺を観察するように、見下ろしていた。
すぐにトドメをさせばいいだろうに、足をもぎ取ったバッタを見下ろすかのように、冷酷に。
苦しい……。
「ゲハッ……!」
俺は風魔術を作り、無理やり肺の中に空気を送り込む。
激しくむせる。
意味がない気がするが、無理やり送り、目一杯溜めてから息を止めた。
「面白い使い方をするな。今のはどんな意味がある? なぜ肺を無詠唱魔術で治癒しない?」
オルステッドは顎に手をやり、俺が苦しむのを興味深そうに見ている。
俺は朦朧とした意識で、右手で火球を生成しようとした。
火魔術は、魔力を注げば注ぐほど温度が上がり、規模が大きくなる。
速度と硬さの岩砲弾がダメなら、熱量と爆発力で……。
「それはもういい。『乱魔』!」
そんな浅はかな考えは、あっさりとかき消された。
オルステッドが俺に右手を向けた瞬間、手の先からまとまりかけていた魔力が掻き乱された。
手の先から魔力を出せども出せども、形にならず、散った。
俺は朦朧としつつも、理解していた。
手から出た魔力に干渉し、かき乱すことで魔術を無効化しているのだと。
右手を封じられたが、まだ俺には左手があった。
俺はもう片方の手で魔術を構築、オルステッドとの中間に、衝撃波を叩き込んだ。
ドンッと重い音がして、オルステッドが後ろに吹き飛ぶ。
同時に、俺もまた背後へと飛ぶ。
「むっ……『乱魔』を無効化したのか? いや、違うな……多重詠唱の一種か。無詠唱でやるとは器用な奴だな……こんな感じか?」
男は左手で、パチンと指を鳴らした。
すると、男の足元から五十センチ四方の小さな窓がせり上がってきた。
銀色で、華美な龍の装飾が施された、綺麗な窓だ。
「ほう、意外と難しいな」
俺はそれを気にせず、オルステッドに対しできうる限りで最も高火力の魔術を放つ。
イメージするのは、巨大な炎。キノコ雲。核爆発。
力をためてぶん殴るように、俺は愚直に魔力を集中させた。エリスやルイジェルドを巻き込んでしまうとかは考えなかった。すでに俺には、考える力は失われていた。
「開け『前龍門』」
オルステッドがぽつりと呟くと、窓が開いた。
その瞬間、俺の左手から魔術になろうとしていた魔力が、吸い取られた。
窓枠がバキンと音を立てて割れた。
同時に、オルステッドの近くで爆発が起こった。
それは想定していたものより圧倒的に小さく、簡単に回避されていた。
「凄まじい魔力量だ。このサイズの『前龍門』では耐え切れんか。まるでラプラス並みだな……人神の使徒なだけはある。だが、なぜ先ほどから肺を治癒しない? 俺の油断を誘っているのか?」
この時、俺の意識は途切れる寸前だった。
判断力なんてなかった。先ほどから満足に息ができていないのだ。
男はなおも観察するように俺を見ていた。
目が合う。
「終わりか?」
ほんの刹那で、オルステッドは俺に肉薄した。
すでに打つ手はなかった。
「魔術以外には、何もできないのか?」
魔術は封じられ、足はすくんで動かない。
圧倒的な殺意を前に、どうすることもできない。
視界の端で窓枠が消えていくが、何もできることがない。
「ごばっ!」
とっさに出そうとしたのは、ドルディア族の村で習得した、なけなしの咆哮。
「むっ……!」
俺の動作に、身構えるオルステッド。
しかしもちろん、血反吐を吐いただけで、何の効果もない。
「……魔力だけか。なんのつもりだ?」
もはや、俺には何もできない。魔術は封じられ、体術では勝てる要素が見当たらない。
あとできることと言えば、土下座しかない。
「まあいい、死ね」
が、オルステッドは土下座すらもさせてくれなかった。
「がふっ……」
超速で打ち出された貫手が、あっさりと俺の体を貫通した。
拳は確実に心臓を貫いた。
確実な致命傷。俺の治癒魔術では治せないであろう傷。
「あっけないな。人神め。闘気も纏えんものを手駒にしたのか。どういうつもりだ……」
引き抜かれる拳には、ベットリと俺の血が付いている。
立とうとするものの、体が言うことを聞かない。
意に反し、崩れ落ちる俺の体。
視界の端で、顔を上げたエリスが、こちらを呆然と見ているのが見えた。目が合う。
「あ……ああ、る、ルーデウ……ルーデウス……!」
薄れゆく意識の中で、俺は冷静に考える。
ああ、まずいな。死にたくない。
まだエリスとの約束を果たしていないんだ。せめて、あと二年。二年待ってほしい。
そうすれば、俺は心置きなく逝けるのに……。
魔力を集めろ、傷は一つだ。治癒魔術だ。
詠唱はできない、肺にも穴が開いている。だが、できる。ゆっくりと、魔力を集めるんだ。
治る、治るさ。まだ死ぬわけにはいかない。
「うわあああああぁぁああ!」
エリスが悲痛な叫びを上げる。
「大事な者だったのか? すまんなエリス・ボレアス・グレイラット。だが、お前もいずれわかる日が来る。いくぞ、ナナホシ」
「え、ええ……」
少女を連れて、オルステッドは悠々と歩み去る。
エリスは立ち上がれない。ダメージか、恐怖か。それともショックか。
ただ叫び声を上げるだけ。剣もなく、ただ泣き叫ぶだけ。
「ルイジェルド! ギレーヌ! お祖父様! お父様! お母様! テレーズ! パウロ! 誰でもいいから、誰でもいいから助けて! ルーデウスが死んじゃう!」
まずい、意識が薄れてきた。
まじかよ。ここで終わりかよ。
死にたく……………………………………な………い……。
「ねえオルステッド、一つ気になったのだけど……。こいつ、生かしておいたほうがいいんじゃないかしら?」
意識が途切れる寸前、そんな声がきこえたような気がした。
第十話 「胸にぽっかり開いた穴」
気づけば、白い場所にいた。
真っ白い空間。何もない空間。
いつもなら、ここは俺を嫌な気持ちにさせる。
体は三十四年間見慣れた醜いものへと戻り、前世の記憶がよみがえる。
後悔、葛藤、卑しさ、甘えた考え。十二年間の記憶が夢のように薄らぎ、落胆がこみ上げる。
長い夢を見ていたような気分に陥り、かきむしるような焦燥感が俺の胸を満たす。
だが、今回に限っては、そうならなかった。
いつものような卑屈な気持ちは湧き上がってこなかった。
その代わり、ポッカリ胸に穴が開いたような喪失感があった。
見てみると、胸に風穴が開いていた。
ああ、やっぱり死んだのか……。
「やあ」
ふと気づくと、人神が立っていた。
相変わらず苛つく笑みを浮かべているが、なぜか今日はそれに苛立ちを覚えない。
なぜだろうか。胸にポッカリ穴が開いているからだろうか。それとも、前に喧嘩腰はやめておこうと決めたからだろうか……まあ、いいか。
「まぁ、なんだ、残念だったね」
ああ、本当、残念だ。
「……今日はいつもと調子が違うね。大丈夫かい? 気分は悪くないかい?」
見ての通り、胸に穴が開いてるよ。
……なあ、一つ聞きたいんだけど、いいか?
「なんだい?」
あいつ、あのオルステッドって奴なんだけどさ。
お前の名前を聞いた瞬間に襲いかかってきたんだけど。
どうなってんだ?
「奴は悪い龍神だからね、善良な僕を目の敵にしているのさ」
善良ね……ま、お前は目の敵にされやすそうだしな。
でも、それなら事前に教えてくれてもよかったんじゃないか?
お前、いろいろと見えてるんだろ?
俺があそこでオルステッドと出会うってことも、わかってたんだろ?
もし一言、オルステッドに聞かれても、自分の名前は出すなって言ってくれれば俺だって……。
「いや、ごめん。実は『龍神』に関しては見えないんだ。未来も現在も見えない。君が奴と出会うこともわからなかったんだ」
そうなのか……どうして?
「奴にはそういう呪いが掛かっているからさ」
呪い。そういうのもあるのか。
「うん。君の世界にはなかったのかい? 生まれつき、魔力が異常を起こしていて、何か変な能力を持ってる子ってのは」
俺の世界には魔力って概念がなかったからな。
霊感が強いって自称する奴はいたけど、正直、信憑性には欠けてたよ。
「へえ、そうなんだ。こっちでは、呪子って言ってね、変なのがいるんだよ。オルステッドもその一人さ。まあ、彼は他にも三つぐらい呪いを持ってるけどね」
全部で四つか。
そりゃすごいや。そういや、聞いたな。神子と呪子だっけか。
「そうそう。同じものなんだけどね。人間は分けて考えるのが好きなんだよ」
そっか。で、あいつはどんな呪いを持ってるんだ?
「ほら、ルイジェルドやエリスが怯えていただろ? あれが奴の呪いの一つだよ。この世界のあらゆる生物に嫌悪されるか恐怖されるんだ」
皆に嫌われるのか、そりゃあなんていうか、嫌だな。
俺ならすぐに心が折れる。嫌われ者の気持ちはわかるんだ。
「おっと、同情は必要ないよ。彼は生まれつき、この世界を滅ぼそうとしている悪者だからね」
まあ、そう言うなよ。
周囲から悪感情ばっかり向けられれば、誰だって世界の一つぐらい滅ぼしたくなるだろうさ。
俺だって前世では、そういう考えを持ったことがあるよ。
みんな死んじまえなんて、よくワールドワイドな網でぼやいてたもんだ。
「ふうん、そういうものかい。僕もあいつは嫌いだから、知ったこっちゃないんだけど」
ん? お前にも呪いの影響があるのか? 見えないってのも、その呪いのせいなんだよな?
嫌われる呪いと、見えなくなる呪いと……あとは?
「さぁね、見えないからよく知らないんだよ」
そっか……でも、そういう危険な奴ならなおさらだ。
この世界にはこういう奴もいるって、前もって教えてほしかったな。
ああいうのはいきなりすぎて困るんだ。
「僕だって、彼と君が出会うなんて思っていなかったんだ。この広い世界を歩きまわって出会う確率なんて……」
砂漠でゴマの一粒を見つけるようなものか。
あ、そういえば、俺はあいつのこと、嫌悪も恐怖もしなかったんだが。
どういうことなんだ?
「それは、君が異世界から来たからじゃないかな?」
異世界人は呪いの影響を受けないのか?
「そうみたいだね。ルイジェルドと出会った時もそうだったろ?」
……え? ちょっとまて、どういうことだ?
ルイジェルドもその呪子ってやつなのか?
「いいや、あれはラプラスの槍の呪いさ。ラプラスも『恐怖の呪い』を持っていたけれど、それを槍に移して、それをスペルド族になすりつけたのさ。緑色の髪をキーとするようにしてね」
呪い? なすりつけた……?
おい。なんだよ、どういうことだ。お前、それ、最初から知ってたのか?
わかってて手伝わせたのか?
無駄なことをさせたのか?
「いや、勘違いしないでくれよ。スペルド族全体への呪いは時間経過でもう消えかけている。ルイジェルド自身にはまだ少し呪いが残っているけど、髪を切ったおかげで急速に薄れつつあるんだ」
そういや、シルフィはイジメられてたけど、恐れられているって感じじゃなかったもんな。
ところで、なんで髪なんだ?
魔力の源だからか?
「ラプラスの髪も緑だったからさ」
ああ、なるほどね。俺の世界でもそういうことはあったな。
共通項や語呂を利用して呪いをかけたり解いたりとか。
「何にせよ、君に関わったおかげで、呪いは消えつつある。まだ根強く差別意識が残っているけど、それは時間経過とルイジェルドの努力次第でどうにかなるものさ」
つまり、無駄じゃなかったってことか?
そりゃよかった……お前も、ちゃんと考えて行動させてたんだな。
「ま、完全に解消するのは難しいだろうけどね」
まあ、難しい問題だもんな。
でも、そうか……とにかく、よかった。
「うん、よかったね。君をルイジェルドと引きあわせたかいがあったというものだよ」
そんな理由で引きあわせたのか?
それならそうと言ってくれればよかったじゃないか。
「君、最初の頃は僕の言葉なんて聞く気なんてなかったでしょ? 余裕もなかったし」
……まあ、それもそうか。
喧嘩腰で突っぱねてただろうな。確かに。
それにしても、そのルイジェルドも、オルステッドには簡単にやられちまったな……。
あんなに簡単にやられるとは思わなかったよ。
「まあ、あいつはルイジェルドじゃ無理だろうね」
なにせ、七大列強だもんな。どうやったら勝てたんだ?
「勝てないよ」
勝てないか。やっぱり地力が違いすぎるからか?
「彼はね、この世界で最強なんだ。いくつもの呪いで制約を受ける身でありながらね」
最強? でも、龍神って七大列強の二位だよな? 一位は?
「技神も強いよ。でも本気で戦えば、勝つのはオルステッドさ。オルステッドは、この世界に現存する全ての技と術を扱える。それに加え、龍神特有の固有魔術まで使えるんだ」
全ての技と術か。どっかの世紀末救世主みたいな奴だな。
「へえ、君の世界にもそういうのがいたのかい?」
それまでに戦った相手の技を全てコピーするんだ。
もっとも、相手の技なんか使わなくても強いんだけどな。
指先一つで相手がボンッてなるぐらいに。
「指先一つか。すごいもんだね。でも、オルステッドも凄いよ。彼が本気になれば、この世界を滅ぼせる」
強いという表現が霞むな。
異常? 天災?
「呪いのせいで本気は出せないんだけどね」
そうなのか、呪いってのも厄介だな。
ところで、一ついいか?
「なんだい?」
お前さ、さっき呪いのことは知らないって言ったよな。
嫌われる呪いと、見えなくなる呪いの他には知らないって言ったのに、なんで本気を出せないって知ってるんだ?
「…………ええと」
ああ、いいよ。
最後なんだ、フレンドリーにいこう。
お前が何を隠していても、俺は気にしないよ。ルイジェルドのことは好意だってわかったしな。この間も、お前のおかげでリーリャとアイシャも助け出せた。それを鑑みれば、多少嘘をつかれたところで気にもならんよ。これから先、お前が俺に何かをさせようとしていたとしても、全ては水の泡となったわけだしな。
本当なら、もっと色々聞きたいことはあるんだけどな。
なんで魔界大帝と引きあわせたのか、とか。他の行方不明者の居場所はどこか、とか。そもそも、お前の本当の目的は何なのか、とか。今更聞いてもしょうがないことばっかりだ。
ま、なんだ。お互い失敗した者同士、フレンドリーにいこう。
無礼講で、パーっと騒ごう。裸踊りもかくし芸もオッケー、もちろん腹芸だって気にしないさ。
「最後?」
ああ、最後さ。
だってそうだろ。俺は死んだんだから。
「なるほど、それで自暴自棄になっているのか……最初の時とは真逆だね?」
あの時は、何がなんだかわからないまま死んだと思ったからな。
今回は、まあ、しょうがない。
それに、なんとなく、死ぬ間際にここに来るような気はしてたからな。
人が死ねばどこに行くのかはわからんが、死ぬ間際にお前が話しかけてくるとは思ってたよ。
────っと、意識が薄れてきた。
そろそろお別れらしいな。最後にお前と穏やかな気分で話ができてよかったよ。
「そうかい……じゃあ、君に朗報だ」
ん?
「君、死んでないよ」
気づけば、胸の穴は消えていた。
★ ★ ★
ふと、目が覚めた。
エリスが近くにいた。目の前だ。俺はエリスを見上げるように、寝転んでいるのだ。
後頭部が暖かく、膝枕だと、すぐに気づいた。
エリスは不安げな顔で見たくないものを見るような目で俺を見ていたが、俺が目を覚ますと、ほっとした顔になった。
目が真っ赤だ。
「る、ルーデウス……目が覚めたの!?」
「う……げはっ!」
何かを喋ろうとして、血が吐き出された。
「ルーデウス!」
エリスに抱きかかえられる。
「ゲホッ……ゲホッ……!」
俺は血を吐き終え、激しくむせた。
エリスに背中を撫でられる。
「……大丈夫?」
エリスの戸惑う表情を見て、俺も首をかしげた。
「なんで……生きてる……?」
胸の傷は、完全にふさがっていた。
完全というのは語弊があるか。俺のローブの中央には大穴が開き、その奥に見える地肌には、まるで溶接したような痕が残っている。
はて、おかしなことだ。俺の右手は寄生獣ではなく、ただの恋人だというのに。
「さっき、あの女が、何か言ったら、あの、オルステッドとかいうのが、治療魔術でルーデウスを治療して……」
俺の純粋な疑問を、自分に対する質問と思ったのか、エリスはしどろもどろになりながら答えてくれた。
「女?」
「ナナホシって言われてた」
ナナホシ。あの少女か。
そういえば、そんな呼ばれ方をしていたな。しかし、ナナホシ、どこかで聞いたことあるな。
それも、ここ一年ぐらいの間でだ。どこだったか、思い出せない。
「殺した相手をわざわざ治療したのか……」
何を考えているのか。
しかし、確実に心臓を貫いていたはずだ。
重要な臓器の破損は中級の治療魔術では、回復しきれない。
てことは上級か、それ以上。
オルステッドは致死レベルの傷でさえ一瞬で治癒する魔術をも使えるのだ。
この世界の全ての技と術を使えるというのも、あながち嘘ではないのかもしれない。
「完敗だな……」
格が違うとは、ああいうことを言うのだろう。
七大列強二位。人神の話では世界最強か。どちらにせよ伊達ではない。
ルイジェルドも、エリスも、俺も、完封された。
余裕の完封だ。しかも奴は本気など出しちゃいないらしい。
「ルイジェルドは?」
「まだ目が覚めてないわ」
見れば、道の端にルイジェルドが寝かされており、馬車も道の端へと寄せられ、焚き火がたかれている。全てエリス一人でやったのか。
「ルイジェルドが横になってるところを見るのは、初めてですね」
「ルーデウス、まだしゃべらないで。さっき血を吐いて……」
「もう大丈夫ですよ。喉に残っていた分だけですから」
そう言いつつも、俺はエリスの膝からどかない。
どきたくない。ずっとここにいたい。今から寝返りを打って反対を向いたらどうなるだろうか。そんなことばかりが頭に浮かんでくる。
生存本能からくるものだろうか。人は死にかけると子孫を残そうとするらしいし……。
あまり実感がわかないのだが。ああ、もういいか。難しいことは考えないことにしよう。
転がっちゃおう。
「生きてるって、素晴らしいな」
そう言いつつ、俺は身体を回転させ、エリスの腰にすがりつくように抱きついた。
思い切り息を吸い込むと、なんともいえない甘酸っぱい匂いがしたような気がした。
「ルーデウス……随分と、元気ね」
「んー、なんかね、いろんな物があり余ってる感じがするんですよ」
普段よりもなお、だ。あのオルステッドという男のせいだろうか。
それとも、人神の夢を見ていたからだろうか。
重ねて言うが、生死の境をさまよったという感覚は俺にはあまりない。
だが、目がさめる前より元気なのは間違いなかった。
「じゃあ、叩いても大丈夫なの?」
エリスの震える声が降ってくる。お怒りのようだ。
まあ、仕方ないね。心配してたのに、いきなりセクハラだもんな。そりゃあ俺だって怒るよ。
「いいですとも」
殴られた。
コツンと、軽く。
そして、胸元まで引き上げられ、頭を抱きしめられた。エリスの柔らかい胸の感触が頬に伝わってくる。その奥の心臓の鼓動と、上から聞こえる静かな嗚咽も。
「…………うっ……ぐすっ……」
エリスは泣いていた。静かに泣いていた。
「よかった……」
エリスはぽつりと呟いた。
俺は脱力し、ぽんぽんと彼女の背中を叩いた。
第十一話 「旅の終わり」
あれから三日が経過し、俺たちはアスラ王国へと入った。
目的地はすでに目前……いや、すでに到着したと言っても過言ではないだろう。
だというのに一行の表情が晴れないのは、先日の出来事が尾を引いているからだ。
街道ですれ違う人々の明るい顔とのギャップが激しい。
なにせ、完敗だったからな。
あっけなく全滅させられて、俺は命まで奪われた。なんの気まぐれか、わざわざ生き返らせてもらったようだが。それがなければ、俺はこの世にいない。
もっとも、俺としては、あまり実感が湧かない。
自分でも不思議なことだが、俺はあの時のことをあまり恐怖していない。
トドメをさされる瞬間、確かに死にたくないと思った。
トラウマになってもおかしくないと思ったというのに、目覚めた時には、なぜかスッキリ爽やか……というわけではなかったが、「ああ、夢か」という感覚があった。
悪夢を見た時と同じ感覚だ。
死ぬ寸前の感覚と夢がつながっていたからか、全て夢だったと感じているのかもしれない。
そう考えると、人神はそれを想定して、俺の意識に割り込んできたのだろうか。
正直、本能的に拒否したくてたまらない感じなのだが、ルイジェルドのことも考えていてくれたようだし、実は悪い奴ではないのかもしれない。
それはそれとして、俺が死にかけて以来、エリスとの距離がどうにも近くなった。
以前は馬車に座っていると、斜め前ぐらいに突っ立って、
「バランスの訓練よ、ルーデウスもやったら?」
なんて言ってたのだが、最近は座るようになった。
俺の横に。太ももが密着するような距離で、である。
そんな距離になると、いろいろと見えてしまうものもある。
例えば昨日など、エリスの服とズボンの裾から地肌が覗いていた。そうしたものが覗いていると、つい撫でたくなってしまうのが人の心というものだ。なので右手でついっと撫でてみたら、真っ赤な顔をして睨まれた。
さすがの俺も少々戸惑った。
殴られなかったのだ。エリスが俺を殴らない。
殴られるようなことをしても、殴らないのだ。
顔を真っ赤にして睨むだけ。ただ、じっと見てくるだけなのだ。
しかも、エリスは変わらず、俺に密着して座っている。
今まではそうした行為をすると、一歩引いた距離を取られたものだが、今は距離が近いまま。
真面目な話、今度はズボンの中に手を突っ込みたくなるから、そろそろ離れてほしい。笑って済ませられることと済ませられないことがあるのは知っている。そして俺は済ませられないことの方がしたいのだと自分でもわかっている。我慢しているのだ。
そんな俺の葛藤を知ってか知らずか、エリスとの距離は近い。
「…………」
手を自由にしているとエリスの方に伸ばしてしまうので、俺はいま左手で魔術を作ろうとし、右手でその魔力をかき乱すという作業をしていた。
オルステッドが使っていた魔術だ。
確か『乱魔』とか言ったか。
手から出される魔力が形になる直前に、別の魔力で妨害し、散らす。
単純で、消費魔力も少ないが凄い技術だ。思い返せば、シーローンでハマった王級の結界も似たような方法で魔術を無効化していたのだろう。
口で言うのは簡単だが、実際にやろうとするとなかなか難しい。
左手で魔術を使おうとしているからか、魔術が不完全ながら形になってしまうことが多い。
オルステッドのように、完全に無効化するのはなかなか骨だ。
しかし、これだけでも牽制にはなるだろう。
いや、いいことを教えてもらった。
「ねえルーデウス、さっきから何してるの?」
「オルステッドが使っていた魔術を真似しようと思いまして」
そう言うと、エリスは俺の手を凝視しだした。
俺の左手に歪な形をした小さな石弾ができて、コロリと落ちる。
また失敗だ。まるで両手でじゃんけんをしているような気分だ。どうしても左手を勝たせてしまう。適当じゃダメなんだろう。
うん? 適当じゃダメってことは、かき乱すときに法則があるってことか。なら、法則を考慮した魔力の放出をすれば、逆に乱魔を無効化できるってことか?
夢が広がるな。
「どういう魔術なの?」
「魔術を無効化する魔術です」
「そんなこと、できるの?」
「いま練習しているところです」
「なんでそんなことしてるの?」
「最近、魔術を封じられて何もできないケースが多かったので、研究ですかね。まぁ、またオルステッドに会って戦うことになったら、逃げ切れるぐらいにはなっておきたいじゃないですか」
エリスはその言葉で絶句して、黙りこんでしまった。
しばらく、石弾がコロコロと落ちる音だけが続いた。
「ねえ、ルーデウスはなんでそんなに強いの?」
エリスはずっと黙っていたが、ふと、そんなことを聞いてきた。
俺は強いのだろうか。
いや、そんなことはあるまい。自慢じゃないが、俺はここ数年、自分の強さを実感することはなかった。無力感だけが残る毎日だ。
「エリスの方が強いと思いますけど?」
「そんなことないわよ」
「……」
「……」
そこで会話が途切れた。
エリスは何かを聞きたそうに、しかし言いにくそうに口をつぐんでいる。
なんだろうか。
わからない。いや、わからないってことはないか。
「先日、簡単にやられてしまったことを気にしてるんですか?」
「…………うん」
仕方ないところだろう。
人神曰く、奴は世界最強の龍神様という話だ。あのルイジェルドですら軽くあしらわれた。
相手が悪い。
この世には、努力では到達できない領域が存在する。
生前、俺はいろんなことをやり、そこそこ上位になったこともあるが、最上級に到達したことは一度もなかった。やりこんだゲーム、これなら負けないと思ったものでも、上には上がいた。
オルステッドは、いろんな制限を課せられているらしい。
それでも体術でルイジェルドを上回り、エリスを片手であしらい、俺を完全に無力化した。
しかも、最大HPにダメージをぴったり合わせるような戦い方で倒された。
まだまだ余力を残しているってことだ。
本気を出せばどれぐらい強いのか、さっぱりわからない。
呪いのせいで本気は出せないらしいが……本気なんか出せなくても、あいつには、勝てない。
おそらく、どれだけ努力しても勝てない。
「相手が悪かったんですよ。あれは仕方がありません」
「…………でも」
エリスが悩む気持ちもわかる。
なにせ、エリスは一発だったからな。剣を受け止められて、そのままぶっ飛ばされた。
「エリスはまだ若いですし、努力しだいでは強くなれますよ」
「そうかしら……?」
「ええ、ギレーヌだって、ルイジェルドだって、そう言ってるじゃないですか」
エリスがふと顔を上げ、まっすぐに俺を見てくる。
「ルーデウスは死ぬところだったのよ? どうして、そんな……簡単に言えるの?」
そりゃあ、あまり感覚が残ってないからだ。
俺は戦おうなんて思ってない。次にあいつの顔を見たら、俺はロケットのように逃げ出すだろう。あるいはネズミのように物陰に隠れるか。逃げ切れないなら、今度は命乞いをするかもしれない。
願わくば、その光景はエリスには見られたくないものだ。
しかし、その情けない本音を口にするのは恥ずかしい。
「次は、死にたくないですからね」
「…………そうね、死にたくは、ないわよね」
「安心してください。もしエリスが危ない目にあっても、なんとか抱えて逃げられるぐらいにはなっておきますから」
エリスは難しい顔をして、俺の肩に頭を載せてきた。
今ここで頭でも撫でてやれば、好感度が上がるかもしれないが、右手は乱魔の最中である。
「まあ、何にせよ、もう少し強くならないといけませんよ」
もう少し、だ。
さすがに、この世界で最強にはなれない。この世界の天井は高すぎる。前世でも俺は世界一になれなかった。その才能の片鱗もなく、努力の仕方もヘタだった。この世界における才能がどれぐらいあるのかわからないが、俺は自分を信じて愚直に何かに打ち込むことはできそうもない。
でも唐突に変な奴に襲われても逃げ切れるくらいにはなっておきたい。
俺はエリスの髪に顔を埋め、くんかくんかと匂いをかぎつつ、そんなことを考えるのであった。
夜になり、エリスが寝静まると、俺はルイジェルドと会話をする。
あの日以来、彼の口数はこれまでにもまして減ってしまった。
普段からあまり饒舌なほうではないのだが、それがむっつりと押し黙るようになってしまった。
彼は責任感の強い男だ。無事に送り届けると約束したのに、それが守れなかったと思っているのかもしれない。
運よくとはいえ、俺はこの通りビンビンだというのに。
「あのオルステッドという男、龍神だそうですよ。『七大列強』第二位の」
まずはジャブとして、そんな言葉から入った。
相手が強いのだから仕方がない。そんなニュアンスを含ませつつ。
「そうか、どうりでな……」
「強いですよね、あの後、僕も手も足も出せずにやられましたよ」
「一目見た瞬間勝てる気がしないと思ったのはラプラス以来だ」
人神曰く、オルステッドはそのラプラスより強いらしい。
本気で戦えない制約がついているらしいが……ルイジェルドはそのことを知るまい。
手加減され、体術だけであしらわれた。その事実はルイジェルドにとってショックだったのかもしれないと、思ったが、
「俺も『七大列強』の上位に対抗できるとは思っていない。奴らは人知の及ばぬ本当の化け物だ。ああいった輩と一本道で遭遇するのは、運が悪いとしか言えん。そして、生き残れたことは運がいいとしか言えん」
言い訳のような言葉であったが、その声音にはどこか自責の念が含まれているように感じた。
どうしようもないが、それと自分が役目を果たせなかったのは別であると、そう思っているのかもしれない。
「ルーデウス、もしまたああいう奴と出会うことがあっても、決して喧嘩は売るなよ。目も合わせるな。今回のようなことになりたくなければな」
「え、ええ。まあ、多分次は目を逸らして通り過ぎます」
怒られてしまった。
まあ、俺が声を掛けなければただすれ違うだけだったはずだしな。そこは反省しておこう。
でも、最初はそんな危なそうな奴には見えなかったんだけどな……いや、ルイジェルドとエリスがあれだけの反応を示していたんだ、もっと警戒してしかるべきだった。
「では、何に悩んでいるんですか?」
聞くと、ルイジェルドはジロリと俺をねめつけた。
「ヒトガミとはなんだ?」
おう。そのことか。
「奴は最初、俺たちを見逃すつもりだった。殺気を撒き散らしつつも、眼中にはなかった。だが、ヒトガミの名前を口にした瞬間、殺気が完全にお前に向いた」
俺は目を閉じた。
言うべきか、言わざるべきか。以前に答えを出したつもりだったが……。
人神はああ見えて、それほど悪い奴ではないようだし、あんな目にあったというのに隠し事をしているという事実も嫌だった。
なので、言うことにした。
「実は、人神というのは────」
あれだけ悩んでいたというのに、決めてしまえばすぐだった。
口もスラスラと動いた。
転移の時から、夢に時折人神と名乗る正体不明の人物が出てくること。
その人物がルイジェルドを助けるように助言したこと。
それ以外にもいくつもの助言を授けてくれたこと。
自分の不審な行動はその助言に従っていたからということ。
そして、どうやらその人神と龍神は敵対関係にあるということ。
人神との会話はおぼろげで、忘れていることも多かったと思うが、大まかなことは全て伝えた。
「人神と龍神……太古の七神か……にわかには信じられん話だ」
「でしょうね」
「だが、納得のいく部分もある」
そう言うと、ルイジェルドは無言になった。
焚き火のパチパチと燃える音だけが、その場を支配する。
火の作り出す影がゆらゆらと揺れ、一人の老戦士の顔を描き出す。
ルイジェルドは種族柄若くみえるが、その表情には歴戦を思わせる何かがある。
ふと、俺は最後の夢で、ルイジェルドの呪いについて触れたことを思い出す。
「そういえば、ルイジェルドさん。スペルド族の汚名ですが、あれは呪いらしいですよ」
「……なに?」
「正確に言えば、ラプラスが自分に掛かっていた呪いを槍に移して、その槍を種族全体に及ぶようにした……という感じだそうです」
「そうか……呪いか……」
朗報と思って話したのだが、ルイジェルドは暗い顔をしてさらに考えこんでしまった。
「呪いを移すなど聞いたこともないが、ラプラスなら可能か。奴はなんでもできたからな」
俺はそれほど詳しくないが、呪いというものに関してはルイジェルドの方が詳しいだろう。
彼はしばらくあれこれと考えていたようだが、最後に力なく笑った。
「呪いならば、解く方法はないな」
「そうなんですか?」
「ああ。呪いは解く方法がないから呪いなのだ」
呪いを解く方法ってのはないのか。
「種族全体に掛かる呪いなど聞いたこともないが……神の言うことならば、本当なのだろう」
俺は無駄なことをしてきたのだ、と自嘲げに笑う。
光の加減だと思うが、目の端に涙が溜まっているようにすら見えた。
「でも」
「なんだ?」
「人神は、槍での呪いは通常とは違うから、時間経過で消えかけていると言ってました」
「なに?」
「ルイジェルドさん本人に残された呪いも、髪を切ったことで急速に薄れつつあると」
「本当か!」
ルイジェルドが唐突に大きな声を上げたせいで、エリスが「んぅ……」と声を出し、もぞりと動いた。この話は彼女にも聞かせたほうが良かったかもしれないが……。
まあ、起きてからでいいか。
「ええ。いま残っているのは呪いの残滓と、最初の呪いでできた先入観だけだそうです。ルイジェルドさんのこれからの努力次第で、スペルド族の人気は少しずつ回復していくそうです」
「そうか……なるほど、そうだったか……」
「でも、人神の言うことです。多少は信用できるとはいえ、鵜呑みにはしないほうがいいかもしれません。今まで通り慎重にやったほうがいいでしょう」
「わかっている。だが、それを聞けただけで俺には十分だ」
ルイジェルドは無言になった。
もう光の加減でそう見えているだけではなかった。
ルイジェルドは涙を流していた。
「じゃあ、僕もそろそろ寝ますね」
「ああ」
俺はその涙を見なかったことにした。
俺たちの頼れる戦士ルイジェルドは、涙なんて流さない強い男なのだ。
★ ★ ★
そして、それから一ヶ月。
俺たちはまっすぐに北を目指す。
王都を経由せず、細い道を北へ、北へ。
小さな農村を転々と経由し、一面の麦畑や水車小屋を横目に見つつ、北へ。
情報なんて集めなかった。できる限りのスピードで北を目指した。
情報は難民キャンプにたどり着けば全てわかると思っていたが、それ以上に、あと少しだから、早く到着したいという考えがあった。
そして、フィットア領にたどり着いた。
フィットア領には、何もなかった。
かつてそこに何かがあったであろう場所にも、何もなかった。一面の麦畑も、バティルスの花畑も、水車小屋も、家畜小屋もなかった。
ただ草原が広がっているだけだった。広い広い草原だ。
その光景に寂寥感を持ちながら、現在唯一ともいえる、フィットア領の町、難民キャンプへと到着する。
最終目的地。
その入り口まであと一歩というところで、ルイジェルドは馬車を止めた。
「ん? どうしました?」
ルイジェルドは御者台を降りてしまう。
魔物でもいるのかと思い周囲を見渡すが、敵影はない。
ルイジェルドは馬車の後ろまで歩いてくると、言った。
「俺はここで別れる」
「えっ!」
唐突に宣言された言葉に、俺は驚きの声を上げていた。
エリスも目を丸くしている。
「ちょ、ちょっと待ってください」
俺たちは転げるように馬車から降りて、ルイジェルドと向かい合う。
早すぎる。難民キャンプに来たばかりだ。いや、あと一歩というところで到着すらしていない。
「せめて一日ぐらい休んだら、いえ、町の中ぐらいまでは一緒に入ったらどうですか?」
「そうよ、だって……」
「必要ない」
そっけない言葉で、ルイジェルドは俺たちを見る。
「ここには戦士しかいない。お守りは必要あるまい」
「…………」
その言葉に、エリスが押し黙った。
正直、俺も少々忘れていたのかもしれない。
ルイジェルドが、あくまで俺たちを故郷に送り届けるためにここまで付いてきたということを。
その目的が達成された以上、別れはあるのだということを。
ずっと一緒にいるものだと思っていた。
「ルイジェルドさん……」
口を開き、俺は迷う。
引き止めれば、留まってはくれるだろうか……。
いや、思い返せば、俺はこの男に多大な苦労を掛けてきた。確かに苦労を掛けられたこともあったが、情けない部分を見せたのは俺の方が多い。
だというのに、彼は俺を戦士と認めてくれている。
これ以上、頼るべきではないだろう。
「ルイジェルドさんがいなければ、三年でここまで来ることはできなかったでしょう」
「いや、お前なら可能だったはずだ」
「そんなことはありません。僕は抜けているところがあるので、どこかで躓いたと思います」
「そう言えるうちは大丈夫だ」
為す術もない状況というのは結構あった。
例えば、シーローンで囚われた時など、ルイジェルドという存在がいなければ、俺はもっと慌て、取り乱していただろう。
「……ルーデウス、前にも言ったが」
ルイジェルドはいつにも増して静かな顔で俺を見下ろす。
「お前は魔術師として、すでに完成の域にある。それだけの才能を持ちながら増長もしていない。その若さでそれだけのことができるということに自覚を持て」
その言葉を、俺は複雑な気持ちで受け止めた。
若さといっても、俺の体感年齢はすでに四十歳を超えている。
増長していないのは、その時の記憶があるからだ。
だが、四十歳といっても、ルイジェルドの年齢から見れば「若い」の範疇に入るだろう。
「僕は……」
ここで自分のダメな部分を羅列することができた。
だが、それはあまりにも情けない気がした。俺はこの男の前では、少々背伸びをしたい。
「いえ、わかりました。ルイジェルドさん、今まで本当にお世話になりました」
そう言って頭を下げようとすると、掴んで止められた。
「ルーデウス、俺に頭は下げるな」
「……どうして?」
「お前は俺に世話になったと考えているかもしれんが、俺はお前に世話になったと考えている。お前のおかげで、一族の名誉回復にも希望の兆しが見えた気がするのだ」
「僕は、何もしてませんよ。ほとんど何もできなかった」
魔大陸においては、デッドエンドの名前をいいものにしようとはした。しかし、それはあくまで冒険者としてという枠組みを出ることはなかったように思う。
ミリス大陸ではネームバリューが使えなくなり、別の方法を考えなければと思っているうちに、どんどん後回しになった。
結局、中央大陸に来てからは、何もできなかった。
今までやってきたことも、少しは影響したと思うけれど、あくまでそれは、少しだ。
世界に大きく残った迫害の歴史を消すことはもちろん、スペルド族に対する偏見をどうにかすることはできなかった。
「いや、お前は色々とやってくれた。俺のように、愚直に子供を助けるだけでなく、いろんな方法があるのだと教えてくれた」
「でも、どれも効果は薄かった」
「だが、確かに変わった。俺は全て覚えているぞ。リカリスの町で、お前の策略でスペルド族を恐れないと言った老婆の言葉を。デッドエンドと聞いて恐れることなく、愉快そうに笑った冒険者の顔を。スペルド族と聞いても認めてくれたドルディア族の戦士との距離感を。家族との再会に涙しながら礼を言った、シーローンの兵士を」
最初の二つはともかく、後の二つはルイジェルドが自分で頑張ったことだ。
俺は何もやっていない。
「……それはルイジェルドさん、あなた自身の力です」
「いや。俺は一人では何もできなかった。戦争から四〇〇年、俺は一人で動き、一歩も前進できなかった。その俺に『一歩』を与えてくれたのはお前だ、ルーデウス」
「……でも、それはあくまで人神の助言で」
「見たこともない神などどうでもいい。実際に助けてくれたのはお前だ。お前がどう思おうと、俺はお前に恩義を感じている。だから頭は下げるな。俺とお前は対等だ。礼を言うなら目を見ろ」
ルイジェルドはそう言って、俺に向かって手を差し伸べた。
俺は彼の目を見ながら、手を握った。
「もう一度言う。ルーデウス、世話になったな」
「こちらこそ、お世話になりました」
手をぎゅっと握ると、ルイジェルドの力強さが伝わってきた。
目頭が熱くなってきた。
こんな情けない俺を、失敗ばかりしてきた俺を、ルイジェルドは認めてくれているのだ。
しばらくして、すっと手が離れる。その手は横へと動き、エリスの頭へと乗せられた。
「エリス」
「……なによ」
「最後に子供扱いをするが、いいか?」
「いいわよ、別に」
エリスはぶっきらぼうに答えた。
ルイジェルドは薄く微笑みながら、エリスの頭を撫でる。
「エリス、お前には才能がある。俺なんかよりも遥かに強くなれる才能だ」
「嘘よ、だって……あいつに……」
エリスは口をへの字に結んで、ムッとした顔をしていた。
ルイジェルドはフッと笑い、いつも訓練で口にする言葉を口にした。
「神の名を冠する者と戦い、その技を受けた。その意味が……」
わかるか? と。
エリスはルイジェルドをキッと睨み。やがて、ハッと眼を見開いた。
「…………わかるわ」
「よし、いい子だ」
ルイジェルドはポンポンとエリスの頭を叩き、その手を外した。
エリスは口をへの字に結んで、拳を握りしめている。
泣きそうなのを、必死に我慢しているように見えた。
俺は彼女から目を逸らし、ルイジェルドに問いかける。
「ルイジェルドさんは、これからどうするんですか?」
「わからん、しばらくは中央大陸でスペルド族の生き残りを探してみるつもりだ。俺一人では、名誉の回復など夢のまた夢だからな」
「そうですか、頑張ってください。僕も暇があれば、何か手を打ってみることにします」
「……フッ、なら俺も、暇があればお前の母親を探してみるとしよう」
ルイジェルドはそう言って背を向ける。
彼には、旅の準備など必要ない。着の身着のままで歩き出しても生きていけるのだ。
だが、ふと立ち止まった。
「そういえば、これを返しておかなければな」
そう言って、ルイジェルドは首から下げたペンダントを外す。
ロキシーからもらったペンダントだ。ミグルド族のペンダント。俺とロキシーをつなぐ、たった一つのアイテム……だったものだ。
「それは、ルイジェルドさんが持っていてください」
「いいのか? 大切なものなのだろう?」
「大切なものだからですよ」
そう言うと、ルイジェルドはコクリと頷いた。
受け取ってくれるようだ。
「ではな、ルーデウス、エリス…………また会おう」
ルイジェルドはそう言って、俺たちの元から去っていく。
付いてくると言った時はあれこれと話をしたのに、去るときは一瞬だった。
言いたいことはたくさんあった。
魔大陸で出会い、アスラ王国に至るまで。本当にいろんなことがあった。言葉にできないぐらい、たくさんのこと、たくさんの気持ち……別れたくない、仲間だという気持ち。
『また会おう』
その気持ちを一言でまとめ、ルイジェルドの背中は遠ざかる。
そうだ、また会えばいいのだ。
きっと会える。互いに生きていれば、必ず……。
俺とエリスはルイジェルドの姿を、見えなくなるまで見送った。
ただ静かに、今までの感謝を込めて。
こうして、俺たちの旅は終わりを告げた。
第十二話 「災害の現実」
難民キャンプは閑散としていた。
規模としては村サイズ。あるいは魔大陸ならギリギリ町といえるかもしれないが、活気はなかった。全体的にひっそりとした空気が漂っていた。
規模に対して、人も少ない。
急造で拵えたであろうログハウスの中には人の気配があるため、滞在している人間は少なからずいるようだが、活力は感じない。
空気が淀んでいた。
そんな難民キャンプの中央。
冒険者ギルドのような場所に俺たちは赴いた。難民キャンプの本部と入り口に書かれている。
中に入ると、人はそれなりにいたが、やはりここも陰鬱としていた。
いやな予感しかしなかった。
「ルーデウス、あれ……」
エリスの指さす先に、今回の件で行方不明になった者の名前が載った紙があった。
細かい字でビッシリと、村や町ごとに、五十音順に書き込まれている。
その一番上には、フィットア領領主ジェイムズ・ボレアス・グレイラットの名前で『行方不明者・死亡者の情報を求む』と書いてある。
「あとにしましょう」
「うん」
凄まじい量の死亡者数。そして領主の名前がサウロスでないこと。
その二つに不安を覚えつつ、俺たちは建物の奥へと進んだ。
カウンターでエリスの名前を告げると、受付のおばさんは、すぐに奥へと引っ込んだ。
そして、凄い勢いで一組の男女を引き連れ、戻ってきた。
見覚えのある男女だった。片方は、白髪に髭を蓄え、執事然とした顔をしつつも、やや裕福そうな町人じみた服装をした壮年の男。アルフォンス。
もう一人は、チョコレート色の肌に剣士風の格好をした女。
「ギレーヌ!」
エリスが喜色満面の笑みを浮かべ、彼女に向かって走った。
尻尾でもあるのかと思えるほど嬉しそうだった。
俺も嬉しい。これまでギレーヌの情報はなかったが、彼女は元気そうだ。パウロのところに情報がいってなかったのは、この一年ですれ違いになったからかもしれない。
ギレーヌもまた、エリスの顔を見て、顔をほころばせた。
「エリス、いや、エリス様、よく無事に……」
「……もう、エリスでいいわよ」
ギレーヌはしばらく嬉しそうな顔をしていたが、すぐにその顔を曇らせた。アルフォンスもまた、エリスを気の毒そうに見ている。
まさか……と、不安な気持ちが俺の心中を襲う。
「エリス……奥で話そう」
ギレーヌの声が硬い。
尻尾もピンと立っている。彼女が緊張している時の顔だ。エリスの帰還をただ喜ぶ顔ではない。
「わかったわ」
エリスも、その顔を見て何かを悟ったらしく、ギレーヌに付いて建物の奥へと歩いていく。
俺もそのまま付いていこうとすると、
「ルーデウス殿は外にてお待ちください」
「え? あ、はい」
アルフォンスに止められた。
そうか、俺も一応雇われ人という立場だから、重要な話は聞かせてもらえないのか。
「だめよ、ルーデウスも一緒」
エリスの口調は強かった。
有無を言わさぬものである。
「エリス様がそうおっしゃられるのであれば」
エリスの口元はいつにもましてギュっと引き締められ、手も白くなるほど握られていた。
俺たちは無言で短い廊下を抜け、執務室のような部屋に入る。
中央に置かれたソファ、部屋の端に置かれた花瓶にはバティルスの花。部屋の奥には余計な装飾のない、安っぽい執務机が置かれている。
エリスはソファに、誰にも言われることなく腰掛けた。
そして、俺の手を取り隣に座らせる。ギレーヌはいつも通り部屋の隅に立っていた。アルフォンスはエリスの正面に立ち、執事然とした仕草で礼をする。
「おかえりなさいませ、エリスお嬢様。お嬢様が帰還なされることはすでに連絡を受け、我ら一同首を長くして……」
「前置きはいいわ、言いなさい。誰が死んだの?」
エリスは執事の言葉を遮り、この場にいる誰よりも強い口調で問いかけた。
誰が死んだの、と。
言葉をオブラートに包むことなく尋ねた。
その姿勢は正しく目線は強い。しかし彼女の心中に不安が渦巻いていることを俺は知っている。
なぜなら、俺の手がギュッと握られているからだ。
「それは……」
アルフォンスは言葉を濁した。
この反応だと、サウロスか。エリスはおじいちゃん子だった。なんでもかんでもサウロスの真似をしていた。それが死んだとなれば、さすがのエリスも落ち込むだろう。
アルフォンスは絞り出すように、告げた。
「サウロス様、フィリップ様、ヒルダ様……お三方ともに、お亡くなりになりました」
その言葉を聞いた瞬間、俺の手が握りつぶされた。
走る激痛。
だが、痛みよりも、アルフォンスに告げられた事実に、脳が混乱していた。
何かの間違いだろう。まだ三年弱。そう、まだ三年も経っていないのだ。
いや、もうすぐ三年も経つというべきか。
「間違い……ないのね?」
エリスの震えた声での問いに、アルフォンスはこくりと頷いた。
「フィリップ様とヒルダ様は共に転移し、紛争地帯にて亡くなられました。これはギレーヌが確認しております」
ギレーヌがこくりと頷く。
「そう……ギレーヌはどこに転移したの?」
「フィリップ様方と同じく、紛争地帯です」
ギレーヌは多くを語らなかった。
紛争地帯を徒歩で突破する最中、フィリップとヒルダの遺体を発見した。
ただ、そう語った。
遺体の状態や、見つけた時の状況を語らなかったが、その表情から酷かったのがわかった。
何が酷いかはわからない。
死体の状態が酷かったのか。死体の状況が酷かったのか。それとも、もっと眼を背けたくなるような何かを見たのか。耳を塞ぎたくなるような何かを聞いたのか。
エリスは、「フン」と鼻息を一つ。
俺を握る手がブルブルと震えている。
「それで、お祖父様は?」
「…………フィットア領転移事件の責任を取らされ、処刑されました」
「馬鹿な」
俺は思わず呟いていた。
「なんでサウロス様が処刑される必要があるんですか?」
あんな天災の責任をとって処刑?
馬鹿言うな。どうしようもないだろ。それとも、未然に防げたっていうのか?
兆候だってなくて、いきなりだったじゃないか。それを、責任?
「ルーデウス、座って」
「…………」
俺はエリスに手を引かれ、座らされる。
いつの間にか立ち上がっていたのだ。
頭の中では、言い表せない感情がグルグルと回っていた。激痛のせいでうまくまとまらない。
手が痛い。
いや、俺だってわかっている。
兆候がなくても。未然に防げなくても。人は死んだし、領地にある畑や、そこから取れる作物は消滅した。損失は計り知れない。不満は大きく、糾弾もされよう。
誰かがその避雷針にならなければならなかった。
生前の日本でも、何か起きればすぐに責任をとって総理が辞任していた。当時は、責任を取るなら事態の収拾が付くまで面倒みろよと思ったものだが、同時に、いい方法なのかもしれないとも思っていた。
死ぬことで、人々の不満を抱えていなくなる。次の椅子には、期待できそうな人物を据える。
そうすれば、多少なりとも溜飲は下がる……。
それだけじゃない。
きっと、貴族連中の間の権力争いも関係している。サウロス爺さんがどれだけの力を持っているのかは知らないが、失脚すれば殺される程度には、力を持っていたのだ。
そう無理やり納得することもできる。
できるが……しかし、それでこの現状なのだろうか。
閑散とした難民キャンプ。人気のない本部。国が本気でフィットア領を再建しようとしているように思えない。
サウロスが生きていれば、あるいはもっと活動的に動いてくれただろう。あの爺さんは、こういう時にこそ役立つ人物のはずだ。
────いや。それは全部建前だ。
そんなことは俺にとっては些細なことだ。
エリスの気持ち。それを考えると、どうしても、心が穏やかではいられない。
彼女の家族はもういないのだ。
フィリップとヒルダの死がいつ伝わったのかはわからない。サウロスの死より先だったのか、後だったのか。
でも、サウロスは生きていた。生きていたのだ。
殺さなくてもいいだろう。
あの災害で、転移事件で、どれだけの人間が死んだと思っているのか。
百や二百できかない数が死んでいるのに、どうしてわざわざ、生還した人を殺すのか。
せっかくエリスが帰ってきたのに……。
ああ、くそう、考えがまとまらない。手が痛い。
「ルーデウス殿、お気持ちはわかりますが……これが、今のアスラ王国です」
そんな言葉ひとつで片付けていい問題じゃないだろう。
アルフォンス。あんたは自分の主君を殺されたんだぞ。
ギレーヌ。お前は自分の命の恩人を殺されたんだぞ。
そう言ってやりたかった。
「…………」
しかし、言葉は出ない。
エリスが何も言わないからだ。この場で、俺が喚いても仕方がない。世話になったとはいえ、親戚筋に当たるとはいえ、俺にとってサウロスは他人だ。家族が何も言わないのに、俺がとやかく言っても仕方がない。
「……それで、どうするの?」
エリスは、珍しく叫びもせず暴れもせず、静かに問いかける。
「ピレモン・ノトス・グレイラット様が、エリス様を妾として迎え入れたいと仰っております」
ギレーヌが殺気を発したのが俺にもわかった。
「アルフォンス! 貴様は、あんな話に乗るつもりか!?」
ギレーヌの怒号。鼓膜が破れるのではないかと思う獣声。
「あの男がなんと言ったか覚えているだろう!」
激昂するギレーヌに対し、あくまでアルフォンスは冷静だった。
「ですが。フィットア領の今後を考えるのであれば、多少の不自由は……」
「あんな男の元に嫁いで幸せになどなるものか!」
「クズでも名家でございます。望まぬ婚姻でも幸せになった例は数多くあります」
「そんな前例など知らん! お前はエリスのことを考えているのか!?」
「私が考えているのはボレアス家とフィットア領のことでございます」
「そのためにエリスを犠牲にするつもりか!」
「必要とあらば」
唐突に言い争いを始める二人を、俺は呆然と見上げていた。
気づけば、エリスが立っていた。
俺の手を離し、両腕を組み、足を開いて、顎をつきだし、立っていた。
「うるさい!」
ギレーヌが耳を手で押さえるほどの大音声。
最近ほとんど聞かなかった、エリスの本気の大声。しかし、元気はそこまでだった。
「……すこし、一人にさせて。考えるから」
しおれた声を聞いて、二人はハッとなったようだ。
まず、アルフォンスが真っ先に部屋から出た。ギレーヌが名残惜しそうにエリスを見て、部屋から出る。
そして、俺が残った。
俺は、彼女になんと声を掛ければいいのか、迷っていた。
「エリス……その……」
「ルーデウス、聞こえなかったの? しばらく一人にさせて」
有無を言わさぬ口調だった。
俺は少しばかり、ショックを受けていた。考えてみれば、ここ数年でエリスに拒絶されたのは、初めてだったかもしれない。
「……わかり……ました」
俺はぺこりと頭を下げると、背中を向けるエリスを見てから、部屋の外へと出る。
そして扉を閉める寸前、グスッと鼻をすする音が聞こえた気がした。
★ ★ ★
アルフォンスは、俺たちのために部屋を用意してくれた。
本部の近くにある家で、恐らく難民用なのだろう、狭い部屋が四つ連なっていた。
俺はそのうちの一つに自分の荷物を運び入れ、エリスの荷物を隣室に運び入れた。
旅装から町用の格好に着替える。
不恰好な縫い跡のあるローブをベッドに放り投げ、部屋を出る。
本部へと戻ってくる。
ギレーヌやアルフォンスと少しでも話そうかと思ったが、姿が見えなかった。
探す気力もなかったので、掲示板をボンヤリと見つめる。
この数ヶ月で何度も見た、パウロの伝言があった。
中央大陸北部を探せ。これが書かれたのは、俺が十歳の時か。
俺はもうすぐ十三歳だ。
随分と時間が経ってしまっていた。
死亡者・行方不明者のリストに目を通す。
ブエナ村の欄。俺の知っている名前が、ずらりと行方不明者リストに並んでいる。
しかし、その半数以上に斜線が引いてある。ちらりと死亡者欄を見ると、斜線を引いたのと同じ名前が書いてあった。どうやら、死亡が確定すると、斜線が引かれ、死亡者欄に載るようだ。
行方不明者の方が若干多いが、それでも死亡者の欄もビッシリと埋まっている。
俺は、行方不明者欄にあるロールズの名前に斜線が引かれているのを見て、眉根を寄せた。
ロールズが死んだことはパウロから聞いている。その死因については詳しく聞き及んでいないが。
そして、そのすぐ下。
行方不明者欄にある、シルフィの文字。
そこには、斜線が引いてあった。
ドクンと、自分の心臓が脈打つ音が聞こえた。
まさか、と思い、死亡者欄を見る。
ロールズの名前の近くにはない。上から順番に見るが、ない。
シルフィエットの名前がなかった……あれ?
「あの、あれ、こっちに斜線が引いてあって、あっちに名前がないんですけど……」
不思議に思い、職員に聞いてみた。
「はい、それは生存が確認された方です」
その言葉に、俺は胸の中の何かがストンと落ちた。
そのまま胸を突き抜けて腹に落ち、腹も突き抜けてウンコを漏らすかと思った。
シルフィが生きているという事実に、俺はほっとした。
「じゃあ、その、連絡先とかもわかりますか?」
「いえ、それは、実際に本部に来ていただいた方でないと……」
「シルフィエットという名前なんです、調べていただけますか?」
「少々お待ちください」
職員に頼むこと数十分。
「申し訳ありません、連絡先は登録されていないようです」
「そう、ですか」
定住していないか、もしくは発見した人物がリストを更新したので本人の連絡先が載っていないか、どちらかだという。
あるいは、記入漏れという可能性もあるだろうが、考えまい。
高確率でシルフィは生き延びている。そのことを今は喜ぼう。
無論、心配もある。
例えば、彼女の髪の色だ。スペルド族とは少々色合いが違うが、同じ緑。人神曰く、呪いはスペルド族にしか適用しないようだし、ブエナ村でも子供たち以外からは積極的にイジメられていなかったはずだ。
だが、心ない者は世の中に大勢いる。
どこかで髪のことを言われ、泣いているかもしれない。
いや、パウロ曰く、シルフィは無詠唱で治癒魔術も使えるという。
聞いただけの話だが、すでに一人で生きていけるだけの力は持っているように感じた。俺と同じように、どこかで冒険者でもしているのかもしれない。家族が死んだことを知らず、探しているのかもしれない。
むしろ、あの転移で生き残ったのなら、その可能性の方が高いだろう。
奴隷とかになっていないことを願おう。
とりあえず俺は、リーリャとアイシャの名前に斜線を引いた。
ルーデウスの名前にはすでに斜線が引いてあった。エリスがこちらに向かっているという報告はあったようだし、俺の情報もあったのだろう。
パウロ一家の中では、ゼニス・グレイラットの名前だけが残っている。
やはり、まだ見つかっていないのか。
今度人神が夢に出てきたら、聞いてみるか。
掲示板を調べおわっても、エリスはまだ部屋から出てこない。
切り替えの早いエリスがこれだけ悩むのは初めてのことではなかろうか。
だが、長いこと旅をしてきて、ようやく帰ってきた故郷には、迎えてくれる家族も温かい家もなかったのだ。さすがのエリスも打ちのめされているのかもしれない。
──やはり戻って慰めるべきだろうか。
いや、もう少し待とう。
そう考えつつ、荷物を運び入れた建物に戻ることにする。
戻ったらあれこれしようと思っていたが、することが思いつかなかった。
少し、休むか。
★ ★ ★
本部を出ていこうとした時、アルフォンスに呼ばれた。
難民キャンプ本部の一室にて、椅子に座らされる。
目の前にはアルフォンス、右手にはギレーヌが座っている。二人が座っているのは、エリスがいないからだろう。俺と違って、きちんと主従関係を理解しているのだ。
「さて、ルーデウス殿、簡潔でよろしいので、報告を」
「報告ですか?」
「はい、この三年間、何をしてらしたのかを」
「あ、そうですね」
俺はアルフォンスに聞かれるがまま、この三年のことを話した。
魔大陸に転移し、ルイジェルドと出会ったこと。
冒険者として登録し、日銭を稼ぎながら移動したこと。
大森林で一騒動あったこと。
ミリシオンでパウロたちフィットア領捜索団と出会い、そこで初めて状況を知ったこと。
情報を探しながら北上し、シーローン王国で一騒動あったこと。
赤竜の下顎でオルステッドと出会ったこと……。
主にエリスに関わることを中心に、極めて簡潔に話した。
アルフォンスは静かに聞いていたが、最後のくだり、ルイジェルドとの別れのところで、ふと声を上げた。
「……その護衛の方はお帰りになられたのですか?」
「はい、彼にはお世話になりました」
「そうですか、落ち着いたら正式に謝礼をとエリス様に進言しようと思ったのですが」
「そうしたものを受け取る人物ではありません」
「左様でございますか」
アルフォンスは頷くと、静かに俺に目線を合わせる。疲れ果てた男の目だ。
「さて、ルーデウス殿……サウロス様に仕えてきた者も、我々だけとなりました」
「……他のメイドさんたちは?」
「戻ってこないところを見ると、死んだか、あるいは故郷に帰ったのかもしれません」
「そうですか」
あの猫耳さんたちも、全滅か。もしかすると何人かは大森林に帰っているかもしれないが。
「サウロス様に世話をしてもらいながら、嘆かわしいことです」
「所
しょ
詮
せん
、金銭だけのつながりでしかなかったのでしょう」
そう言うと、アルフォンスはポーカーフェイスをピクリと動かした。
きつい言い方かもしれないが、そういうことだろう。
「まだ若いルーデウス殿をここに加えるかは迷いましたが……そうした受け答えができるのであれば問題ないでしょう。あなたはエリス様を守り、無事に送り届けた。その功績を認め、ボレアス・グレイラット家の家臣団への入団を認めます」
家臣団。
これはそういう集まりであるらしい。
「これより、家臣団の会議を始めようと思いますが、構いませんな?」
会議か。
きっと、転移事件前にも、俺のいないところでやっていたんだろう。多分、ギレーヌも以前は加わっていなかったに違いない。今は俺を含めても三人しかいないようだが、かつてはそりゃあもうたくさんの家臣が話し合いをしたのだろうな。
「ありがとうございます。それで議題は?」
俺は無駄話をするつもりなく、そう聞いた。なにせ、すでにサウロスもフィリップもいないのだ。誰の話題になるのか、なんて決まりきっている。
「エリス様のことです」
ほらな。
「具体的には、エリス様の今後について話し合おうと思います」
「今後、ですか?」
エリスは故郷に帰ってきたが、そこには何もなかった。家族もいなければ、家もない。以前のような暮らしには戻れない。
「確か、サウロス様とフィリップ様はお亡くなりになりましたが、ボレアス家自体は滅んではいないはずでしょう? 住む家ぐらいは用意してくれるのではないですか?」
「ジェイムズ様は、風聞を気にされるお方ですので、エリス様をお引き取りになることを拒絶なさるでしょう」
ジェイムズ、エリスの叔父か。
現在の領主だ。確か、フィリップと権力争いして勝った奴だ。
風聞を気にするなら、確かに貴族っぽくないエリスを身内には加えたくないか。
礼儀作法も曖昧だし、貴族の子女としては扱いにくい。
また、彼の元には一応エリスの兄弟がいるはずだ。他にも何人か、従兄弟が。エリスがそいつらと問題を起こすのは、想像に難くない。
問題が起こるとわかっていて引き取るほど、エリスに甘くはないのだ。
「もし仮にお引き取りになられたところで、果たして貴族として扱ってもらえるかどうかも怪しい……エリス様が下女の真似事をされるなど考えられません。ですので、これは却下とさせていただきます」
その言葉に、俺はこくりと頷いた。
そうだな、やめておいたほうがいい。エリスもだいぶ丸くなったとはいえ、荒い気性はそのままだ。見下されて殴り返さないほど大人になったわけでもない。
「次に、ピレモン・ノトス・グレイラット様より、エリス様が帰ってきた時に行き場がないのなら、ぜひ自分の妾にしたいという旨を伝えられております」
ピレモン。俺の叔父か。パウロの弟。
現在のノトス家の当主だったか。サウロス爺さんは彼を嫌っていたようだが……。
先ほどの口喧嘩の元となった人物だ。
ギレーヌはと見ると、眉根を寄せて目を瞑っている。
「悪い話ではないのですが、ピレモン様には黒い噂もあります」
「黒い噂、ですか?」
「はい、最近急速に力をつけてきたダリウス上級大臣に取り入ろうという噂です」
それのどこが黒い噂なのだろうか。貴族にも色々あるだろうし、権力者がより上の権力者に取り入るなど、普通ではないのだろうか。
「ダリウス卿は、この十数年で力をつけてきた方で、第一王子を擁立し、第二王女を国外へと追放させた立役者でございます」
いきなり第一だの第二だのと言われてもわからん。俺が知ってるのはラジオ体操ぐらいだ。
「ピレモン様は第二王女を擁立する派閥に属していたのですが……」
「国外追放となったことで、その力を急速に落としている?」
「その通りです」
要するに、自分ところのボスが負けちゃったので、勝った側に寝返ろうって魂胆だろう。
「それならそれでいいじゃないですか。何が問題なんですか?」
「ルーデウス殿、いつぞやの、誘拐事件を覚えておいでですか?」
「誘拐事件?」
「本物の誘拐犯にエリス様が攫われた、あの事件です」
俺が提案したやつか。
「あの誘拐犯の裏にいたのは、ダリウス卿です」
「…………ほう」
「ダリウス卿は、一度だけフィットア領においでなさりましたが、その時、一目見た時から、エリス様のことを大層気に入っていたそうです」
「それは、性的な意味で?」
「無論でございます」
で、気に入ったから、サウロスにくれるように言ったが、あっけなく断られたので、攫おうとしたわけか。
数年越しに明かされる真実。
否、実際には当時すでに判明していたのだろう。相手が大物だから騒ぎ立てなかっただけで。
サウロスはなぜ断ったのだろうか。
……ダリウスが嫌いだからか。そういう感情で物事を決めることもある爺さんだった。
まあ、どういう基準で決めたのかは、この際どうでもいいな。
「ピレモン様は、恐らくエリス様を妾にした場合、何らかの理由を付けて、ダリウス卿にさし出すでしょう。ピレモン様はエリス様のことをモノとしてしか扱っておられないようでしたので」
ふむ、ダリウスは変態貴族ってやつか。
アスラ王国には多いらしいが……求めているのがエリスなら、趣味は悪くないと思える。
悪くないのは趣味だけだが。
「では、却下ですね」
「いえ、ダリウス卿本人については、私としても顔をしかめざるをえませんが、しかし、ダリウス卿は、いま王都で最も勢いのある方です。エリス様も多少は苦労をされるでしょうが、身分と待遇は保証されるでしょう」
「しかし……」
「多少のわがままであれば、ダリウス卿も聞いてくださるはずです。例えば、フィットア領の領民のために開拓村を作るだとか……」
なるほど。権力者の女になれば、多少ならその金も使えるということか。とはいえ、エリスがそんな変態のものになるのは嫌だな。
「他には?」
「他の貴族の方は、恐らくエリス様とは……サウロス様やフィリップ様が死んだ以上、エリス様に貴族の子女としての価値はほとんどございませんので」
価値、価値か……。
そういうものなのだろうか。俺に言わせれば、エリスは単体で十分に価値があるんだが……。
「ルーデウス殿は、いかがなされるのがいいと思われますか?」
「…………僕の意見を言う前に、ギレーヌの意見を聞いてもいいですか?」
唐突の問いに、俺はやんわりとそう言って逃げた。
まだ考えがまとまっていなかった。
「私は、エリスお嬢様はルーデウスと一緒になればいいと思う」
「僕と、ですか?」
「お前はパウロの息子だ。ゼニスもミリシオンの有力な貴族。身元も血筋もハッキリしているのなら、アスラ王国の貴族になれるはずだ」
いや、それはどうだろう。
なれないと思うが。そう思ってアルフォンスを見る。
「不可能ではありません。パウロ殿には今回の一件で功績もありますし、それを利用すれば、ルーデウス殿を貴族にすることもできるでしょう。しかし、フィットア領の管理者になれるほどとなると、難しいでしょうな。パウロ殿のご子息が権力を持つことをピレモン様が許すとは思えません。また、エリス様が権力者に嫁ぐことに関し、ダリウス卿とジェイムズ様がいい顔をするとは思えません」
だろうな……。
でも、なんとなくわかった。アルフォンスの考えは、あくまでこの領地の再生なのだ。
「ならば、ルーデウスがエリスお嬢様を連れて逃げればいい」
「フィットア領のことはどうなさると?」
「お前がどうにかしろ」
ギレーヌの言葉は突き放すようだった。
アルフォンスとは根本的に仲が悪いのかもしれない。
「サウロス様が愛したこの土地をエリス様が統治してこそ、我々の悲願は為されるのではないのですか?」
「それはあくまでお前の悲願だ、一緒にするな。あたしはエリスお嬢様が幸せになれれば、それでいい」
「ルーデウス殿と逃げれば幸せになれると?」
「少なくとも、ピレモンに嫁がせるよりはな」
「領民はどうします」
「知ったことではない。エリスお嬢様は元々、そうした分野には何一つ期待されていなかった」
家臣団の半数は意見を違えている。
──まとめてみよう。
要するに、アルフォンスは、エリスにサウロスやフィリップの跡を継いでもらい、この土地を治めてもらいたい。そのためなら、多少の変態貴族に変態なことをされるぐらいは我慢しろという。
ギレーヌは、そんなことは関係ないから、エリスが幸せになってほしい。そのためなら、権力や家名なんか捨てて、俺と逃避行しろという。
俺としては、ギレーヌ寄りの考えである。
理屈ではなく、感情的なものだ。
だって、ここまで守ってきた子が、ブタみたいな奴のモノになるとかイヤだしね。
それなら、まだエリスと逃避行したほうがいい。俺は権力なんかどうでもいいしな。
しかし、アルフォンスの言いたいことも多少はわかる。
サウロスがやっていたことをエリスが引き継ぐ。そのことに重きを置く考えも、とりあえずは理解できる。納得はできないがね。
まあ、どちらにしてもだ。
「埒が明きませんね」
ぽつりというと、言い争っていた二人が、こちらを見る。
「どういう意味ですか?」
アルフォンスの問いかけに、答える。
「どちらにせよ、決めるのはエリスです。僕らがこうして話をしていても、何の意味もない。そんなことより、もっと建設的な話題を探しましょう。他に何かないんですか?」
アルフォンスは唖然とした顔で俺を見ていた。
ギレーヌもまた、黙りこんでいる。
「ないのでしたら、僕は休ませてもらいます」
その日の会議は、それで終了となった。
第十三話 「お嬢様の決意」
会議が終わる頃には、日がすっかり落ちていた。
俺は部屋に戻った。
最低限の家具の置いてある部屋には、荷物が乱雑に置かれていた。整理をすべきだと思いつつも、しかし何もやる気が起きず、ベッドに座る。
身体が、硬いベッドに沈み込むかと思った。
思った以上に疲れているらしい。
「ふぅ……」
今日はさして疲れることはしていないはずなのに。疲労がベットリと身体の内側にくっついている。これはもしや気疲れというやつだろうか。
いや、違うな。
俺もまたショックを受けていたのだ。
サウロス、フィリップ、ヒルダ。
彼らとは、それほど親しく話したことがあるわけではない。
だが、目をつぶれば今でも思い出せる。遠乗りに出かけ、領地の農作物を確認しつつエリスの様子を聞いてきたサウロス爺さん。悪い笑みを浮かべながら、一緒にボレアス家を乗っ取ろうと提案したフィリップ。エリスと結婚してうちの子になれと言ってくれたヒルダ。
彼らはもういない。
そもそも、家すら残っていない。
あの広く、時折大声の響き渡る館はもうない。エリスとダンスを踊った大広間も、サウロス爺さんが情事にふけっていた塔も、領地の書類が大量に置かれていた書庫も、何もかも、なくなってしまった。
館だけじゃない。ブエナ村もだ。
実際に見てはいないが。ゼニスが大事にしていた庭木も、ロキシーに水聖級魔術を習った時に雷が落ちて焼け焦げた木も、シルフィと一緒に遊んでいた大木も、全てなくなってしまった。
……なんで、ブエナ村で思い出すのが木ばかりなんだろうか。
まあいい。
とにかく、全てなくなった。
パウロから聞いて頭では理解していたが、こうして実際に見てみると、思いのほかショックが大きい。あったものがなくなるというのは、いつだって辛いのだ。
「ふぅ……」
二度目のため息をついた時。
コンコンと、扉がノックされた。
「……どうぞ」
返事をするのも億劫だと思いつつ、入室を促す。入ってきたのはエリスだった。
「こんばんは、ルーデウス」
「エリス、もういいんですか?」
「大丈夫よ」
エリスはそう言うと、俺の前に立ち、いつものポーズを取った。
落ち込んでいる様子はない。
さすがエリスだな。肉親が全滅したというのに、俺よりずっと強いらしい。
いや、落ち込んでいるのかもしれない。いつもならドアはノックなんかしない。蹴り破っていたはずだ。
「まあ、こんなことになるんじゃないかとは思っていたわ」
「そうですか……」
エリスは事もなげに言った。
以前、彼女は覚悟を決めていると言っていたような気がする。
家族が死ぬことを覚悟する。俺にはできそうもない。俺は今だって、見つかっていないゼニスはどこかで生きていると考えている。死んでいる可能性の方が高いと、頭では理解しているが。
「エリスは、これからどうするんですか?」
「どうって?」
「えっと、アルフォンスさんから、話は聞きましたか?」
「聞いたわ。でも、そんなのどうでもいいわ」
「どうでもいいって……」
エリスは俺をまっすぐに見ていた。
ふと今更になって気づいたが、格好がいつもと違った。
ミリシオンで購入してから、一度しか着なかった黒のワンピースを着ている。ワンピースは彼女の赤い髪によく似合っていて、まるでドレスのようだ。やや薄手の服なせいか、胸のポッチが浮かび上がっているのがよくわかる。
うん? ノーブラなのか。
よく見てみると、エリスの髪はしっとりと濡れているようだ。
風呂上がり特有の、石鹸臭もする。それだけじゃない、普段のエリスからは香らない、やや甘い香りもする。なんだろう、どこかで嗅いだことがあるな。
香水だろうか。
「ルーデウス。私、一人になっちゃったわ」
一人に。
そうだ。彼女は、もう家族がいない。血のつながった兄弟はいても、家族じゃない。
「それでね、私この間十五歳になったのよ」
十五歳になったと聞いて、俺は慌てた。
いつだ。彼女の誕生日はいつだった?
俺の誕生日はもう一~二ヶ月後だ。てことは、一ヶ月以上前に過ぎたってことになる。
気づかなかった。
「えっと、すいません、全然気づいていませんでした」
いつだろうか。
全然、そんな素振りは見せていなかったと思う。エリスなら、誕生日になったら騒ぐと思っていた。
何かなかったか。エリスがそれらしいことを言っていた日は……。
「ルーデウスは気づいてなかったけど、ルイジェルドに一人前って言ってもらえた日よ」
「あ」
あれか、あの日か。
覚えている。道のど真ん中だ。
なるほど、だからルイジェルドはエリスを一人前と言い出したのか。
まずい、本気で気づいてなかった……。
「ええと、今から何か用意したほうがいいですかね? 欲しいものとか、ありますか?」
「そうね、欲しいものが一つあるわ」
「なんでしょうか」
「家族よ」
言われて絶句した。
それは、俺には用意できない。人を生き返らせることはできないのだ。
「ルーデウス、私の家族になりなさい」
「え?」
ふとエリスの顔を見ると、彼女の顔は暗がりでもわかるほど真っ赤だった。
それはあれか。プロポーズか? いやまさかな。
「それは、つまり、姉弟ということですか?」
「関係なんてなんでもいいわ」
エリスは耳まで真っ赤にした顔で、しかし目線を逸らさない。
「つまり、その、い、一緒に寝ましょうってことよ」
どういうことだってばよ?
おちつけ、言葉の意味を考えよう。
……寝ましょうという言葉から推察するに、つまり、なんだかんだ言って、エリスもショックを受けているのだ。その心の痛みを癒すために、俺に傍にいてもらいたいのだろう。
家族。この場合は、家族ごっこか。
けど……。
「今日は寂しい気持ちなので、エッチなことをしちゃうかもしれませんよ?」
いつかの夜と、同じことを言った。
正直、俺には自信がない。エリスと一緒のベッドに入り、その体温を近くで感じ、我慢できる自信がない。エリスだって、そのぐらいわかっているだろう。
だろうに……。
「きょ、今日は、いいわよ」
「だから、前にも言ったでしょう、ちょっとぐらいじゃすまないって」
「覚えているわ。今日は、ぐっちゃぐっちゃにしてもいいって言ってるのよ」
そんな返事に、俺はまじまじとエリスの顔を見てしまった。
何を言ってるんだと思ってしまった。え、だって。
そんなこと言われたら、もうウチの息子はスタンディングオベーション状態ですよ?
「な、なんで突然そんなことを言い出したんですか?」
「十五歳になったらって、約束したじゃない?」
「あれは、僕が十五歳になったらって話でしょう?」
「どっちでも構わないわ」
「構いますよ」
おかしい。何かおかしい。考えろ、何がおかしい?
そうだ。
つまり、エリスは寂しがっているのだ。自暴自棄になっているのかもしれない。
エロゲーでもこういうシーンは何度か体験した。誰かの死を癒すために、誰かと慰め合う。肉体関係を結ぶ。うん、理解できる。
けど、それに手を出す俺はなんだ。まるで弱みにつけこんでいるみたいじゃないか。
そりゃヤリたいよ? 俺のダメな子の部分は、童貞喪失だぜ! って喜んでいる。
でも、それはもっと平常な状態でやるべきじゃないのだろうか。こんな精神状態ではよくないと思う。お互いに辛い状態で、なし崩し的にやってしまったら、後で後悔するように思う。
ああ、でも、エリスがいいよって言うチャンスはもうないかもしれないし……。
もし、エリスがピレモンのところに行くとか言い出したら、きっと十五歳の約束は反故ってことになるだろう。いや、そもそもエリスの初めてが他人に奪われるのは……。
したい。やりたい。けど、なんかダメな気がする。
俺は優柔不断なハーレム系物語の主人公をバカにしてきた。
いざというときに男として奮起しない腰抜けだと言ってきた……けど、実際に自分の番になると、尻込みをしてしまう。いい言葉も思い浮かばない。
どうすればいいんだ。どっちを選んでも、俺は後になって後悔する気がする。
後悔しないのは、きっと今から約二年後。
俺の十五歳の誕生日に、エリスが身体にリボンでも巻きつけて、
「誕生日プレゼントよ。思わず殴っちゃうかもしれないから手は縛ってあるわ。好きにしてね」
なんて言ってベッドの上に転がっているパターンだけだろう。
ああ、いやまて。
俺はこの間死にかけたばかりだ。あの時は、死ぬ直前、スゲー後悔した。まだやり残したことがあるって思った。あと二年の間に似たようなことがないとも限らない。何度も九死に一生を得られるわけではないんだ。ここで後腐れなく捨てておいたほうがいいんじゃないか?
いや、でも、しかしなぁ……。
「……もうっ!」
煮え切らない俺に何を思ったのか。
エリスはコホンと咳払いし、そっと、俺の膝の上に座った。
彼女が横抱きになるような体勢で俺の首に手を回す。すると、日に焼けた胸元と、エリスの綺麗な顔が視界いっぱいに広がった。エリスは口を開きかけ、ふと自分の太ももに当たる感触に気づいた。そして、顔がさらに真っ赤になっていく。
「なによこれ……」
「エリスが可愛いもので」
エリスはふうんと言いつつ、太ももの裏でうちの息子の頭をぐりぐりと押さえつける。
その感触は柔らかく甘美。
息子は歓喜し、オヤジのほうの鼻息が荒くなる。
「これって興奮してるってことよね?」
「うん」
「私がイヤってわけじゃないのよね?」
「うん」
「お父様とお祖父様のことを気にしてるの?」
「うん」
「ルーデウス、さっきから目線がエッチね」
「うん」
「でもダメっていうの?」
「……うん」
俺が最後に頷いた。
すでに視線は彼女の胸元や首筋に釘付けだった。エリスの柔らかい太ももや、押し付けられる胸の感触、吸い込めば胸いっぱいに広がるエリスの香り。身体の方はすでに屈服し、尻尾を振っていた。最後に残ったなけなしの理性を振り絞り、俺は口に出す。
「約束は、約束じゃないですか……。十五歳になるまでって、言ったじゃないですか」
もちろん、そんなものは建前だ。この瞬間、はっきり言ってどうでもいいとさえ思っていた。
自分がなぜ抵抗しているのかすら、曖昧だった。
そんな俺の言葉に、エリスがフッと一つ息を吐く。吐息が頬に当たる。
「ねえ、ルーデウス。お母様から習ったのだけれど、禁止されてるし、恥ずかしいから一回しか言わないわ」
彼女は、そう言うと、深呼吸を一つ。
俺の耳元に、そっと顔を近づけた。
そして、一言。甘えるような声音で。禁断の封を解いた。
「私、ルーデウスの子猫が欲しいニャん」
そいつは、俺の耳から素早く脳へと侵入し、最後の抵抗を続ける理性をあっさりと食い殺した。
そいつは、巷
ちまた
で狂犬と呼ばれる犬にそっくりだった。
そいつは、犬なのに語尾がニャんだった。
俺は本能のみになった。
本能のみになった野獣は、エリスをベッドに押し倒した。
★ ★ ★
その晩。俺はエリスと仲良く大人の階段をのぼった。
この時、俺は難しいことは全て忘れていた。ただ、エリスと一緒になろうと思った。口には出さなかったが、彼女が好きだと思った。ずっと守っていこうと思った。他の諸事情なんてどうでもいいと思った。
パウロも言ってたじゃないか。貴族の義務なんてどうでもいいって。難しいことなんて考えなくていいんだ。彼女を助けるため、なんでもすればいいんだと思っていた。ついでに、子供は三人がいいけど、もっと作っちゃうんだろうなとかも思っていた。
そう、言ってみれば……浮かれていたのだった。
エリスが何を考えているかなんて、考えてもいなかった。
★ エリス視点 ★
私、エリス・ボレアス・グレイラットは、その日、大人になった。
十五歳の誕生日プレゼントにルーデウスをもらった。約束とはちょっと違うけれど、ルーデウスと結ばれた。
私は彼を愛している。
はっきりと自覚したのはいつからだったか……。そう、確か最初に好きだと気づいたのは、彼の十歳の誕生日の時だ。
寝ているところを母に叩き起こされて、真っ赤な寝間着を着せられて、真剣な顔で「彼の部屋に行って、そして彼に身を委ねなさい」と言われた時だ。
嫌じゃなかった。
けれど、戸惑いもしていた。そういうことは、母やエドナから何度も聞いていた。いずれそうなるのだ、と言い含められていた。
けれど、その時はまだまだ覚悟がなかったし、もっと先のことだと思っていた。
私の戸惑いを知ってか知らずか、ルーデウスは私の身体に触れた。
彼は父と、遅くまで話していたようだったし、もしかすると、そういう話が通っているのかもしれない。
そう考えて、私の中である考えが浮かび上がった。
『彼は私が好きではないのかもしれない』
もしかすると、父に言われて仕方なく、私に手を出しているのかもしれない。
ルーデウスは当時からすごい人だった。
なんでも知っているし、なんでもできるのに学ぼうとする意志を決して衰えさせることなく、どんどん先に進んでいった。
そんな私と彼は釣り合っているのだろうか。鼻息を荒くしたルーデウスは、私の気持ちなどどうでもいいように思えた。
私は父から彼に与えられた報酬。そう考えると、嫌になった。
私は彼を突き飛ばして、逃げ出した。
部屋まで逃げようとして、今度は恐ろしくなった。自分は今、取り返しのつかないことをしてしまったのではないか、と。
もしかすると、今、私は最後のチャンスを失ったのではないか。ルーデウス以外にもらってくれる人なんていない、と母は言った。
その通りだと思う。貴族の子供たちには何度か会ったことがあるが、ルーデウスほど気骨のあるのはいなかった。
ルーデウスは幼い頃から私の身体に興味津々だった。すぐにスカートをめくってパンツを下ろそうとしてくるし、事あるごとに胸を触ろうとしてくる。
その度に殴って追い払った。
学校にちょっとだけ通っていた頃、男の子にからかわれて殴ったら、その子は二度とナマイキな口を利かなくなった。けど、ルーデウスは全然こたえなかった。
ルーデウスしかいない、という母の言葉の意味を強く実感した。
彼に嫌われたら、自分は一生一人だと思った。
報酬でもいいじゃないかと思った。……一緒にいられるなら。
私はルーデウスの部屋にとって返した。
私の姿を見ると、彼はカエルのように這いつくばった。自分が悪いと謝ってくれた。覚悟ができていないのは私の方だったのに……。
そんな彼に対し、私は上から目線で、あと五年待てと告げた。当時は、それぐらいはいいだろうと思った。大人なルーデウスなら、待っててくれるだろうと思った。
あの時には、私は彼のことが好きになっていた。
しかし、すぐに事態は急転した。
訳のわからないところに飛ばされて、目が覚めたら目の前にスペルド族がいた。
罰があたったんだと思った。今まで好き放題してきた罰があたったんだと。お母様には、我儘ばかり言っていると、スペルド族が来て食べてしまうと何度も言われていた。だから私は、この悪魔に食べられるのだと思った。
せめて、あの時、ルーデウスに好きにさせてあげればよかった。
本格的なのは十五歳になってからでもいいのだ。ルーデウスの満足がいくまで、自分が我慢すればよかっただけなのだ。
私は泣き叫んで、地面に蹲った。
助けてくれたのは、ギレーヌでもお祖父様でもなく、ルーデウスだった。
彼は、あのスペルド族と話をつけたのだ。自分だって不安でたまらないだろうに、年上である私を慰め、宥めた。なんて勇気があるんだろうと思った。
また一つ好きになった。
それから、ルーデウスは頑張っていた。
青い顔をしながら魔族と渡り合っていた。ご飯もほとんど喉を通ってなかった。体調が悪いのを隠していた。きっと私に心配させないため、見えないところで苦しんでいたのだ。
だから、私は我慢することにした。
叫びだしたいのをこらえて、ルーデウスに任せることにした。できる限り、いつも通りに振る舞おうとした。でも、どうしても我慢できないことは何度もあった。不安は止めどなく、私の奥底から湧いて出た。
辛い状況で、なんと我儘なことだったろうと思う。
ルーデウスは怒るでもなく、私の傍にいてくれた。嫌味の一つも言わず、頭を撫でて、肩を抱いて、慰めてくれた。そういう時、彼はエッチなことは一切しなかった。普段はあれほどギラついているのに、そういう時だけは、私の身体に必要以上に触れようとしなかった。
エッチなのは、彼なりの茶目っ気なのかもしれない。そう考えた。
普段通りに振る舞うことで、安心させようとしてくれているのかもしれない。そう考えた。
彼は自分のことだけでなく、私のことを考えてくれている。
私は強くなろうと思った。せめてルーデウスの足手まといにならないように。私がルーデウスよりうまくできるのは、剣を振ることだけ。戦うことだけだ。それすらも、仲間になったルイジェルドに遠く及ばない。剣だけならともかく、魔術を駆使したルーデウスにも勝てないだろう。
ルーデウスは、そんな私に経験をつませてくれた。
きっと、ルーデウスとルイジェルドだけだったら、もっと簡単に魔物を倒して、もっと簡単に旅を続けたに違いない。
そう考えると泣きそうになった。
ルーデウスがそれに気づいたら、旅の途中で嫌われたら、置いていかれるかもしれない。そう思った。
だから、必死に強くなった。
ルイジェルドに稽古を申し込み、何度も打ち倒された。
その度にルイジェルドは、「わかったか」と聞いてきた。
その度に私は、ギレーヌの言葉を思い出して頷いた。
合理、そう、合理だ。
達人の動きには合理性がある。自分より強い者を見たら、まずよく観察しろ。
ルイジェルドは強い。恐らくギレーヌよりも強い。
だから、私は見た。ひたすらに彼の動きを見て、自分ができることは真似した。
ルイジェルドは、強くなろうとする私を手伝ってくれた。夜中、ルーデウスが疲れて寝てしまった後、嫌な顔一つせずに、稽古に付き合ってくれたこともある。
特訓もした。
ルイジェルドは当然のように、私を打ちのめしてくれた。子供が好きな彼にとって、私を打ちのめすのは辛いことだったかもしれない。
私にとっては、ルイジェルドも師匠と呼べる存在である。
旅を開始して一年。
強くはなれたと思う。ギレーヌに口をすっぱく合理合理と言われ、わかった気分になっていた当時とは違う。ルイジェルドとの稽古で、私は合理の真の意味を理解した。今まで適当でいいと思っていた体の動きの隅々にまで意味が存在した。小ざかしいと思っていたフェイントや、今まで何気なくやっていた先制攻撃の意味も理解した。
そんなある日、ルイジェルドから初めて一本をとれた。
今思えば、彼は何か他のことに気を取られていたように思う。けど、私にとっては、そんな隙でも構わなかった。
初めて、一本とれたのだ。これで足手まといにはならなくなった。ルーデウスの隣で歩いていける。そう、私は調子に乗っていた。
そんな増長を、ルーデウスは簡単に打ち砕いてくれた。
いきなり魔眼を手に入れてきて、いとも簡単に私を組み伏せた。
ルーデウスに、負けた。それも、魔術なしの真っ向勝負で。
ショックだった。もう、何も彼に勝てるものがない。ずるいと思った。あんなのは反則だと思った。私が何年も掛けて歩んできた道を、一発で覆された。
同時に事実が突きつけられる。
私は変わらず足手まといだ。
人知れず泣いた。
翌日の早朝、海辺で剣を振りながら、泣いた。
ルイジェルドは気にするなと言ってくれた。元々、魔眼はルーデウスと相性がいい。お前は鍛えればより強くなれる。才能はある、だから諦めるな、と言ってくれた。
何が才能だ。
ギレーヌもルイジェルドも嘘ばっかりだ。
そう思っていた。
この頃、ルーデウスが大きく見えた。
あまりに大きく、直視できないほどの輝きを持って見えた。
神格化というのだろうか。
完璧な人間は誰かと聞かれれば、間違いなくルーデウスと答えただろう。
どうにか追いつきたいと思ったけど、無理だとどこかで諦めていた。
それが変わりだしたのは、ミリス大陸に渡ってからだ。
ギースに会って、世の中には剣や魔術以外にも、いろんな技術があることを知った。
覚えようと思ったが、断られた。なんでだろう、とその時は思った。納得なんてできなかった。
そして、ミリシオンでの出来事だ。
せめて、自分一人でもなんとかできるようにと、最も簡単なゴブリン討伐に行ってきた。
私だって一人でやれるんだと、少しは思いたかった。
その時、私は初めて自分の才能の片鱗に気づいた。変な暗殺者のような相手と戦い、圧倒できた。いつの間にか、私も成長していたのだ。
そして、帰ってくると、ルーデウスが弱っていた。
なんとか事情を聞き出すと、この町にはパウロがいて、ルーデウスに辛く当たったらしい。
泣いてはいないものの、深く落ち込んでいるルーデウスを見て、私は彼がまだ二歳年下の子供なのだと思い出した。
それなのに、こんなワガママな女の家庭教師になって、十歳の誕生日を家族にも祝ってもらえなくて、足手まといを引き連れて魔大陸を旅してきて……。
そして父親に突き放されたのだ。
到底許せるものではなかった。アスラ貴族の末席に名を連ねる者として、パウロ・グレイラットを斬ろうと心に決めた。パウロという人物の強さは父からよく聞いていた。なんでも剣神流・水神流・北神流の三流派を上級まで収めた、天才剣士という話だ。
そして、あのルーデウスの父親。
でも、勝てないかもしれないとは思わなかった。ルイジェルドに教えてもらったことは、私の中できちんと力になっている。ギレーヌに教わった剣術と、ルイジェルドに教わった戦闘術。
二つを足して打ち倒せないはずはない。
外道に負けてはいけないのだ。
しかし、ルイジェルドに止められた。なぜと聞くと、これは親子喧嘩だからだと言う。
ルイジェルドが自分の子供のことで悔やんでいることは聞いていた。
だから、今回はルイジェルドの言う通りにすることにした。
今になって考えてみればルーデウスもなんだかんだ言って、パウロのことを話す時は楽しそうだった。仲の良い親子が、ちょっとした仲違いをしているだけ。そう思えば、ストンと腑に落ちるものがある。
でも、あの頃の私には納得できなかった。
結局、ルーデウスとパウロは仲直りした。ルイジェルドの言う通りだったのだ。
もう一度言おう、納得できなかった。
どうしてルーデウスが父親を許すのかわからなかった。
そう、許したのだ。彼は、あんな非道な父親を。
自分なら絶対に許さないであろう相手を。
ルーデウスはそのことについて、多くは語らなかった。ルイジェルドも教えてはくれなかった。
彼らは大人なのだ。
それから、中央大陸に渡った。
この頃になるとルーデウスも元気になってきたのか、ご飯をたくさん食べるようになった。
そして、相変わらずルーデウスは凄かった。
シーローン王国では、一日で第三王子と仲良くなって家族を救出した。
私といえば、ルイジェルドと一緒に暴れただけだ。
結果として、考えなしに暴れたことが、ルーデウスを助けることになったが……。
彼は「僕は何もしていません」「助かりました」なんて言ってたけど、あの調子なら一人で全て解決していたに違いない。
ルーデウスは大きかった。
大きすぎた。その大きな彼は、あの日、龍神と出会った日に、さらに大きくなる。
龍神との対決。私とルイジェルドが、あの恐怖の象徴みたいな奴におびえた時、ルーデウスだけが平然としていた。
ルイジェルドが手も足も出なかった相手に、一撃入れたりもした。
あの時に出した魔術は、私の目には見えなかった。
ルーデウスは岩砲弾だと言っていたが、今まであんな凄まじい岩砲弾は見たことがなかった。
凄いのだ。本気を出したルーデウスは。
世界最強とも言われている龍神と、ちゃんと戦えるのだ。
そう思った次の瞬間、ルーデウスは死んだ。私はその瞬間まで、自分たちと死は無縁だと考えていた。ルーデウスは強いし、絶対に死なない。彼に守ってもらえる限り、私も死なない。ルイジェルドもいるし、安全。そう考えていた。
勘違いだった。
もし、あの龍神の連れの少女が気まぐれを起こしていなければ、あるいは龍神が治癒魔術を使えなければ、ルーデウスはいなくなっていただろう。
怖くなった。
私は足手まといで、彼の荷物になっている。
そう、改めて感じていた。
それでもなお、私はルーデウスを神格化していた。
なぜなら、彼は殺されかけてもケロっとしていたからだ。あまつさえ、またあの龍神と戦うことを想定して、訓練をつんでいた。死にかけた三日後に、である。
私はそれが理解できなかった。
理解できないけど、とにかく怖くて、彼の傍にいた。傍にいなければいなくなってしまう気がした。置いていかれてしまう気がした。
そして、ルイジェルドと別れた。
ルイジェルドは、あの龍神に勝つのは無理だと言ったけど、最後の最後に、教えてくれた。
龍神の使った技を、思い出させてくれた。目に焼き付いたあの光景、龍神の動き、私の斬撃を受け流した技。その中から私は合理性を見出していた。龍神は正体不明の怪物なんかじゃない。
人の技術を使う達人なのだ。
そして、最後に。
家に帰り着いて、何もないことを知った。
父と祖父、母の死を知った。悲しかった。あんなに辛い思いをして帰ってきたのに、私には何もなかったのだ。家も、家族もいなかった。ギレーヌとアルフォンスはいたけど、なんだか別人のように余所余所しかった。
もう、私にはルーデウスしかいなかった。
だから私は、彼と家族になろうと思った。
焦っていた。
彼の仕事は、もう終わりかけている。契約期間は五年で、もうとっくに過ぎている。私を送り届けるという役目も終わった。彼の家族はまだ全員見つかっていない。すぐにでも、彼は旅立ってしまうだろう。私を置いて。
そう思った。
引き止めるため、身体で迫った。
彼は最初渋っていた。もらってくれないかな、と思った。
ルーデウスは私の下着には興味を示していたけど、決して私の水浴びを覗いたりすることはなかった。ミリス大陸に渡る船の中でも、その気になればいくらでも触ったり脱がせたりできたのに、しなかった。
だから、体には興味がないのかも、と思っていた。
剣の修行ばかりしていたから、私は他の子よりも、ちょっと女らしさが足りないし。いくらエッチなルーデウスでも、こんなのを実際に抱くにはイヤなのかな、って思っていた。
そんなことはなかった。
ルーデウスは、すごく興奮していた。そんなルーデウスを見て、私も興奮した。
そして、初めて身体を重ねた。
私は、最初こそ痛かったが、次第に気持よくなっていった。対するルーデウスは、最初こそ気持ちよさげにしていたが、途中からは弱くて、か細くて、折れてしまいそうになっていた。
そこで、気づいた。また、気づいた。
ルーデウスは、私よりも小さいのだ。
もちろん、私を女にしたモノは逞しいものだったが、背丈はもちろん、全体的に彼は小さいのだ。私よりも。
ルーデウスは、自分より年下なのだとその時、初めて理解した。
ルーデウスはこんなに幼いのに、私をずっと守ってくれた。船に乗った時だって、ずっとヒーリングをかけ続けてくれた。船を降りた時、彼は随分と疲れていた。あんな気持ち悪い乗り物に乗って、彼だって平気でいられたはずはないのに。
そうだ。もし、あのヒーリングがなければ、船から降りた後、ルーデウスは獣族に後れなんて取らなかったかもしれない。
それに比べて、私はどうだろうか。力は強くなった。剣術だって、それなりに上手になった。
けど、ルーデウスのことはあまり考えなかった。
彼の大きさばかりに目を取られ、小ささには目をそむけていた。
最終的には、家族を失った不安を盾にルーデウスに迫り、自分の欲望のまま、こんな仕打ちをしてしまった。
もう一度言おう。
私はルーデウスを愛している。けれども、私はルーデウスに相応しくない。私はルーデウスの負担にしかならない。
家族にはなったけど、それ以上の関係にはなれない。
夫婦にはなれない。彼の言う通り、姉弟ぐらいが丁度いいだろう。
私は彼に釣り合いがとれていない。一緒になっても、彼の足を引っ張り続けることになるだろう。
しばらく、ルーデウスとは距離を置いたほうがいい。
自然とそう思えた。
ルーデウスと一緒にいると、私は彼に甘えてしまうだろう。あの甘美な感覚はまだお腹の奥に残っている。ちょっと物足りないぐらいだ。この浅ましさは、グレイラット家特有のものだ。案外、ルーデウスはあまりそういう方向では強くないかもしれない。頑張ろうとするルーデウスを、こっちの方面でも惑わせてしまうかもしれない。
それは、イケナイことだ。
とはいえ、私はやっぱり彼が好きだ。
アルフォンスが言うように、他の男のところに嫁ぐつもりはない。大体、今更貴族の子女らしく生きろというのも、無理な話だ。見知らぬ領民のために尽力しろと言われても、ピンと来ない。大体、なんで私がそんなことをしなければならないのか理解できない。
お祖父様もお父様もお母様も、もういない。
フィットア領ももうない。
なら、私も『ボレアス』の名を捨てよう。けれども、サウロスお祖父様の孫として、お父様とお母様の娘として。鋼の意志で生きていかなければ。
強くなろう。
改めてそう思った。
彼と別れて、もっともっと修行するのだ。
せめて、ルーデウスと肩を並べられると思えるまで。彼に勝てなくてもいい。
でもせめて、ルーデウスと釣り合う女になるのだ。くっついているだけだと後ろ指を指されたりしない女にだ。私には、ルーデウスのように賢く生きるのは無理だ。
だから、力を求めよう。
ギレーヌも、ルイジェルドも、ギースも言っていた。
私には、剣の才能がある。ルーデウスと出会ってから今まで、一度たりとも自分が強いと思えたことはない。けど、私を成長させてくれた彼らの言葉を信じよう。
ギレーヌの勧めに従い、剣の聖地に赴く。
そこで、強靭な剣士になるのだ。
剣士と魔術師。
男と女が逆だ。
でも、私たちはそれでいい。
成長できて、強くなれて、もう一度会えたら。
その時こそ、家族の一歩上、夫婦になるのだ。彼の子供を産んで、幸せに暮らすのだ。
うん。そうしよう。
さて、しかし、なんと言って別れようか。
ルーデウスは口が達者だ。なんだかんだと言って引き止められるかもしれない。私だけでは心配だと、自分のことは置いといて、付いてきてくれようとするかもしれない。
書き置きか……。
でも、私では、書き置きに、何かしら痕跡を残してしまうかもしれない。
それを見て、ルーデウスが追いかけてきたら、大変だ。彼は、私なんかにかかずらわっていてはいけない。もっとどんどん先に行く人だ。私も足を引っ張りたくない。
こういう時、物語の剣士は黙って出ていく。
けれども、ルーデウスはそういうのは嫌いだろう。旅の間も、何度も報告・連絡・相談と口を酸っぱくして言っていた。彼に嫌われたいわけではない。
よし。
一言だけ、残していこう。それで、ルーデウスはきっとわかってくれる。
★ ルーデウス視点 ★
グッモーニン、エブリワン。
おはよう、いい朝だね童貞諸君!
童貞が許されるのは小学生までらしいけど、君たちは大丈夫かい?
おおっと、僕はダメだったよ。ハハッ、もうすぐ十三歳だからね。換算すれば中学生になってしまうよ。ハハッ!
そしてこんにちは、非童貞の諸君!
今日から僕も君たちの仲間入りサ! いわゆる、リア充、ってやつだね!
まさか僕もそっち側に入れるとは思っていなかったけど、リア充初心者として温かく迎え入れてくれたまえよ。金持ち喧嘩せずって言うしね、仲良くしようじゃないか!
女の身体よりオナ○ールの方が気持ちいいなんて噂を聞いたことがあったけど、ありゃ嘘だね。
なにせオナ○ールには、あれとかこれとか唇とか舌とかついてないからね。身体全体で味わえるものでなければ意味がないね。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、全てを充足させるものがそこにはあったよ。
いやなんていうのかな。
一度抱いたぐらいで彼氏面しないでよ、なんてセリフがあるよね。
言いたいことはわかるよ。
でもね。もうなんていうか、ね。彼女の腰のあたりに手を回して、ぎゅっと抱き寄せるだろ。すると、彼女は俺の背中に手を回して、ぎゅっと抱き返してくれる。耳元で聞こえる荒い息、顔を見ればガッチリと絡み合う視線。口のあたりを舐めれば彼女も舌を出してきて、上も下も大洪水。
もうね、互いが互いの物になってる感じがしてハッスルですよ。
精神的充足っていうの?
求め合い、与え合う。そりゃあ、ヤリなれた人なら、それで勘違いするなって思っちゃうよね。
けど、俺みたいな初心者には無理さ。彼氏面しちゃうもん。そして、お互いに初心者なら、問題もないのさ。エリスだって彼女面したくなってるだろうさ。
おっととと。失礼。童貞諸君には少々刺激が強すぎる話題だったかな。
失敬失敬。私もね、もう少し落ち着いていようと思うんだがね。
体感時間にして四十七年。渇望してやまなかったものが手にはいり、少々浮き足立っているようだ。おっと、この場合は手から離れて、かな?
昔は、もし自分がそうなってもクールでいようと思っていたのだがね。ハハハ、自分というものはなかなかコントロールできないものだ!
おや、もうこんな時間か。
失礼、カノジョとの朝のピロートークの予定があるのでね。
いやー、リア充というのは本当に忙しいね。特に夜の予定が忙しいね!
きっと今晩もビーストモードでバーニングタイムさ。もしかすると、昼間から忙しくなってしまうかもしれない。
ほらエリス、朝だよ。起きて。起きないとイタズラしちゃうぞう。
っと、いない。
ベッドの隣側は空だ。
彼女は起きるのが早いからな。初めての朝はピロートークからのコーヒーブレイクと相場が決まっているのに。まったく、恥ずかしがり屋さんなんだからもう。
「よっと」
起き上がる。
腰のあたりが心地よいけだるさを返してくる。このおかげで、昨晩の一件が夢ではなかったと思えてくる。実に心地いい。
とりあえず脱ぎ散らかした服を着る。ズボンが見つかったが、下着がない。
仕方がないのでノーパンでズボンを履き、ベッドの脇にエリスのパンツがあったのでポケットに入れておく。上着を羽織って、大きく伸びをする。
「んー、グッドだ」
これほどまでに清々しい朝は、そうないだろう。
と、俺はそこで、床に散らばるものに気がついた。
赤いものが散乱していた。
「えっ……?」
髪だった。
真っ赤な毛が、床にバサリと落ちていたのだ。
「なんぞ……これ……」
俺はその毛を一房つかみ、臭いを嗅いでみる。昨晩たくさん嗅いだ、エリスの臭いがした。
「ええ……?」
混乱しつつ、視線を前へと送ってみる。
すると、そこには一枚の紙が置いてあった。
そのまま拾い上げ、そこに書いてある文字を読む。
『今の私とルーデウスでは釣り合いが取れません。旅に出ます』
その意味を、俺は、じっくりと噛み締める。
一秒。二秒。三秒。
部屋を飛び出した。
エリスの部屋を見る。荷物がない。すぐに外に飛び出す。
本部に入る。
アルフォンスを見つける。
「あ、アルフォンスさん、エリスは!?」
「ギレーヌと共に旅立たれました」
「ど、どこに?」
聞くと、アルフォンスは、やや冷ややかな目で俺を見た。そして、ゆっくりと口を開く。
「ルーデウス様には口外するなと、申し伝わっております」
「あ……そう、ですか」
あれ?
なんで……?
わけがわからない。
あれ?
俺はなんで振られたんだ?
いや、捨てられた?
置いていかれた?
あれ?
家族……?
あれ?
★ ★ ★
一週間ほど呆然として過ごした。
時折、アルフォンスが来て、俺に何ごとかと仕事を言いつけた。
フィットア領には何もないと思ったが、小さな開拓村は少しずつ増えているらしい。
難民キャンプから少し移動したところでは、麦の栽培を始めていた。
俺はアルフォンスに言われるがまま、村の周囲に土魔術で防壁を張り巡らせたり、堤がなくなって氾濫しがちな川に堤防を作ったりしていた。ゆっくりだが、復興は進んでいるのだ。
もっとも、本格的な開拓はミリシオンからの大規模移民が終わってからだそうだ。
エリスは死亡したことにするらしい。
エリス・ボレアス・グレイラットはいなくなり、ただのエリスが誕生したわけだ。
そのせいで色々と苦しいことになるそうなので、正式に発表するのは数年後、とアルフォンスは言っていた。ダリウスとやらに支援でも受けているのだろうか。
まあ、どうでもいいか。
エリスがいなくなっても、アルフォンスは何事もなかったような顔をしていた。
エリスに逃げられて残念ですね、と冗談交じりに言ってみたら、「何にせよ、私はフィットア領を復興するだけです」と、事もなげに言い返された。
本当はもっと色々と聞いて状況を知らなければいけないのかもしれない。
だが、エリスがいない以上、わりとどうでもいい気分になっていた。
もう、権力争いでもなんでも、勝手にやっていてくれという感じだ。
で、俺が一週間、何を考えていたのかというと、だ。
エリスがいなくなった理由をずっと考えていた。あの晩の自分の言動や行動を思い返していた。
しかし、思い返しても、ピンク色の場面しか思い浮かばない。俺の記憶は全てあの瞬間に上書きされていた。
もしかすると、俺はヘタだったのだろうか。欲望のままに襲いかかったから、幻滅されてしまったのだろうか。いやそれはおかしい。襲ったのは俺だが、誘ったのはエリスだったはずだ。
いや、言うまい。
俺は愛想をつかされたのだ。
思えば、この三年、旅の最中は失敗ばかりしてきた。
結果的にうまくいくことも多かったが、ルイジェルドに助けられてのことだ。そんな相手に、あと二年も付きまとわれるのはエリスもイヤだったんだろう。だから、約束を先払いで済ませて、さようならしたのだ。
思わせぶりな態度を取っていた理由はわからないが……。
とりあえず、そう結論付けた。
結局、俺は何も成長できていない。愛想をつかされても仕方がないだろう。
そう諦めた時、ふと思い至った。
「ああそうだ、ゼニスを探さないとな……」
こうして、俺は中央大陸の北部へと旅立った。
間 話 「出会ってしまった二人」
ロキシー・ミグルディアはクラスマの町にたどり着いた。
クラスマの町は魔大陸の北西の先端に位置する。
クラスマの町はリカリスの町ほどではないが、栄えた町である。
一見すると何の特徴もない、どこにでもある何もない町であるが、実はこの周辺一帯に君臨する魔王は海人族と懇意であり、交易のやりとりがあった。クラスマの町はその交易の拠点であり、海人族の物資と魔族の物資が集まる場所なのだ。
海人族からもたらされる海の幸と、魔大陸特有の刺激の強い香草。
クラスマの町では、この二つの合わさった非常に美味な料理を味わうことができる。
魔大陸の中では一、二を争う食事の美味しさを誇る町と言えよう。
ちなみに、争っているのはウェンポートである。
「ここの料理は酒に合うのう!」
この町に来てからというもの、タルハンドはご機嫌である。
クラスマの町では、魔大陸の辛い酒だけでなく、海人族の甘い酒も存在している。
炭鉱族のタルハンドは酒好きである。楽しい酒であるなら、どれだけまずい酒でも大丈夫なようで、酒場に行けば必ずその場にいる荒くれ者の男たちと意気投合し、浴びるほどの酒を飲む。酒場はどこにでもあり、気のいい男たちはどこにでもいる。それにうまい料理が合わされば、タルハンドにとっては楽園といえよう。
もっとも、いい歳をして子供舌であるロキシーには、この町の料理は少々合わない。
元々魔大陸の料理や味付けは口に合わなかった。だから、それがどう進化したところで、美味しいと思えるわけもない。彼女は甘いものが好きなのだ。
しかし、海族特有の甘い酒。これはよかった。
基本的に酒は辛いものという認識のあったロキシーにとって、甘い酒というのは衝撃であった。
匂いを嗅げばふんわりと磯の香りがして、口に含むとなんとも言えない甘さが口いっぱいに広がる。後味に少しばかりしょっぱさが残るが、そこでツマミを食べると食も進んだ。
「なんじゃなんじゃ、珍しいのう! ロキシーも飲んどるのか!」
「はい、いただいてます」
「今日はごきげんじゃな! 店主、樽を持ってこい! 炭鉱族の飲み方を教えてやるわい!」
タルハンドは飲んでいるロキシーを見て、上機嫌で追加注文した。
こういう時、魔大陸の物価の安さはありがたいとロキシーは思う。
なにせ、どれだけ大量に飲み食いしても、アスラ銅貨が一枚もあれば賄えてしまうのだから。
「じいさん、いい飲みっぷりじゃねえか!」
「イッキ! イッキ! イッキ! イッキ!」
「さすが炭鉱族だぜぇぇ!」
「っしゃあ、勝負だコラァ! 店主、俺も樽だ!」
樽単位で飲み始めたタルハンドに触発され、他の客も飲み始める。
ちなみに、すでにエリナリーゼは意気投合した男と夜の町へと消えていった。
ロキシーはいつもならやや疎外感を覚えるところだが、気づけば隣に座っていた少女と一緒に、騒ぐタルハンドをやんややんやと騒ぎ立てていた。
「ファーハハハ! 気持ちのいい炭鉱族じゃのう! 樽じゃぞ樽! 炭鉱族はいつの世も変わらんな! なぁ、お前もそう思うじゃろ?」
「ええ、そうですね」
「おお、始まるぞ、ほれイッキ! イッキ! イッキ!」
「いっき、いっき!」
タルハンドは堂々とした態度で巨漢の魔族と樽を抱えて、ガボガボと酒を飲む。
横幅の大きな体とはいえ、一体どこに入っていくのか。
一抱えもある樽を飲み干すと、ガフゥーと息を吐いた。
すぐさま、次の酒が運ばれてくる。
「おい酒追加おせえぞ!」
「うるせぇ! もう品切れだよ!」
「ねえなら隣の酒場から買ってこいや!」
「おおう、その手があったか! よっしゃ、お前買ってこい!」
「まかせろや! てめえら、カンパしろカンパ! 今日はとことん飲むぞコラァ!」
「オオオォォォ!」
そんな調子でカンパ袋が回りだす。
「ハハァ! お嬢様、哀れな酔っ払いめに施しを!」
「はい、今日は、わたしの、奢りです!」
ロキシーは回ってきた袋に緑鉱銭を一枚投げ入れる。それを見て、男はニヤついた笑みを張り付かせたまま、ヘヘェと頭を下げる。
「さすがでございますお嬢様! よ、お金持ち!」
「ふふ、当たり前じゃあ、ないですか」
ふわふわと気持ちのいい気分でロキシーは大仰に頷く。
受け答えはいつも通りに聞こえるが、彼女も酔っていた。
「ファーハハハ! 妾も今日は金を持っているのじゃ、ほれたーんと受け取れ! そしてどんどん騒ぐのじゃ! 今日は無礼講じゃ!」
隣の少女もまた、懐からくず鉄銭を取り出すと、カンパ袋に投げ入れた。
普通なら、大口叩いてくず鉄銭かと軽口を叩かれるところであるが、カンパ袋を持っている奴もまた、酔っていた。
「ウエヘヘ! ありがとうごぜえますお姫様! 今日はこいつで吐くまで飲ませていただきやす!」
「よしよし、たくさん吐けよ!」
少女は偉そうに頷くと、カンパ男は周囲を巡り、金を集めていく。
「ええのう、ええのう、この空気、昔を思い出すわ!」
少女がいつロキシーの隣に座ったのか、ロキシーにはわからない。
気づけば、少女は隣にいて、エリナリーゼが残したものをムシャムシャと食べていた。
ロキシーは気にしない。酔っぱらいだから。
「まあ、どうぞ、一杯」
「おお、すまんのう。いやそれにしても楽しそうな気配を感じて来てみてよかった。ぐびぐび。ほれ、おぬしも飲まんか!」
「飲んでますよ」
「もっとじゃ!」
「もっとですか、仕方ありませんね……」
ロキシーも少女に言われ、クピクピと杯を空ける。
「ぷはっ」
「へいお嬢様に追加一丁!」
「あ、どうも」
ドンとテーブルに杯を置くと、どこからか陽気な男がやってきて、酒を注いだ。
本当に、この甘い酒はいくらでも飲めた。
「おぬしもなかなかのうわばみのようじゃな! まだ若いのに素晴らしいことじゃ!」
「まだ若いなんて、あなたに言われたくはありません」
ロキシーは少女をじろじろと見る。
膝まであるブーツ、レザーのホットパンツ、レザーのチューブトップ。青白い肌に、鎖骨、寸胴、ヘソ、ふともも。ボリュームのあるウェーブのかかった紫色の髪と、山羊のような角。
どう見ても自分より年下だ。
「ふふ、世辞はよい。自分の歳はわきまえておるでな!」
こんな種族いただろうか、と普段のロキシーなら考えただろうが、今は考えない。
酔っぱらいだから。
「わたしも自分の歳はわきまえてますよ。まあどうぞ一杯」
「おお、すまんのう。しかし、ここ何百年かで酒も随分とうまくなった。昔は魔大陸にこんな甘い酒などなかったものだが」
「海族のお酒らしいですよ。ここの魔王様が取引しているんだとか」
「なんと! バグラーハグラーめ、妾に隠しておったな! 許せん!」
「いいじゃないですか、無礼講、無礼講」
「おお、そうじゃったな、今日は無礼講じゃった!」
魔王バグラーハグラーはこの辺一帯に君臨する魔王である。
でっぷりと太った豚顔の魔王で、食と酒に関しては魔大陸でも随一の知識を持つと言われている。穏健派であるが、ラプラス戦役においては急先鋒として参加。人族の領地からあらゆる食料や酒を軒並み奪い取ったことで、『略奪魔王』の称号を得た。
「うぉお、潰れたぞ!」
「うぃぃぃっく、次は誰じゃい、誰でもよいぞ、なんなら二人まとめてかかってこい」
「誰か、誰かいねえのか!」
タルハンドはいつしか上半身裸になり、テーブルの上にどっかりと座り込み、樽に肘をかけて貫禄を見せつけていた。
名乗りを上げたのは、隣に座る少女だった。
「よっしゃ、妾にまかせい!」
「なんじゃい、お嬢ちゃん、儂に勝てるつもりか? あと二〇年は経ってから出なおしたほうがよいのではないか?」
「ファーハハハ! 愚かな炭鉱族よ! 妾はこれでもすでに三〇〇年は生きておるのじゃ! 二〇年ごときでは何も変わらぬわ!」
「そうかいそうかい、そいつぁ悪かった。じゃあ掛かってこい!」
「おうとも……と、その前に名前を聞いておいてやろう! 妾に挑んだ愚か者として覚えておいてやろう!」
「『厳しき大峰のタルハンド』じゃ」
「そうか! 貴様を倒したのは『魔眼の魔帝キシリカ・キシリス』じゃ!」
そうして、キシリカとタルハンドの戦いは始まった。
追加で購入した酒はあっという間に尽きて、二度、三度のカンパが募られた。
ロキシーは自分の責任とばかりに緑鉱銭を五枚ほどカンパし、丁稚を走らせた。
屈強な男どもによって大量に酒が運び込まれ、それを全員で飲み回しながら、タルハンドとキリシカが空けていく。
ロキシーは審判だった。なにをどう審判すればいいのかわからなかったが、間に座って酒を飲みつつ、なんとなく飲んだ数をカウントする係だった。
「四〇杯目です」
運命の時。
その瞬間まで、勝負は拮抗しているように思えた。
見た目通りの炭鉱族のタルハンドはともかく、魔帝を名乗る見た目が少女のキシリカは、その体の一体どこに酒が入っていくのか……。
誰も気にしなかったのは、みんな酔っぱらいだからだ。
そして、決着がつく。
「むぐっ……ケピュ……」
タルハンドが、奇妙な音を立てた瞬間、口から噴水のように酒を吐いた。
そして、その名の通り樽のようになった腹を抱え、倒れた。
テーブルの上から床までドウと音を立てて落ち、口から酒臭い液体をゴボゴボと漏らしている。
「妾の勝ちじゃ!」
「ウオオォォォ! すげぇ! 酒飲み勝負で炭鉱族を倒しちまった!」
「妾の名はキシリカ、魔界大帝キシリカ・キシリスじゃ! 妾の名を言ってみろ!」
「キッシリカ! キッシリカ! キッシリカ!」
「この世で一番偉いのは誰じゃ!」
「キッシリカ! キッシリカ! キッシリカ!」
キシリカの勝ち名乗りと同時に、シュプレヒコールが始まり、キシリカは大層気分を良くした。
「ファーハハハハハハ! ファーハハハハ!」
「いいぞーいいぞー!」
「脱げー! 脱げー!」
それからのことを、ロキシーはよく覚えていない。
ロキシーも飲みすぎてフラフラだった。
仲間を打ち倒されたことで敵を討たなくてはと思いつつ、しかしそれは叶うことなく、意識は沈んでいく。
最後に見たのは、カウンターの上に乗り、全裸で踊りまくるキシリカの姿だった。
翌日、ロキシーは目を覚ました。
「うっ……」
ガンガンと痛む頭、自分の吐く息の酒臭さに、顔をしかめた。
即座に酒用の解毒を使って身体の毒素を抜き、ヒーリングを頭に施す。
周囲を見渡してみると、酒場だった。乱闘でもあったのか、テーブルは壊れ、酒瓶は割れ、そして大量の空樽が転がっていた。
「うう、飲みすぎましたね……」
記憶は曖昧だったが、飲みすぎたという記憶はハッキリと残っている。
ふと脇を見ると、上半身裸のタルハンドが白目をむいて転がっていた。
一瞬死んでいるのかと思ったが、炭鉱族が酒を飲んで死ぬなどありえない。
もしそれで死んだとしても、彼らは子供の頃には酒におぼれて死にたいと一度は夢見るそうだし、本望だろう。
しかし、とロキシーは再度周囲を見る。
死屍累々である。
酒に強い種族も、酒に弱い種族も、みんな転がってうめき声を上げている。中には、あのカンパ男の姿もあった。誰もが酔いつぶれ、二日酔いに苦しんでいた。
治癒魔術も使えないのに無茶な飲み方をするからだ、とロキシーは思う。
そして、そんな中に二人、立っている者がいた。
「だから弁償だよ弁償。さすがにこんなに滅茶苦茶にされたんじゃ、商売なんてできやしねえ」
「いや、あの、しかしな」
「なんだ、払えねえのか? あんた、自分の奢りだって言ってたじゃないか」
「そうじゃが、最初に支払った分で足りるかと思ってな……」
怒れる店主としょぼくれるキシリカの姿があった。
「金はねえんだな?」
「いやその、すいません、スッカラカンじゃ……」
「じゃあ、奴隷市場に売るしかねえな」
「なんと! 妾を売るじゃと……! まてまて、今すぐハグラーに連絡を取るゆえ、しばしまて」
「待てねえよ。そういって逃げるつもりだろ」
ロキシーはため息をついて、自分の懐を探った。
そして、金貨袋を取り出して中を見て、顔をしかめた。
酔っぱらいつつ、かなりの量をカンパしてしまっていた。
(いや、実際に飲んだのはタルハンドさんですから)
ロキシーはそう言い訳しつつ、気絶したタルハンドの腰から、金貨袋を外した。
中を見て、十分な量があることを確認し、ロキシーは立ち上がった。
肩のあたりから酸っぱい匂いがして顔をしかめつつ、店主に近づいた。
「どうぞ、お代です」
「ん?」
ロキシーは金貨袋から緑鉱銭を六枚ほど取り出すと、店主に握らせた。
「ちと足りねえぞ」
「この店の酒を飲み尽くしてあげたんですから、売り上げもあるでしょう?」
「…………まあ、いいか」
店主はそう言うと、踵を返し、厨房へと入っていった。
ロキシーはため息をつきつつ、金貨袋をタルハンドの腹の上に放った。
「おお……おおお……すまん、すまんのう!」
キシリカがわなわなと震えつつ、ロキシーを見上げていた。
ロキシーはそれを見下ろしつつ、その昔村長から聞いたことのある、魔界大帝のことを思い出していた。
少々イメージと違ったが、特徴は酷似している。
長寿の種族なら、見た目と年齢が一致していなくてもおかしくはない。昨晩は酔っ払っていたので気にもとめなかったが、魔王とも懇意なようだ。
「失礼、今一度お聞きしますが、魔界大帝キシリカ・キシリス様ご本人で間違いありませんね?」
「ん? おお、そうじゃぞ。最近は信じてもらえんがな。おぬしの名前は?」
「申し遅れました。ビエゴヤ地方のミグルド族、ロキシーと申します」
ロキシーが名乗ると、キシリカはおお、と頷いた。
「ロキシー? おー、知っておる知っておる。ルーデウスの師匠じゃな!」
「…………ルディを知っているんですか?」
「ウェンポートで偶然にも出会ったことがあるのじゃ。なかなか面白い男じゃったな!」
「そ、そうですか……」
一体、彼は自分のことをなんと話したのだろうと疑問に思ったロキシーだったが、恐ろしくて聞けなかった。実は、キシリカはここに来るまでの情報により、知ったかぶりをしているだけなのだが、ロキシーにはわからない。
「ふむ、ルーデウスにも助けてもらったし、おぬしらは本当によい師弟じゃな。おぬしにも助けてもらった、どれ、褒美をやるとしよう」
褒美と聞いて、ロキシーは心を躍らせた。
魔界大帝から下賜される魔眼といえば有名だ。
その能力があったからこそ、魔界大帝は魔王ではなく魔帝と呼ばれ、人魔大戦を引き起こせるほどの戦力を得たのだ。
と、そこまで考え、ロキシーはふとあることを思いついた。
「その、陛下の魔眼で、行方不明の者を探すことはできますか?」
「うん、できるぞ。この間は偶然にもバーディと出会えたからの、この世で妾の見つけられぬ者はおらぬ」
「そうですか……では、ルーデウスとその家族の居場所を。彼らは現在行方不明なのです」
ロキシーは、迷うことなく言った。
キシリカからもらえるであろう魔眼は惜しいと思ったが、キシリカの持つ上位魔眼の一つ『万里眼』であるなら、この世で見通せぬものはないと聞く。
「ほう、たった一つの願いを他人のために使うとは、あっぱれな奴じゃな! 世が世なら魔王の地位を与えてやってもよいぐらいじゃ」
「いえ、それはいりません」
「そうかそうか、謙虚な奴じゃ。どうれ……」
ぐるりと。キシリカの目の色が変わった。
それから彼女は、あちらこちらへと首をめぐらし、うむと頷いた。
「ルーデウスは中央大陸の北部におる。身軽な格好で走っておる。訓練でもしておるのかのう」
ロキシーはそれに、こくんと頷いた。
どうやら、彼はあの伝言の通り、中央大陸北部を探すことにしたようだ。
ミリシオンからそのままベガリット大陸に行く可能性もあるかと思ったが、やはり故郷の様子は見ておきたかったのだろう。
「父親はミリシオンにおるな。メイドと一緒じゃ。……ふむ、このメイドはリーリャというらしいの……っと、娘二人も同じ建物で暮らしておるらしいな」
ほう、とロキシーは息を漏らした。
リーリャとアイシャはまだ行方不明だと聞いていたが、無事見つかったらしい。
もしかすると、ルーデウスが魔大陸で発見し、送り届けたのかもしれない。デッドエンドは三人だったが、パーティを組んでいなければ他に二人いることなどわかるまい。
「母親は……ちょいまて」
キシリカはむむむと顔をしかめ、目に力を込める。
そして、見た。ゼニスの居場所を。
「ベガリット大陸、迷宮都市ラパン……かのう」
ロキシーは顔を輝かせた。
ここからは遠い位置だが、これで全員の生存が確認できた。
一人か二人は死んでいてもおかしくないと思ったが、さすがグレイラット家というべきか。
運が強いらしい。
「じゃが……ちとおかしいのう」
キシリカは顔をしかめ、ぐりぐりと目を動かす。
「何か問題が?」
「いや、ふーむ、ちとよく見えん」
「よく見えない? 陛下の目を持ってしても、ですか?」
「妾もまだ本調子ではないからのう……ま、行ってみればわかるじゃろ」
「それでは困ります。何か問題があるなら詳細を……」
何事もなく言うキシリカだったが、ロキシーはさらにつっこんで話を聞こうとする。
これまで旅をしてきた中で、難民が悲惨な目にあってきているのは見てきた。魔界大帝の魔眼を持ってしても見えない大変なこと。その内容によっては、今の喜びが、ぬか喜びになる可能性もあるのだ。
「なんじゃ……そんなこと言われても、見えんものは見えんのじゃ。おお、そうじゃ。案外、迷宮の中におるのかもしれんぞ。迷宮都市じゃし、妾は行ったことないけど」
「迷宮の中は見えないのですか?」
「うむ。ベガリットの迷宮は高濃度の魔力で満ちておるからのう」
ロキシーは考える。
ゼニスはかつて、パウロやエリナリーゼ、タルハンドと共に迷宮探索をしていたと聞く。
エリナリーゼ、タルハンドの実力はこの旅の間で十分にわかっている。彼らと旅をしていたのなら、迷宮にも潜れるだろう。
しかし、なぜ今まで連絡もせずにいるのか。もう三年も経つというのに……。
「とにかく、生きてはいるんですね?」
「うむ、それは間違いない」
ロキシーはその言葉を信じることにした。
何らかの理由があって、迷宮に潜らなければいけないことになっているとそう考え、ロキシーは頭を下げた。
「わかりました。ありがとうございます」
「よいよい。助けてもらった礼じゃ」
キシリカは大仰に頷くと、ややフラフラとしながら、酒場を出ていった。
★ ★ ★
その日の午後。
何事もなかったかのように起き上がって迎え酒を飲み始めたタルハンドと、首筋に大量のキスマークをつけて帰ってきたエリナリーゼ。
二人と一緒に会議を行う。
「魔界大帝に出会えるなんて運がいいですわね」
キシリカについて話した時、エリナリーゼはそう静かに笑っただけだった。
ロキシーもあまり大事件とは思えない。酒場で酔っ払っていた時に出会ったからだろうか。それとも、あまりにも威厳がなかったからだろうか。
「じゃが、これで我らの旅も終わりじゃな」
タルハンドが少々名残惜しそうに言った。
これからミリス大陸に戻るまで、急いでも一年ほど掛かるが、旅の目的は達成した。
パウロの家族全員の生存を確認し、残った一人の居場所も特定した。終わりだ。
「ロキシーはどうしますの?」
「わたしはミリシオンに戻って、パウロさんにこのことを話すつもりです」
「そう、じゃあ途中でお別れになるわね」
エリナリーゼとタルハンドはパウロとは顔を合わせたくないらしい。
別れ際の大げんかが理由だそうだが、何があったのかはついぞ話してもらえなかった。
ロキシーもそれほど興味はないので、しつこく聞きはしなかったが。
「ふうむ、しかし、ルーデウス一人だけ、遠いな」
タルハンドは顎に手をやり、ぽつりと言った。
それを聞いて、ロキシーもハッとなった。
これからロキシーはミリシオンに戻る。恐らく、そのままパウロたちにくっついてベガリット大陸へと赴くことになるだろう。そうすると、ルーデウス一人だけが事情を知らないまま、中央大陸北部を探すこととなる。
捜索中ということは所在地もわかっていないので、手紙も届くまい。
「どうにかして知らせてあげたいですわね……」
エリナリーゼもそう言って悩む。
しかし、方法はない。中央大陸北部は近いように見えて遠いのだ。
ロキシーもまた、考える。
ルーデウスは優秀だがまだ若い。
今の時期を徒労で過ごさせるのはさすがにかわいそうでもある。
家族と合流するにしても、そのまま一人立ちするにしても、せめて一言、もう探さなくていいよ、と伝えてあげたいところだ。
「そこに妾がババババーン!」
「そして我輩もバンババン!」
唐突に。唐突にその二人は現れた。
「話は聞かせてもらった!」
「盗み聞きでな!」
バンと扉を開けて入ってきたのは偉丈夫だった。
一目で魔族とわかる黒曜石のような肌に、六本の腕。一番上は腕組みされ、中段は矢印を作ってビシっとロキシーを差し、下段は腰に当てられている。
腰まで伸びる長髪は紫。
そして、その肩の上でふんぞり返っているのは何を隠そう、魔界大帝。
「よし! 妾はキシリカ・キシリス! 人呼んで、魔・界・大・帝!」
「そしてその婚約者、魔王バーディガーディ!」
唐突に現れた二人に、ポカンとした三人。
まず最初に反応したのは、エリナリーゼだった。
「えっと、今朝ぶりですわね、お兄さん」
「フハハハハ、最高の一晩だったぞお姉さん!」
グっと拳を握り、人差し指と中指の中に親指をいれ、バーディが答える。
ロキシーが冷や汗をたらしつつ、聞く。
「し、知り合いなんですか?」
「ええと、一応、そうですわね……?」
なんでも昨晩、男と一緒に酒場を出てから、エリナリーゼは別の酒場に入ったそうだ。
男は下心たっぷりでエリナリーゼに飲ませまくり、エリナリーゼもまた下心たっぷりで飲みまくった。ぐでんぐでんに酔っ払ったエリナリーゼはそのまま宿へと連れ込まれ……。
気づいたら、この真っ黒い男の腕の中で目覚めたそうだ。
そして、なんとなくそのまま突入して、午後までヤっていたそうだ。
「えっ? でもいま、婚約者って……あれ? あ、挨拶が先でしょうか?」
ロキシーは目を白黒させつつ、とりあえず頭を下げた。
「うむ、ロキシーよ、面をあげい。なに、バーディはモテるゆえ、こうしたことなど日常茶飯事じゃ」
「うむ、というよりキシリカにはまだ物理的に入らんから仕方がないのだ!」
そのフリーダムな発言に、ロキシーの脳の処理能力は追いつかない。
最近ではエリナリーゼのせいで相当な耳年増に育ちつつあるロキシーだが、魔界大帝の婚約者の魔王を名乗る男が自分の仲間と不倫、となれば、理解の範疇を超えていた。
「しかぁし! そんなことはよいのだ!」
「うむ、どうせ通り過ぎあっただけの関係だしな!」
テンションの高い二人に、正直ロキシーはついていける気がしなかった。
魔王バーディガーディの名は知っている。ビエゴヤ地方に君臨する魔王だ。
『不死身の魔王バーディガーディ』。ラプラス戦役で暴れまわった『不死魔王アトーフェ』の弟。
ラプラス戦役においては穏健派に属し、キシリカ城にて魔神ラプラスと戦って敗れている。
現在行方不明だが、偉い人であるはずだ。
「ロキシーよ、妾もルーデウスには恩のある身。ルーデウスが道に迷っているというのなら、妾も力を貸そう!」
「といっても、我輩の権力を使うがゆえ、又貸しだがな!」
混乱するロキシーより先に、タルハンドが蘇った。
彼はたっぷりと蓄えたヒゲを撫でつつ、訝しげな視線をキシリカに送る。
「よろしいのですかな?」
「おお、そなたは昨日の炭鉱族! よいともよいとも、なあバーディ?」
キシリカが頭をポンと叩くと、魔王はこくりと頷いた。
「うむ、我輩もキシリカが事あるごとに凄いというルーデウスというクソガキのことは気になっていたのでな! 本当にすごいのかどうかこの目で確かめてやるのだ!」
「なんじゃなんじゃ、嫉妬かダーリン?」
「おうとも嫉妬さハニー」
「まったく、バーディはまだまだ子供じゃのう。妾が愛しているのはおぬしだけだというのに……」
「ふっ、我輩は愛の上にあぐらをかかんのだ。恋敵は叩き潰すのみ」
叩き潰されると困るのだが、と思うロキシーだったが、この二人は聞いてくれる気がしなかった。
「ふふふ」
「フハハ」
「ファーハハハハ! ファーハハハ! ファーハぐげほげほ」
「フハハハハハ! フハハハハ! フハ……大丈夫か?」
ロキシーの理解が追いつかないまま、話がグイグイと進んでいった。
★ ★ ★
この世界の常識の一つだが、世界中の海は海族に支配され、地上に住む人々はその通行を制限されている。これはラプラス戦役の戦後処理中に起きたゴタゴタが関係しているのだが、それはおいておこう。
魔王バグラーハグラーは海族の王と個人的な交友がある。
交友があったところで海族全体で決められた掟を破るわけにはいかないのだが、そこはそれ。
個人的な友人のみをこっそりと通すことは黙認されているらしい。
魔王バーディガーディと魔王バグラーハグラーは旧知の仲である。そのツテを使えば、天大陸を経由せずとも、中央大陸へと渡ることは造作もない、ということだ。
しかし、ここでロキシーを含め三人が海を渡ってしまうと、ミリシオンへの報告が遅れることとなる。誰かはミリシオンへと向かわなければならない。そして、魔大陸は一人では通過できない。
安全な中央大陸ならまだしも、魔大陸は危険な魔物が多い。
例えば、ロキシーは優秀な魔術師だ。
判断も素早く、詠唱も速い。戦闘だけならロキシー一人でも切り抜けられるかもしれない。
だが、夜は眠らなければならないし、集団で襲い掛かってくる敵相手に、不覚を取る可能性はある。最低でも二人は必要なのだ。
「わたくしは嫌ですわ。パウロなんて顔も見たくない」
「儂もじゃ」
「わかりました。ではわたしが行きましょう」
二人にわがままを言われ、まずロキシーはミリシオンへと向かうこととなった。
ロキシーとしては、ルーデウスの顔を見たかったのだが、仕方がない。
そして、もう一人。二人は顔を見合わせ、すぐにタルハンドが折れた。
「ふむでは、儂かの。実を言うと、船には乗りたくないしのう……」
「悪いですわね、タルハンド」
肩を落とすタルハンド。
別にミリシオンまで赴いたら手紙でも出せばいいと思うロキシーだったが、二人には二人の考えがあるので、深く考えないことにした。
自分には、パウロに会いたくない理由などないのだから。
そうして、ロキシー一行は二手に分かれることとなった。
ロキシーとタルハンドは来た道をもどってミリシオンへと。エリナリーゼは魔界大帝キシリカ・キシリス、魔王バーディガーディと共に中央大陸北部へ。
船が出るまでは少々時間があったが、ロキシーは先に出立することにした。
「エリナリーゼさん、今までありがとうございました」
「こちらこそですわ。ロキシー」
エリナリーゼと固く握手を交わすロキシー。
「ロキシー、いいオトコを見つけたら、逃がしてはいけませんわよ。上の口と下の口の両方を使ってガッチリと捕まえておかないといけませんわ」
「またその話ですか?」
「いいからお聞きなさいな。本当に好きな相手にはグイグイいきなさい。愛なんてその後にゆっくりと育んでいけばいいんですから」
エリナリーゼの言葉に、タルハンドがため息をついた。
「おぬし、それ、ゼニスにも言っとったじゃろ?」
「そうですわ。それでゼニスはパウロを手に入れた。わたくしの教えは完璧ですわ」
そう言われ、ロキシーはなるほどと思った。
ロキシーにとって、パウロとゼニスは理想の夫婦だった。
エリナリーゼの助言でああいう風になったのであれば、聞く価値はあるだろう。
「わかりましたエリナリーゼさん。グイグイいってみます」
手を離す。ロキシーは背が低いため、エリナリーゼを見上げる形となる。
「ルディには私がよろしく言っていたと、伝えてください」
「もちろんですわ。ロキシーが夜中に切なくなってゴソゴソやっていたことを教えてさしあげます」
「ちょ、なんで知ってるんですか。やめてくださいそういうことを言うのは。別にルディを想ってやっていたわけじゃありませんし」
「はいはい」
そこでふとロキシーは思った。
もしかすると、ルーデウスとエリナリーゼが出会うと、そのまま一緒の宿に泊まってしまうのではないだろうか、と。
今から北部を探せば、一年ぐらいでエリナリーゼはルーデウスを見つけるだろう。
あれから十年近い年月が流れている。ルーデウスはもう、十三歳か十四歳ぐらいのはずである。それぐらいなら、エリナリーゼの目にとまってもおかしくはない。
それは、ちょっとだけ、嫌だった。
「なんですの、唐突に黙りこんで」
「いえ、その、やっぱりルディがいい男になっていたら、手を出すんですか?」
さり気なさを装って聞いてみると、エリナリーゼは「ハッ」と息を吐いた。
「わたくし、パウロの娘になるつもりは毛頭ございませんことよ」
本気で嫌そうだった。
ロキシーはほっとしつつ、「そうですか」と答えた。
「では、そろそろ出立します」
「行ってらっしゃいロキシー。お元気で」
「はい、エリナリーゼさんも」
エリナリーゼはちらりとタルハンドを見る。
虫けらを見下ろすような目で、自分より背丈のちいさな炭鉱族を見下ろした。
「タルハンドはどっかで野垂れ死になさいな」
タルハンドは心底不愉快な顔をして、ペッと唾を吐いた。
「その言葉、そっくりそのままお返しするわい」
ロキシーはそれを見て、この二人はそこそこ仲がよかったんだな、と再認識した。
そして、エリナリーゼは船に乗る。
大昔から存在する、海族の船。海の魔獣によって牽かれる船は、人族のそれに比べるとややみすぼらしく見えるが、人族のそれよりも高速で、安全性の高いものであった。
エリナリーゼはバーディガーディと共にタラップを渡る。
すると、背後からキシリカの笑い声が響き渡った。
「ファーハハハハ! ではまた会おうバーディよ! 会いたくなったらすぐにでも魔大陸に戻ってくるがよい!」
「うむ、我が婚約者殿も達者でな! またいずれ会おう! フハハハハ!」
「今度は何年後になるかわからんがのう! ファーハハハハ!」
魔界大帝キシリカ・キシリスは船には乗らなかった。
エリナリーゼはそのことに首をかしげた。
「あら? あのお方は乗らないんですの?」
「うむ、キシリカは魔大陸から出られんのだ!」
「そう、呪いですの?」
「似たようなものである」
魔界大帝キシリカは魔大陸からは出られない。
ゆえに、今日も今日とて、魔大陸を彷徨うこととなる。
ロキシーはそんなこととはつゆ知らず、キシリカは一緒に船に乗り、ルーデウスに出会いに行ったのだろうと考えていた。
エリナリーゼは、そんなことならロキシーの方についててほしいと思った。
魔大陸はあれでいて、危険が多い。
タルハンドが一緒なら万が一もないだろうが、もう一人ついているだけで安全性が上がる。
それが魔界大帝ともなれば、安全は確保されたようなものだ。
が、直後にその考えを打ち消した。
あんなのにまとわりつかれたらロキシーがかわいそうだ、と。
ロキシー・ミグルディアの旅は続く。
番外編 『歪でも変わらないもの』
サナキア王国には、水田が大きく広がっている。
その水田を割るように走る一本の街道に、ノロノロと移動する馬車の影があった。
馬車は数名の兵士によって守られているものの、剣呑な気配はない。兵士たちも、どこか休暇のような気の抜けた顔をしながら歩いていた。それだけでも、馬車の中に要人が乗っていないことが見てとれるだろう。
その上、金目のものを持っている気配もなく、しかし護衛だけは多いこの馬車を襲う者はそういまい。
実際、馬車に要人は乗っていなかった。
馬車に乗っているのは、三人の女だ。
そのうちの一人は、シーローン王国の騎士ジンジャー・ヨークである。
彼女は馬車の出口付近に座り、残り二人の女の会話を聞いていた。
「飼主のお兄ちゃん、かっこよかったなぁ」
元気いっぱいに喋っているのは、ダブダブのメイド服を来た少女、アイシャだ。
「やっぱり、結婚するならああいう相手だよね、ね、お母さん?」
「え、ええ、そうですね」
対するは、やはりメイド姿の女性。
アイシャをそのまま大きくして眼鏡を掛けたような彼女の名はリーリャ。
彼女を見た者は、その眼鏡の奥にある冷たい眼光を見て、クールで冷めた女性という印象を持つ……のだが、現在は目が泳いでいた。
「あたしを助けてくれた時なんてすごかったんだよ? こう、指先をくいっと向けただけで地面に穴が開いたり、ポーンと上に飛んだりしてね……あれも魔術なのかな? 無詠唱で何でもできるって、すごいよね。まるでお伽話に出てくる魔法だよ」
「そうですね、無詠唱魔術は……素晴らしいものです」
アイシャは先ほどから、『カイヌシのお兄ちゃん』をベタ褒めしていた。
対するリーリャは、少々戸惑い気味だ。
どうやら、娘は『飼主』の正体が己の兄ルーデウスだと気づいていないらしい。
出がけにお兄ちゃんと言ったから、てっきり気づいているものと思っていたが、あくまで「年上の男性」という意味の「お兄ちゃん」であるらしかった。
「それで、あたしもあんなの初めてだったから、怖くておもらししちゃったんだけど、なんかね、カイヌシのお兄ちゃん相手だと恥ずかしくなかったんだよね。もう、この人なら見られてもいいかな、って思っちゃって……もしかして、これが恋なのかな?」
手を祈るように組んで目をキラキラさせるアイシャ。
リーリャはそんなアイシャを見て、迷っていた。
今、このタイミングで飼主がルーデウスであることを言うべきかどうかを。
つい先日まで、アイシャはルーデウスを嫌っていた。
ルーデウスはこんな素晴らしい人間なのだというリーリャに反発し、そんなはずはないじゃんと嫌悪感をあらわにそっぽを向くのがアイシャだった。
無論、リーリャのやり方にも問題があった。リーリャはアイシャをルーデウスに仕えさせようと思うあまり、彼の良いところや凄いところばかりを言ってしまったのだ。
優秀であるアイシャは、ルーデウスが非の打ちどころのない完璧な人間であると聞けば、それがありえないことであるとすぐに見抜く。そして、母の隠しているルーデウスの悪い部分を見つけ出し、それを自分の中でクローズアップさせてしまう。
人は、他人から聞いたことより、己が見つけたり気づいたことを重要視する。
あるいは数年後のアイシャなら、自分が気づこうと相手に教えられようと、その情報の信憑性は同等であると気づいただろうが、彼女はまだ若かった。
母の言い分は嘘ばかりで、ルーデウスはろくでもない人間だと、考えてしまっていた。
その点について、リーリャは反省している。もっと別の言い方もあっただろうに、偶像のような兄を押し付けるような言い方をしてしまったことを。
もっとも、リーリャがいくら反省しても、一度決まった印象というものはなかなか戻せない。
シーローン王国に滞在中、リーリャは半ば、アイシャの認識を改めることを諦めていた。
しかし、何の因果か、今のアイシャは、『飼主のお兄ちゃん』をベタ褒めしている。
リーリャは考える。
ベタ褒めしている飼主の正体がルーデウスであることを明かせば、アイシャの兄嫌いも治るのではないか。
そして、自分の希望通り、アイシャはルーデウスに仕えてくれるのではないか。
そんな風に思う反面、ルーデウスが己の正体を隠していたことを憂慮していた。
彼は最後まで正体を隠していた。
なぜそんなことをしていたのかわからない。
だが、アイシャは嘘やごまかしが嫌いだ。
賢い子であるから、大人が適当に言ったことを見抜き、糾弾してくる。
今更になって「実はカイヌシの正体はルーデウスでした」と明かすことで、アイシャがより一層ルーデウスを嫌いになる可能性がある。
ルーデウスが最後まで正体を明かさなかったのは、心に後ろ暗いところがあるからだ、やっぱりお兄ちゃんは変態なんだ、嘘をついてまであたしのパンツを洗いたかったんだ、と曲解されてしまうかもしれない。
リーリャとしては、それは避けたかった。
「ねー、お母さーん。お兄ちゃんがもし死んでたらさ、カイヌシさんに仕えてみたいな~」
「……」
普段なら、アイシャがそんなことを言えば、リーリャは縁起でもないことを言うなとばかりにアイシャの頭を叩く。
しかし、今は何もできず、ただただ冷や汗を流しながら苦笑するだけだった。
カイヌシがルーデウスであることを伝えるべきか否か。
うまく伝えれば、アイシャは兄を好きになってくれる。
失敗すれば、アイシャはより一層兄を嫌いになる。
後者は許容できないが、この賢すぎる娘を誘導できるほど、リーリャは己の口に自信を持っていない。
どうすべきか。わからないまま、アイシャの話だけが続いていく。
「カイヌシさんに仕えたあたしはね、カイヌシさんのために身を粉にして働くの。でもカイヌシさんを警戒していないあたしは、着替えとかも無防備で、ある日、ついむらむらっときたカイヌシさんに押し倒されて、お手つきになっちゃうの。その日から始まる、みだらにとろけた毎日……あたしは体だけって割り切ってるんだけど、ある日カイヌシさんが「お前の心も欲しい」っていって結婚を申し込んできて……きゃー」
「……」
悩むリーリャとは裏腹に、アイシャは心中で笑っていた。
カイヌシが兄であること、兄が変態ではなかったこと、完璧ではないがしかし母の言うとおり優秀だったこと……。
そんなことはすでに見抜いていた。
その上で、母をからかっていた。
正直アイシャは、小さな頃からあれをしろ、これをしろとアイシャを束縛し続けた母のことがあまり好きではなかった。
理由を聞いても、とにかくやりなさいと言われるだけの毎日。
顔も見たことのない兄に仕えるためだけの訓練……嫌気がさすのも当然だ。
だが、それも実際に兄を見るまでの話だった。
無詠唱で魔術を操り機転を利かせて包囲を脱出する判断力、単身でシーローン王城に乗り込んで母を助け出す胆力、見知らぬ少女におしっこを引っ掛けられても嫌な顔一つしない優しさ、それらはアイシャの中で『カッコイイとはこういうことさ』というキャッチフレーズが乱舞するほどだ。
あの優秀な兄の役に立ちたいのであれば、大抵のことはできなければダメだろう。
そう納得することはできたし、今ではむしろ感謝すらしている。
幼少からの訓練がなければ、自分はあの兄に仕えることに尻込みをしてしまっただろう。
「あーあ、お兄ちゃん、死んでないかなぁ、そしたらカイヌシさんのところにひとっ飛びなのになぁ」
「る、ルーデウス様が死んでなかったら、ちゃんとお仕えするんですよ?」
「もちろんだよ~、わかってるよ~」
が、それはそれとして。
狼狽する母を見るのは、アイシャとしても初めての経験であった。
「あ、でも一年ぐらいでいいでしょ? その後は、ずっとカイヌシさんのところにいたいなぁ」
「そ、それはいけま……うーん……」
なかなかに楽しいこの状況を、彼女はまだしばらく、楽しむことにしたのであった。
★ ★ ★
リーリャという女は、アスラ王国の片田舎で生まれた。
ドナーティ領にある、さして大きくもない町の、水神流の道場の一人娘だ。
苗字はない。
アスラ王国では平民に苗字はつかない。
リーリャはただのリーリャとして生まれ、道場の娘として幼い頃から剣を握りながら、すくすくと育った。
リーリャは親に似て口下手であった。
幼い頃から無口でクールな振る舞いの目立つ少女であった。
可愛げは、あまりなかっただろう。
だが、一生懸命な子だったため、周囲には愛されていた。
剣術の才が無いのは誰の目にも明らかであるにもかかわらず、懸命に剣を振るリーリャの姿は、他の門下生たちの目には、非常に愛らしく映った。
門下生たちはリーリャを妹のように、あるいはマスコットのように可愛がり、リーリャもまた彼らを兄のように慕った。
誰の目から見ても平和な、村の道場の風景であった。
門下生の見る目が変わり始めたのは、リーリャが十三歳の頃からか。
二次性徴期を迎えたリーリャの体は、急速に女らしくなっていった。
門下生たちは一緒に水浴びするのを遠慮するようになり、二人きりで話すのを避けるようになり、かといってリーリャを避けたりのけ者にするわけではなく、時折熱い視線を送るようになった。
リーリャも、薄々感づいていた。
彼女は思春期だが、現実的な子だった。
自分には、兄も弟もいない。母はリーリャを産んだ後に体を悪くしてしまった。
道場の跡取りは存在せず、父は頭を悩ませ、母は申し訳なさそうにしていた。
ゆえにリーリャは、自分はいずれ門下生の誰かと結婚して、その門下生が道場を継ぐのだと考えた。門下生の面々は全員が兄か弟のようなものなのでピンとはこなかったが、彼らが互いに牽制しあっているのを見れば、漠然とでも想像はつく。
思春期の女剣士と、それをそわそわと見守る門下生たち。
道場内では、道場主である父親が、娘の結婚相手として誰を選ぶか……次の道場主として誰を選ぶかという話題でもちきりとなり、次の道場主になりたい者や、単純にリーリャが好きで結婚したい者が水面下で争い始めた。
そのまま何事もなく時がすぎれば、いずれ誰かが何かを決断し、リーリャの想像通りの結末が待っていただろう。
道場にパウロが転がり込んできたのは、そんな時期である。
金もなく、住む場所もないパウロを、リーリャの父は快く迎えた。
活発で明朗な性格の持ち主であるパウロは、瞬く間に周囲の人気者となった。
また、彼は剣術の才能にも恵まれていた。
元々剣神流の剣術を習得していたということもあったのだろうが、リーリャが十年かけて学んできたことを瞬く間に吸収し、追いつき、抜き去り、あっという間に道場主であるリーリャの父ですら太刀打ちできぬほどの実力になった。
剣術の才能があり、門下生からも人気がある。
そうなると、パウロがリーリャの伴侶となる流れができた。
リーリャは戸惑いつつも、唐突に降って湧いた話の展開に、心を躍らせていた。
パウロは、それまでリーリャが見てきた人物の誰とも違って見えたからだ。
奔放で、剣術に対する凝り固まった考えがなく、家柄や跡継ぎに固執しない。その自由な生き方は、リーリャの目には眩しく見えた。
だが、パウロはあまりにも違いすぎた。
剣術に対する考え方も、家や跡継ぎに対する考え方も……そして『女』に対する考え方も。
考え方の違いは、それまでパウロを快く受け入れていたはずの門下生と確執を生んだ。
門下生たちも、唐突にやってきたパウロに道場主の座を奪われるのを面白くは思わなかったが、しかしこいつなら仕方ないと思える程度にはパウロのことを認めていたのだが、自分たちが大切にし、手に入れようと競ってきたものを無価値だと断じられれば、話は別だ。
彼らは、パウロを排除しようと決めた。
打ち合いの稽古の時に集中的に攻撃をしたり、後ろから蹴り飛ばしたり、道着にわざと水をこぼしたり……。
リーリャはそんなパウロをかばい、門下生たちを叱責した。だが、門下生たちがそれを面白いと思うわけもなく、行為はエスカレートした。
もし、パウロが普通の少年であったなら、そこで終わっていただろう。
門下生たちにヘコヘコして道を譲るか、追い出されるように道場から出ていくか……。
だが、パウロは悪童だった。
居心地の悪くなった彼は暴挙に出た。
ある日の晩、リーリャの寝所に夜這いを掛け、その純潔を奪ったのだ。
リーリャはもちろん抵抗したが、為す術もなかった。
事が終わった後、リーリャは呆然としていた。
自分の身に何が起こったのかわからなかった。先日まで朗らかに話していたパウロがそんなことをするなどとは、思ってもいなかったからだ。
彼女の母親が、いつまで経っても起きてこない彼女の様子を見て悲鳴を上げる頃には、パウロはとっくに町を出ていた。
それから、リーリャはしばらく男性不信に陥った。
門下生からの視線に恐怖を感じるようになり、身体的な接触は露骨に避けるようになった。
十五歳で成人した後も、それは変わらなかった。
リーリャの父は、代々受け継がれている道場を存続させる義務があった。
己には息子がおらず、リーリャの母もリーリャを産んだ後に体を壊してしまった。
リーリャと門下生の誰かを結婚させて、存続させなければいけない。
だが、父は父だった。リーリャがここまで心に深いキズを負っているのに、無理に男とくっつけるのは、親としてできなかった。
ゆえに独自のツテを使い、リーリャをアスラ王家の『近衛侍女』として推薦することにしたのであった。
そうして近衛侍女となったリーリャは、仕事の中でいつしか男性不信を克服し、王女を守って負傷をし、実家に戻らずフィットア領へと行き、何の因果かパウロに拾われ、抱かれ、子供ができて、妻となった。
正直な話、当時のリーリャは、自分が幸せなのかどうかわからなかった。
妾のような立場で、パウロは恐らく、自分よりゼニスの方をより愛していた。
ゼニスのことは友人として好きだったが、後ろめたさのような、申し訳なさのような、複雑な思いもあった。
彼らは自分を受け入れてくれてはいるが、不安定で不安な日々が続いていた。
心の拠りどころとなったのは、自分を助けてくれたルーデウスだ。
娘を彼に仕えさせるというのは自分の心が完全に理解できないリーリャにとって、最も確かなことであり、その後の行動の指針となった。
一方で、自分は娘を愛していないのではないか、と思うところもあった。
父は自分を考慮して、道場の存続とは別の道を作ってくれた。
だというのに自分は娘を、アイシャの気持ちを考慮せず、自分の心の安寧に利用しているだけではないのか、と。
その思いは、アイシャが通常の子供よりも優秀であることがわかればわかるほど肥大化した。
不安だった。
転機となったのは、奇しくも転移事件だった。
リーリャはアイシャと共に、シーローン王国へと転移した。
リーリャにはもちろん、何が起きているのかなど、わからなかった。
唐突に気を失ったと思ったら、気づいた時にはずいぶんと高価そうな部屋にいて、あれよあれよという間に兵士に囲まれていた。
敵意と殺意にあふれる兵士たちを前にしたリーリャの脳裏は真っ白で、何も理解できぬまま、咄嗟に思ったのは「娘を守らねば」だった。
近くにあった燭台を掴み、アイシャを己の背中に押し込めて、リーリャは戦った。
しかし長いこと実戦から離れていたリーリャの体は思うように動かず、足の古傷が動きをさらに鈍らせた。
さしたる抵抗もできず取り押さえられ、アイシャは兵士たちの手によってリーリャの後ろから引きずり出された。
「お願いします! その子だけは! 娘だけは助けてください! 私はどうなっても構いません! だから娘だけは!」
みっともなく泣きながら叫んだのは咄嗟のことで、無意識で、本心だった。
本心だったのだ。
その後、リーリャたちは抑留された。
城に軟禁され、外部との通信を遮断され、メイドとしての仕事を強要された。
しかし、リーリャの心は以前よりも晴れやかであった。
彼女は、咄嗟に出てきた言葉がアイシャを助けるものであったことに満足していた。
もはや、アイシャに対する想いへの不安はなかった。
すでに、ルーデウスに仕えさせるということに何の疑問も抱かなかった。
自分の行動が利己的な欲求だけから来るものでないと、確信したからだ。
パウロの血筋ゆえか、自由で奔放な性格をしているアイシャは束縛されることを嫌がり、リーリャを煙たがった。
ルーデウスに仕える意味を理解できず、賢い彼女は意味のわからない目的に対して努力することを嫌がった。
でも、リーリャは諦めなかった。親として半ば無理やりにでも自分の知る、ありとあらゆる知識を教えこんだ。
いつか、アイシャもわかってくれる。
ルーデウスがあの日と変わらない限りは、彼女もきっとわかってくれる。
そう思いながら……。
★ ★ ★
「カイヌシのお兄ちゃん……ああ、思い出してもうっとりしちゃうなぁ。あたしを抱き上げたあのたくましい腕、凛々しい顔、狼狽した態度……」
そして、アイシャはわかってくれた。
実際にルーデウスを見て、リーリャの行動の意味を理解してくれた。
──と、最近の彼女の言動を見ていて思うのだが、何か違う。
想定外の伝わり方である。
「アイシャ」
しかし、リーリャの気持ちに変わりはない。
彼女は揺れる馬車の中、ゆっくりと立ち上がった。
楽しげに、イタズラな笑みを浮かべて話を続けていたアイシャは、母の動きにビクリと身を震わせた。
リーリャは、アイシャが悪い言動をすると、ゲンコツで頭を叩く癖があった。
もっとも、アイシャは賢い。ある程度は自分が叩かれる状況を予測している。わざと悪いことを言って、叩かれて舌をペロリと出してごめんなさいするまでが、彼女のお茶目だ。
しかし、今回はなぜ母が怒ったのかわからなかった。
褒めているのだ。母が仕えろと言われた兄を。アイシャなりに。
言い方を間違えただろうか。それとも、カイヌシは、本当は兄ではなかったのだろうか。
そんな不安が一瞬でアイシャの頭をよぎり、リーリャの手がアイシャの頭に迫った。
「……?」
アイシャが体を硬直させた瞬間、アイシャが頭に感じたのは、柔らかな感触だった。
リーリャがアイシャの頭を撫でていた。
彼女がアイシャを撫でることは、実は少ない。
優秀なアイシャはできて当然なことが多いため、どうしても褒めることが少なくなってしまっていたのだ。
「お母さん?」
娘に呼びかけられ、リーリャは己の顔を見せるのがなぜか恥ずかしくなった。
撫でる手をアイシャの背中にまわし、その小さな体を抱き寄せた。
「アイシャ……カイヌシさんでも、ルーデウス様でもいいです」
ルーデウスには、現状でアイシャは連れていけないと断られた。
だが、それはあくまで、今は無理だという話だ。
数年後、ルーデウスと再会する日が来るだろう。確実に。
「その時が来たら、精一杯、仕えなさい」
リーリャはそう言うと共に、その時まで、アイシャを立派に育てようと誓っていた。
それは決してルーデウスのためではない、リーリャ自身のためではない。
リーリャは己の考えに利己的なものも含まれていることを自覚しつつも、それでも、アイシャに立派に育ってほしいと、心から願っていたのだ。
「あはは、やっぱりバレてた……かな……?」
アイシャは己の頭にある柔らかい感触にむず痒い感覚を覚えて、口元をゆるめた。
「も、もちろんわかってたよ? カイヌシが、お兄ちゃんだって……それで、お母さんをちょっとその、からかってみただけで……」
アイシャはしどろもどろに言い訳をしながら、ふと思った。
そういえば、母にこうして抱きしめられたことはなかったかもしれない、と。
そう思った時、どこからか無性に嬉しさが湧いてきた。
ついぞなかった感情に、アイシャはなぜか、己の目から涙がこぼれ落ちるのを感じた。
嬉しくて泣いたのは、幼いアイシャにとって、初めての経験だった。
止めどなく溢れてくる涙に戸惑いつつも、しかし止めようという気にはならず、ただ母の背中に触れ、ただ母の肩を汚した。
「……」
二人を見ていたジンジャーは目を逸らした。
彼女の視線の先には、風に揺れる水田がどこまでもどこまでも続いていた。
作者闲话
『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ XX』
理不尽な孫の手先生 こぼれ話
皆さんこんにちは。
理不尽な孫の手です。
『無職転生』も六巻となりました。
実を言うと、もし書籍になったら、最低でもここまでは出したいと思っていたラインが、六巻でした。六巻まで出せたら打ち切りでもいいや、次を頑張ろう、ぐらいに思っていたのですが、なんとか七巻以降も出させて頂けるようです。
それもこれも皆様のお陰です。ありがとうございます。
さて、六巻では二巻の最後に起きた転移事件が一応ながらの結末を迎え、同時にルーデウスの少年期も終わり、肉体的にも精神的にも次のステップへと以降します。
物語としての区切りの一つです。
というわけで、ここで無職転生の『少年期』を振り返ってみようと思います。
・二巻
幼年期(一巻)が終わり、少年期が始まります。
七歳となったルーデウスは、新たなるステージとしてフィットア領の城塞都市ロアへと向かいます。
そこで行うのは出来の悪い生徒への家庭教師です。
自己の鍛錬や、過去からの脱却を主軸をおいた一巻から、自分が学んだことを他人に教えることを主軸においた二巻へ、さらに三巻以降のメインキャラクターであるエリスがどういう人物で、ルーデウスがどう仲良くなったのか、という事を掘り下げる巻となります。
・三巻
転移事件が起こり、ルーデウスは魔大陸へと飛ばされます。
そこで出会ったのが、一族の名誉回復を願いつつ旅をしている戦士ルイジェルド。
彼に助けられつつ、アスラ王国へと帰るための大冒険が始まる……というわけではありません。金も何もない状態からのスタート。始めるのは小銭稼ぎです。あくまでも現実的な一歩からです。
人としては現実的でありながら、しかし冒険者としての第一歩は、一巻と二巻で学んだ事を大いに活用して飛ばしつつ、ルーデウスは冒険者として歩み始める話となります。
・四巻~五巻
四巻から五巻は、冒険を楽しんでいたルーデウスが、現実に引き戻される話です。
ルイジェルドやエリスと親交を深め、冒険者という職業を楽しみながら、ゆるやかに目的地へと移動していくルーデウス。道中では紆余曲折ありつつも、無防備なエリスの姿に我慢できなくなったり、無防備な幼女におさわりしたり、それが原因で牢屋に入れられたりと、楽しいイベントが盛りだくさんで、頑張っているつもりでもどこか余裕のあったルーデウス。
そんな彼は、五巻においてパウロと再会し、ルーデウスは転移事件というイベントを楽しんでしまっていた事に気づきます。
ここで、主人公はまた一つ大人になり、またこの世界の住人としての自覚のようなものを持ち始めるようになります。
・六巻
そして、六巻。
六巻では、三巻の時に設定した目標である中央大陸、そしてフィットア領へと到着します。
そこで、ルーデウスは初めて、自分の周囲で何が起こったのかということを目の当たりにします。
一巻の時のような生活に戻ることは出来ない。
これからは何を目指していけばいいのか、まったく思いつかないが、でも今までエリスと一緒にやってきた。今まで通り彼女を助け頑張っていこう、と結論つけます。
しかし、それもほんのちょっとした意思疎通の齟齬から、結局はエリスと別れる事になってしまいます。
傷心のルーデウスは、この世界にきて初めて「一人」になってしまうのです。
無職転生を書き始めた頃「主人公は、章が変わると違う場所に行き、今までと違う立ち位置で、違う事をする」というのを念頭に置いて書こうと考えていました。
そうすることで、物語にメリハリが出ると思ったからです。
ゆえに当初、三章から六章はひとつの章でまとめてしまおう、一巻分の長さでやってしまおう……と考えていたのですが、私の力量不足もあって、これほどの長さになってしまいました。
ともあれ六巻でエリスの家庭教師であり保護者という立場は終わり、七巻からはまた別の立ち位置の人間として動き始めます。
六巻までにあった様々な困難を乗り越え、時には挫折しかけて知り合いに助けてもらったルーデウス。
成長したような、成長していないような、三歩進んで二歩下がるような、ゆっくりとした成長をしていく彼が、次にどんな立ち位置の人間になり、どんな活躍をするのか。
楽しみにお待ちください。
文库版 无职转生~到了异世界就拿出真本事~