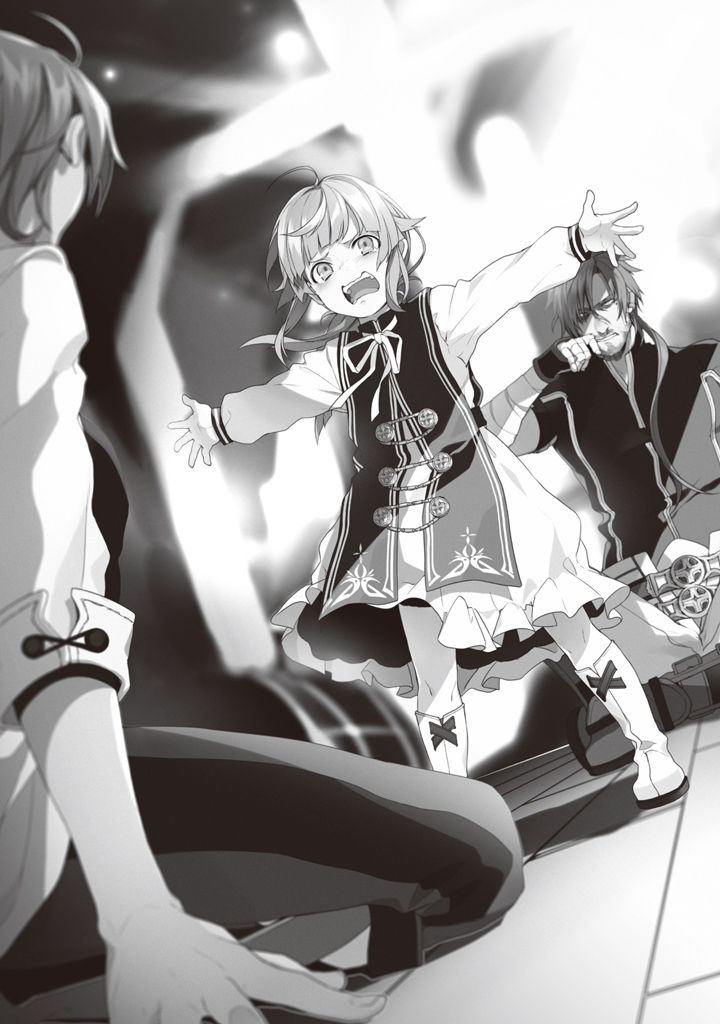制作信息
简介
简介
新たな大地で待っていたのは……まさかの親子喧嘩!?
獣族の誘拐事件を解決したルーデウスは、暴力お嬢様のエリス、歴戦の勇者ルイジェルド、そして新たな仲間のギースと共にミリス神聖国の首都ミリシオンに到達する。城下町で束の間の休息を取ろうとした矢先、ルーデウスはまたもや誘拐事件に遭遇する!!
『デッドエンド』の掟に基づき攫われた少年を救い出すため、誘拐犯のアジトに潜入するが、不測の事態によって戦闘を余儀なくされる。
敵の団長と戦う最中、その人物の口から漏れた言葉は「ルディ」という自らの懐かしい愛称だった……!?
憧れの人生やり直し型転生ファンタジー、息もつかせぬ第五弾!
目录
CONTENTS
第五章 少年期 再会編
「敗北を知る者は、強い」
── The way of daring to become inoccupation
著:ルーデウス・グレイラット
译:ジーン・RF・マゴット
第一話 「ミリス神聖国」
俺の名前はルーデウス・グレイラット。
前世は大人、体は十一歳のスーパーハンサムボーイだ。
得意なのは魔術。
詠唱なしで独自にアレンジした魔術を使えるってことで、他の連中からも一目置かれている。
一年半ほど前、俺は災害に巻き込まれ魔大陸という所に転移してしまった。
魔大陸は故郷であるアスラ王国フィットア領から見て、世界のちょうど反対側に位置しており、世界を半周しなければ戻ることはできない。
俺は冒険者となり、帰郷のための長い旅路を歩き始めた。
そうして一年半。俺は魔大陸を縦断し、大森林をも突破したのだ。
★ ★ ★
ミリス神聖国・首都ミリシオン。
その町の全貌は聖剣街道から見ることができる。
青竜山脈より流れ出るニコラウス川は、青く輝くグラン湖へと流れこむ。
グラン湖の中央に浮かぶは偉大なる純白のホワイトパレス。
さらに流れるニコラウス川の川沿いには、金色に輝く大聖堂と、銀に光る冒険者ギルド本部が存在している。
周囲には碁盤上に並んだ規則正しい町並み。
そして町を囲むように配置された勇ましき七つの塔と、外に大きく広がる草原地帯……。
尊厳と調和。二つを併せ持つ、この世界で最も美しい都市である。
冒険家・ブラッディーカント著 『世界を歩く』より抜粋。
ファンタジー世界ならではの緑と青の調和。
それに加えて、江戸や札幌のような規則正しい町並み。
リカリスの町を見た時にはおぼえなかった感動がそこにある。
確かに美しい。
「わぁ……」
呆けた顔で口を開けっ放しにしている少女の名はエリス。
エリス・ボレアス・グレイラット。アスラ王国フィットア領の領主サウロスの孫娘で、俺が家庭教師を務めていた相手である。とんでもなく獰猛なお嬢様で、俺の言うことこそ聞いてくれるものの、気に入らないと大統領でもぶん殴っちまうような暴れん坊だ。ただし、船酔いするので、船だけは勘弁な様子。
「ほう」
眼を細めている色白スキンヘッドの男はルイジェルド。
ルイジェルド・スペルディア。
今はスキンヘッドであるためわからないが、彼はエメラルドグリーンの髪をしたスペルド族という種族で、この世界では緑色の髪をした魔族は、恐怖の象徴として認識されている。
ちょっと物騒なところはあるが、俺たちにとってはたんなる子供好きのおじちゃんだ。
この二人は花より団子の方だと思っていたが、美しいものにはきちんと感動というものを覚えるらしい。
「すげえだろ?」
と、自慢げに言った猿顔の男の名はギース。
冒険者だが、賭け事でヘマをして牢屋に叩き込まれるような抜けた男だ。パーティに入ったというわけではないが、ミリス神聖国まで一緒に行きたいというので、大森林からこっち、俺たちに付いてきている。
なんでお前が自慢げなんだと思うところだが、こんな光景を知っているのであれば、わからないでもない。俺だって、自慢する。
「凄いけど、あんな大きな湖じゃあ、雨期は大変なんじゃないのか?」
とはいえ、こいつを調子に乗らせるのは少しばかり癪だったため、つい憎まれ口を叩いてしまう。
けれど、これは純粋な疑問でもある。
なにせ町のほぼ中央に巨大な湖がある上、すぐ北にある大森林で三ヶ月も雨が続くのだ。
こちらにだって影響はあるだろう。
「そりゃ昔は大変だったらしいが、今はあの七つの魔術塔が天候を完璧にコントロールしてる。だから安心して湖の真ん中に城が建ってわけだ。城壁もねえだろ? そりゃあ、あの塔が常に結界を張ってるからよ」
「なるほど、つまりミリス神聖国を攻め落としたければ、まずあの塔をなんとかするところからってことか」
「物騒なこと言うなよ、冗談でも聖騎士連中に聞かれたら捕まるぜ?」
「……気をつけましょう」
ギースの話によると、あの七つの塔がある限り、首都は決して災害に襲われないし、疫病が流行ることもないらしい。どういう原理かはわからないが、便利なものだ。
「はやく行きましょうよ!」
エリスのワクワクした一声で、俺たちは馬車を進ませた。
ミリシオンの町は、四つの地区に分けられる。
北側にある『居住区』。
民家が立ち並ぶ区画。貴族や騎士団の家族が住んでいる地区と、一般市民の住む地区とで多少の違いはあるが、基本的には民家のみだ。
東側にある『商業区』。
あらゆる業種が集まる区画。小売店はあるものの、規模は小さい。大手の商会が幅をきかせている区画で、この世界のビジネス街だ。鍛冶場や競売場があるのもここである。
南側にある『冒険者区』。
冒険者たちが集まる場所だ。冒険者ギルドの本部を中心に、冒険者向けの店や宿屋などが揃っている。冒険者崩れの住むスラム街や、賭博場もあるので注意が必要である。一応、奴隷市場も商業区ではなくこちらにあるのだとか。
西側にある『神聖区』。
聖ミリス教会の関係者が多く住む場所だ。巨大な大聖堂と、墓地がある。また、ミリス聖騎士団の本部もここにある。
ということを、ギースは一つ一つ、丁寧に教えてくれた。
俺たちはぐるりと回りこみ、冒険者区から町中へと入った。
ギース曰く、町の外の人間が冒険者区以外から出入りすると、いらぬ疑いを掛けられて時間が掛かるらしい。面倒な町だね。
町に入った瞬間、雑多な空気が身を包む。
遠目には綺麗に見えたミリシオンだが、中に入ってしまえば他の町と大差はない。
町の入り口には宿屋と馬屋。
そこから進むと露天商たちが立ち並び、煩く客の呼び込みをしている。
大通りの少し奥まった所には、武具の商店も見えた。
細い路地の奥には、普通よりちょっと値の張る宿屋なんかがあるのだろう。
ちなみに、銀色に輝く冒険者ギルドの本部とやらは、入り口からでも見ることができた。
俺たちはとりあえず、馬車を馬屋に預けた。
聞いてみると、荷物を宿に届けてくれるサービスまであるらしい。
他の町にはなかったサービスだ。
やはり大きな町だと、そういうサービスを充実させなければ、生き残ることができないのかもしれない。
「さてと、俺はアテがあるから、ここらで失礼するぜ!」
馬屋に荷馬車を預けるのを見届けると、ギースは唐突にそう言った。
「え? もう別れるのか?」
俺は意外に思った。宿までは一緒にいると思っていたのだ。
「なんだ先輩、寂しいのか?」
「そりゃ寂しいさ」
からかうような言葉に、俺は正直に答える。
ギースとは短い付き合いだったが、悪いやつじゃなかった。波長が合う相手というのは旅において貴重なものだ。ギースのお陰で俺のストレスがどれだけ軽減されたか……。
それに、彼がいなくなると、また食事が味気ないものになる。やるせない。
「寂しがんなよ先輩。同じ町にいりゃあ、また会えるって」
ギースは肩をすくめて、俺の頭をぽんぽんと撫でた。
そして、そのまま手をヒラヒラさせながら歩み去ろうとすると、エリスが立ちふさがった。
「ギース!」
腕を組んで顎を反らして、いつもの仁王立ち。
「今度会った時は料理を教えなさいよ!」
「だから嫌だっつの。しつけえなあ」
ギースは後ろ頭をポリポリと掻きつつ、その脇を抜ける。
ついでとばかりに、ルイジェルドの肩をぽんと叩いた。
「じゃ、旦那も達者でな」
「お前もな。あまり悪さはするなよ」
「わかってるって」
ギースは今度こそひらひらと手を振りながら、雑踏へと消えていく。
二ヶ月も一緒にいたとは思えない。本当にあっさりとした別れだった。
「あ、そうだ先輩」
と、サル顔は雑踏に消えていく前に振り返った。
「冒険者ギルドには忘れず顔出せよ!」
「……ん? おう!」
金は稼がないといけないだろうし、冒険者ギルドには行く。
しかし、なぜ今それを言うのだろうか。
わからないが、ギースは俺が返事をするのを聞くと、雑踏へと消えていった。
★ ★ ★
まずは宿を探す。
宿を取るというのは、俺たちが町に来た時の基本行動だ。
ミリシオンでは宿は大通りから離れた所に多いため、路地を抜けて少し歩くと宿屋街のような場所に出た。ひと通り見て回った後、一つの宿に決定。
『夜明けの光亭』
この宿は、大通りからは少々外れた場所にあるが、スラム街よりは遠く、治安も悪くない。
各種サービスも充実しており、C~Bランク冒険者の向けの宿と言える。
日当たりが少し悪いのが、欠点といえば欠点か。
宿を取り、部屋で旅の整理をして、時間があれば冒険者ギルドを含めた町の要所を見て回り、さらに時間が余れば適当に自由時間を満喫した後、宿に戻って作戦会議。
それが一連の流れである。
「もっと安い所に泊まればいいじゃない……」
エリスは呆れ顔でそう言った。
彼女のいうことももっともだ。
金は節約すべきというのは、俺が常々言っている言葉だ。
だが、今は少しだけ余裕がある。三ヶ月間、ドルディアの村を警備して得たお金に、獣族の戦士長ギュエスからもらった金。二つ合わせてミリス金貨七枚とちょっと。稼がなければならないのは確かだが、今すぐ金欠に陥るというほどでもない。
だから、これぐらいの贅沢はいいだろう。
俺だって、たまには柔らかいベッドで眠りたいのだ。
「まあ、たまにはいいじゃないですか」
呆れるエリスを尻目に部屋へと入る。
なかなかに小綺麗ないい部屋だ。部屋の隅にテーブルと椅子が用意されているのがいいね。
部屋には鍵も掛けられるし、窓には鎧戸が付いている。
生前の世界におけるビジネスホテルにすら遠く及ばないが、この世界の宿屋としては十分すぎるほどである。
さて、宿に入った後の行動は決まっている。
装備の手入れと、補充すべき消耗品をメモ。ベッドを乾燥に掛け、シーツも洗濯、ついでに掃除。
この動作はルーチンワークと化しており、指示を出さずとも全員が無言で動いた。
全てが終わる頃、日が落ちて周囲が暗くなっていた。
到着したのが昼下がりだったからか。
ギルドに行く時間がなくなってしまったが、一日や二日ギルドに行くのが遅れたところで、大したことはあるまい。
宿の隣の酒場で食事を終え、部屋へと戻ってくる。
三人で車座に座り、顔を突き合わせる。
「それでは、チーム『デッドエンド』の作戦会議を始めます。ミリス首都に着いて初めての会議です、盛り上がっていきましょう」
俺が「拍手」と口にして手を叩くと、エリスとルイジェルドがおざなりな拍手を返してくれた。
ノリが悪いが、まあいいか。
「さて、ようやくここまでやってまいりました」
俺はまず、そんな言葉をしみじみと口にした。
長い道のりだった。魔大陸で一年とちょっと、大森林で四ヶ月。
一年半も掛けて、ようやく。ようやく、人族の住む領域にたどり着いたのだ。
危険な場所は抜けた。ここからは街道も整備されているし、道も平坦だ。今までに比べれば、安全と言っても過言ではないだろう。
もっとも、距離としてはまだまだ長い。
ミリスからアスラまでは、世界を四分の一周するような距離だ。いくら移動しやすい道のりといっても、距離が縮まるわけではない。やはり一年ぐらい掛かるだろう。
となると、一番の問題は金である。
「とりあえず、しばらくこの町で金を稼ぎたいと思います」
「なんで?」
エリスの疑問に、丁寧に答える。
「魔大陸、大森林と渡ってきましたが、人族の領域は物価が高いです」
と、俺は今までに調べた相場を思い出す。
ザントポートの相場を調べることはできなかったが、魔大陸の全体的な相場と、宿場町での物価は覚えている。それに比べると、ミリス神聖国やアスラ王国の物価は高い。
この宿の金額も、魔大陸の宿の相場から見れば眼が飛び出るほどである。
人族は意地汚いので、貨幣というものを他種族よりも重要視しているのだ。
「ミリスの貨幣価値は高いです。アスラ王国の次に高く、世界では二番目。物価は高いですが、依頼料も高いそうです。魔大陸のように町に行く都度、一週間滞在して金を稼ぐより、この町で一ヶ月ほど金稼ぎに集中したほうが、効率がいいでしょう」
ミリスの貨幣価値が高いということは、ミリスで今後のために十分な金を稼いでおけば、中央大陸南部を通る時も、金に困ることはなくなるはずだ。
「スペルド族が船に乗るのにいくら掛かるのかもわかりませんしね」
船というと、エリスは露骨に嫌そうな顔をした。
船酔いのことを思い出したのだろう。
彼女にとっては嫌な思い出だが、俺にとってはいい思い出だ。あの時のエリスを思い出して、何度もお世話になっています。
「ここで金を貯めて、一気にアスラまで移動します。もしかするとスペルド族の宣伝はできないかもしれませんが、ルイジェルドさん、それでもいいですか?」
「ああ」
ルイジェルドはこくりと頷いた。
まあ、スペルド族の宣伝は俺が好きでやってることである。
俺としては、もっと腰を落ち着けてスペルド族の汚名返上に尽力したいところだ。
半年か、一年か。大きな町なら、それだけ影響力も強いはずだ。
だが、ここに来るまでに一年半の歳月を費やしてしまった。
一年半という期間は、短くはないし、これ以上時間は掛けたくない。
考えて見れば、俺は一年半も消息不明なのだ。パウロたちだって心配しているはずだ。
彼らはどうしているだろうか……。
あ、そういやまだ手紙を出していなかったな。出そう出そうとは思っていたのだが、色々あって忘れてしまっていた。
手紙か……よし。
「明日は休日にしましょう」
休日、という概念は、今までもたまに使ってきた。
最初はエリスを気遣って作ったものだったが、途中からは自分自身を休めるためだった。
エリスは疲れを見せないし、ルイジェルドもタフガイ。情けない軟弱者は俺なのだ。
もちろん、俺だって生前に比べれば体力はついている。二人には敵わないが、この世界における一般的な冒険者ぐらいの体力はあるから、肉体的に疲れるわけではない。
精神的なものだ。
俺は未だに生物を殺すことに忌避感があるのか、魔物を殺すたびに変なストレスが溜まってしまうのだ。
もっとも、今回は疲れているわけではない。情報収集、ギルドでの依頼確認、その他もろもろとやっていれば、きっと手紙のことなんて忘れてしまう。
今までだってそうだったのだ。
だから、今回は忘れないように、明日一日、手紙を書くことに費やす。
「ルーデウス、また身体の調子が悪いの?」
「いえ、今回は別件です。手紙を書こうと思いまして」
「手紙?」
エリスの問いに、俺はこくりと頷く。
「はい、無事を知らせる手紙です」
「ふぅん……まあ、ルーデウスにまかせておけば大丈夫よね」
「ええ」
明日は、手紙を書く。ブエナ村のことを思い出しつつ、パウロやシルフィに手紙を書こう。
家庭教師をしていた頃、手紙は出すなと言われていたが、なに、こんな状況だ、パウロも嫌とは言うまい。
出した手紙がたどり着く可能性はそれほど高くない。
アスラ─シーローン間でロキシーと文通していた時も、七通に一通は届かなかった。
なので、同じ内容の手紙を何通か別便で出したものだ。
今回もそうすることにしよう。
「二人はどうしますか?」
「私は、ゴブリン討伐をしてくるわ!」
俺の問いに対し、エリスからそんな返答が返ってきた。
「ゴブリン?」
ゴブリンというと、あのゴブリンだろうか。
人の半分ぐらいのサイズで、棍棒等を装備し、黄緑色の肌をしており、繁殖力旺盛で、ファンタジー系のエロゲーには高確率で登場し、アダルトビデオの汁男優のごとき役割を果たすという。
「このあたりにはゴブリンが出るって、さっき町中で聞いたのよ。冒険者ならゴブリンぐらい見ておかないと!」
エリスは元気よく言った。
わからないフリをしてみたが、実はゴブリンについては旅の途中で聞き及んでいる。
ゴブリンとは、この世界におけるネズミのような存在だ。
繁殖力が強く人に悪さをする。一応は言葉が通じるので魔獣の類に属されるが、言葉が通じるだけで本能のまま生きる個体が多数を占めるので、増えてきたら駆除される(らしい)。
「わかりました。ルイジェルド、護衛を……」
「ゴブリンぐらい一人で大丈夫よ!」
俺の言葉を遮って、エリスが大声を上げた。
心外だと言わんばかりの顔である。
「……」
どうしたもんか。
エリスは強い。ゴブリンはランク的にはEランクで戦う魔物だったはずだ。
魔大陸にはいないので実際に見たことはないが、多少剣術をかじっただけの子供でも倒せる相手だと聞いている。
対し、エリスはBランクの魔物とも対等に戦える。
そのエリスにルイジェルドという護衛をつけるのは、さすがに過保護すぎるだろうか……。
いやでも、女冒険者がゴブリンに敗北すれば肉奴隷一直線だ。
この世界のゴブリンについてはよく知らないが、俺の世界のゴブリンはだいたいそんな感じだった。もし俺がゴブリンで、運よくエリスを気絶させることができたら。それはもう充実したゴブリン毎日を送ってしまうだろう。
誰だってそうする。俺だってそうする。
十中八九大丈夫だと思う。
けれど。けれども、だ。
俺が目を離した隙にエリスがそんなことになったら、ギレーヌやフィリップに合わせる顔がない。
「ルーデウス。大丈夫だ。やらせてみろ」
考え込んでいると、ルイジェルドが助け舟を出した。
珍しい。
この一年半、ルイジェルドはエリスにあらゆる相手への戦い方をレクチャーしていた。
教え方は俺には理解しにくいものであったが、エリスはきちんと学んでいた。
なら……大丈夫か。
「わかりました。エリス、相手が弱いからって決して油断しないように」
「もちろんよ!」
「準備はしっかりしていってください」
「わかってるわ!」
「危なくなったら、脱兎の如く逃げるんですよ」
「わかってるってば!」
「万が一の時には相手の手を掴み、大声で『この人痴漢です』と……」
「しつこいわね! 私にだってゴブリン討伐ぐらいできるわよ!」
怒られてしまった。
まだ不安は残るが、ここは歴戦の戦士の言葉を信じることにしよう。
「でしたら、僕から言うことはありません。頑張ってください」
「ええ、頑張るわ!」
エリスは満足そうに頷いた。
「で、ルイジェルドさんはどうします?」
「俺は知り合いと会ってくる」
ルイジェルドから知り合いなどという単語を聞くのは初めてだ。
「ほう、知り合いですか。ルイジェルドさんにも知り合いなんていたんですね」
「当たり前だ」
ずっとボッチかと思っていたが……。
そりゃ五百年も生きていれば、知り合いの相手の一人や二人存在するか。
なぜミリシオンにと思わなくもないが、逆にこれだけ広い町だからこそ、ルイジェルドの知り合いが住んでいるのかもしれない。
「どういう方なんですか?」
「戦士だ」
戦士ってことは、その昔、魔大陸で助けた系の人かな。
ま、余計な詮索はすまい。
親じゃあるまいし、休日に誰と会うのかを詳しく聞くなんてなぁ、野暮ってもんだ。
★ ★ ★
翌日、エリスとルイジェルドはそれぞれ出かけていった。
俺もまた紙、ペン、インクを買いに町に繰り出すことにする。
露店を見まわるついでに、ミリス神聖国の物価についても調べておく。
食料品については、魔大陸よりもかなり安い。品揃えも魔大陸のそれとは比べ物にならない。肉や魚はさばきたての新鮮なモノが並んでいるし、嬉しいことに生野菜も売られている。
何より驚いたのは卵だ。
鶏卵が極めて安い価格で売っているのだ。新鮮な卵、今日採れたての卵が、である。
魔大陸でも時折、卵を売っている店はあったが、鶏ではなく、魔獣の卵だった。インプリンティングを利用して調教するのだそうだ。
もちろん食料品ではなく、気安く目玉焼きにできるような値段でもない。
ちなみに、この世界にも養鶏はある。
ブエナ村にも鶏を飼っている人がいたし、ミリスでも養鶏が盛んに行われているらしい。
久しぶりにご飯に溶いた生卵をぶっ掛けて食ってみたいという衝動にかられる。
TKGは完全食である。
しかし、卵はあってもご飯と醤油がない。
アスラ王国同様、ミリス神聖国の主食もパンのようだし、市場にも売っていない。
もっとも、この世界には米があることは確認済みだ。米を主食としているのは、中央大陸の北部から東部にかけてである。
シーローン王国でも米が出てくると、ロキシーの手紙に書いてあった。
肉、野菜、魚介類などを混ぜてチャーハンだかパエリアのようにして食べるのが主流だそうだ。
しかし、逆にあの辺りでは、養鶏が行われていないらしい。
気候が合わないのか鶏がいないのか、とにかく、鶏卵が滅多に手に入らないそうだ。
また、醤油というものも見たことがない。
植物辞典によると、大豆によく似た植物はあるようなのだが、それを発酵させてソースにする、という試みは行われていないようだ。
いや、きっと探せばあるはずだ。卵と米は存在しているのだからな。
いずれ手に入れ、そして食べよう、TKG
たまごかけごはん
を。
卵の衛生状態なんか気にしない。お腹を壊したら解毒で治せばいいんだからな!
市場調査を終え、レターセットも購入。宿へと戻りながら手紙の文面はどうしようかと考える。
思えば、パウロやシルフィに手紙を送るのはこれが初めてだ。
ボレアス家でのことから書くべきだろうか……いや、それより生存報告が大事か。
魔大陸に転移されてからのことでいいだろう。
思えば、色々あったな。
スペルド族と旅をして、魔界大帝に会って、獣族の集落で三ヶ月過ごして……。
信じてくれるだろうか。
信じようが信じまいが、事実として書きはするが、少なくとも魔界大帝に出会って魔眼をもらった話は信じてくれまい。
獣族の集落といえば、ギレーヌは無事なのだろうか。彼女も転移したはずだ。
あの強さだし、よほど変な場所に転移しない限りは大丈夫だと思うが……。
転移したといえば、転移の光は城塞都市ロアから広がった。てことは、ボレアス家の面々も転移しているかもしれない。
フィリップ、サウロス、ヒルダ。執事のアルフォンスや、メイドの人々。
サウロス爺さんはどこにいっても元気よく大声出してそうだが……。
「心配だなぁ」
などと呟きつつ、細い路地へと入る。
ミリシオンには、こうした細い路地が多い。
遠目から見ると綺麗な碁盤目だが、長いこと建物を建てたり崩したりをしたせいで建物の大きさや位置が少しずつズレ、こうした細くてジメジメした路地ができるのだ。
もっとも、碁盤目に並んでいるからか、迷う心配はない。
なので、ちょっと近道をしつつ、違う道を通るのだ。
もしかすると、恋人の小径とか見つかるかもしれない。
うちの赤毛はちょっと乱暴者だが、あれでいて綺麗なものをきちんと愛でる感性はあったりするようだし、一ヶ月も滞在するとなれば、デートをする機会もあるだろう。
その時にステキな場所に案内して好感度アップって作戦よ。
などと考えていると、細い路地の向こうから、五人ほどの男が急ぎ足で向かってくるのが見えた。
冒険者風ではない。どちらかというと町のチンピラか。
やや威嚇気味な服装だ。一言で言えば、若い。
しかし、こんな狭い路地にそんな大人数で入ってくるのは感心できない。
道というのは譲り合いだ。いくら俺が子供で、ナリが小さいとはいえ、そんな道一杯に広がって歩いたら、お互いにぶつかってしまうだろう。ここは一列縦隊で目線を斜め下方に向け、お互いに譲り合い……。
「どけ!」
俺は素直に壁に張り付いた。
いや、勘違いしないでほしい。俺は余計な争いを避けただけだ。
彼らは急いでいるようだったし、俺は急いでいないわけだし。
別に、DQNっぽかったから避けたわけではない。
ホントだよ。嘘じゃない、びびってなんかねーし。
それに、人を見かけで判断できない。チンピラ風だけど、実は名のある剣豪でした、なんてこともある。自分の強さを過信して相手の暴力を注意したら、実は相手は狂乱の貴公子でした、デッドエンド……なんてこともありうるのだ。
なにせ、道端で餓死寸前の幼女が魔界大帝だってことがありうる世界だからな。
うん。余計な争いは避けるに限る。
と、思ったのだが、通り過ぎた瞬間、真ん中の二人が麻袋を持っているのが見えた。
二人がかりで脇に抱えた袋からは、小さな手がはみ出ていた。
恐らく、あの中には、子供が一人、入っているのだろう。
(……また人攫いか)
この世界は、本当に人攫いが多い。
犯罪者はスキを見ては子供を攫おうとしている。
アスラ王国でも、魔大陸でも、大森林でも、ミリス神聖国でも、どこにでも人攫いがいる。
ギース曰く、人攫いは儲かるのだそうだ。
現在、世界は多少の紛争はあるものの概ね平和で、奴隷といえば中央大陸の中部や北部から多少流れてくる程度だが、奴隷を欲する人は多い。
特にミリス神聖国やアスラ王国といった裕福な国で顕著だ。これらの国には、奴隷を所有したい裕福な層がいるのだ。
つまるところ、需要に対して供給が足りないのだ。
攫えば高値で売れる。ゆえに人攫いはいなくならない。人攫いを撲滅するには、大規模な戦争が起こるしかないらしい。
さて、しかし子供か。
五人で運んでいるってことは、計画的な犯行なのだろうか。麻袋に入っているのは、高名な人物のご子息あるいはご息女とか……。
正直、あまり関わりあいになりたくないところだ。
子供を助けたら、一味と勘違いされて牢屋に入るって出来事がつい何ヶ月か前にあったばかりだ。
じゃあ、見捨てるか?
いや、まさか。この世界から人攫いはなくならないのと、俺がそれで苦い経験をしたのと、子供を助けないのは、全部別の話である。
『デッドエンド』の掟その一。子供は見捨てるな。
『デッドエンド』の掟その二。子供は絶対に見捨てるな。
『デッドエンド』は正義の味方。悪者はすべからく撃破。子供はおしなべて救出。
そうやって少しずつスペルド族の名を広めるのだ。
俺は五人の後を追った。
★ ★ ★
俺の隠密スキルはレベルアップしていた。ドルディアの村でエリスたちに近づくために鍛えたからだろうか。
五人は俺の尾行に気づくことなく、一軒の倉庫へと入っていった。
迂闊な奴らだ。俺を見つけたければ、鼻を鍛えるんだな。発情の臭いを嗅ぎとれれば一発だし。
倉庫の場所は冒険者区の一画。俺の泊まっている宿よりも、さらに奥まった場所にある。
通りには面していなくて、細い路地からしか入れない。
馬車はもちろん入れないし、道が狭いので大きな荷物も入らない。なんでこんな所に倉庫なんて作ったんだと、責任者を呼びたくなるデッドスペースに建っていた。
恐らく、倉庫が先で、周囲の建物が後なのだろう。区画整理の弊害ってやつだ。
なんてどうでもいいことを考えつつ、俺は男たちが入っていったのを確認し、裏に回った。
土の魔術を使って自らの身体をエレベートし、明かり取り用の窓から中へと入った。
雑然とつまれた木箱の一つに身を隠し、様子を窺う。
五人はあれこれと話し合っている。
どうやら、隣の酒場に大勢の仲間がいるらしく、仕事が終わったから誰かを呼んでこいと言っているのが聞こえる。
仲間を呼ばれる前に片付けるか、それとも、仲間の顔を確認した上で、子供だけを助けるか。
俺はもちろん、後者を選ぶ。
なので、しばらくはこの木箱の中に待機だ。
しかし、暗かったのでよく確かめなかったが、この木箱には一体何が入っているのだろうか。
布であるというのはわかるが、服というには少々小さい。しかし、包まれていると不思議と安らかな気分になる。
一つを手にとってみる。この感触、形、覚えがある。
立体的に縫製された布には、三つの穴が開いている。一部分だけ布が二重になっており、その部分からは、そこはかとないステキなサムシングを感じる。
「って、パンツじゃねえか!」
「誰だ!」
し、しまった! 見つかった!
くそう。こんな罠を用意しているとは。卑劣な。
「木箱の中か?」
「出てこい!」
「おい、団長たちを呼んでこい!」
まずい。もたもたしているうちに仲間を呼ばれてしまった。
計画変更だ。子供だけサッと助けてサッと逃げよう。そうしよう。しかし顔を見られてしまう。
いや、問題ない。仮面は手元にある。
フオォォゥ! 気分はエクスタシー! なんちゃって。
正体を隠すためにローブもクロスアウトしようかと思ったが、よくよく考えると、買い物のために出てきたので、ローブも着用していないし、杖も持っていなかった。
よし、これでいこう!
「うおっ!」
「ぱ、パンツをかぶってやがる……」
「変態だ……」
男たちの度肝を抜きつつ、登場。そして口上。
「幼き者を守護者から引き離し、己の醜い欲望の糧とする者よ。その行いを恥と知れ! 人、それを……『誘拐』という!」
と、某正義のお兄さんを真似しながら登場。
「だ、誰だお前は!」
「『デッドエンドのルイジェルド』だ!」
「なにぃデッドエンドだ?」
あー、いかん、しまった!
ついいつもの癖で名乗ってしまった。ここは名乗ってはいけない場面だった。
ごめんなさいルイジェルドさん。あなたは今日からパンツをかぶって人助けをする変態です!
でも、ちゃんと子供は助けますから!
「人攫いめ! お前たちのせいで、今一人の男が濡れ衣を着せられたぞ! 絶対に許しはしない!」
「おいガキ、正義の味方ごっこなら他所でやれよ。俺たちはな」
「問答無用! さんらーいず・あたーっく!」
「ぐげぇ!」
とりあえず、岩砲弾を撃ち込んだ。
やはり先手必勝はいい。思えば、魔界大帝を変態ロリコンオヤジの魔の手から救った時も、こうやって先手を打ったものだ。
「そーらそら!」
「げぇ!」
「うごぉ!」
またたく間に四人気絶させ、俺は少年の元へと駆け寄った。
「大丈夫か少年! と思ったら、気絶してる……」
どこかで見たことのあるような少年だ。
ホント、見覚えがある……あれ? どこで見たっけな。思い出せない。
まあいい。こんなことをしてる暇はない。早くしないと敵の増援がきてしまう……と、思ったら、すでに倉庫の入り口にゾロゾロと男たちが現れた。
「うおっ! みんなやられてるじゃねえか!」
「ガキだが手練れだぞ、はやく団長たちを呼んでこい!」
「団長、今日はそうとう飲んでるぞ!」
「飲んでても強いから!」
二人が抜け、外へと走っていく。
すでに十人以上いるのだが、まだ増援が来るらしい。
ヤバイな。非常にヤバイ。やっぱ見捨てたほうが良かったかもしれない。
あるいは、明日にでもルイジェルドに相談するとか……どっちにしても失敗した。
もう、全員倒して突破するしかない。
「なんて奴だ、パンツなんてかぶりやがって」
「もしかして、パンツを盗みに来たんじゃないの!」
「女の敵ってこと!?」
よく見ると、数名ほど女性が混じっていた。
ごめんルイジェルド。本当にごめん。
心の中で平謝りしつつ、戦闘を開始した。
幸いにして、彼らは強くはなかった。のこのこと走って近づいてこようとするのを、岩砲弾で迎撃。彼らはそれを回避できず、だいたい一発で気絶した。
武器も持っていなかったし、魔術師もいないようだ。楽勝だな。
「ち、近づけねえ」
「なんだよあれ、魔力付与品でも使ってるのか!?」
「団長はまだか!」
半分ほど気絶させたところで、残りが浮き足立った。
これならいける、そう思った時──。
「団長はすぐに来ます! それまで持ちこたえましょう!」
倉庫の入り口から、二人の女が入ってきた。
ビキニアーマーの女戦士と、ローブ姿の魔術師だ。
増援か……お早い到着だが、隣の酒場にいたらしいし、当然か。
ビキニアーマーのせいで、彼女だけ肌の露出が極めて高い。魔大陸でもこんな露出狂みたいな女はいなかった。他の女はしっかりとローブを着込んでいたりするから、彼女だけが異様に目立っている。
くそっ、一体何者なんだ、目が離せねぇっ!
「凌ぎます! シェラ、援護して!」
「はい!」
ビキニアーマーは腰から剣を抜き放ち、こちらへと走ってきた。
彼女の背後で、ローブ姿の魔術師が杖を構え……あ、やばい、ビキニちゃんの胸が、ステップに合わせてぽよんぽよんって。
あんなに激しく揺れ動いたら、こぼれてしまう。
おかしい、ビキニアーマーは戦闘の邪魔にならないように胸を固定する役目もあったはず。あれでは意味を為さないのではないだろうか。
右に、左に、ああ、すごい!
左右に揺れながら、だんだんと近づいて、一旦下に沈んでから、上に……。
「ちぇりああぁぁ!」
気づけば女戦士は俺の目の前で剣を振りかぶっていた。
「おわぁっ!」
間一髪、俺は女戦士の斬撃を転がって回避した。
あ、危なっ!
くそっ、なんて奴だ。
さてはあの格好は相手を惑わすためか?
と、そこで俺の耳にかすかに声が届いた。
「──清涼なるせせらぎの流れを今ここに『水弾』」
魔術の詠唱!
水弾が飛んでくる!
「っ!」
俺は、咄嗟に先ほどの魔術師に向けて、手を向けた。
使う魔術は岩壁。
水を使った魔術は砂や土で受け止めて吸収する! レジストだ。
魔術を完成させつつそちらを見ると、魔術師の杖は俺に向けられており、ちょうどその先端から、高速で水の塊が撃ち出されたところだった。
水弾は、射出とほぼ同時に、俺の作り出した岩の壁にぶつかり、水音とは思えないほどの巨大な破裂音を立てて霧散。周囲に飛沫を飛び散らせた。
「なっ! 何が!?」
動揺する魔術師の声を聞きつつ、先ほどのビキニアーマーへと振り返る。
「!」
巨乳は遠心力によって振り回され、今にもビキニから零れ落ちそうになっていた。
見えそ……!
「ちぇええあ!!」
裂帛の声で、俺は我に返り、また転がって回避した。
そのまま、距離を取りつつ立ち上がる。
ビキニアーマーが剣を地面に叩きつけた姿勢のまま、こちらを睨みつけていた。
「ゴキブリみたいに逃げて……! 変態め!」
そう言いながら、剣を中段へと構えなおした。
勢いにまかせて攻めるのをやめたのか、じりじりとすり足で距離を詰めてきている。
俺はそれに合わせて、ゆっくりと後ろに……あっ、前で構えたことで胸が挟まれ、谷間ができてる。
ああっ、くそ、いかん、これは罠だ!
視線を誘導されている!
これじゃまともに戦えない。
あの女戦士と魔術師の腕は大したことないが、このままではまずい。
もし、果実がまろび出てしまったら、俺は確実にあの剣の餌食となるだろう。
くそっ、一体どこから俺の弱点が漏れたんだ……!
いや、違う。
俺が勝手に胸に気を取られているだけだ。別にあいつの戦術じゃないはずだ。
しかし、どうする。
なんとかしてあの胸をしまってもらわなければ、戦いにならない。
ついでに、尻肉のあふれている下の方も隠してほしい。
どうすれば隠してもらえるのか。オッサンっぽいセリフでも言えば、恥ずかしがって隠してくれるだろうか。いや、わざとあの格好をしているのなら逆効果かもしれない。
「はっ!」
……そうだ思いついた! 北風と太陽だ。
かつて、北風と太陽は、旅人の服を脱がそうと勝負した。
北風は冷たい突風で旅人の服を脱がそうとしたが、旅人は逆にしっかりと服を着込んだ。
対する太陽は、気温を高くすることで、旅人の体温を上げ、服を自発的に脱がしたのだ。
つまり暖かくすれば、あのビキニを……。
いや違う、脱いでもらっちゃダメなんだ。
よし、冷気だ。
「追い詰めたぞ」
言われるまま後ろを振り向くと、倉庫の壁があった。
しかし、俺の戦術はすでに決まっている。
女戦士に対し、無言で両手を向けた。
「『氷結領域』」
右手に魔力を込めた瞬間、倉庫内に冷気がほとばしった。
温度が一気に三〇度は下がり、一瞬にして倉庫内が極寒の地と化す。
「な、なにっ!?」
女戦士の二の腕に、鳥肌が立つ。
加えて、左手に魔力を込める。
「『突風』」
俺の左手から突風が吹き荒れ、女戦士を吹き飛ばした。
女戦士は倉庫の地面をゴロゴロと転がしながら、入り口へと押し戻された。
これこそ、混合魔術『寒冷突風』だ。
「へぃくちっ!」
俺も風邪引きそうなほどに寒いが、しかし効果は抜群だ。
女戦士は一瞬で体温を奪われ、ガタガタと震えながら、別の団員に上着を要求している。
これなら、もう大丈夫だ。
あの厄介な胸さえ隠してしまえば、俺に敗北はない。
さっさと全員気絶させて、この場を突破させてもらおうか。
「おう、待たせたな!」
そこで、そいつは現れた。
堂々と倉庫の入り口に立っていた。
どこかで見たことのあるような男、懐かしい感じのする顔……。
でも、どこで見たかは、思い出せない。
「チッ、好き放題やってくれやがって。ヒック……てめえらは手を出すなよ。ガキ一人に大勢で掛かるこたぁねえ、俺一人でやる」
男は腕に自信があるようだが、酔っ払っているようだった。遠目にも足はフラフラで、顔も赤い。
しかし、本当にどこかで見たような顔だ。
茶髪で、DQNっぽくて、若干、パウロに似てるか……そういえば、声もパウロそっくりだ。
パウロを窶れさせて、顔から余裕をなくせばあんな感じになるか。本気で攻撃するのを躊躇いたくなる顔だ。
けど、こんな所にパウロがいるわけもない。
「てめえ、うちの団員相手に好き勝手やってくれやがって、覚悟はできてんだろうなぁ!」
先頭に立つ男が気炎を吐いて、二本の剣を抜いた。
二刀流か。恐らく達人系の剣士だろう。先ほどの女戦士より、数段上の気配を感じる。
岩砲弾でなんとかなるか?
いや、しかし、殺すのはちょっと……。
と、迷う俺に、男は突っ込んでくる。
「……っ!」
一手遅れた俺は、反射的に岩砲弾を放った。
男の反応は速かった。右手の剣を斜めに構えると、岩砲弾を受け流したのだ。
「水神流か!」
「それだけじゃねえぜ!」
男の踏み込み。俺は反射的に衝撃波を放ちつつ、後ろへと飛んだ。
「ヘッ!」
「おっと!」
予見眼を使い、先を見つつ回避する。
男の剣は速いが、やや足元がおぼつかない。
酔っているせいだろうか。それならなんとかなるか。
「チッ、アイツみてぇな動きしやがる……ヴェラ! シェラ! 手を貸せ!」
先ほどのビキニアーマーと、魔術師っぽい格好の女が前に出てくる。一人でやるんじゃなかったのか。おのれ男らしくない奴!
外套を羽織ったビキニアーマーが俺の横へと回りこみ、魔術師が詠唱を始める。
まずい。
男の攻撃は苛烈。俺は回避に精一杯だが……まだ手はある。
「ワッ!」
「うっ!」
声の魔術を使い、男の動きを一瞬だけ停止。同時に衝撃波で男をふっ飛ばす。
「岩砲弾!」
男が吹っ飛ぶのを視界の端にとらえつつ、岩砲弾を魔術師に飛ばす。
さらに、切り込んでくるビキニに対し、予見眼を使い、カウンターを打ち込む。
魔術師は詠唱に集中しているところに岩砲弾を撃ち込まれて気絶。
ビキニは殴られてたたらを踏んだが、まだ大丈夫らしく、眼を輝かせて俺を睨んでくる。
そして、男も迫る。
「シェラ! てめぇ、よくも!」
男が踏み込んでくるのを、泥沼を発生させて妨害。
男は無様に泥沼に足を取られ、転んだ。
「団長!」
よそ見しちゃいかんよと、口に出すこともなく、俺は無言で岩砲弾を射出。
「あっ……!」。
ビキニも気絶。
「ヴェラ! ちくしょう!」
男が片方の剣を鞘に戻し、もう片方を口に加えた。
予見眼。
[四つん這いで走ってくる]
犬かこいつは。
俺は岩砲弾で迎撃しつつ、背後へと距離を取る。
しかしここは狭い倉庫だ、接近を阻めるようなものはない。
「うおおらぁ!」
四つん這いから、身体にひねりを加えながらの跳躍。
獣じみた動きの中で、腰の剣を抜刀。
奇妙な体勢から、身体を大きくひねるように斬撃が繰り出される。鋭い!
[同時に、口に加えた剣を左手に持ち替え、逆手での一撃]
奇抜な攻撃。
俺の予想を上回る。予見眼がなければ、これを回避することはできなかっただろう。
斬撃は俺の鼻先をかすめた。鼻に、ジンとした痛み。
「……」
心臓がバクバクと鳴り始める。
俺は男を殺そうとは考えていなかったが、奴は俺を殺そうとしていた。
そんな当たり前の事実に、いま気づいた。
俺も本気を出さなければ、やられる。
そう思い、俺は腰を深く落とす。
ルイジェルドと、そしてエリスとの訓練を思い出す。
男の獣じみた動きは、どちらかというと、本気を出した時のルイジェルドの動きに近い。
だが、この男の身のこなしはルイジェルドほどではない。
奇抜なだけ、やれるはずだ。次に来たら、カウンターで……。と、思ったところで、男の動きが止まっていることに気づいた。
ふと見ると、俺の顔を覆っていたパンツが地面に落ちている。
まずい、顔を見られ……。
「お前、ルディか……?」
ルディ。俺をその名前で呼ぶ男は、一人しかいない。
そして、その呆気に取られた声は、怒声の混じった、酔っぱらいのダミ声ではなく、ひどく聞き慣れたものだった。
「……父様?」
★ ★ ★
久しぶりに会ったパウロ・グライラットは大きく様変わりしていた。
頬はげっそりと窶れ、目の下には隈があり、無精髭を生やして、髪はボサボサで、息は酒臭く、全体的にやさぐれていた。
俺の記憶にあるパウロとは、似ても似つかなかった。
第二話 「一年半のパウロ」
★ パウロ視点 ★
目が覚めた時、オレは草原にいた。
草原……草原としか言いようがない。何の変哲もない草原だが、不思議なことに見覚えがあった。
どこかと考えること数分。すぐに思い出した。
ここはアスラ王国の南部、かつて滞在していた町の近くだ。
当時は、町で水神流を習っていた……リーリャの故郷の近くだな。
自然と、これは夢だと考えた。オレがこんな場所にいるはずがないからな。
それにしても懐かしい場所だ。ここで暮らしたのは何年だったか。一年か、それとも二年か。
それほど長くいなかったことだけは覚えている。
記憶にあるのは道場でのことばかりで、思い出すのは兄弟子たちだ。
口ばかりで、いけ好かない連中だった。
才能あるオレの頭を抑えつけ、自分の上に行くなと厳命するような連中だった。
オレは上下関係というものが嫌いだ。
実家を飛び出したのも、父親に頭を抑えつけられたからだ。
それでも、まだ父親はマシだった。なんだかんだ言って、有無を言わさぬ力を持っていた。
だが、あの兄弟子らには力がなかった。口と自尊心だけが発達した有象無象だ。
オレが中級の域に達した時、奴らは初級の出口あたりでウロウロしている程度の低さだった。
道場主にしても、せいぜい水神流の上級剣士で、自分の力量のなさを棚にあげて精神論ばかり吐く老害だった。
オレはあいつらに、いつか自分の力を見せてやろうと思っていたものだ。
もっとも、結局、オレがそいつらに自分の力を見せつけることはなかった。
いろんなことに我慢できなくなり、あてつけるようにリーリャを犯し、逃げた。
元より狙っていたのもあるが、あいつら全員が大切にしているものを踏みにじってやりたかった。
奴らはオレが逃げた翌日から、血眼でオレを探しまわった。
オレは奴らをあざ笑うように国外に逃亡した。
思えば、オレもガキだった。
兄弟子たちのことはどうでもいいが、リーリャには、悪いことをしたと思っている。
「……ん」
風が吹いた。
目にゴミが入り、顔をしかめる。すると、オレの裾を引っ張る者がいた。
「おとうさん……ここ、どこ……?」
「うん?」
気づけば、俺はノルンを胸に抱いていた。
彼女は不安げな顔でオレを見ている。
そこでようやく、俺は部屋着のまま、草原に立っていることに気づいた。足の裏には地面の感覚。腕の中にはノルンの温もり。
──これは夢ではない。
「……なんだこりゃ?」
自分がなぜ、ここにいるのかわからない。
一人なら、最後まで夢だと思っただろう。
だが、胸にはノルンがいる。
三年前に生まれたばかりのノルン。小さなノルン。オレの可愛い娘。
オレは滅多に娘を抱かない。厳格な父親を目指しているため、肉体的な接触を避けているのだ。
そんなオレが、なぜノルンを抱いているのか……。
……そうだ、思い出した。
先ほどまで、家でゼニスたちと話をしていたのだ。
『娘は大きくなると父親との接触を嫌がるようになるから、今のうちに抱いておいたほうがいいわよ』
『いやいや、オレは威厳のある父親を目指そうと思っている。ルーデウスと違ってノルンは平凡なようだし、ここは偉大な父親と認識してもらわなければ』
『それって、嫌いだったお義父さんと一緒なんじゃないの?』
『……そうだな、じゃあやっぱり抱かせてくれ』
そんな、他愛のない会話だ。
その近くでは、リーリャがアイシャに何かを教えていた。
リーリャはアイシャに英才教育を施すつもりのようで、オレはもっと伸び伸びと自由に育てさせるべきだと反対したのだが、リーリャに鬼気迫る様子で、押し切られたのだ。
アイシャは成長が早かった。何かを教えればすぐに覚えたし、歩き出すのも早かった。リーリャの教育がよかったのかもしれないが、ノルンが知恵遅れなのかと不安になるぐらい優秀だ。
リーリャは「ルーデウス様ほどではありません。ノルンお嬢様ぐらいが普通です」と言っていた。
普通でも異常でもどちらでもいいのだが、将来、優秀な兄と妹に挟まれるノルンを思うと、少しだけ不憫だ。
そう思っていた時だ。
唐突に白い光に包まれたのだ。
ああ、覚えている。記憶は連続している。それが証拠に、ノルンが胸に抱かれている。
もうとっくに歩けるノルンを、胸に抱いている。
……何かが起こったらしい。そう瞬時に悟った。
「……おとうさん?」
オレの顔を見て、ノルンが不安そうな声を上げた。
「大丈夫だ」
オレはノルンの頭を優しく撫で、周囲を見渡す。
ゼニスとリーリャの姿がない。近くにいるのか、それともオレだけが飛ばされたのか。
なら、なぜノルンが一緒にいるのか。
……覚えがある。
迷宮で一度だけ引っかかったことのある凶悪な罠。転移の魔法陣に乗ってしまった時と似ている。
当時は運よく近くに転移したが、つい裾を掴んでしまったエリナリーゼが本気で怒っていた。
運が悪ければ即死する罠だ。
引っかかったのは斥候のサルが発見できなかったのが全部悪いのだが……。
そんな話はどうでもいい。つまるところ、転移とは接触している相手だけを瞬時に移動させる。
だから、抱いていたノルンが、オレについてきたのだ。
しかし、どうしてそんなことが起きたのか。
唐突すぎる。誰の仕業か。
正直、オレは各地に敵がいる。誰に何をされても不思議はないぐらい、悪いことをやった。
だが、転移となると話は別だ。転移魔術に詠唱はない。
ゆえに魔法陣か魔力付与品を使わなければならない。
転移の魔力付与品は世界的に見ても禁制品で、転移魔法陣の技術は禁術として指定され、失われて久しい。
オレ一人に復讐するのに、なぜそんな危険な橋を渡る必要があるのか。
そして、なぜこんな、何もない場所に飛ばす必要があるのか……。
まさか、当時の門弟の一人が犯人か?
あの時のことを覚えていて、リーリャを手に入れるために、オレを転移させた。
この場所なのは、あてつけだ。家に帰ったら、ゼニスとリーリャが野卑な男どもに犯されているのかもしれない。
くそっ、奴らの考えそうなことだ。
「ねぇ、おとうさん……」
「ノルン。大丈夫だ、すぐに家に帰ろう」
オレはむしろ自分に言い聞かせるように言って、町に向かった。
幸いにして、何かあった時のために、アスラ金貨を剣の鞘のホルダーに忍ばせてある。
冒険者時代の癖もあり、剣は常に身につけている。寝る時だって外しはしない。外すのは女を抱く時だけだ。
鞘のホルダーには冒険者カードも付けている。
こんな時のために、だ。
オレは冒険者ギルドに赴いて、一枚のアスラ金貨を両替。銀貨九枚と大銅貨八枚を手に入れた。
いつのまにか手数料が上がっていたが、これだけあれば十分だ。
冒険者ギルドの依頼をサッと確認し、緊急の配達依頼があったので、それを受諾する。
受付嬢は、更新が途絶えて文字の消えたカードに魔力を通し、そこに書いてあるランクがSであることを確かめ、驚いた後、Sランク冒険者がなぜこんなクエストを、と二度驚いていた。
緊急依頼であるためランクに関係なく受けられるが、本来ならEランクの依頼だ。
別に隠すこともないのだが、説明するのも面倒なので適当に言葉を濁し、馬を借りる。
緊急の配達依頼は、Sランクの特典により、馬を無償で借りることができる。
無論、依頼達成と同時に返さなければいけないが……。
今回、配達依頼とは別方向に行く。依頼人には悪いと思うが、オレも緊急だ。
連れられてきた馬は、かなりの名馬だった。
運がいい。それだけ緊急ということだろう。
これは、冒険者資格が剥奪される可能性もあるな。
だが、それならそれでいい。もう冒険者として生きていくつもりもないからな。
ノルンを馬に乗せ、オレも後ろに飛び乗る。
そして、すぐに町を発った。
途中でノルンが体調を崩した。
乗馬の経験のないノルンは、昼夜を問わず移動し続けるには、まだ子供すぎたのだ。
その看病に時間を取られ、フィットア領にたどり着くのに二ヶ月は掛かっていた。
最初から馬車を使っておけばよかった、と思う日数だ。
配達依頼はとっくの昔に失敗になっているが、罰金は大した金額ではない。
「……」
だが、オレは絶望していた。
ブエナ村にたどり着く前に、事の重大さがわかったからだ。
フィットア領が消滅していた。
オレは混乱の極地にあった。
何が起こったのか、ブエナ村はどこにいったのか。
ゼニスは? リーリャは?
城塞都市ロアも消滅している……となると、ルーデウスもいないのか?
馬鹿な……オレは知らずに、地面に膝をついていた。
『転移の罠で全滅』
そんな単語が、オレの脳内に渦巻いた。
冒険者時代、迷宮に潜るようになってから、何度も耳にした。
転移は一番気をつけなければいけない罠。パーティはバラバラになり、現在位置もわからなくなる。絶対に引っかかってはいけない罠。
当時、そんな罠で全滅したパーティの話は何度も聞いた。
パーティ全員で魔法陣に引っかかり、なんとか一人と合流して入り口まで戻ってくると、自分以外のパーティが全滅していたって話を、呆然とした顔で語る男を見たことだってある。
だが、まさか、こんな所で、自分が……。
「おとうさん……おうち、まだなの?」
そんな言葉で、オレはハッと我に返った。
オレの服の裾を掴んだ、三歳になる娘がいた。
「……」
オレは無言で、彼女を抱きしめた。
「おとうさん? どうしたの?」
そうだ。オレはおとうさん。父親だ。
娘は、まだ何が起こったのかわかっていない。
だが、オレがいるから、安心している。
オレは父親だ。父親なのだ。
弱みを見せてはいけない。毅然とした態度でいなければならない。
そうだとも。
転移は確かに恐ろしい罠で、なぜこんな事態になっているのかはわからない。
だが、オレは生きていた。
ゼニスだって元冒険者で、リーリャだって後遺症はあるものの、剣を使える。
アイシャは……思い出せ、あの時、あの瞬間、リーリャはアイシャと接触していたか?
……思い出せん。
いや、諦めるな。
あの時、リーリャはアイシャの手を握っていた……今はとりあえず、そう考えよう。
★ ★ ★
最寄りの町で馬を返し、情報を集めてみる。
転移の災害はフィットア領全土で起こった。
フィリップもサウロスも行方不明で、現在はフィリップの兄弟が領主になっている。
だが、フィリップの兄弟は災害の責任を取らされ、今にも失脚しそうである。
自分の保身に走るあまり、災害に対する手が打てていないらしい。領民を守ることより、まず保身。これだからアスラ貴族は気に食わない。
情報を集めている中、アルフォンスという老人が接触してきた。
彼はフィリップに仕えていた執事の一人だという。
ボレアス・グレイラット家に忠誠を誓っていた彼は、こんな状況になろうとも己の意志を変えなかった。自分の財産を使い、難民キャンプの設営を開始していたのだ。
アルフォンスは、オレにその手伝いをしてほしいと接触してきた。
なぜオレを、と聞くと、フィリップからオレの話を聞いていたらしい。
フィリップ曰く『いざという時に力を発揮する人物だが、先を見通す力はないので、自分のミスでいざという時を作り出す危うい人物だ』ということらしい。
余計なお世話だ。
アルフォンスとしては、低評価なオレに接触するのは迷ったらしいが、ルーデウスの父親であることを加味し、協力を仰いだという話だった。手紙で近況を聞いていただけだが、息子があまり接触していないであろうこの執事にも評価されていたことを嬉しく思う。
オレは快く承諾し、アルフォンスの指示に従った。
そうして一ヶ月。
アルフォンスは顔が広く、各所に手を回して人材を集め、難民キャンプを立ち上げた。
見事な手腕だった。
オレは集まってきた若者を集め、「フィットア領捜索団」を組織した。
各地に転移し、難民と化した人々を救うのだ。
もっとも、オレの目的は見ず知らずの他人を助けることではなく、家族を探すことだ。
その頃には、王都の方でも権力争いに決着がついたのか、復興資金がアルフォンスに送られるようになっていた。
難民キャンプにメモを残し、冒険者ギルドの本部があるミリス神聖国を目指す。
アスラとミリス、この二つの大国を押さえておけば、どちらかには情報がはいるだろう。
そういう判断だ。
なに、全員すぐに見つかる……と、その時は思っていた。
浅はかだった。
★ ★ ★
ミリスで活動し、半年の時間が流れた。
かなりの人間がミリス大陸へと転移していた。
オレはそれを全員、片っ端から救助した。
中には奴隷として売られていた者もいた。奴隷を無理やり解放するというのは、ミリスの法律に触れるところである。だが、ゼニスやリーリャがもし奴隷になっていたらと考えれば、犯罪だからと躊躇する理由にはならなかった。
全員救うという姿勢を保つのだ。
そうすれば、誰がどんな状況でも、大義名分が立つ。助けないという前例は作らない。
そう考え、オレはゼニスの実家を頼った。
ゼニスの実家はミリスでは力のある貴族であり、何人もの優秀な騎士を輩出してきた名門である。
彼らに頼り、奴隷を解放するための下地を作ったのだ。
その甲斐もあってか難民救助は順調だった。動きが早かったため、難民として困窮している人々はすぐに見つかったのだ。
彼らを助け、自分の足で帰るという者には旅費を、捜索を手伝うという者は捜索団に迎え入れ、老人や子供には住む場所を提供した。奴隷は金で片がつくなら金で、片がつかないならゼニスの実家の権力で、それでもダメなら、隙を見て攫って身柄を隠した。
もちろん、問題は起きた。
無理やりに奴隷を奪うオレたちをミリス貴族たちは疎ましく思い、私兵を引き連れてオレを強襲する貴族もいた。
団員に死者も出た。
だが、オレは止まらなかった。
オレには大義名分があった。人々を救うという大義名分が。
だから団員たちも付いてきた。
オレはアスラの上級貴族グレイラット家の名前、ゼニスの実家、かつての冒険者としての名声、あらゆるものを使って問題を解決した。
しかし、一向に、まったく、全然、ゼニスとリーリャの情報は入ってこなかった。
それどころか、ルーデウスもだ。
あの、どこにいても目立ちそうな息子の情報すら、一切入ってこないのだ。
★ ★ ★
あっという間に一年が経過してしまった。
この頃になると、難民の発見報告もかなりナリを潜めた。
中央大陸南部とミリス大陸で見つけられる相手は、大体見つけたと言えよう。
まだいくつか探していない村はあるし、まだ何人か奴隷を手放さない奴らがいる程度だ。
奴隷の解放は計画的に進んでいる。身柄を確保してしまえばこちらのものだ。
強引であることは承知している。一部の貴族連中に唾棄され、目をつけられていることも理解している。それで団員が襲われ、死亡したり大怪我をしたこともあった。
団員たちの中には、そのことでオレを責める奴もいた。
あんたがもっとうまくやってりゃ、こんなことにはならなかったんだ、と。
何を言われても、オレの行動は変わらない。
今更変えるわけにはいかないのだ。
最近、難民の発見報告より、死亡報告が多く上がってくる。
いや、最近などというのは曖昧か。最初から死亡報告は多かったのだ。
はっきり言って、生存者より死亡者の方が圧倒的に多い。
エト、クロエ、ロールズ、ボニー、レーン、マリオン、モンティ……。
知り合いの死亡報告を聞く度に、オレの背筋がヒヤリと冷えた。
報告を受けて泣き崩れる者もいた。あと一歩間に合わず、死亡したというケースもあって、オレに食ってかかる者もいた。なんでもっと早くあの場所を探してくれなかったんだ、と責められることもあった。
その度に、やるせない気持ちになる。
そして、時が流れれば流れるほど、死亡報告すらも曖昧になっていった。
死んだかもしれない、そういう風体の奴が死体になっているのを見たかもしれない。森の奥で、そいつの持っていた何かを見たかもしれない、そんな報告だ。
実際に赴いてみると、徒労であることも多かった。
オレの家族に関する情報は、未だ一切入ってこない。
失敗したかもしれないと思った。魔大陸や中央大陸の北部を先に探すべきだったのかもしれない。
奴隷になったところで、命まで奪われるわけではないのだ。
後回しにできるものは後回しにして、まずは危険な場所を探すべきだったのではないか、と。
……いや、無理だ。捜索団のメンバーは戦いに優れているわけではない。
大半が元は農民や町民。冒険者もいるが数は少ないし、アスラ王国で活動していたような冒険者で、オレに言わせりゃ駆け出しもいいところだ。
そんなメンツでは、魔大陸や中央大陸北部、ベガリット大陸では、戦闘に耐えられない。
自分たちが遭難しかねない。
だから間違ってなかったと思う。
おかげで、数千人単位で難民を救うことができたのだと。
あるいはオレの昔のパーティ『黒狼の牙』の連中がいてくれれば、魔大陸やベガリット大陸も捜索してくれただろう。
だが、連絡を取ってきたのは一人だけだった。その一人も、一度連絡を取ってから、フラリとどこかにいなくなり、今では何をやっているのかサッパリわからない。
薄情な連中だとは思わない。
もともと仲は悪かったし、別れ際にも大喧嘩をした。
最悪な別れだったし、全員がオレを恨んでいてもおかしくはない。
なぜ、昔のオレはあんな別れ方をしたのか。
ガキだったからだ……と、後悔しても始まらない。
★ ★ ★
一年半が経過した。
このごろ、酒に頼らなければやってられなくなってきていて、朝から晩まで飲んでいる。
素面の時なんてない。
こんなことではいけない、と思いつつも、酔いが覚めると、どうしてもダメだった。
家族が死んだと考えてしまう。
どんな死に様だったのか、死体はどうなったのか……そんなことばかりを考えてしまう。
なにせ、あの優秀な息子ですら、音沙汰の一つもないのだ。
考えたくはない。
考えたくはないが、恐らく、生きてはいまい。
きっと、みんな、この一年半の間に、オレの助けを待ち、泣きながら死んでいったのだ。
そう考え、発狂しそうになった。なぜオレはこんな所にいるのか、他者のことなどかなぐり捨てて、最初から危険な場所を探していればよかったのではないのか。
最悪、オレ一人でもなんとかなったのだ。
選択ミスで、すぐそばにあったものが失われた。一番大切なものが、無残にも奪われた。
それを信じたくなくて、オレは酒を飲む。
酔っ払っている時だけが、幸せだった。
仕事はまったく手につかなかった。
半年後、ミリス大陸で見つかった人々をフィットア領へと返す作戦が始まる。
老人や女子供、あるいは病気で動けない人間ばかりだ。
金があっても長旅に耐えられるかわからない、けど故郷へと帰りたいと願う者たち。
彼らを護衛しつつ、フィットア領へと戻るのだ。
その計画が進んでいる中、オレは責任者であるにもかかわらず、会議にも参加せず、一日中飲んだくれていた。
オレを含めた主要メンバーはミリスに残るが、その作戦を最後に、捜索活動は縮小される。
二年。たった二年で捜索が打ち切りなのだ。早すぎると思うが、こんなものだと納得している自分もいる。これ以上捜索を続けても、無駄に資金を浪費していくだけだと。
結局、俺は家族の一人も見つけることができなかった。
ダメな男だ。
どうしてオレはこんなにダメなんだ。いつまでたっても大人になれない。
酒浸りになるオレに、最近は団員たちは一歩距離をおいている。
当然だ。誰だって、こんな酒浸りのバカを相手にしたくない。
もっとも、例外は何人かいる。
そのうちの一人が、ノルンだ。
「お父さん! あのね、さっきね、道でね! おっきな人がね!」
オレがどれだけ酔っ払っていても、ノルンは嬉しそうに話しかけてきてくれる。
ノルンはオレにとって、最後の家族だ。
一番大切なものだ。オレには、もうノルンしかいない。
そうだ。魔大陸やベガリット大陸に行かなかったのだって、ノルンの存在があったからだ。
当時まだ四歳だった娘を、どうして放り出せよう。
どうして彼女を置き去りにし、自分が死ぬかもしれない危険な場所へと赴けようか。
「おお? どうしたノルン。何か面白いことでもあったのか?」
「うん! さっき道で転びそうになったら、ハゲ頭の人が助けてくれたの! それでね、コレ! もらったの!」
ノルンはそう言って、嬉しそうに手の中のものを見せてくれた。
りんごだった。真っ赤なりんごだ。
実に美味しそうな色をしている。
「そうか、それはよかったな。ちゃんとお礼は言ったか?」
「うん! ありがとうって言ったら、ハゲのおじさんは頭を撫でてくれたの!」
「そうかそうか。いい人だな。でも、ハゲって言っちゃダメだぞ、気にしてるかもしれないからな」
娘との会話はいつも楽しい。
ノルンはオレの宝だ。もしノルンに手を出すような輩がいたら、それがミリス教団の法王でも喧嘩を売る覚悟がある……と、そんなことを思っていた時だ。
「団長! 大変です!」
団員の一人が、オレの部屋に飛び込んできた。
娘との会話を中断され、俺は少し不機嫌になる。
いつもなら、怒鳴り散らして追い返すところだろうが、娘の手前、くだらないプライドが、俺を冷静にさせた。
「どうした?」
「仕事に行ってた奴らが襲われたんだ!」
「襲われただぁ?」
襲われた、誰に?
決まってる、あのくだらない貴族連中だ。
アスラ王国の領民が災害によって奴隷に落ちたのだと説明しても、決して身柄を渡そうとしなかった、強欲な連中だ。確か今日は、そのうちの一人を救出するという話だったか。
「よし、全員、装備つけろ! いくぞ!」
取るものも取りあえず、荒事用の団員に声を掛ける。
大して強い連中ではないが、相手だって迷宮に潜るような冒険者ではない。
十分互角に戦える。
そして、そいつらを引き連れ、問題が起きたとされる場所へと向かう。
すぐ近く、というか隣だった。
捜索団の倉庫の一つで、団員の衣料品などを保管している場所だ。
ここを嗅ぎつけられたのはまずいな。拠点を変える必要があるかもしれない。
「パウロさん、敵は一人だが、強い。気をつけてくれ」
「……剣を使うのか?」
「いや、魔術師だ。多分ガキだが、顔を隠している」
魔術師のガキ……それも、素人とはいえ、大人の団員を何人も倒しうる相手。
恐らくは小人族だろう。奴らは子供のような見た目で、平気で他人を騙す。
小人族の手練れ……酔っていて、勝てるだろうか。
そこらのチンピラに負けない自信はあるが……。
いや、問題ない。やりようはいくらでもある。
そう思い、俺は倉庫へと入った。
第三話 「親子喧嘩」
パウロの泊まっている宿屋『門の夜明け亭』。
その隣にある酒場。木製の丸テーブルが十席ほど並んでいる中に、俺は座っていた。
目の前には、パウロが座っている。
酒場にいるのはパウロだけではない。まだ昼間だというのに、全ての席に人が埋まっている。
先ほど気絶させた奴らも、パウロの仲間の治癒術師に治療してもらい、座っている。
言うまでもないことだが、俺に対してはあまりいい目を向けていない。
ここにいる全員、パウロの仲間だそうだ。
そのお仲間さんの中で、特に気になるのは、パウロの後ろ斜め後方に座っている女戦士だ。
髪は栗色で外ハネショートにアヒル口。チャーミングな印象を受けるが、特筆すべきはその体つきと格好だ。バインとでかい胸と、キュっとくびれた腰、むっちりとした尻。
これらをいわゆるビキニアーマーに身を包んだ、十代後半の少女。
パウロにヴェラと呼ばれていた女戦士で、俺が苦戦した相手だ。
それはもうパウロの好きそうな体をしており、俺ですら見ただけで釘付けになってしまうような体をビキニアーマーに包んでいる。
ビキニアーマーというのは、この世界ではそれほど珍しくない。
なんせ多少の傷なら治癒魔術で簡単に治る世界だ。攻撃を受けることを前提にして、より軽量を目指す剣士が大勢いる。
魔大陸でも結構見たし、恐らく、彼女もそんな一人なのだろう。
しかし、ここまで薄着なのは初めてだ。
普通は薄手の服の上につけるものだし、肩や肘といった関節にはプロテクターをつける。
今は酒場だからはずしているにしても、それなら普通は外套を羽織ったりする。
少なくとも、今まで魔大陸で見てきたお姉さま方はそうしていた。おばさま方の中にはあまり頓着していない人もいたが……。
ていうか、倉庫で一度は上着を羽織ったはずだが、なんでまた脱いでるんだろうか。
とりあえず拝んでおこう。眼福眼福……と見ていると、ふと目が合った。
バチッとウインクされたので、ウインクを返しておいた。
「おいルディ……ルディ?」
と、パウロに呼ばれ、俺は女戦士から目線を剥がした。
「父様、お久しぶりです」
「まあ、なんだ、ルディ……よく生きていてくれたな」
パウロは、疲れた声で言った。
なんというか、随分と変わっていた。
頬はげっそりと窶れ、目の下には隈があり、無精髭を生やして、髪はボサボサで、息は酒臭く、全体的にやさぐれている。
俺の記憶にあるパウロとは似ても似つかない。
「ええ……まあ……」
どうにも、頭がついていかない。
なぜ、パウロがここにいるのだろうか。
ここはミリス神聖国。アスラ王国とはアフリカとモンゴルぐらい離れている。
俺を探しにきてくれたのだろうか?
いや、魔大陸に転移したなんてわからないはずだ。
なら、別件か。ブエナ村を守るという仕事はどうなっているのだろうか。
「その、父様はどうしてここに?」
まずはそこだ、そう思って聞くと、パウロは意外そうな顔をした。
「どうしてって、伝言を見ただろう?」
「伝言……ですか?」
伝言。なんの話だろうか。そうしたものを見かけた記憶はない。
疑問符を浮かべる俺の顔を見て、パウロはむっと顔をしかめた。
何か気に障るようなことでも言っただろうか。
「なあルディ、お前、今までどうしてきた?」
「どうといわれても、大変でしたよ」
事情を聞きたいのはこっちなのだがと思いつつも、俺は今までの道程を話した。
魔大陸に転移し、ある魔族に助けられ、冒険者となり、エリスと共に一年間かけて魔大陸を抜けてきたこと。
思い返すと、なかなか楽しい旅だった。
最初の出だしこそ悪かったものの、半年経過したぐらいから冒険者としての生活にも慣れた。
それがゆえに、俺の口調は次第に饒舌になり、これまでの旅におけるエピソードを語る口調に熱が入った。
語られるは完全ノンフィクションの一大スペクタクル。
旅の内容は三部によって分けられた。
第一部、心の友ルイジェルドとの出会い、そしてリカリス村での大騒動。
第二部、ルイジェルドを助け、大魔術師ルーデウスが世直しをする旅。
第三部、卑劣な獣族の罠に掛かり、とらわれの身となって絶体絶命な俺。
一部誇張表現はあるものの、俺の口は滑らかに動き、段々楽しくなってきて身振り手振りを交え、大げさな擬音を発しての大演説へと発展した。
ちなみに、人神のことはボカした。
「そして、ウェンポートへとたどり着いた僕らが目にしたのは……」
「……」
第二部『魔大陸ブラリ三人旅・人情編』が終わったところで、俺はふと言葉を止めた。
パウロが不機嫌になっていた。
顔をゆがませ、イラついた表情でテーブルをトントンと指で叩いていた。
何が気に障ったのだろうか……俺は理解できぬまま、続きを話そうとした。
「それで、その後大森林に赴いて」
「もういい」
パウロはイライラした声音で、俺の言葉を遮った。
「お前がこの一年ちょっとの間、遊び歩いてたってことは、よくわかった」
パウロの言葉に、俺は少しばかりカチンときた。
「僕も大変だったんですが」
「どこがだ?」
「えっ?」
聞き返されて、俺は変な声を出した。
「お前の口調からは、大変さなんて微塵も感じられねえ」
それは、そういうふうに話したからだ。
確かに、ちょっと調子には乗っていたかもしれないけど。
「なあ、ルディ、一つ聞きたいんだが」
「なんでしょう」
「お前、どうして魔大陸で、他に転移した奴らの情報を集めなかったんだ?」
俺は黙った。黙らざるをえなかった。
どうして、といわれても答えようがなかった。
そんなのはただ一つ。理由はただひとつ。
忘れていたからだ。
最初は自分たちのことで精一杯で、しかし余裕が戻ってきた時には、まさか自分たち以外の人物が魔大陸にいるとは思っていなかった。
「わ、忘れていました……その、余裕がなくて」
「余裕がない? 見ず知らずの魔族を助ける余裕はあっても、他に転移されたであろう人たちを気にかける余裕はないってか」
俺は黙る。
優先順位を間違ったと言われれば、確かにそうかもしれない。
けど、後になってからそんなことを言われても困る。
あの時は、本当に忘れていたのだ。仕方がないだろう。
「ハッ! 人も探さず、手紙の一つもよこさず、可愛い可愛いお嬢様と二人で、遠足気分で冒険者暮らし。しかも、強力な護衛まで付いているときた。それで。ハッ、なんだ、ミリシオンに来て最初にやったことが、人攫いの現場を見つけて、パンツかぶって正義の味方ごっこか?」
パウロはあざ笑うように息を吐くと、隣のテーブルにおいてあった酒瓶を手にとる。
グッと一息で半分飲んだ。
そして俺を馬鹿にするように、ペッと唾を吐いた。
そのあからさまに馬鹿にした仕草にイラッとする。
酒を飲むなとは言わないが、今は大事な話をしてるんじゃないのか?
「僕だって一杯一杯だったんですよ。右も左もわからない状況で、でもエリスだけは守らなきゃって思って……。多少抜けてることがあったって仕方ないでしょう?」
「別に悪くはねえよ」
馬鹿にするような口調。
とうとう、俺は声を荒げた。
「じゃあ、なんで突っかかってくるんですか!」
我慢にも限界があった。
パウロがなんでこんなことを言うのかわからない。
「なんで?」
パウロは再度、ペッと唾を吐き捨てた。
「お前こそ、なんでだ?」
「なんでって、何が?」
理解できない。パウロは何を言いたいのか。
「エリスってのはフィリップの娘だったか?」
「え? ああ、もちろん、そうですよ」
「オレぁ見たことがねえが、さぞ可愛いお嬢さんなんだろうな。手紙を出さなかったのは、お嬢様の護衛が増えると、イチャイチャすんのを邪魔されるとでも思ったからか?」
「だから、それは、忘れていたからだって言ったじゃないですか!」
それ以上のことは考えていない。
確かに、エリスはいいところのお嬢さんだ。
グレイラット家はでかいし偉い。あるいは、ザントポートの領主あたりに話をすれば、護衛の一人や二人はつけてくれたかもしれない。
けど、それは俺が獣族の村で捕まっていたから無理だったとちゃんと説明……は、してないか、そこまでは話していない。
だとしても、だ。
俺は俺なりにできることはやってきたつもりだ。
全てを最善手で行えてはいないが、だからといってそれを責められる筋合いはない。
「……」
「団長。それぐらいにしてあげたらどうです? まだ小さいんですから、あんまり言ったってしょうがないじゃないですか」
俺が黙っていると、先ほどのビキニが、後ろからパウロの肩に手を置いた。
それを見て、俺は鼻で笑った。
結局こうだ。この男は、偉そうなことを言ったって、女に見境がない男なのだ。
それが、そんな男が、どうして俺に何かを言えるというのだ。
俺はエリスには一切手出ししていない。
確かに危ない瞬間はあった。煩悩に支配されそうにもなった。けど、決して、俺は、手を出していない。
「女のことで、父様にとやかく言われたくないですよ」
「……あ?」
パウロの目が据わった。
そのことに、俺は気づかない。
「その女の人は、なんなんですか?」
「ヴェラがどうかしたのか?」
「近くにそんな綺麗な女の人がいるって、母様やリーリャは知ってるんですか?」
「……知らねえよ。知ってるわけねえだろ」
パウロの顔が悔しげにゆがむが、俺はそれを見ていない。
ただ口喧嘩に勝ちつつあると錯覚していた。
「じゃあ、浮気し放題ってわけだ。ずいぶんとエロい格好させちゃってまあ。こりゃ、新しい弟か妹ができる日も近いですかね」
気づけば。
気づけば俺は殴られて、地面に倒れていた。
パウロが憎々しげな顔をして、俺を見下ろしている。
「ふざけたこと言ってんじゃねえぞルディ」
殴られた。なんでだ、ちくしょう。
「てめえ、ルディ。ここに来たってことは、ザントポートにも足を運んだんだろうが」
「それがどうしたってんだよ」
「なら知ってるだろうが!」
何がだよ! もうワケがわからない。
ただ、パウロが何かを隠匿し、それを知らない俺を、知っていて当然だと、糾弾していることだけはわかった。
ふざけるんじゃない。
俺にだって知らないことはある。知らないことだらけだ。
「知らねぇつってんだろ!」
俺は拳を振り上げ、パウロに殴りかかった。
避けられる。同時に予見眼を開眼する。
[足を掛けられて転ばされる]
俺は思い切りパウロの足を踏みつけ、振り向きざまにパウロの顎先を狙う。
[避けられ、カウンターで殴り返される]
酔っ払ってるのによく動く。
俺は右手に魔力を込めた。肉弾戦でパウロに及ばないなら、魔術を使えばいいのだ。
右手から竜巻を発生させ、パウロに叩きつける。
「うおお!?」
パウロはキリモミしながらぶっ飛び、カウンターの奥へと突っ込んだ。
ガシャンと酒瓶をばら撒きながら、床に落ちる。
「くそっ! やりやがったな!」
すぐに起き上がってくるが、足にきている。
飲みすぎだ、バカが。
昔のパウロはもっと強かった。恐らくあんな体勢でも、俺の竜巻を受け流してみせたはずだ。
「てめえ、ルディ……」
「団長!」
よろめくパウロに、別の女の人が駆け寄っていく。
ローブ姿の魔術師だ。
自分は女に囲まれてるってのに、よくもまぁ俺のことをとやかく言えたもんだ。
「触んじゃねえ!」
パウロはその人を振り払い、俺の前まで歩いてくる。
「パウロ。お前、俺がいない間に何人と浮気してんだ?」
「黙りやがれ!」
[右拳で殴りかかってくる]
なんとも無様なテレフォンパンチだ。これが本当にあのパウロだろうか。
予見眼なしでも回避できそうじゃないか。
「だあああ!」
俺はその腕を掴み、一本背負いの要領で投げ飛ばした。
もちろん、俺は柔道なんざできない。
風魔術を使い、反動をつけて無理やり、力任せに地面に叩きつけたのだ。
「ぐはぁ……!」
受け身も満足に取れなかったらしい。
俺は無様に倒れたパウロに馬乗りになって、エリスがいつもやっているように、膝で両腕を押さえこみ、抵抗できなくする。
「俺だって! 一生懸命やってきたんだ!」
殴った。
殴った。
殴った。
パウロは歯を食いしばり、憎々しげな顔を俺に向けてくる。
くそっ。なんだよその眼は。なんでそんな顔されなきゃいけないんだよ。
「仕方ないだろ! 何も知らない場所で! 誰も知っている人がいなくて! それでなんとかここまで来たんだ! なんで責められなきゃいけないんだよ!」
「……てめぇなら、もっとうまくできただろうが!」
「できねぇよ!」
それから、俺は無言で何度もパウロを殴った。
パウロは何も言わない、ただ口の端から血を流して俺を見ているだけだった。
苛立たしそうに、話の通じない奴を見るように。
なんでだ。
こんな顔する奴じゃなかったはずだろ……くっそ……くそ。
「やめてえええぇぇ!」
その時、横合いから何かが飛び込んできて、俺にぶつかった。
俺はその反動でパウロの上でよろめき、次の瞬間には、パウロは俺を突き飛ばして起き上がっていた。
俺は追撃がくると即座に身構える。
しかし、パウロは動かなかった。俺たちの間には、一人の少女が立ちはだかっていたからだ。
「もうやめて!」
パウロによく似た鼻立ちと、ゼニスによく似た金色の髪。
一目見てわかった。
ノルンだ。ノルン・グレイラット。
妹だ。俺の妹。随分と大きくなった。今、確か五歳だったか? いや、もう六歳になったのか?
なんで、俺の方を向いて、両手を広げてるんだ?
「お父さんをイジメないで!」
「…………え?」
俺は呆然と、その言葉を受け止めた。
イジメ?
いや、だって。え?
ノルンは泣きそうな目で俺を睨んできている。ふと周囲を見ると、なぜだろうか。俺に批難の目が集まっていた。
「……なんだよ、それ」
すっと心が冷えた。
何十年も前のことを思い出す。
生前、イジメられていた時のことだ。
あの時も、ちょっと俺が何か言い返せば、教室中から批難の目が集まったものだ。
ああそうだろうとも。俺は間違ったことを言ったんだろうさ。
──諦めた。心が折れた。
もういい。帰ろう。何も見なかった。俺は何もしなかった。
宿に戻って、エリスとルイジェルドを待とう。そしてすぐに旅立とう。明日か、明後日か。なに、首都じゃなくても金は稼げる。ウェストポートにだって冒険者ギルドはあるはずだ。
「ルディ。転移したのはお前だけじゃねえ、フィットア領のブエナ村の奴らも全員、転移災害に巻き込まれた」
パウロが何かを言っているのを、ボンヤリと聞いた。
「……」
ん、え?
なに、今、なんつった?
「ザントポートにも、ウェストポートにも、伝言は残した。冒険者ギルドだ。お前、冒険者になったんだろ? なんで見てねえんだよ……」
そんなことを言われたってザントポートにもそんなもの……。
いや、そうだ。ザントポートの冒険者ギルドには寄ってない。
ルイジェルドを迎えに行って、そのままドルディア族の村に行ったから。
「お前がのんきに旅してる間に、何人も死んだ」
何人も。
あの規模。魔力災害。転移災害。どうして思い至らなかったんだ。人神だって、『大規模な魔力災害』と言っていた。俺は、どうして、ブエナ村が無事だって思ったんだ?
そうか。みんな行方不明……。
「ってことは……シルフィも?」
そう言うと、パウロはまた苛立たしそうな顔をした。
「ルディ。お前、自分の母親より女の心配か?」
うっ、と俺は息を飲んだ。
「か、母様も見つかってないんですか!?」
「ああ。まったく見つからねえよ! リーリャもな!」
パウロの悲痛で、叩きつけるような言葉。
俺はぶん殴られたようによろめいた。
足がフラフラする。倒れそうになってよろめいた先には、椅子があった。
なんとかすがりつく。
「オレたちは、転移した奴らを探すために、こうして捜索団を組織している」
捜索団。
そうか、これは、ここにいる人たちは捜索団なのか。
「そ、捜索団が、なんで、人攫いを?」
「奴隷になった奴もいるんだよ」
奴隷。
転移されて、そこがどこだかわからない状態で、騙されて、奴隷にされて……。
そんな人が、大勢いたという。
パウロたちは、行方不明者のリストと照らし合わせ、奴隷を一人ひとり訪ねては、その主人に対し、解放するように頼み込んだらしい。
だが、中には、そうして手に入れた奴隷を手放したくない人も多い。
ミリスの奴隷法によると、いかなる事情があれど、一度奴隷に落ちてしまえば、その者は主人の所有物だ。
なので、パウロは、無理やり奴隷を攫うという手を使ったのだという。
奴隷を盗むのは当然犯罪だが、法には抜け道がある。
パウロはその法の穴をついて、奴隷を何人も解放した。
もちろん、望むなら、そのまま奴隷でいることも許した。
けれど、ほとんどの奴隷は、故郷に帰りたいと涙ながらに懇願したという。
今回救出された少年も、そんな一人だ。
どこかで見たことがあると思ったら、あの少年は、昔シルフィをいじめていたうちの一人、ソマルだった。彼はこの一年の間、男娼のような扱いを受けていたという。
奴隷となった者の悲痛な叫びを聞いて、しかし中には助けられなかった者もいるという。
一部の貴族たちからは疎まれ、団員たちにも、その強引なやり方についていけないという者も出てきているという。
上からも、下からも、横からも責められて。パウロは神経をすり減らすような毎日を送りながら、しかし決してあきらめることなく、頑張ってきた。
ただ、魔力災害で転移した人を助けるために。
「ルディ。お前はとっくに事情を察して、すでに動いてくれてると思ってたよ」
パウロの言葉に、俺は力なくうなだれた。
無茶、言うなよ……どうやって事情を知れっていうんだよ。
ああ、でも、そうか。
そうだな。もしかすると、今まで旅してきた魔大陸の町にも、フィットア領から転移した人がいたのかもしれない。
その人たちから話を聞けば、災害の規模がどれぐらいだったか、わかったかもしれないのだ。
俺は状況確認を怠った。災害のことを知るよりもまず、ルイジェルドのことを優先した。
失敗だ。
「それが、のんきに冒険とはな……」
能天気。
ああそうだ。そうだな。俺がエリスのパンツに興奮したり、冒険者ギルドのお姉さんの体に興奮したり、魔界大帝の太ももをなめたり、猫耳少女の体をまさぐったりしている間、パウロは懸命に家族を探していたのだ。
怒るわけだ。
「……」
ただ、俺も謝罪は出てこなかった。
だって、仕方ないじゃないか。
どうしろっていうんだ。
あのときは、あれが最善だと思っていたんだ。
「……」
パウロは何も言わない。
ノルンも黙っている。
ただ、その視線からは、強い拒絶の感情を感じた。この感覚は、俺をえぐる。
心をえぐる。魂をえぐる。
周囲を見回すと、パウロの仲間だという団員も、俺を責めるような目で見ていた。
脳裏に昔のことがよぎる。
あれは、不良に全裸にされてはりつけにされた次の日。
クラスに入った時の、全員の視線の……。
頭の中が真っ白になった。
★ ★ ★
気づけば、俺は自分の宿、自分の部屋に戻ってきていた。
ベッドに倒れこむ。
よくわからない。
何がどうなっているのか、わからない。何も考えられない。
「……?」
服の中でガサリと音がした。
探ってみると、便箋が出てきた。俺はそれをクシャリと握りつぶして捨てた。
「はぁ……」
ため息をついて、足を抱えてベッドに座る。
何もしたくなかった。
思えば、俺は両親に冷たくされるのは初めてだった。前世でも、今世でも。
なんだかんだ言いつつも、親は俺に甘かった。
さっきのパウロは完全に俺を突き放していた。あの態度はそう、俺を家の外に放り出した時の兄貴の態度だ。
何がいけなかったのだろうか。
わからない。
うまくやったつもりだ。
思い返してみても、自分の判断に致命的なミスはない。あえて言うなら、最初にルイジェルドを頼ったことぐらいだ。神を疑いつつも助言に従い、ルイジェルドを助けた。
旅のことも、なるべく楽しく話した。
調子に乗っていたのもあるが、パウロを心配させることはないと思ったし、自尊心もあった。
俺はやれるんだぜ、って言いたかった。
パウロにしてみれば、面白くなかったかもしれない。パウロの仲間たちにしても、やはり面白くなかっただろう。
確かに失言もした。
母親よりもシルフィを優先したつもりはない。だって、パウロとノルンがいたんだ。普通はゼニスだって大丈夫だったと思うだろう?
いや、言い訳だな。
俺はあの瞬間、ゼニスのことは頭になかった。
女のことは、あいつから言い出したことだ。俺はエリスに手なんか出していない。
だから、浮気症のパウロにどうこう言われる筋合いは……。
ああ、そうなのか。もしかすると、パウロも手を出していなかったのか。
なるほど。それなら怒るわけだ。
オッケー、少しまとまってきたような気がする。
よし。明日、もう一度話そう。
なに、パウロだってちょっと感情的になっただけだ。前にもこういうことはあったじゃないか。
話せばわかるさ。そう、大丈夫。俺だって、家族のことを心配してないわけじゃない。調べなかったのは、ちょっとした情報の行き違いだ。
確かに、一年半、魔大陸を捜索できた俺が何もしなかったのは痛い。
だが、俺だって生きていたんだ。なんとかなるさ。
そうとも。じっくり探せば大丈夫だ。パウロだってわかってるはずだ。この広い世界で、すぐに探し人が見つかるわけがないと。
だからパウロを落ち着かせて、今後の計画を練るんだ。
まだ探していない所を重点的に。
俺も手伝おう。エリスをアスラに届けたら、その足で北部か別の場所に行けばいい。
そう、まずはパウロに会って……あの……酒場に……戻って……パウロに会って……。
「………うっぷ」
唐突に吐き気がして、俺はトイレに走った。
そのまま、ゲーゲーと全てを吐き出す。
理屈でわかっていても、心は晴れない。
久しぶりに家族から向けられた拒絶に、心はすっかり潰れていた。
★ ★ ★
昼下がり、ルイジェルドが帰ってきた。
ルイジェルドはいつもよりちょっと嬉しそうな顔で、何かを手に入れたのか、封筒のようなものを見せようとしたが、ベッドに座る俺を見て顔をしかめた。
「何かあったのか?」
そう聞かれた。
「この町に、父様がいました」
と答えると、ルイジェルドの顔はさらに険しくなった。
「……何か、嫌なことでも言われたのか?」
「ええ」
「久しぶりに会ったのだろう?」
「まあ」
「喧嘩したのか?」
「ええ」
「詳しく話せ」
包み隠さず、何が起こったのかを話した。
一部始終を話し終えると、ルイジェルドは「そうか」と一言。
会話が途切れ、しばらくして彼はいなくなった。
夕方頃、エリスが帰ってきた。
何があったのか、ずいぶんと興奮した様子だった。
服には葉っぱがついていて、頬には土埃がついている……けど、嬉しそうだ。
あの調子だと、うまいことゴブリンは狩れたらしい。
よかった。
「おかえり」
「ただいまルーデウス、あのね! あ……」
笑いかけると、エリスはギョッとした顔になった。
そして、そのまま駆け寄ってくると、
「誰よ、誰にやられたの!」
必死な表情で俺の肩を揺さぶった。
「なんでもないよ」
「そんなはずない!」
何度か、そんな問答が続いた。
しつこかったので、パウロに会ったことを伝えた。
包み隠さず、淡々と。どんな話をして、どんな反応が返ってきて、どんなことが起こったのかを伝えた。
「なんなのよ、それは!」
すると、エリスは大層ご立腹となった。
「そんな勝手なことを言うなんて、許せない! ルーデウスがどれだけ頑張ったと思ってるの! それを遊んでいたなんて……! 絶対に許せない! 父親失格よ! ぶっ殺してやるわ!」
物騒なことを言って、剣を片手に飛び出していった。
俺は止める気力もなくそれを見送った。
数分後、エリスが戻ってきた。
ルイジェルドに首根っこを掴まれ、猫のように。
「離しなさいよ!」
「親子喧嘩に口をだすな」
ルイジェルドはそう言い放つと、エリスを床に下ろした。
エリスはすぐに振り返り、ルイジェルドを睨みつける。
「親子喧嘩でも言っていいことと悪いことがあるわ!」
「ああ、だが、俺にはルーデウスの父親の気持ちもわかる」
「じゃあルーデウスの気持ちはどうなるの! あのルーデウスが! いつも飄々としてて、蹴っても殴っても平然としてるルーデウスが! こんなに弱ってるのよ!」
「弱っているなら、お前が慰めてやれ。女なら、それぐらいできるだろう」
「なっ!」
エリスは絶句して、ルイジェルドは、下に降りていった。
「……」
部屋に残ったエリスは、落ち着かなげにあっちにうろうろ、こっちにうろうろ。
チラチラと俺の方を見ては、たまに腕を組んで仁王立ちをして、口を開きかけてはやめて、またうろうろ。
落ち着きがない。動物園の熊みたいだ。
最終的には、エリスは俺の隣に座った。
おとなしく、何も言わず座った。微妙に距離を開けて。
エリスはどんな顔をしていただろうか。
よく見ていなかった。人の顔を見る余裕がなかった。
「……」
しばらく時間が流れた。
ふと気づくと、エリスは隣にいなかった。
どこに行ったんだと思った時、後ろから抱きしめられた。
「大丈夫よ、私がついてるから……」
エリスはそう言って、俺の頭を抱えた。
柔らかくて、熱くて、ちょっと汗臭くて。その全てが、ここ一年で嗅ぎ慣れた、エリスの匂いだった。
安心感があった。
家族に突き放された不安感が、恐怖心が、すべて払拭されていくような感じがした。
もう、エリスも俺の家族なのかもしれない。
もし前世にエリスがいれば、俺はもっと早い段階で救われていたかもしれない。
そう思える抱擁だった。
「ありがとう、エリス」
「ごめんなさいルーデウス。私、あんまり、こういうの得意じゃないから」
俺は前に回されたエリスの手を握った。
剣ダコがあって、力強くて、貴族の令嬢とは思えない手。努力の手。
「いえ、助かりました」
「……うん」
折れた心がつながり、少しだけ、余裕が戻ってきた。
俺はそのことを実感し、ほっとしつつ、エリスに体重を預けた。
今は寄り掛からせてもらおう。
第四話 「パウロとの再会」
★ パウロ視点 ★
酒場。
もうすぐ日が暮れるということもあり、団員以外の客が増え始めているが、逆に団員は減っている。
そんな中、俺はテーブルの一つに座り、延々と飲み続けていた。
不機嫌さが漂っているのだろう、誰も近づいてこない。
「よう、探したぜ?」
と、思ったら声を掛けられた。
顔を上げると、サル顔の男が口の端をあげている。この顔を見るのは一年ぶりだ。
「ギース……てめえ……どこ行ってやがった」
「おうおう、なんだなんだ、相変わらず不機嫌そうだな」
「当たり前だ」
チッと舌打ちして、頬を触る。
ルーデウスに殴られたところは、まだ痛みが残っている。
見栄を張ったが、治癒術師にヒーリングを掛けてもらったほうがよかったかもしれない。
クソッ、ルーデウスめ。何が「魔大陸とかいって、僕の魔術に掛かれば余裕でしたよ」だ。
そんだけ余裕なら、人探しぐらいできるだろうが。
それどころか、大王陸亀の喰い方について延々と語りやがって。何が「もし土魔術で土鍋を作ることを思いつかなければ、一年もあの糞不味い焼肉を食い続けることになりましたよ」だ。
食材なんか探す暇があったら、別のことができただろうが。
くそ。
挙句、オレが浮気してるだと?
ふざけやがって。転移してこの方、女のことなんざ一切考えたことなんてねえ。
自分が何もできなかったことを棚に上げてオレのことを責めるたぁ。
ふざけやがって。何が知らなかっただ。お前がきちんと魔大陸を調べてりゃ、今頃ゼニスかリーリャのどっちかとは再会できたかもしれねえってのによ。
ふざけやがって。
「ヘヘッ、その様子じゃあ、まだ会ってねえみてえだな」
ギースは何が嬉しいのか、ヘラヘラと笑いながら何かを注文していた。
どうせ酒だろう。この男は炭鉱族のタルハンド以上に酒好きだった。
「パウロ。お前よ、明日冒険者ギルドに顔出せよ」
「なんでだよ」
「面白ぇ人物と会えるぜ」
面白い人物。
オレの不機嫌が直る相手と、ギースが今日顔を出した理由と、そして今日出会った人物。
三つを照らしあわせると、おのずと答えは出た。
「ルディか?」
聞くと、サル顔は口を尖らせ、ポリポリと頭を掻いた。
「なんでぇ、知ってたのか?」
「会ったんだよ」
「その割にゃあ、あんまり嬉しそうじゃねえな。喧嘩でもしたのか?」
喧嘩?
……まあ、喧嘩か。喧嘩にもなってなかったが。
くそっ、思い出したらまた疼いてきやがった。
「何があったんだよパウロ、話してみろよ」
ギースは、その人のよさそうな顔で、椅子をオレの隣に移動させてきた。
こいつは昔から、他人の悩みを聞くのが上手な奴だった。
今回も、おせっかいを焼いて、わざわざオレの愚痴を聞いてくれるらしい。
「ああ、聞いてくれよ……」
と、オレは先ほどあったことをギースに話した。
出会えて嬉しかったこと。
けれども、何か話が噛み合わず、ルーデウスに今までどうしていたのか聞いたこと。
すると、ルーデウスがあまりにも楽しそうに旅の話をし始めたこと。
くだらない自慢話を延々と聞かされたこと。
そんな自慢より、もっと別のことができただろうと指摘したこと。
逆ギレされたこと。
女のことを指摘されてカチンときたこと。
喧嘩してボロ負けしたこと。
「……あー……なるほどなぁ……」
ギースは、各所で相槌を打ちながら、うんうんと頷きながら同意してくれたり、納得してくれたりといった感じで聞いていたが、最後に言った。
「お前さ、息子に期待しすぎじゃねえのか?」
「…………あ?」
オレは自分でもマヌケな声を上げたと認識していた。
期待しすぎた?
なにを、誰に?
「オレが? ルディにか?」
「だってよ、よおっく、考えてみろよ」
戸惑うオレに、ギースはたたみかけるように言葉をつなげる。
「あいつは確かにすげえよ。無詠唱で魔術を使うヤツなんざ見たことがねえ。魔術師の身で北聖ガルスと対等に渡りあったのを見た日にゃ、そりゃ背筋が震えたさ。ルーデウスは、それこそ、百年に一人の天才ってヤツなんだろうよ」
そうだ。ルディは天才だ。
天才なのだ。
小さい頃からなんだってできる奴だった。
一時期はわりとダメなところもあるのかと思ったが、あのフィリップが娘をやってもいいとさえ言ったんだ。オレのことをあれだけこき下ろしたフィリップが、だ。
「おう、そうさ。あいつはスゲぇぜ。なんせ五歳の時には……」
「けど、まだガキだ」
ぴしゃりと遮られて、オレは黙った。
「ルーデウスは、まだ十一歳のガキだ」
ギースは噛み締めるように、もう一度言った。
「お前だって、家を出たのは十二歳の時なんだろ?」
「ああ……」
「十二歳未満はガキだって、お前、昔から言ってたもんな?」
「なんだよ、それがどうしたっていうんだよ」
ルディはもうオレより強いんだぞ。
確かに今日は酒が入っていたが、それを差し引いたって、アイツは強くなっていた。
酔っていたとはいえ、オレは本気だったんだ。本気で、使いたくもねえ北神流『四足の型』と、剣神流『無音の太刀』まで使ったんだ。それなのに、オレの剣はアイツのかぶっていたパンツのヒモを斬っただけだ。
ルディは全然本気じゃなかった。
それが証拠に、団員は全員、軽傷で済んでいた。手加減抜きで戦って、手加減されて負けたんだ。
会わなかった間にどれだけ強くなったかはわからねえ。
ただ、ルディは七歳の時にはもうオレよりずっと賢かった。
腕っ節がオレ以上に強くて。頭もオレ以上にいい。
なら、オレ以上のことができたっておかしくねえだろ。
歳がなんだってんだ。
「パウロ、お前、十一歳の頃は何してた?」
「何って……」
確か、家で剣術を習いつつ、毎日毎日、親父に叱られる毎日だった。
一挙手一投足、全てに文句を言われ、殴られた。
「その頃のお前に、魔大陸で生きていけつって、できたか?」
「ハッ、ギース、そりゃ前提がおかしいぜ。ルディはな、強い魔族に護衛についてもらったんだ。人間語も魔神語も、獣神語もできて、Aランクの魔物だって一人で倒しちまうっつー、化け物みたいな奴に護衛についてもらったんだ。オレじゃなくたって魔大陸縦断ぐらいできるさ」
「できねえな。お前はできねえ、絶対にできねえ。もし、今のお前で魔大陸に行っても一人じゃ帰ってこられねえ」
断言されて、オレは鼻白んだ。
ギースは相変わらず、ヘラヘラと笑ったままだ。
こいつの笑みは、相変わらず苛つく。
「ハッ! じゃあなおさらじゃねえか! オレにできねえことをやった。天才だ。ルディは天才だ! オレの息子は天才だ。もう立派に一人前だ。オレが何を言うこともねえ。能力のある奴に、能力に見合った仕事を期待するのは、間違っているか? ええギース、オレは間違っているか?」
「間違ってるね。お前はいつだって間違ってる」
ギースはヘラヘラと笑いながら、運ばれてきたビールを一気に飲んだ。
「ぷはっ、うめえ。やっぱ大森林じゃこういうのは飲めねえからな」
「ギース!」
「わかってるよ、うるせえな」
ギースはドンと木のコップを置いて、急に真面目な顔になった。
「パウロ。お前、魔大陸には行ったことねえんだろ?」
「……それがどうした」
オレは魔大陸に行ったことはない。
そりゃ、もちろん、人から聞いたことはある。
危険な土地だって噂だ。道を歩けば魔物が出て、魔物を食わなきゃ生きていけない。
だが、魔物が多いぐらいなら、どうにでもなる。
「知っての通り、俺は魔大陸の出身だ。で、その俺に言わせりゃあ、魔大陸ってのはヤバイ」
「そういや、お前から魔大陸の話を聞いたことはなかったな。どうヤベぇんだ?」
「まず、街道がねえ。道はあるが、ミリス大陸や中央大陸で言われてるような、魔物の数が少ない安全な道ってのは存在しねえ。どこを歩いていても、Cランク以上の魔物が襲い掛かってくる」
確かに魔物は多いと聞いていたが、Cランク?
中央大陸じゃ、森の奥にしか出てこないような相手だ。
群れるか、特殊な能力を持っている奴が多い。
「そりゃいくらなんでもフカしすぎだろ?」
「いや、本当のことだ。俺は今、一切嘘を言ってねえ。魔大陸ってのはそういう大陸だ。とにかく、魔物が多いんだ」
ギースの目は本気だったが、この男はこういう目をしながら、案外簡単に嘘をつく。
騙されるものか。
「そんな大陸で、優秀とはいえ実戦経験のない子供が放り出される」
「……おう」
実戦経験がないってのは、ルディのことか。
言われてみりゃあ、あいつが誰かと戦ったって話は聞いたことがねえ。
ただ、人攫いはうまいこと撃退したって聞いたし、距離さえ開ければギレーヌでも勝てないかもしれないって話は聞いた。
オレはギレーヌ以上の剣士を知らない。アイツが近づけないってんなら、適切な距離を置いたルディに勝てる奴は世界で千人もいない。
だから実戦経験がないなんてのは、関係ない話だ。
かの北神二世、アレックス=R=カールマンだって、初めての実戦で剣帝を斬り殺したって話だ。
「で、そこに助けてくれるって大人が現れる。魔族、それも強いヤツだ。スペルド族。知ってるよな。あのスペルド族だ」
「ああ」
スペルド族に関しては、正直、半信半疑だ。
魔大陸にだってスペルド族はもうほとんど残っちゃいねえって話だしな。
「右も左もわからない状態で手を差し伸べてくれる存在。弱っているところを助けてくれる存在。けど、スペルド族は怖い。なにせ断りゃあ何されるかわかんねえしな。そりゃ、その手を握っちまうだろ」
「……まあ、そうだろうな」
「で、助けてもらっているうちに、賢いルーデウスはこう思うわけだ。こいつの狙いは一体なんなんだ、ってな」
確かに。
ルーデウスなら、思うだろう。
オレじゃあ気づかないが、そういうことには敏い奴だ。
かつて、リーリャを助けた時も、子供とは思えないような敏さを見せた。
「でも、相手の目的なんざわかるわきゃねえ」
だろうな。
相手の狙いがわからないから、ギースみたいなヤツが生きていける。
「今は助けてもらっているが、いずれは切り捨てられるかもしれない……と、そこでルーデウスは考える。切り捨てられないように恩を売ろう、とな」
「なんだそりゃ? 恩? うまくいくのか?」
「茶化すなよ。恩って言い方があれなら、情に訴えるとか、仲間意識を芽生えさせるとか、そんな感じでいい」
仲間意識を芽生えさせるか。
なるほどな。
そうすると、ルディの行動も頷ける。
守ってくれるという魔族にゴマすって、いざという時のために自分の腕も磨いておく。
合理的だ。最も安全な道を選んでいると言える。
ふん、さすがだな、やるじゃないか。
「チッ、それだけ考えられるのに、なんでそれ以上のことができねえんだ」
ポツリと漏らすと、ギースは指を広げた。
それを一つずつ折っておく。
「初めての土地、初めての冒険、いくら賢いったって、知らねえことばかりだ。騙されないために、自分も学んでいかなきゃならねえ。その上で、いつ裏切るかわからねえ魔族相手に気を配り、すぐ後ろには守らなきゃいけない妹分……」
ギースは淡々とした口調で言いつつ、指を全て折った、
そして、最後にこう、締めくくった。
「これで転移した別の奴らまで探し出したってんなら、そりゃ超人だぜ、超人。『七大列強』に数えられていてもおかしくねえ」
七大列強か。懐かしい名前を聞いたな。
昔は、オレもそれだけ有名になりたいと思っていたっけか。
親の贔屓目抜きで見ても、ルディはそれになれる実力はあると思うがな。
「明らかにオーバーワークだ。ルーデウスがいくら天才といったところで、人間にゃ、限界がある。ましてや、あいつはまだ子供だ」
「限界ギリギリの奴が、なんであんな楽しげに冒険の話を語るんだ? ありゃ、どう見たって迷宮に遠足気分で入って浅いところで遊んで帰るお貴族様だぜ?」
ルディが、もし本当にきつかったというのなら、あんな言い方はしないはずだ。
旅の辛いところ、苦しいところを語るはずだ。だが、ルーデウスはそんなところは一切語らなかった。
「そりゃ、お前を心配させないためだろ」
「…………は?」
また間抜けな声が出た。
「なんでアイツが、オレの心配なんてしてんだ? ダメな親父だからか?」
「そうだ。お前がダメな親父だからだ」
「チッ、そうかよ。そうだろうな、オレはくっだらねえことで酒に逃げちまうような弱い男さ。天才様の目には、さぞ哀れに映ったんだろうな」
「別に天才じゃなくたって、今のお前は哀れに見えるぜ、パウロ」
ギースはため息をついた。
「自分の顔は自分じゃ見れねえだろうから言うけど、お前、今ひっでぇ顔してるぜ?」
「息子に同情されるような顔をか?」
「ああ。今のお前となら、喧嘩別れせずに済みそうだ」
哀れすぎて何も言えなくなっちまうからな、とギースは付け加えた。
オレは自分の顔に触れる。
何日も剃っていないひげがジャリっと音を立てた。
「なあパウロ、もう一度言わせてもらうぜ」
ギースは念を押すように、言った。
「お前は、息子に期待しすぎだ」
期待して、何がいけないんだと思う。
ルディは生まれた時からなんでもうまくやった。オレは父親面しようとして、それを引っ掻き回しただけだ。ルディには、オレは必要なかった。
「なあ、パウロよ。なんで素直に再会を喜ばねえんだ? いいじゃねえか。ルーデウスがどんな旅してきたって。能天気にのんびり旅してきたって。女とイチャコラ旅してたって。お互い元気で会えたんだ。まずはそれを喜べよ」
「…………」
そうだ。
オレだって、最初は喜んだはずだ。
「それとも、体のどっかを失って、目もうつろな息子に会いたかったのか? 死体になって再会って可能性も大いにあったんだぜ? ……いや、魔大陸なら死体も残らねえな」
ルディが、死ぬ?
あの元気なルディを見た後では、現実味のない話だ。
だが、ほんの数日前、オレはその想像をして、陰鬱としていたのではなかったのか?
「あーあー、かわいそうになー。すっげぇ苦労して旅してきて、せぇっかく父親と再会したってのに、その父親は酒浸りのクズなんだもんな。こりゃ、俺だったら縁を切るな」
チッ、芝居掛かった口調で喋りやがって。
「わかったギース。お前の言うことはもっともだ。けど、一つ、不思議なことがある」
「なんだ?」
「なんでルディは、ブエナ村の情報を知らなかったんだ? ザントポートにだって伝言は残したはずだ」
ギースは、「そりゃあ」と言いかけて、苦い顔をした。
これは、コイツが何かを隠している時の顔だ。
「運悪く、見つけらんなかったってことだろ」
「……ギース、お前はどこでルディを見つけたんだ? ザントポートで見つけたんじゃないのか?」
ギースがこの一年間どこにいたのか、俺にはわからない。
だが、ルーデウスは北から来た。
北でギースが活動できるようなでかい町といえば、ザントポートぐらいだ。
ザントポートには、きちんと伝言が残っている。
それにあそこには、団員が駐在しているはずだ。
魔大陸から誰かが渡ってきた時、その人物から情報を得るためだ。
冒険者なら、冒険者ギルドに寄らない理由はない。
「俺がルーデウスに会ったのは、ドルディア族の村だ。ビックリしたぜ、何せ、聖獣に襲いかかったって嫌疑を掛けられて、全裸で牢屋に入れられてたんだからな」
「獣族に全裸で牢屋って……マジかよ」
ギレーヌから聞いたことがある。
ドルディア族にとって、全裸にされる、檻に入れられる、鎖に繋がれる、冷水を掛けられる、といったことは、この上ない屈辱なのだ。他人に対しては滅多なことではやらないし、やられたら死ぬまで覚えている。
冗談でギレーヌに水を掛けた時、本気で睨まれた。
「そ、それで、どうなったんだ?」
「なんだ、ルーデウスから聞いてねえのか?」
「魔大陸を旅したって話しか聞いてねえんだよ」
そうだ、なんでザントポートで伝言を見なかったのか。
一番重要な部分は聞いていなかった。
なんでだ……ああ、オレが聞かなかったんだ。
ちくしょう。なんでオレってやつはいつもこう、短気なんだ。
落ち着け。ルディは優秀だ。優秀なのに、情報を得ていなかった。
そのことを、もっと冷静に考えるべきだ。
ザントポートまで行けば、嫌でも耳に入ったはずなんだ。
つまり、ザントポートで何らかの事件に巻き込まれたってことだ。
ドルディア族に捕まるような事件……大事件じゃないのか。
もう二、三日もすればザントポートにいる団員が情報を持って帰ってくるが、向こうの方で何か事件が起きたんじゃないのか?
「いや、俺も詳しいことは知らないんだけどよ、大森林のミルデット族んところにいた時にな、デドルディアの村に人族のガキが捕まったって噂を耳にしたのよ」
「ん? ちょっとまて、お前、今、どこにいたって?」
ミルデット族?
確か、獣族の一種だったはずだ。
ウサギみたいな耳を持つ種族だ。
「ミルデット族の村だ。族長がいるところだから、結構でかいんだが──」
ギースの説明は、長く、うっとうしかった。
正直、途中で「もういい」と言いたくなるような長さだ。
だが、さっきもルディの話を最後まで聞かず、重要な部分を知らずに終わったばかりだ。
同じ失敗ばかりしているオレでも、さすがに同じ日に二度も繰り返さねえ。
──話が終わった。
整理してみる。
「ギース、つまりお前は、大森林の各種族に、人族の迷い人がいたらミリシオンまで送ってくれって言って回ってたのか?」
「おう。ヘヘッ、感謝してもいいぜ」
「してもしきれねえよ……」
たまに、大森林の方からオレを頼ってくる難民がいると思ったが、そうか、そういうカラクリだったか……。
「ま、んな話はいいんだよ」
「……ああ」
後で詳しく聞かせてもらうが、今は置いておく。
「人族の子供ってことでピンときた俺は、早速ドルディアの村へと移動した。自慢じゃねえが、俺は顔が広い。ドルディアの村にだって何人も知り合いがいる。その知り合いの一人、懇意にしてる戦士の一人に頼んで、同じ牢屋に入れてもらうように仕組んでもらったのよ」
「ちょっとまて、なんでお前が入る必要がある?」
「いざとなったら、逃げ出すためよ。獣族の牢屋ってのは、外より中からの方が逃げ出しやすいからな」
ギースの脱獄の腕は俺も知っている。
イカサマで捕まっても、何気ない顔で出てくる男だ。
「で、な。捕まった人族の子供が、哀れに泣き叫んで絶望してるかと思ったら……ぷくく」
「なんだ、どうなってたんだ?」
「全裸で余裕こいて寝転んで『ようこそ。人生の終着点へ』だぜ? もう何を言い返していいのかわかんなかったっつーの!」
ギースはゲラゲラと笑った。
「笑い事じゃねえだろ」
「笑い事だね。俺は一目見てわかったもんよ。こいつはパウロの息子だってな」
それの何が面白いっていうんだ。
というより、それのどこに俺の息子と断定する部分があるんだ。
「昔のお前そっくりだぜ。初対面でもふてぶてしいところとか、無駄に偉っそうなところとか、獣族の女を口説こうとして、『発情の臭いがする』なんて見透かされてよ、それでも懲りずにエロい目で見てるところとかよ!」
ギースは何がツボに入ったのか、またゲラゲラと笑った。
昔のことをほじくられると背筋が痒くなる。
「ま、確信を持つまでには、もう少し時間掛かったけどよ」
ギースはそう言って、ビールを飲み干した。
「ま、そういうことだからよ。あいつが情報を知らねえのは、仕方ねえんだ。ザントポートには寄らなかったって話だしな」
「ん? まてよギース、お前、同じ牢屋に入ってたんだよな。じゃあ」
こいつが説明すれば。
「ま、ま、親子の間でわだかまりはあるかもしれねえが、ここは俺っちの顔を立てて、仲直りしといてくれや」
ギースは早口でそう言って、席を立った。
「おい、まてよ、まだ話は終わって……」
「あそうだ。言い忘れてたけどな、魔大陸にはエリナリーゼたちが向かったみたいだぜ。ザントポートで男を食いまくった長耳族の噂を聞いたから間違いねえ」
「エリナリーゼが?」
あいつは、一番俺のことを嫌っていると思っていたが……。
「ヘヘッ、なんだかんだ言って、あいつらもお前のこと、そんなには嫌いじゃねえんだよ」
最後にそう言い残して、ギースは酒場を出ていった。
もちろん、金は払っていない。あいつはそういう奴だ。
まあ、今日のところはいいだろう。
奢ってやる。
よし、これだけ飲んだら、俺も今日は寝るとしよう。
そんで、明日にでもルディと話し合うか……。
「もう飲むんじゃねえぞ。明日、素面で『夜明けの光亭』に行け、いいな」
と、ギースが戻ってきた。
「わぁってるよ!」
釘を刺されて、オレはため息をついて杯を置いた。
考えてみれば、最近のオレは飲みすぎていた。
なんでこんなものに逃げていたんだか。やるべきことは、まだまだ残ってるだろうに。
「あの……パウロ団長、お話、終わりましたか?」
などと思っていると、一人の女が申し訳なさそうに縮こまっていた。
酔った頭で彼女の顔をまじまじと見てみると、それが団員の一人、ヴェラであるとわかった。
「ヘッ、なんだよ、今日は随分とおとなしい格好じゃねえか」
「ええ、まあ……」
ヴェラは曖昧に頷くと、先ほどまでギースの座っていた席についた。
今日の彼女は、いつものような攻撃的かつ刺激的な格好はしていない。
どこにでもいるような、普通の地味な町娘の格好をしている。
「昼間の喧嘩、もしかして、私のせいなんじゃないかと思って」
「お前のせい? なんでよ」
「いや、その、私が、こんなだから……その、ご、ご子息が、勘違いされたんじゃないかな、って」
「関係ねえよ。どうせあいつは、お前のそのでっけぇ胸を見て、邪推したんだ」
ヴェラが普段から薄着をしているのは、理由がある。
昔は普通の冒険者だった彼女だが、あの転移で装備もなしにミリス大陸に飛ばされ、盗賊に捕まって慰み者になった。普通なら心を閉ざしてしまいそうな酷い目にあったが、彼女は凄まじい精神力でそれを乗り切った。
しかし、乗り切れなかった女もいる。
ヴェラの妹であるシェラがそうだ。
あの子は、男の視線を受けると、未だに震えが止まらなくなる。
そんなのは、団員以外にも何人かいる。
ヴェラはそんな子たちを男の視線から守るため、男の視線が自分に行くように、いつもあんな格好をしている。
また、似たような目にあって沈んでいる他の女のケア係としても優秀だ。
辱めを受けた女の気持ちがわからない俺にとって、なくてはならない部下の一人だ。
もちろん、肉体関係はない。
あるわけがない。
「わかったら行け」
「……はい」
ヴェラはしょんぼりしながら、女が集まっている席へと戻っていった。
「ったく……」
よくよく周りを見てみれば、オレのことを心配そうに見てる目の多いこと、多いこと。
「変な顔で見てんじゃねえよお前ら! 明日には仲直りするよ!」
俺は最後にそう言って、席を立った。
部屋に戻ると、そこにはノルンが一人で寝ていた。
オレはテーブルに置いてある水差しから、水を一杯、コップへと汲んだ。
ごくりと飲む。
ぬるま湯は、オレのドロドロになった胃袋にすとんと落ちた。
ゆっくりと酔いが醒めていく。昔から、オレは酔いにくい体質で、大量に飲めば泥酔できるが、長時間は残らない。
頭がゆっくりと醒めてくるのを自覚しつつ、毛布を抱きしめるように眠るノルンの頭をさらりと撫でた。
ノルンはかわいそうな子だと思う。
こんな父親の近くで言いたいこともあるだろうに、文句一ついわずに、健気に振る舞っている。
もしノルンが死ねば、オレは生きていられない。
「んうぅ……お父さん……」
ノルンが身動ぎをした。
起きてはいない。寝言だろう。
彼女は平凡な子だ。
ルディとは違う。オレが守ってやらないと……。
「……」
ふと、思った。
もしルディが平凡だったら、ルディもまた、ここで寝ていたのではなかろうか。
家庭教師には行かず、ずっと実家で過ごして、転移した時に、オレの裾でも掴んで、僕にもノルンを抱かせてよ、なんて言っていたかもしれない。
平凡なルディだ。平凡な十一歳のルディ。俺はそれを、守るべき対象として、こうやって……。
足が震えた。
ギースが「十一歳のガキだ」といった理由がようやく理解できた。
そうだ。平凡だろうが、天才だろうが、何が違う。
同じじゃないか。
もし、ノルンが天才だったら、オレは同じことを言ったのか?
ノルンに、何も知らず、ただ呑気に旅をしてきたノルンに、あんなことを言ったのか。
お前にはもっと期待していたなんて、言ったのか?
想像して、眠れなくなった。
横になる気がしなかった。
宿の外に出る。
火事用に溜めてある水瓶の水を、頭からかぶった。
酒場を出ていった時のルディの顔を思い出して、吐いた。
ルディにあんな顔をさせたのは誰だ。
桶に溜まった水には、馬鹿な男の顔が映っていた。
世界で一番、父親に似つかわしくない男の顔だった。
「ハッ、こりゃ、ダメかもしれねえな……」
オレだったら、こんな男とは縁を切るね。
★ ルーデウス視点 ★
翌朝。
俺はいささかスッキリした気分で朝食を取っていた。
場所は宿屋の隣にある酒場。
ミリシオンの食事はなかなかうまい。大森林からこっち、移動すればするほど食事がうまくなる。
今日の朝食は焼きたてのパンと、スッキリした味わいの透明なスープに生野菜のサラダ、そして分厚いベーコンだ。
昨晩はありつけなかったが、夕飯にはなんとデザートが付いているらしい。
最近流行りの、幼い魔術師の冒険者譚の詩に出てくるデザートで、若い冒険者に人気の甘いゼリーだそうだ。
楽しみにしておこう。
飯を食うというのは幸せなことだ。
腹が減ると、イライラしてくるからな。イライラすると食欲がなくなり、食欲がなくなると、腹が減る。
見事な悪循環だ。アンドロイドも不機嫌になろう。
「……いらっしゃい」
と、そんなことを考えて、食後にコーヒーのような飲み物を飲んでいると、酒場の店主がふと入り口に目を向けた。
ゲッソリと窶れた、青い顔をした男が立っていた。
俺はその顔を見た瞬間、あからさまにビクついた。
男はきょろきょろと店内を見渡し、俺を見つけた。
その途端、俺の心中に昨日の感情が浮かび上がり、何も言われていないのに、自然と目線を逸らした。
「……」
そんな俺の様子を見て、同席の二人は、すぐにこの人物が誰か察したらしい。
ルイジェルドが眉をひそめ、エリスが椅子を蹴って立ち上がる。
「誰よあんた」
こちらへと歩いてくる男。
その眼前に、エリスは立ちふさがった。
両腕を組んで、足を肩幅に開いて、アゴをくっと上にあげ、厳然とした態度で、頭二つは高い位置にある男の顔を睨みつけた。
「パウロ・グレイラット……そいつの父親だ」
「知ってるわ!」
俺がエリスの背中を見ていると、頭上から声が降ってきた。
苦笑するような声だった。
「なんだルディ、女の後ろなんかに隠れやがって、随分と色男じゃねえか」
その声音、その口調に、俺はちょっとだけ、ほっとした。
そうそう。昔のパウロは、こんな感じで俺をおちょくってきた。
懐かしい。
俺はこの態度を、パウロなりの歩み寄りだと考えることにした。朝一でわざわざ酒場までやってきてくれたのだ。俺にだって、話をする余裕ぐらいはある。
「ルーデウスが私に隠れてるんじゃないわ! 私がルーデウスを隠しているのよ! ダメな父親からね!」
エリスはブルブルと拳を握りしめ、今にもパウロの顎に向かって拳を振るいそうだった。
俺はルイジェルドに目線で合図をする。
すると、彼は察してくれたのか、エリスの首根っこを掴んで持ち上げた。
「ちょっ! ルイジェルド! 離しなさいよ!」
「二人にさせてやれ」
「あなたも昨日のルーデウスは見たでしょ! あんなの父親じゃない!」
「そう言ってやるな。父親なんてあんなものだ」
なんてことを言いながら、この場から立ち去ろうとする。
と、ルイジェルドはパウロの横を通り過ぎる時、ぽつりと言った。
「お前にも言い分はあるだろうが、その言い分が通るのは、息子が生きている時だけだ」
「お、おう……」
ルイジェルドの言葉は重い。
彼は、自分のことを世界一ダメな父親だと考えていそうだしな。
同じくダメな父親に、シンパシーでも感じているのかもしれない。
「ルディ、年上をアゴで指図すんなよ」
「違いますよ。顎じゃないです。信頼のアイコンタクトです」
「似たようなもんだろうが」
パウロはそう言いつつ、俺の前へと座った。
「あれが、昨日言ってた魔族か……?」
「はい、スペルド族のルイジェルドさんです」
「スペルド族ねぇ。随分と気の良さそうな奴じゃないか。噂と実物は違うってことか」
「怖がったりしないんですか?」
「馬鹿言え、息子の恩人だぞ」
昨日の意見とは随分と違うようだが……余計なことは言うまい。
さて、と。
「それで、何をしにきたんですか?」
思った以上に、硬い声が出た。
すると、パウロはびくりと身を震わせた。
「いや……その、謝ろうと、思ってな」
「何をですか?」
「昨日のことだよ」
「謝る必要はありませんよ」
謝ってもらえるのは好都合だが、俺だって、エリスの胸枕で一晩ぐっすり寝て、きちんと反省したのだ。
「ハッキリ言って、僕はこれまで遊び気分でした」
最初はともかく、旅は概ね順調で、エロいことに気を取られるぐらいには余裕があった。
フィットア領についての情報収集をしなかったのは、間違いなく俺の落ち度だ。
ザントポートでは無理だったが、ウェンポートでは多少の時間があった。
そこで情報屋にでも接触を取れば、何らかの情報は得られたはずだ。
聞いて、調べて当然のことを調べていなかった。
俺のミスだ。
「ですので、父様が怒るのも仕方ありません。この大変な時期に、僕の方こそ、すいませんでした」
フィットア領が消滅して、一家がバラバラになった。
その時のパウロの心境を思えば、責めることはできない。
俺は知らなかったおかげで、能天気でいられた。悲劇を知らないのは、幸せなことだったのだ。
「いや、そんなことはないだろう。ルディだって一生懸命だったんだろ」
「いえいえ、全然。余裕でしたよ」
ルイジェルドがいてくれたからな。
リカリスの町を出た後は、比較的楽だった。
魔物に奇襲を受けることもないし、黙っていてもご飯を捕まえてきてくれるし、エリスの喧嘩は止めてくれるし、俺としては楽な旅だった。
イージーオペレーションだ。
「そっか、余裕か……」
パウロが何を考えているのか、俺にはわからない。
ただ一つ言えるのは、その声が少しばかり、震えているということだ。
「伝言とやらを見つけられなかったのは、申し訳なかったと思っています。何が書いてあったんですか?」
「……オレのことはいいから、中央大陸の北部を探せって」
「そうですか。では、エリスをフィットア領まで送り届けたら、北部を探すことにしましょう」
俺は機械的にそう答えた。
どうにも、自分の言葉が硬いように感じる。
緊張しているのだろうか。
なぜだろうか。
俺はパウロを許したし、パウロだって俺を許した。昔通りとはいかないが、今は緊急事態。緊急事態だから緊張する。
当然か。
「それはそれとして、フィットア領の現状について、もう一度、詳しく聞かせてください」
「…………ああ」
パウロの声音も硬く、震えたままだ。
彼も緊張しているのだろうか。
いや、それ以前に俺自身も、やっぱり何かがおかしい。
いつも通りに振る舞えない。前は、パウロとどうやって話していたっけか。軽口を叩き合うような間柄だったはずなんだが。
「まず何から話すか……」
パウロは硬い声で、フィットア領で何が起こったのかを話してくれた。
建物がすべて消滅していたこと。
そこに暮らしていた人々がすべて転移したこと。
死者も大勢確認されているということ。
まだまだ行方不明者が多数だということ。
パウロは有志を募り、捜索隊を組織したこと。
そのため、冒険者ギルドの本部があり、情報が集まりやすいミリシオンに拠点を置いたこと。
ちなみに、もう一つの拠点はアスラ王国の首都にあり、そこはあの執事アルフォンスさんが担当している。アルフォンスさんはこの捜索団の総責任者であり、現在もフィットア領で難民の救助をしているらしい。
そして、パウロは各地に伝言を残した。
俺に、手分けして家族を探すように指示を出していたのだ。
一人前に独り立ちしている、長男の義務として。
年齢的にはまだまだ子供であるはずだが、俺も精神的には大人なつもりだ。もしその伝言を見れば、奮起したことだろう。
ゼニスとリーリャ、アイシャは見つかっていない。
もしかすると、魔大陸のどこかですれ違ったかもしれない。
そう思えば、俺の行動は悔やまれる。旅を急ぐあまり、一つの町への滞在を短くしすぎたのだ。
「ノルンは無事だったんですね?」
「ああ、運よく俺と接触していてな」
パウロ曰く、転移というのは体のどこかが接触していれば、一緒に飛ばされるらしい。
「ノルンは元気にしていますか?」
「ああ、最初は知らない土地でちょっと戸惑ってたみたいだけどな、今じゃ団員のアイドルみたいになってるよ」
「そうですか、それはよかった」
そうか、ノルンは元気か。
うん、実にイイことだ。まさに不幸中の幸い。喜ばしいことといえる。
けど、なぜか、俺の心は晴れない。
「……」
「…………」
会話が途切れた。
妙に間が悪い。
俺とパウロの関係ってのは、こんなじゃなかったはずだ。もっとこう、軽い感じの関係だったはずだ。おかしいな。
それからしばらく。
パウロは何かを言っていたが、俺はそれにうまく返すことができなかった。
気のない、硬い返事を繰り返すばかりだった。
いつしか客は俺たち以外にいなくなっていた。
そろそろ、仕込みを始めるから出ていってくれないかと言われそうだ。
パウロもその気配は察知したらしい。
「ルディ、お前はこれからどうするんだ?」
最後に、そう聞かれた。
「……とりあえず、エリスをフィットア領に送ります」
「だが、フィットア領には何もないぞ?」
「でも、帰ります」
帰らなければならない。
フィリップも、サウロスも、ギレーヌも、誰も見つかっていないらしい。
帰っても誰もいないだろうが、戻らなければならない。
それが旅の目的だからだ。
初志貫徹。まずはフィットア領にたどり着き、その現状をこの目で確認するのだ。そこから、中央大陸北部に移動して捜索するもよし、ルイジェルドあたりに頼み込んで魔大陸に戻り、各地を捜索するもよしだ。
一応言語がわかるからベガリット大陸に行くのもいいかもしれない。
「その後、他の場所を探します」
「……そうか」
こうして会話はすぐに途切れた。
何を言うべきかわからない。
「ほれ」
と、その時、酒場のマスターが俺たちの前にコップを置いた。
コトリと置かれた木のコップから湯気がたっている。
「サービスだ」
「ありがとうございます」
気づけば、喉がカラカラに乾いていた。
手はギュっと握られており、手のひらには汗がベットリとついていた。
同時に、背中や脇下がやけに冷たいことに気づく。前髪が額に張り付いている。
「なあ坊主。詳しいことはわかんねえが……」
「……?」
「顔ぐらい見てやれよ」
言われて、初めて気づいた。
俺は、パウロの顔を、一度も見ていなかった。
最初に目を逸らしてから、一度も、パウロの顔を見ることができなかったのだ。
ごくりと唾を飲み、父親の顔を見る。
不安そうな顔だった。今にも泣きそうな、ひどい顔だった。
「なんですか、その顔は」
「なんだって、なんだよ」
苦笑するパウロの顔には、元気がない。
表情も相まって、こけた頬のせいで別人に見える。
だが、同じような顔を、どこかで見たような気が。どこだったか。昔だな──。
────思い出した。
自宅の洗面所だ。
イジメられて引きこもってから、一年か二年。
まだ間に合うと思いつつも、しかし、周囲とは決して埋まらない差ができたと自覚しだした頃。
でも外に出るのは怖くて、焦りと不安ばかりが募った、一番、情緒不安定だった頃だったはずだ。
なるほどそういうことか。
パウロは今、情緒不安定なのだ。
探し人が見つからなくて、いつまで経っても音沙汰がなくて、心配して、心配して、もしかして怪我をしてるんじゃないかとか。もしかして病気になってるんじゃないかとか。それともあるいは、もうとっくに……と考えて、心配して、心配して……。ようやく現れた俺が、あまりにも想像と違ってあっさりしていたから、ついイライラしてしまったのだ。
俺にだって覚えはある。
あれは引きこもり始めてすぐの頃だ。
中学時代の知り合いが訪ねてきて、学校でのことをいくつか話してくれた。
自分がこんなに落ち込んでいるのに、こんなに荒れているのに、相手があまりにも能天気に学校生活のことを語って、俺は胃が痛くなってそいつにキツイ言葉を吐いて、八つ当たりしたのだ。
その翌日、もしあいつが次に来たら謝ろうと思った。
けれど、そいつは来なかった。自分から出向くことはしなかった。変なプライドがあった。
思い出した。この顔は、あの時の顔だ。
「提案があります」
「ルディ?」
「こんな状況です、僕らは大人にならなきゃいけません」
「ああ、まあ、確かにオレは大人げないとは思うが……何が言いたいんだ?」
心の中がスッと晴れた。
ようやく、パウロの気持ちを理解できた。
そう思えば、あとは簡単だった。
昔を思い出す。パウロに叱られて、強い口調で言い返した時の話だ。
当時は、仕方がない奴だと思った。
二十四歳で、父親としては若いから、仕方がないと思った。
あれから六年。パウロは三十歳になった。
生前の俺より、まだまだ年下だ。
そして、生前の俺に比べれば、立派なもんだ。
俺はやることもやらず、相手を責めることばかり考えていた。それに比べりゃ立派なもんだ。
俺はあの頃とは違う。
そう誓ったはずだ。
最近は忘れていたが、同じ過ちを繰り返さないと。
この世界では本気で生きると、誓ったはずだ。
今回は、規模こそ大きくなったが、同じことをしている。
六年前と、同じことをしている。
俺たちは同じ失敗を繰り返している。成長したつもりになって、前に進んだつもりになって、ずっと同じ場所で足踏みしていたのだ。それに関しては、素直に反省しよう。
そして、反省した上で、先に進もう。
「昨日のことはなかったことにしましょう」
俺は、そう提案した。
今回、俺は、傷ついた。心がポッキリと折れそうになった。
きっと、当時、俺を心配してくれた友人も、そんな気持ちだったのだろう。
そして、そんな気持ちのまま、二度と会わなかったのだ。
今回はそうはならない。俺はパウロとのつながりを、決して断ちはしない。
「昨日、僕らは喧嘩なんかしなかった。今、この瞬間、数年ぶりに再会した父と子……。そういうことにしましょう」
「ルディ? 何言ってるんだ?」
「いいから、ほら、両手を広げて、さぁ」
「お、おう?」
言われるがまま両手を広げるパウロ。
俺はその胸に、飛び込んだ。
「父様! 会いたかった!」
むわりと酒臭さが漂う。
今は素面のようだが、二日酔いなのかもしれない。
ていうか、昔は酒なんて一滴も飲まなかったよな……。
「る、ルディ?」
パウロは戸惑っている。
俺はパウロの肩に顎を載せて、ゆっくりと言う。
「ほら、久々に再会した息子へ、一言あるでしょう」
とんだ茶番だと思いながら、もう一度パウロのゴツい体を力一杯抱きしめた。
顔は痩け、身体も一回り小さくなったような気がする。
俺の身体が大きくなったのもあるだろうが、パウロも苦労したのだ、俺以上に。
パウロは戸惑いつつも、ポツリと漏らした。
「お、オレも会いたかった……」
一言いうと、何かが決壊したらしい。
「オレも会いたかった……会いたかったんだよ、ルディ……。ずっと、誰も、見つからなくて、死んでるんじゃないかって、思って……お前が、お前の姿、見て……」
見上げると、パウロは涙を流していた。
顔をくしゃくしゃに歪めて。
大の男がみっともなく、しゃくりあげながら、泣いていた。
「ごめん、ごめんな、ルディ……」
なんだか俺も泣けてきた。
俺はパウロの頭をぽんぽんと叩き、しばらく二人で泣いた。
こうして、俺は約五年ぶりに父親と再会することができたのだ。
第五話 「方針の再確認」
その日、丸一日パウロと話をした。
大したことを話したわけではない。他愛ない話だ。
まず、ブエナ村での出来事だ。
俺が城塞都市ロアへと赴いてからの数年間、パウロは二人の奥さんに囲まれながら、しかし酒池肉林とはいかなかったらしい。
ゼニスとリーリャの間では何度も話し合いが行われ、基本的にリーリャとの性的な接触はなし。
ただしゼニスが三人目を妊娠して、どうしても我慢できなくなった場合は許可を求めることという流れになったらしい。
ゼニスにも葛藤があったようだが、パウロにとっては都合のいい結末である。
羨ましいね。
「それで、三人目の妹は生まれそうなんですか?」
「いや、それがなかなかな……。お前の時は一発だったんだが」
「一発でこんな優秀な息子が生まれるとは、父様も運がいい」
「言ってろよ」
十一歳の息子と父親の会話じゃないなと思いつつ、しかし心地良さを感じていた。
ゼニスやリーリャの生死には触れないのは、意図的なものだ。
お互いわかっているのだ。生死のことを話題にしても、決して楽しいことにはならず、やるせない気持ちだけが残るということが。
「シルフィは元気でやっていたんですか?」
「ああ、あの子はすごい。お前に教師としての才能を感じたよ」
シルフィは元気でやっていたらしい。
午前は走りこみと魔力の鍛錬をして、午後はゼニスの所で治癒魔術を習う。
アイシャがある程度大きくなってからは、リーリャに行儀作法などを習っていたそうだ。
「ひたむきって言うんだろうな。よくウチにきて、ルディの部屋で何かやってたよ」
「……シルフィは、そこで何かを見つけたりとかしていませんよね?」
「なんだ? 何か見られて困るもんでも隠してたのか?」
「いえ、まさか、そんなはずあるわけないじゃないですか」
やだなもう。
「ま、みんな消えちまったみたいだがな」
パウロの話によると、フィットア領にあった物体は、そのほとんどが消滅してしまったらしい。
羽ペンやインク壺といった小さなものから、家や橋といった建築物に至るまで全てが消えてしまったらしい。で、唯一身につけていたものだけ、一緒に転移した、と。
「そうですか」
それは残念だ。
何が残念なのかさっぱり思い出せないが、心の中には言い得ぬ寂寥感がある。
「お前はどうしてたんだ?」
「ロアでのことですか?」
聞かれ、俺も話した。
初日にエリスにぶん殴られて心が折れそうになったこと、偶然人攫いに連れ去られて、なんとか脱出したこと、そのことをキッカケに、エリスと少し仲良くなれたこと、でも授業は聞いてくれなかったこと、ギレーヌに泣きついたこと、彼女のおかげでエリスが授業を聞いてくれるようになったこと、そこから少しずつ仲良くなったこと。一緒にダンスを習ったこと。そして、十歳の誕生日のこと。
「誕生日か、悪かったな……」
「何がですか?」
「顔も見せてやれなかった」
アスラ王国民にとって、節目歳である十歳は極めて重要な歳である。
どうして重要なのかは未だわかっていないが、縁起物なのだろう。
盛大にお祝いをするし、プレゼントも渡す。
「それは構いません。エリスの家族にしっかりお祝いしてもらいましたから」
「そうか、何をもらったんだ?」
「高価な杖です。『傲慢なる水竜王』なんていう、ちょっとこっ恥ずかしい名前なんですが」
「そうか? カッコイイじゃないか」
カッコイイ?
なにを馬鹿な、背中が痒くなるような名前じゃないか。
でも、この世界では凄い性能のものにほど、大仰な名前をつけるのかもしれない。
「それと、アルフォンスから聞いたぜ、ルディ。もう一つ、いいものをもらったらしいじゃねえか」
「いいものですか?」
はて、何をもらったのだろうか。
知恵と勇気と無限のパワーだろうか。どれもまだまだ足りないと思うが。
「ほら、フィリップんところのお嬢さんだよ。さっき初めて見たが、健気で可愛らしい子じゃないか。お前のことを必死に守ろうとしてよ……」
……もらったと、言われると少し違う気がする。
いや、確かにフィリップから「よし」と許可されたが、「いただきます」には至っていない。
彼女は大事にしたい。
昨日のこともある。落ち込んでいる時に誰かに優しく抱きしめられ、眠るまで頭を撫でてもらったのは初めてだ。
エリスのことは絶対に裏切れない。
俺が十五歳になったら、という約束もあるが、たとえ十五歳になったとしても、彼女が嫌がるうちは我慢できる。
性欲に関してはやや暴走しがちな俺だ。四年後、恐らく今より強い性欲を保持した状態で耐え切れるかどうかわからないが…少なくとも、今はそう決意している。
「エリスは大切な存在だと思っています。が、しかし、もらった、なんてモノみたいな言い方は好きになれませんね」
「まあ入り婿だもんな。もらうってより、もらわれるってほうが正しいか」
「はえ?」
変な声が出た。
婿?
「お前、フィリップに後ろ盾についてもらって貴族になるんだろ?」
「なんですかそれは、いつそういう話になったんですか?」
「いつも何も、転移の一年ぐらい前からだよ。お前とエリスがいい仲で、お前自身の気持ちも固まりつつあるから、婿に迎えたいって手紙がきてたぞ。オレはアスラ貴族なんて糞みたいなものだと思っているが、お前が決めたことなら好きにしろと返しておいたんだが……」
なるほど。つまり、フィリップは十歳の時には、すでにパウロへの根回しを終えていたのだ。
もし、あそこで断ったとしても、それから数年の間に、あの手この手で俺とエリスをくっつけようとしたに違いない。何が酒の席での話だ。
となれば、パウロが俺とエリスの仲を邪推したのも頷ける。
結婚の約束をした二人、不安でたまらない二人。互いに好き同士となれば、旅の途中でイチャイチャしていたと思われても仕方がない。
「その様子だと、フィリップにハメられたようだな」
「そのようですね」
二人してため息をついた。
今、俺とパウロの脳裏には、同じ男の顔が浮かんでいることだろう。
フィリップ。アスラ王国の上級貴族としてドロドロした社交界を乗りきれる力を持った男の顔だ。
「で、お嬢様とはそこそこの仲として、シルフィのことは……あ、いや、なんでもない。忘れてくれ」
パウロは失言だったと言わんばかりに言葉を濁した。
シルフィは、まだ見つかっていない。少なくとも、パウロの知る範囲では、だ。
なんでもないと言われたが、考える。
シルフィは好きだが、エリスに感じている感情とは少し違う。
シルフィはどちらかというと、妹や娘のような感覚が強い。イジメられて、可哀想で、俺が育ててやらなくちゃ、という感じだ。それ以上の感情になる手前で別れてしまったというのもある。
エリスも似たような感じだが、彼女には助けられている部分も多い。
どちらに軍配が上がるか、と言われればエリスに上がる。
もっとも、それは二人を総合的に見て判断しているわけではない。
年月の問題だ。
やはり、長いこと一緒にいるというのは大きい。幼馴染という存在は様々な話に出てくるが、長い時間を一緒に過ごした、というのはそれだけ強力なのだ。
シルフィよりも、エリスと二倍近く一緒に過ごしている。
内容も濃い。
とはいえ、それと行方不明のシルフィの心配をしないというのは、別の話だ。
「シルフィ、無事だといいですが……」
「お前ほどじゃないが、あの子も頑張っていた。なに、無詠唱で治癒魔術まで使えるんだ。どこでだって生きていけるさ。治癒術師ってのは、ミリス大陸以外じゃ結構貴重なんだ」
「そうですか……」
あれ、今ちょっと、聞き捨てならない話を聞いたような。
「ちょっと待ってください。シルフィは、無詠唱で治癒魔術を使えるんですか?」
「ん? ああ、ゼニスが驚いていたな。でも、ルディだって使えるだろ?」
「治癒魔術は使えませんよ」
俺は治癒魔術を詠唱なしでは使えない。原理を理解していないからだ。
魔術で傷を治すメカニズムは、何度使っても解明できない。
「そうなのか?」
「ええ、詠唱すれば使えるんですが……」
「まあ、オレも魔術に関してはそう詳しくないが、魔術には相性があるっていうしな。シルフィにはそっちの才能があったんじゃないのか?」
もしかすると、シルフィはしばらく見ないうちに、俺なんかよりもずっと強くなっているのではないだろうか。
会うのが少し怖いな。
再会して「ルディ、全然成長してないね」なんて言われたらどうしよう……。
なんて話をしているうちに、俺とパウロの間にあった溝は完全に消えていた。
夕方、パウロに迎えが来た。
例のビキニアーマーのお姉さんと、治癒術師のお姉さんだ。
今日のビキニお姉さんはビキニではなく、地味な町娘のような格好をしていた。
昨日の格好は何だったんだろうか。
まあ、喧嘩の原因の一つでもあるから、自重してくれたのかもしれない。
「父様」
「なんだ?」
「もちろん僕は父様を信じているのですが、昨日の一件もあり、一応のことながら改めて聞いておきます。浮気はしてないんですよね?」
「してねえよ」
なら安心だ。
俺とパウロの昨日の口論は、邪推と邪推のぶつかり合い。
事実関係はなく、互いの女癖の悪さを指摘されただけの結果……っと、なかったことにしたんだったか、失敗失敗。
まあ、パウロも女なんかに構っている暇はないという感じだ。
家庭崩壊の引き金に指が掛かることもない。
俺もそれを見習って、これからは少しエロを抑えていくとしよう。
「ルディ」
パウロは最後に、俺の意志を確かめるように聞いてきた。
「お前はエリスを護衛して、フィットア領に行くんだったな?」
「はい」
俺はその言葉に強く頷きつつ、聞き返す。
「それとも、僕も捜索団に参加したほうがいいですか?」
「いや、その必要はない。どの道、ボレアスの血縁はアスラ王国に送り届けなきゃいけないからな」
「……そう聞くと重要任務に聞こえますが、僕にまかせてもいいんですか?」
「お前以上の適任はいないだろう。信頼関係もあるしな」
随分と信頼されているらしい。
ふと思ったが、パウロは俺を過大評価しすぎではないだろうか。
いや、どんな評価をされようと、期待には応えたい。
「もっとも、別に、団員から何人か護衛を出して、お前はミリシオンに残ってもいいんだぞ?」
パウロがニヤリと笑いつつ、何か甘いことを口走った。
損得だけで考えるなら、それでもいい。
もちろん、ミリシオンに残るのではなく、エリスと別れ個別に捜索をする、という意味だ。
今から魔大陸に戻って捜索するというのも一つの手ではあるが、あくまでそれは損得だけで考えた場合だ。
エリスを置き去りにして、自分を優先するわけにはいかない。
俺は彼女を守らなければいけない。
それに、何かを放置して他の何かに着手するということに、あまりいい記憶はない。
生前、全てを中途半端に終わらせてきた俺だ。両方が中途半端な結果に終わるに違いない。
今回の場合なら、エリスはフィットア領にたどり着けず、俺は魔大陸で何の成果も上げられないまま終わる。
なら、片方ずつだ。
ルイジェルドのこともあるしな。
あの堅物が、捜索団の団員と仲良くできるとは思えないし、途中で抜けるなんて言ったら戦士としてあるまじき行いだと怒られそうだ。
「いえ、やはり僕が送ったほうがいいでしょう」
「ま、うちの団にはお前より強い奴はいないし、お前としても任せられないだろうな」
そう言いつつ、パウロは複雑そうな顔をしている。
もしかすると、俺に喧嘩で負けたことを気にしているのかもしれない。
酒を飲んでいたし、ノーカンだと思うが、ここで変に慰めても立場がないだろう。
ここは触れないでおいてやるのが吉だ。
「ミリシオンからはどれぐらいで発つんだ?」
「そうですね、旅費を貯めたいので、一ヶ月ぐらいですかね」
「旅費なら出すぞ」
パウロは女二人へと振り返り、ローブを着た治癒術師のお姉ちゃん、ソバカスの残るおとなしめな感じの子に、声を掛ける。
「あったよな?」
「ボレアス家の面々が見つかった時のためにと、アルフォンス様から預かった資金がございます」
アルフォンスは、ミリスで誰かが見つかった時のため、何不自由なく移動できるだけの金を、パウロに持たせていたらしい。
「というわけだ」
「なるほど、そんな金が酒代に消えなくてよかった」
「資金はシェラが管理してるからな」
自慢げに言う、我が父親の情けなさ……いや、言うまい。
「それで、いくらぐらいになるんですか?」
「王札二〇枚相当となります」
シェラに聞くと、即答された。
王札は、ミリスで一番高い貨幣だ。石銭=一円として換算すると、一枚五万。
それが二〇枚ってことはつまり、
「ひゃくまんえん!」
「……どういうリアクションだそりゃ」
呆れ顔のパウロ。
俺は金に目が眩んでいた。
なにせ、この一年半。守銭奴のように金のことばかり考えてきた俺だ。そんな俺に、いきなり一〇〇万円である。
「そんな大金……一生遊んで暮らせるじゃないですか!」
「まあ、南部なら家ぐらいは建つと思うが、一生は遊んでは暮らせねえよ」
えー、だって一〇〇万ですよ。ヒャックマンですよ。
緑鉱銭にして一〇〇〇枚だぜ! スペルド族だって船に乗れちまう!
と、喜んだところで、もう一つの問題を思い出す。
「あ、もう一つ問題がありました」
「まだあるのか?」
「はい。ウェンポートではスペルド族が海を渡るのに、莫大な渡航費用が要求されました。ウェストポートではいくら掛かるかわかりませんが、やはり大金を要求されそうです。王札二〇枚で足りるかどうか……」
「そのことか……」
パウロは腕を組んだ。
まさか、ルイジェルドを置いていけ、なんて言うんじゃなかろうな。
「シェラ。スペルド族が海を渡るのに必要な金はいくらだ?」
唐突にパウロは尋ねると、シェラは「はい」と頷き、
「王札一〇〇枚です」
と、答えた。
全て暗記しているのだろうか。先ほどのこともそうだし、彼女は優秀そうだ。見た目からして秘書って感じだしな。
「……っ!」
と、目が合うと、彼女は小さく悲鳴を上げてうつむいてしまった。
元ビキニの人が、さりげない感じで俺の視線を遮るように立ち位置を変えた。
ちょっとショック。
「ごめんなさい、この子、ちょっと視線が苦手なのよ。あまり見ないであげて」
「はあ……」
元ビキニの人に言われ、俺は曖昧な言葉を返す。
パウロとの仲は元通りになったけど、他の団員には嫌われたままだったか。
まあ、それはいいや。
しかし、王札一〇〇枚か。約五〇〇万円といったところだ。
簡単に貯まる金額ではない。
ため息が出る。
「なんでスペルド族だけ、そんなに高いんでしょうね」
「その法律が制定された頃は、スペルド族の迫害が最も苛烈な時期だったからです」
と、元ビキニの後ろから、シェラが当然と言わんばかりに答えた。ウェンポートの関所の人でも知らないことを、あっさりと。おっぱいはちっぱいけど、脳みそはいっぱいか。
「しかも、あそこの税関の貴族は、魔族嫌いで有名だ。金を積んでも、なんだかんだで通してくれないかもしれん」
「そうですか……ええっと、母様の実家の力でも、どうにかなりませんか?」
「すまんが、今回のことであの家もギリギリの橋を渡っている。これ以上は迷惑を掛けられん」
となると、また密航か。
密航には嫌な思い出があるし、なるべくなら頼りたくない。
大体、同じ大陸での出来事だ。密輸組織同士のつながりで、俺たちがブラックリストに載っている可能性だってありうる。
スペルド族と渡航費用、考えれば考えるほど頭が痛くなりそうだ。
「わかりました。渡航費用については、自分で対策を練ります」
「すまんな」
そう言うと、パウロはニヤリと笑った。
そして、背後に控える女二人に、ドヤ顔で振り返った。
「どうよ、オレの息子は? 頼もしいもんだろ?」
「はあ」
「えっと……」
女二人は苦笑して顔を見合わせた。
どうもこうも、その息子とみっともなく喧嘩してたのは誰だ。
「父様。淑女に息子の具合を聞くなんて下品なことはやめてください。グレイラット家の品性が疑われます」
「お前の発言の方がよっぽど下品だよ」
そう言って、俺たちは笑いあった。
女二人はドン引きしていたが、構うことはない。
「さてと、ルディ、オレはそろそろ行くぜ」
「はい」
パウロは立ち上がり、コキコキと肩を鳴らした。
随分と長い時間、喋っていたようだ。
カウンターを見ると、マスターの苦笑する顔が見えた。ランチタイムもずっと居座っていたからな。ちょっと多めに支払っておこう。
「旅の予定が決まったら連絡をくれ。出発する前に、ノルンと一緒に飯でも食おう」
「ええ、わかりました」
そう言って、俺はパウロを見送った。
二人の女を引き連れて酒場を出ていこうとするパウロの背中を「こうして見ると、本当に女好きのダメ親父だなぁ」なんて思いながら。
★ ★ ★
パウロがいなくなってしばらくして、エリスとルイジェルドが戻ってきた。
エリスは目の辺りに大きな痣を作り、ルイジェルドが難しそうな顔をしていた。
「どうしたんですか、二人とも」
「なんでもないわ。それで、あの男とはどうなったの?」
エリスがさも不機嫌ですと言わんばかりに、腕を組んでフンと鼻息。
「仲直りしました」
すると、エリスの眦がみるみるうちにつり上がった。
「なんでよ!」
握りしめた拳を、ドンとテーブルに叩きつけると、パガンとでかい音がしてテーブルが砕けた。
んまあ、パワフルだこと……。
「そうか。仲直りできたか」
対するルイジェルドが嬉しそうだ。
「ルーデウス!」
エリスは俺の両肩を掴んで、ギリギリと締め付けてきた。
凄まじい力である。
「なんでよっ!」
「なんでって、何がですか」
若干戸惑いつつも、俺はそう聞く。
「昨日、あんなに落ち込んでたじゃない!」
「ええ、昨日は助かりました。エリスが抱きしめてくれたおかげで、僕もかなり落ち着くことができました」
今日、パウロの顔を見ることができたのは、紛れもなくエリスのおかげだ。
もし、あの抱擁がなければ、俺はしばらく宿の一室に閉じこもっていたかもしれない。
「そうじゃない! あの男は、ルーデウスの十歳の誕生日にも来なかったのよ! それで、魔大陸で、あんなに大変な旅をして! 大森林では、牢屋になんか入って! それで、やっと、やっと会えたのに! あんな風になるようなことをしたのよ! 突き放すようなことを言ったのよ!? なんで許せるのよ!」
一気にまくし立てるエリス。
彼女の言い分もわかる。
確かにそう言われると、パウロは最低だ。
俺のことを嫌っているのだと断言されても信じられる。
俺が普通の子供であれば、パウロを決して許してはいけないだろう。
が、パウロが俺に対して失敗するのは仕方がないことだ。
俺は生前の記憶を引き継ぎ、うまいことやってきた。そんな歪な息子に対して、普通の対応をしろってのが無理というものだ。パウロは俺との距離を測りかねているし、俺の扱いについて迷ってもいる。それに、俺が言うのもなんだが、正しい父親っていうのがどういうものか、イマイチわかっていない部分もある。
それが悪いこととは思わない。
俺としては、息子という立場を持って、上から目線で見守ってやるだけだ。
パウロは俺でいくらでも失敗すればいいのだ。
俺の心はもう折れない。いくらでも受け止めてやる。
もっとも、すぐに別れることになるわけだがね。
「エリス」
「なによ……」
なんというべきか、迷った。
エリスは俺のために怒っている。
しかし、俺としては、もう解決したことなのだ。
「父様も一人の人間です。失敗ぐらいしますよ」
俺はそう言って、エリスの目の痣にヒーリングを施した。
エリスはヒーリングをおとなしく受け入れたが、その表情を見ると、納得していないことがありありとわかった。治療が終わると、むっとした顔のまま宿屋の自室へと戻っていった。
それを目で追いつつ、俺はルイジェルドに問いかける。
「で、ルイジェルドさん」
「なんだ?」
「なんですか、あの痣は」
エリスの目の痣。あんなもの、昨日はなかったはずだ。
「止めるのに苦労した」
平然と言ってのけた。
普段、子供を殴れば烈火のごとく怒る男だが、さて、どういう心境の変化か。
どうしてもパウロを許せないということでエリスが暴れたのだろうが、エリスとルイジェルドは師弟関係にある。その二人が訓練をしてエリスが怪我を負うのも初めてではない。
いや、よく見ろ。
ルイジェルドの顔。平然としてはいない。あまり表情豊かではないこの男だが、今はやや苦々しそうだ。不本意そうだ。
仕方ない、か。
何があったのか、どんな会話があったのか。どういう経緯でこうなったのか。
俺にはさっぱりわからない。
ただ一つだけ言えることがある。ルイジェルドとエリスが争ったのは、俺のせいだ。
俺はパウロと仲直りできた……なら、俺が言うのはお礼だけだ。
「ありがとうございました。おかげで父様と仲直りすることができました」
「礼には及ばん」
しかし、今のエリスはルイジェルドが殴らないと止められないのか。
知らない間にどんどん強くなるな。
その後、しばらくしてから作戦会議を行った。
「さて、ではミリシオンにおける、第二回の作戦会議を行います」
場所は酒場。
考えてみると、俺は本日、酒場から一歩も動いていない。
ここの酒場は居心地がいい。客も少ないし。店主には不本意かもしれないが。
「一昨日したばっかりじゃないの」
エリスはもう怒っていない。
拗ねて部屋に閉じこもるかと思ったが、十分ぐらいで戻ってきた。
彼女の切り替えの早さは見習いたいものだ。
「状況が変わりました。具体的にいうと、金を稼ぐ必要がなくなりました。なので、近いうちにミリシオンを発とうと思います」
王札二〇枚がもらえるということで、金を稼ぐ必要がなくなった。
情報収集も、パウロから聞けることは聞いた。とりあえずは必要ない。スペルド族の名誉に関しては、とりあえず保留となれば、この町でできることは少なくなったということを、かいつまんで話す。
フィットア領の現状について、エリスに話すのは迷った。
だが、あえて話すことにした。
実際に現地に赴いて、絶望的な気分を味わうより、今から覚悟しておいたほうがいい。
「エリス、僕らの故郷は、もう存在してないみたいです」
「そう」
「フィリップ様も、サウロス様も、まだ見つかっていないらしい」
「仕方ないわね」
「ギレーヌの居所もわからないというし、もしかすると……」
「あのね、ルーデウス」
エリスは腕を組み、顎を上げて俺を見た。
「そのぐらい覚悟していたわ」
エリスの目に迷いはなかった。
いつも通り力強く、傲岸不遜で、自分の未来に一変の疑いも持たない目だった。
忘れていたわけではなく、覚悟していたのだと、そう言った。
「ギレーヌはどこかで生きていると思うけど、お父様やお祖父様は死んでいてもおかしくないわね」
フンと鼻息一つで、そう言った。
つまり、自分が魔大陸に転移して大変だったから、他の人が死んでいるかもしれない、とすでに予想していたと、そういうことだろうか。
いや、強がっているだけかもしれない。
エリスは強がっている時と、本当に自信がある時の見分けがつきにくい。
「ルーデウスが隠していたって、ちゃんと知ってるんだから」
何を知っているのかは知らないが、強がっている感じはしない。
エリスはエリスなりに、色々と考えているのだ。
つまり、当事者でフィットア領のことをスッポリと忘れていたのは、俺だけ。
ちょっと恥ずかしいな。
「そうですか。わかりました」
エリスはさすがだと、そう思うことにして話を続ける。
「とりあえず、一週間ほどでこの町を出ようと思いますが……」
「いいのか?」
聞いたのはルイジェルド。
「何がですか?」
「旅立てば、父親と二度と会えんかもしれんぞ」
「また随分と不吉なことを……」
ルイジェルドが言うと、少々重みが違う。
だが、今は戦争中というわけではない。
「今は探さなければ二度と会えないかもしれない家族がいるので、そちらを優先したいと思います」
「そうか、そうだな」
ルイジェルドが納得したところで、本題に入る。
「これからの旅では、情報収集を中心に行っていきましょう」
一つの町に滞在する期間はやはり一週間前後。
しかし、その間は金稼ぎではなく、情報収集を主に行う。
探すのは、主に転移した人間だ。
ミリスからアスラまでの道のり。
それはこの世界で最も人通りが多く、最も多くの商人が生息するとされる、この世界のシルクロード。当然、捜索隊によって調べつくされているだろうが、もしかすると、先達が見つけられなかった何かを発見できるかもしれない。
スペルド族の名誉回復は、その作業の中でもなんとかなる。
もっとも、ミリスや中央大陸では『デッドエンド』の名前はあまり知られてない。
どうやって名前を売るか、また考えなければいけないかもしれない
「問題は渡航費用ですね」
一番の問題だ。
この世界においては、海を渡るというのは、それなりに特別な意味があるらしい。
陸路で他国へと入る時はいくらでもごまかせるそうだが、海だけは簡単には渡れない。
特に、スペルド族は。
「そのことだが、ルーデウス、これを見てくれ」
と、ルイジェルドが取り出したのは、一枚の紙片。
昨日、俺に見せようとしてやめた、あの封筒だ。
受け取ってみると、表には『バクシール公爵へ』と殴り書きされた文字。
裏は赤い蝋で封印がなされている。模様は家紋だろうか、実に無骨な感じだ。
「これは?」
「昨日、知り合いに書いてもらったものだ」
知り合い……そういえば、ルイジェルドは知り合いに会ってくると言ったのだ。
「知り合いというのは、どういう人なんですか?」
「ガッシュ・ブラッシュという男だ」
「ご職業は?」
「知らん。だが、偉そうにはしていたぞ」
なんでも、ガッシュとは四十年前に出会ったらしい。
魔大陸でのことだ。
ルイジェルドは魔物に襲われて全滅しかけている一団を助け、その中にガッシュがいたそうだ。
当時のガッシュはまだ子供であり、ルイジェルドを見て恐怖と敵愾心のこもった目をしていたが、別れ際にはわりとフレンドリーな感じになっていたそうだ。
町に送り届けた時、もしミリシオンに来ることがあったら訪ねてくれと言われ、機会がないまま忘れていたが、冒険者区の入り口に入るべく外周を回っている時、ふと『眼』に映り、思い出したそうだ。
なので、一応は訪ねてみる気になったものの、もしかすると相手も忘れているかもしれない。そんな不安を胸にルイジェルドが向かうと、向こうは当然のように覚えていて、大層な歓迎を受けたらしい。
最初は挨拶程度で済ませるつもりだったが、意気投合。
ここまでの旅を話すと、ならウェストポートを渡る時にはこれを見せろ、と一筆書いてくれたそうだ。
ルイジェルドと意気投合。
獣族のギュスターヴみたいな感じの人なのだろうか。即座に一筆書くあたり、かなり偉い立場にありそうな感じだが……。
中身を覗いて見てみたいが、確かこういうのは封印を破ったら中身は無効になるんだったか。
「そのガッシュという人、貴族なんでしょうかね」
「さてな、配下はたくさんいたが……」
配下。
ルイジェルドらしい言い方だ。
召使いか何かだろうか。たくさんという言い方も曖昧だ。
とはいえ、なにせ、ルイジェルドの知り合いだ。優しい王様を目指している魔王候補の一人だったとしてもおかしくない。
「家まで行ったんですか?」
「ああ」
「大きかったんですか?」
「大きかったな」
「どれぐらいですか?」
「キシリス城ほどではないな」
キシリス城。
それより小さいというと、湖の中心にあるホワイトパレスではないな。
さすがに王族ではないらしいが、それを比較対象に出すような大きさの建物か。
うーむ。
ルイジェルドの知り合いだ。悪い奴ではないと思うが……。
パウロ曰く、税関の責任者である貴族は魔族嫌いだそうだ。生半可な人物であれば、手紙を渡して問題が起きる可能性もありうる。
ガッシュとやらがどういう人物なのか、調べたほうがいいだろうか。
いや、手紙を取り出した時のルイジェルドの嬉しそうな顔。
変に邪推して、また信用云々の話になったら嫌だな。
まあ、いい。何にせよ、他に方法も思いつかないのだ。ここはルイジェルドの顔を立てよう。
そして、ガッシュという名前について、後でこっそりパウロあたりに聞いておこう。
「わかりました、では、この手紙に頼ってみましょう」
俺の言葉に、ルイジェルドは頷いた。
出発は一週間後。
それまでに、ここでできることを済ませておこう。
「私は別に明日出発でもいいけどね!」
エリスの言葉に苦笑しつつ、作戦会議は終わった。
第六話 「ミリシオンでの一週間」
俺は、今後の予定を話すため、捜索団の拠点を訪れた。
何の変哲もない二階建ての建物。
そこの会議室のような場所で、パウロは実に真面目に働いていた。
十数人の男たちの中で、何やら話し合いをしている。
耳をそばだててみると、大きなプロジェクトが動いているらしい。
ミリシオンに来てからは酔っ払っているか二日酔いかの二パターンしか見ていなかったが、こうして仕事をしているところを見ると、我が父上はなかなか逞しくカッコよく見える。
出会ったタイミングが悪かっただけで、別に毎日飲んだくれてくだを巻いていたわけではなかったのだ。
と思ったが、話の内容を拾ってみると、なんでもここ一ヶ月ほどは酒浸りでロクに仕事をしていなかったらしい。それが、昨日から急にやる気を出し、昔のように戻ったのだそうだ。
きっと、俺にいいところを見せたいのだろう。つまり、奴が働くのは俺のおかげだ。
はぁやれやれ、アテクシったら罪な男だワ。
わざとらしく嘆いた後、パウロに暇な時間ができるまで待つことにした。
じっとしているのも何なので、建物内を探索していると、ある部屋で、遊んでいるノルンを見かけた。
周囲には、ノルンと同じぐらいの年恰好の子供たちもいる。彼らは楽しそうに積み木のようなもので遊んでいた。恐らく、ここは託児所か何かだ。
「やぁ」
ノルンと目が合ったので、気軽に手を上げて声を掛けてみる。
すると、彼女はびっくりした顔になったが、すぐに俺を睨みつけて、手に持った積み木を投げつけてきた。
パシリとキャッチ。
「あっち行って!」
はっきりとした拒絶である。
はて。俺は彼女に嫌われることをしただろうか。心当たりといえば、パウロをぶん殴ったことぐらいである。
うん。まさにそれであろう。
「えっと、父様とはちゃんと仲直りしたんですよ?」
弁明をしてみたが、
「うそ!」
ノルンは大きな声でそう言って、スルリと逃げてしまった。
どうやら、かなり嫌われてしまっているらしい。
ちとショックだ。
嫌われた相手の近くにいるのもなんなので、待合所のような場所に戻り、しばらくパウロを待つことにした。
隅の方に座っていると、チラチラと俺を見てくる視線がある。
視線の中には先日、人攫いをした連中も混ざっていた。
やはり俺はここでは嫌われているのだろうか。
居心地の悪さを感じていると、やたら肌色の目立つ人物が入ってきた。
彼女は昨日の地味さはなんだったのかと思うビキニアーマーで、周囲の目線を集めつつ、ふと俺に気づいて、俺の方へと歩いてきた。
「おはようございます」
「おはようございます、今日はどうしました?」
ビキニさんはにこやかな笑みを浮かべつつ、小首をかしげた。
「はい、父に会いにきました、ええと」
ええと、この人名前なんだっけか。
まだ聞いてなかったよな。
「失礼、自己紹介がまだでしたね。ルーデウス・グレイラットと申します」
立ち上がり、胸に手を当てて、貴族流の挨拶。
すると、ヴェラは慌てた様子で手をわたわたさせて、
「あっと、えっと……わ、私はヴェラです。パウロ団長の部下の一人です」
若干慌てながら答えた。
頭を下げると、必然的に深淵の奥底がかいま見える。
目の毒だ。そして毒は時に薬となり、薬は保養となる。
控えめと決めた手前、あまり見たくはないが、目に入るとどうしても追ってしまう。
どれだけ心の中で何かを決めていようと、俺の目線は追い立てられた狐のように、ある一点へと引きずりだされてしまう。
卑怯だ。
「先日は失礼しました。父は女癖がやや悪いので、少々勘違いしてしまいました」
「い、いえいえ、いいんです。私もこういう格好をしていますので仕方ありません」
取り繕いつつ答えると、ヴェラはぶんぶんと首を振った。
すると、ある部分もプルプルと揺れる。
ビキニアーマーとはいえ、一応は固定されているようだが、しかし振動があると、それが伝わって波打つのだ。大きいから。
いやいや…………と、なんとかして視線を引き剥がす。
「あまりそういう格好で男の前をうろつかないほうがいいと思います。他の方にとっても目の毒でしょう。せめて外套を羽織ってはどうでしょうか」
「……理由あってのことですから」
ヴェラは苦笑して、そう言った。
気のせいか、他の団員の目線が集まっている気がする。
何か悪いことを言っただろうか……わからん。あとでパウロにでも聞いておこう。
「父様はいつごろ終わりますか?」
話を変えると、ヴェラは首を捻った。
「ええと、ここ一ヶ月ほどの仕事が溜まっているので、しばらくは忙しいと思います」
「そうですか……とりあえず、僕は七日後にミリシオンを発つつもりだと、そう伝えていただけますか?」
「七日ですか? 随分と急なんですね」
「僕らにとっては、普段通りです」
「そうですか……わかりました、今シェラを呼んできます。少し待っていてください」
そういうと、彼女はパタパタと建物の奥へと走っていった。
しばらくして、ローブ姿の治癒術師を連れて戻ってくる。
彼女は俺の視線を受けると、ウッと一声漏らして、ヴェラの後ろに隠れた。
「団長の予定は詰まっていますが、四日後の夜に時間が取れます。お食事でしたら、その時にお願いします」
「無理にとは言いませんが?」
「あなたと話す時の団長はいきいきとしています。なので、無理にでもお願いします」
シェラは後ろに隠れつつも、淡々とした口調で答えた。
随分と嫌われているな、いや、恐れられているのだろうか。
不本意だが……まあいい。
「四日後の夜ですね、わかりました。宿の方に行けばいいでしょうか?」
「普段から団が使うレストランを予約しておきますので、そちらに直接お越しください」
と、シェラは淡々と場所と時間を伝えてくれた。
『レイジ・ミリス』という、商業区にあるレストランだそうだ。
一応聞いてみたが、ドレスコードはないらしい。
しかし、なんだな、まるで大企業の社長との会食のセッティングをしている気分だ。
秘書にスケジュールを管理させるとは、パウロも偉くなったものだよ。
「お連れ様はいますか?」
最後にそう聞かれ、ふとエリスの顔が浮かんだが、同時に「ぶっ殺してやるわ」というセリフも思い出した。
「いえ、一人でいきます」
それで打ち合わせは終了、俺は建物を出た。
★ ★ ★
さて、一週間は短い、有意義に使わなければいけない。
そう思い、ミリシオンの冒険者ギルドへとやってきた。
本部というだけあって、かなりの巨大建築物であった。二階建てで、今まで見たギルドの中では一番大きい。
とはいえ、俺も巨大建築物はいくつか見てきているため、さほど感動は覚えない。
まずは情報収集である。
さしあたっては、主にフィットア領のことについてだが、パウロから聞いた以上の情報は得られなかった。このあたりで一番詳しいのは、やはりパウロたち捜索団ということだろう。
次に調べたのは、ミリシオン周囲の魔物の情報。
魔大陸に比べると脅威度が大きく違うようだ。
ジャイアントローカストという名前のでかいだけのバッタ、ミートカットラビットという名の肉食のウサギ、ロックワームという名の大きなミミズ等など。
極めて危険性の低い生き物が多い。
魔大陸に比べると、サイズも小さい。
かの試される大地では、魔物の大きさは人の背丈の数倍がざらである。俺たちが絶滅寸前に追い込んだ(誇張)あのパクスコヨーテですら、体長は二メートル以上。
アシッドウルフなど、三メートル以上の大きさだ。
大王陸亀ともなれば、平均で八メートル前後、最大で二〇メートル以上である。
大森林の雨期に見た魔物も、人と同じぐらいの大きさを持つ魔物が多かった。
それに比べるとミリシオン周辺の魔物の大きさは、人の膝ぐらいしかないような生き物が多い。
大きければ強いというわけではないようだが、大きさというのはそれだけで武器になる。
要するに、ミリシオン周辺の魔物は弱い。
安全なのはいいことだ。
次に、スペルド族の名誉回復について考える。
だが、これに関しては難しい。
というのも、ミリシオンには魔族を排斥しようとする派閥があるらしい。
それを先導しているのがミリス聖騎士団の一つ、神殿騎士団である。
彼らはミリス大陸からの魔族の排斥を声高に主張している。
とはいえ、現在ミリシオンで最も強い勢力を持っているのはその派閥ではなく、魔族との共存を主張する一派だ。その長が現在の教皇であるゆえ、神殿騎士団も表立って魔族を排斥することはない。
が、魔族が町中で問題を起こせば、すぐにでも飛んできて難癖をつけるらしい。
大義名分を得れば、立場が弱くとも強く出るというわけだ。
ルイジェルドが『スペルド族』だと主張し、堂々と活動すれば、すぐに神殿騎士団に目をつけられるだろう。
町中には、常に神殿騎士団の目が光っている。
──ならば、町の外でならどうだろうと思った俺は、ある依頼を受けてみた。
丁度貼り出されたばかりのBランク依頼。
近隣の村で一匹の魔物が暴れているので、退治してほしいというもの。
距離的には日帰りで行ける場所である。
討伐対象は、緑葉虎。
本来なら大森林の南部に生息する魔物であるが、なんらかの理由で大森林から南下してきて、この近くに住み着いてしまったらしい。
かの魔物は、斑模様の緑を下地に、茶色の模様が入っているため、森の中に潜まれると風景に完全に隠れてしまう。その隠密性の高さと、数匹の群れで行動することから、Bランクに相当する魔物と言われている。
だが今回の対象は一匹であり、かつ平地にいるので、アシッドウルフよりも危険性は低いといえる。危険度でランク付けするなら、せいぜいDランクといったところだろう。
魔大陸にいた頃は、こういう依頼を見つけると歓喜したものだ。
早速行ってみると、丁度緑色の虎が鶏を咥えて、悠々と村を出ていくところだった。
こちらに気づくと、獲物を置いて唸り声を上げたが、エリスが「任せて」と一言、タッと走りだし、あっという間に真っ二つにした。
依頼完了、あっけないものである。
村の人々には、大層感謝された。
この虎は最近、このへんで暴れまわっており、家畜や村人にも少なからぬ被害が出ていたそうだ。
いつもなら、この村の警護にはいずれかの聖騎士団が来てくれるのだが、なんでも先日、この近隣で神子が襲撃を受けるという大事件があったらしい。
神殿騎士団の護衛は部隊長を残して全滅。
神子はギリギリのところで助かったが、部隊員を全滅させた部隊長は責任を取らされ、更迭されたそうだ。
最近は奴隷の誘拐といったきな臭い事件も多く、騎士団もピリピリしていたところに、そんな事件が勃発。そのせいで、教団も騎士団も大わらわ。ゆえに、Bランクという危険度の高い魔物が野放しになってしまい、仕方なく冒険者ギルドに依頼を出したそうだ。
まあ、騎士団云々は俺たちには関係のない話だろう。
さて、情報を得たところで実験開始だ。
彼らに対してスペルド族の宣伝をする。
実はルイジェルドはスペルド族であり、スペルド族は世界中の人々と仲良くするために善行を積んで歩いている。
スペルド族は一見すると取っ付きにくい種族であるが……そこで、この石像の登場。
これを見せてルイジェルドの名前を出せば、どんな恐ろしい外見をしたスペルド族であっても、あっという間に態度が軟化、孫を見た頑固ジジイのように頬を緩め、数分後には百年来のソウルブラザーになるだろう。
そう説明した。
我ながら完璧なセールストークだったと思う。
だが、村長には微妙な顔をされた。
ルイジェルド個人には感謝はしているが、この程度では魔族全体に対する偏見は消えないし、ミリス教徒である自分たちが魔族の像を持っていることには抵抗がある。
そう言われて像を突き返された。
実験はうまくいかなかった。
やはり、一足飛びにうまくいくものではないらしい。
それとも、やはり美少女フィギュアでなければダメなのだろうか。
今からでもルイジェルドフィギュアの女体化を検討に入れてみるか。
いや、それだと意味がないか。
「こんなものを作っていたのか……」
ミリシオンに帰る途中、ルイジェルドがフィギュアをまじまじと見てしきりに感心していた。
「そうよ、ルーデウスはこういうのを作るのがうまいんだから!」
そして、それを見てなぜかエリスが自慢げにしていた。
今回は突き返されたが、俺のフィギュアは結構な値段で売れるのだ。
獣族の剣王様や、どこぞの国の王子の目にも留まる逸品だしな。
王室御用達と言っても過言ではない。
……などと考えて鼻を高くしていたのだが、
「しかし、この構えは隙だらけだな」
「そうね、構えはよくないわね。もっと低くないと……」
最後にはダメ出しされた。
にょ○ーん。
★ ★ ★
三日後、会食の前日。
家族との会食であるが、着ていく服がない。
ドレスコードはないらしいが、魔大陸で購入した服はこの辺りでは少々みすぼらしく見える。
ということで、エリスを伴って服屋を見てまわった。
いわばデートである。
といっても、それほど色気のあるものではない。
エリスは服を買うという点においてはそれほど積極的ではなく、どれでもいいじゃないか、という感じだ。そんな彼女の分の服も購入しておきたい。
ここから先は人族の領域。先入観は見た目からというし、せめて、一目見て侮られない程度の格好はしておきたい。
この場に誰か、最近の服飾について詳しい人でもいれば、アドバイスを求めるのだが、俺の知り合いでというと、サル顔の新入りかヴェラくらいだ。サル顔の新入りはどこにいるかわからないし、ヴェラに何かを頼めるほど親しくはない。
なので、道行く人を見て、その格好で判断することにした。
エリスと二人で道端に座り込み、趣味は人間観察ですと言わんばかりに人を見る。
若干だが、青い色を着た人が多い。
その上に、上着を着たり着なかったり。気候がいいため、上着も薄手である。
「最近の流行は青みたいですね」
「ルーデウスに青は似合わないわ」
エリスにはそう切って捨てられた。
まあ、流行の最先端を追う気はさらさらないのだが。
「じゃあどういうのが似合うって言うんですか」
「ギースにもらったのがあるじゃない。あれでいいわよ」
あの毛皮のベストか。
ただ、あれはちょっとサイズがデカイのだ。丈が余って、コートみたいになっている。
とはいえ、着心地は悪くないので、ちょっと肌寒い日は着ているのだが……。
「あれも悪くはないですけど、ちょっと丈が余ってますからね」
「そうね、確かにちょっと長いわよね。切ったら?」
「それはもったいないですよ。背も伸びてますし」
なんて会話をしつつ、買うものを決めた。
さほど時間が掛からなかったのは、やはり俺とエリスの服飾に関する関心のなさの表れであろう。
と、思ったが、エリスは最後に黒いワンピースを買っていた。
結構オシャレな感じのする品で、黒い生地に、白い薔薇の刺繍が入っている。
「エリス、それ買うんですか?」
「……なによ、悪いの?」
「いいえ。似合うと思いますよ」
「ふん、別にお世辞なんていらないわ」
そんな会話で、その日の買い物は終了した。
会食の日。
俺は出発前にルイジェルドとエリスの二人に、一言告げた。
「今日の夜は父さんとご飯を食べてきます」
そう言うと、ルイジェルドはほっとしたような顔をした。
「ああ、行ってこい」
温かい目だ。
こうした顔をするということは、やはりルイジェルドは俺にパウロと仲良くしてほしいと思っているのだろう。
言われるまでもない。
今日はパウロと水入らず、たっぷりと親睦を深めて帰ってくるとしよう。
「私も行くわ!」
見ると、エリスは腕を組んだいつものポーズで俺を見下ろしていた。
「ええっと……」
「なによ、ダメなの?」
先日のことがなければ「どうぞどうぞ」と言うところだが、エリスは未だ、パウロに敵意を抱いている。
殺意と言い換えてもいいぐらい、強いものだ。
気持ちを理解できなくはないが、俺はパウロと仲良くしようと決めている。
それだけなら、エリスとパウロを仲良くさせるためにあれこれ動くが、今回は一応、数年ぶりの家族水入らず。
俺とノルンの仲も改善されていない。
ついでに言えば、一人で行くとも言っちゃったし。
「エリスは、家で留守番しててもらえませんか?」
なので、エリスには遠慮してもらうことにした。
爆弾を抱えて山火事に飛び込むわけにはいかない。
彼女と一緒に現場に赴くのは、もっと俺がエリスと仲良くなってから、だ。
「嫌よ! 私もいくわ!」
ま、エリスならそう言うだろうね。
エリスは『遠慮』なんて言葉は知らないのだ。
「ルイジェルドさんからも何とか言ってはもらえませんか?」
「……」
俺が一声掛けると、ルイジェルドは考えるように顎に手をあてた。
睨
にら
むような目つきで、俺とエリスを交互に見る。
「いや、仲直りしたのなら問題ないだろう? 二人で行ってこい」
おおう。敵に回った。
この間はエリスを殴ってでも止めてくれたのに……。
仕方ないか。二対一、今回は民主主義ということにしておこう。
「ルイジェルドさんがそう言うのなら……」
「ふん、当然よ!」
「ただしエリス、僕は父様とは仲良くしたいと思ってるんですから、お行儀よくしてくださいよ?」
「…………わかったわ!」
俺の経験上、これは『わかってない時のわかったわ』だが……。
大丈夫かなぁ。
それから俺はおろしたての服を着て、新しい俺、ニューデウスとなってレストランへと赴く。
先日買ったワンピースを着たニューエリスも一緒だ。
なるべく裏路地は通らない。
裏路地には人攫いが多く、所により血の雨が降るからだ。
血で服が汚れたら大変だ。
表通りも危険がいっぱいだ。飯時ということもあって、露店で焼き鳥のようなものを買った連中が歩いている。ドンとぶつかればベチャリは自明の理である。
また、エリスと彼らがぶつかれば、ボレアスパンチの返り血で、俺たちの服も真っ赤に染め上がるだろう。
ゆえに、俺は魔眼の封印を解いた。
一秒先を見据えながら、人混みを華麗に回避する。
──なんて無駄に能力を使っているうちに、到着した。
『レイジ・ミリス』
予約などというから身構えていたが、ごくごく普通の店だった。
宿屋に併設されていない酒場で、町人が多いらしく、客層に物騒な感じがしない。
店の給仕に名前を告げると、俺とエリスはあっさりと席に案内された。
人数に関しても特に何も言われなかった。
「すいません、少々遅れましたか?」
苦笑したパウロと、ムスッとしたノルンが座っていた。
「いいや……悪かったな。シェラがなんか張り切っててよ。別にいつもの酒場でいいって言ったんだがな……」
「たまにはいいじゃないですか」
そう言いつつ、俺も席につこうとして、エリスがノルンと似たような表情でムスッとしているのを見て、はたと止まった。
初対面というわけではないが、改めて紹介しておいたほうがいいだろう。
「えっと、父様、こちらはエリス。先日も話しましたが、フィリップさんのご息女で、ボレアスの……」
「ああ、いや。わかっている」
パウロは俺を制するように立ち上がった。
エリスに向かってまっすぐ立ち、胸に手を当て、会釈程度に頭を下げる。
フィリップ並みに洗練された挨拶だった。
「初めまして、ルーデウスの父、パウロ・グレイラットです」
「……え、エリス・グレイラットよ……です」
エリスは面食らったような顔で俺を見ようとして、しかしパウロから視線を外さなかった。
ムッとした顔のまま、スカートの両端をつまんで、ぎこちない挨拶をした。
暴れるタイミングも、叫ぶタイミングも逸した感じだ。
やるなパウロ。伊達に女の扱いには慣れていないか。
ていうか、あんな挨拶もできたんだな。
「ま、座ろうか」
ともあれ、こうしてグレイラット家の会食は始まった。
ひとまず、俺とエリスは席についた。
エリスは今のところ静かだが、何かあればすぐに牙を剥くだろう。
パウロもぎこちない表情。
ノルンもそっぽを向いたままだ。
どうにも空気が悪い。やはりエリスをこの場に連れてきたのは失敗だっただろうか。
そう思ったのは、俺だけではなかったらしい。パウロも困った顔で、ノルンに話しかけた。
「ほら、ノルン、お兄ちゃんだぞ。挨拶しなさい」
「やだ。お父さんを殴る人とご飯なんて食べたくない」
その言葉に、エリスがムッとした顔をして口を開きかけたが、その前にパウロがノルンを叱った。
「こら、そんなこと言っちゃだめだろ。お父さんだって悪いことをしたら殴られるんだ」
「お父さん、悪くないもん」
ノルンは頬をぷくりと膨れさせて、実に可愛らしく拗ねていた。
「お父さんとお兄ちゃんはもう仲直りしたんだ。なあルディ」
おっと、唐突に振られた。
だが、ここは一つ、ウィットに富んだ受け答えで俺のコミュニュケーション能力の高さを見せてやろうじゃないか。
「もちろんですとも。なんならキスだってできますよ」
「えっ?」
「えっ?」
場が凍った。
息子とのキスは嫌と申すか……と思ったが、俺も親父とのキスは嫌だな。
失言である。
「ま、まぁ……お父さんとお兄ちゃんは仲良くするから。ノルンもお兄ちゃんと仲良くしよう、なっ?」
「やだ」
パウロがノルンの頭をぽふぽふと撫でる。
ノルンの髪は綺麗な金髪。
この髪を見ているとゼニスのことを思い出す。
ゼニスもまた、気に食わないことがあると、こうやって拗ねてパウロを困らせていた。
こういうところは親の血を継いでいるのかもしれない。
ノルンはしばらくパウロのなすがまま撫でられていたが、キッと俺を睨んできた。
やや上目遣いで。凄んでいるつもりなのかもしれないが、ただ可愛いだけである。
「お父さんは、すごくがんばってるんだもん」
それが俺に対して言ったのだということは、すぐにわかった。
なので、俺は応えよう。
「ええ、承知しています」
「女の人と遊んでなんかいないもん」
「聞き及びました。疑って申し訳ないと思っています」
「あたしにも、優しくしてくれるもん」
ノルンの目に、じわじわと涙が浮かんできている。
まずい。何かひどいことを言っただろうか。泣かれるのはちょっと困る。
「お父さん、いっつも泣きそうになってるんだもん!」
「……そうなんですか?」
「いや、まぁ、最近はな……」
泣きそうなノルンに、俺とパウロはしどろもどろに問答する。
「お父さんは、可哀想なんだもん!」
「……」「……」
「殴るなんて、ひどいんだもん!」
俺はそれを見て、心の中で深いため息をついた。
パウロとノルンは一緒に転移した。その経緯については聞いた。
途中で、ノルンが病気にもなったし、魔物にも襲われたそうだ。
それを守ってきたのは、パウロだ。
母と離れ、メイドと離れ、妹と離れ、不安が胸を締め付ける中、パウロはたった一人の味方であり、そしてたった一人の頼れる家族だったのだ。
それを、いきなり現れた男が、馬乗りになってぶん殴る。
トラウマになりかねない状況だ。
「ノルン、あれは、父さんが……」
「父様、仕方ありませんよ」
せめて、もう少し大きければ、話し合いでなんとかなったかもしれない。
が、この歳では難しいだろう。
互いに悪い部分があり、悪い部分を認め合って納得した──ということを理解させるには、まだ幼すぎる。
「ノルンはまだ幼いですし、それに、もし、僕が逆の立場だったら、父親をぶん殴った奴を許したりはしませんから」
ここでノルンに嫌われるのは仕方がない。
もう何年かしてから、ゆっくりと話し合えばいいのだ。
その時には、ノルンだってきっとわかってくれるはず。
時間は有限だが、物事を落ち着かせる力があるのだから。
「いや」
だが、パウロはそうは思わなかったらしい。
「もしかすると、もうたった二人の兄妹かもしれないんだ。仲良くしないと」
たった二人の兄妹かもしれない。
その意味に思い至り、俺は眉をひそめた。
「父様がそんな不吉なことを言わないでください」
「…………そうだな、すまん」
おっといかん。
空気が重くなってしまった。
ここは空気を読もう。
「ところで父様、この店の名物はなんなんですか? 今日はお昼を抜いたので、もうお腹がペコペコで」
露骨な話題変更だったが、パウロも察してくれたようだ。
ぎこちない笑いを浮かべつつも、答えてくれた。
「ん、そうだな。南の海の方で取れる魚介類のシチューがうまい。それから、牛だな。このへんでは牛を飼っている農家が多いんだ。アスラの牛肉とはまた違った味わいで、煮込むことが多いんだが、こってりとした味がやみつきになる」
「それは楽しみですね。魔大陸では肉がまずくてまずくて」
「大王陸亀だったか? 魔物の肉ってなぁ、大概まずいもんだ」
そんな感じで、パウロとの会話は弾んだが、ノルンはそっぽを向いたままだった。
パウロが声を掛けると返事はするものの、俺の方は決して見ない。
仕方ない、仕方ないとは思っていても、ちょっとクルものがあるな。
この間、俺がパウロ相手にやったことだ。胸が痛む。パウロには悪いことをした。
エリスはそんなノルンの態度が気に入らないのか、ノルンの方を見ている。
喧嘩はしないでほしいものだが……ひとまずは置いておこう。
「そういえば父様、一つお尋ねしたいことがあるのですが」
「なんだ?」
「ガッシュ・ブラッシュという人物を知っていますか?」
「……いや、知らんな。どこで聞いた名前なんだ?」
と、俺はルイジェルドが持ってきた手紙について聞いてみることにした。
一応、紋章の写しもとってあるので、それも見せる。
「羊、鷹、剣か。守護騎士の家系だな。だが、ガッシュ・ブラッシュという名前には聞き覚えがない。オレもミリスの貴族に関してはそう詳しくないからな……」
「そうですか……シェラさんに聞けばわかりますかね」
「どうだろうな。後で聞いてみよう」
ルイジェルドの持ってきた手紙に、一抹の不安を覚えつつも、その話はそこで終わった。
その後は、また他愛ない話だ。
誕生日のこと。
俺の十歳の誕生日の一ヶ月ほど前から、森の魔物が活性化していたらしい。パウロとゼニスはその対応に追われ、誕生日プレゼントを送る暇がなかったそうだ。
魔物の活性化自体は誕生日の前日に収まったらしいが、そろそろ品を送ろうかと思っていた頃、転移されたのだとか。
エリスはその話を聞いて、口をアヒルのように尖らせていた。
そういえば、俺の十歳の誕生日の時、パウロが来れないと聞いて、悲しそうな顔をしてくれたっけなぁ……。
「ちなみに、何をくださるつもりだったんですか?」
「オレからは篭手だな。倉庫の奥で見つけたもので悪いと思ったが、一応は迷宮の奥で見つけた魔力付与品だ。羽のように軽いやつで、オレにはサイズが合わなかったが、ルディには合うかと思ってな」
「へぇ、そういうのもあるんですね」
「ああ。ゼニスの方はナイショだって話だったが、リーリャは、鍵の掛かった小さな箱を満足そうに見ていたから、それだろうな」
「箱ですか」
何だったのだろうか、少々気になる話だ。
ま、手に入らなかったものをとやかく言っても仕方あるまい。
それから話はゼニスの実家の話題に及んだ。
ゼニスの実家は優秀な騎士を何人も輩出している名家だそうだが、ゼニスは勘当同然で、俺の祖父母に当たる人物は捜索に乗り気ではなかったらしい。
でも、ノルンを見て態度を一変させたらしい。
どこの世界でも、祖父母は孫に弱いのだ。
「僕が顔を出せば、もっと資金とかもらえたりしますかね」
「いや、お前だと逆効果だろうな……」
「……でしょうね」
孫の可愛らしさを演技することはできるが、墓穴を掘りそうだ。
やめておこう。
なんて話をしていると、食事が運ばれてきた。
「さて、食おうか。どれにしよっかなぁっと……」
わざとらしくフォークを迷わせるパウロ。
「確かにお腹がへったわね……!」
エリスもそう呟きつつ、目を輝かせてテーブルに並んだ料理を見渡した。
この二人の方が親子みたいだ。
パウロとフィリップは従兄弟という話だし、似たようなものなのかもしれないが。
ま、ここはノルンの前だ。ちょいとお兄ちゃん風を吹かせておこうじゃないの。
「父様。お行儀が──」
「お父さん違う! 食べる前はちゃんとお祈りしなきゃダメ!」
俺が言いかけたところで、ノルンがとっさとも言える感じでそう言った。
ノルンが驚いた顔で俺の方を見たが、すぐにぷいっとそっぽを向いてしまった。
「はは、こりゃ参ったな」
「……わかってるわよ」
パウロは頭の後ろを掻きながら、エリスはしぶしぶといった感じで、椅子に座り直した。
その後、皆でミリス式のお祈りをした。
両手を組んで、数秒間目をつむるだけのお祈り。
俺もエリスも、そして恐らくパウロもミリス教徒ではないが、食べる前の「いただきます」のようなものだ。郷に入れば郷に従え。誰も文句を言わず、そのポーズを取った。
しかし、祈りを終えた時、なんとなくだが、ノルンとエリスの機嫌がよくなったような気がした。
その後、また他愛のない話をしながら、楽しく食事を終えた。
楽しくといっても、会話が弾んだのは俺とパウロだけで、結局ノルンには最後までそっぽを向かれたままで、エリスも終始だんまりを決め込んでいた。
パウロも何度か彼女に話しかけようとしていたが、彼女から放たれる殺気を感じ取ったのだろう、結局は話をすることはなかった。触らぬ神に祟りなしといったところか。
エリスはレストランから出た後「フン、今回は手を出さなかったみたいね」と小声で呟いた。
パウロが俺を殴ったり怒鳴ったりしていたらエリスがどう動いたのか、考えたくもない。
だが、何もしなかったことで、エリスのパウロに対する殺気が、若干ながら和らいだ気がした。
なら、有意義な食事会だったといえよう。
あっという間に一週間が経過した。
旅立ちの日、場所は冒険者区の入り口。
馬車に乗って、さぁ出発しようと思っていたところ、パウロが見送りに来た。
「ルディ。もう少しだけ滞在してもいいんだぞ?」
パウロが何やら甘いことを言い出したが、今更だ。
「もう少し、もう少し、そう言ってダラダラと一年ぐらい滞在してしまいそうです」
「ノルンとだって仲直りできてないんだし」
「ノルンとの仲については、あと三人を見つけてからでも遅くはありません」
それに、と俺はエリスをチラ見する。
エリスはルイジェルドに首根っこを掴まれつつ、悪鬼のような顔でパウロを睨んでいた。
切り替えが早いと思ったが、そんなことはないらしい。
「家族に会いたいのは、僕だけじゃありませんしね」
「そうか、だがボレアス家はおそらく……」
「やめてください」
難しそうな顔をするパウロの言葉を、俺は手でさえぎった。
「情報が届いていないだけで、僕らがフィットア領に着く頃には、フィリップ様やサウロス様も帰り着いているかもしれません」
「……そうか。そうだな。けどなルディ」
パウロは真剣な顔で言った。
「あまり、楽観視するなよ。もしフィリップたちが無事に帰り着いたって、あの災害の規模じゃ、どうなるかわからない」
「どういう意味ですか?」
パウロは少しだけ声をひそめて、
「フィリップの兄ジェイムズが、保身のためにどっちかに全部の責任をおっかぶせる可能性が高いって話だよ」
と、言った。
言われてみると確かに起こりうる話だ。
領主のサウロスと、町長のフィリップ。彼らは、領地の責任者だ。
無事に帰っても、領土・領民を失った責任はついて回る。
アスラ王国の法における、貴族の責任の取り方がどうなっているのかはわからないが、少なくとも、二人が無事故郷に帰り着いたところで、そのまま領主としての辣腕を振るうことはないだろう。
あるいは、フィリップの兄の逃げ場を塞ぎ、政治的に叩き潰すため、混乱に乗じて謀殺される可能性だって多いにある。
「何かあるようなら、お嬢様はお前が守ってやれ。貴族の義務を持ちだしてくる奴もいるかもしれねえが、構うことなんてないからな」
「はい。肝に銘じておきます」
俺は顔を引き締め、頷いた。
パウロも誇らしげな顔になり、頷く。
「それから、あの手紙の主についてだが、シェラもわからんらしい」
「そうですか……」
「危険人物ではないだろう、とは言っていたがな」
「わかりました。お礼を言っておいてください」
パウロはこくりと頷いた。
そして、後ろを振り向くと、そこにいる少女に声を掛ける。
「ほら、ノルン、お兄ちゃんにお別れの挨拶をしろ」
「……やだ」
ノルンはパウロの後ろに隠れていた。
半分だけ顔を覗かせているのが、実に可愛い。
将来はゼニスに似た美人になることだろう。
「ノルン、何年後かわかりませんが、また会いましょう」
「…………やだ」
ノルンは最後まで、俺と顔を合わせてくれなかった。
俺は苦笑しつつ、馬車へと戻った。
こうして、俺はミリシオンから旅立った。
★ パウロ視点 ★
ルーデウスが旅立った。
相変わらず優秀な奴だ。
次から次へとポンポン決断して、どんどん行動している。
エリナリーゼは俺を生き急いでいるなんて言ったが、ルーデウスを見たらなんて思うだろうか。
会わせてみたいところだが……。
いや、会わせないほうがいいな。
オレはエリナリーゼのパパになんざなりたくねえ。
などと考えていると、ポンと肩を叩かれた。
みると、サル顔の男がニヤニヤと笑っていた。
「よぉパウロ。息子とのお別れは済んだのか?」
「ギース……」
このサル顔の男には、感謝してもしきれない。
コイツがいなければ、オレはルーデウスと仲たがいしたままだっただろう。
「お前には世話になったな」
「いいってことよ」
と、そこでオレは、ギースが旅装していることに気づいた。
「なんだギース、どこに行くつもりなんだ?」
「決めてねえが、まだ探してねえところは多いんだろ?」
その言葉で、オレはギースが捜索を続けてくれるということに気づいた。
衝撃だった。
ギースはパーティ解散で一番苦労した男のはずだ。
戦う力はなく、何でもできるが何にもできない、他のパーティにも入れてもらえず、単独で依頼もこなせず、冒険者を断念せざるをえなかった奴だ。
オレのことを、一番恨んでいてもおかしくない、そんな奴だ。
「お前、なんで、そこまで親身になって探してくれんだ?」
そう聞くと、サル顔は口の端を歪め、いつものようにニヒルに笑った。
「ジンクスだよ」
いつものように言って、サル顔は背を向けた。
オレは腰に手を当てて、苦笑する。
あいつのジンクスは、多すぎてわからない。
だが、何か心地良いものを感じ、ギースの背中が見えなくなるまで見送った。
「よし」
オレは一声気勢を上げると、ノルンを肩車した。
やる気が満ち溢れていた。
まずは、難民の大移動を成功させる。その後、必ず家族を見つけ出してみせる。
そう決意し、町へと戻ったのだ。
間 話 「エリスのゴブリン討伐」
唐突だが、クリフ・グリモルという少年の話をしよう。
クリフは現在十二歳。エリスとルーデウスの丁度中間の年齢である。
彼は物心ついた時には孤児院にいた。
ミリシオンの孤児院で、ミリス教団の威信や権威の象徴とも言える孤児院である。
当然、経営的なもので悩むことはなく、子供も何不自由なく成長し、里親へと引き取られていく。
そんな裕福な孤児院で育ったクリフは、五歳の時、現在の里親に引き取られた。
ハリー・グリモルという名の老人である。
彼はミリス教団内でも高い地位を持つ人物である。
クリフはハリーに引き取られた先で、英才教育を受け、数年であっという間に治療・解毒・神撃を上級まで習得。攻撃魔術も、全ての属性で中級まで扱うことができた。火魔術に至っては上級である。
クリフは天才であった。
周囲からは称賛の雨あられ、将来はきっと凄い人物になるに違いないとあらゆる人に期待された。
ルーデウスとよく似た幼年期であると言えよう。
が、転生前の記憶を持っていたルーデウスと違い、クリフは増長した。
これ以上ないほど、テングになった。
なにせ、教師陣の中にも、クリフほど多彩に魔術を使いこなせる者はいないのだ。治癒魔術を聖級まで扱える者はいる。解毒魔術を聖級まで扱える者はいる。けれども、全てを上級となると、クリフのみであった。
その多彩さがゆえ、賢者の卵などと言われるようになった。
クリフはさらに増長した。教師の話を次第に聞かなくなった。
将来、クリフは養父の職業を継ぐことになる。
クリフもそれは理解しているのだが、彼は現在、冒険者に憧れていた。
なぜ冒険者か。
それは、孤児院に暮らしていた時期の出来事が影響している。
孤児院の出身者には冒険者が多い。孤児院の子供は、十歳までに里親が見つからなければ、ミリス教団の経営する学校へと入れられる。
そこで五年間、訓練を受ける。剣術や魔術といった戦うための授業である。そうして、自分の才能に合った職業へと就いていく。
勉学も剣術も魔術も優秀であれば騎士になることもできるが、大抵の者は冒険者になった。
ゆえに孤児院の出身者には冒険者が多く、彼らはよく孤児院に来た。
かつての先生に挨拶すると同時に、孤児たちに楽しい冒険のみやげ話を持ってきてくれるのだ。
孤児たちはそれを聞き、冒険者に憧れる。
例に漏れず、クリフも冒険者に憧れていた。
もちろん、クリフはその夢が叶うとは思っていない。
憧れてはいるが、自分の現状もよく理解していた。孤児出身である以上、身勝手は許されない。
我慢できていた……そう、最初の頃は。
窮屈な生活はクリフの鬱憤を溜め、褒められ続ける毎日はクリフを増長させた。
クリフはある日、家を脱走し、冒険者登録をすることを思いつく。
ちょっとした力試しである。
教師たちの中にも、昔は冒険者としてブイブイ言わせていた者もいるのだ。自分だって若い頃にそうした経験は積んでおきたいと、自分を説得して準備を開始。
十歳の誕生日に養父よりもらった杖を手に、神聖区から冒険者区へと入って魔術師っぽいローブを購入。色は青にした。
そのまま冒険者ギルドへと足を踏み入れる。
治癒術師として登録すれば、すぐに教団に見つかるだろうが、魔術師なら大丈夫。
そんな浅はかなことを考えつつ、冒険者登録を済ませた。
これで自分もいっぱしの冒険者。
まだ見ぬ世界への大冒険が控えている。
と、ワクワクしながら周囲を見回すと、誰もが屈強な男だった。
戦士や剣士ばかりなのは見て取れた。
クリフは孤児院の先輩から、どのパーティも優秀な魔術師を喉から手が出るほど欲しがっているという話を聞いていたので、自分は魔術師だと名乗れば、すぐにパーティに入れるだろう、と考えた。
クリフは冒険者ランクの話を聞き流していた。
彼はパーティというものは、ランクに関係なく組めるものだと考えていた。
「いや、無理だよ」
当然のように断られる。
すげなく断られる。何度も断られ、四度目でクリフの我慢は限界に達した。
「なんでだよ! なんで僕がパーティに入れないんだ!」
「だから、ランクが違うって言ってるだろ」
「ランクがなんだ! 本当は僕はAランクぐらいの強さがあるんだ! けれど、しょうがないから君らで我慢してやろうって言ってるんだ!」
「なんだと……ガキ、あんまり調子に乗るなよ! 魔術師がこの距離で喧嘩売って勝てると思ってんのか……」
「剣しか振れない能なしどものくせに、調子に乗るんじゃない!」
「このクソガキ……」
クリフは胸ぐらを掴まれ、しかしこいつをなんとか退けてみせれば、自分の力を示すことになるんじゃないか、と考えた。
「やめなさいよ。大人げないわよ」
そう言って割り込んできたのは、クリフと同じぐらいの年齢の赤毛の少女であった。
★ ★ ★
話は巻き戻る。
エリス・ボレアス・グレイラットは、ルーデウスたちと別れた後、冒険者ギルドへと足を向けた。
彼女は傍から見て微笑ましいぐらいニマニマしながら足早に大通りを歩いていく。
服装はいつも通りの冒険者風の格好。
厚手の服に、皮のプロテクター。皮のズボンに、靴底は薄いが丈夫な素材でできたブーツ。腰には剣を差し、一目で誰もが剣士とわかる。
いつものフードはつけていない。冒険者ギルドであのフードをつけると魔術師と間違えられ、変な男子が寄ってくるのは、この一年で何度も経験した。
エリスは冒険者ギルドの前にたどり着いた。
ミリシオンの冒険者ギルドは、大通りの奥にある。
本部というだけあって、冒険者区で最も大きな建物である。
その威風堂々たる巨大な門構えに気圧されることなく、エリスは中へと踏み込んだ。
そして、その広大なロビーを見て、思わず腕を組みそうになった。なにせそこは、ロアにある館の大広間どころか、今まで見たどの冒険者ギルドよりも広かったからだ。
もし、初めて冒険者になるという少年少女であれば、そんな広さを目の当たりにし、二の足を踏んでしまうだろう。
だが、そこはエリスである。
彼女はAランク。いっぱしの冒険者。すぐに目的の方向へと歩き出す。
依頼の掲示板である。
他よりもはるかに大きなその掲示板には、所狭しと依頼が貼り付けてある。
エリスは腕を組んでそれを見る。
普段見ているBランク依頼ではなく、今回はEランク付近。
その中でも自由依頼に分類されるものを探す。
自由依頼とは、国が定期的に発行している依頼である。報酬は低めだが、緊急度が高いため、どのランクの冒険者でも受けることができる。
魔大陸で見かけないのは、国が無いからだ。
エリスはその中から、目当てのものを探しだした。
フリー
・仕事:ゴブリン討伐
・報酬:耳一つにつきミリス銅貨10枚
・仕事内容:ゴブリンの間引き
・場所:ミリシオン東
・期間:特になし ・期限:特になし
・依頼主の名前:ミリス聖堂騎士団
・備考:新人は時折発生するホブゴブリンに注意。なお、この依頼は剥がさず、収集したものをカウンターにそのままお持ちください。
ゴブリンは森と平原の境界あたりに住む魔物だ。
人の形をしており、簡素な武器を使うが、人語は解さない。数匹なら放っておいてもいいが、放っておくとどんどん増殖し、周辺の村々を襲い始める害獣である。
とはいえ、森との境に生息するため、森に発生する魔物の防波堤となる。
また、ゴブリンは弱く、ちょっと剣をかじった程度の少年でも十分に相手することができる。
冒険者ギルドはそれを利用し、新人にとって割のいい報酬を用意し、討伐系依頼の入門としてゴブリン討伐を斡旋している。
また、これはエリスの知らないことであるが、ゴブリンというのは、敵国のスパイへの拷問道具としても使える。
これらの理由により、ミリスではゴブリンを絶滅させず、生かさず殺さず、適度に調整している。
さて、もはや実力的にはルイジェルドのお墨付き、そこらのCランク冒険者程度なら素手で制圧できるAランク冒険者のエリスが、なぜ今更そんな依頼を受けるのか。
理由は二つ。
エリスは単純に、憧れていたのだ。
かつて、ほんの短い時間だけ学校に通っていた頃、クラスメイトの男子が集まって何やら話していた話題に。
その話題とは、自分が冒険者になったらどうするか、というものである。
最初はゴブリン狩りをし、そこで力とお金を蓄えて、ゆくゆくは中央大陸の南部に進出し、高ランクの依頼や迷宮へと挑んでいく。そんな夢物語である。
エリスはそれを傍で聞きながら、いずれは自分も、と妄想した。
妄想は膨らみ、楽しそうに話をする男子に、自分も会話に交ぜなさいよと話しかけ、色々あって喧嘩して三人ともぶちのめした。
それから学校を退学となり、ギレーヌと出会い、彼女から話を聞く度に、冒険者への思いを強くし、ルーデウスと出会ってからは、彼と一緒に冒険に出ることばかり夢見た。
剣士の私と、魔術師のルーデウス。
二人で迷宮に挑むのだ。
しかし、実際に旅に出てみると、夢とは違った。特にルーデウスは想像以上に現実的で冷めていた。危険だからと迷宮には一切近寄らなかった。ゴブリン狩りなど提案すれば、「何のために?」と呆れ顔で聞いてくるだろう。
エリスとて、魔大陸で冒険者としてやってきた女である。
現状でゴブリンを狩ることの意味は見いだせない。
が、意味はさておき、ゴブリン狩りは、エリスが『冒険者になってやりたいこと』の一番上にランクしていた。
たとえ意味がなくとも、やってみたいことなのだ。
それが理由の一つで、もう一つ理由は……ナイショである。
「日が沈む前に戻ってこれるかしらね……?」
エリスは依頼を見つつ、行き帰りの時間を考える。
今回は徒歩である。時刻はまだ朝であるが、余裕を持って行動したほうがいいだろう。
「……ん?」
ふとFランクの外、掲示板の欄外に、あるメモが貼り付けられていた。
『フィットア領出身の難民は下記まで連絡すること』
と、そこまで読んでエリスは目線を外した。
このメモはザントポートの冒険者ギルドでも見た。
ルーデウスはフィットア領のことは口に出さない。きっと、自分を不安にさせないように、という配慮だとエリスは考えていた。本日別行動をしたのも、この一件で何かをしようと考えているのだろう。
エリスは自分には難しい話は理解できないと考えている。
自分が深く考えずとも、ルーデウスはしっかり考えてくれているだろうし、時がくれば、ルーデウスもきちんと自分にわかる言葉で話してくれると、そう考えている。
まさかルーデウスがこうしたメモの存在を知らないなどとは、夢にも思っていない。
「さてと!」
依頼を確認したところで、エリスは意気揚々とギルドを出ていこうとする。
後はただ東に行き、ゴブリンを狩るだけである。
今のエリスのやる気なら、巣の一つや二つは壊滅するであろう。もはや彼女の足を止めるものは何もない。哀れなるゴブリンにレクイエムを。
「なんでだよっ!」
と、思われたが、ふと聞こえた叫び声に、エリスの足は止まった。
そちらを見てみると、少年が自分の背丈の二倍はあろうかという男たちに囲まれていた。
「なんで僕がパーティに入れないんだ!」
叫んだ少年は、青色のローブを身につけていた。
背丈はルーデウスよりもやや小さく、髪の色はダークブラウン。
長い前髪で目が隠れている。杖もルーデウスの『傲慢なる水竜王』ほど立派なものではないけれど、それなりに高い素材を使っていることは、魔石の大きさからもわかる。
私の家の方が格上ね、とエリスは自然に思った。
「本当は僕はAランクぐらいの強さがあるんだ! けれど、しょうがないから君らで我慢してやろうって言ってるんだ!」
そんな傲慢な物言いに、男たちも当然ながらカチンときている。
エリスだって、あんなことを言われれば、無言でぶん殴るであろう。
「なんだと……ガキ、あんまり調子に乗るなよ! 魔術師がこの距離で喧嘩売って勝てると思ってんのか……」
「剣しか振れない能なしのくせに、調子に乗るんじゃない!」
「このクソガキィ……」
男に胸ぐらを掴まれ、少年はまだ余裕そうな面を見せているが、若干ながら足が震えているのを、エリスは見逃さなかった。エリスはふと歩き出し、二人の間に割って入った。
「やめなさいよ。大人げないわよ」
もしここにルーデウスがいたら瞠目したであろう。
大人げない。普段のエリスからは想像もつかないセリフであると。
ちなみに、エリスは自分の行動に酔っていた。自分はAランクの冒険者であり、怒れる男たちよりも格上。男が新人にお痛する、それを諌める自分。カッコイイ。
普段ルイジェルドが自分に対してやっていることであるが、そんなことは棚の上にポイである。
「……チッ、そうだな。確かに大人げねえ」
男はあっさりと少年から手を離した。
エリスの中では、すでに男と戦闘に入ることを想定していたため、ちょっとだけ拍子抜け。
「お前ら、行こうぜ」
男たちが立ち去り、そこには少年だけが残った。
エリスはすまし顔で、少年のお礼を待った。
『助けてくれてありがとう、あなたは?』
『名乗るほどのものじゃないわ』
『せめてお名前だけでも』
『そうね、『デッドエンド』のルイジェルド、とでも名乗っておきましょうか』
なんてやり取りを考えていた。
ちなみに、ルーデウスがたまにやっていることである。
「誰が助けてくれなんて言ったんだよ!」
少年がそんな言葉を吐いて、エリスの自慢げな顔が凍りついた。
「あのぐらい僕の魔法ならなんとかなったんだ! 勝手に出てきて勝手に解決するなよ! ブス!」
彼は幸せだった。
なにせ、一撃で気絶できたのだから。そして、先ほどの男が、まだ近くにいたのだから。
男が激昂したエリスを必死で止めていなければ、きっと少年は男として大切な二つの玉を失っていたであろう。
★ ★ ★
エリスはやや不機嫌になりながらも、ミリシオンの入り口へと来ていた。
切り替えの早い彼女であるが、まだ不機嫌である。それはなぜか。
「まって! まってください!」
気絶から回復した少年が、走って追いついてきたからだ。
「先ほどはすいませんでした。ちょっと気が動転していて……」
少年はそう言って、礼儀正しく頭を下げた。そのおかげで、エリスの不機嫌は「やや」の範疇に収まった。少年は九死に一生を得たのである。もっとも、もし一撃で気絶していなければ、エリスを追いかけようなどという蛮行には及ばなかっただろうが。
「僕はクリフです。クリフ・グリモル!」
「…………エリスよ」
エリスは『デッドエンド』の名前を出そうかと思い、やめた。
我慢せずに殴ってしまった相手にルイジェルドの名前は出せない。
「エリスさん! すごいいい名前です! その格好、剣士なんですよね! ぜひとも僕とパーティを組んでください!」
往来のどまんなかでまくし立てるクリフを、エリスは反射的に殴り倒してしまおうかと考えたが、とりあえず我慢する。
「嫌よ」
エリスはぷいっとそっぽを向いて、歩き出した。
正直、こういう相手には慣れていない。
殴ってもまだ近づいてくるなんて、ルーデウスぐらいなものである。
「そうですか、ならせめて、後ろから援護させてください! 僕も巷では賢者の卵と言われています、必ず役立ちます!」
もしこの場にルーデウスがいれば、エリスに猛烈なアタックを掛ける彼に対し「何が賢者の卵だ、どうせ無精卵なんだろ童貞野郎!」などと憎まれ口を叩いたであろう。心の中で。
エリスはそんな下品な憎まれ口は叩かない。
卵なら叩き割って目玉焼きにでもしてやろうか、と思っただけである。
「エリスさんも、僕ほどの魔術師は見たことがないと思いますよ。なにせ、そんじょそこらのAランク魔術師よりも上ですからね」
そんなことを言われて、エリスはカチンときた。
彼女の中で最高の魔術師といえば、それはすなわちルーデウスのことである。
ルーデウスはあのルイジェルドですら一目置くほどの魔術師である。たしかにAランクだが、そんじょそこらなんて一括りにされたくはない。
「ぜひともその目で確かめてみてください!」
じゃあ見てやろうじゃないの、とエリスは思ってしまった。
「わかったわ。じゃあ付いてきなさい」
「はい!」
こうして、エリスとクリフはゴブリン狩りへと出発した。
★ ★ ★
七匹のゴブリンが一瞬で焼失した。
「どうですか! 凄いもんでしょう! そこらの魔術師ではこうはいきませんよ!」
クリフはどうだと言わんばかりの顔で、全滅したゴブリンを見渡した。
ゴブリンたちは完全に炭化し、耳も取れない状態である。
「そう? 全然凄くないわ」
強がりではない。エリスは、心の底からそう思っていた。
上級火炎魔術『獄炎火弾』。
これはルーデウスが使うところを見たことがある。クリフのように長々と詠唱なんかしなかったし、威力もずっと上だった。けれど、ルーデウスなら、きっとゴブリン相手にそんな魔術は使わない。
ルーデウスなら、きっと耳を取れなくするようなヘマはしない。
また、一応クリフの力を見るということで、詠唱が終わるまでエリスがゴブリンを引きつけていたのだが、詠唱を終えた時にクリフが何も言わなかったため、危うく巻き込まれかけたのだ。
ルーデウスなら、そんな危険な真似は絶対にしない。
「エリスさんは魔術のことをよく知らないようですね。いいですか、魔術というのはそもそも……」
クリフは長々と、魔術には初級から上級とそれ以上があり、今自分が使ったのは上級魔術で、そこらの大人でも使えない高度な魔術であると語った。
もちろん、エリスは知っている。ルーデウスの授業で習ったことがあるからだ。
そして、クリフの説明より、ルーデウスの授業の方が十倍はわかりやすかった。
「わかりましたか、僕がどれだけ凄いかってことが」
殴ろうかな、とエリスは思った。
せっかく憧れていたゴブリン狩りなのに、こいつのせいで台無しであると感じていた。
ゆえにエリスは腕を組んだ仁王立ちのポーズのまま、クリフに冷酷に言った。
「もう、いいわよ、役に立ちそうにないし、帰っても」
もしルーデウスであれば、ここは一時的な撤退を選択するだろう。
だがクリフは空気がまるで読めなかった。
「何を言ってるんですか! ゴブリン数匹に苦戦するようなエリスさんを一人にはできませんよ!」
気づけば拳は振りぬかれていた。
クリフは鼻血をだらだらと流しながら、顔を押さえている。彼はすぐにヒーリングを詠唱し、鼻血を止めた。
「なにするんですか!」
「チッ」
エリスは舌打ちした。
平原で気絶させたまま見捨てていくわけにもいかないと手加減したが、調子に乗らせる結果になってしまったようである。
仕方がないのでもう一発、と拳を握りしめたところで、クリフもようやく事態に気づいた。
「ええ、もちろんわかっていますよ! エリスさんが強いのはよーくわかっています。じゃあ、今度は森の方に行ってみましょう。ゴブリンでは僕の真価が発揮できませんからね」
クリフの言葉に裏表はない。
彼はエリスに凄いところを見せたいのである。
しかし、それは決して、好きな女の子にカッコイイところを見せよう、などというものではない。
単純に強い自分に酔いしれたいだけなのだ。
「森はダメよ」
エリスは短く言った。
森はダメ。それはルーデウスが常々言っていることで、ルイジェルドもそれに同意している。
なので、エリスは素直に従うだけだ。
「エリスさんともあろうお方が、怖いんですか?」
「怖くないわ!」
が、エリスもまた単純な娘である。こんな言い方をされてしまえば、簡単に釣れてしまう。
ボレアス家は駆け出しの冒険者如きになめられてはいけないのである。
「森ね! いいわよ、行きましょう!」
こうして、二人は薄暗い森へと足を運んでいく。
「森といっても、ミリスは大したことないわね」
エリスはそう言いながら、ウータンと呼ばれる猿の魔物を斬り捨てた。
Dランクの魔物であるが、エリスの敵ではない。
「そうですね、僕の敵でもないです!」
クリフもまた、中級の風魔術でウータンを倒しつつ、森の中へずんずん入っていく。
「あっ」
ふと、エリスが声を上げる。
「どうしましたエリスさん!」
クリフは嬉しそうにエリスに近づいてくる。
エリスは露骨に嫌そうな顔をする。
そして腕を組み、足を肩幅程度に開き、顎を上げてクリフを見下ろした。
「あなた、帰り道はちゃんと把握してる?」
「把握してないです」
当然、クリフはそんなものを把握してなどいない。
突発的な思いつきで行動したため、森に入る装備などというものは持ってきていないのだ。
「そう、じゃあ迷子ね」
エリスは平然と言い放った。
「…………」
クリフは押し黙った。そして、その顔がみるみる青くなっていく。
「ど、どうしましょう」
エリスが平然としていたため、クリフは彼女に何か策があるのだと考えた。
しかし、エリスもまた内心ではまずいと思っていた。森の中で迷子になったなんて知れたら、二人に呆れられる。ゴブリン狩りでどうして森に入ったのだと、呆れられる。
もっとも、態度には決して出さない。グレイラット家の淑女は常に泰然としていなければならないのだ。
「クリフ、ちょっと空を飛んで上から町の方向を確かめなさい」
「そんなこと、できるわけないじゃないですか」
「ルーデウスならできるわ」
「ルーデウス? 誰ですかそれは」
「私の先生よ」
「ええっ!?」
エリスは一つ息をつく。言い争いをしても意味がない。こんな時はどうするか。
そして思いつく、ギレーヌに、迷子になった時のことを教えてもらった。
確かそう、木の枝を集めて火をつけるのだ。
煙が空に上り、遠くからでも発見できる。
──しかし、誰が。
ルイジェルドは用事があると言っていた。ルーデウスもだ。
誰も気づかない。
「…………」
エリスは、知らず知らずのうちに腕を組み、口をへの字に曲げて仁王立ちしていた。
目を閉じてよく考える。ギレーヌは言っていた。不安な時こそ、冷静になれ、と。
だから彼女はどんな時でも慌てない。
「え、エリスさん、どうしましょう」
「この森には、別の冒険者がいるはずよ」
「な、なるほど、彼らを頼れば……探しましょう」
クリフは慌てて走りだそうとするが、エリスは動かない。
ルイジェルドに教わった。こういう時は、動いてはいけない。動かないで、気配を探るのだ、と。
気配の探り方も教わった。第三眼がなくても、音と空気、そして魔力の流れは感じ取れる。
エリスは未熟だが、毎日練習はしている。
「エリスさん……?」
「黙って!」
エリスは深呼吸をして、眼を閉じたまま、心を研ぎ澄ませる。
森の音。葉のこすれあう音。獣が動く音。虫が飛ぶ音。そして、かすかに聞こえる剣戟の音。
「見つけたわ。こっちよ」
即決即断。エリスは迷うことなく歩き出した。
「なんですか、何が見つかったんですか!」
「人よ、向こうにいるわ」
「どうやって!?」
「気配を探ったのよ」
「それも先生に習ったんですか!?」
聞かれ、エリスは少しだけ考える。
ルイジェルドは先生か。先生だろう。ギレーヌほどではないが、彼にも様々なことを教わっている。先生、いや、師匠と呼んでも差し支えない人物である。
「そうよ」
「凄いんですね、そのルーデウスって人は……」
「ん? ……そうね、ルーデウスは凄いわね」
なぜ突然ルーデウスの名前が出てきたのかわからないまま、エリスは先を進む。
森を抜けた瞬間、轍の真ん中で、馬車が横転しているのが見えた。
「伏せて!」
「ぐえっ!」
エリスはとっさにクリフの頭を掴み、地面に叩きつけ、自らもしゃがみ、状況を確認する。
「……」
立っている人物は六人。
一人は兜までつけた全身甲冑の騎士。
騎士は木に背中を預けるように立ち、剣を構えている。
その周囲には、黒ずくめの男たち、五人。黒ずくめは騎士を取り囲んでいる。
周囲には、三つの死体。全員が囲まれている騎士と同じ鎧を身につけていた。
黒ずくめはじりじりと騎士に対する包囲を縮めている。
もはや戦力差は歴然としているというのに、なぜあの騎士は逃げないのか。
よく見ると、騎士の背後にある木。その根本には、一人の少女がしゃがみ込んでいる。
不安と絶望にまみれた顔で、顔は涙に濡れている。
「エリスさん、あの鎧は神殿騎士団ですよ!」
クリフが小声で告げてくる。
エリスの心臓が高なった。
神殿騎士団。聞いたことがある。ミリスにある三つの騎士団の一つ。
ミリスの自国防衛を司るエリート集団、聖堂騎士団。
世界中にミリスの教えを広め、その威光を知らしめんと傭兵紛いの働きをする、教導騎士団。
そして、異端審問官を抱え、異教徒を断罪する恐怖の代名詞、神殿騎士団。
聖堂騎士団は白。
教導騎士団は銀。
神殿騎士団は蒼の鎧を身につけている。
遠方からでもそれとわかる蒼天色の鎧。
間違いない。目下追い詰められているのは、神殿騎士である。
「貴様ら! この御方がどなたか、わかっているのだろうな!」
声を上げて初めてわかる。
追い詰められている騎士は女だった。黒ずくめの男たちは、互いに顔を見合わせ、フッと笑った。
「無論だ」
「ならばなぜ!」
「言うまでもなかろう」
「貴様ら! 教皇派か!」
エリスには、彼らの話が飲み込めない。
だが、黒ずくめの悪そうな奴らが、あの少女を殺そうとしているのはわかった。
エリスは腰の剣に手をかけた。クリフがそれを見咎める。
「な、なにをする気ですかエリスさん。どうみてもヤバイですよ。あの子は次期教皇候補と言われている神子です。てことは、あの黒ずくめはきっと、ミリス教皇お抱えの暗殺集団です。手練れ揃いです、いくら僕でも勝ち目はありません……」
クリフがなぜそこまで詳しいのか、エリスは疑問にすら思わなかった。彼女が気にしていたのは、今自分が助けなければ、あの少女は殺されるということだけである。
そして、エリスは『デッドエンド』の一員だ。子供を見捨てたとあっては、ルイジェルドに申し訳が立たない。ルーデウスも常々そう言って、人助けをしている。
「ここは気づかれないように、やり過ごしましょう……」
「無駄よ。もう気づかれているわ」
エリスはわかっている。あの黒ずくめの一人は、クリフを伏せさせた際に、こちらに気づいた。
黒ずくめが何を考えているのかはわからないが、何を考えていようと、エリスは先手を取るつもりであった。
「クリフはそこで隠れているといいわ!」
「え、エリスさん!」
エリスは抜刀しつつ、飛び出した。
黒ずくめが一瞬で散開するが……。
「遅い!」
エリスの踏み込みは、黒ずくめの男の予想を軽く凌駕していた。
剣神流上級技『無音の太刀』。光の太刀の下位に位置するこの技は、風切り音を一切残さない。
エリスの剣術の腕は、ギレーヌとルイジェルドにより、相当に伸びている。
剣は黒ずくめの一人の肩から入り、肋骨をたやすく両断し、袈裟懸けに真っ二つにした。
エリスは初めて人を斬った感触に戸惑うことなく、次の相手に剣を向ける。
黒ずくめはエリスを囲むように動くが、エリスの動きはそれ以上に速い。
彼女はルイジェルドから、複数に囲まれたときの動き方をよくレクチャーされている。
魔物には群れる奴も多い。囲まれる前に倒しきるのがセオリーである。
「ハアァァァ!」
一人の黒ずくめが、またたく間に斬り捨てられた。
男たちの間に動揺が走る。エリスのリズムは変則的で、意識の外から予備動作なしの斬撃が飛んでくる。回避に専念してもなお避けにくいものを、別のことをしながらで回避できるわけもない。
だが、黒ずくめもプロである。
一人を犠牲にし、包囲が完成する。二人の黒ずくめが時間差でエリスに躍りかかった。
速い──しかしルイジェルドほどではない。
魔大陸のパクスコヨーテのように上下の連携があるわけでもない。
──温い。
「そいつらの短刀には毒が塗ってある! 気をつけろ!」
背中に少女を隠していた騎士は、そう叫びつつ包囲の外から、男の一人に斬りかかっていた。
エリスは彼女の動きから、その後の黒ずくめたちの動きを正確に予測しつつ、包囲の綻びを見つける。
勝てると確信し、それと同時に、一人を斬り伏せた。残りは二人。
「くっ、引くぞ!」
黒ずくめの一人がそう叫ぶと、二人は一瞬で踵を返し、逃走にかかる。しかし、エリスは詰めの甘い女ではなかった。またたく間に片方に追いつくと、その背中に鋭い斬撃を放つ。黒ずくめは上半身と下半身が離れ、臓物を撒き散らしながら倒れた。
もう一人は背後を見ることなく、平原の彼方へと消えていった。
「フンッ!」
エリスは鼻息を一つ。
剣についた血糊を、一振りで飛ばす。
外面はいつも通りだが、しかし心臓はバクバクと動いていた。
考えてみれば、人を相手にした実戦は初めてであり、人を殺したのも初めてである。
しかも、相手は毒塗りの短刀を持っていた。一撃でももらえば致命傷となる武器である。
ルーデウスやルイジェルドといった、背中を守ってくれる人もいない。考えなしに飛び出したが、あの女騎士がいなければ、死んでいたかもしれない。
──だが、エリスはそんなことをおくびにも出さない。
剣を鞘へと納刀し、女騎士へと振り返る。
「ごめんなさい。一人逃したわ」
その言葉に、女騎士はやや呆気に取られた。
まだ成人もしていないであろう少女が、決死の修羅場を大立ち回りでくぐり抜け、あまりにも平然としていたからだ。
女騎士は兜を脱ぐことなく、腹のあたりに拳を当てて、ミリス騎士の正式な礼をする。
「ご助力を感謝致します」
「子供が無事ならいいわ」
エリスは返礼せず、ルイジェルドの言い方を思い返しつつ、ぶっきらぼうに言った。
「私は神殿騎士団のテレーズ・ラトレイアと申す者です。冒険者とお見受けしますが、名前を伺っても?」
「私はエ……」
エリスは本名を名乗ろうとして、はたと止まった。
そうじゃない。ルーデウスはそうしていない。
「『デッドエンドのルイジェルド』。こう見えてもスペルド族よ」
スペルド族というと、テレーズは表情を険しくした。
エリスは知らないことであるが、神殿騎士団は魔族の排斥を唱っている。
無論、エリスにスペルド族の特徴はないので、テレーズも表情を緩めた。
本名を名乗らず、神殿騎士が快く思わない種族を名乗るということは、自分たちと、ひいてはこの一件に関して、深く関わりあいになりたくないのだと判断したのだ。
要人を助けても礼を要求しないその態度を、テレーズは好ましく思った。
「そうですか。わかりました……」
テレーズは腕を組んで睨んでくるエリスをまじまじと見て、その顔を覚えた。
それから、口笛を吹く。
すると、森の奥から馬が一匹、走ってきた。馬車を引き倒された時に逃げ出した馬が、訓練通りに戻ってきたのである。
彼女は少女を馬に乗せると、自身も飛び乗る。
「何か困ったことがあれば、神殿騎士テレーズの名を!」
テレーズはそう言い残し、馬に乗って走り去る。
エリスはそれを黙って見送る。
そして、物陰で腰を抜かしたままで立てない少年は、走りゆく馬上の騎士と、それを見送る恐れ知らずの赤毛の剣士を、まるでお伽話の一場面であるかのように、ただただ見ているだけだった。
★ ★ ★
ミリス教団のある司祭が、小人族の女性と恋に落ちた。
二人の間に生まれた子供が成長し、一人の女性と結婚。そうして生まれたのがクリフである。
クリフが生まれた頃、その司祭は権力争いの真っ最中であった。
クリフの両親はそれに巻き込まれ、死亡する。
司祭は孫であるクリフを権力争いから遠ざけるため、一旦孤児院へと預けた。
そして、司祭は権力争いに勝利して教皇となり、クリフを迎え入れた。
つまり、クリフ・グリモルは教皇の孫である。もっとも、それを知る者は教団内でも、ごく僅かである。
そんなクリフは、今回襲撃を受けていたのが誰か、よくわかっている。
現在進行形で祖父と争っている大司教派の切り札であり、奇跡の力を持つとされる神子だ。
面識もある。そんな子がどうしてあんなところにいたのかは、クリフにもわからないが、あの黒ずくめの集団はよく知っている。
クリフを教えていた教師たちだ。彼らがそういう仕事を担当しているということを、クリフは知っていた。
そして、彼らの強さも知っていた。
何度も稽古で相手をしたことがあるが、少なくとも、自分は一度も勝てなかった。
そんな彼らを、エリスは物ともしなかった。
実際はギリギリの勝利であったのだが、クリフの目には、自分が逆立ちしても勝てない相手を圧倒したと映った。
気づけば、クリフはエリスを憧れの目で見ていた。
町に向かって疲れた顔で歩く彼女。この人はきっと、すごい人になると思うと、思わずこんな言葉が口からあふれていた。
「エリスさん、結婚してください!」
「えっ、絶対に嫌よ!」
エリスは即座に嫌そうな顔をつくり、即答した。
クリフは、この才能あふれる自分の求婚を断るなんてありえないと思った。
なぜだろうと、考える。
彼女との本日の会話を鑑みる。
そう、先生という存在だ。彼女は、先生が、先生がと言っていた。名前は確か、ル……ル……。
「ルーデウス」
その単語を思い出し、口に出してみると、エリスが振り向いた。
「ルーデウスというのは、どういう人なんですか?」
クリフは数分後、質問をした自分を呪うこととなる。
エリスは無口な子だと思っていたが、そんなことはなかった。
ルーデウスという人物を語らせれば自分の右に出る者はいないとばかりに、自慢げに話しだした。
平原から冒険者ギルドに戻るまで、ずっとである。
しかもその表情はまさに恋する乙女のそれであり、内容は褒め倒しであった。
クリフを嫉妬させるに十分なものであった。
「……僕、そろそろ帰りますね」
クリフは自分でも憮然とした顔をしているのを自覚しながら、エリスにそう言った。
エリスはまだまだ語り足りないという感じだったが、クリフが帰るというと、「あっそ」という感じで手を振った。
「じゃあね」
そのそっけない態度は、先ほど熱烈に一人の人物を語っていたとは思えないものであった。
クリフは、その背中が見えなくなるまで、無言で見送った。
この強くて美しくて完璧なエリスをここまで骨抜きにさせたルーデウスという男。
クリフはまだ見ぬルーデウスのことを思い浮かべながら教団へと戻り、探していた人々にお叱りを受ける。
そして、今回の一件により教団内の権力闘争が激化。
クリフがミリシオンにいることを危険と考えた教皇が孫を別の国へと移すのだが、それはエリスとはまったく関係のない話である。
ちなみに、エリスはというと、宿に帰りついて落ち込んだルーデウスを見た瞬間、今回のことを記憶の片隅へとやって忘れてしまうのだが、それはまた、別の話である。
第七話 「中央大陸へ」
二ヶ月経過し、港町ウェストポートに到着した。
ミリス大陸の北端にあるザントポートとそっくりな町並みだが、町の規模は大きい。
ミリス神聖国首都からアスラ王国の首都までの道は、この世界におけるシルクロードで、各所に交易の拠点となりうる町があり、ウェストポートもそのうちの一つだ。
ミリシオンの商業地区ほどではないが、いくつかの商会の本部があり、その傘下にいる商人たちがひしめき合っている、大きな町である。
さて、馬車はここまでだ。
この世界では生前のフェリーと違い、馬車を積載して運ぶようなことはできないので、魔大陸からミリス大陸へと渡った時と同様、乗り物を売っぱらい、海を渡った後に買い直すのだ。
トカゲの時と違ってあまり情も移っていないので名前をつけてやろう。さようならハル○ララ。
馬を売却した後、俺たちは関所へと赴く。
ウェンポートと違い大きな建物で、入り口には甲冑姿の衛兵も立っている。
甲冑姿の騎士はミリシオンの町中でもよく見かけた。一見すると堅牢な装備だ。
だが、エリスやルイジェルドを見ていると、あんな鎧で身を守れるのかと不安になる。
この世界の生物は攻撃力が高い。甲冑なんか着ていたところで、一発攻撃を食らえばパカンと下着姿になってしまうことだってありうる。攻撃を受けた反動で穴に落ちればジエンドである。
と、冗談はさておき。
関所に入ってみると、中は人でごった返していた。
冒険者風の人々、商人風の人々。そんな群衆を精力的な表情でテキパキと捌く職員。
閑散とし、職員のやる気もなかったウェンポートとは大違いである。
「こんにちは」
「はい、なんでしょうか」
俺はとりあえず、カウンターの一つに向かい、係員に話しかける。
ここの受付の人も巨乳である。この世界には、受付は巨乳でなければいけないという不文律でもあるのだろうかと、そんなことを考えつつも、おくびにも出さない。
「あの、渡航の申請をしたいのですが」
「はい、それではこちらをお持ちになってお待ちください」
と、渡されたのは木製の番号札で、三四という数字が書かれていた。
実にお役所仕事という感じだ。
待合所に戻って椅子の一つに座ると、すぐにエリスが隣にちょこんと座った。
ルイジェルドは立っている。周囲を見ると、俺たちと同じように待っている人が多いようだ。
「しばらく掛かりそうですね」
「書状は渡さないのか?」
ルイジェルドの問いに、俺は首を振った。
「番号が呼ばれてからですよ」
「そういうものか……」
エリスは、なにやらそわそわしている。
彼女は、あまり待つということに慣れていない。仕方がないのかもしれない。
「ルーデウス。なんか見られてるわ……」
エリスに言われ、彼女に視線を送る存在を探す。
彼女を見ていたのは、衛兵たちであった。彼らはエリスの方をチラチラと見ていた。エリスはその視線を受けて、ムッとした顔で睨み返している。
「喧嘩しちゃダメですよ」
「しないわよ」
信用ならん……が、さて、衛兵がエリスを見る理由はなんだろうか。
心当たりがない。
彼女の美しさに眼を奪われているのだろうか。エリスは最近、結構美人になってきているけど、まだまだ子供の範疇だ。騎士たちが全員ロリコンというわけでもなければ、ありえまい。
「三四番の方、どうぞ」
呼ばれたので、立ち上がってカウンターへ。
受付嬢に書状を渡し、渡航したい旨を告げると、彼女は笑顔で書状を受け取り、裏面の宛先の名前を見た瞬間、怪訝そうな顔をした。
「少々お待ちください」
そして、立ち上がると事務所の奥へと消えていった。
しばらくすると、事務所の奥で何か大きな音がした。
同時に、誰かの怒鳴り声。事務所の奥から衛兵が走り出てきて、別の衛兵に何か耳打ちをする。
険しい面持ちのまま、耳打ちされた衛兵が外へと走っていく。
なにやらきな臭い雰囲気である。
ルイジェルドを信用して書状を出してはみたものの、やはりガッシュ・ブラッシュという人物について、もっとくわしく調べたほうがよかったかもしれない。
「……おまたせしました!」
先ほどの受付嬢が戻ってきた。緊張の面持ちを隠せていない。
「バクシール公爵がお会いになるそうです」
嫌な予感しかしなかった。
「ミリス大陸税関所長、バクシール・フォン・ヴィーザー公爵である」
その豚は豚にそっくりだった。
間違えた。その人物は豚にそっくりだった。
首まわりは脂肪で覆われ、顎は完全に埋もれている。ペタリと額に張り付いた淡い金髪。目の下にはクマがあり、さながらたぬきのような印象も受ける。豚でたぬきで不機嫌そうな表情を隠さない。
昔、あんな感じの男を見たことがある──鏡の前で。
「ふん、薄汚い魔族がこんな書状を持ってこようとはな」
バクシールは豪華そうな革張りの椅子に座っている。
立つことなく、手に持った紙をパンと叩き、椅子をギシギシと鳴らしながらこちらを睥睨する。
高級そうな執務机の上には、大量の書類と共に、封の破られた便箋が見える。
となれば、あの紙が手紙の中身だろう。
「大物の名前を出したものだ。封もまた本物によく似ておる。だが儂は騙されんぞ。これは偽物だ」
バクシールがバッと紙を放り投げたのを、俺は反射的に掴みとった。
この者、スペルド族なれど、私が大恩を受けた者也。
言葉少ななれど、心意気や天晴。
渡航費用を無料にし、丁重に中央大陸へと送り届けるべし。
──教導騎士団団長・ガルガード・ナッシュ・ヴェニク
俺はその名前を見て、めまいがしそうになった。ガッシュ・ブラッシュという名前はどこにいったのか。
ガルガード・ナッシュ・ヴェニクって……あ、略してガッシュなのか。
あるいは気さくな人物なら、「自分のことをガッシュと呼んでくれ」とでも言うかもしれない。
ルイジェルドがそれを真に受け、ガッシュという名前だと思い込んだのかもしれない。
しかしブラッシュとはどこから出てきたのか。
しかも、その役職。
教導騎士団団長。ミリス三騎士団の一つ、その団長。
頭が痛くなる。なんでそんなのがルイジェルドの知り合いなんだ……。
いや、予想はできる。
例えばそう……立場だ。教導騎士団団長ともなれば、それなりに高い地位にいる人物であろう。
それがスペルド族と仲良くしていると吹聴されるのはまずいから偽名を使った、とか。
もっと単純に考えてもいい。
ルイジェルドと出会ったのは四十年前だというし、その間に結婚やらで改名した、とか。
「大体、あの無口な男が手紙など書くわけがない。儂はあの男をよく知っておる。筆不精どころか、必要な書面すら書かない男だ。それがお前のような魔族のために儂に書状? 冗談もほどほどにするがいい」
ルイジェルドはというと、難しい顔をしている。
自分の持ってきた手紙が偽物だと断じられた理由は、自分がスペルド族だから。
彼にしてみれば、そう思ってしまうかもしれない。
実際、パウロの話によると、このバクシールという男は魔族嫌いで有名だそうだしな。
あながち間違ってもいないかもしれない。
しかし、有名だというのなら、ガッシュだかガルガードだかわからないが、彼もこのバクシールという男がどういう男か知っていたのだろう。なら、もう少し説得するような文面にしてほしいものである。
あるいは、本当は偽物なのか?
いやいや。ルイジェルドの話を思い出せ。
ガッシュがいたのは大きな建物だという話だ。キシリス城と比べられるほどに大きな建物。個人の家にしてはかなり大きいと言えようが、それが騎士団の本部か何かであったならどうだ。建物は大きく、中には騎士も大勢いただろう。団長ともなれば、その場にいる騎士は全員が部下であるはずだ。ルイジェルドの言う、「配下がたくさんいた」という言葉とも合致する。
とはいえ、それがわかったところで意味はない。
バクシールはすでに書状を偽物だと断じている。
そしてここまで来れば、偽物でしたか失礼しましたさようなら、とはいくまい。
俺は一歩前へと出た。
「つまり、公爵閣下はこの書類が偽物であると?」
「なんだ貴様は……子供は引っ込んでいろ」
バクシール公爵は怪訝そうな顔をした。子供扱いされるのは久しぶりな気がする。
新鮮な気分だ。子供扱いされたいときには子供扱いされず、大人扱いされたいときには子供扱いされる。ままならん。
そう思いつつ、とりあえず俺は右手を胸に手を当て、貴族風の挨拶をする。
「申し遅れました。私はルーデウス・グレイラットと申します」
そう言うと、バクシールはぴくりと眉を動かした。
「グレイラット……だと?」
「はい。恥ずかしながら、アスラの上級貴族、グレイラット家の末席に名を連ねる者でございます」
「ふむ……だが、グレイラットには太古の風神の名が付くはずだ」
「はい。私は分家ですので、その名を名乗ることは許されておりません」
分家。そう聞いたバクシールの目が俺を見下すものへと変わりかける。
その瞬間、俺はエリスを手のひらで示す。
「ですが、こちらのエリスお嬢様は、正真正銘ボレアス・グレイラットの名を持つ者でございます」
ぽんと背中を叩くと、エリスが一歩前に出た。
彼女はびっくりした顔で俺を見て、しかしそれ以上は動じない。
腕を組んで足を肩幅に開き──いやいや、そうじゃないと、腕を外し、スカートの端をちょこっと摘んだ淑女の挨拶をしようとして、しかしスカートでないことを思い出し、俺と同じような、胸に手を当てた挨拶をする。
「フィリップ・ボレアス・グレイラットが娘、エリス・ボレアス・グレイラットと申しますワ」
なんか硬い上、ちょっと間違っている気がする。
バクシールの顔色を窺う。
ちょっと判別しがたいが……まあいい。ここはエリスの家の威光に頼ろう。
「ふん、なぜアスラ貴族の娘がここにいる」
当然の疑問に対し、嘘は必要ない。
「公爵閣下は、二年ほど前にフィットア領で起こった魔力災害をご存知ですか?」
「知っておる。大量の人間が転移したそうだな」
「はい。我々もそれに巻き込まれました」
そこから、俺はお嬢様を守るため、ルイジェルドを護衛にして魔大陸を縦断。
ミリス大陸への関税では手持ちの財産を売ってなんとかしたが、ミリスから中央大陸に渡るには資金が足りない。特にルイジェルドの渡航費用は高すぎる。
なので、グレイラット家の知己であり、ルイジェルドの親友でもあるガルガード卿を頼った。
ガルガード卿は快く書状を書いてくれた。
そういうストーリーをでっち上げた。
「お嬢様はこのように冒険者の格好をしていますが、それは高貴の出だと気づかれて良からぬ輩に目を付けられぬため。公爵閣下もおわかりでしょう」
「なるほど」
バクシールの顔は渋いままである。
「つまり貴様らは、最近ミリシオンで暴れている、奴隷を無理やりにでも奪い取る『フィットア領捜索団』の一味であると、そういうわけか」
「ち……違いますよ、何を言ってるんですか」
「儂はエリス・ボレアス・グレイラットなどという名は知らん」
ブタのように鼻を鳴らし、バクシールは「だが」と続ける。
「パウロ・グレイラットとかいう小悪党の名前は知っておる。最近、奴隷を無理やりに攫うという、噂
のな」
パパの悪名が酷い。
「つまり、公爵はこう仰りたいわけですね。ガルガード様の書状は偽物、エリス様もアスラ貴族などではない。そして我々はそのパウロ・グレイラットとかいう、女にだらしなく、足が臭く、酒ばかり飲んで息子に当たり散らし、娘に苦労をさせているダメ人間の一味だと」
「うむ」
なんてひどい奴だろうか。
パウロはあいつなりに頑張っているんだ。確かに至らないところもあるし、方法も間違っているかもしれないけど、それをダメ人間だなどと切って捨てるとは、まったく許せない。
「なぜ書状にされていた封印も偽物だと?」
そう言って俺は机の上、便箋を指さす。
バクシールは少しばかり眉をひそめ、そして頷く。
「教導騎士団の印は偽造品が出回りやすいのだ」
そうなのか。それは初耳だな。
「なぜ私の雇い主であるお嬢様が偽者であると?」
「アスラ貴族の令嬢がそんな山出しの剣士みたいであってたまるものか」
エリスを見ると、彼女は腕を組んでのいつものポーズ。
その腕は傷こそないものの、令嬢とは思えないほど日焼けしており、そこらの若手冒険者よりも、引き締まった筋肉が見える。
「なるほど。公爵閣下はサウロス様をご存知ないようだ」
俺はフッと笑う。バクシールはすぐに食いついた。
「サウロス……だと? フィットア領の領主のか?」
エリスの名前は知らずとも、サウロス爺さんの名前は知っているらしい。
「そして、エリス様の祖父の、です。あのお方はエリス様に剣士としての英才教育を施したのです」
「なぜそんなことを……」
「これは内密な話となりますが……。エリス様はノトス家に嫁ぐことが決まっているのです。そして、サウロス様はノトス家の当主様がお嫌いでして……」
「なるほど」
要約すると、エリスがこんな山猿みたいに育ってるのは、ノトス家の当主を寝室でぶっ殺すために鍛えたからだよ、って意味である。
エリスは首をかしげている。
意味がわかったら俺の顔が陥没するだろう。
「ゆえに、お嬢様はアスラへと戻らねばなりません。そんなお嬢様を偽者と断じるのであれば、我々はミリシオンへと戻り、然るべきところに願い出るまでです」
その然るべきところがどこになるかはわからない。
調べてないからな。
「ふん、本物だというのであれば、ここで証明してみせよ」
「ガルガード様の書状が何よりの証拠」
「くだらん。水掛け論だ」
「水掛け論でも結構。あなたにアスラのグレイラットと対立する気がおありか?」
やばい。自分でも何を言ってるのかわからなくなってきた。
しかし、とりあえず通じているらしく、バクシールはギロリとした目で俺を睨んでいる。
「よかろう。ならば、お前とそのお嬢様、二人の通行を許そう」
「しかし、護衛は」
「バクシール公爵の名において、騎士を数名つけよう。魔族などに頼るよりは、そちらの方が安全であろう?」
なるほど、魔族を通すぐらいなら、手すきの騎士を二人、つけるということか。
とにかくバクシールはルイジェルドを渡航させるつもりはないらしい。ここまで意固地とは……目の当たりするのは初めてだが、思った以上に魔族に対する差別意識が強い。
さて、どうしたものか。
ルイジェルドだけ、別で運ぶべきか。
それでまた密輸人と喧嘩か……ありうる話だ。いやだなあ。
──コンコン。
と、その時、不意に部屋がノックされた。
「なんだ、今は取り込み中だぞ?」
バクシールが怪訝そうな顔をするが、扉は返事を待たずに開いていた。
そこには、青色の甲冑に身を包んだ、金髪の女性が立っていた。
「失礼、こちらに『デッドエンドのルイジェルド』がいると聞いたのだが」
「……母様?」
ゼニスだった。
「えっ?」
俺が母様とつぶやいたことで、その場にいた全員の視線が女性へと向かった。
彼女はムッとした顔で俺を睨みつけた。
「私は独身だ。君のような大きな子供はいない」
ちょ、ゼニスさん? 俺の知らないうちに記憶をなくしたんですか?
それともパウロに愛想を尽かしたんですか?
そう、思いつつ、まじまじと見つめると、ゼニスと少しばかり違う部分が明らかになった。
数年別れていたこともあってゼニスの顔はあまり覚えていないのだが、顔の輪郭や髪の色も少し違う。別人だ。
「失礼。行方不明の母に似ていたもので」
「……そうか」
憐憫の眼差しで見られた。
母親と生き別れた子供に見られたのかもしれない。最近はあまり子供扱いされないが、俺も見た目は子供だからな。
「これはこれは……左遷されたばかりの神殿騎士殿が、いかなる用だ?」
バクシールはフンと鼻息一つ、ゼニス似の騎士を睨みつけた。
「ミリス国内にスペルド族が現れたのだ。仕事熱心な私がここに来るのは当然だろう?」
「お前の着任は十日後からだ。首を突っ込むな」
「首を突っ込むな? おかしな話だ公爵。確かに私はまだ正式には着任していない。しかし、前任はすでにミリシオンへと発ち、この場にはいない。税関にて問題が起きた時は神殿騎士が事を運ぶはずだというのに、この場には私以外の神殿騎士の姿がない。一体これはどういうことか?」
ゼニス似の騎士がそうまくし立てる。
バクシールは「ウッ」と顔色を悪くした。
「税関の守護は二つの頭にて行われるべし。それはミリス教団の定めた絶対の鉄則。よもやバクシール卿。ミリス教団に弓引くつもりではあるまいな」
「まさか、そんなことはない。ただ、そなたもまだこの町に来て間もない。ゆっくりと羽を伸ばされてはどうかとだな……?」
「必要ない」
ブタ公爵の顔が茹で上がったタコみたいになっていた。
こりゃ次に豚肉を食べるときは美味しく食べられそうだ。
「それで、どんな話になっているのか?」
この騎士は、どうやら公爵と同じぐらい偉いらしい。
普通なら、公爵といえば貴族でも最上級であるはずだが……。
ミリス神聖国は宗教色が強いから、そのへんが関係しているのだろう。
「実は……」
と、バクシールが説明する。
時折バクシールの思い込み発言があったので、俺が適当に補足しつつ説明。
女騎士は、それを黙って最後まで聞くと、こちらを一瞥。
「ふむ……確かに魔族だな……」
特に、ルイジェルドには強い目を向けるが、エリスを見た瞬間、その目の力が緩んだ。
そして最後に、俺と目が合い、はたと考えるように顎に手を当てた。
「……君、先ほど私と母親を間違えたと言ったな。母親の名前を聞いても?」
「ゼニスです。ゼニス・グレイラット」
「父親の名前は?」
俺はチラリとバクシールの方を見る。
うーむ。言いたくないなぁ……。
「パウロ・グレイラットです」
一応、正直に言ってみたら、バクシールの眼が見開かれた。
俺の父親は例のクズ人間とは別人。そう言い張ろう。
俺の父親は神様みたいな人だよ。ちょっと叩けば金だってくれる。
「そうか」
女騎士はそう言うと、しゃがみこんで俺をギュっと抱きしめた。
「……えっ!」
驚いた。いきなりの抱擁であった。
「大変だったな……」
そう言いながら、彼女は俺の頭を撫でた。
ごつい甲冑なのであまり感触的にはよろしくないが、フワリと芳しい女の香りがした。
自然と俺の下半身がおっき……しない。
おかしい。
なぜだ、息子よ、どうしたというのだ。お前の大好きな女の汗っぽいスメルだというのに。
この間だってエリスので……と、エリスの方を見ると、眼を見開いて拳を握りしめていた。
怖い。
「えっと……あの?」
女騎士はぽんぽんと俺の頭を撫でてから、すっくと立ち上がった。
そして、俺の方を見ず、バクシールに宣言した。
「彼らの身柄は私が保証しよう」
「なに! 魔族もいるのだぞ!」
慌てるバクシールを尻目に、女騎士は俺の手から書状を奪い取ると、サッと目を通す。
「書状も問題ない。ガルガード殿の筆跡だ」
「まさか、神殿騎士がミリス教団の教えに逆らうというのか……」
そこで、エリスが「あっ」と声を上げた。
女騎士がエリスに向かい、ウインクする。
なんだ?
「神殿騎士団『盾グループ』の中隊長であるこの私が言っているのだ」
「くっ、部下を失ってこんなところに左遷されてきた分際で」
「ふん。その言葉、そっくりそのままお返ししよう。もっとも、任務を果たした私と、途中で断念したあなたとでは、随分と立場が違うがな」
バクシールは、ぐぬぬと歯噛みをした。どうやら、彼も左遷されてここにいるらしい。そう考えると、公爵という地位でも矮小に思えてくるから不思議だ。
バクシールの目が、憎悪に染まっていく。
「貴様、いくら高貴なる出自だといっても、あまり図に乗ると……」
バクシールの文言は最後までは発せられなかった。
女騎士がぺこりと頭を下げたのだ。
「いや、すまん。言いすぎたな。こんなところに来た以上、私もお前と仲たがいするつもりはないのだ。今回は、私的な件も絡んでいるのだ。許してほしい」
うまいタイミングだと思った。
言いたい放題言ったのち、あっさりと謝る。バクシールの怒気も、今の一言でスルリと抜けた。
今度誰かを怒らせた時に真似しよう。
「私的な件だと?」
「うむ」
バクシールの怪訝そうな顔に、女騎士はこくりと頷いた。
そして、俺の肩にポンと手を置く。
「この子は私の甥なのだ」
なんだってぇ!?
★ ★ ★
テレーズ・ラトレイア。
彼女はミリス貴族であるラトレイア家の四女であり、若くして神殿騎士団の中隊長に就いた新進気鋭の騎士である。
実家はラトレイア伯爵家。ゼニスの実家もラトレイア伯爵家。
俺が彼女の身内であると知ると、バクシールは何かを諦めたような顔になり、大きなため息をついて、俺たちの渡航費用をタダにしてくれた。
現在、俺はウェストポートの宿屋で、テレーズに抱きかかえられている。
部屋にいるのは俺とテレーズとエリスの三人だ。ルイジェルドは空気でも読んだのか、この場にはいない。
「ルーデウス君。君のことは姉様からの手紙で知っていた」
「そうですか。母はなんと?」
「すごく可愛いと。実物を見て、まさかと思ったが、確かにこれはすごい可愛い」
テレーズはそう言いながら、俺の首筋に顔を埋めてくる。
思えば、約十二年間、生意気だの胡散臭いだの気持ち悪いだのとは言われてきたが、可愛いと言ってくれたのはゼニスだけだったように思う。
しかし、巨乳美人な人に抱えられているというのに、なぜか俺の股間のレールガンは超電磁な何かをコイントスしない。そういえば、ゼニス相手にも俺のヴィクトリーはスタンダップしなかった。
考えてみれば、ノルンとも必要以上に仲良くしようとは思わなかった。
……血がつながっているからだろうか。
「テレーズ。そろそろルーデウスを離しなさい」
エリスは頬杖をついて、テーブルをトントンと叩く。
機嫌が悪そうだ。嫉妬しているのかもしれない。俺は罪な男だ。
「エリス様。お気持ちはわかりますが、いつまたルーデウス君と会えるかわかりません。そして、きっと次に会う時はこの可愛らしさは失われているでしょう。ほんのひと時の思い出なのです。どうかご容赦を」
テレーズは悪びれもせず、俺の身体を撫で回してくる。
「テレーズさん、なぜエリスに対しては敬語を?」
「命の恩人だからだ」
そこを掘り下げて聞いてみる。
エリスがゴブリン討伐に出かけた時、偶然にも敵性勢力に襲われて絶体絶命だったテレーズを助けた。
テレーズはその時、ある要人の護衛中であり、エリスがいなければ、要人も含めて命を奪われていた、ということらしい。
まったく聞いていない話だ。エリスを見ると、彼女はバツの悪そうな顔をした。
「言うの、忘れてたわ……」
エリス曰く、俺が落ち込んでいるのを見て、ゴブリン討伐のことはすっかり記憶の彼方に消え去ってしまったらしい。
俺のせいか。じゃあしょうがないな。
テレーズは、(背後から抱きしめられているのでわからないが)恐らく恍惚とした表情で、俺の身体をまさぐっている。
気持ち悪いとまではいかないが、なんだか居心地が悪い。
なにせ、背中におっぱいを押し付けられた状態で身体を弄られても興奮しないのだ。
新感覚といえる。
「ああ、それにしてもルーデウス君は可愛いな。食べてしまいたいくらいだ」
「食べるとは、性的な意味でですか?」
適当に軽口を叩いてみると、口を手で塞がれた。
「……君は喋らないほうが可愛いな。喋ると、あのパウロの顔を思い出す」
どうやら、テレーズはパウロのことがあまり好きではないらしい。
「しかし、ガッシュ団長は相変わらずだな」
と、俺をなでなでしながら、テレーズは話題を変えた。
「バクシールにあんな手紙を出せば、ああなることはわかりきっていただろうに」
ガルガード・ナッシュ・ヴェニクとは、教導騎士団の団長だ。
教導騎士団とは、紛争地帯に若い騎士を送り込んで戦場を経験させると同時に、各地にミリス教団の教えを広めるという役割を持った、傭兵部隊である。現在は遠征と遠征の合間の募集期間であり、団員を募集するために国内に戻ってきているのだそうだ。
ガッシュこと、ガルガード・ナッシュ・ヴェニクはその団長だ。
かつて魔大陸に遠征した際に戻ってきた生き残りで、この数十年で教導騎士団を歴代最強といわれるまでに引き上げた立役者。無口で無骨な人物であり、滅多に笑わない。どんな悪人に対してでも平等に接するできた人物と噂される。
ミリス騎士は、教導騎士団の遠征に参加することで騎士として一人前になる。
ガッシュが団長になってから、教導騎士団の生還率は九〇%を超えている。
故に、現在の教導騎士団は歴代最強の呼び名が高い。
ガッシュに命を救われた者も数多く存在しており、現在の騎士で、ガッシュを尊敬していない者は存在しないのだそうだ。
「そして、筆不精かつ言葉足らずというのも有名なのだ」
戦場ではテキパキと指示をだすが、普段は気が抜けていて、ロクすっぽ挨拶も返さないのだとか。
手紙を出すこともほとんどなく、書類も基本的には印鑑のみ。
その筆跡を見たことのある人物はほとんど存在しないため、偽造の書類が多く出回っている。
ルイジェルドの話では、饒舌で激情家という感じだった。
もっとも、ルイジェルドもあまり饒舌ではないほうだからな。
基準が違うのだろう。もしくは、ルイジェルド相手だけは別なのだろうか。
「ねえ、いつまでくっついているのよ……」
エリスがだんだんとマジギレ五秒前な感じになってきたので、俺はテレーズから離れた。
「あぁ……ルーデウス君の温もりが……」
テレーズが名残惜しそうな顔をするが、俺は抱きまくらじゃない。
抱かれていても嬉しくないしな。
「ルーデウス、こっちにきなさい」
そう言われ、隣に座ると、キュっと手を握られた。
「…………」
エリスの顔を見ると、耳まで真っ赤になっている。
その横顔を見ているだけで、俺の口元もゆるもうというものだ。
見れば、テレーズが枕をボスボスと殴っていた。
壁でも殴ればいいのに。筋肉が足りなさそうだけど。
「はぁ……若いっていいなぁ……」
テレーズはため息を一つついて、真面目な顔をした。
「そうだ、ルーデウス君。一つだけ忠告をさせてもらおう。もうすぐミリスを発つ君には意味のない忠告になるかもしれないが……」
と、前置きをしてから、テレーズは口を開いた。
「国内でスペルド族の名前は出さないほうがいい」
「どうして?」
「ミリス教団の古い教えには、魔族は完全に排斥すべし、というものがある」
魔族は全てミリス大陸から叩きだすべし。
それがミリスの教えである。現在は形骸化されているが、神殿騎士団はそれを従順に守っている。
スペルド族のように有名な種族は、たとえ偽物であっても全力を持って排除しなければならないらしい。
「ルーデウス君が世話になったとあっては私も見逃さざるをえないが、本来なら絶対に見逃さないところだ」
「無理ね」
真面目な顔のテレーズに答えたのは、冷めた顔をしたエリスである。
「あなたたちでは、何人で掛かってもルイジェルドには勝てないわ」
「そうですね。エリス様の言う通りです」
当然と言わんばかりの口調に、テレーズが苦笑した。
「けれども、私も含め、神殿騎士団とは狂信者の集まりですから。たとえ勝てないとわかっていても、戦わざるをえないのです」
ミリス騎士団には、そうした者たちが何人もいる。
だから、もし将来、ミリス大陸に戻ってくることがあったら気をつけろと、念をおされた。
今回の一件は魔族に対する差別の根深さを再認識させられることとなった。
これからの旅でスペルド族の名誉を回復していくのは難しいかもしれない。
あと、もし俺がロキシーを神として信仰していると知られれば、異端審問に掛けられて、ひどい目にあうかもしれないので、俺の宗派は黙っておくとしよう。
★ ★ ★
船旅は順調に終わった。
テレーズは船旅に必要なものを全て用意してくれた。
旅の途中の食料から、船酔いの薬までだ。この世界は薬学はあまり発達していないと思ったが、治癒魔術だけがこの世界の医療というわけではないらしく、船酔いの薬ぐらいはあるようだ。
もっとも、かなり高価であるらしい。親戚のコネというのは素晴らしい。
テレーズはエリスに対しては最大限の便宜を図ってくれたが、ルイジェルドに対する目には厳しいものがあった。もっとも、それも仕方あるまい。物事は奇数ばかり。割り切れるものではないのだ。
エリスは船酔いの薬のおかげで、やや不快そうではあるものの、俺のヒーリングをねだらない程度には、元気であった。
本音を言うと、しおらしいエリスが見れなくて残念である。
もっとも、そのおかげで、俺のゲージは溜まらず、バスターウルフは暴走せず、エリスのサニーパンチをもらうこともない。平常通りである。
しかし、エリスは前回のことで不安なのか、船の中では常に俺にくっついていた。
しおらしくはないが、海を見てはしゃいでいるエリスを見ることができて、俺も満足である。
「ようお二人さん、お熱いねえ! 王竜王国で結婚式かい?」
二人で海を見ていると、船員がヒューヒューと冷やかしてきた。
「ええ、盛大なやつをね」
なので調子に乗ってエリスの肩を抱いたら、殴られた。
「け、結婚なんてまだ早いわよ!」
エリスは俺を殴りつつも、満更でもないらしく、ややもじもじしていた。
人に冷やかされるのは嫌いらしい。そういうことは二人っきりで、人気のない、ムードのある場所でということだ。
剣を持てば阿修羅なエリスも、色恋沙汰に関しては乙女なのだ。
しかし、結婚か。
俺とエリスをくっつけようとしていたフィリップたちはどうなっているのだろうか。
パウロは、楽観視するなと言っていたが……。
彼らだけじゃない。ゼニスとリーリャは行方不明。アイシャだってどこにいるのかわからない。シルフィも情報がない。ギレーヌだって生きているかわからない。
不安だらけだ。
いや、あまり悪い方へと考えるのはよそう。
案外、フィットア領に帰ってみると、皆元気で帰還しているかもしれない。
楽観的な考えだ。絶対にそんなはずがないとわかっているけど、少なくとも、今、不安に思いすぎることはない。
そう思うことにしよう。
こうして、俺たちはミリス大陸を後にしたのだった。
間 話 「ロキシーの帰還」
ルーデウスたちがミリスを発った頃。
ロキシー・ミグルディアは故郷へと帰ってきていた。
ミグルド族の村。
様子は変わっていなかった。村の知り合いも、その顔ぶれもほとんど変わらない。
住人は増えていたが、不気味なほどに静かなところは昔のままだった。
かつては不気味などと思わなかったが、世界中を見て回ったロキシーに言わせれば、この村は異常だ。ただ静かで、ただ一言の会話もないのに、村人の意思疎通はできているのだから。
彼らはロキシーを見ると、ただじっと見つめてきた。
ロキシーは知っている。彼らはミグルド族の特殊能力、念話によって話しかけてきているのだ。
しかし、ロキシーにはわからない。僅かにノイズのようなものは聞こえるが、それだけである。
ロキシーが彼らの言葉に答えることはない。
しばらくすると、両親が姿を現した。久しぶりに会った両親もまた変わっていなかった。
彼らは帰ってきたロキシーを見て喜び、歓迎し、今までどうしていたのか、一人で来たのか、と心配そうな声で聞いてくれた。
エリナリーゼとタルハンドの二人は里の外で待っている。帰郷ということに、何か思うところがあるらしい。
ロキシーは今までの旅を淡々と語った。
両親は話を聞いて驚き、ほっとした顔をして「好きなだけいなさい」と言ってくれた。
だが、ロキシーは疎外感を感じていた。
心配する言葉も、歓迎する言葉も、彼らにとっては外国語だ。彼らは、本当に大切な言葉は、決して口には出さないのだ。特に、愛を囁く言葉は。
もしかすると、心の底から心配してくれているのかもしれないけれど、それはロキシーには伝わらない。ミグルド族の能力が使えない自分には伝わらない。
そのことを、ロキシーは寂しく思う。
これ以上ここにいても辛いだけ。自分がミグルド族として出来損ないであると確認することとなる。
そう思ったロキシーは、長く滞在せず、すぐに発つことを決めた。
「もう行ってしまうのか?」
「はい」
「せめて一晩ぐらい」
「いいえ、急ぐ旅の中、少し寄っただけなので」
心配そうな表情を作る父に、ロキシーは無表情で首を振る。
「次はいつ帰ってくる?」
「わかりません。もう帰ってこないかもしれません」
ロキシーは正直に言った。
すると父の隣にいる母もまた、心配そうな表情を作っていた。
「ロキシー……二十年に一度ぐらいは帰ってきてね」
「そうですね……」
生返事で答える。
「……五十年以内には、戻ってくるかもしれません」
「本当? 約束よ」
「はい」
ロキシーが曖昧に頷くと、母はポロリと涙を流した。
「あっ、お母さん……?」
「あら、ごめんなさい。泣かないって決めていたのに、ごめんなさいね」
母の涙を見て、ロキシーの中に動くものがあった。
知らずうちに、母を抱きしめていた。
すると、父がロキシーと母をまとめて抱き寄せた。
その時、ようやくロキシーは悟った。言葉だけではないのだ、と。
結局、村には三日ほど滞在した。
久々にゆっくりとした日々を過ごしたのだ。
★ ★ ★
『デッドエンドの飼主』の正体はルーデウス・グレイラットである。
そのことを認めるのに、ロキシーは若干の時間を要した。
魔大陸に入り、ルーデウスの情報を求めて北へ北へと移動した。北に行けば行くほど、ルーデウスという単語を聞くようになった。
近づいている。
そう思うと同時に、何かがおかしいと思うようになった。
『偽デッドエンド』の情報と、ルーデウスの目撃情報がやけに被るのだ。無詠唱で魔術を使う人族の少年と、偽デッドエンドの『飼主』は、もはや同一人物といっても過言ではないと、途中で何度もタルハンドに言われた。
いや、最初から気づいていたのだ。気づかずにすれ違っていたと認めたくなかったのだ。
だが、リカリスの町まで来て、認めざるを得なくなった。
二年前に起こったという『デッドエンド』事件。
かつてのパーティメンバーだったノコパラの証言。
そして、故郷の両親の証言──全てを統合して、ようやくロキシーは認めた。
『デッドエンドの飼主』はルーデウスであった、と。
現在、ロキシーはノコパラと一緒に、酒場で食事を取っている。
ルーデウスの話を聞いた時、ノコパラは随分と言いにくそうにしていた。
どうやら、彼は人に言えない類の職業に転向しているらしい。
ロキシーとしては、それを責めるつもりはない。魔大陸では、それも仕方のないことだ。
「そうですか……ブレイズは死にましたか……」
「ああ、赤喰大蛇に丸呑みだそうだ」
魔大陸を離れて数年。
つもる話があるはずなのだが、出てくるのは昔のことばかりだった。
ロキシーは目を閉じ、ブレイズのことを思い出す。
豚みたいな顔で、口が悪く、ロキシーが何か失敗する度に悪態をついてきたが、嫌な奴ではなかった。戦士として頼れる男だった。
死ぬ間際には、Bランク冒険者パーティをまとめるベテランに育っていたという。
魔大陸におけるBランク冒険者パーティのリーダー。
あの皮肉屋が立派なものだと思うが、しかしパーティ名はスーパーブレイズ。
ネーミングセンスは昔から変わっていなかったらしい。
そんなベテランパーティを全滅させた相手を、パーティを結成して間もないルーデウスたちが倒したらしい。冒険を始めてすぐにAランクの魔物を討伐する。
昔のロキシーには逆立ちをしてもできそうにない。
だが、それもまたルーデウスらしい、とロキシーは薄く笑った。
「ロキシーは、随分変わったな」
ノコパラは魔大陸特有の刺激の強い酒をチビチビと飲みながら、ポツリと言った。
ロキシーは杯の水面に映る自分の顔を見て、そうだろうか、と考える。
「自分ではわかりませんが……」
「いや、随分と大人っぽくなった」
「なんですかそれは、馬鹿にしてるんですか?」
ノコパラたちと冒険をしていた頃、ロキシーはすでにミグルド族として成人した姿だった。
それ以来、体型等も大きな変化はない。自分では何も変わっていないとロキシーは自覚している。
「馬鹿にはしてねえよ。なんつーか、雰囲気がな。昔のお前は、もっと子供っぽかった」
「外見が変わらないだけで、ちゃんと生きていますからね」
ロキシーはそう言いつつ、ポリポリとツマミである炒り豆を食べる。
この豆はストーントゥレントの種子である。ロキシーの味覚では、さして美味しいとは思えない。
ただ、なんとなく口に運んでいる。癖になる味である。
「そういうところだよ。昔はお前、大人に見られようと必死だったじゃねえか。昔のお前だったら、俺の言葉に舞い上がってたぜ?」
「そうですか? ……そうですね、そういう時期もありました」
身の丈というものがわかっていなかった頃の話である。
昔は周囲に子供だと思われないように、ナメられないようにと頑張ってきた。
自分は魔術師だ、苦手属性は無い、なんでもできると吹聴していた。
いつしか、その評価は逆転し、名前ばかりが一人歩きしている。
今は、できないことばかりを押し付けられそうになる。
そういえば、魔大陸においても、ルーデウスの師匠だというと、やけに驚かれた。
ルーデウスは、事あるごとに「師匠の教えの賜物です」と吹聴しているらしい。
おかげで、ロキシーまで無詠唱で魔術が使えるものと思われていた。無詠唱魔術など、できるはずもないのに。
かつて、自分のことを罵倒した師匠もこんな気持ちだったのだろうか、とロキシーは思う。
そうであったのなら、悪いことをしたと反省するところである。
優秀すぎる弟子を持った師匠の苦悩。実際にその立場に立ってみないとわからないものである。
誇らしいと思うと同時に、恥ずかしいのだ。
けれども不思議と現在、師匠と呼ばないでほしい、とは言いたくない。
ルーデウスが言いつけを守らず、ロキシーが師匠だと吹聴しているという事実が、単純に嬉しいのだ。
「ノコパラは変わりませんね」
「そうか?」
「ええ、見た目以外は」
金に意地汚く、弱者を狙うところは、昔のままである。
ロキシーはかつて、ノコパラだけは敵には回したくない、と何度も思ったものだ。
「なんだそりゃ、遠回しに老けたって言いてえのか?」
「そうとも言いますね。ノコパラは老けました」
「言うようになったじゃねえか」
ノコパラはヒヒンとニヒルに笑った。
「懐かしいなぁ……」
「そうですね」
当時、ここにはもう二人いた。
ノコパラが何か言う度に悪態をつく少年と、喧嘩するたびにヤレヤレといいつつ諌めてくれる少年が。
もはや二人はいなく、残ったのは中年二人である。
もっとも、片方は種族柄、それほど歳を食っているわけではないが……。
過ぎた日は戻ってこない。
その日、ノコパラが酔いつぶれるまで、二人は思い出話に花を咲かせた。
両親と、古馴染。
この二つに会えただけでも、ここに帰ってきた意味はあった。
そんな思いで、ロキシーの胸は一杯になった。
★ ★ ★
ルーデウスは今頃、ミリシオンにたどり着いただろうか。
ウェンポートですれ違ったとして、そこから半年。
雨期と丁度重なったとはいえ、聖剣街道は何もない道である。長耳族や炭鉱族の集落に寄り道しなければ、ミリシオンにはたどり着いているはずだ。
やはり、探す必要などなかったのだ。パウロが伝言で残した通り、彼は大丈夫だった。一緒に転移したというエリスという女の子。彼女と共に、楽々と魔大陸を抜けたのだ。
普通ならどこかでもたつくところを、いとも簡単に、あっさりと。
しかも、途中でロキシーの恐れてやまないスペルド族を仲間にまでして。
「ロキシーの弟子は優秀じゃな」
「本当に。パウロの息子とは思えませんわね」
エリナリーゼとタルハンドもそう言って褒めていた。
誰の弟子とか、誰の息子とかは関係ないのだ、とロキシーは思う。ルーデウスは、自分と出会う前から天才だったのだ、と。もし自分と出会わなくとも、これぐらいのことはできただろう、と。
それはさておき。
「これからどうしますの?」
エリナリーゼに聞かれ、ロキシーは考える。一応の目標であるルーデウスは、恐らくすでにミリシオンに到着しているだろう。
彼に会いたいのは山々であるが、目的を履き違えてはいけない。
「魔大陸の北西部を探しましょう」
ルーデウスは見つかったが、残り三人はまだ見つかっていない。
今までの道中でも、フィットア領出身の難民は何人かいた。
なら北西部にもいるだろう。
「弟子に会わなくてもええのか?」
「構いません」
タルハンドにそう聞かれ、ロキシーは首を振る。
第一、気づかずにすれ違ったなどと知られれば、会わせる顔もない。
ただでさえ師匠として情けない立場なのだ。
「魔大陸の町はまだまだあるんです。今まで通り、一つずつ回っていきましょう」
二人は顔を見合わせ、くすりと笑った。
ロキシー・ミグルディアの旅は続く。
番外編一 「ドラゴン肉のナナホシ焼き」
イーストポート。
王竜王国の領土であるそこは、世界で最も大きな港町だ。
言語は変わらないが、ミリス神聖国とは、店の名前や雰囲気が少しだけ違う。
だが、俺にとって四つ目となる港町だ。さすがに目新しく感じることもなく、船から降りてからはルーチンワークのように宿を探していた。
そんな時、エリスがポツリと言った。
「いい匂いがするわね」
いい匂いというと、訓練直後のエリスの首筋あたりの匂いのことだろうか。
などと思いつつ鼻をひくつかせてみると、なるほど確かに、どこからともなく美味しそうな匂いが漂ってきていた。
見れば太陽もすっかり高い位置にあり、お腹の方もスッカラカンになっている。
「お腹がへりましたね」
「そうね……」
エリスが頷く。
その視線の先には、この匂いのもとであると思われる一軒の飯屋があった。
店の外見は汚い。
レンガ造りの壁はボロボロで、穴も開いている。薄汚れ、掠れ、文字の読み取れない木製の看板。
蝶番がハズレ、今にも倒れそうな扉は、飯屋というよりあばら屋といったほうがしっくりくる。
しかし、そこから漂ってくる匂いだけは本物だった。
ふわりと漂う匂い。食欲をそそる香ばしさはなかったが、どこか懐かしく、俺の胃袋をキュンとさせた。
「入るのか?」
ルイジェルドに聞かれ、ハッとなった。
自分の足がフラフラと店に吸い寄せられていたのだ。
「……ええ、何か問題でも?」
「お前はいつも、店構えは綺麗な方がいいと言っていなかったか?」
言ってたような気がする。
でも、それは魔大陸での話だ。
魔大陸では、店構えの綺麗さは、そのまま料理のうまさにも直結していた。
たまにそれで超絶にうまい店もあるのだが……ともあれ、いつもの俺なら、こんな店には入らないだろう。
だが、なぜだろうか、気になる。
「たまにはいいでしょう」
「まあ、お前がいいならいいが……」
俺に追従するように、二人もついてきた。
ギギギと嫌な音を立てる扉を開けて、中に入ると、中もやはり汚かった。
いや、汚いという言い方は適切ではない。
飯屋として必要な清潔さは保たれていると見るべきだろう。
ただ、ボロいのだ。
椅子の足は足りず、テーブルにはヒビが入り、床には穴が開いているところもある。
もちろん、客はいない。
「貸切ね」
エリスが嬉しそうに呟いた。
昼飯時に客がいないことに関して、特に疑問は持っていないらしい。
俺も不安に思うところだが、なぜか不安が期待を上回っている。
「いらっしゃいませ……」
席につくと、骸骨のような男がメニューを持ってやってきた。
店主だろうか。
それにしても、不景気そうな顔だ。
繁盛してないのは見ればわかるが、客の前なのだからスマイルの一つでも見せるべきだろう。
「ルーデウス、やはりやめておいたほうがいいのではないか?」
ルイジェルドがそんなことを言うとは珍しい。
だが、人を見た目で判断しちゃいけない。
「まぁまぁ、味の方はいいかもしれませんし」
そう言うと、骸骨男は苦笑いをしつつ、メニューを開いてみせた。
メニューに書かれていた料理は二種類。
・ドラゴン肉のナナホシ焼き
・アルバーフィッシュの煮物
ミリシオンのレストランでは十種類以上から選べた。
品数をウリとしない酒場でも、もう少し数が多い。
そう考えると品揃えの悪い店だが、値段は安いのでよしとしよう。
「どちらに致しますか?」
肉か魚か。
アルバーフィッシュというのは、南の海で取れる魚である。
ここら一帯ではよく食べられる魚で、ウェストポートでも口にした。煮物とあるが、この場合は石狩鍋のようなスープであろう。王竜王国ではよく食べられている代表的な料理の一つだ。
対して、ドラゴン肉のナナホシ焼き。
こちらは聞いたことがない。
王竜王国の近くにある王竜山脈には、その名の通り、王竜というドラゴンが住んでいる。
なんでも重力を操るドラゴンらしいが、それの肉なのだろうか。
もしくは、それによく似た生物か……。
そして、ナナホシ焼き。
初めて耳にする調理法である。もっとも、俺もこの世界の料理には詳しくない。
王竜王国ではポピュラーなのかもしれない。
ともあれ、興味をそそられた。
「私は肉ね」
「俺も肉だ」
「じゃあ肉三つで」
肉食系三人から注文をうけると、骸骨男は無言で厨房の奥へと消えていった。
もちろん、水はない。
この世界には、基本的にそうしたサービスはない。
なので、俺は土魔術でコップを作り、水を注いで二人に配った。
セルフ、というやつだ。
いくつか氷を浮かべれば、歩き疲れた身体を癒す清涼剤となる。
「ルーデウス、おかわり」
エリスはごくごくと一瞬で飲み干し、ゴリゴリと氷を噛み砕いて、コップを突き出す。
俺ははいはいしょうがないですねと、水を入れてやる。
外でなら、自分で詠唱しなさいというところだが、ここは店の中だ。
制御をミスって水浸しにするわけにもいくまい。
「…………」
ルイジェルドは、いつも通り、チビリチビリと飲んでいる。
この男は、食うときは早いが、飲み物は一気には飲まない。
「この港町には、大した情報はなさそうですね」
「そうね、もう少し剣を見ていたいけど、さっさと次の町に行ったほうがいいかもしれないわね」
栄えた理由が理由だからか、この王竜王国には刀剣類が多数売られている。
そこらの露店にも、ズラリと剣が並んでいるのだ。
エリスもさっきまでそれらを見て眼を輝かせていたが、すぐに売られているのが初心者を騙すためのナマクラばかりだと気づいたらしい。
剣の腕は上達しているエリスだが、目利きの方はまだまだというわけだ。
当然か。
「邪魔するぜぇっ!」
などと話をしていると、唐突に扉がバンと開けられた。
ガラの悪い男が一人、ズカズカと土足で店の中に入ってくる。
いや、靴を脱ぐ習慣はないから、俺も土足なのだが。
と、その声を聞いて店の奥から骸骨男が出てきた。
「シャガール……」
「ランドルフ、今日こそいい返事を聞かせてもらうぜ!」
「何度来てもらっても、返事は変わりません、お引き取りください」
「ハッ! こんなシケた店、いつまで続けてんだ」
「先祖代々の店ですからね……無論、死ぬまで……」
その言葉で、俺はなんとなく、この店の状況を察した。
要するに、経営難だ。この店はきっと借金とかをしつつ、なんとか経営を続けているのだ。
あのガラの悪いのは、地上げ屋か何かだろう。
「待ってください……今日はお客様もいるんです」
「客だぁ……とぉ、確かにお客がいるじゃねえか、珍しい」
「お客様が一人でもいる限り、私は諦めませんよ」
「ハッ」
ガラの悪い男はその言葉を鼻で笑い、近くの椅子に座った。
骸骨男はそれを尻目に、厨房へと戻っていった。
大変そうだな。
よくわからんが、飯がうまかったら、宣伝の一つもしてやろうかな。
「あいつ、こっち見てるわ」
「……」
「ちょっとルーデウス、見えないわよ」
エリスがガン付けられてキレそうだったので、目隠しをしておく。
ここは拳ではなく、料理で決着をつけるべきだからな。
あっ、やめてエリス、俺の手首を掴まないで、折れちゃう、折れちゃう。
「おまたせしました」
エリスと遊んでいると、料理が運ばれてきた。
その料理を見て、俺は眼を見開いた。
「これは……!」
ドラゴン肉のナナホシ焼き。
その料理は、三つに分かれていた。
まず、汁物。透明な野菜スープで、スッキリとした味わいが楽しめることが一目見てわかる。
それはいい。残り二つが問題だ。
まず、左側にあるのは、俺がこの世界に来てからついぞ見たことのない主食だ。
白銀の帝王──白米であった。
否。白米というには、少々色合いがおかしい。米だけでなく、他の穀物もいくつか混ぜられているのだろう。穀米だ。久しぶりに見たせいか、少々見間違えたか。
しかし、何か懐かしい匂いがすると思ったら、これだったのだ。
米を炊いた時の匂い。懐かしく、身体が吸い寄せられるはずである。
さて、もう一つ。
きつね色にこんがりと焼かれたそれはどうみても、どうみても……。
唐揚げだった。
つまり、汁物こそ味噌汁ではないものの、ご飯も白米ではないものの。
この料理は『唐揚げ定食』である。
「すごい!」
「どうしたの……?」
テーブルに手をついてブルブルと震える俺を、エリスが怪訝そうな顔で見ていた。
「いえ……なんでもないです」
まさかこの世界にも唐揚げがあったとは……これが天の恵みか。
あの人神も、ようやく俺の求めるものが何かわかってきたらしい。
よし食おう。すぐ食おう。早く食おう。
手を合わせ、天と地とあまねく精霊に祈りを捧げる。
「いただきます」
箸はないので、フォークにて白米を口にする。
「ふぁああ……」
涙が出た。
生前、俺は米が好きで好きでしょうがない人間であった。
特に三十代に入る直前ぐらいは、米さえあればとにかく大丈夫だと公言してはばからず、一日に二升ほどの白米を平らげていた。
当時食っていた米に比べれば、この米は一言、まずい。
恐らく、日本の食味ランキングで言えば、Cランクにも及ぶまい。
だが、米だ。米は米なのだ。
米に貴賎がないということを、俺は今、生まれて初めて実感していた。
「ル、ルーデウス……どうしたの?」
「なんでもない、なんでもないんや」
シベリア抑留から帰ってきた日本兵の如く、俺は涙を流して米を食った。
一つ噛み締める度に、米の味がした。
おっといかん、そんなに量はないのだから、おかずも一緒に食べなくては。
と、唐揚げに食指を伸ばす。
フォークで突き刺して、口の中へ。
「ムオッ!」
米の感動が吹き飛んだ。
結論から言えば、それはフライではあったが、唐揚げではなかった。
表面はべちゃりとしていて油臭く、肉はボソボソとして硬かった。
噛めば噛むほど、肉の臭みと油の臭みが鼻の奥に充満した。
吐き気がする。
「…………」
怒りが湧いてきた。
こんなもので。
こんなもので、米を食べろというのだろうか。
いや、米なら、俺はいくらでも食べることができる。塩があればなおいい。
白米と塩。十分だ。それだけで俺のサムライは戦える。
だが、俺の中にいいえぬ怒りがあった。この唐揚げは、白米に対する冒涜だ。
「女将を呼べ!」
★ ★ ★
おどおどした表情でやってきた店主に対し、俺はまず、褒めるところから始めた。
まず、スープは合格だ。
すまし汁にも似た塩味の野菜スープは、独特な五穀米に妙に合っていた。
飯とスープだけで十分と思える相性の良さである。
職人の技が感じられるスープだった。
それに、米の炊き方も合格だ。
水の分量も火加減も、おそらくちょうどいい。
プロの味だ。米の一粒一粒が感涙にむせび泣いている。
あと一点、水にさえこだわれば最高点をあげてもいいだろう。
なんだったら、ルーデウス印のおいしい水をメガトン単位でプレゼントしてもいい。
俺が丹精込めて作った水は、そこらの井戸水より美味しいからな。
そう褒めた上で、俺は唐揚げ──ナナホシ焼きを貶した。
徹底的に叩いた。
これは人の食べるものではない。金を払わせておいてこんなものを食べさせるとは。俺をデッドエンドのルーデウスと知りながらこんなものを出したのか! この私も舐められたものだ!
と、どこかの美食倶楽部の主宰者のように怒った。
自分でも、なぜこんなに怒ったのかよくわからない。
もしかすると、腹が減っていただけだったのかもしれない。エリスとルイジェルドもドン引きしていたし、最終的に俺は二人の手で店から引きずりだされた。
ちょっと言いすぎた。
それぐらい俺は米が好きだったのだが……明らかに言いすぎだった。
素人のくせに調子に乗ってしまった。
この世界には生前の世界のような材料はないのだ。
唐揚げを揚げるための油だって、高級品があるわけでもないだろう。
白米をおかずと共に食べるという文化があり、唐揚げという調理法があることを知ることができた。それだけでも僥倖であろうに、俺はなにをこんなに怒っているのか。
店を出る間際、店主は小さくなり、目の端に涙すら浮かべていた。
我ながら大人げなかった。
反省しよう。
★ 店主視点 ★
経営不振。
客足が途絶えて、すでに数年。たまにくる一見の客も定着はせず、借金ばかりが膨らんだ。
挙句、今日のお客には盛大にダメ出しされた。
油はもっと高い温度を使わなければダメだとか、肉の中に水分を閉じ込めなければ意味がないだとか、肉には甘じょっぱい下味をつけてから衣を付けなければダメだとか。
最後には「それ以前に肉の選び方からして間違っている」とまで言われた。
でも、ドラゴンの肉は数百年続く我が店の伝統だ。
そんな根本的なところを指摘されても、どうしようもない。
「いや、びっくりしたな、オイ……」
悩む私に、賊のような格好をした男が声を掛けてきた。
シャガール・ガルガンティス。
ここ数年、私につきまとい続けている男だ。
「でも、これでわかっただろ。あんなガキにダメ出しされるレベルなんだよ、お前の料理は」
シャガールはいつも通り、いやらしい笑みを張り付かせている。
真面目な顔をしていればそれなりに麗しい顔をしている男だし、頭も悪くないはずだ。
しかるべきところに行けば、何十人もの配下が彼に頭を下げる。
なのに、こんな頭の悪そうな格好をして、嫌らしい笑みを浮かべている。
変装のつもりかもしれない。
「ああ……だが……」
「先祖代々の店を守りたいという気持ちはわかる。けどな、お前には商才がない。店を守る力もな」
ズバリ言われて、胸が痛い。
その通りだ。自分には商売の才能はもちろん、料理の才能すらない。
あんな子供にまで、美味しいと言ってもらえないのだから、相当なものだろう。
「でも、お前には別に、もっと得意なことがある。人には、向き不向きがあるんだ、そうだろう?」
「そうだな……」
私は頷かざるをえない。
もはやここまで、という意識が脳内を埋め尽くしていた。
「わかった。店を畳もう」
創業二五〇年。大昔から伝わる店を自分の代で終わらせる。
そのことを生き恥とし、これからの人生を生きよう。
私はそう思った。
その日。
王竜王国の大将軍シャガール・ガルガンティスはある人物のスカウトに成功する。
七大列強四位『死神』ランドルフ・マリーアン。
長年スカウトされ続けても決して首を縦に振らなかった彼が、どうしてある日突然シャガールの誘いに応じたのか。
それを知る者は、少ない。
番外編二 「アリエルの死」
私の名前はグスタフ。
アスラ王国王都アルスの片隅に住む、ケチな情報屋だ。
ケチではあるが、アスラ王国内で起きたことで調べられないことはないと豪語できる程度には凄腕を自負している。
ある日、そんな私の耳に、ある噂が届いた。
『第二王女アリエル。ラノア魔法大学へと留学に行く途中、何者かに殺害さる。犯人は不明』
聡明な私は、この噂がアリエル王女の敵である、グラーヴェル王子の流したものだとすぐにわかった。
アリエルは、ほんの一ヶ月ほど前に留学という名目で、この王都を出立した。
送迎は盛大ではなかった。
アリエルは王都の民に人気があり、もし大々的な見送りのパレードなどをすれば収拾がつかなくなるとの理由で、こっそりと出立したのだ。
アリエル王女についていた護衛の数は従者を含めて十七。王女の護衛にしては少ないが、この国一番の伊達男として有名なルーク・ノトス・グレイラット、そして『無言のフィッツ』という目立つ護衛がついているため、私の情報網にはすぐに引っかかった。
そうでなくとも、町中ではアリエルが政争に負けて島流しになったのだと噂になっていたが。
そんな中で、この噂。
本当にアリエルが殺害されたにしては、ずいぶんと情報が回るのが早い。
犯人を目撃した者がいるのならまだしも、不明。情報の出処も不明。
信憑性がない割に、情報の回りが早すぎるのは、誰かが操作している証拠だ。
さて、情報屋としては、この事件の真相を暴きたいと思うところだが、情報操作をしているであろう悪巧みの得意な王宮の貴族たちに目をつけられても面白くない。
この一件は知らぬ存ぜぬ調べぬを貫こう。
と、決めていたのだが、情報が流れ始めてしばらくして、私の元にある人物が訪れた。
凄腕の情報屋である私は、その人物を知っていた。
アリエル派の首魁、ピレモン・ノトス・グレイラットの配下で、主に情報を取り扱っている者だ。
無論変装はしていたし、偽名も使っていたが、私には無意味なことだ。
彼は当初、私のことを胡散臭いモノ扱いし、居丈高な態度を取っていたが、正体を看破してやると、すぐに頭を下げて、依頼内容を提示してきた。
「アリエル王女の生死を確かめてほしい」
私はそれを聞いて、非常に驚いた。
まさかアリエル派の者が、アリエルの姿を見失い、安否すらわからない状態だとは思わなかった。いやはや、聡明な私にも、わからぬことはあるのだ。
調べないと決めた一件……であったが、私はこの依頼を受けた。
なぜかって?
当然、報酬が良かったからさ。
★ ★ ★
情報収集は、アリエル王女の足跡を追うところから始まった。
アリエル王女は王都から出て、まっすぐ北へと向かっていた。
ラノア王国は北にある。魔法大学へと留学するという偽の情報を流し、別方向へと逃げたということはないようだ。
アリエルの足跡を追いながら情報収集をしていくと、アリエルに追っ手が掛かっていたことがわかる。
アリエルが通過した頃に前後して、怪しげな黒ずくめの集団を見たという情報があったからだ。
そして、その目撃情報があった場所から次の町では、アリエルの護衛の数が減っていた。
しかし、これは予想できていたことである。
何の心配もなく旅ができていたのなら、アリエル派の者が慌てて安否を確かめようとすることもないだろう。
アリエルは護衛を一人、また一人と失いつつも、着々と北へと移動していった。
最終的に護衛が十人まで減ったところで、アリエルは北の関所へとたどり着いた。
アスラ王国の北国境。
赤竜の上顎と呼ばれる渓谷の南広がる森を押さえつけるように存在する関所。
そこで、私は有力な証言を手に入れることができた。
彼は、アリエルが関所へと訪れた時のことを、しっかりと覚えていた。
★ 出国管理官スマイリー・ガトリンの証言 ★
あの日、私はふてくされていました。
まぁ、ずっとふてくされているようなものでしたがね。
なにせ、当時の私は、この仕事は自分にふさわしくないとまで思っていましたから。
え? どんな仕事かって?
まあ、つまらない仕事ですよ。
国内側から来る者の通行証を確認し、場合によっては密輸品などを持ち込んでいないかチェックするというものです。もっとも、ここに来るのは、北と交易をしたいという物好きな商人か、冒険者や傭兵ぐらいしかいませんがね。
大抵の商人は通行証を持っているし、冒険者は冒険者カードがそのまま通行証となります。
傭兵団や通行証を持たぬ旅人は改めて通行証発行の査定をしなければなりませんが、それは私の仕事ではありません。別の管理官に任せるだけです。よほどの大犯罪者でもない限り、すぐに通行証が発行されることでしょう。
なにせ、アスラ王国は国外に出る者より、国内に入ってくる者の方が圧倒的に多いのですから。
まあ、偽造通行証で国境を越えようとする犯罪者を止めるのも仕事といっちゃ仕事ですが、荒事は私の仕事ではありませんからね、兵士にお任せです。
ですが先ほども申しました通り、よほど悪いことをしない限り、国外へと出るための通行証は簡単に出ます。通行証が発行されないような大犯罪者は指名手配されていますし、指名手配されるような者は、関所になど訪れず、密輸組織を頼るでしょう。
そして、密輸組織の発見・壊滅も私の仕事ではない。
なんともつまらない、やりがいのない仕事です。
どれだけ努力したところで誰に評価されるでもなく、一生自分はここで老いていくのだろうと思うと、やるせなさばかりが募る仕事でした。
一緒に仕事をする兵士たちと、あまり仲が良くなかったのもありましたしね。
こっちは兵士たちをただの馬鹿だと思っていましたし、兵士たちはこっちを頭でっかちのモヤシだと思っていました。命令系統が違うっていうのも、仲の悪い原因だったでしょう。
名誉ある王都の貴族学院を卒業したこの私は、本来はこんな辺境にいるべき人間ではない、もっとふさわしい仕事がある、と本気で思っていましたね。
アリエル王女が現れたのは……正午を回った頃だったでしょうか。
二人乗りの豪華な馬車に、周囲を歩く七人の護衛。
御者台に一人、馬車の中に二人いると考えれば、総勢で十人。
私は最初、貴族が物見遊山に来たのかと思いました。
ですが、ここは国境、この先は他国、それも北方大地と言われる、雪と魔物の危険な土地です。
他国に旅行に出かける貴族はいないではありませんが、最低でも三つ以上の馬車に、二十人以上の護衛をつけるものです。
あるいは高ランクの屈強な冒険者なら少数でもいいかもしれませんが、その一行は全員が屈強とは言いがたかったですしね。全員が旅装をしていましたが、護衛というには明らかにひ弱そうな者や、旅慣れていなさそうな者の姿もありました。
物見遊山でないのなら、この国境そのものに用があるのだろうかとも考えました。
偉い貴族のお忍びによる視察の可能性ですね。
ひとまず私は、いつも通り振る舞うことにしました。
「通行証を拝見いたします」
「ああ」
私の言葉に応じたのは、先頭に立つ青年でした。
彼は私の目から見てもわかるほどの美男子でしたが、顔には疲労の色が濃く。目の下にはクマもできていました。
何か様子がおかしいと思ったのはそのときですね。
もっとも、通行証には問題はありませんでした。アスラ王国から発行されている、本物の通行証です。通行証に記された認印はノトス家のもので、何の問題もありませんでした。
いつもなら、すぐに彼らを通したでしょう。
でも、どうにも、男の顔が気になったのです。どこかで見たことがあると。
今になって思えば、彼はアリエルの護衛騎士である、ルーク・ノトス・グレイラットその人でしたが、間近で見たこともなかったので、思い出せなかったのです。
そして、私は職業柄ピンときた相手を止めることにしています。
なにせ、私が憶えている顔と言えば、指名手配犯の似顔絵ぐらいなものですからね。
「失礼ですが、馬車の中を拝見させていただいてもよろしいですか?」
私の言葉で関所内に立つ兵士の何人かが、出口を塞ぐように動いてくれました。仲が悪いとはいえ、職務ですからね。
それに応じて、馬車を守る護衛の何人かが剣呑な表情で身構えた。
やはり指名手配犯か、と私が身構えたところで、疲れ顔の青年が首を振りました。
「故あって、正体を明かすわけにはいかんのだ」
もちろん、それが通るはずもありません。
いいから馬車の中身を見せろと通告すると、青年の顔が苦々しく歪みました。
他の数名……旅慣れている者たちですね。彼らも険しい表情をして、腰の剣に手を掛けました。その動きから、手練れとまではいかずとも、場数を踏んでいる空気が感じられました。
特に青年のすぐ後ろに立つ人物。やや小柄で白い髪をしている少年は怖かったですね。持っているのは初級魔術を覚えたばかりの時にもらえる初心者用の小さなロッドでしたが、彼はすでに歴戦の戦士の如き隙のなさや凄みのようなものが窺えました。
あれが、噂の『無言のフィッツ』だったんでしょうかね。正直、自分の半分も生きてなさそうな子が怖いと思ったのは初めてですよ。
経験上、こういう手合いは少なからぬ被害が出ることが予想できました。すぐに取り押さえるよう、周囲の兵に言うべきか、どうすべきか。
一瞬迷ったところで、馬車の中から声がしたのです。
「ルーク、おやめなさい」
その声は、私の耳朶を心地よく打ち、あっという間に脳髄をとろけさせました。
ずっと聞いていたい、そんな魔性が含まれた声。
聞いたことがありました。この声は、記憶に残っていました。
十年前、王都の学院の卒業式で、首席卒業の者に祝辞を述べるという、ただ一度だけの文言でしたが、忘れるはずもありません。あの声を、忘れるはずもないのです。
あの場にいた卒業生のほとんどが「もっと勉強しておけば」と後悔するほどの声を。
「彼らは職務に忠実なだけです」
馬車の扉が開かれた瞬間、背筋に震えが走るのを感じました。
その姿、忘れるはずもありません。
あの卒業式で、貴賓の一人として参加していた小さな王女の姿を。
自分は、この方に仕える。この王国に仕える。誇り高き国の一員となるのだ、と心の底から湧き上がってくるような感動を。
忘れるはずがないのです。
「し、失礼しました」
当時ですら目が潰れるほどに美しかった金髪の王女が、さらに美しくなって私の目の前に立った瞬間、私は即座に膝をついていました。
紛れもない、アスラ王国第二王女アリエル・アネモイ・アスラ。
市政のイベントにも積極的に出席する市民の味方といわれ、王室で最も人気のある人物。
兵たちの中にも、遠目には見たことはあるものは大勢いたでしょう。しかし、触れられるような距離で見ることは、その場にいる誰もが初めてであったに違いありません。
「膝をつく必要はありません。確か、関所では特別なことがない限り、膝をつかなくてもよいという法がありましたね」
王女はそう言いながら、馬車から降り立ちました。
周囲の兵士たちのほとんどが、私に釣られるように膝をついていました。
王女の言葉通り、関所の兵士は、特別な事情がない限り、膝をつく必要はありません。
理由はわかりませんが、昔からそう決められているのです。
事実、私は膝をついたことなどありませんし、この場にいる兵士たちが膝をつくのを見るのも初めてでした。それで今まで、何のお咎めもなかったのです。
もっとも、必要はないということは、つまり禁じられているわけではないのだと言わんばかりに、私たちは膝をつき、アリエル王女に頭を垂れました。
ただ、そうしなければいけないと思ったからです。
「ア、アリエル王女殿下……い、一応、しょ、職務としてお聞きしますが……その、なにゆえ、このような関所に、少数の護衛でおいでなさったのですか?」
「何も、聞いておりませんか?」
何か事情があるのだとわかりました。
そして、その返答で、記憶を探ると、ふと一ヶ月ほど前の記憶が蘇ったのです。
この関所の最高責任者は、当然ながら私ではありません、私の直接の上司である、上級管理官殿でもありません。最寄りの宿場町の町長でもある貴族なのです。
彼は月に一度も来ませんが、何か用事があると私たちのところに来て、命令を下します。
以前の命令が、私の頭の中で再生されました。
『もしかすると、何ヶ月かしたら、さる高貴な方が通るかもしれない』
私は高貴な方と聞いて、何十台もの馬車と従者を引き連れた行列を想定していました。
ゆえに、こうしてアリエル王女を見るまで、それが思い出せなかったのです。
「高貴な方がおいでになるかもしれない、と……」
「それだけでしたか?」
そう聞かれ、私の頭の記憶に、当時の記憶がまざまざと蘇った。
そう、確か貴族はこう言っていました。
『おそらくその高貴なる方は、国境を越えて北に逃げようとなさるだろう。しかし、決して通してはいけません。なんだかんだと難癖を付けて、数日は国境付近の宿場町へと押しとどめるのです』
通すな。ここで止めろ。
つまりソレは、ここでアリエル王女が死ぬということです。
上司からそういった命令を受けるのは、初めてではありません。
王都で何かをやらかした貴族が逃げてくることはよくあるし、その度に似たような命令はきます。
「通せ」という命令なら貴族は何事もなく北へと逃れられますが、「通すな」という命令なら、その貴族は、国境を抜けたところにある森で行方不明となります。
私は王都の出身でありますが、平民です。
王宮の貴族同士の派閥については疎い。
とはいえ、王宮で貴族同士が汚い政権争いをしていることぐらいは知っています。
生かすか殺すかの選定基準が金目当てや、ましてランダムでないことは、さすがの私も理解していました。つまり、この関所の責任者である上司と同じ派閥であるか、否かですね。
そしてどうやら、この麗しき姫君は、上司の所属する派閥に敗北し逃げているのだ、となんとなく察することができました。
「……」
「どうしました、答えなさい」
私は考えました。
ここでにこやかな顔をして「いいえ何も、丁重にお通ししろと言われただけです。しかし通行証に少々の不備が見受けられます。少し確認を取りますので、明日また来ていただきますか?」と言うのは簡単です。私はいつもそうしてきたのだから。難癖をつけて押しとどめておくなど、造作もないことだ。
だが、本当にそれでいいのだろうかという気持ちが湧き出てきました。
自分は何のためにこの国境で仕事をしているのか、という気持ちが。
国を守るためだとは口が裂けても言えません。
仕事中に『国のために』などと思ったことは一度もないのですから。
でもそんな私でも、確かに一度だけ、似たようなことを思ったことがあるのです。
先ほども話しましたが、アリエル王女を見た、卒業式の日です。
確かに私はあの日『自分はこの方に仕えている誇り高い王国の一員だ』と思ったのです。
それを思い出してしまった今、この目の前にいる年端もいかない姫君を、みすみす見殺しにしてしまっていいのだろうかと考えた時、すぐに結論は出ました。
迷うまでもありません。
「自分は、高貴なお方をこの場で止め、数日は宿場町に足止めするようにと仰せつかっております」
私がそう言った瞬間、護衛たちの気配が明らかに変わりました。
ですが、アリエル王女だけは、平然としたまま問い返してきたのです。
「そうですか、それで、いかが為さるおつもりですか?」
「……何も致しません」
「職務を全うしないのですか? 如何に不可解な命令でも、従わなければ首を刎ねられかねませんよ?」
アリエル王女の堂々とした態度に、私はフッと笑みが漏れました。
「さて、命令とは何のことやら。自分の知る限り『高貴な方』というものは、このように貧相な馬車一台と十人未満の護衛で他国に赴いたりなど致しません」
「ほう」
「私の目の前には、名も知らぬ、やけに偉そうな小娘が一人いるだけ……お嬢様、改めて、お名前を聞いてもよろしいですか?」
アリエル王女もまた、愉快そうに笑って答えました。
もしかすると、私との茶番を楽しんでいただけたのかもしれません。
「アリエル・カナルーサと申します。こう見えても下級貴族の一人娘ですの」
「では、アリエル・カナルーサ様、北へは何をしに?」
「ラノア魔法大学に留学を」
「そうですか。通行証に不備はございませんので、お通りください。よい旅を」
「ありがとうございます」
アリエル王女は、王族しかやらないような優雅な礼をして、馬車へと戻っていきました。
御者が馬を動かし、護衛たちはあっけに取られたような顔で先へと進んでいきました。
「さて、次の者……」
と、呼ぼうとしたところで、ふと私は自分に向けられた視線に気づきました。
無数の視線。私はこの部屋にいる、ほぼ全ての兵士たちから睨まれていたのです。
早まっただろうかと思いました。
この場にいるのは、職務に忠実な兵士たちです。彼らは私とは違う。王都で考えることを放棄して上に従う訓練を受けた、能なし戦士たちです。
この場においては一応私の部下となりますが、所詮は部署の違う者たちである。
あるいは、彼らにも上司から直接「アリエルを通すな」という命が下っていたのかもしれない。
それに従わなかったと怒られるのは、彼らも一緒だ。
第二王女アリエルともなれば派閥の頭であろうことは彼らにも想像がつくでしょう。上司にとっても、絶対に逃したくない、最も重要な相手ですから、末端まで情報を行き届かせていたとしても、なんら不思議はありません。
そして逃した今、私も含め、この場にいる全員の首が刎ねられたとしても、おかしくはない。
私は覚悟しました。事が露見する前に、せめてもの腹いせに痛めつけられることを。
アリエル王女を逃したのは私の独断でしたからね。
私が覚悟を決めた時、兵士のうちの一人が、ゆっくりと近づいてきました。
私のゆうに三倍はあろうかという肩幅を持つ、この場の兵士たちのチーフです。
彼はフライパンのような固く大きな手を振り上げて、私へと叩きつけてきました。
体がバラバラになることを覚悟しましたが、痛みはほとんどなく、衝撃で一歩前へとたたらを踏みました。
「やるじゃねえか」
チーフがそう言った途端、部屋中の兵士が拳を振り上げました。
ピューと口笛を吹いている者もいましたね。
あとから知った話になりますが、この関所にいる兵士は、ほとんどがアリエル王女のシンパだそうです。
アリエル王女は、兵士たちの卒業式にもお顔をお出しになられていたというわけですね。
大半の者は、ただ一声掛けてもらっただけですが、私も似たようなものですからね。その言葉はすんなりと受け入れられましたよ。
「スマイリー中級管理官殿! 俺らもこんな辺境に連れてこられて腐ってたが、久しぶりにいい気分になれた、なぁ、みんなそうだろう?」
「おおぉ!」
「今日は、宿場町の酒場に来な、俺がおごってやるよ!」
チーフにもう一度背を叩かれ、私は何やら不思議な気持ちになりましたね。
つい今朝方まで「こいつらは自分と別種の人間だ」と思っていたのですから。
王族に敬意を払うわけでもなく、ただ粗野で勉強のできない連中だってね。
でも、そんなことはなかった。
こいつらも自分と同じ、辺境に飛ばされ、イヤな奴の指示を聞くように命じられて、腐りながらも仕事をしていたのです。
そう気づいた途端……なんていうか、私は自分の仕事に誇りのようなものを感じたのですよ。
それ以来、兵士たちと仲たがいすることもなく、毎日楽しく仕事をさせていただいています。
すべては、アリエル様のおかげですね。
あのお方は、ただ関所を通るだけで、その場を平和にしてしまったのです。
※この後、スマイリー中級管理官はいかに自分がアリエル王女に心酔しているかを延々と話し続けたため、割愛。
★ ★ ★
さて。
この話の後、スマイリー中級管理官のアリエル王女を褒め称える言葉は聞いていてなかなかに面白かったが、聞きたいのはそんなことではない。
「アリエル王女を追って、黒ずくめの男が関所を通りましたか?」
そう聞くと、スマイリー中級管理官は表情を曇らせた。
「追っ手……ではありませんでしたね」
「と、いうと?」
「アリエル王女が来る三日ほど前、私が非番の日に、怪しい集団が関所を越えたというのを、後になって聞きました」
なるほど。
つまり追っ手はすでに関所を越え、アリエル王女を待ち構えていたというわけだ。
「もし知っていれば、せめて警告の一つでも言えたのに……今は無事を祈るしかありません」
「なるほど、ありがとうございました」
どうやら、スマイリー中級管理官は、アリエルが死亡したという噂を知らないようである。
やはりあの噂は、王都で発生した噂なのだろう。
しかし、これではまだアリエルの生死は判別しない。
私は情報収集を続けることにした。
現時点の情報だけでは、仕事を完遂することはできないからだ。
他の管理官や、兵士にも聞き込みをし、さらには宿場町に移動して、関所に詳しそうな者に話を聞いて回った。
アリエルがその後、どうなったのか。
森を抜けることはできたのか、それとも森を抜けられず、噂通り殺されてしまったのか。
それを知る者を探し、宿場町を駆けずり回った結果……。
凄腕である私は、ある若い行商人に出会い、話を聞くことに成功した。
★ 行商人ブルーノの証言 ★
あの日はいつも通り、商品をアスラ王国へと運ぶ途中だったよ。
赤竜の上顎を抜けて、竜の髭の一本道を……え? ああ、この辺の奴らは、北の森のことをみんなそういうんだ。誰が呼び始めたのかは知らないけどな。
で、商品……運んでたのはなんだったかなぁ。確か北方大地でしか取れない毛皮の類だったかな。
人数? 一人だよ。
護衛? いないよ。そんな金を持ってるように見えるか?
俺自身、腕も立つしな。こう見えても、剣の聖地で修行してたこともあるんだぜ?
ええっと、何の話だったっけか。
そうそう、竜の髭を移動していた時のことだ。
相棒のロビンソンと一緒にな。え? そのロビンソンはどこにいるのかって? 馬小屋にいるよ。ロバだけどな。
とにかく、俺はそいつと一緒に移動していた。
気分はよかったな。なにせ商売は順風満帆、そろそろ馬車を購入する資金が貯まりそうだったんだ。ロバでも引けるような小型の馬車でも、運べる商品の量はグッと増えるからな。ウキウキしてたよ。
でも、ふと道の先から、剣戟が聞こえてきたんだ。
ついでに、きな臭い雰囲気も漂ってきた。
俺も一人で行商人をやってるわけだから、こういう気配には敏感なつもりだ。
危険を避けるってのは、一番重要なことだからな。
とはいえ、一本道だ。引き返すわけにもいかないってんで、俺はロビンソンと共に森へと入り、脇を通り抜けることにした。
ロバを置いてったほうが賢いってのはわかってたが、何せ大切な相棒だからな。ほったらかして魔物にでも襲われたら大変だ。
てことで、俺とロビンソンは森の中を隠れるように進んだ。
剣戟の音は次第に大きくなり、人の叫び声も聞こえてくるようになった。ロビンソンは怯えていたが、長年苦楽を共にしてきた俺が一緒だ、怯えた声を上げることなく静かに移動していた。
なに? 前置きはいいから、現場のことを教えろって?
せっかちな野郎だな……まあいいか。
現場、茂みに隠れていた俺の目に飛び込んできたのは、馬車だった。あまり大きい馬車じゃない。せいぜい御者を含めて三人しか乗れないような馬車だ。一頭立てのサイズだったが、馬は二頭。恐らく特注品だろうな……なんで詳しいのかって? そりゃ、俺も馬車を買おうとしてたからさ。ロバが引けるようなのをな。その時に馬車屋の商人に聞いたんだが……あぁ、わかったわかった、そんな怖い顔するなよ。オーケー、脱線はなしだ。
俺は一目見て、馬車が襲われているのがわかった。
何しろ、馬車は横倒しになっていて、周囲で護衛と思わしき者と、黒ずくめの男たちが戦っていたからな。
黒ずくめが七人に対して、護衛側が四人だ。すでに馬車の護衛、いや従者かな? とにかく二人ほど地面に倒れていたな。馬車の近くで女が四人震えていた。恐らく彼女らは護衛対象の方だったんだろうな。
っても、黒ずくめが優勢ってわけじゃなかった。
なにせ、黒ずくめの方が多く倒されていたからだ。
地面に転がってる黒ずくめの数は、ゆうに十はいたな。
俺はそれを見た時、呆れたね。こんな弱い奴らを襲撃者にするなんて、馬鹿じゃねえのかって。
でも違った。
よく見てみると、黒ずくめの動きは悪くないんだ。
むしろ、護衛たちよりも手練れで、一対一なら黒ずくめたちは万が一にも負けないんじゃないかってほど差があった。
え? なんでそんなことわかんのかって?
さっきも言っただろ。俺はこう見えても、腕には自信があるんだ。戦ってるところを見りゃあ、そいつらがどれぐらい強いかぐらいはわかる。
でまぁ、おかしいと思った俺は、つい足を止めて、その戦いに見入ってしまった。
するとな、護衛の中に一人だけ、ずいぶんと動きのいい奴がいるんだよ。
白い髪をして、初心者用のロッドを持った少年だ。
あいつ一人だけ、次元が違ったな。
剣の聖地で剣聖とか、剣王になるような奴らは、俺らとは違う時間を生きてるんじゃないかって思えるぐらい素早くて判断力が高い。
そいつはそこまでじゃなかったけど、でもいわゆる状況判断能力ってやつがずば抜けて高いのはすぐにわかったよ。
味方がやられそうになったら、そこに即座に援護の魔術を飛ばすんだ。
それも、魔力切れを考慮してか、初級の魔術をな。
あの神がかった援護は、やろうと思ってもできるもんじゃないな。
よっぽど頭を使った上で訓練しなきゃ、ああは動けねえな。
俺の位置からじゃあ詠唱は聞こえなかったが、もしかするとあれは、無詠唱ってやつなんじゃねえかな。詠唱なしで魔術を使うっていう……見たことはねえが、いるところにはいるもんだな。
とはいえ、だ。
恐らく黒ずくめの方も、仲間が倒される間に、その戦い方に慣れてしまったんだろうな。
加えて言えば、護衛たちの方も疲労の色が濃かった。
見た目以上に拮抗していたんだろうな。どっちかが一人でも倒されれば、その均衡が崩れて敗北する。そんな雰囲気を感じ取れたよ。
でまぁ、余裕があったのは、黒ずくめの方だったな。
黒ずくめたちは、ある瞬間、戦法を変えたんだ。恐らく、直前に目配せなり合図なりしたんだろうが、俺の目にはわからなかった。
黒ずくめはそれまで、常に二対一の状況を崩さず、残った一人が遊撃しながら真正面から攻めてたんだが、唐突に、七人全員が白い髪の少年に向かっていったんだ。
護衛、剣を持ってる三人はそれに反応できなかった。
白い髪の少年は反応した。
すさまじい集中力で、とっさに範囲魔術を放って、二人を葬った。
黒ずくめたちはそこで散開し、二人は白い髪の少年へ、三人は馬車の隅で震える女どもの方へと躍りかかった。一瞬の間隙をついて、防衛網が突破された瞬間だ。
白い髪の少年は、そこでもまだ動いていた。
自分に向かってくる二人には目もくれず、女どもの方に向かった黒ずくめに向けて、杖を向けたんだ。すげぇよな。普通は自分に向かってくる相手に意識がいっちまうところだ。
さて、次の瞬間は、ほぼ同時だ。
まず、白い髪の少年が放った魔術。こいつは三人のうち、二人を巻き込んで殺した。
白い少年に向かっていた黒ずくめ。こいつらは、白い少年を守ろうと体を飛び込ませた二人の護衛と相打ちになった。
最後に残った黒ずくめは、馬車の近くで固まって震える女の中から一人を引きずりだし、その首を撥ねた。一撃でな。
一瞬遅れて、護衛の最後の一人が、黒ずくめを後ろから刺した。
最後の黒ずくめは、手に持った首を自慢げに持ち上げて、満足そうな顔をして、死んでいったよ。
恐らく、あれが護衛たちが守ろうとしていた、貴族のお嬢さんか何かだったんだろうな。
残った五人は、呆然としていたよ。
仲間が死に、守るべき対象も失ったんだから、当然だろうな。
俺は決着がついたのを確認して、すぐにその場を離れたよ。
血の匂いに誘われて、魔物が近づいてきたら面倒だし、なんか頼まれごとをするのも嫌だったしな。
ロビンソンと共に、あっという間にその場を離れたよ。
★ ★ ★
行商人ブルーノの話は以上で終わりだった。
中級管理官スマイリーの話と総合すると、無事に関所を抜けたアリエル王女は、森の中で待ち伏せを受け、激戦の末、暗殺者の手に掛かってしまったということになる。
噂は真実であり、アリエル派の貴族たちが危惧している通り、アリエルは死んでしまった。
ただ、未だ少し謎が残っている。
例えば、生き残った護衛はどうなってしまったのか。
話によると五人は生存している。
『ルーク・ノトス・グレイラット』はわからないが、少なくとも『無言のフィッツ』は生き残っている。
目立つ風貌をした彼が、王都に戻ってきたという情報はなかった。
あるいは私の探したのとまったく別ルートで戻ってきた可能性もあるが、しかしこの国境を通ったのは間違いないはずで、そこで情報を得られないとなると、やはりそのまま北へと移動してしまったのだろうか。
さもありなん。アリエル王女の護衛に失敗して、どの面を下げて戻れるというのか。
そのまま北方大地へと逃げ延びたほうがいいと判断したのかもしれない。
それも国境を越えて北へと赴けばわかることだが……。
残念ながら、私はアスラ王国内で起きたことで調べられないことはないと豪語する情報屋。
アスラ王国の外で起きたことは調べられないのだ。
それに、私が調べてこいと言われたのは、アリエル・アネモイ・アスラ第二王女の行方である。
その護衛に関しては管轄外だ。
というわけで、私は王都へと戻ることにした。
シティボーイである私にとって、国境はどうにも馴染めない。
しかし、行商人ブルーノから北方大地の珍しい酒を手に入れることができた。仕事がすんだらコイツを一杯やるとしよう。
★ ★ ★
報告を終えた時の、アリエル派の落胆した顔は見ものであった。
普段私より上位の情報を扱っているであろう者が、私のごとき者が集められる情報を得て感情を変化させるのは、実に新鮮な感覚だった。
ともあれ、報酬も受け取り、私の仕事は終わりだ。
今日は彼の顔と、受け取った報酬と、ブルーノから購入した酒で、気持よい晩餐を迎えよう。
そう思い、私は酒瓶を手に酒場へと赴いた。
マスターに肴を頼み、お気に入りの席にゆったりと座る。店の中の様子がよく見えるこの席は、私の定位置だ。
ここに座って耳をすませるだけで、酒場中の話題を聞き取ることができるというのも、私の能力の一つだ。この能力により、私はどんな情報も聞き逃すことなく、凄腕の情報屋として生計を立てている。
「そういや、少し前に王女が死んだって噂、流れてたらしいな?」
「ああ、残念ですよね、俺ファンだったのに……」
「なんだ、お前、あんな噂を本気にしてるのか?」
「いや、俺だって信じたくはないですけど……」
ホットな話題が聞こえてきて、私はそちらに顔を向けた。
ガッシリとした体つきの男と、初老の男が二人、向い合って酒を飲んでいた。
彼らも、きっと真相は知らない。噂に踊らされるダンサーなのだ。そう考えると、非常に気分がいい。情報屋をやっててよかったと思う瞬間である。
「俺はさ、国境に勤めてんだ」
「改めて言わなくても、叔父さんの勤務地ぐらい知っていますよ。勤務二十年で長期休暇をもらってこっちに戻ってきてるってこともね」
「へぇ、そいつは物知りだな。じゃあ、俺が関所のどこで仕事してるのか、知ってるか?」
「それは知らないけど」
話題は変化し、私の興味も薄れていく。
マスターが私の肴を作り上げたのが見える。もういいだろう、終わった仕事だ。次の仕事は、この酒の美味しい飲み方を探ることだ。
「物見の塔さ」
しかし、次の言葉で、私の意識は酒から男へと戻された。
「あの関所のてっぺんには、森の出口を監視するための遠見の魔道具がある。俺はそこのチーフだ」
「へぇ」
「でな、関所をアリエル様が通ったって話は、わりと兵士たちの間では有名でな。俺たち見張り部隊も一目でいいからアリエル様の姿を見たいと思って、目を皿のようにして見てたんだ」
「そ、それで? 見れたんですか?」
「ああ、バッチリな。紛れもなくアリエル様だった」
私はその言葉を疑った。
この兵士が嘘をついているのか、それともブルーノが嘘をついたのか。
いいや、そうではあるまい。恐らく、ブルーノは勘違いをしていたのだ。黒ずくめが最後に殺したのは、アリエル王女ではなかったのだ。
アスラの王族には、影武者を仕立てるための魔道具の類もあると聞く。それを用いて、あの襲撃を脱したのだろう。
つまり、私は早とちりをしてしまったのだ。
依頼人に間違った情報を渡してしまった。
これはいけない、すぐに今の話の裏を取り、依頼人に真実を伝えなくては……!
「……おまちどさん」
そこで、マスターが料理を運んできた。
目の前には、湯気の立つ料理と、王都ではなかなか飲めない珍しい酒。
「まあいいか」
私は浮かしかけた腰をおろした。
本当に生きていて、ラノア魔法大学に留学したというのなら、そのうち真実が世に広まるだろう。
報酬を返せと言われても困るし、しばらくしたら王都から離れることにしよう。
それにしても、監視塔の兵士がアリエルの姿を確認していたとは……いやはや、聡明な私にも、わからぬことはあるのだ。
情報屋グスタフによって伝えられた誤情報。
それにより、アリエル派の筆頭貴族ピレモン・ノトス・グレイラットはひとつの辛い選択を強いられ、窮地へと追い込まれるのだが……それはもっとずっと後の話である。
作者闲话
『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ XX』
理不尽な孫の手先生 こぼれ話
皆さんこんにちは。
5巻まで読んだのに初めましてという方はいないと思いますが……。
5巻を楽しむには、1巻での出来事をリフレインして頂く必要があるので、是非1巻から読んで見てください。
あ、申し遅れました。
初めまして、理不尽な孫の手です。
5巻は、無職転生の主旨の一つでもある『前世のやり直し』や『家族との和解』がメインテーマとなったお話です。
数年ぶりに出会った親子が、それぞれの苦悩を不器用にぶつけあい、ぶつかり合い、後悔し、反省し、歩み寄り、許し合い、和解する。
そんなお話です。
普通だったら、こんな綺麗に仲直りしたりは出来ないものですが、そこは家族とぶつかり合うのは二度目のルーデウス氏という事で、不器用なりに頑張って動いてくれます。
コミュニケーションは互いの努力。
だから二人が頑張れば、必ず落ち着く所に落ち着く……。
というのは、あくまで私の願望ですが、説得力のある内容になっていたのではないかと思います。
さて、今回もキャラクターの話をしていきましょう。
今回はルーデウスのパパ。
パウロ・グレイラットについてお話していきましょう。
・父親という存在
パウロは当初、父親として誕生しました。
転生系の小説によくいる、普通の父親です。
剣術は一流で、強くて、可愛い奥さんを持っていて、村で一番頼りにされている騎士。
普段はちょっと情けない所もあるけど、いざという時には主人公を叱ってくれたり、かっこいい所を見せてくれる頼れる親父。
でも、書いている時に思いました。
あれ、パウロってまだ若いよな、と。
『無職転生』の世界、特にアスラ王国では成人は「15歳」と定められています。
国によって違う所もあるのですが、基本的に人族は15歳前後で成人します。
15歳前後で成人を迎えていた昔の日本では、20歳を過ぎると年増・行き遅れなんて言われていたそうです。
もちろん、中には20歳をずっと過ぎてから結婚した人もいるでしょう。
でも、大半は10代中盤から後半に掛けて結婚し、20歳までに出産したのではないないか。
その時代には、それが「平凡」だったのではないか。
ルーデウスの生まれてくる家庭は、平凡な家庭であるべきだ、と私は考えていました。
なぜなら、彼の前世の家がそんな家庭だったからです。
凄く裕福ではないけど、ことさらに貧乏でもなく余裕はあって、子供を四人養える家。
中流階級か、平均よりちょっと上ぐらいの家。
その世界における平凡だからこそ、彼は家の事を言い訳にせず「やり直す」ことができるのだ。
でも、平凡だとすると、パウロは若いはず、20歳そこそこなはず。
この現代日本においても、20代前半といえば、色々と不安定な時期です。
周囲の20代前半の若者達を見てみてください。
高校生かと思うほど考えたらずで、行動や言動が幼稚な奴。
実は30代なんじゃないかと思えるほど大人びた奴。
いろんなのがいると思います。
もっとも、パウロは仮にも結婚して子供も作り、従兄弟に頭を下げて、家と仕事ももらった。
子育てをする覚悟のようなものは決めている男です。
というわけで誕生したのが「良い父親であろうとしている普通の若者」。
パウロ・グレイラットです。
彼は偉大でもなんでもなく、父親としての威厳もなく、己の欲望に忠実で、子育てといっても右も左もわからない、どこにでもいる若者なのです。
・パウロとルーデウス
さて、そんな初心者パパが最初に授かった子供、それがルーデウスです。
ルーデウスは前世において、34歳であるにも関わらず、分別もなにもついていないクズニートでした。
とはいえ、彼も34年間を生きてきた経験から、「どうすれば賢く生きていけるか」を考え、努力しながら育っていきます。
20年近くもニートとして生きてきた奴……でも3歳です。
3歳児が、34歳児の思考能力を持って、行動し、発言するのです。
パウロの父親としての予定は、大きく狂ってしまいます。
厳格な父親であろう、立派な父親であろうと思ったパウロは、事ある毎に失敗します。
偏見で子供を怒鳴りつけ、殴ったり。
自分の欲望に負けて浮気をしてしまったり。
そうしてルーデウスに助けられ、気付かせられ、父親としての威厳を失っていきます。
でも、成長していきます。
人として、父親として。
少しずつ、「大人」へ、いい父親へと近づいて行くのです。
そしてまたルーデウスも、成長するパウロと接する事で前世の事を思い出し、悔恨し、省みて、成長していくのです。
今後、ルーデウスにとってパウロがどういう存在になっていくのか。
そして、パウロという存在によってルーデウスがどう変わっていくのか。
お楽しみにしていてください。
WEB版既読の人はネタバレしないようにお口にチャックで。
文库版 无职转生~到了异世界就拿出真本事~