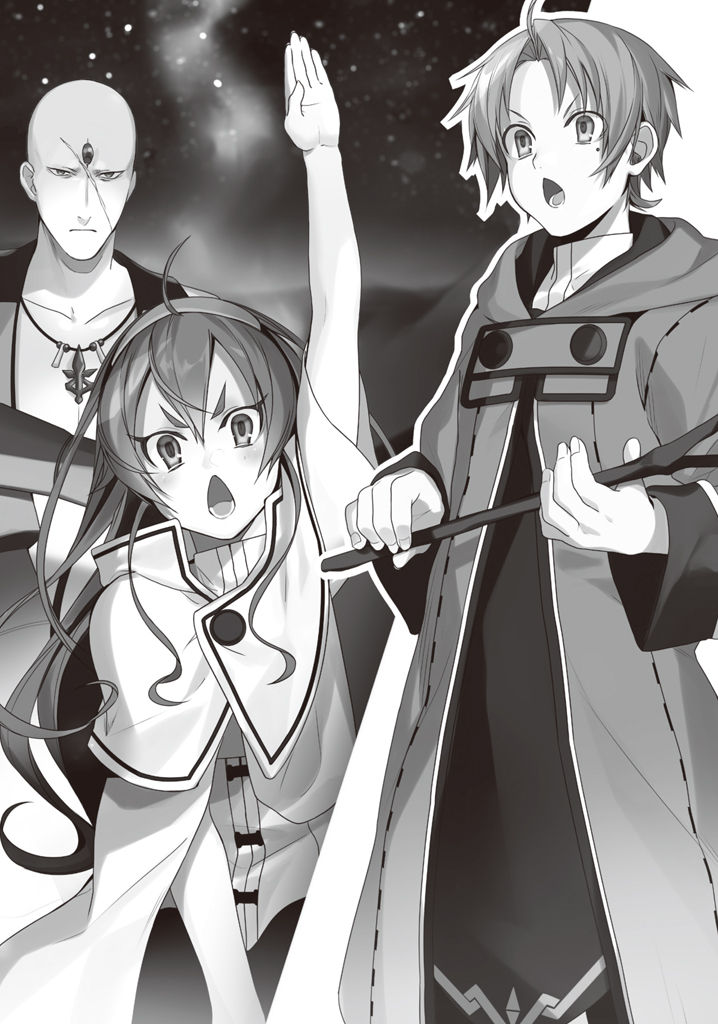無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
第三巻
著者:理不尽な孫の手 角色原案:シロタカ
发售时间:2014年05月23日
特装版发售时间:2020年12月16日
本馆一并提供Epub电子书下载 请自行前往 洛琪希图书馆借书柜台 借阅
制作信息
简介
简介
愛する家族を取り戻せ。“人生やり直し型”ファンタジー第三弾!
無職ニートだった男・ルーデウスは、原因不明の魔力災害に巻き込まれてしまったことで、家族と離れ離れになってしまう。
災害によって転移した先は見知らぬ場所。一緒にいたのは、家庭教師の教え子でもあるお嬢様のエリス。不安が募るルーデウスの側に怪しい人影が……!?
エメラルドグリーンの髪に白磁のような白い肌、赤い宝石のような額の感覚器官。それは、ルーデウスの師匠だったロキシーから「絶対に近づくな」と教えられていた存在――スペルド族だった!!
あの幸せを取り戻せ! 大人気の“人生やり直し型”異世界ファンタジー第三弾!
目录
CONTENTS
第三章 少年期 冒険者入門編
「僕が簡単にできることを、君はできない。
君が簡単にできることを、僕はできない。それだけの事さ」
── Since working is very difficult, please do not say simply.
著:ルーデウス・グレイラット
译:ジーン・RF・マゴット
第一話 「神を名乗る詐欺師」
夢を見ていた。
夢の中で俺はエリスを抱えて飛んでいた。
意識は朦朧としていたが、飛んでいる、という感覚だけはなぜかあった。
目の前の景色は、凄まじい速度で変化していく。
まるで音か光にでもなったかのようなスピードで、上下左右、不規則に動きながら飛んでいる。
なぜこんなことになっているのかわからない。ただ、気を抜けば、いや、気を抜かずともいずれ失速して落ちるという確信だけはあった。
俺は意識を集中させる。
めまぐるしく変わる景色の中で、比較的安全そうな場所を探し、着陸しようとした。
なぜと聞かれてもわからない。
ただ、そうしなければ死ぬ予感がした。
しかし速すぎる。
スロットの目押しなど比べ物にならない速度で目の前の光景が変わっていく。
俺はさらに意識を集中させ、魔力を目に込めるようにした。すると、一瞬だけ速度がゆっくりになった。
まずい、落ちる。
そう思った時に地上が見えた。
平地だ。海はまずい、山もまずい、森も危険、だが平地なら、あるいは……。
そんな望みを掛けて、俺は降りる。
どうにかして急ブレーキを掛けて、赤茶けた大地へと落ちた。
意識が途絶える。
★ ★ ★
目を開けた瞬間、俺は真っ白い空間にいた。何もない空間だ。
ゆえに、すぐに夢だとわかった。明晰夢というやつだろう。
それにしても、夢だというのに身体が重い。
「………え?」
俺はふと自分の身体を見下ろし、驚愕で目を見開いた。
三十四年間見慣れた、あの姿だった。
それと同時に、前世の記憶が蘇ってきた。
後悔、葛藤、卑しさ、甘えた考え。
この十年間が夢のように思え、俺の中に落胆がこみ上げてきた。
戻ったと、直感的に悟り、その現実を俺は簡単に受け止めた。
やはり夢だったのだ。
長い夢だと思ったが、俺にとっては幸せすぎた。
温かい家庭に生まれ、可愛い女の子と接しながらの十年。もっと楽しみたかったが。
そうか。終わりか……。
ルーデウスとしての記憶が薄れていくのを感じる。
夢なんて、覚めてみるとあっけないものだ。
何を期待していたのだか。あんな幸せで順調な人生、俺に送れるはずがないのにな。
★ ★ ★
ふと気づくと、目の前に変な奴がいた。
のっぺりとした白い顔で、にこやかに笑っている。
特徴はない。こういう顔の部位だと認識すると、すぐに記憶から抜けていった。覚えることができないのだ。そのせいか、まるで彼全体にモザイクが掛かっているような印象を受ける。
ただ、穏やかそうな人物だと思った。
「やあ、初めましてかな。こんにちは、ルーデウス君」
落胆に暮れていると、卑猥なモザイク野郎が話しかけてきた。中性的な声だ。男か女かわからない。モザイク掛かってるし、女だと考えたほうがエロくていいかもな。
「聞こえているよね?」
ああ、もちろんともさ。はいはい、こんにちは。
「うんうん、挨拶ができるのはいいことだね」
声は出なかったが、相手には通じたらしい。そのまま会話をすることにしよう。
「いいね君、適応力あるよ」
そんなことはありませんよ。
「んふふ。そんなことはあるよ」
で、あなたはどこのどなた様?
「見ての通りだよ」
見ての通り? モザイクでよく見えないんだが……。絶倫戦士スペルマンとか?
「スペルマン? 誰だいそれは、僕に似てるのかい?」
ええ、全身がモザイクで見えないところがそっくりだ。
「なるほど、君の世界にはそういうのもいるのか」
いませんけどね。
「いないのかい……。まあいいや。僕は神様だよ。人神だ」
はあ。ヒトガミ……。
「気のない返事だ」
いえ……そんな神様がどうして俺に話しかけてきたのかな、と。
ていうか、登場するの遅くないですか?
神様って、普通はもっと早く出てくるものじゃないのか?
「もっと早く……? どういう意味だい?」
なんでもないです。続きをどうぞ。
「君のこと、見てたよ。なかなか面白い人生を送っているじゃないか!」
ノゾキは面白いですもんね。
「そう、面白い。だから、見守ってやることにしたんだよ」
見守って、やる。
そりゃどうも。恩着せがましいですね。
しかも見下されてる感じがむかつきますね。
「つれないねえ。君が困っているだろうと思って声を掛けたのに」
困った時に声を掛けてくるヤツにはロクなのがいません。
「僕は君の味方だよ」
ハッ! 味方! 笑っちゃうね。
生前に、そういって擦り寄ってきたヤツはいたよ。
僕は君の味方だ。さぁ、僕が守ってやるから頑張ってみようってな。
無責任なヤツラだったよ。部屋の外にさえ出せば後はどうにかなるなんて考えてやがる。
問題の本質ってやつをまるで理解してないヤツラだ。今のお前の発言から、そういう匂いがする。
信用できないね。
「そこまで言われちゃうと困るなあ……。じゃあ、とりあえず助言をさせてくれよ」
助言ねえ……。
「従うも従わないも、君の自由ってことさ」
ああ。そういうタイプね。
いたいた、いたよ。助言つって、感情論を語って、俺の思考が内ではなく外に向かうように誘導するんだ。
ほんと、本質がわかってねえんだ。今更ポジティブになったって意味はないんだよ。心の持ちようでどうにかなる時期はとっくに過ぎたんだよ。ポジティブになった分だけ、絶望が加算されて戻ってくるのさ。
今みたいにな! 夢見させやがって、何が異世界だ! 転生とかいっていい気分にさせておいて、キリのいいところで引き戻すのがお前のやり方かよ。
「いやいや、勘違いしないでくれよ。前世のことじゃなくて、今の話をしているんだから」
……ん?
じゃあこの姿は?
「君の精神体だよ。肉体は別」
精神体。
「もちろん、肉体は無事だ」
なら、これはただの夢? 目が覚めても、このクソみたいな身体に戻るわけじゃ……ない?
「イエス。これは夢だよ。目が覚めれば、君の身体は元通りだ。安心したかい?」
安心した。そうか、夢か……。
「おっと、ただの夢じゃないよ。僕が君の精神に直接語りかけているんだ。驚いたね、精神と肉体がここまで違うとは……」
直接ね。で、どうしようっていうんだ?
異物はウザいから元の世界に戻そうっていうのか?
「まさか、六面世界以外の異世界には、僕にだって送り返せないよ。そんな当たり前のこともわからないのかい?」
むっ。何が当たり前で、何がそうじゃないのかなんて、俺にわかるわけないだろ。
「ごもっとも」
まてよ。送り返せないってことは、あんたがこの世界に転生させたわけじゃないってことか。
「まぁね。大体、僕は転生なんてさせられないよ。そういうのは、悪い龍神の得意とするところさ」
ふむ。
悪い龍神のねえ……。
「で、聞くかい? 助言」
…………聞かない。
「えっ! どうしてだい?」
今の状況がどうであれ、おまえは胡散臭い。胡散臭いヤツの話は最初から耳を貸さないに限る。
「胡散臭い、かなあ……?」
ああ、胡散臭い。騙そう騙そうって感じがプンプンするね。
ネトゲで詐欺に遭った時によく似てる。話を聞いた時点で操られてるんだ。
「詐欺じゃないよ。それなら聞くか、聞かないかなんて言わないよ」
それも作戦だろ。
「信じてくれよぉ」
神のくせに情けない声を出しやがって。
大体、俺が信じてる神はお前じゃないんだ。
ちゃんと奇跡を与えてくれたお方なんだよ。異教の神が変なこと言ってきたら、疑って当然だろうが。それにな、信じる、信じないを口にするヤツは嘘つきなんだ。俺の愛読書にそう書いてあったから、間違いない。
「そんなこと言わずにさ。最初の一回だけでいいんだ」
なんだよ、その先っぽだけでいいから、みたいなのは。絶対に騙そうとしてるだろ。
大体、俺が生前で何度神に祈ったと思ってるんだ。
死ぬまで助けてくれなかったくせに、今更助言?
「いや、君の前世の世界の神様と僕は違うから。それに、これから助けようって言ってるんだよ?」
だから、それが信用できないって言ってるだろ。言葉だけじゃダメなんだよ。信用してほしいなら、奇跡でも起こしてみろよ。
「起こしてるじゃないか。夢を通して語りかけるなんて、僕にしかできないよ」
語りかけるぐらい、夢を通さなくてもできるだろうが。手紙でもなんでも出せばいい。
「ごもっとも。とはいえ、信用できないって言われてもねえ。このままだと君、死んじゃうよ?」
……死ぬ? なんで?
「魔大陸って過酷な大陸だもん。食べ物だってほとんどない。魔物は中央大陸とは比べ物にならないぐらい大量にいるし、言葉はわかるみたいだけど、常識も結構違うよ? やっていけるのかな? 自信あるの?」
は? 魔大陸?
魔大陸っていうと、世界の端にある、あの大陸か?
ちょっと待って、なにそれ? なんで俺がそんな所に?
「君はね、大規模な魔力災害に巻き込まれて転移したの」
魔力災害。あの光のことか。
「そう。あの光のこと」
転移。あれは転移だったのか……。
……そうだ、巻き込まれたのは俺だけじゃない。
俺が元いた、フィットア領の人たちは無事なんだろうか。生まれ故郷であるブエナ村は距離もあったし大丈夫だろうけど、家族たちも心配しているに違いない……。
と、そこのところ、どうなんだ?
「それを僕に聞いて、信じるのかい? 助言は聞かないのに?」
そうだな。お前は簡単に嘘をつきそうだ。
「僕に言えるのは、みんな君の無事を祈ってるってことさ。生きて帰ってきてほしい、ってね」
そりゃ……誰だってそう思うだろ。
「そうかなー? 君は、心のどこかでは、自分が消えて他の皆が安心してるんじゃ……って思ってるんじゃないのかな?」
……思っていないと言えば、嘘になる。
俺はいらない人間として前世を終えた。それはいまだに引きずっている。
「けど、この世界の君はいらない存在じゃない。無事に帰らないとね」
ああ、そうだな。
「僕の助言に従えば、絶対とは言わないけど、高確率で帰ることができるよ?」
まて。その前にお前の目的を聞きたい。なんで俺にそこまでこだわるんだ?
「くどいなあ……。君が生きていると面白そうだから。それでいいじゃないか」
面白いって理由で行動するヤツに、ロクなのはいない。
「君の前世ではそうなのかい?」
面白いという理由で行動するヤツは、他人を手のひらに乗せて楽しむ輩だ。
「僕にもそういう部分はあるかもね」
大体、俺を見ていて面白いわけがないだろうが。
「面白いというか、興味深いのかな。異世界人なんて滅多に見ないからね。僕が助言を与えて、いろんな人と触れ合い。それがどんな結果に繋がっていくのか……」
なるほどな。猿に曖昧な命令を与えて、それをどういう風にクリアするのかを楽しむってわけか。
大層なご趣味だな。
「はぁ………君ね。最初の質問、忘れてないよね?」
最初の質問?
「もう一度聞くよ。自信はあるかい? 知らない危険な土地で、生きていく自信は」
……ないよ。
「じゃあ、聞いたほうがいいんじゃないかい? もう一度言うけど、従うも、従わないも、君の自由なんだから」
わかったよ。わかりました。助言でもなんでも勝手にすればいいだろう。
こんなぐだぐだと長いこと話しやがって。一方的に告げて、さっさと終わらせればよかったんだ。
「……はいはい。ルーデウスよ。よくお聞きなさい。目が覚めた時に近くにいる男を頼り、そして彼を助けるのです」
モザイク神は、それだけ言うと、エコーを残しながら消えていった。
第二話 「スペルド族」
目覚めると夜だった。
見えるのは満天の星と、ゆらゆらと揺れる炎の影。
聞こえるのは木が燃えるパチパチという音。
焚き火の側で寝ていたらしい。
もちろん、俺には焚き火をおこした記憶もなければ、野宿を始めた記憶もない。
最後の記憶は……そうだ。空がいきなり変色したと思ったら、白い光に包まれたのだ。
そして、あの夢だ。くそ。嫌な夢を見た。
「はっ……!」
慌てて自分の身体を見下ろす。
鈍重で何もできない身体ではない。幼くも力強いルーデウスに戻っていた。
それを確認すると同時に、先ほどの記憶が夢のように薄れていく。ほっと一安心。
「ちっ……」
人神め、嫌な感覚を思い出させてくれる。
けれど本当によかった。俺はまだ、この世界で生きていけるらしい。
やり残したことがいっぱいあるからな。……せめて、魔法使いの証ぐらいは捨てたい。
身体を起こしてみると、背中が痛かった。地面にそのまま寝かせられていたのか。
周囲を見渡すと、夜空の下、ひび割れた大地が広がっていた。草木はほとんど生えていない。
虫すらいないのか、焚き火の音以外には何も聞こえてこない。
静かだ。
音を立てれば、どこまでも吸い込まれていきそうな気配すらあった。
少なくとも、俺の記憶にはこんな場所はない。アスラ王国は全土が森か草原だ。あの白い光でこんな風になったのか……?
ああ、いや。違う。そうじゃない。人神が言っていた。俺は転移したんだ。
魔大陸に。
なら、ここは魔大陸だ。
きっと、あの光のせいで……あ。
(ギレーヌとエリスは……!)
立ち上がろうとしたところで、すぐ後ろで一人の少女が俺の裾を掴んで寝ていることに気づいた。
勝ち気そうな赤毛の少女である。
エリス・ボレアス・グレイラット。
彼女は、俺がフィットア領で家庭教師を務めていた相手だ。
なぜ俺が彼女の家庭教師を務めることになったか、という経緯は省くが、俺はこの三年間、彼女に読み書きや算術を教えていた。
エリスは最初、傍若無人でワガママ、どうしようもなく手がつけられない悪童だったが、誘拐されそうになったのを助けたり、誕生日にダンスを教えてやったりと順調にイベントをこなしたせいか、最近はなんとか俺の言うことは聞くようになってきていた。
それでも、殴ったり蹴ったりは日常茶飯事な乱暴者であることに変わりはないが。
「……」
なぜかエリスには、マントのようなものが掛けてあった。俺はなにも掛けてなかったんだが……。
まぁ、レディファーストということにしておこう。
また、彼女の背後には俺の杖である『傲慢なる水竜王』も転がっている。つい先日、俺の十歳の誕生日にエリスからもらった、高級な杖だ。
とりあえず、エリスに外傷はなさそうだったので、ほっとする。
ギレーヌはどこだろうか。
ギレーヌとは、俺の剣術の師匠にして、エリスの護衛の女剣士のことだ。
すさまじい剣の腕を持つ獣族の剣士で、俺は彼女に剣術を教わる代わりに、彼女に勉強を教えていた。もっとも、脳みそまで筋肉でできているらしく、出来はエリスよりも悪かったが……こういう非常事態では、俺なんかとは比べ物にならないぐらい、頼りになる人だ。
エリスのマントも、彼女が掛けたのかもしれない。
ひとまず、寝ているエリスは放っておき、ギレーヌの姿を探す。
辺りを見回すと、先ほどは気づかなかったが、焚き火の近くに人影があった。
「……!?」
ギレーヌではない。座っているのは男だった。
「……」
彼は俺を観察するように、微動だにせず、じっと見ていた。
俺は肉食獣に睨まれた草食動物のように動きを止め、彼を見た。
驚きつつも、俺は彼の様子を冷静に観察していた。
警戒している感じではない。むしろ、何かにこう。なんだっけな。そうだ。猫に恐る恐る近づく時の姉貴みたいな感じだ。こちらが子供だから、怯えられないか心配なのだろうか。なら、敵意はなさそうだ。
ほっとした瞬間、俺は男の風貌に気づいた。
エメラルドグリーンの髪。白磁のような白い肌。赤い宝石のような額の感覚器官。顔には縦断する傷。眼光は鋭く、表情は厳しく、剣呑とした印象。
極めつけに、脇においてある三叉槍。
幼少期、俺の先生であり、人生においてもっとも重要なことを教えてくれた魔術師──ロキシーから教えられた種族名が思い浮かぶ。
スペルド族。
同時に、ロキシーの教えを思い出す。
『スペルド族には近づくな、話しかけるな』
俺はとっさにエリスを抱えて全力で逃げようとして、寸前で思いとどまった。
人神の言葉を思い出したのだ。
『近くにいる男を頼り、助けるのです』
あの自称神の言葉は信用できない。
あんな話の後で、こんな怪しい男をポンと出して、信じられるわけもない。
しかもスペルド族だ。ロキシーからこの種族の怖さはさんざん教えられてきた。
いくら神に頼って助けろと言われたところで、どうして信じられよう。
どっちを信じる? 得体の知れない人神と、ロキシーと。
言うまでもない。信じたいのはロキシーだ。だから、俺はすぐに逃げるべきだ。
いや。だからこその『助言』なのかもしれない。何の情報もなければ、俺はこの男から逃げただろう。その結果、運良く逃げ切ることができたら……どうなる?
周囲を見ろ。
この暗くて見覚えのない風景を。岩ばかりでひび割れた地面を。
魔大陸に転移したという言葉をそのまま信じるのなら、ここは魔大陸だ。
そういえば、人神のインパクトで忘れていたが、その前に奇妙な夢を見た。
この世界のあらゆる場所を飛んでいる夢だ。
山の上、海の中、森の奥、谷の底……。即死するような場所もたくさんあった。
あれがただの夢でないのなら、転移したのは、恐らく本当だろう。
そして、ここが魔大陸だというのも、恐らくは……。
だが、魔大陸だとしても、魔大陸のどこかもわからない。
逃げれば、広い大陸のどまんなかを彷徨うこととなる。
結局、選択肢などないのだ。
ここでこの男から逃げ出し、エリスと二人で魔大陸を彷徨ったところでいいことはない。
それとも、賭けるか? 夜が明けたら、近くに人里があることを賭けるか?
無茶をいうな。
道がわからないということがどれぐらい辛いことか、俺はよく知っているじゃないか。
落ち着け。深呼吸しろ。
人神は信じられない。だが、この男個人はどうだ?
よく見ろ。顔色を窺え。あの表情はなんだ?
あれは不安だ。不安と諦めの混じった顔だ。少なくとも、彼は感情のない化け物ではない。
ロキシーは近づくなと言っていたが、実際にスペルド族と会ったことはないとも言っていた。
俺は『差別』や『迫害』、『魔女狩り』という概念を知っている。
スペルド族が恐れられているのは、誤解である可能性も考えられる。
ロキシーは嘘を言ったつもりはなく、ただ誤解していただけなのかもしれない。
俺の感覚では、彼に危険はない。少なくとも、人神に感じた胡散臭さは微塵も感じられない。
今はロキシーでも人神でもなく、自分の感覚を信じよう。
俺は最初に一目見た時、嫌な印象や怖い印象は持たなかった。外見を見て警戒しただけだ。
なら、話だけはしてみよう。それで判断しよう。
「おはようございます」
「………ああ」
挨拶をすると、返事が返ってきた。さて、なんと聞くべきか。
「神様の使いですか?」
その質問に、男は首をかしげた。
「質問の意図がわからんが、お前たちは空から降ってきた。人族の子供はひよわだ。焚き火を作って身体を暖めておいた」
人神の名前は出なかった。あの神は、この男には話を通していないのだろうか。
俺を見ているのが面白いから、という言葉をそのまま信じるのであれば、むしろ俺の行動だけではなく、俺と接触した彼の行動も面白おかしく鑑賞するつもりなのか。
だとすれば、彼は信じられるかもしれない。
「助けていただいたんですね。ありがとうございます」
「……お前は、目が見えないのか?」
「は?」
唐突に変なことを聞かれた。
「いえ、両の眼ともしっかり開眼していますよ?」
「ならば、親にスペルドについて聞かずに育ったのか?」
「親はともかく、師匠には厳重に注意されましたね。近づくなって」
「……師匠の教えは守らなくていいのか?」
彼はゆっくりと、確かめるように聞いてきた。自分はスペルド族だけど、大丈夫なのかって話だ。
意外と臆病なんだな。
「お前は、俺を見ても、怖くはないのか?」
怖くはない。恐怖はないのだ。ただ、疑っているだけだ。
だが、それを言う必要もない。
「助けていただいた方を怖がるのは失礼ですよ」
「お前は不思議なことを言う子供だな」
彼の顔には、困惑の表情が張り付いていた。
不思議、か。スペルド族としては、忌避されるという感覚が普通なのだろう。
ラプラス戦役については習った。五〇〇年前に始まり、一〇〇年以上にわたり人族と魔族で争ったという戦争だ。
戦争後、スペルド族が迫害を受けてきたのも知っている。
他の魔族への差別は薄れつつあるようだが、スペルド族に対してだけは異常だ。まるで戦中の米兵に対する日本人のように、あらゆる種族が毛嫌いしている。
この世に絶対悪があるとすれば、それはスペルド族だとでも言わんばかりに。
俺が生前に差別を良しとしない日本人でなければ、彼を見た瞬間に叫び声でも上げていたかもしれない。
「……」
彼が枯れ枝を焚き火へと放り込むと、パキンと音がした。
その音を聞いたのか、エリスが「んぅ」と身動ぎをした。起きるかもしれない。
っと、いかん。エリスが起きたら絶対に騒ぐからな。
ぐちゃぐちゃになる前に、自己紹介ぐらいはしておくか。
「僕はルーデウス・グレイラットです。お名前をお聞きしても?」
「ルイジェルド・スペルディア」
特定の魔族は種族ごとに、決められた苗字を持つ。
家名、なんてものをつけているのは、基本的に人族だけだ。たまに他の種族も酔狂でつけたりするらしいが。
ちなみに、ロキシーはミグルディアである。エリスの家庭教師をしていた時に送ってもらったロキシーの魔族辞典に、そう書いてあった。
「ルイジェルドさん。もうすぐこっちの子が起きると思うんですが、ちょっと騒がしい子なので、先に謝っておきます。申し訳ない」
「構わん。慣れているからな」
エリスなら、ルイジェルドの顔を見るなり殴りかかってもおかしくない。
敵対しないためにも、必要な会話は終わらせておくべきだろう。
「隣、失礼します」
エリスの寝顔をチラリと見て、まだ大丈夫そうだなと思い、俺はルイジェルドの隣に移動した。
彼は暗い明かりの下で見てみると、なんとも民族性溢れる格好をしていた。イメージとしてはインディアンだろうか。刺繍の入ったチョッキとズボンだ。
「む……」
居心地悪そうにしている。人神のようにグイグイと来ない分、好印象だ。
「ところで話は変わりますが、ここはどこなんですか?」
「ここは魔大陸の北東、ビエゴヤ地方。旧キシリス城の近くだ」
「魔大陸……」
確か、キシリス城は魔大陸の北東だ。
「どうしてそんなところに落ちたんでしょうね」
「お前たちにわからんのなら、俺にもわからん」
「そりゃ、そうですね」
ファンタジー世界だし、何が起こっても不思議ではないと思うが……。
転移の寸前、ペルギウスの配下とかいう大物も登場したし、偶然の産物ではないのかもしれない。
ていうか、あの人神が関与してる可能性も高い。巻き込まれたのが偶然なら、生きてるだけで儲けものだ。
「ともあれ、助けていただいたことには感謝します」
「礼はいらん。それより、どこに住んでいるのだ?」
「中央大陸のアスラ王国、フィットア領のロアという都市です」
「アスラ……遠いな」
「そうですね」
「だが安心しろ、必ず送り届けてやろう」
魔大陸の北東とアスラ王国は地図の端と端だ。ラスベガスとパリぐらい離れている。
しかもこの世界では、船が限られた場所しか通れないから陸路でぐるりと回らなければいけない。
「何が起こったか、心当たりはないのか?」
「心当たりというか……空が光ったと思ったら、光輝のアルマンフィって人が来て、異変を止めに来たと言いました。その人と話していたら、いきなり白い光が押し寄せてきて……。次の瞬間にはここで眼が覚めました」
「アルマンフィ……ペルギウスが動いたのか。ならば、本当に何かが起こったのだろう。転移ぐらいで済んでよかったな」
「まったくです。あれが爆発とかだったら即死ですからね」
ルイジェルドは、ペルギウスという名前を聞いても動じなかった。
意外と、何かあると動く人なんだろうか。ペルギウスって。
「ところで、人神という存在に聞き覚えは?」
「ヒトガミ? ないな。人の名前か?」
「いえ、知らないならいいです」
嘘をついている感じはない。彼が人神のことを伏せる理由は思い至らない。
「それにしても、アスラ王国か」
「遠いですよね。いいですよ。近くの集落にでも送ってくだされば……」
「いや。スペルドの戦士は一度決めたことは覆さん」
頑固だが実直な言葉だ。人神の助言がなくても、それだけで信頼してしまったかもしれない。
しかし、今は疑心暗鬼だ。
「世界の端と端ですよ?」
「子供が余計な気遣いをするな」
恐る恐るといった感じで俺の頭に手が載せられ、おずおずといった感じで撫でられた。
俺が拒否しないでいると、彼はほっとした顔をした。
この人、子供好きなのかな?
しかし、歩いて一〇分の所にあるわけじゃないのだ。そんな軽々しく送ると言われても、信用できない。
「言葉は通じるのか? 金はあるのか? 道はわかるのか?」
言われて、そういえば、と思った。
俺は先ほどから人間語で話しているが、この魔族の男は流暢に返事を返してくる。
「魔神語はできます。魔術ができるので金はなんとか稼げます。人のいる所にさえ連れていってもらえれば、道は自分で調べます」
なるべく断る方向で話を進めたかった。この男は信用できるかもしれないが、人神の思惑通りに事が進むのは、避けたほうがいい気がしたのだ。
疑り深い俺の言葉に思うところもあるはずだが、ルイジェルドは実直な返事をした。
「そうか……ならば護衛だけはさせてくれ。小さな子供を放り出したとあっては、スペルドの誇りに傷がつく」
「誇り高い一族なんですね」
「傷だらけの誇りだがな」
その冗談に、俺はハハッと笑った。ルイジェルドの口端もつり上がっていた。笑っているのだ。
人神の胡散臭い笑みとは違う、温かい笑みだった。
「とにかく、明日は俺が世話になっている集落まで行こう」
「はい」
神は信じられないが、この男は信じられるかもしれない。
少なくとも、その集落とやらに行くまでは、信じてやろうと思った。
★ ★ ★
しばらくして、エリスの目がパチリと開いた。
ガバッと身体を起こし、キョロキョロと周囲を見渡す。次第に不安そうな顔になり、俺と目が合って、あからさまにほっとした表情になる。すぐに、隣に座るルイジェルドと目が合った。
「キャアアアアアアアアァァァァァァァァ!!」
絶叫だった。転がるように後ろに下がり、そのまま立ち上がって逃げようとして、腰砕けになって倒れた。腰が抜けたのだ。
「イヤァァァアアアアア!」
エリスはパニックになった。
しかし暴れもしなければ、這いずって逃げるでもない。
その場にうずくまって、ガタガタと震えて、ただ声だけは張り上げて叫んだ。
「ヤダ! ヤダヤダ! 怖い! 怖い怖い怖い! 助けてギレーヌ! ギレーヌ! ギレェーヌ! どうして来てくれないのよ! イヤ、イヤ! 死にたくない! 死にたくない! ごめんなさい! ごめんなさい! ごめんなさいルーデウス! 突き飛ばしてごめんなさい! 勇気がなくてごめんなさい! 約束を守れなくてごめんなざぁぁあ、あ、あぁぁぁん! うえええぇぇええん!」
最終的には、亀のように縮こまって泣きだしてしまった。
俺はその光景に戦慄を覚えた。
(あの、エリスが、こんなに怖がっている……)
エリスは気の強い女の子だ。座右の銘は恐らく天上天下唯我独尊。ワガママで乱暴で、とりあえず殴ってから考える、そんな子だ。
そんな子が、この有り様だ。
もしかして、俺はとんでもない勘違いをしていたんじゃないか?
スペルド族は、決して触れてはいけない相手なんじゃないのか?
チラリとルイジェルドを見てみる。彼は平然としていた。
「あれが、普通の反応だ」
そんな馬鹿な。
「僕は異常ですか」
「異常だ。だが……」
「だが?」
「悪くはない」
ルイジェルドの横顔は、随分と寂しそうに見えた。
思うところがあった。俺は立ち上がり、エリスのところまで移動する。
足音に気づいて、エリスはびくりと身体を震わせた。
俺はその背中を優しく撫でた。はるか昔、何かに怖がって泣いていたら、ばあちゃんがこうやって背中を撫でてくれたのを思い出しながら。
「ほーら、怖くない。怖くない」
「ひっく、怖くないわけないじゃない! す、スペルド族よ!」
そんなに怖がる理由が、俺にはわからない。
だって、あのエリスだ。剣王ギレーヌ相手にも牙を剥いたエリスだ。
彼女に怖いものなんてあるはずがない。
「本当に怖い人なんですか?」
「だ、だって、す、スペルド族は! 子供を、たべ、食べっ! 食べるのよ? ひっく……」
「食べませんよ」
食べないよね? とルイジェルドを見ると、首を振った。
「子供は食べん」
だよね。
「ほら、食べないって」
「だ、だ、だって! だってスペルド族よ! 魔族なのよ!」
「魔族だけど、人間語は通じましたよ」
「言葉の問題じゃない!」
ガバッと顔を上げて、エリスが睨んでくる。いつもの調子に戻ってきた。
やはり、エリスはこうでなくては。
「あっ、大丈夫なんですか? ちゃんと縮こまってないと、食べられちゃいますよ?」
「ば、馬鹿にしないでよ!」
馬鹿にした口調で言うと、エリスは俺をキッと睨んだ。そしてそのまま、ルイジェルドの方もキッと睨んで……カタカタと震えた。目が潤んでいる。
もし、いつものように仁王立ちしたら、足もカクカクになっていただろう。
「は、はじ、はじ、はじめ、て、お、おめにかかります。え、え、エリス・ボボ、ボレアス……グレイラットです!」
半泣きになりながら、自己紹介をした。
偉そうに相手を睨んでの自己紹介なのが、ちょっと笑えるところだ。
いや、そういえば昔、俺がそういう風に教えたかもしれない。人と会ったら、とりあえず自己紹介をして先制攻撃しろ、と。
「エリス・ボボボレアス・グレイラットか。知らない間に、人族はおかしな名前を付けるようになったな」
「違うわよ! エリス・ボレアス・グレイラットよ! ちょっと噛んだだけよ! それよりあんたも名乗りなさいよ!」
叫んでから、エリスは「あっ」と、不安そうな顔になった。
自分が誰に向かって叫んだか、思い出したのだ。
「そうか。すまん。ルイジェルド・スペルディアだ」
エリスがほっとした表情になり、ドヤ顔をしてくる。
どお、怖くなんてないんだから、という顔だ。
「ね、大丈夫だったでしょう? 話が通じればみんな友達になれるんですよ」
「そうね! ルーデウスの言う通りね! お母様ったら、嘘ばっかり!」
ヒルダが教えたのか。しかし、どれだけ恐ろしい伝承だったんだろうか。
いや、俺だってテケテケとか、ナマハゲを実際に見たらビビるかもしれない。
「ヒルダさんはなんと?」
「早く寝ないとスペルド族が来て食べちゃうって」
なるほど、子供を寝かしつけるための迷信として使っているのか。
し○っちゃうオジサンみたいなもんだ。
「でも、食べられていない。むしろ、スペルド族と友達になったら、みんなに自慢できるかも」
「お、お祖父様やギレーヌにも自慢できるかしら……?」
「もちろんですとも」
チラリとルイジェルドを見ると、驚いた顔をしていた。よし。
「ルイジェルドさんは友達が少ないみたいだから、エリスが頼めばすぐに仲良くしてくれると思いますけどね」
「で、でも……」
ちょっと子供っぽい言い方すぎるかと思ったが、エリスは迷っている。
考えてみれば、エリスに友達はいない。俺は……ちょっと違うだろう。友達という単語に気後れしているのかもしれない。あとひと押しが必要か。
「ほら、ルイジェルドさんも!」
促すと、ルイジェルドもなんとなく流れがわかったらしい。
「え? あ、ああ。エリス……よろしく頼む」
「! しょ、しょうがないわね! わ、私が友達になってあげるわ!」
ルイジェルドが頭を下げたのを見て、エリスの中で何かが崩れたらしい。
よかった。それにしても、エリスは単純だ。あれこれと考えているのが馬鹿らしくなる。
でも、エリスが単純な分、俺が考えないとな……。
「ふう、とりあえず今日はもう少し休みます」
「なによ、もう寝るの?」
「うん、エリス、僕はつかれたよ。なんだか、とても眠いんだ」
「そうなの? しょうがないわね。おやすみ」
俺が横になると、エリスは自分の側にあった、マントのようなもの(おそらくルイジェルドの私物)を掛けてくれた。どっと疲れた。
意識が途切れる寸前、会話が聞こえた。
「お前、もう怖くはないのか?」
「ルーデウスが一緒だもの、大丈夫よ」
ああ、エリスだけでも無事に送り届けないとな。
そんなことを思いつつ、俺の意識は落ちた。
第三話 「師匠の秘密」
夢を見た。天使が空から降りてくる夢だ。
先日の夢と違い、いい夢に違いないと思ったが、天使の局部にはモザイクが掛かっており、嫌らしい顔をでゅふふと笑っていた。どうやら悪夢らしいと気づくと、目が覚めた。
「夢か……」
目の前には岩と土だらけの世界が広がっている。
魔大陸。
人魔大戦によって引き裂かれた巨大陸の片割れ。
かつて、魔神ラプラスがまとめあげた魔族たちの領域。
面積は中央大陸の半分程度だが植物はほとんどなく、地面はひび割れ、巨大な階段のような高低差がいくつもあり、背丈よりも高い岩が行く手を阻む、天然の迷路のような土地。
さらに、魔力濃度が濃く、強い魔物が数多く存在している。
歩いて渡ろうと思えば、中央大陸の三倍は掛かるであろうと言われている。
長旅になることをどうやってエリスに説明しようかと考えていたが、彼女は元気なものだった。
魔大陸の大地をキラキラした目で見ていた。
「エリス。ここは魔大陸なのですが……」
「魔大陸! 冒険が始まるのね!」
喜ばれた。余裕だな。今すぐ言って不安を煽ることもないか。
「行くぞ、ついてこい」
ルイジェルドの号令で、俺たちは移動を開始する。
★ ★ ★
俺が寝ている間に、エリスはルイジェルドと仲良くなっていた。
彼女は家での自分のことをはじめ、魔術や剣術の授業のことを嬉しそうに話している。
ルイジェルドは言葉少なだったが、エリスの話にいちいち相槌を打っていた。
最初のあの怯えようはなんだったのか。この恐ろしい男に、エリスは物怖じしなくなっていた。
会話中、たまにすごく失礼なことを言ったりしてヒヤリとしたが、ルイジェルドは特に怒らなかった。何を言われても、さらりと受け流している。
誰だよ、キレやすいって噂を流したのは。
もっとも、昔はともかく、今のエリスは多少なら空気も読める。
そのへんについては、エドナと一緒にキッチリ教えたから、いきなり相手を怒らせるようなことは言わないだろう。そう願いたい。
ただ、知らない相手はどんな言葉が堪忍袋の緒につながっているのかわからない。くれぐれも慎重になってほしいと思う。
ついでに言うと、エリスの堪忍袋の緒も非常に切れやすいので、ルイジェルドにも慎重になってほしいと思う。
などと思っていると、早速エリスが声を荒げ始めた。
「ルーデウスはお前の兄なのか」
「違うわよ!」
「だが、グレイラットというのは家名だろう?」
「そうだけど、違うのよ!」
「腹違いか、種違いか?」
「どっちも違うわよ」
「人族のことはわからんが、家族は大切にしろ」
「違うって言ってるじゃない!」
「いいから、大切にしろ」
「う……」
エリスがたじろぐぐらい、強い口調だった。
「た、大切にするわよ……」
ま、本当に兄妹じゃないんだけどね。エリスのほうが年上だし。
魔大陸は岩ばかりで、高低差が激しかった。
地面は固く、パラパラとした土だった。栄養がなく、砂漠一歩手前、といった感じだ。こんな土地に閉じ込められれば、魔族だって戦争を起こすだろう。
植物もほとんどない。たまにサボテンのような変な岩がある程度だ。
「む。少し待っていろ。絶対に動くな」
十数分に一度、ルイジェルドはそう言って進行方向上に走りだす。岩山をぴょんぴょんと飛び越えて、あっという間に見えなくなる。
凄まじい身体能力である。ギレーヌも凄まじかったが、敏捷性を数値に表せば、ルイジェルドが上回るかもしれない。
ルイジェルドは走りだしてから、五分もしないうちに帰ってくる。
「待たせたな、行こう」
特になにも言わないが、三叉槍の先から、わずかな血臭がする。
恐らく、俺たちの行く手を遮る魔物を倒しているのだ。
確か、あの額の赤い宝石がレーダーのような役割を持っていると、ロキシー辞典に書いてあった。
そのお陰で敵を早期発見できて、魔物が俺たちに気づく前に奇襲して、一瞬で倒すのだ。
「ねえ! さっきから何をしてるのよ」
エリスが無遠慮に聞く。
「先にいる魔物を倒している」
ルイジェルドは簡潔に答えた。
「どうして見えないのにいるってわかるのよ!」
「俺には見える」
ルイジェルドはそう言って、髪をかきあげた。
額が露わになり、赤い宝石が見える。
エリスはそれを見て一瞬たじろいだが、よく見るとあの宝石も綺麗なものだ。すぐに興味深そうな顔になった。
「便利ね!」
「便利かもしれんが、こんなものはないほうがいいと、何度も思ったな」
「じゃあもらってあげてもいいわよ! こう、ほじくりだして!」
「そうもいかんさ」
苦笑するルイジェルド。
エリスも冗談を言うようになったか……冗談だよな?
「そういえば、魔大陸の魔物は強いと聞いていたんですが」
「この辺りはそうでもない。街道から外れているから、数は多いがな」
そう、数が多い。さっきから十数分ごとにルイジェルドが動いている。
アスラ王国では、馬車で数時間移動しても一度も魔物になんか遭遇しない。
アスラ王国では騎士団や冒険者が定期的に駆除しているとはいえ、魔大陸のエンカウント率はひどすぎる。
「先ほどから一人で戦ってらっしゃいますけど、大丈夫なんですか?」
「問題ない。全て一撃だ」
「そうですか……疲れたらおっしゃってください。僕も援護ぐらいはできますし、治癒魔術も使えますから」
「子供は余計な気遣いをするな」
そう言って、ルイジェルドは俺の頭に手を載せて、おずおずと撫でた。
この人あれかな、子供の頭を撫でるのが好きなんかな?
「お前は妹の側にいて、守ってやればいい」
「だから! 誰が妹よ! 私の方がお姉さんなんだからね!」
「む、そうだったのか、すまん」
ルイジェルドはそう言って、むくれるエリスの頭も撫でようとして、パシンと手を払われた。
哀れルイジェルド。
★ ★ ★
「ついたぞ」
歩いたのは三時間ほどだろうか。
高低差が激しく、さらにぐねぐねと曲がりくねる道を通ったため、結構時間が掛かってしまった。
だが、直線距離にして一キロも離れていないだろう。
結構疲れた。昨日もそうだったが、なんだか身体が重い。
転移の影響だろうか。それとも、単純に俺の体力がないだけだろうか。ギレーヌの指導のもと、体力作りは欠かさずやっていたはずだが。
「村ね!」
エリスは全然疲れていないようで、興味深そうに集落を見ている。彼女の体力に嫉妬。
エリスは村と言ったが、集落という感じだった。
十数軒ほどの家の集まりを粗末な柵でぐるっと囲んである。
柵の内側には、小さな畑があった。畑で何を育てているのかはよくわからないが、豊作という感じはしない。こんな川もない場所で作物を育てるのは、無理があるんじゃなかろうか。
「止まれ!」
入り口で止められた。見ると、中学生ぐらいの少年が一人、門の脇に立っていた。
青い髪だ。ロキシーを思い出す。
「ルイジェルド、なんだそいつらは!」
魔神語である。どうやら、ヒヤリングは問題ないらしい。
「例の流星だ」
「怪しいな、そいつらを村に入れることはできん!」
「なぜだ。どこが怪しい?」
ルイジェルドは険しい顔で、門番に詰め寄った。ものすごい殺気だった。
出会った時にあんな殺気を放たれていたら、俺は何も考えずに逃げ出していただろう。
「ど、どう見ても怪しいだろう!」
「彼らはアスラで起きた魔力災害に巻き込まれ、転移してしまっただけだ」
「し、しかしなぁ」
「貴様、こんな子供を見捨てるつもりか……?」
ルイジェルドが拳を握る。俺は反射的に、その手を掴んだ。
「彼もお仕事ですので、抑えて」
「なに……?」
「ていうか、彼のような下っ端では埒が明きません、もっと偉い方を呼んできてもらったほうがいいのでは?」
下っ端という言葉に、少年は眉根を寄せた。
「そうだな。ロイン。長を呼んでくれ」
コレ以上ぐだぐだぬかすな、と凄まじい眼光で睨みながら、ルイジェルドがそう言った。
「ああ、俺もそうしようと思っていたところさ」
ロインと呼ばれた少年は目をつぶった。そのまま、十秒ほど時間が流れる……。
「…………」
なにしてんだ、早く行けよ。目なんてつぶりやがって、寝てるんじゃねえだろな。
それともキスでも待ってるのか?
「ルイジェルドさん、あれは……?」
「ミグルド族は同じ種族同士なら、離れていても会話ができる」
「あ、そういえば、師匠にそんなことを教えてもらった気がします」
正確には、ロキシーにもらった本の中に書いてあったのだ。ミグルド族は近しい者同士で交信ができる、と。ついでに、わたしはそれができないので村を出た、とも書いてあった。
不憫なロキシー……。
てか、ここミグルド族の集落かよ。
ロキシーの名前とか出したほうがいいんだろうか。
いや、ロキシーとこの村の関係がわからない以上、やぶ蛇になる可能性もあるしな。
「長が来るそうです」
「こちらから出向いてもよかったが?」
「里に入れられるか!」
「そうか」
しばらく居心地の悪い空気が流れ、エリスがくいくいと俺の袖を引っ張った。
「ねえ、どうなってるの?」
エリスは魔神語がわからない。
「僕らが怪しいから、村長さんが直々に確かめるんだってさ」
「なによそれ、どこが怪しいのよ……」
エリスは眉を顰めながら、自分の服装を見下ろしている。町の外に出るからと、剣術の時の訓練着姿だ。ちょっと軽装すぎるが、おかしくはない。少なくとも、俺の目にはルイジェルドと大差ない。ドレスとかだったら、ムチャクチャ怪しかっただろうが。
「大丈夫なんでしょうね?」
「なにが?」
「何がって言われても困るけど、なんかこう、そういうのよ……」
「大丈夫だよ」
「そーぉ……?」
さすがのエリスも、入り口でもめているとなると、少々の不安があるらしい。
けど、俺に大丈夫と言われて、すぐにおとなしくなった。
「長が来たようだ」
村の奥から杖をついたとっつぁん坊やみたいなのが歩いてきた。脇に、二人の女子中学生……ぐらいの歳の少女を連れている。皆、小さい。もしかして、ミグルド族って、成人しても中学生ぐらいにしかならんのか?
そんなことはロキシー辞典には書いていなかったが……。
いや、挿絵に描いてあったのは中学生ぐらいの絵だった。ロキシーの自画像だと思ってほっこりしていたのだが、もしかすると、あれは成人したミグルド族の姿なのか。
なんて考えていると、長とロインが話し始めた。
「そちらの子たちかね……?」
「はい、片方は魔神語を話せるようです。なんとも怪しい」
「言葉ぐらい、勉強すれば誰だって話せるじゃろう?」
「あの歳の人族が、どうして魔神語なんて勉強するんですか!」
まったくだ。思わず納得しそうになる言葉だったが、長はぽんぽんとロインの肩を叩く。
「まあまあ。君はもう少し落ち着いて待っていなさい」
長はゆっくりとこちらに歩いてくる。とりあえず、俺は頭を下げた。貴族用のやつではなく、日本式のOJIGIだ。
「初めまして、ルーデウス・グレイラットです」
「おや、これは礼儀ただしい。この集落の長のロックスです」
俺はエリスにも目配せする。彼女は自分と同い年ぐらいの見た目の、でもちょっと雰囲気の違う人にどうしていいのかわからず、腕を組んだり戻したりと、落ち着かなげにしていた。
腕を組んでの仁王立ちをするか迷っているのか。
「エリス。挨拶して」
「で、でも、言葉わからないわよ?」
「授業で習った通りでいいから。僕が伝えます」
「うー……。お、お初にお目にかかります。エリス・ボレアス・グレイラットです」
エリスは、礼儀作法の授業で習った通りに挨拶をした。
ロックスはそれを見て、相好を崩した。
「こちらのお嬢さんは、もしや挨拶をしてくださったのかな?」
「そうです。僕らの故郷での挨拶となります」
「ほう、君のとは違うようだが?」
「男と女で違うんですよ」
ロックスはそうかそうかと頷くと、俺の真似をしてエリスに頭を下げた。
「この集落の長のロックスです」
エリスは突然頭を下げられておろおろと俺を見た。
「ルーデウス、なんて言ったの?」
「この集落の長のロックスです、って」
「そ、そうなの、ふ、ふーん、ルーデウスの言う通り、ちゃんと通じたのね」
エリスは口の端を持ち上げて、にまにまと笑った。
よし、こっちはこれでいいだろう。
「それで、集落には入れていただけるのでしょうか?」
「ふむ」
ロックスは俺の身体を無遠慮に、舐め回すように見てきた。やめろよな。そんな熱い視線を受けたら脱ぎたくなっちまうじゃねえか……。
ロックスの視点が俺の胸元で止まった。
「そのペンダントはどこで手にいれなさった?」
「師匠にもらいました」
「師匠はどこの誰かね?」
「名前はロキシー」
俺は素直にロキシーの名前を出した。よく考えてみれば、尊敬する師匠の名前だ。
どうして隠す必要があるのか。
「なんだって!」
と、声を上げたのはロインだ。彼は凄い勢いで歩いてきて、俺の肩を掴んだ。
「お、お前、い、今ロキシーといったか!」
「はい、師匠です………」
答えると同時に、視界の端で拳を握りしめるのが見えたルイジェルドに制止を掛ける。ロインの顔に怒りの色はなかった。ただ焦燥があった。
「ロ、ロキシーは、今どこにいるんだ!」
「さて、僕は結構会ってないので……」
「教えてくれ! ロキシーは、ロキシーは、俺の娘なんだよ!」
ごめん、なんだって?
「すいません、ちょっとよく聞こえませんでした」
「ロキシーは俺の娘なんだ! あいつはまだ生きているのか?」
ぱーどぅん? いや、聞こえましたよ。ちょっと、この中学生ぐらいの男の年齢が気になっただけさ。見た目、むしろロキシーの弟に見えるからな。
でも、そうか。へー。
「教えてくれ、二十年以上前に村を出ていったきり、音沙汰がないんだ!」
どうやら、ロキシーは親に黙って家出していたらしい。
そういう話は聞いていないのだが……まったく、うちの師匠は説明が足りない。
てか、二十年って。あれ? じゃあロキシーって、今何歳なんだ?
「頼む、黙ってないでなんとか言ってくれよ」
おっと失礼。
「ロキシーの今の居場所は……」
と、そこで俺は肩を掴まれっぱなしということに気づいた。
まるで脅されているみたいだ。
脅されて喋るってのは、なんか違うよな。まるで俺が暴力に屈したみたいじゃないか。
暴力で俺を屈しさせたければ、せめてバットでパソコンを破壊して空手でボコボコにしたあと、聞くに堪えない罵詈雑言で心を折ってくれないと。
ここは毅然とした態度を取らないとな。エリスが不安に思うかもしれないし。
「その前に、僕の質問に答えてください。ロキシーは今、何歳なんですか?」
「年齢? いや、そんなことより……」
「大事なことなんです! それとミグルド族の寿命も教えてください!」
ここは聞いておかなければいけないことだった。
「あ、ああ……。ロキシーは確か……今年で四十四歳だったはずだ。ミグルド族の寿命は二〇〇歳ぐらいだな。病気で死ぬ者も少なくないが、老衰となると、それぐらいだ」
同い年だった。ちょっと嬉しい。
「そうですか……。あ、ついでに手を離してください」
ロインはようやく手を離した。よしよし、これで話ができるな。
「ロキシーは、半年前まではシーローンにいたはずですよ。
直接会ったわけじゃないけど、手紙のやり取りはしてましたから」
「手紙……? あいつ、人間語の文字なんて書けたのか?」
「少なくとも、七年前にはもう完璧でしたよ」
「そ、そうか……じゃあ、無事なんだな?」
「急病や事故に遭ったりとかしていなければ、元気でしょうね」
そう言うと、ロインはよろよろと膝をついた。
ほっとした表情で、目元には涙が浮いている。
「そうか……無事か……無事なのか……はは……よかったぁ」
よかったね、お義父さん。
しかし、この姿を見ているとパウロを思い出すな。パウロも俺が無事と知ったら、泣いてくれるだろうか。ブエナ村への手紙、早く送りたいものだ。
「それで、集落には入れてくれるんでしょうか?」
泣き崩れるロインを尻目に、長ロックスへと話を振る。
「無論だ。ロキシーの無事を知らせてくれた者を、なぜ無下にできようか」
ロキシーからもらったペンダントは抜群の効果を発揮した。
最初から見せてればよかったよ。いや、でも会話の流れによっては俺がロキシーを殺して奪った、とか考えられたりしたかもしれない。魔族は長生きなようだしな。見た目と年齢が違うことも多々あるのだろう。いくら俺が十歳児の見た目をしているとしても、中身が四十歳超えてるとバレれば、変な疑いを掛けられることもある。
気をつけないとな。
せいぜい子供っぽく振る舞うとしよう。
こうして、俺たちは『ミグルド族の里』へと入った。
第四話 「信用の理由」
しかし、この姿を見ているとパウロを思い出すな。パウロも俺が無事と知ったら、泣いてくれるだろうか。ブエナ村への手紙、早く送りたいものだ。
「それで、集落には入れてくれるんでしょうか?」
泣き崩れるロインを尻目に、長ロックスへと話を振る。
「無論だ。ロキシーの無事を知らせてくれた者を、なぜ無下にできようか」
ロキシーからもらったペンダントは抜群の効果を発揮した。
最初から見せてればよかったよ。いや、でも会話の流れによっては俺がロキシーを殺して奪った、とか考えられたりしたかもしれない。魔族は長生きなようだしな。見た目と年齢が違うことも多々あるのだろう。いくら俺が十歳児の見た目をしているとしても、中身が四十歳超えてるとバレれば、変な疑いを掛けられることもある。
気をつけないとな。
せいぜい子供っぽく振る舞うとしよう。
こうして、俺たちは『ミグルド族の里』へと入った。
第四話「信用の理由」
ミグルド族の村を一言で表すなら『極貧』だった。
世帯数は十数。
家の形は説明しにくい。地面を掘って、掘った穴に亀の甲羅をかぶせた感じだ。
ここと比べるとアスラ王国の建築技術が高いのがよくわかる。もっとも、アスラ王国の建築技師が木材の取れないこの土地に来ても、材料がなくてお手上げ状態だろう。
外からも見えたが、畑にはしなびた葉っぱをもつ植物が均等に並んでいる。枯れかけに見えるが、大丈夫なのだろうか。ロキシーの作った魔族辞典には農業のことはあまり詳しく書かれていなかった。野菜は苦くて美味しくない、とかその程度だ。
ちなみに、畑の端には、パッ○ンフラワーみたいな牙の生えた禍々しい花が咲いていた。植物なのか動物なのか、乱ぐい歯をギリギリと鳴らしている。あれは確か、畑に侵入する害獣対策だ。
村の端の方では、中学生ぐらいの娘たちが火を囲んで何かをやっている。林間学校か何かのようにも見えるが、彼女らがしているのは食事の準備だ。一ヶ所で作って、みんなで分けるのだ。
男はほとんどいない。
幼い男の子はいるが大人は、先ほど門番をしていたロインと、長ぐらいか。
確か男は狩りに出て、女は家を守るという集落なので、狩りに出ているのだろう。
「このへんで狩れる獲物ってなんです?」
「魔物だ」
恐らくこの答えは正鵠を射ているのだろうが、ちょっと説明不足だ。漁師に向かって何が取れるのか聞いて魚介類と答えられたようなもんだ。ま、突っ込んで聞いていけばいいか。
「えっと。あの家の上に乗っかってるのも、魔物なんですか?」
「大王陸亀だ。甲羅は硬く、肉はうまい。筋は弓の弦になる」
「それを主に狩ってるんですか?」
「ああ」
肉はうまいのか。しかし、あのサイズの亀とか想像がつかないな。一番大きい家の甲羅とか、二〇メートルぐらいありそうだし。
などと考えていると、ルイジェルドとロックスはその家の中へと入っていく。
一番大きい所=長の家、ってのはどこの世界でも一緒らしい。
「お邪魔します」
「お、お招きいただき、ありがとう御座いますわ……」
俺とエリスも、一応の挨拶をしつつ、中へと入る。
「おぉ……」
外から見るより、中は広かった。
床には毛皮が敷き詰められ、壁には色彩豊かな壁掛けが掛けられている。
部屋の中央には囲炉裏のようなものがあり、火が細々と燃え、部屋の中を明るく照らしていた。
家の中に区切りはない。夜になれば、そこらの毛皮にくるまって眠るのだろう。
端の方に剣や弓も置いてあり、狩猟民族であることがよくわかる。
村長についてきた二人の女性は家の中まではついてこなかった。
「さて、では話を聞くとしましょう」
ロックスは囲炉裏の近くにどっかりと座り、そう言った。
ルイジェルドがその正面につく。俺はルイジェルドの隣にあぐらをかいて座った。
エリスはとみると、所在なげに立っていた。
「家の中でも床に座るの?」
「剣術の授業では、よく床に座ってただろ?」
「そ、それもそうね」
エリスは地べたに座ることを躊躇するタイプではないが、礼儀作法で習ったこととのギャップに戸惑っているのだろう。
人前だから礼儀正しくしなければいけない。けれども習ったことと違うので、戸惑っているのだ。
エリスが床に座ったのを見つつ、帰った時に礼儀作法に悪影響がでなければいいが……少し不安になりつつ、俺は長へと向き直った。
★ ★ ★
今後について話す前に、俺は自分の名前・歳・職業・住所。エリスとの関係・エリスの身分といった個人情報。ワケのわからないうちに魔大陸に来てしまったので帰りたい、という旨を伝えた。
人神のことは黙っていた。あの神が魔族の間でどういう立ち位置かわからない。邪神扱いされていたら、変な疑いを持たれるかもしれないからだ。
「……と、いうわけです」
「ふむ」
ロックスはそれを聞いて、中学生が難問を前に悩んでいるような顔で考えだした。
「……そうさのう」
結論を待っていると、エリスが隣で船を漕ぎ始めた。傍目から見るとまだまだ元気がありそうだったのだが、やはりなれない旅で体力を消耗していたのかもしれない。
昨晩も、あれからずっと起きていたようだし。さすがに限界か。
「話は僕が聞いておくから、寝ててもいいよ」
「………寝るって、どうやってよ」
「多分そのへんの毛皮にくるまって」
「枕がないわ」
「僕の膝を使いなよ」
アン○ンマン風に言って、太ももをぽんぽんと叩いた。
「ひ、膝ってなによ……」
「膝を枕にしていいってこと」
「…………そう? あ、ありがと」
いつものエリスなら、なんやかんや言ったかもしれない。だが、眠気がマックスだったのか、遠慮する素振りもなく、俺の膝に頭を載せた。緊張した面持ちで手なんかギュっと握りしめていたが、目を閉じて、数秒もしないうちに、ストンと眠りに落ちてしまった。やっぱり疲れていたか。
エリスの赤毛をさらりと撫でると、彼女はむず痒そうに身を捩った。むふふ。
ふと、視線を感じた。
「……なんです?」
ロックスになんとも微笑ましいものを見る目で見られていた。ちょっと恥ずかしい。
「仲がよろしいのですな」
「それはもう」
けど、まだお触りは厳禁な仲だ。うちのお嬢様は貞操観念をしっかりと持っているのだ。そして、俺はそれを尊重するのだ。
「それで、どうやって帰るつもりかね?」
ロックスの質問は、ルイジェルドにされたものと同じであった。
「お金を稼ぎながら、徒歩で」
「子供二人でかね?」
「いいえ、金は僕が一人で稼ぎます」
世間知らずのエリスに任せるわけにもいかないだろう。世間知らずという点では俺も大概だが。
「二人ではない。俺が付いていく」
と、ルイジェルドが口を挟んだ。彼は心強い味方だが、人神の件もある。信用したいのは山々だが、ここで別れたほうがいいだろう。後顧の憂いは絶っておくのだ。
しかし、さて、どうやって断るべきか。
悩んでいると、ロックスが難色を示した。
「ルイジェルド、おぬし、付いていってどうするつもりかね?」
「どうもこうもない。俺が二人を守り、無事に故郷に送り届けるのだ」
ムッとするルイジェルド。
微妙に噛み合っていない返答にロックスはため息をついた。
「お主、町に入れんじゃろう?」
「む……」
む? 町に入れない?
「子供を連れて町に近づいたら、どうなる? 衛兵に追い回され、討伐隊を組まれたのは、百年前じゃったか?」
百年?
「それは、だが……俺ひとりで町の外で待てば」
「町の中の出来事は知らんか。無責任じゃのう」
呆れ顔になるロックスに、ルイジェルドはぐっと歯噛みした。
スペルド族は嫌われている。それは魔大陸でも変わらない。しかし、討伐隊はやりすぎではなかろうか。魔物扱いなのだろうか。
「町中で何かあれば……」
「あれば、どうするんじゃ?」
「町の人間を皆殺しにしてでも二人を救い出す」
目が本気だった。この男は本気でやる、そんな覚悟が窺えた。
「子供のこととなると見境がないのぉ。……思えば、この里で認められたのも、魔物に襲われていた子を助けてくれたことじゃったか」
「そうだな」
「あれが五年前か、時が経つのは早いもんじゃな……」
長がやれやれとため息をついた。味方をしてもらっているのに大変申し訳ないのだが、かなりむかつく動作だ。調子こいた中学生が大人の馬鹿さ加減を嘲笑っているようにしか見えない。
「しかしルイジェルドよ。そんな強引さで、お主の目的は達成できるのかな?」
「む……」
ルイジェルドは眉を顰めた。この男は何か目的があるらしい。
「その目的というのは?」
と、口を挟んで聞いてみる。
「単純なことじゃ。スペルドの悪評を取り除きたい、というな」
それは無理だと言いそうになった。
差別問題というのは、一人が頑張ったところでどうにかなるものではない。クラス単位のイジメですら、一人では解決できないのだ。まして、スペルド族の迫害は全世界に根付いている。あのエリスがあんなに怯えるぐらいだ。それほど悪と断じられてきた存在を、どうやって善に変えるのだ。
「でも、戦争で敵味方区別なく襲ったというのは本当のことなんでしょう?」
「それは!」
「いくら悪評とは言っても、スペルド族が怖い種族だって事実は……」
「違う! 事実ではない!」
ルイジェルドに胸ぐらを掴まれた。すんげー怖い目で見てくる。やばい震えてきた。あわわ……。
「あれはラプラスの陰謀だ! スペルドは恐ろしい種族ではない!」
なん、なん、なんなの? やめてちょっとこわい。身体の震えが止まらない。ていうか、陰謀? 陰謀論なの? ラプラスって五〇〇年前の人物だよね?
「ラ、ラプラスがどうしたって言うんですか?」
「奴は俺たちの忠誠を裏切った!」
力が弱まった。ルイジェルドの腕をぽんぽんと叩くと、彼は俺の胸ぐらから手を離した。
「奴は……奴はな………!」
しかし、その手はわなわなと震えている。
「その話、詳しく聞いても?」
「長いぞ」
「構いません」
そこからルイジェルドが話したのは、歴史の裏とも言える話だった。
★ ★ ★
魔神ラプラス。彼は魔族を統一し、人族から魔族の権利を勝ち取った英雄だ。
スペルド族は極めて早い段階からラプラスの配下となっていた。高い敏捷性と、凶悪な索敵能力に加え、極めて高い戦闘能力を持つ彼らは、ラプラスの親衛隊の一つであり、その専門は奇襲と夜襲だった。額の眼はレーダーのように周囲を見ることができるため、彼らは決して奇襲を受けず、必ず奇襲を成功させることができた。
精鋭だったという。
当時の魔大陸において、スペルド族という名前が畏怖と尊敬を持って呼ばれるほどに。
ラプラス戦役の中期。
ちょうど中央大陸の侵攻が始まった頃、ラプラスがある槍を持って戦士団を訪問した。
ラプラスが持っていたのは、後に悪魔の槍と呼ばれる槍である。
ラプラスはそれを戦士団に下賜した。見た目はスペルド族の持つ三叉槍と一緒だが、黒く禍々しく、魔槍と一目でわかったという。
もちろん、戦士団の中には反対する者もいた。「槍はスペルド族の魂。それを捨ててこんなものを使うことなどできない」と。しかし、主君たるラプラスの用意した物だ。最終的にリーダーであったルイジェルドは、全員にその槍を使うことを強要する形となった。
それがラプラスへの忠誠を示すものだと信じて。
「ん? リーダー?」
「ああ、俺はスペルド族の戦士団のリーダーだった」
「……今、何歳なんですか?」
「五〇〇から先は数えていない」
「あ、そう……」
ロキシー辞典には、スペルド族が長寿だって書いてあったっけか。まあいい。
スペルド族の戦士団は、自前の槍をある場所に突き立て、悪魔の槍で戦い続けた。
悪魔の槍は強力な力を持っていた。身体能力を数倍に引き上げ、人族の使う魔術を無効化し、感覚はさらに鋭敏になり、圧倒的な全能感をもたらした。
その結果、スペルド族は次第に悪魔と呼ばれる存在へと変貌していった。
悪魔の槍は血を吸えば吸うほど、使用者の魂を黒く染め上げた。
誰も疑問に思わなかった。全員が同じぐらいの頻度で精神を蝕まれていたがゆえに、誰も自分の、そして周囲の変化に気がつかなかったのだ。
そして、悲劇が起こり始める。
戦士団はいつからか敵味方の区別がつかなくなり、周囲にいる者たちを無差別に襲いだすようになる。老若男女関係なく、子供であろうと容赦なく、分け隔てなく、あらゆる者に襲いかかった。
ルイジェルドはその時の記憶を鮮明に覚えているという。
いつしか魔族からは「スペルド族は裏切った」と言われ、人族からは「スペルド族は血も涙もない悪魔だ」と言われるようになる。
当時のルイジェルドたちは、その噂を愉悦の表情で聞いたらしい。それこそが「誉れ」だと。
敵だらけの中で、悪魔の槍を持ったスペルド族は強かった。槍の力によって一騎当千となった者たちを殲滅できる者はおらず、戦士団は世界で最も恐れられる集団となっていた。
しかし、消耗がないわけではない。人族、魔族、双方から敵対され、日夜を問わず戦いを続け、スペルド族の戦士団は一人、また一人と数を減らした。
だというのに、誰もそれを疑問には思わなかった。戦いの中で死ぬこと、それこそがまさに至高だと酔っていた。
そんな中、風の噂で、スペルド族の集落が襲われているという話を聞く。
場所はルイジェルドの出身地。これはスペルド族をおびき出す罠なのだが、正常な判断を下せる者は残っていなかった。
スペルド族の戦士団は、久しぶりに帰ってきた集落を──襲った。
そこに人がいるのだから殺さなくては、と思ったのだ。
ルイジェルドは親を殺し、妻を殺し、姉妹を殺し、最後に残った己の子供を刺し殺した。
子供とはいえ、彼はスペルド族の戦士になるべく鍛えていた。死闘というほどの戦いではなかったが、戦いの最後に、子供は悪魔の槍を折った。
その瞬間、気持ちのいい夢は終わった。
同時に、悪夢が始まった。
ルイジェルドの口の中にコリコリとした何かがあった。それが息子の指だと気づいて、ルイジェルドは吐いた。まず自殺を考え、すぐにその考えを打ち消した。死ぬよりまず、やることがあった。
たとえ死んでも噛みちぎるべき敵の存在がいる、と。
そのとき、スペルド族の集落を魔族の討伐軍が包囲していた。戦士団は一〇人。
悪魔の槍を持った時には二〇〇人近くいた戦士団が、あの勇猛果敢な戦士たちが、すでに一〇人しかいなかったのだ。ボロボロの一〇人だ。片腕を失った者や、片目や、額の宝石を砕かれた者もいた。彼らは満身創痍でなお、好戦的な表情で一〇〇〇人近い討伐軍を睨みつけていた。
犬死にになる、とルイジェルドは悟った。
ルイジェルドはまず、仲間たちの持っていた悪魔の槍を、全て叩き折った。
次々と我に返り、呆然とする仲間たち。
家族を手に掛けたことを嘆く者、滂沱の涙を流す者。
しかし、あのまま夢を見させてくれと言う者はいなかった。そんな軟弱者は一人もいなかった。誰もがラプラスに復讐を誓った。誰一人として、ルイジェルドを責める者はいなかった。彼らはもはや、悪魔ではなかった。戦士などという誇り高い者でもなかった。
ただの薄汚い復讐鬼であった。
一〇人がどうなったのか、ルイジェルドは知らない。
恐らく、生きてはいないとルイジェルドは言う。
悪魔の槍を手放せば、スペルド族はちょっと強いだけの戦士でしかない。まして手に馴染んだ己の槍もなく、他人の槍で戦って生き残れるはずもない。だが、ルイジェルドは包囲を突破した。半死半生で逃げ切った。三日三晩、生死の境を彷徨った。
生き延びたルイジェルドが唯一持っていたのは、息子の槍だった。息子は悪魔の槍を折り、己の魂でルイジェルドを守ったのだ。
それから。数年間の潜伏生活の末、復讐に成功した。
魔神殺しの三英雄とラプラスとの戦いに横槍を入れ、一矢報いることに成功したのだという。
だが、ラプラスを倒しても、全てがリセットされるわけではない。
スペルド族は迫害され、ルイジェルドたちの手で滅ぼされた集落以外のいくつかの集落もまた、迫害を受けて散り散りとなった。
彼らを逃がすため、ルイジェルドはまた魔族を殺した。
戦後のスペルド族の迫害は、それほど苛烈を極め、ルイジェルドの反撃もまた、烈火のようであったという。
ルイジェルドはもう三〇〇年近く、魔大陸で他のスペルド族には会っていないという。
他のスペルド族が全滅したのか、それとも、生き延びてどこかに村を作ったのか、ルイジェルドにもわからないらしい。
「こんなことになったのは、全てラプラスのせいだ。だが、スペルド族の悪評は、俺の責任でもある。たとえ俺が最後の一人でも、この悪評だけはなくしたい」
そう、ルイジェルドは締めくくった。
★ ★ ★
言葉は拙く、決して情に訴えかけるようなものではなかった。
だが、ルイジェルドの無念、怒り、やるせなさ、あらゆる感情が伝わってきた。
もしこれが作り話であるなら、あるいは話し方や声音が演技であるなら、俺は別の意味でルイジェルドを尊敬するだろう。
「酷い話ですね……」
話を鵜呑みにするなら、スペルド族が恐ろしい種族というのは誤りだ。
ラプラスが何のために悪魔の槍を渡したのかはわからない。戦後の後始末を考え、スペルド族をスケープゴートに仕立てあげようとしたのかもしれない。だとしたら、ラプラスは最低のド畜生だ。
スペルド族の忠義は厚かった。スケープゴートにするにしても、騙し討ちのようなやり方で切り捨てる必要なんてなかったはずなのだ。
「わかりました。僕もできる限りのお手伝いをしましょう」
心のどこかで、別の俺が言った。
そんな余裕はあるのか、他人のことを考えている余裕はあるのか、自分のことで精一杯じゃないのか、旅はお前が思っているより大変だぞ、と。
しかし、口の方は止まらなかった。
「アイデアがあるわけではありませんが、人族の子供である僕が手伝えば、何かしらの変化があるかもしれません」
もちろん、哀れみや善意だけじゃない。打算的な気持ちもある。
話が本当であれば、ルイジェルドは強い。英雄と同クラスの力を持っている。そんな力で俺たちを守ってくれるというのだ。少なくとも、道中で魔物に襲われて死ぬことはないだろう。
ルイジェルドを連れて歩くということは、町の外では安心を、町の中では不安を、それぞれ持つことになる。町中での不安が解消できるなら、この上ない戦力となる。
なにせ、奇襲も夜襲もくらわないと豪語する猛者である。町中でスリや盗賊なんかに狙われる可能性もぐっと低くなるはずだ。
それに。なんとなくで、何の根拠もない話だが、嘘をつけない不器用な男に見える。信じられる人物かもしれない。
「できる限りのことをすると、約束しましょう」
「あ、ああ」
ルイジェルドは驚いた顔をしていた。俺の目から、猜疑的な色が消えたからだろうか。
なんでもいいさ。俺は信じることを決めた。あんな話一つで、コロっと騙されたのだ。生前は、お涙頂戴のストーリーを聞いても、鼻で笑っていたのに。こんなにあっさりと。それだけ心に響いたのだ。だからいいじゃないか。騙されたって。
「しかし、本当にスペルド族は……」
「いいんです、ロックスさん。なんとかしますから」
町の外では守ってもらい、町の中では守ってやる。ギブアンドテイクだ。
「ルイジェルドさん。明日から、よろしくお願いします」
一つ不安があるとすれば、恐らくこの流れが、人神の思惑通りということだ。
第五話 「最寄りの町まで三日間」
翌日。村を出る時に、ロインの姿を見つけた。彼は今日も門のところに立っていた。
「おはようございます、今日も門番ですか?」
「ああ、狩りの連中が戻るまではね」
そういえば、昨日は夜になっても男衆が戻ってこなかった。もしかすると夜通し立っていたのかもしれない。RPGに出てくる門番のように。朝も昼も夜も、ずっと立っているだけの簡単なお仕事ですとばかりに。
それにしても、帰ってくるまでずっと一人で門番なのだろうか。あ、長もいるか。こういう集落だから、長もきっちり働くだろう。
「もう行くのか?」
「ええ、昨日のうちに話もまとまりましたし」
「娘の話を聞きたかったんだが……」
「そうしたいのは山々ですが、あまりのんびりもしていられませんので」
「そうか……」
残念そうだ。俺としても、ロキシーの幼少時代の話とか、もっとよく聞きたかった。
「また、会ったら連絡を取るように伝えておきます」
「頼む……」
頭を下げられ、ロキシーに出会った時に忘れずに伝えようと、心の中にメモっておく。
「あ、そうだ、ちょっと待っていてくれ」
ロインは、ふと思いついたように言うと、村の中へと駈けだした。
一軒の家(おそらくロキシーの実家)に入って、数分後。ロキシーによくにた女の子と一緒に戻ってきた。誰かを呼び出すなら念話を使えばいいのではないか、と思ったが、何か剣のようなものを持っていた。くれるのだろうか。
「家内だ」
「ロカリーです」
ロキシーのお母さんらしい。
「ルーデウス・グレイラットです。お若いですね」
ロキシーを生んだこの人たちがいなければ、俺は外の世界に出ることができなかった。そう思うと、自然と頭も下がった。
「そんな若いだなんて……今年でもう一〇二歳ですよ」
「ま、まだまだ十分若いですよ」
ちなみに。ミグルド族は十歳ぐらいで成人と同じぐらいまで成長し、そこからは一五〇歳ぐらいまで容姿が変わらないらしい。
「ロキシー先生には世話になりました」
「先生……あの子が人に教えられるようなことなんて、何かあったかしら……」
「知らないことをたくさん教えてもらいましたよ」
笑ってそう言うと、ロカリーは「まあ」と顔を赤らめた。何か勘違いしているらしい。
「しかし、ちょうど俺が門番をしている時に来てくれてよかったよ」
「そうですね。本当に、会えてよかった。ロキシー先生には、本当にお世話になりましたから。なんだったら、お義父さんと呼ばせてもらってもいいですか?」
「はっはは……やめてくれ」
真顔で拒否された。ちょっとショック。でも、この真顔もロキシーぽくて、なんだか懐かしい。
「冗談はさておき、これを受け取ってくれ」
ロインはそう言って、一振りの剣を差し出した。
「いくらルイジェルドがいるとはいえ、丸腰じゃ心もとないだろう」
「僕は丸腰じゃないんですがね……」
と、言いつつも受け取り、鞘から抜いてみる。
片刃で幅広。刃は六〇センチぐらいで小ぶり。若干湾曲している。マチェット……いや、カトラスに近いか。年季を感じる傷が各所についているが刃こぼれは一切ない。よく手入れされているのか刀身は綺麗だが、ギラついた殺意のようなものがにじみ出ているように感じられる。
全体的に鈍色だが、光の反射で若干緑色に光っているせいか。
「昔、フラっと集落に寄った鍛冶師にもらった物だ。長年使っていても刃こぼれ一つないほど頑丈だ。よかったら使ってくれ」
「ありがたく頂戴します」
遠慮はすまい。遠慮できるような状況でもない。もらえるものはもらっておくべきだ。
俺はともかく、エリスが丸腰なのはかわいそうだからな。彼女だって、剣神流を扱える。剣の一つも持っていたほうが安心できるだろう。
「それから、こっちは金だ。大して入ってはいないが、宿に二、三日泊まれる程度にはあるはずだ」
わーい、お小遣いだと喜び勇んで袋を開けてみると、石でできた粗末な硬貨と、鈍色の金属でできた硬貨が入っていた。
確か、魔大陸の貨幣は緑鉱銭・鉄銭・屑鉄銭・石銭の四つだったな。価値としては世界最低で、一番高い緑鉱銭でも、アスラ大銅貨一枚と同等か、やや及ばないぐらいだ。鉄銭が銅貨と同じ程度か。ちなみに、アスラ王国と魔大陸の貨幣を日本円に換算してみると、以下の感じだ。
一番安い石銭を一円とした場合。
アスラ金貨 一〇万円
アスラ銀貨 一万円
アスラ大銅貨 一〇〇〇円
アスラ銅貨 一〇〇円
緑鉱銭 一〇〇〇円
鉄銭 一〇〇円
屑鉄銭 一〇円
石銭 一円
アスラがどれだけ大国なのか、魔大陸がどれだけ過酷なのか、一目でわかる数値だ。
もっとも、魔大陸には魔大陸の相場がある。だから魔族がことさら貧乏というわけでもない。
「……ありがとう御座います」
「本当は、もっとゆっくりロキシーの話をしたかったのだけれど」
ロカリーもロインと同じようなことを言った。やはり、娘のことが心配なのか。
四十四歳という話だが、人族に換算すると……二十歳ぐらいだもんな。心配といえば、心配か。
「なんなら、あと一日ぐらい滞在しましょうか?」
そう提案してみたが、ロインは首を振った。
「いいんだ。無事だとわかればね。なあ?」
「ええ。あの子は、この里ではあまりうまくやっていけない子ですから」
うまくやっていけないというのは、きっと、あの念話の力の問題なのだろう。
村からは基本的に会話が聞こえない。皆無言なのだ。念話で話しているのだろう。ロキシーはこの念話ができないと言った。会話に交ざれない、他人の会話が聞こえないとなると、確かに家出もしたくなる。
「わかりました。それでは、また会いましょう」
「ああ、けど、お義父さんはごめんだぞ?」
「あはは、も、もちろんですよ」
きっちり釘を刺された。ロキシーと会えるかはわからないが、いずれ金だけでも返しに来よう。
★ ★ ★
最寄りの町までは、徒歩で三日掛かるらしい。
初日で早速、ルイジェルドの重要性を痛感した。仲間にしておいてよかった。
長年一人で旅をし続けてきたルイジェルドは、道を知っており、野宿の仕度も完璧にこなした。もちろん、生体レーダーも持っているので、索敵もお手の物。この人、便利すぎる。
「できれば、色々と教えていただけませんか?」
「覚えてどうするんだ?」
「役立てます」
というわけで俺とエリスはこの三日間で野宿をマスターすべく、彼に教えを請うこととなった。
「まず、焚き火だ。だが、魔大陸では薪となる木はない」
ふむ。そういえば、ルイジェルドと出会った時も、最初は焚き火だった。
「どうするんですか?」
「魔物を狩る」
魔大陸では、とにかく魔物を狩らなければ生計が立てられないらしい。
「丁度いいところにいるな。ちょっと待っていろ」
「おっと、待ってください」
と、駆け出そうとするルイジェルドを、俺は肩を掴んで止めた。
「なんだ?」
「一人で戦うつもりですか?」
「ああ。狩りは戦士の務めだ。子供は待っていろ」
なるほど。ルイジェルドは、この先もずっとこの調子で行くつもりだったらしい。
まあ、五〇〇年以上生きているルイジェルドから見れば、俺たちなんて子供どころか孫にすら遠くおよばないのだろう。
しかも、ルイジェルドはむちゃくちゃ強い。任せっきりでも大丈夫だろう。
しかし、万が一もありうる。
何らかの理由でルイジェルドが動けなくなった場合、あるいは彼が死んでしまった場合、実戦経験がほぼ皆無な俺とエリスが残ってしまう。
それは、深い森の中かもしれない。凶悪な魔物の前かもしれない。
そのときに生き残るためにも、実戦経験は今のうちから積んでおきたい。
(だから、どうにかして、戦い方を教えてもらわないと……)
いや、その考え方はよくないな。俺と彼との関係はギブアンドテイク。対等だ。
教えてもらうのではなく、戦いの連携を二人で構築していくのだ。
「僕らは子供じゃありませんよ」
「いいや、子供だ」
「あのなぁ……ルイジェルド」
強い口調で呼び捨てにする。彼はちょっと勘違いしている。立場はハッキリさせないといけない。俺たちは、どっちが上でもないのだと。
「俺たちはお前を手伝い、お前は俺たちを手伝う。目的は違えど、共に戦う仲間であり、対等な……戦士だろ?」
そして、ルイジェルドの眼を見る。できる限り、険しい顔でだ。十数秒の葛藤。ルイジェルドの決断は早かった。
「…………わかった。お前は戦士だ」
やれやれといった感じだったが、これで保護者付きで危険なことの練習ができる。
「当然、エリスも戦うけど、いいね!」
「も、もちろんよ!」
エリスは目を丸くしてボケっとしていたが、こくこくと頷いた。よしよし、いい子だ。
「では、ルイジェルドさん。魔物の場所に案内してください」
演技はおしまい。やはり交渉は強気でやんなくちゃな。
★ ★ ★
最初に相手にしたのは、ストーントゥレントという魔物だった。
トゥレントというのは、一言で言えば木の魔物だ。木が魔力を吸い上げ、変異して人を襲うようになったもの。それらを一括してトゥレントと呼んでいる。
木の魔物というアバウトな分類であるから、その種類は多岐にわたる。
まず、全世界で確認されているレッサートゥレント。これは若木が変化したもので、基本的には木に擬態して人を襲う。力も弱く、動きも遅く、一般的な成人男性なら訓練を積んでいなくても、斧で叩き切ることができる。
これが、大森林にある妖精の泉より養分を吸い取ると、エルダートゥレントという魔物に変化する。極めて濃い魔力濃度を持つ妖精の泉の力により、水の魔術を扱えるようになるという。
他にも、大樹が変化したオールドトゥレントや、枯れ木が変化したゾンビトゥレント等、多くの種類がいる。
種類は違えども、基本的な行動パターンは変わらない。木に擬態し、近くに来た相手に襲いかかり、しばらくすると種子を残し、勝手に増える。
しかし、このストーントゥレントはちょっと特殊だ。
なんと、岩に擬態している。
木がどうやって、と疑問に思うだろう。
何も不思議なことではない。種の時点で魔物になるのが、ストーントゥレントだ。
普段は巨大な種の形をしており、人が近づくと一瞬で木に変化して襲いかかってくるのだ。
種といっても、ヒマワリの種のようにわかりやすい形状をしているわけではない。そこらに転がっている岩と似たような、丸くてゴツゴツした形状だ。
ジャガイモが一番似ているかもしれない。
「戦ううえで注意点はありますか?」
「ルーデウス。お前は確か魔術師だったな」
「はい」
「なら、火は使うな」
「効かないんですか?」
「燃えては薪にならん」
「なるほど」
「水もやめておけ」
「濡れると薪として使いにくいからですか?」
「そうだ」
この一連の会話だけで、ルイジェルドがあの魔物を薪としてしか見ていないことがわかるものだ。
つまり、ルイジェルドがいる限り、この魔物と戦う危険性は、ほぼゼロだと考えてもいいだろう。
安全に戦える相手だ。
「じゃあ、試しに僕とエリスで戦ってみます。エリスが危なくなったら助けてください」
「俺が戦わないことに意味はあるのか?」
「とりあえず、俺とエリスがどの程度戦えるかわからないので。その後、ルイジェルドさんの一人で戦うところを見せてもらって、参考にします」
「わかった」
というわけで、エリスが前衛、俺が後衛という形で戦うことにする。
これはエリスの剣術の腕を鑑みてのことだ。可愛い可愛いエリスを前衛に出すのは気が引けるが、彼女は中衛にいてもあまり役に立たない。他人に合わせられないからだ。ついでに言えば、ルイジェルドにサポートは必要ない。
だから、エリスには自由に戦わせて、ルイジェルドと俺がサポートする。
そういう形が望ましいだろう。
「じゃあエリス、僕が遠距離から一発デカイのをぶちこむから、弱ったのを叩いてください。一応、使う魔術の名前だけは言うようにするけど、急いでるときは端折るから、そのつもりで」
「わかったわ!」
エリスはもらったばかりの剣の振り心地を確かめながら、やる気満々で頷いた。戦意はバッチリ。
よし、と俺も杖を構える。
火と水はだめ。形状を見るに、風はあまり効かなさそうだから、土か。
土は得意だ。なにせ、フィギュアを作りまくっていたしな。
だが、魔物を相手にするのは初めてだし、最初は全力でいこう。
「ふぅ……」
深呼吸を一つ。手の先に魔力を集める。
何万回と繰り返してきた作業だ。今なら、たとえ足が切り落とされた状態でも、魔術を使える。
「よし」
生成:砲弾型の岩石。硬さ:できるだけ硬く。
変形:砲弾の先端は平たくし、凹みと刻みを入れる。
変化:高速回転。サイズ:拳大よりやや大きめ。速度:できる限り最速。
「『岩砲弾』!」
杖の先から、ゴウンと空気を切り裂いて、岩の砲弾が飛び出した。
砲弾はすんげー速度でほぼ水平に飛んでいき、まだ擬態しているストーントゥレントに着弾。
耳を塞ぎたくなるような音が鳴り響き──トゥレントは爆散した。
バラバラになった。
即死だ。
エリスはすでに走りだしていたが、着弾と同時に足を止め、拗ねた顔で睨んでくる。
「何が弱らせるよ! 私に死体を斬れっていうの!?」
「ご、ごめん、僕も初めてだから加減がわかんなくて」
「もうっ!」
初めての戦闘に水をさされた形で、エリスはご立腹だった。
しかし、いやまさか一撃とは。普通の岩砲弾をホローポイント弾風にアレンジしただけなんだが、やはり元の世界の人間ってのは、考えることがえげつないね。
ルイジェルドの視線を感じた。
「その杖は、魔道具か?」
彼は、俺の杖を見ていた。
「いえ、普通の杖ですよ。まあ、ちょっと材料は高いらしいですが」
「詠唱も魔法陣も使っていなかったが?」
「詠唱なしでやらないと、砲弾の形状が変化させられないんですよ」
「……そうか」
ルイジェルドが無言になった。五〇〇年生きている彼でも、無詠唱は珍しいのだろうか。
「それで……あれがお前の最大の魔術か?」
「いえ、今のを着弾と同時に爆発させることもできますよ」
「お前の魔術は、仲間が敵の近くにいる時は、使わんほうがいいな」
「でしょうね」
何かに当てたのは初めてだったけど、予想以上の破壊力だ。かするだけでも即死しかねない。何かサポートに向いた魔術があればいいんだが、どうにも前々から一人で戦うことばかりを考えていたせいで、思いつかない。この世界の魔術師は、どうやって戦っているのだろうか。
「ルイジェルドさん、もし魔術でサポートするとしたら、どんな動きをすればいいですかね?」
「わからん、今まで魔術師と共に戦ったことはなかったからな」
まあ、ルイジェルドは歴戦のスペルド族だ。他のパーティの真似をすることもないだろう。
連携については、おいおい考えていけばいい。今は実戦経験を積むことを考えよう。
「申し訳ありませんが、もう一度索敵お願いします」
「ああ……だが、その前にやることがある」
「やること?」
殺した相手にお祈りでもするのだろうか?
「薪拾いだ。随分散らばったからな」
薪は風の魔術でかき集めた。
★ ★ ★
その後、日が暮れるまで、移動しながら四度の戦闘を行った。
ストーントゥレント、大王陸亀、アシッドウルフ、パクスコヨーテ。
大王陸亀はルイジェルドが一撃で仕留めた。
真正面から脳天をぶちぬいて一撃だ。実にスマートかつ鮮やか。これが創業五〇〇年、ずっとソロで魔物を狩り続けてきた男の手際か。ストーントゥレントを爆散させていい気になっていた自分が恥ずかしい。
アシッドウルフは、口から酸を吐く狼だ。
一匹だったので、エリスが倒した。鋭い踏み込みからの一閃で、首がポーンと空を飛んだ。ルイジェルドに比べると雑だが、一撃は一撃である。
エリスは返り血をモロに浴びて、苦い顔をしていた。
酸を吐くなら血も危ないんじゃないかと思ったが、大丈夫そうだ。
初の実戦でこれなら十分だ、とはルイジェルドの談。
ちなみに二匹目のストーントゥレントは俺が即死させた。
きっちりダメージを与えつつ、しかし殺さない威力で弱らせてエリスに実戦経験を積ませようと思ったのだが、どうにも調節が難しい。
きちんと調整できるまでは、人に向けても撃たないほうがよさそうだ。
相手を殺さなければいけないという状況でも、スプラッタは見たくない。
そして現在はパクスコヨーテの群れとの戦闘中だ。
パクスコヨーテは、数十匹の集団を作る。
群れているわけではない。パクスコヨーテは分裂するのだ。といっても、戦闘中にポコポコ増えていくわけではない。分裂するのは数ヶ月に一回、増えた個体はリーダーが完全に制御する。
そうしてどんどん増えていくのだ。
たとえ本体を倒したとしても、他の個体がリーダーを引き継ぎ、戦闘を続行する。
数は力。群れを完全に制御下に置けるというのは、それだけで十分すぎるほどに強い。
そんなパクスコヨーテが二〇匹、並の冒険者なら命を落とす数であるにもかかわらず、エリスはルイジェルドにあれこれ教わりつつ、楽しそうに剣を振るっていた。
エリスも今日が初めての実戦だというのに、あまり気負っていない。あれだけ練習したんだから大丈夫、と言わんばかりの自信満々の表情で、次々とパクスコヨーテを斬り捨てている。生き物を殺すということに躊躇はないらしい。
俺はそれを見ているだけだ。
いざとなれば手出しをしようと考えていたが、ルイジェルドのサポートは神がかっている。
俺が何かすれば、やぶ蛇になりかねない。
それにしても暇だ。仲間はずれ感がすごい。
はやく、うまい連携を考えなければ。
しかし、やはりエリスは強い。
結局、彼女は俺の誕生日の直前ぐらいに剣神流の上級まで行ったんだったか。最近は魔術を使わなければまったく勝てる気がしない。
上級といえばパウロと同じ……とはいえ、水神流と北神流も上級だから、さすがにパウロの方が上だろう。実戦経験の差もある。
けれどギレーヌは、エリスの才能はパウロより上だと言っていた。いずれ追い抜くだろう。
ざまぁねえなパウロ。
「ルーデウス! こっちだ!」
ルイジェルドに呼ばれる。いつしか、パクスコヨーテは全滅していた。
「パクスコヨーテは毛皮が売れる。剥ぐぞ。こんなに数がいるとは、運がいいな」
ルイジェルドは、ナイフを取り出しつつ、そう言った。
彼にとっては、数が多いというのは、獲物が多いということに他ならない。
「ちょっと待っててください」
ルイジェルドにそう言って、俺はエリスへと近づいた。
「はぁ……はぁ……」
エリスは三ヶ所ぐらい怪我をして、息を乱していた。時間にして三十分も経っていないが、ルイジェルドはあくまでサポートに回っていたため、ほとんどエリスが倒したのだ。
疲れもするだろう。
「神なる力は芳醇なる糧、力失いしかの者に再び立ち上がる力を与えん、ヒーリング」
とりあえず傷を治しておく。
「ありがと」
「大丈夫ですか?」
「ふふん、余裕よ……むぐぅ」
ドヤリと笑ったその顔に返り血がついていたので、袖で拭ってやる。
エリスは本当に初めての戦闘の後だというのに、落ち着いている。俺なんか血の匂いでむせ返りそうだというのに。
「余裕ですか、今日が初の実戦でしょう?」
「関係ないわ。全部ギレーヌに教わったもん」
練習は本番のように。本番は練習のように。ってやつか。
エリスは素直だから、実戦でも練習の成果を一〇〇%発揮できたというわけだ。
練習通りなら、相手が血を流しても関係ないといったところか。
「まったく……」
俺は苦笑しつつ、ルイジェルドの所に戻る。彼は、俺たちのやりとりをじっと見ていた。
「エリスに戦わせてどうするつもりだ?」
「ずっと僕が守れるわけじゃないんですよ。いざという時に、自分の身は自分で守れないと」
「そうか」
「ところで、ルイジェルドさん。どうです、エリスは?」
そう尋ねてみると、ルイジェルドはこくりと頷いた。
「精進すれば一流の戦士になれる」
「ほんと!? やった!」
飛び上がるエリス。嬉しそうだ。過去の英雄に褒められれば、そりゃ嬉しいだろうとも。
そして、それは俺にとっても悪くない。ルイジェルドがエリスの才能を認めているなら、今後も密な連携を取っていける。
「ルイジェルドさん。これからはエリスが前衛、僕が後衛という陣形で行こうと思います」
「俺はどうすればいい?」
「遊撃で。自由に戦いつつ、僕らの死角をカバーしてください。そして、何か危ないことがあったら、指示を飛ばしてください」
「わかった」
こうして、陣形は決まった。数日の間で、俺とエリスは着々と戦闘経験を積んでいくことになる。
★ ★ ★
そして、野宿。
夕飯は大王陸亀の肉だ。食べきれないので、半分以上はルイジェルドの指示で干し肉にした。
大王陸亀の肉。ハッキリ言うと、あまりうまくない。かなり生臭いし、硬い。普通なら長い時間かけて煮込むものらしいが、ルイジェルドは手っ取り早く焼いた。
焚き火で焼いた。
焚き火と言えば、ストーントゥレントは死亡するとカラカラに乾くため、乾かさなくても薪として使えるらしい。ルイジェルドがあの魔物を薪としてしか見ていない理由が、わかった気がする。
「……」
それにしても、肉がまずい。誰だ、大王陸亀の肉がうまいなんて言ったヤツは。
ルイジェルドお前だよ。こういう肉は生姜とかで臭みを取らないと食えたもんじゃない。
ああ、牛が食いたい。米と牛が食いたい。
生前に読んだ漫画に、こんなセリフがある。
『焼肉は偉いよ。うまいから偉い』
美味くない焼肉には、何の偉さもないことを如実に表す言葉だ。
思えば、アスラ王国の食事は良かった。パン食が中心だったが、肉、魚、野菜、デザートと、さながら三つ星レストランのようだった。田舎出身の俺でこれなのだから、お嬢様育ちのエリスはさぞ大変だろうと思ったが、彼女は平気な顔をしてもっちゃもっちゃと食っていた。
「意外とイケるわね」
うそーん。いや、これはあれだろうか。今までいいものしか与えられてこなかった子供が、ある日ジャンクフードを食うとうまいと感じるようなものか。
「なによ?」
「いや別に、おいしい?」
「うん! こういうのね、もぐもぐ、憧れてたのよ」
なんでも、ギレーヌから話を聞いて、焚き火で肉を焼いて食うのに憧れていたらしい。
変なところに憧れるんだな。
「生でも食えないことはない」
ルイジェルドの言葉にエリスは眼を輝かせた。
「やめなさい」
試しに、と口にしかけたエリスを、俺は必死で止めた。
寄生虫とかいたらどうするんだ、まったく……。
★ ★ ★
寝る前に、ルイジェルドがエリスに剣の手入れの方法を教えていたので、一応俺も聞いておく。
もっとも、ルイジェルドの使っている槍は金属ではないし、エリスの使っている剣も、特殊な金属を特殊な鍛造法で作り出したものだから、錆びるということもないらしい。
だが、手入れは必要だそうだ。
血糊をそのままにしておくと、他の魔物が寄ってくるし切れ味も鈍る。それに、戦士として、己の武器を管理するのは当然のことだと、ルイジェルドは語った。
「そういえば、その槍って、何でできているんですか?」
ふと、気になったので聞いてみる。
スペルド族の三叉槍。純白の短槍。装飾はなく、柄と刃が一体になった構造をしている。
「俺だ」
「……は?」
「槍はスペルドの魂でできている」
哲学的な返答だった。
そうかそうか、なるほど。そうだね、命ってのはつまり魂。槍は魂、命。命とはすなわちハート。ハートとはすなわち愛。ルイジェルドの愛情は槍に注がれてるってことか。
「スペルド族は、生まれた時から槍を持っている」
俺が混乱しているとルイジェルドはそう教えてくれた。
スペルド族は、生まれた時、三叉の尻尾が生えているのだそうだ。それは成長と共に伸び、ある一定の年齢になると突然硬化して、体から離れる。槍は体から離れた後も体の一部であるらしく、使えば使うほど、その鋭さを増していく。
決して折れず、何物にも砕けず、あらゆるものを貫く最強の槍……に、なる可能性もあるらしい、本人の鍛え方次第で。
「だから、死ぬまで槍を離してはいかんのだ」
それは、四〇〇年前にしてしまった失敗を悔いる男の顔だった。恐らく彼の槍は、他のスペルド族の誰よりも硬く鋭いのだろう。頼もしいな。
けど、そういう考え方はよくないんだぜ?
頑固ってことは、他人を受け入れないってことだ。他人を受け入れないってことは、他人からも受け入れられないってことさ。
危険だよ、その考え方は。
なんて感じで旅をしていたら、あっという間に三日が過ぎ、町にたどり着いた。
第六話 「侵入と変装」
リカリスの町。
魔大陸三大都市の一つ。
人魔大戦の頃、魔界大帝キシリカ・キシリスが本拠地にしていたという町である。
別名、旧キシリス城。
まずその町を見て驚くのは、町の場所である。なんと、巨大なクレーターの中にできているのだ。クレーターは天然の城壁であり、幾度となく敵軍の侵入を防いだとされる。現在でも、魔物の侵入を防ぐのに役立つ、自然の結界である。
町の中心には半壊したキシリス城。この城は、ラプラス戦役において破壊された。当時のキシリカ派の魔王と、魔神ラプラスが戦った痕跡である。
頼もしき城壁と、かつての栄華の面影を残す黒金の城。
その二つは当時の魔界大帝の威光と、魔族の過酷な歴史を人々に知らしめる。
リカリスは由緒正しき町である。
旅人は夕刻にて、この町の本当の美しさを知るであろう。
──冒険家・ブラッディーカント著 『世界を歩く』より抜粋。
というのが、俺の知識にある「リカリスの町」である。
町の入り口は三つ。クレーターの裂け目がそのまま入り口となっている。
クレーターは高く、空でも飛べなければ入り口以外から侵入するのは難しいだろう。
そして、入り口には二人の門番。つまり、この町の警備は厳重だ。
ルイジェルドを見る。
「どうした……?」
「ルイジェルドさん。この町……入れますよね?」
「入ったことはない。いつも追い返されるからな」
ミグルド族の里での話を思い出す。人族の間でも、スペルド族はかなり嫌われている。それはもう遺伝子レベルでだ。初対面の時のエリスのあの態度を見ればわかる。
魔大陸ならあるいはと思ったが、そんなことはないらしい。
「ちなみに、どんな感じで追い返されます?」
「まず、町に近寄ると門番が叫び、しばらくすると大量の冒険者がやってくる」
俺の脳裏に、衛兵が「ストップ!!」とか言い出し、町中から屈強な男たちが次々と出てきて、襲いかかってくる光景が浮かんだ。
「じゃあ、変装とかしたほうがいいですね」
そう言うと、ルイジェルドはむっとした顔で俺を睨んだ。
「変装だと?」
嫌なんだろうか。
「落ち着いてください。まずは町中に入ることです」
「いや、変装とはなんだ?」
「え?」
変装を知らないらしい。文化の違いだろうか。
いや、そもそも知っていれば、町中ぐらいには入れただろう。
「変装とは、外見を変えて、身分を偽ることです」
「ほう……どうやってやるんだ?」
「そうですね……とりあえず、顔を隠しましょうか」
俺はとりあえず、その場に座り込み、地面に手を当てて魔力を込めた。
★ ★ ★
「止まれ!」
町の入り口には、兵士が立っていた。
蛇の頭をした、いかつい感じの奴と、豚のような頭をした、ふてぶてしい感じの奴だ。
「何者だ! 何をしに来た!」
腰の剣に手をやって誰何したのは、蛇の方だ。
豚の方はいやらしい目でエリスを見ている。
この豚野郎……気が合いそうじゃねえか。
「旅の者です」
打ち合わせ通り、俺が前に出る。
「冒険者か?」
「は……いえ、違います。旅の者です」
思わずハイと答えそうになったが、証明できるものがない。
俺とエリスぐらいの年齢なら、冒険者志望と言っても、おかしくないだろうが。
「そっちの男は? 怪しい風体だが」
ルイジェルドは俺の作った岩石製のフルフェイスの兜で顔を隠している。
槍は布で穂先を巻いて、杖のように見えなくもない。
怪しい風体とはいえ、スペルド族の姿よりはマシだろう。
「兄です。変な冒険者が持ってきた兜を身に着けたら、外れなくなったんですよ。この町なら、外してくれる人もいるかと思って……」
「ハッハ! マヌケな話だな! そういうことなら、仕方ないな。道具屋の婆さんにでも頼めば、なんとかしてくれるさ」
蛇頭が笑いながら一歩下がった。
あまり警戒されていない。日本なら、フルフェイスのヘルメットを被った男が現れたら、もっと警戒されるのだが。子供連れだからか、それとも、兜を着けたヤツは少なくないのだろうか。
「ところで、この町で稼げるところってどこにありますか?」
「稼げるところ? そんなこと聞いて、何になる?」
「兄の兜が外れるまでは滞在しなきゃいけませんし、もし外すのにお金を要求されたら、稼がなきゃいけません」
蛇頭は、「そうか、あのババアならありうるか」と呟いた。
道具屋は業突く張りなのだろうか……関係ないか。
「なら、冒険者ギルドだな。あそこなら、よそ者でも元手なしで日銭を稼ぐことができる」
「なるほど」
「冒険者ギルドは、この道をまっすぐだ。大きな建物だから、すぐに見つかるはずだ」
「ありがとうございます」
「冒険者ギルドに登録すれば、宿がちょっと割安になる。登録だけでもしといたほうがいいぜ」
俺は適当に会釈をしつつ、門を通り過ぎた。そして、ふと立ち止まる。
「そういえば、この町っていつもあんなに物々しいんですか?」
「いや、最近、この近くで『デッドエンド』が目撃されたらしいからな。警戒中だよ」
「なんですって! それは怖いですね………」
「そうだな、早くどっかにいっちまうことを祈るよ」
『出会えば死ぬ』か。
怖い名前だ。さぞ恐ろしい魔物なんだろう。
★ ★ ★
ロアと比べていささか背の低い町並みが広がっていた。
しかし、町の構成はどこでも似たような感じらしい。
入り口付近には、商人向けの宿屋や馬屋といった店が軒を連ねていた。
「さて、冒険者か……」
今までの人生の中で聞いた話を総合すると、冒険者というのは派遣社員だ。手に職をもっている人たちが、冒険者ギルドという名の人材派遣会社に登録し、仕事を紹介してもらいつつ、自分の評価を高めていく。
人々が冒険者ギルドを通して仕事を依頼すると、能力に自信のある冒険者が送られてくる。
「稼げるかどうかはわからないけど、登録しといたほうがいいのかな? 身分証明にもなりそうだし、エリスはどう思う?」
「冒険者! なる! なるわ!」
エリスの目がキラキラしていた。そういえば、エリスは何度もギレーヌの冒険者時代の話を聞いていた。案外、憧れていたのかもしれない。
「ルイジェルドさんって、もう冒険者だったりします?」
「いや、俺は冒険者ギルドのあるような大きな町には入ったことがない」
そうでしたか。なるほど、冒険者ギルドは大きな町にしかないのね。
「ま、その方が都合がいいか……」
俺の頭の中で、着々と予定が整っていく。
いつまでもこんな重たいヘルメットを被っているわけにもいかない。
顔を隠したままでは、いつまで経ってもスペルド族の名声は得られない。
何か大きなことをやって、実はスペルド族でしたっていう流れでもいいのかもしれないが、冒険者の最低ランクの仕事は町中の雑用という話だ。むしろ、大きなことをするより、こういう小さなことで意外性を出したほうがいいのかもしれない。
うまくすれば町中での信用につながる。
ルイジェルドの人柄は悪くない。
いきなり強い魔物を倒して、町を守ったんだから受け入れてくれというより、迷子の子供を助けました、というギャップの方が受ける。それはミグルドの里でも証明済みだ。魔物退治より、人助けを中心にしたほうがいいだろう。先入観なしで人と接するのだ。
ルイジェルドの人柄なら、それでも十分だろう。
しかし、人助けをするのに、このヘルメットはよくない。表情が見えないのはマイナスだ。
俺だったら、顔を隠したヤツは信用しない。
髪と額だけ隠したヘルメットにするか……いや、それでも怪しいな。この世界に人と会うのに被り物を脱ぐ云々の文化があるかどうかは知らないが、俺だったら、失礼だと思ってしまう。
しかし、少しずつ小さなことをやったところで、時間が掛かるだけだ。
ルイジェルドという存在を町中に浸透させ、それを善とするようにしなければ。
「うーむ……どうすべきか」
まずは知名度が必要だ。いくらいいことをやっても、名もなき青年の所業では意味がないのだ。
やはり、名前を覚えてもらうためにも、最初に大きく魔物退治の一つもやったほうがいいかもしれない。
この世界では、力ある者は受け入れられる傾向にある。知名度の高い魔物を退治することで、多少なりとも地位が向上する可能性もある。もっとも、スペルド族の場合は強いということはすでにわかっているから逆効果になる可能性も高いか。
まてよ、でも、町に迫る危機に対して、ならどうだろうか。誰もが窮地に陥った中で、処刑ソングと共に颯爽登場、魔界美青年ルイジェルド、って感じで一撃で相手を仕留めたら。
おお、いいんじゃないか?
問題は、その相手を何にするかだが、ちょうどいい相手の名前を、先ほど聞いたばかりだ。
「ルイジェルドさん。『デッドエンド』って何のことだか知ってます?」
『デッドエンド』とかいう魔物を町に誘導。
町をパニックに。それをルイジェルドが倒す。勧善懲悪のストーリー。完璧だ。
しかし、返ってきた答えは予想外のものだった。
「俺のことだ」
「……どういうことですか?」
なんだそれは? また哲学なのか!? と、思ったが……。
「俺は一部では、そう呼ばれている」
ルイジェルド=『デッドエンド』
ということらしい。なるほどね。納得だよ。
スペルド族が町の近くを歩いていたら、そりゃ警戒もするよね。
それにしても、そんな危ない二つ名まで付けて恐れられているとは。どんだけ恐れられているんだか……。
門番ももうちょっとちゃんと仕事しろよなと思う。
きっと、スペルド族を人として見ていないのだ。暴れまくるだけの魔族だから、変装する知能なんてないと思っているのだ。
「どうしたものか……」
しかし、この二つ名、知名度は高そうだな。利用できるかもしれない。
「賞金とか、懸かってないですよね?」
「ああ。それは大丈夫だ」
本当かな? 本当だよね? 信じるよ? 嘘ついちゃ、やーよ?
とりあえず、少し計画を変更だ。
★ ★ ★
まず、冒険者ギルドに行く前に、露店を見て回った。
入り口付近にある露店はどこも似たようなものであるとはいえ、売っている物は大きく違う。
例えば、ロアでは馬屋の代わりに、トカゲのような生物が売られている。高低差と岩の多い魔大陸では、馬よりこうした生物のほうが役立つのだろう。また、乗合馬車はないが、商人が個別で馬車を出している。
これから長い旅をするに当たって、欲しいものは多い。
少しずつ、買い集めていく必要があるだろうが、今回買うものは決まっている。
ざっと相場を調べながら、なるべく安い店を探す。急いでいるわけではないが、それほど時間も掛けたくない。目当てのものは、染料とフードだ。あと、あればレモンのようなものも欲しい。
「おっちゃん、この染料、ちょっと高すぎない? ボってんじゃないの?」
「バカ言え、適正価格だ」
「本当かなー」
「あったりまえよ!」
「でもあっちで同じのが半値で売ってたよ?」
「なにぃ!?」
「品質の差もあるだろうしなー。あ、このフードいいな。コレと、そっちのレモンっぽいのも一緒に買うから、オマケしてくんない?」
「坊主、お前交渉上手だな。わかったよ。もってけ」
「あ、そうだ。これ買い取ってよ。パクスコヨーテの毛皮と、アシッドウルフの牙とかあんだけど」
「結構あるな。ちょっとまってろ……にのふのよの……屑鉄銭三枚ってところでどうだ?」
「そりゃないよ。せめて六枚」
「しゃーねーな。じゃあ四枚だ」
「おっけ、それでいこう」
などと交渉して、一度で売買を終わらせる。相場はわからないため、これがどれほどの金額かはわからない。正直、交渉はしてはみたものの、ボラれた感もある。
残りの持ち金は鉄銭一枚、屑鉄銭四枚、石銭一〇枚。
ロキシーの両親からもらったお金だ。大切に使わないとな。
俺たちは人気のない裏通りへと入る。変な奴らに絡まれないといいが……いや、絡まれたらルイジェルドがなんとかしてくれるか。お金を増やすチャンスだ。
「ルイジェルドさん。もし誰かに絡まれたら、半殺しでいきましょう」
「半殺し? 半死半生にしろということか?」
「いえ、普通に叩きのめすだけで」
が、残念ながら絡まれなかった。
もっとも、カツアゲするような奴らだ。金なんて持っていないだろう。
「ルイジェルドさん。まずは髪を染めましょう」
「髪を、染める……?」
「はい。この染料で」
「なるほど、髪色を変えるのか。面白いことを思いつくな」
感心された。どうやら、この世界には髪を染めるという習慣はないらしい。
いや、ルイジェルドが知らないだけかな?
あんまり人里に降りてこないようだし。
「しかし、ならばもっと違う色のほうがいいのではないか?」
俺が選んだのは、青色だ。できる限りミグルド族の色に近いものを選んだ。
「いえ、ここから徒歩三日の位置にミグルド族の集落があります。それを知っている人は多いでしょう。ですので、ルイジェルドさんは今日からミグルド族です」
「……お前たちは?」
「僕らはそのへんで拾われたルイジェルドさんの子分その一とその二です」
「子分? 対等な戦士ではなかったのか?」
「そういう設定なんです。別に覚えなくてもいいですが、他の人にそう見えるように、僕が演技します」
これからやるのはお芝居だ。俺はルイジェルドに『設定』を語った。
今日からルイジェルドは、スペルド族の『デッドエンド』を騙る、ミグルドの青年ロイスである。ミグルドの青年ロイスは、常々皆から畏怖されるような存在でありたいと思っていた。そんなある日、二人の子供を拾う。魔術と剣術を使う子供たち。彼らは助けてくれたロイスに心酔した。
「心酔してるのか?」
「僕は別に」
「そうか」
この二人は結構強い。それに眼をつけたロイスはあることを思いつく。
自分はミグルド族の中でも背が高いから『デッドエンド』のルイジェルドを騙れば、もっと簡単に皆に恐れてもらえるかもしれない、と。
この二人は、子供だがなかなか使える。利用して、一気に有名になってやろう、と。
「俺の名を騙るのか、許せん男だな」
「そうでしょう、確かに許せない。でも、もし偽ルイジェルドが、良いことをしたら。人々はどう思いますか?」
「……どう思うんだ?」
「明らかに偽者だとわかるヤツだが、結構いいヤツだ、とそう思うだろう」
必要なのはコミカルさとちぐはぐさだ。他人を騙るようなヤツだが、根は悪いヤツじゃない。
そう思わせるのが肝要だ。
「ふむ……」
「偽ルイジェルドはいいヤツだ。という噂が流れればこっちのものです。いずれ噂は曖昧になり、『ルイジェルドはいいヤツだ』という形になります」
「……それはすごいが、本当になるのか?」
「なります」
断言した。少なくとも、今のルイジェルドがコレ以上評判を落とすことはない。
現時点で最低評価だからな。
「そうか、そんな簡単なことでよかったのか……」
「簡単じゃないですよ。成功するかどうかもわかりませんし」
計画ってのは、どこかで必ずほころびが生じるもんだ。綿密にすればするほど、後半で計画が狂う。だが、うまくいけば噂を重ねることで、ルイジェルドの本性が正しく伝わるかもしれない。
「しかし、嘘がバレたらどうする?」
「やだな。ルイジェルドさんは嘘なんてついてないんですよ」
「……どういうことだ?」
ミグルド族のフリをして、スペルド族を名乗る。予定通り、人に好かれるような良いことをする。名前だって偽らない。ロイス云々は、本物のスペルド族だとバレそうになった時の布石で、当人はルイジェルドと名乗る。
スペルド族のルイジェルド。それを周囲が勝手にミグルド族のロイスが、ルイジェルドのフリをしているのだと勘違いするだけだ。
だから嘘なんてついていない。嘘をつくのは俺だけだ。
ルイジェルドは嘘をつくのに抵抗があるようだから、それは黙っておこう。
「向こうが勝手にミグルド族だって勘違いするだけです」
「む……ああ、そうか。俺が俺を騙るから、しかしロイスの振りを……。頭がこんがらがりそうだ。俺はどうすればいい?」
「普段どおりでいいですよ」
ルイジェルドは難しい顔をしていた。演技派の俳優にはなれないな、この男は。
「でも、安い挑発で切れて相手を殺したりはしないでください」
「ふむ……それは、喧嘩をするなということか?」
「してもいいですけど、苦戦するフリをしてください。何発かもらって、肩で息をして、で、最終的にはなんとか勝った、って感じにしてください」
言ってみてから、そんな演技、できるのだろうかと思ったが、
「手加減をするのか。どういう意味があるんだ?」
そこは大丈夫らしい。
「ホンモノのルイジェルドならこんなに弱くない、と思うと同時に、ホンモノだったら俺って結構すごいんじゃね? と思わせることができます」
「よくわからんな……」
「こっちを偽者だと思わせると同時に、相手の気分がよくなるんですよ」
「気分がよくなってどうする」
「スペルド族が弱いという噂を流してくれます」
すると、ルイジェルドはむっとした顔になった。
「スペルド族は弱くないぞ」
「知っています。けれど、強いから恐れられているんです。弱いとわかれば、今のような状況も緩和されるかもしれません」
とはいえ、あまり弱いと思われすぎるのも問題だ。
知らない土地で生き残っている(かもしれない)スペルド族。
彼らに対し、また迫害が起きるかもしれないから、バランスが大事だ。
「そういうものか……」
さて、こんなものか。
あまり色々言っても、ボロが出るだけだからな。
「僕は全力でサポートしますけど、どう転ぶかはルイジェルドさんの頑張り次第です」
「ああ、わかっている。頼む」
俺は露店で買ったレモンっぽい果物の果汁を使ってルイジェルドの髪を脱色。
元々エメラルドグリーンで色素が薄いところを脱色に成功。染料でベットリと着色。
うーむ。あまり綺麗ではない。むしろ汚い。
が、少なくとも緑っぽくはない。遠目ならミグルド族には……見えないか、背丈が違いすぎて。
けど、スペルド族っぽくは見えないかもしれない。
まあ、変装は曖昧なぐらいがちょうどいい。
ミグルド族っぽいけど、スペルド族って名乗ってるし、でもどっちでもないし、あれ? ってぐらいでいい。
「あと、これを渡しておきます」
俺は首からネックレスを外し、ルイジェルドの首に掛けた。
「これは、ミグルドの守りか」
「はい。僕の師匠が卒業祝いにくれたものです。以来、肌身離さずつけています」
これをつけていれば、少なくともミグルド族の関係者だとは思ってもらえるはずだ。
知っている相手には、ね。
「大切なものだな。必ず返そう」
「絶対ですよ」
「ああ」
「なくしたら本気でぶっ殺しますよ」
「わかっている」
「具体的に言うと、土の魔術でこの町の入り口を閉鎖、クレーターが完全に埋まるまでマグマを流し込みます」
「他の町人も巻き込むつもりか? 子供もいるんだぞ」
「子供の命を助けたかったら、絶対になくさないでください」
「むぅ……そんなに不安なら最初からお前が持っていたほうがいいんじゃないか?」
「いえ、もちろん冗談ですよ」
「………」
さて、フードの方はエリスに被ってもらうか。彼女の赤い髪は目立つだろうからな。
視点は一つに集めなければ。
「エリス、このフードなんだけど……」
と、先ほど買ったフードを広げてみると、『耳用の袋』がついていた。
なんというかファイ○ルファンタジーⅢに出てくる、導師の被っているフードだ。
獣族用なのだろうか。これは買い物を間違ったかもしれない……。
エリスはあまり服装には拘らないが、あのボレアス流の挨拶を見ていればわかる。
あまり獣族っぽい格好やポーズはしたくないのだ。
「あの、エリス、これ、なんです、けど」
「そっ! それっ! ど、どうするの!」
「え、エリスに、どうかなぁ~って……」
「ホント!」
と、思っていたのだが、すごく喜ばれた。あのポーズ自体は嫌じゃなかったんだろうか。
「大切にするね!」
早速フードを着けたエリスが、満面の笑みで言った。
まあ、あれだな。なんだか知らんがとにかくよし! ってやつだ。
さて、まずは冒険者ギルドだ。必要なのはコミカルさ。そいつを忘れないように。
うまくいくことを祈ろう。
第七話 「冒険者ギルド」
冒険者ギルド。
そこは数々の猛者が集まる場所だ。
肉体に自信を持つ者、魔術に自信を持つ者。
ある者は剣を、ある者は斧を、ある者は杖を、またある者は素手で。
自分は他者より強いと豪語する者、そんな者を心中であざ笑う者。
鎧を着けた剣士がいれば、軽装の魔術師もいる。
ブタのような男、下半身が蛇の女、翅の生えた男、馬の足を持つ女。
あらゆる種族が集い、ひしめき合っている。
それが魔大陸の冒険者ギルド。
リカリスの町の冒険者ギルド。
その巨大なスイングドアが、バンと乱暴に開かれた。
何事かと、視線が集まる。冒険者ギルドの扉を乱暴に開ける者は少ない。
どこかのパーティが帰ってきたのか? 魔物が襲ってきて、門番が救援を要請したのか? あるいはただの風の悪戯か? そういえば、デッドエンドが近くに出没したと聞いたが、まさか……。
そう思った彼らの目に、三人の人物が映る。
一番前に立つのは、少年。まだ幼い。しかし自信満々の表情。布を巻いた杖、薄汚れてはいるが高級そうな服。大人だらけ強面だらけのここに、一切気圧されることなく、堂々と入ってくる。
何者だ、と何人かが思った。あまりに不釣り合いだ、と。
あるいは、見た目と年齢が比例しない種族なのやも、と。
少年の陰に隠れるように立つのは、恐らく少女。その顔は目深に被ったフードのおかげで窺い知ることはできない。だが、年齢に反して物腰と眼光は鋭く、腰に差した剣は一目で使い込まれたものだとわかる。この場にいる何人かが、彼女を腕利きの剣士と認めた。
最後の一人は、背の高い偉丈夫。額に赤い宝石、顔を縦断する切り傷。『デッドエンド』の特徴とそっくりだ。悲鳴を上げそうになった者もいた。しかし、その青い髪。すぐに勘違いだと知る。よく似た別人だ、と。
異様。まさに異様だ。
誰一人として普通ではない三人組は何をしに来たのか検討もつかない不気味さを持っていた。
少年が大声を張り上げた。
「おいおいおいおい! シケたツラしてんなぁ! こちらにおわす方をどなたと心得る!」
いやいや、誰だよ知らねえよ、と誰もが思った。
「なんとあのスペルド族の悪魔! 『デッドエンド』のルイジェルド様だ! 黙りこくってねえで、怯えるか逃げるかしろってんだ!」
いやいやソレはねえよ、と誰もが思った。スペルド族の髪の色は目が醒めるような緑だ。
あんな暗くて汚い青色ではない。
「兄貴! こんな田舎にゃあ『デッドエンド』の顔は知られてないようですぜ! まったく、ちょいと足を運んでみりゃあ、噂はしてても、だーれも気づかねえ」
どうやら、少年はあの青年を『デッドエンド』と言い張りたいらしい。そうわかると、あの少年の甲高い口上がやけに滑稽に思えてきた。あっという間に、不気味さが消えていく。
あの兄貴と呼ばれた青年。なるほど、確かにあの額の赤い眼と、顔の傷はそれっぽい。
だが、大事なところを間違っていやがる。
「プッ」
吹き出したのは誰だったか。
「なんだてめえ! なに笑ってやがる!」
少年は耳ざとく聞きつけて、怒りの顔を声の方向へと向ける。その動作があまりに滑稽で、ギルド内の含み笑いが徐々に多くなる。
誰かが言った。
「プスッ……フッ……だ、だってよ。スペルド族の髪は……緑だぜ?」
そのとたん、冒険者ギルドのロビーに大爆笑が起こった。
★ ★ ★
笑い声を聞きながら、俺はつかみはオッケーだなと感じていた。
冒険者ギルド。想像はしていたが、思った以上に粗野な感じだ。
種族が様々なのは、魔大陸だからだろうか。馬面の男、カマキリみたいな鎌を持った男、蝶みたいな翅を持った女、ヘビみたいな足の女。
人とよく似ているが、どこかしらに違いがある。
また、部位が動物じゃないからといって、人間そっくりとは限らない。肩から棘みたいなのが生えてるヤツもいるし、全身の肌が青いヤツもいる。腕が四本だとか、頭が二つあるヤツもいる。人間そっくりだけど、どこかがちょっとずつ違う。
考えてみれば、ミグルドやスペルドは人族にかなり近い種族だろう。
「あ、兄貴をバカにしてんじゃねえよ! 兄貴はな、俺たちが荒野で魔物に襲われてるところを助けてくれたんだぞ!」
気圧されることなく、俺は適当に演技しながら中へと入っていく。
「聞いたか! で、デッドエンドが人助けだってよ!」
「ヒャハハハハ! す、すげぇいいヤツじゃん!」
「マジかよ! 俺も助けてもらいてぇ! ギャハハハ!!」
いつもなら、こういう嘲笑を聞くと足が竦むところだが、演技をしているせいか、あるいは笑ってる奴らに現実味がないせいか。
それとも、俺も成長したからかな?
いやいや。増長はすまい。大体、今の笑いは俺ではなく、ルイジェルドに向いているのだ。俺の足が竦むわけがない。調子に乗るのは、自分に対する敵意を対処できるようになってからにしよう。
とりあえず辺りを見渡し、ルイジェルドを本物だと思ってる奴はいないことを確認。
ここで、事前に用意しておいたセリフA。
「こいつら許せねえ! 兄貴! やっちまってくださいよ」
「ふっ、笑いたい奴は、笑わせておけばよいのだ」
ちなみに、笑わなかったパターンのBも存在している。
「よいのだ……(渋い顔)、だってよ!」
「も、もう大物気取りかよ!」
「や、やべぇ、俺、謝っちゃいそう」
こいつら、ルイジェルドがホンモノだってわかったら、泣いて謝るんだろうな……。
「ふん! てめえら、兄貴の寛大さにせいぜい感謝するんだな!」
俺は捨て台詞を言って、周囲を見渡す。
左手には、紙がベタベタと貼り付けられた巨大な掲示板。右手には、四つのカウンターが並んで、職員が呆気に取られた顔でこちらを見ている。右手だな。
俺は二人を伴って歩いていき……ってカウンター高ぇな。
ルイジェルドに目配せして、持ち上げてもらう。
「おい職員! 冒険者登録したい!」
ギャラリーに聞こえるように、大声で言った。後ろで沸き起こる大爆笑。
「で、で、デッドエンドが、に、新人だってよぉ!」
「げはっげほっ……腹いてぇよ!」
「すげぇ、お、俺、デッドエンドの先輩になっちゃった!」
「そ、それマジ自慢できるわ!」
よし、もういいだろう。
「うるせえな。職員の声が聞こえないだろが!」
そう叫ぶと、冒険者たちはニヤケ顔のまま、口をつぐんで静かになった。
「わ、わかった、わかったよ」
「さ、最初の説明は大事だもんな……ぷすす」
「くくく」
まだ含み笑いが聞こえるが、よし、これでいいだろう。
★ ★ ★
苦節約四十四年。とうとう俺は、念願のハローワークへと赴いた。
『水聖級魔術師』という資格を手に、途中で仲間になった『百年単位の無職』と共に……。脇には養わなければいけないワガママ娘が一人。
働かなければ、食っていけない──というのはさておき。
「では職員さん。お騒がせしました。よろしくお願いします」
オレンジ色の髪をして牙を生やした女性職員。
胸元の大きく開いた服装で、もちろん谷間が見えている。もっとも、乳房が三つ並んでいるので、谷間は二つある。一つ増えるだけで二倍になるもの、なーんだ。
「え? あ、はい。冒険者登録……ですよね?」
彼女はいきなり態度の変わった俺に戸惑ったようすだった。ま、ずっと演技していてもボロが出るだけだしな。ナメられないように演技してたってことでオッケーよ。
「はい。なにせ、新人なもので」
「でしたら、こちらの用紙にご記入ください」
三枚の紙と細くとがった炭が渡される。紙はどれも同じものだ。名前と職業を書く欄があり、注意事項と規約が書いてある。文字が読めない奴はどうするんだと、思っていると。
「文字が読めないのでしたら、代わりに読み上げますよ?」
そういうことらしい。
「いえ、必要ありません」
俺が読み上げて、エリスに聞かせてやる。
一.冒険者ギルドの利用
冒険者ギルドに登録することで、冒険者ギルドのサービスを受けることができる。
二.サービス内容
全世界における冒険者ギルドでは、仕事の仲介、報酬の受け渡し、素材の買取、貨幣の両替等のサービスを行っている。
世界情勢の変化で、通知することなくサービス内容が変更されるものとする。
三.登録情報
登録された情報は冒険者カードにて冒険者自身が管理することとなる。
紛失すれば再発行は可能だが、ランクはFからとなる。
また、各地域ごとの罰金が発生する。
四.冒険者ギルドの脱退
ギルドに申し出れば、脱退が可能。
再登録も可能だが、ランクはFからとなる。
五.禁止行為
以下に定める行為を禁止する。
(1)各国の法令に違反する行為
(2)ギルドの品位を著しく貶める行為
(3)他冒険者の依頼を妨害する行為
(4)依頼の売買行為
禁止行為が認められた場合、罰金と冒険者資格を剥奪とする。
六.違約金の発生
請け負った依頼を失敗すると、違約金として報酬の二割を支払う。
期限は半年間。支払えなければ、冒険者資格は剥奪となる。
七.ランク
冒険者はその実力に応じて、SからFまでの七段階でランク分けされる。
原則として、自分のランクの上下一つ以内の依頼までしか請けることはできない。
八.昇級と降級
ランクに応じた規定の回数の依頼を成功させることで、昇級することが可能。
ただし、実力が伴わないと感じたら、そのままのランクでいることも可能。
また、一定回数連続で依頼を失敗することで、一つ下のランクへと降級する。
九.義務
魔物の襲撃などで国より要請を受けた場合、冒険者はそれに従う義務がある。
また、緊急事態において、冒険者はギルド職員の命令に従う義務がある。
エリスは途中からうんざりした顔をしていた。彼女は、こういう堅苦しい文章は苦手なのだ。
俺も、そんなに得意じゃないけど、こういうのはきちんと読んでおかないとな。
とりあえず、特に問題はなさそうだが──。
「職員さん、質問があるんですが」
「なんでしょうか」
「この文字って、どこの言葉でもいいんですか?」
「どこの言葉というと、例えば……?」
「人間語とか」
「あ、それでしたら大丈夫です」
それでしたらというと、マイナーな部族が使っている特殊な文字とかはダメなんだろう。
もちろん、日本語も無理だろうから、俺は魔神語で書いておく。人族と思われるより、見た目が年若い魔族と見られていたほうが都合がいい。
「エリスも自分で書いてください」
エリスにも自分で書くように伝える。こういう契約書は、自分で書いたほうがいい。
ちなみに、ギルド内での会話は全て魔神語だ。
エリスがむっとしつつも静かなのは、周囲の言葉がわからないからだ。もし彼女が嘲笑を生で聞いたら、剣を抜き放って襲いかかったかもしれない。
「使う気はまったくないんですが、もし偽名を使った場合はどうなりますか?」
「特に罰則はありません。あくまで登録名なので」
「犯罪者が名前を変えている場合もありますよね?」
「魔大陸と他の大陸では犯罪者の定義も違いますので、冒険者ギルドに迷惑を掛けなければ問題ありません。ですが、一度冒険者資格を剥奪されたら、少なくともこの大陸で二度目の登録はできないと考えてください」
「それで大丈夫なんですか?」
「問題はありますが、魔大陸には生まれた時に名前を持たない方も大勢います。なので、偽名を禁止すると登録できない方が大勢出てきてしまいます」
なるほど。大陸ごとで冒険者ギルドの管轄は違うのかもしれない。
スペルド族だと冒険者ギルドに登録できない可能性もあったからロイスという偽名も考えておいたが、とりあえず、問題なさそうだ。
「ここで登録してから別大陸に渡った場合、登録しなおす必要は?」
「ありません」
だよね。
「書かれましたら、こちらに手を載せていただきます」
と、用意されたのはエロゲーの箱ぐらいの大きさを持った透明な板で、真ん中のあたりに魔法陣が刻まれている。下には、金属のカードが敷かれている。
ふむ。なんだろうか。
「こうですか?」
まず俺からぺたりと手を載せると、職員が板の端をポンと指で叩いた。
「名前:ルーデウス・グレイラット。職業:魔術師。ランク:F」
職員が用紙の内容を淡々と読みあげて、もう一度ぽんと指先で叩く。すると、魔法陣がほんわりと赤く光り、すぐに消えた。
「どうぞ、こちらがあなたの冒険者カードになります」
何の変哲もない鉄の板には、ボンヤリと光る文字で、
名前:ルーデウス・グレイラット
性別:男
種族:人族
年齢:十
職業:魔術師
ランク:F
そう書かれていた。人間語だ。しかしなるほど。そういう魔道具か。
てか、これを使えば本を書くの簡単なんじゃなかろうか。
冒険者ギルドのような公的な場所で使われているなら、もっと出回っていてもいいはずだし……。
いや、こっちのプレートにも仕掛けがあるのかもしれない。名前、職業、ランクに関しては職員が手動で入力するみたいだが、性別、種族、年齢に関しては手から読み取れるのか……。
まずいな。人族であることを隠しておこうと思ったのに、年齢と種族名が出てしまった。
まあいいか。なんとかなるだろう。
名前:ルイジェルド・スペルディア
性別:男
種族:魔族
年齢:五六六
職業:戦士
ランク:F
あ、もしかして、これスペルド族って出ちゃうんじゃねえのと、思ったが、ルイジェルドのカードには魔族との表示。実にアバウトだが、ほっとする。
年齢が出てしまったが、職員の人も別に気にしていない。魔族だとそれほど珍しくもないのか。
ルイジェルド・スペルディアという名前も、あまり気にしていないようだ。
偽名とでも思っているんだろうか。心外だな、使わないと言ったばかりだというのに。
それとも、もしかして『デッドエンド』の本名がルイジェルド・スペルディアだとは知らないのかもしれない。さっきから、デッドエンドって単語は聞くけど、ルイジェルドって単語は聞かないもんな。
ちなみに、彼のカードは魔神語で書かれていた。
名前:エリス・ボレアス・グレイラット
性別:女
種族:人族
年齢:十二
職業:剣士
ランク:F
エリスのも人間語だった。
「僕と彼ので文字が違うようですが?」
「はい、文字は種族ごとで変わります」
なるほど、人族は人間語、ってことか。
「ハーフの場合はどうなるんですか?」
「混ざることもありますが、基本的には血の強いほうで表示されます」
「人族でも魔神語しか読めない人とかはいますよね?」
「その場合は、カードの真ん中を指で押さえて、変えたい言語を言ってください」
試しに、カードの真ん中を押さえ、『獣神語』と言ってみる。
すると、表示が変わった。
なるほど。面白い。
『魔神語』、『闘神語』。
次々に変えてみると、職員にたしなめられた。
「あまりやりすぎますと、カードの魔力が切れるのが早くなりますので、お気をつけください」
「切れるとどうなるんですか?」
「ギルドにて補充が必要となります」
やはりカードの方にも仕掛けがあるのか。
小さな魔力結晶でも埋め込んであるのだろうか。
「魔力が切れると、情報が消えるとかはない?」
「ございません」
「長いこと一つのカードを使い続けると、電池の減りが早くなるとかは?」
「でんち……? 魔力のことでしたら、ありません。魔力は通常で一年ほどは持ちますが、依頼完了の都度、魔力充填を行いますので、通常は切れることはありません」
「再充填にはいくら掛かるんですか?」
「料金は掛かりませんが……」
じゃあなんでたしなめるようなことを言ったんだと思ったが、あんがいカードの魔力が切れて冒険者ギルドに怒鳴りこんでくる奴がいるのかもしれない。どこの世界にもクレーマーはいそうだしな。
「わかりました、気をつけましょう」
それにしても、充填式か……。誰が考えたのか知らないが、面白いシステムだな。これを利用すれば、もっとあれこれできると思うんだが……。冒険者ギルドが技術を独占しているのだろうか。
まあ、今は考えないでおこう。
「んふふ」
エリスは自分のカードを見て、にまにまと笑っていた。
嬉しいのはわかるけど、なくすなよ?
「パーティの登録はなさいますか?」
「パーティ登録? あ、します」
職員に言われて気づく。書類にパーティのことが書いてなかったから失念していた。
最初から、パーティは組む予定だったのだ。
「その前に、パーティについて詳細を伺っても?」
頷くと、職員が説明してくれる。
・パーティは最大七人まで入ることができる。
・パーティにはリーダーの上下一ランクまでしか入ることができない。
・受けられる依頼はパーティランクで決まる。
・パーティランクはメンバーの平均値。
・依頼成功時の昇格値はパーティ員全員に入る。
・パーティに加入していても、個人での依頼受注は可能。
・加入にはリーダーとギルドの承認が必要。
・脱退にはギルドの承認だけでいい。
・リーダーにはメンバーを強制脱退させる権限がある。
・リーダー死亡時には、自動的にパーティ解散となる。
・二つ以上のパーティでクランを結成することができる。
・優秀なクランにはギルドより様々な特典がある。
クランの部分はまあいいか。しばらくは関係なさそうだし。
クランの部分はまあいいか。しばらくは関係なさそうだし。
「では、パーティ名は何に致しますか?」
「『デッドエンド』でお願いします」
職員の顔がひきつったが、そこはさすがプロ。すぐに笑顔を取り戻した。
「わかりました。冒険者カードをお預けください」
俺たちはしまったばかりのカードを取り出し、渡す。職員はそれを持って奥へと行き、ちょっとして戻ってきた。
「はい、どうぞご確認ください」
カードを見ると、最後の項目に『パーティ:デッドエンド(F)』という文字が増えていた。(F)と付いているのはパーティランクだろう。しかし、デッドエンドとか文字で見てみると恥ずかしいな。人の口から聞くと、あんなに恐ろしい響きなのに……。
「以上で登録終了となります。お疲れ様でした」
「はい、お疲れ様です」
「依頼を受ける際には、そちらの掲示板よりお剥がしになり、受付まで持ってきてください」
「はい」
「買取は建物の裏となっておりますので、お間違えのないようにお願いします」
「裏ですね。ありがとうございました」
ふう、ようやく終わったか。
★ ★ ★
早速、俺たちは掲示板の方へと移動する。
その途中には、ニヤニヤと笑う冒険者たちがいる。
どいつもコイツも、俺たちを動物園の猿を見るような目で見ている。だが、中にはいくつか、単純に面白くない、という表情をした奴らもいる。
ああいうのは要注意だな。
一応、ルイジェルドには喧嘩はオッケーだという話はしてあるが、彼の演技力にはあまり期待していない。厄介事を福と転じる流れにはするつもりだが、うまくいくとは限らないからな。
今日のところは、なるべく喧嘩なんかはしないでおきたいものである。
「っと」
見ると、俺の進行方向に、一本の足が突き出ていた。
足の主は、実にふてぶてしい顔をしたカエルだった。青色に黒い斑点模様のカエルで、頬をプクプクと膨らませつつ、笑いをこらえた表情で、足を伸ばしていた。
足を引っ掛けようとでもいうのだろうか。
なんか嫌な記憶が蘇ってくるが、俺はそれを振り払いつつ、その足をまたいで避けた。
「ギャハハハハハ!」
「ケーッヒヒヒヒヒ!」
「ゲーコゲコゲコ!」
その途端、笑い声が周囲に響き渡った。
ビクリと肩を竦ませると、さらに笑い声が大きくなる。
おちつけ。こんなのはどうってこたぁない。俺が何をしたって、笑うつもりだったのだ。生前と一緒。典型的なイジメみたいなもんだ。
俺につづいてエリスがその足をまたごうとすると、カエル男はひょいと足を上げて、エリスのつま先を引っ掛けた。
『キャっ!』
エリスは転びかけたものの、寸前でダンと足を踏み鳴らしつつ、転倒を避けた。しかし、その動作に反応して、やはり周囲で笑い声が巻き起こる。
エリスは顔を真っ赤にして拳を握りしめ、ギリギリと歯ぎしりをしながら、カエルを睨みつけた。
「ぉ、わっりぃわりぃ、ちょいと足が細長くってよぉ」
男の謝罪はエリスには通じない。まずい。もしかして喧嘩になるだろうか。
エリスが殴りかかるのはあまりよくないのだが……と、思っていると、エリスは「フン」と鼻息を一つ、ぷいっとそっぽを向いて、俺の方へと向かってきた。
その表情は般若だが……よく我慢したね。エリス、偉いよ!
敢闘賞をあげよう! 一〇〇点追加だ!
「……」
と心の中で褒めていたところ、最後にルイジェルドが足の前に立った。
自分の前に突出された足。カエルのように細長い足だ。あんな足で冒険者をやっていくのは大丈夫なのだろうか。それとも、カエルのような凄まじいジャンプ力を持っていたりするんだろうか。
いや、そんなことよりルイジェルドだ。
「…………」
ルイジェルドはその足を、大きくまたいで通ろうとした。
カエル男はひょいと足を上げ、エリスの時と同様、ルイジェルドの足に引っ掛けようとする。
「うおっ!?」
次の瞬間、バランスを崩したのは、カエル男だった。
ルイジェルドは自分の足に掛かった足を蹴り上げるように持ち上げ、カエルの重心を崩したのだ。
カエルは椅子から転げ落ちて、ひっくり返った。カエルだけに。
潰れたカエルのようにベチャリと地面に落ちた瞬間、周囲から笑い声が上がった。
「ゲタゲタゲタゲタ!」
「にゅ、ニュービーに転ばされてやんの!」
「さ、さすがスペルド族、マジウケる!」
その笑い声を聞いて、カエル男の青い顔が、みるみるうちに赤くなった。やはり変温動物なのだろうか。
「てっめぇ!」
カエル男はカエルのように起き上がりつつ、腰からナイフを抜いて、ルイジェルドに向けた。
えっ。うそ。マジで? そんなんで殺し合いまでいくの?
「ふざけた真似してくれやがって」
「……俺をあまりなめてると、痛い目を見るぞ」
ルイジェルドさん、それ、喧嘩の時のセリフですけど。相手はナイフ、いや、これぐらいなら喧嘩の範疇で済むのか? どうなんだ?
「おいおい、やめとけってペルトコ」
と、そこに割り込んできたのは、馬の頭をした男だった。
「ニュービーいじめなんて、今どき流行んねえだろ?」
「しかしよぉ」
「おめぇが勝手にコケたんだろ?」
「でもノコパラよ、こいつのツラ……」
「おめぇが、勝手に、コケたんだろ? な?」
馬面がそう言うと、カエル男はしぶしぶといった感じで、チッと舌打ちをして、足早に冒険者ギルドから出ていった。
その様子を見て、周囲も白けたと言わんばかりの表情で三々五々、散っていった。
喧嘩に関してはある程度考えていたが、実際に目の当たりにすると、やっぱ緊張するな。
なんて思いつつ、俺は改めて、掲示板へと移動した。
馬面の男が何やら不気味な視線を送っていることに、気づかずに。
★ ★ ★
掲示板には、大量の貼り紙があった。
依頼の山だ。
受けられる依頼はFとEだが、そのランクに大した依頼はない。ほとんどが町中でできる仕事だ。
倉庫整理、調理補助、帳簿記入、迷子のペット探し、害虫駆除。
どれも簡単にできそうで、どれも賃金が安かった。
ちなみに、依頼書はこんな感じだ。
F
・仕事:倉庫整理 ・報酬:石銭五枚
・仕事内容:重いものの運搬 ・場所:リカリス町一二番地、赤い扉の倉庫
・期間:半日~一日 ・期限:無期限
・依頼主の名前:オルテ族のドガム
・備考:荷物が多くて手が足りねえ。誰か手伝ってくれ。力があればあるほどいい。
F
・仕事:調理補助 ・報酬:石銭六枚
・仕事内容:皿洗い、食事の運搬等 ・場所:リカリス町四番地、足踏亭
・期間:一日 ・期限:次の満月まで
・依頼主の名前:カナンデ族のシニトラ
・備考:大勢の予約客が入った。手伝いが必要だ。ついでに味見もしてくれると助かる。
E
・仕事:迷子のペット探し ・報酬:屑鉄銭一枚
・仕事内容:いなくなったペットの捜索・捕獲
・場所:リカリス町二番地、キリブ長屋・三号室
・期間:見つかるまで ・期限:特になし
・依頼主の名前:ホウガ族のメイセル
・備考:うちのペットがいなくなっちゃって帰ってきません。
お小遣いをはたいて依頼します。誰か探してください。
どれもパーティで受けるようなものではなさそうだ。
低ランクのときは、基本的にソロなのだろうか。依頼成功時の昇格値は全員に入るらしいし、低ランクの時はパーティでいくつかの依頼を受けて、手分けするという方法が主流なのかもしれない。
「とりあえずは、何か簡単そうなものからかな……」
しかし、なんでペット探しがEなんだろうか……あ、町が広いからか。
ついでに言えば、「見つかるまで」ってのがキツイと見た。死んでいる可能性もあるからな。でも『お小遣いをはたいて』か、きっと可憐な少女に違いない。誰か行ってやらないとかわいそうだなぁ……。
「ドラゴンと戦うのとかないの?」「Sランクにあるぞ。これだ」「ほんと!? ……読めない」「北の方にはぐれ竜が一匹住み着いたと書いてある」「勝てるかな?」「やめておいたほうがいい。竜は強いからな」「そう。でも、討伐系がいいわね……」「討伐系はCランクからだな」「Cランクからしかないの?」「そのようだ」「最初はゴブリンとかと戦うって聞いたことあるけど?」「この大陸にそんな弱い魔物はいない」
エリスはルイジェルドに依頼内容を読んでもらい、物騒なことを言っていた。
ルイジェルドは面倒見がいいなぁ。
「おいおい、ぷくく、で、デッドエンドの皆さんよ。そこは、ふふ、ちょっと、くくく、ランクがたけえんじゃ、ねえのかい?」
と、さっき笑っていたうちの一人が、ニヤニヤしながら二人に近づいてきた。
馬の頭を持った、筋肉ムキムキマッチョマン。確か、先ほど喧嘩の仲裁をしてくれた奴だ。
俺は素早く移動し、二人と馬面の間に割ってはいる。
「うるせーな! ちゃんとFかEを受けるよ!」
「おいおい、怒んなよ。アドバイスしてやろーってんじゃねえか」
「なんだとぉ?」
「ほら、この依頼だよ。迷子のペット探し」
ペリッと剥がしたのは、さっき俺が見ていたやつだ。
「これは町が広すぎるから難しいって思ったんだよ」
「おいおいおいおいおい。お前さんの兄貴は『デッドエンド』、スペルド族だぜ?」
「だからなんだってんだよ!」
「額に付いてる眼は飾りか? 広いっても、その眼がありゃ一日も掛かんねぇじゃねえか」
む。なるほど。言われてみれば確かに。生物の探しもの系はルイジェルドがいれば楽勝だ。
たとえ相手が猫でも、彼なら……てか、何がアドバイスだ。
俺たちを偽者だと思って煽ってるだけじゃねえか。
「うるせえな! ほっとけよ!」
と、突っぱねては見たものの、迷子のペット探しは、ルイジェルドの能力をうまく活かせる。
頭の片隅にとどめておいたほうがいいだろう。
「兄貴! 行きましょう!」
「ん? 依頼は受けなくていいのか?」
「いいんスよ! こんな状態で依頼を受けたってロクなことがないっすからね!」
どのみち、今日は顔見せと登録だけのつもりだった。依頼はどんなものがあるかと見てみただけだ。本格的な活動は明日からだ。
「行きましょう」
俺たちが冒険者ギルドを出ると、ギルド内に残った奴らから、また爆笑が起こった。
「おいおい、依頼も受けずに帰るのかよ!」
「さすがデッドエンドさんは余裕だぜェー!」
「ギャハハハハハ!」
ルイジェルドは困惑の表情をしていた。本当にこれでいいのか、と。
これでいい。とりあえずは成功だ。デッドエンドの名前を聞いて、警戒でも緊張でもなく、笑いが起こっている。理想的とはいえないかもしれない。だが間違いなく、一歩前に進んだ。
少なくとも、俺はそう確信していた。
──こうして、俺たちは冒険者となった。
第八話 「冒険者の宿」
冒険者ギルドから出ると、周囲がやけに暗かった。
まだ空は明るいのに、町中だけが妙に暗い。それが、この町がクレーターの下にあるからだと気づいたのは、その数秒後だ。高い壁があるせいで、夕暮れ時から影ができているのだ。
すぐにでも真っ暗になるだろう。
「はやく宿を探しましょう」
と、提案すると、エリスは不思議そうな顔をした。
「別に町の外で野宿してもいいんじゃないの?」
「まあまあ、そう言わずに、町中でぐらいゆっくり休みたいじゃないですか」
「そう?」
ルイジェルドはどっちでもよさそうだ。
野宿時の夜の見張り番は、ルイジェルドに任せっきりになっていることも多い。彼は半分寝ながらも、近づいてくる相手に気がつけるのだ。夜中に何かの破裂音が聞こえたと思って起きたら、ルイジェルドが魔物と戦っている音でした、なんてのは心臓に悪い。
まあ、宿だ。腹も減った。
何か買うのもいいが、先日の干し肉がまだ残っている。ここは食費を抑えるためにも、それで我慢するか……とはいえ、お腹はペコちゃんだし、腰を落ち着けてガッツリと食いたい気分だ。
「ねえルーデウス! 見て!」
エリスの興奮した言葉。なんだい、ナニを見せてくれるんだいと思って顔を上げると、クレーターの内壁がボンヤリと光っていた。日が落ちるにつれて、光が強くなっていく。
「すごい! すごいわ! こんなの初めて見た!」
日が完全に落ちると、クレーターの内壁は、石と土でできた町中を明るく照らしだした。
まるでライトアップされた遊園地のようだ。
「へえ、確かにこれはすごいですね」
生前、深夜でも真っ暗にならない場所に住んでいた俺の感動は薄い。
だが幻想的な風景であることは認めざるをえない。しかし、なんで光っているのだろうか。
「あれは、魔照石だな」
「む、知っているのかラ○デン……!」
「ラ○デン? 誰だ……? 何代目かの剣神にそんな名前の奴がいたような……?」
当然ながらネタは通じない。この世界にはこういうネタが通じるヤツがいないと思うと、ちょっと寂しい。
「失礼。僕の知り合いに、そういう名前の何でも知ってる人がいたんですよ。物知りな人でね、ちょっと間違えました」
「そうか」
頭を撫でられた。まるで死んだ父親を懐かしがる子供をあやすような仕草だ。別にラ○デンが父親の名前ってわけじゃないですよ? 父親の名前はパウなんとかっていう人ですよ。父親としてはそれなりですけど、人としてはダメな部類の。
「それで、魔照石というのは?」
「魔石の一種だ」
「どういう効果なんですか?」
「昼の間は日の光を蓄え、暗くなるとああして光るんだ。もっとも、昼間の半分も光が続くわけではないがな」
ソーラー充電か。
アスラ王国では見なかったな。便利なんだからもっと使えばいいのに。
「夜に明かりになるなら、もっと出まわっていてもいいんじゃないんですか?」
「いや、あれはかなり希少な石だ」
「え? じゃあ、あそこにあるのは?」
町中を照らせるぐらいの量があるようだが。
「魔界大帝が存命の時に、集めさせたのだそうだ。見ろ」
と、ルイジェルドが指さす先には、光の中でぼんやりと浮かび上がる、半壊した城の姿。
「あの城を美しく見せるためだけにな」
「凄いことを考えるんですね」
魔界大帝さんの姿がほわんほわんと思い浮かぶ。ボンデージファッションに身を包んだエリスが、わたくしを美しくみせるためには光が必要なのよ! と叫んでいた。
「盗まれたりはしないんですか?」
「一応、禁止されているという話だが、詳しくは知らん」
まあ、ルイジェルドも町に入るのは初めてという話だしな。結構高い位置が光っているし、飛べたりしなければそう簡単には取れないか。
「当時は散々ワガママだと言われたそうだが、今ではこうして役に立っている」
「案外、人々のために集めたのかもしれませんよ」
「まさか。魔界大帝は自堕落で退廃的だと有名だ」
自堕落で退廃的か。生きているのなら、ぜひお会いしたいものだ。
きっとサキュバスみたいなエッチでビッチなお姉さんに違いない。
「事実は小説より奇なり、ですかね」
「それは人族独特の言い回しか?」
「そうですよ。スペルド族だって、本当は心優しい種族じゃないですか」
頭を撫でられた。この歳になって頭を撫でられるとか、どうなんだと思うが、考えてみてほしい。精神年齢四〇代中盤の男が、実年齢五六〇代中盤の男に撫でられている状況を。
よくわからないなら、〇を取ってみよう。
年齢四歳の男が、年齢五六歳の男に撫でられている状況。微笑ましいとは思わんかね?
「ねえ! お城に行ってみたい!」
エリスが暗闇に浮かび上がる漆黒の魔城(半壊)を指さして言うけど、俺は却下する。
「今日はダメ。先に宿に行きましょう」
「なんでよ、いいじゃない、少しぐらい!」
ぷくっと頬を膨らませるエリス。それを見ると、少しぐらいいいか、という気分になるが、それほど長く光り続けるわけではない、とルイジェルドは言っていた。
城にたどり着く頃に消えていたら面白くない。
「最近、ちょっと疲れ気味なんですよ。宿に行きましょう」
「え? 大丈夫なの?」
慣れない旅で疲れているのもあるが、ちょっとだけ身体が重い気がする。
実際には魔物との戦闘でも動けているから問題はないんだが、いつもより疲れが溜まるのが早い気がする。気苦労だろうか。
「大丈夫ですよ。ちょっとだけですから」
「そう……? じゃあ、我慢するわ」
我慢、か。昔のエリスからは出てこなかった単語だ。
エリスはちゃんと成長しているな~なんて思いつつ、宿へと移動した。
★ ★ ★
狼の足爪亭。
一二部屋。一泊・石銭五枚。
建物は老朽化しているが、冒険者の初心者向けという姿勢であり、良心的な値段。
石銭をさらに一枚支払えば、朝夜の食事が付く。
冒険者としてパーティを組んで二人以上で一部屋に泊まれば、食事代が無料となる。
初心者向けということで、ベッド数が多くても値段は一律。
入り口は酒場兼ロビーになっていて、席数は決して多くないがテーブル席とカウンター席が並んでいる。テーブルには初心者向けという言葉通り、三人の若い冒険者がいた。
若いといっても、年齢は今の俺より上。エリスと同じぐらい。全員が少年だ。
彼らは、俺たちを無遠慮に見てきた。
「どうする?」
ルイジェルドがここでも演技をするのか、という視線を向けつつ聞いてきた。
「やめておきましょう」
俺はちょっと考えて、首を振った。
「寝る所でも気を張りたくありません」
この宿に何泊することになるのかはわからないが、彼らはまだ子供だ。泊まる場所が一緒であるなら、否が応にもルイジェルドの人の良さを目の当たりにするだろう。
「パーティで三人。とりあえず、三日分」
「あいよ。食事はどうするんだ?」
愛想の悪い店員だ。
「食事もお願いします」
とりあえず三日分の料金を払っておく。食事代がタダになるのはいいな。
残り金額は鉄銭一枚、屑鉄銭三枚、石銭二枚で石銭換算で一三二枚。
「き、君も新人なのかい?」
宿屋の決まりなんかを店主に聞いていると、エリスが新人に声を掛けられていた。額に角があるやつだ。白髪頭で、まあ、美男子と言えなくもないかな。百歩譲ってな。
他二人も……まあ、美少年だろう。ちょっとゴツい感じがする偉丈夫に育ちそうな、腕四本の少年と、口が嘴になってて、頭に羽毛が生えている少年。
まあ。うん。美少年、と言えなくもない。タイプはそれぞれ違うが。
最初の奴が「ノーマル」とするなら、残り二人は「かくとう」と「ひこう」だろう。
「お、俺たちもそうなんだ。どうだい、一緒に食事でも」
ナンパかよ。ガキが粋がりやがって。でも、ちょっと声が震えている。
微笑ましいと言えなくもない。
「依頼を受ける時のコツとか、教えられるって思うしさ」
『…………ふん』
ぷいっと顔をそむけるエリス。
さっすがエリスさん! ナンパはガン無視に限りますよね!
まあ、言葉がわかんないからでしょうけど。
「なあ、ちょっとでいいんだよ。そっちの弟君も一緒に」
『……』
そろそろ助けに入ろうか、と思っていたら、エリスは、すっと視線を外して、彼らから離れようとした。知っているぞあの技は。エドナさん直伝の礼儀作法。
「相手にしたくない貴族の避け方・初歩編」だ!
どうする、角少年。紳士なら、ここは察して引いておくべきだ。
「無視するなよ」
角少年は紳士ではなかった。イラっとしたのか、エリスのフードの端を掴み、グッと引っ張った。
後ろに引っ張られる形となったエリスだが、つんのめったりしなかった。足腰がかなり鍛えられているからだ。
かといって、角少年も引きずられたりはしない。冒険者なんかやっているところを見ると、結構力自慢なのかもしれない。
両者の力は、その中間にダメージを与えた。
ビッ、と、安物のフードの端が、嫌な音を立てて破れる。
『……え?』
エリスがその音を聞いて、そして、破れた部分を見た。
フードの縫い目にはいった、小さな小さな裂傷を見た。
──ブチン。
俺は確かに聞いた。エリスの何かがキレた音を。
『何すんのよ!』
宿を揺らすほどの金切り声がゴングだった。
振り向き様に、ボレアスパンチ。
サウロスから学び、ギレーヌの訓練を経て完成されたターンパンチは、少年の顔面を正確に捉えた。少年の首は骨が折れるんじゃないかってぐらい、ぐりんと回った。キリモミしながら倒れ、後頭部を床にぶつけ、一発で気を失う。
素人の俺でも、相当な破壊力を持っているとわかるパンチだった。もしここに最凶死刑囚がいたのなら、「なんてパンチだ」と呟いたことだろう。強引なナンパの末路、いい気味だ。
彼もこれに反省したら、二度とエリスに声を掛けるなんて危険な真似はしないだろう。
教訓だ。さて、残り二人と喧嘩になるだろうから、今のうちに割って入るか。
『私を誰だと思っているのよ! 身の程をわきまえなさいよ!』
しかし、エリスは一撃では終わらなかった。
ボレアスキック。サウロスから学び、ギレーヌの訓練によって完成された喧嘩キックは、二人目のみぞおちを正確に捉えた。
「ぐぅぇえ……!」
四本腕の少年は悶絶しながら膝を落とし、そこに、膝蹴りで追い打ちが入った。
腕少年は顎を跳ね飛ばすように吹っ飛んだ。
「え? え? ええ?」
最後の一人、鳥少年は、まだ事態をうまく飲み込めていなかったが、それでも本能的に向かってくるエリスを迎撃しようと思ったのだろう、腰の剣に手をやる。
剣はやりすぎだろうと、俺は慌てて魔術を使って割って入ろうとする。
しかし、エリスの方が数倍はやりすぎだった。彼女は鳥の少年が剣を抜くより前に、少年の顎先に向けて的確に拳を放った。拳は鳥少年の顎先をかすめるようにヒット。鳥少年は白目のないはずの瞳で白目を剥いてぶっ倒れた。
一瞬で三人が無力化された。
エリスは、つかつかと最初の角少年の所に歩き、その頭をサッカーボールのように蹴り上げた。
少年は一発目で目を覚まし、しかし何もできず、ただ丸まって耐えた。
エリスはそんな少年を、何度も、何度も、執拗に蹴り上げる。
『これは、ルーデウスが、初めて、買ってくれた、服なんだからね!』
あらまあ! エリスさん! そんなに俺のことを!
あんな安物なのに、赤毛は目立つからって被せただけなのに……おじさん、キュンときちゃう!
エリスは少年を蹴り転がし、仰向けにして片足を掴み、恐ろしい形相で恐ろしいことを言った。
『一生後悔させてやるわ! 踏み潰してやる!』
ナニを? 何がナニかは怖くて聞けない。
目を覚ましたばかりの少年も、彼女が何を言っているのかわからないが、何をするのかわかったのだろう。助けてくれ、ごめんなさいと言って逃げようとする。
しかし、エリスには言葉は通じず、通じたとしても逃がすつもりもなかった。
エリスはそんな詰めの甘い女ではない。エリスは徹底的にやる。
あの少年の末路は、三年前、逃げきれなかった時の俺の末路だ。
『エリス、待って!』
ここで、俺はようやく止めに入ることができた。突然の出来事すぎて、どうにも割って入るのが遅れてしまった。
『抑えて! エリス、それ以上はいけない! ハウス!』
『なによ、ルーデウス! 邪魔をするの!』
後ろから抱きついて止める。手に胸が触れる。柔らかい感触だ。
けど、それを楽しむ暇はない。エリスは暴れ、今にも少年のを踏み潰しそうだ。
少年の何を? ナニが何かは怖くて言えない。
『縫えば、縫えばいいから! 俺が縫うから! だから許してあげて! さすがにそれはかわいそう!』
『なによ………ふん!』
俺が必死に言うと、エリスは怒り心頭といった表情のまま暴れるのをやめ、肩をいからせてルイジェルドの方に歩いていった。
ルイジェルドは酒場の椅子に座り、何か微笑ましいものを見る目で見物していた。
『ルイジェルドさんも! 次からは止めてください!』
『ん? 子供の喧嘩だろう?』
『子供の喧嘩を止めるのも保護者の仕事です!』
明らかに実力が違うじゃないですか。
★ ★ ★
「大丈夫ですか?」
「あ、ああ、だ、大丈夫……」
なんとなく仲間意識を感じつつ、俺は、倒れた少年たちにヒーリングを掛け、助け起こした。
「悪かったね。彼女、魔神語が喋れないんですよ」
「こ、怖かった……な、なんで怒ってたの?」
「しつこいのが嫌いなのと、フードが大事なものだから、かな?」
「そ、そっか……すまなかったと伝えてくれないか?」
エリスを見ると、フードを外し、その破れ目を睨んでギリギリと歯ぎしりしている。
もう、絶対に許さないって顔だ。あんな顔は久しぶりに見た。具体的に言うと、初対面の時以外には見たことがない。『!?』とか『ビキビキ』とかいう効果音がついてそうな顔だ。
「今話しかけたら、多分僕でも殴られます」
「そ、そっか。可愛いけど、怖いんだな」
最近はお淑やかになったと思ったが、猫を被っていたのだろうか。
成長したと思ってたのに、ちょっとショック。
「そうとも。可愛いんだ。だから、あんまり気安く話しかけないほうがいい」
「う、うん。そうだね」
「それと、もし今回のことで復讐しようとかも、考えないほうがいいですね。今回は不慮の事故だから止めたけど、次は命を落としますよ」
きちんと釘を刺しておく。
少年はしばらく目を丸くして鼻をさすったり、後頭部にこぶがないかを確認していたが、落ち着いたらしく、名前を名乗った。
「……オレはクルト。君は?」
「僕はルーデウス・グレイラット。さっきのはエリス」
名乗り合うと、遠巻きにしていた二人の少年も寄ってきた。クルトがヤンチャしたせいでとばっちりをくった二人だ。「バチロウ」と、腕四本のゴツイほう。「ガブリン」と、鳥っぽいほう。
二人はそう名乗ると、クルトの両脇に移動し、ポーズを取った。
「三人揃って、『トクラブ村愚連隊!』」
「…………」
ア○ナエクスクラメーションみたいなポーズを取る三人。
俺は素直にダサいと思った。愚連隊ってなんだよ。暴力団かよ。トクラブ村ってどこの田舎だよ。
「もうすぐDランクに上がりそうだし、そろそろ女の子の魔術師が欲しいなって話してたんだ」
「女の子の魔術師?」
そんなのがどこにいるんだ? ここにいる魔術師は俺だけだ。
別に魔術師らしい格好をしているわけではないし……ん? 魔術師らしい格好?
「もしかして、フードを被ったエリスを見て、魔術師だと思った?」
「うん。だって、フードをつけるのは魔術師だろう?」
「剣を持ってるでしょう?」
「え? あ、本当だ」
剣は目に入らなかったらしい。きっと、彼は自分の都合のいいことしか見えないタイプなのだ。
「君は魔術師だよね。治癒魔術が使えるなんてすごいよ」
「まあ、一応は」
「二人一緒にどうだい?」
愚連隊に俺が? 冗談じゃないよ。ていうか、エリスにあれだけやられて懲りてないのか?
「僕が入ると、あっちの人も一緒に入ることになりますよ」
ルイジェルドは何やらエリスに言い含めており、エリスはムッとした顔をしつつ素直に頷いていた。
「え? あの人もパーティなのかい?」
「そうとも。名前はルイジェルド」
「ルイジェルド……? パーティ名は?」
「『デッドエンド』」
その単語に、彼らは「はぁ?」という顔をした。なんてものを騙ってるんだ、と言わんばかりだ。
「そんな名前、大丈夫なのか?」
「本人の許可は取ってあります」
「なんだそりゃ」
冗談みたいな真実だ。
「ま、いいじゃないか。そういうわけだから、俺もエリスも君らと一緒にはいけないよ」
こいつらと組んで良いこともなさそうだしな。俺は冒険者ごっこをやりたいわけではないのだ。
「そっか、でも後悔するなよ。オレたちはこの町で有名になるから。後になってパーティに入れてくれ、ってのは無しな?」
有名って……。いや、でもそういうものか。町で冒険者デビュー。将来に希望を持つ若手。
さっきの冒険者ギルドでも、こういう若手は微笑ましい目で受け入れられるのだろう。
「はっ、エリス相手に何もできずに転がされて、よく言うよ」
「さ、さっきのは油断してたんだよ」
「お前それ、魔大陸の平原でも同じこと言えんの?」
「ぐっ……」
言い負かした。実に気分がいい。
さすが魔大陸平原のパクスコヨーテは説得力が違うぜ。
そんな会話の後、俺は『トクラブ村愚連隊』と別れた。
★ ★ ★
食事を終えて部屋に入る。毛皮のベッドが三つ並んだ部屋だ。
「ふぅ……」
俺は無言でベッドに腰掛けた。
疲れた。今日も疲れた。
体調がやや良くないのもあるが、人と会ったり、笑われたり、馬鹿にされたりするのは精神的に疲れるのだ。たとえそれが演技でも。
「……」
エリスは窓の外を見ていた。
そこには、徐々に暗くなっていく町の風景がある。
半壊した城は幻想的だと思うが、よく背景を気にしている余裕があるものだとも思う。
考えなければいけないことはたくさんあるってのに、全部俺に丸投げか。いい気なもんだ。
──いや、ネガティブな考えはよそう。彼女が考えてないのは、俺を信頼してくれているからだ。それが証拠に、ワガママもあまり言わないじゃないか。
(ワガママは言わないけど、喧嘩はするけどね)
寝転び、天井を見ながら考える。これからどうするか。
必要なものは、そう、まずは金だ。
この宿は三人分で石銭一五枚。最低でも、一日にそれ以上は稼がなければいけない。
だが、依頼を見たところ、Fランクの相場は石銭五枚前後。Eランクでも屑鉄銭一枚前後だ。
一人なら、Fランクの仕事を一日に一回以上やることで宿代を払い、ランクの上昇にしたがってもらえる金額が増えて金が貯まる。F・Eは基本的に町中の仕事だが、Dランク以上になってくれば採取の依頼も増える。F・Eランクで金を貯めつつ、装備を買ってDランクの仕事を受けていく──というシステムなのだろう。
よくできているが、俺たちは三人だ。
(一日に昼飯代・消耗品代も込みで考えて、石銭二〇枚。最低でも一日に一回依頼をこなせるとして、石銭一〇から一五。現在の手持ちを石銭で換算すると、一三二枚)
二週間持たない。あっという間になくなる。
俺たちは一日に二つか三つ以上の仕事をしなければ元が取れない。
手分けをすれば、一日に石銭二〇枚程度の仕事はできるだろうけど、ルイジェルドを一人にさせた結果、正体がバレるかもしれない。エリスは言葉が喋れないから、依頼をこなすのも大変だろう。短気なエリスのことだ。出先で喧嘩するかもしれない。そもそも、別々に仕事をすると、ルイジェルドの宣伝ができない。
ランクアップすれば、金の問題は解決だ。
戦闘系の依頼なら、ルイジェルドやエリスが得意とするところ。すぐに軌道に乗るだろう。とはいえ、討伐系は基本的にCランクから。二週間以内にDランクに上がれば、なんとかなるけど、それには一日一回の依頼をこなすだけでは無理だろう。
何回依頼をこなせばランクアップできるかは聞きそびれたが、少なくとも、能力があるから飛び級できるわけではないようだし、地道にこなしていかなければならないのだ。
また、俺の体調も本調子ではない。
大丈夫だとは思うが、俺やエリスが解毒で治らない類の病気になる可能性もある。
それに、他にもどんな時に金を使うかわからない。
ルイジェルド用の染料も定期的に買い足す必要もある。
服だって、着の身着のままというわけにはいかない。元々上等なものだから丈夫だし、魔術を使えば洗濯もすぐに済むけど、魔術による乾燥は服の生地が結構傷むし、今後破れるかもしれない。早めに着回せるようにしたい。
石鹸だって欲しい。俺もエリスも、最近はお湯を絞った布で身体を拭いているだけだ。
その他、生活用品はこれからもどんどん必要になっていくだろう。
どうにしろ金はいる。
そうだ、借金をするか? この町にだって、探せば金融業者ぐらいいるだろうし。
いや、借金はなるべくしたくない。少なくとも、返すアテがないうちは。
いっそ、『傲慢なる水竜王』を売るか?
いや、それは最後の手段だ。エリスが誕生日にくれたものを、そう簡単に手放せるか。
(まさか家計で悩むとはね……)
生前、金のことを口に出そうとした両親を床ドンで黙らせたことを思い出す。
胃が痛くなるような光景だ。二度と思い出したくない。また、数年前、学費を二人分出してくれと言った時のパウロの顔も思い出す。ちょっと、金のことを甘くみていた。
(反省するより、金を稼ごう)
どうすれば効率よく稼げるだろうか。
毎日依頼をこなすのが一番か。
いや、依頼をこなすより、平原に出て魔物でも狩ったほうがいいかもしれない。冒険者にこだわる必要はない。
でも、それだと『デッドエンド』の名前を広めることができない。『デッドエンド』を広めるためには、冒険者ランクは上げておいたほうがいい。それはきっと、今後のためにもなる。魔物の素材の買取も、ギルドを通したほうが高いしな。
でも、そんなことをしている暇はあるのか? ルイジェルドのことは置いといて、まずは金を貯めて、生活の基盤を作ってからにすべきじゃないのか?
(思考が堂々巡りだな……)
金を稼ぐ、ルイジェルドの評判を上げる。二つ同時にやらなきゃいけないのが辛いところだ。
(なにか……いい方法があればいいんだがな)
何も思いつかないまま、俺は静かに眠りに落ちた。
★ ★ ★
夢。白い場所だった何もない場所。
同時に、鈍重で卑屈な気持ちが湧き上がってくる。
またか、とため息をつく。
気づけば、目の前に卑猥な奴が立っていた。
今度はなんだよと、イライラしながら、モザイク野郎に問いかける。
なるべくなら、手短に終わらせてほしいものだ。
「今回もつれないね。ルイジェルドを頼ったお陰で、町までたどり着いただろう?」
確かにな。でも、ルイジェルドの性格を考えるにだ。もし俺たちが逃げても、陰ながら守ってくれただろうさ。
「随分と彼を信頼してるねえ。なのに、どうして僕は信用してくれないんだい?」
わかんねえのか? 神を名乗っているくせに?
「さて、そんなことより、次の助言だ」
はいはい、わかったよ。手短に終わらせてくれ。
モザイク野郎の声を聞くのも嫌なら、この感覚も嫌なのだ。ルーデウスが夢の記憶として薄れ、クソニートの感覚がよみがえるこの感覚は。どうせ最終的には聞かされることになるんだから、最初から聞いたほうがいい。
「卑屈だねえ」
どうせ、お前の手のひらの上で踊らされることになるんだろう?
「そんなことはないさ。どう動くも君次第」
御託はいいから、さっさと話を進めろよ。
「はいはい……。ルーデウスよ、ペット探しの依頼を受けなさい……。それであなたの不安は解消されるでしょう……」
でしょう……でしょう……でしょう……。
エコーを聞きながら、俺の意識は沈んでいった。
★ ★ ★
夜中に目覚める。
嫌な夢を見た。正直、あのお告げは勘弁してほしい。いいタイミングで出てきやがって。間違いなくあいつは邪神だな。人の心の弱い部分を突くのがうまい邪神だ。モッ○スだ。
「ふぅ……」
ため息を一つして、左を見る。
ルイジェルドは寝ている。ベッドではなく、なぜか部屋の隅で槍を抱えるように。
右を見ると──エリスは起きていた。
ベッドに腰掛け、膝を抱いて、すっかり暗くなった窓の外を眺めていた。
俺は静かに起き上がると、彼女の隣に座った。窓から外を見る。この世界も、月はひとつだ。
「眠れないんですか?」
「……うん」
エリスは窓の外を見ながら、こくりと頷いた。
「ねえ、ルーデウス」
「はい」
「私たち、帰れるのかな……?」
不安げな声。
「それは……」
俺は自分の不明を恥じた。
彼女は今まで通りだと思っていた。不安なんてないし、この状況を、冒険を、純粋に楽しんでいるのだと思っていた。
違うのだ。彼女も不安だったのだ。
それを俺に悟られないように振る舞っていたのだ。
ストレスも溜まっていたはずだ。
だから、あんな喧嘩をしたのだ。気づいてやれなかった。なんてことだ。
「帰れますよ」
そっと肩を抱くと、こつんと頭が肩に載せられた。エリスはここ数日、満足に風呂に入っていない。ふわりと香る匂いも、以前に嗅いだのとは全然違うものだ。
けれど、嫌じゃなかった。嫌じゃないので、俺のキカンボウが暴れそうになる。
我慢我慢……帰るまでは鈍感系だ。
あの時とは状況が違う。今は、我慢しなければならない理由がある。とってつけたような理由だが、不安に思っている彼女に付け入るような、卑怯なマネもしたくない。
「ねえ、ルーデウス。任せても、大丈夫よね?」
「安心してください。なんとしても、帰りましょう」
ああ、しおらしい時のお嬢様は可愛い。サウロス爺さんの気持ちもわかるよ。
こりゃ甘やかしたくなる。てか、爺さんたちはどうなったんだろうか。あの光はフィットア領を覆い尽くしていた。てことは──。
──いや、今は、考えないようにしよう。自分のことで精一杯だ。
「頑張りましょう。エリスも寝てください。明日から忙しいですよ」
俺はエリスの頭にポンと手を載せるように撫でてから自分のベッドへと戻ると、ルイジェルドと目が合った。聞かれていたか。
ちょっと恥ずかしいが、彼はすぐに目を閉じた。
見て見ぬふりをしてくれたらしい。ああ、いい人だなあ。パウロだったらきっと、有無をいわさずからかってきただろうに。
やっぱり、この人のことを後回しにしちゃいけない。
しかし、パウロか。心配してくれているだろうか。命に別状はないという手紙を送らないとな。届くかどうかはわからないけど……。
(ペット探しか……)
人神が何を考えているかわからないが、今回だけは、何も考えずに従ってやろうじゃないか。
不安の渦巻く中、冒険者生活の一日目は静かに終わりを告げた。
第九話 「人の命と初仕事」
リカリス町二番地・キリブ長屋。
そこは一階建ての建物で、横に長い建物に四つの入り口が付いている。
住んでいる者たちは、決して裕福とは言えないが、スラムほど貧困にあえいでいるわけではない。魔大陸の一般層である。
そんな場所に、三つの影があった。小さな影が二つ、大きな影が一つ。
彼らは傍若無人にのしのしと道を歩き、そして誰にはばかることなく長屋の一室の前に立った。
「こんにちはー。冒険者ギルドの方から来ましたー」
幼い少年が高い声を上げて、一室をノックした。
不気味だ。このへんの冒険者に、こんな丁寧な口調で話す奴はいない。
冒険者とは、基本的に粗野な連中なのだ。
しかし、その優しげな声で、部屋の住人はあっさりと騙されてしまったらしい。
扉ががちゃりと音を立てて開き、出てきたのは、齢七歳ぐらい、トカゲのような長い尻尾と、先が二つに割れた舌が特徴的なホウガ族だ。
三人を見て目を丸くする彼女に、少年はにこやかに話しかけた。
「どうもこんにちは。こちら、メイセルさんのお宅でよろしかったですか?」
「え、あ、あの?」
「あ、申し遅れました。わたくし、『デッドエンド』のルーデウスと申しますです、はい」
「で、でっどえんど?」
少女──メイセルもデッドエンドの名前は知っていた。
デッドエンド。四〇〇年前、ラプラス戦役において数多の武功を上げ、味方をも蹂躙した悪魔、スペルド族。その中でも最も凶暴凶悪とされる個体。
会えば死ぬと言われており、遭遇した者は、誰しも「必死で逃げなければ死んでいた」と口にする、魔大陸における恐怖の代名詞である。
どんな魔物でも打ち倒せると豪語する屈強な冒険者でも、デッドエンドの名前を聞けば震え上がる。デッドエンドの特徴はメイセルも知っている。こんなチビではない。
「本日は、ペットの捜索ということで、ご依頼を受けさせていただきました。その詳細をお聞きしに伺いましたが、お時間の方はよろしいでしょうか?」
デッドエンド。恐ろしい名前だ。後ろの二人はちょっと不気味だが、この馬鹿丁寧に喋る少年を見ていると、怖さは薄れた。そして、彼らは冒険者で、自分の依頼を受けてくれたらしい。
「うちのミーを見つけてください」
「はい。名前は、ミーちゃんというのですね。可愛らしい名前ですねえ」
「わたしがつけたんです」
「ほう、それは素晴らしいネーミングセンスです」
そんな言葉で、メイセルは気を良くした。
「それで、ミーちゃんというのは、どういう方なのですか?」
メイセルはペットの外見、三日前から行方不明なこと、帰ってこないこと、いつもは呼んだらすぐ来るのに来ないこと、餌を食べてないからお腹が空いているはずということなどを話してくれた。
歳相応の要領を得ない話し方だった。
普通の大人なら、その話し方にウンザリして途中で帰ってしまったかもしれない。けれども、少年はニコニコしながら聞いてくれた。一生懸命喋る少女の言葉に一つ一つ頷きながら。
「わかりました。それでは探して参ります。このデッドエンドにお任せください!」
少年はグッと親指を立てた。なんだろうか。見れば、後ろの二人も立てていた。メイセルはよくわからなかったが、真似して立ててみた。
それを確認すると、少年はいい顔で踵を返した。脇のフードを被った女の人も付いていく。一番大きな男の人は、しゃがみこんで少女の頭に手を載せた。
「必ず見つけてみせる。安心して待っていてくれ」
顔を縦断する傷。額の宝石。そして、まだら模様の青い髪。怖い顔だ。
だが、載せられた手には温かみがあった。少女はこくりと頷いた。
「お、お願いします」
「ああ、任せておけ」
去っていく三人。その三人の背中を見ながら、メイセルは大きな人に聞いた。
「あの、お名前はなんていうんですか?」
「ルイジェルドだ」
彼は短くそう言うと、すぐに背中を向けて歩き出した。メイセルは頬を赤く染めて、ルイジェルドの名を口の中で呟いた。
★ ルーデウス視点 ★
依頼主との邂逅で、俺は確かな手応えを掴んでいた。
依頼主との邂逅で、俺は確かな手応えを掴んでいた。
生前、よくウチに来た訪問販売員の真似をしてみたが、うまくいったようだ。
冒険者には笑われてもいいが、依頼主には良い人だと思われなければいけない。依頼人に対しては慇懃な態度で話をするのだ。
「さすがだな。あんな演技もできるのか」
ほっとしていると、ルイジェルドが話しかけてきた。
「いえいえ、ルイジェルドさんこそ最後のアレ、よかったですよ」
「最後のアレ? 何のことだ?」
「あの子の頭に手を載せて、何か言ってたじゃないですか」
あれは完全にアドリブだった。
何を言うかとヒヤヒヤしたが、俺が思った以上にいい成果を出していた。
「ああ、あれか、何がいいんだ?」
何がもなにも、あの少女は顔を真っ赤に染め、上気した顔でルイジェルドを見ていた。
俺があんな目を向けられたら、理性の一つも飛んでしまっただろう。
しかし、そんなことを真顔で言えば、子供好きのルイジェルドのことだ、むっとした顔で俺の言動を諌めるだろう。
「ヘヘッ、あの女、完全に兄貴にイカれちまってましたよ、ぐへへへ」
だから、冗談めかした口調で、ルイジェルドの太ももを肘でツンツンする。
ルイジェルドは苦笑し、そんなことはないだろう、と自信なさそうに言った。
「ウェヘヘヘ、兄貴が本気になりゃあ、あんな小娘一人……あイタ!」
後ろからベシッと頭を叩かれた。振り向くと、エリスが口を尖らせていた。
「変な笑い方しないでよ! 演技だったんじゃないの?」
どうやら、俺が下衆っぽい仕草をしていたのが気に入らないらしい。
エリスは下衆が嫌いだ。あの誘拐事件の時からだ。
城塞都市ロアの町中でも、盗賊っぽい格好の人間を見かける度に顔をしかめていたものだ。
冗談のつもりだが、エリスには気に食わなかったらしい。
「ごめんなさい」
「もう! グレイラット家が品のない笑いをしちゃいけないんだから」
その言葉に、俺はあやうく吹き出すところだった。
聞きました奥さん。エリスが品ですって。扉を蹴破らなければ気がすまなかったお嬢様が、なんともお淑やかに成長したもので。
でも、そういうことを言うなら、昨日みたいに突然キレて喧嘩するのもやめてほしいものです。
いや、サウロスを見る限り、突然キレて相手を殴るぐらいはまだ上品のうちに入るのか。いや、そんな馬鹿な。
……アスラ貴族における品位の線引きがわからない。
「ところでペットの方は、見つかりますかね」
わからないので、話を変える。
聞いた話によると、ペットは猫っぽい。
色は黒で、子供の頃からずっと一緒に育ってきたらしい。
大きさは結構なものだ。少女が両手を広げて大きさを表現していた。それをそのまま信じるなら、柴犬ぐらいの大きさだろうか。猫にしては結構大きい。
「もちろんだ。見つけると約束したからな」
ルイジェルドはっきりと断言した。
頼もしいことで、彼はそのまま先頭を歩き出した。足取りに迷いはないが、俺はちょっと不安だ。
いくらルイジェルドが生体レーダーを備えているといっても、町中から動物を一匹見つけ出すのは容易ではない。
「策はあるんですか?」
「動物の動きは単純だ。見ろ」
ルイジェルドの指さす先には、かすかながらも、肉球が土を踏みしめた跡があった。
すげえ。全然気づかなかった。
「これを追っていけば、たどり着けると?」
「いや、これは別の奴だろう。聞いていた話より足が小さい」
確かにこのサイズでは、普通の猫がいいところだろう。少女の表現は誇張だと思うがね。
「ふむ」
「探している獲物の縄張りに、別の奴が入りこみつつあるのだ」
「そうなんですか?」
「間違いない。匂いが薄れつつあるからな」
匂い? もしかして、縄張り用のマーキングを、この男は嗅ぎ分けているのだろうか。
「こっちだ」
ルイジェルドは、一人で何やら納得しつつ、路地の奥へと入っていく。
俺は無言で追従する。
よくわからないが、名探偵の後ろを付いていく助手は、こんな気分なんだろうか。圧倒的な追跡術で犯人を追い詰め、恐怖による誘導尋問と、魔界式バリツで自白を強要。どんな事件もスピード解決。名探偵ルイジェルド、ここに見参ってか。
「見つけた、恐らくコイツだろう」
ルイジェルドは、路地の一角を指さして、そう言った。何を見つけて、何が恐らくなのか、俺にはさっぱりわからない。少なくとも、肉球の足跡なんかは残っていない。
「こっちだ」
ルイジェルドは路地をスルスルと進んだ。
足取りに迷いはない。どんどん狭い路地へと入っていく。
まるで猫が通りそうな細い路地だ。
彼が何を考えて動いているのかわからないが、恐らく、順調に足取りを追っているのだろう。
「見ろ。ここで争った跡があるな」
袋小路で、ルイジェルドの足が止まった。見ろと言われても、俺にはそんな跡は見えない。
別に血の跡がついているわけでもないし、地面がどうにかなっているわけでもない。
「こっちだ」
ルイジェルドが先行する。俺とエリスは付いていくだけ。なんて楽な仕事なんだろうか。
路地を抜けて、通りを横切り、また路地へ。路地を抜けて、裏路地へ、そしてまた路地へ。
迷路のような場所をズンズンと進んでいく。ある路地を抜けると、周囲の風景が変わった。
先ほどよりも幾分か寂れたものへと変わっている。建物は崩れ、外壁は禿げ、粗末なものへ。
剣呑な目つきで俺たちを睨んでくる奴。路上で寝転ぶ奴。汚い身なりの子供も多い。
スラムだ。次第に、という感じではなかった。
抜け道から迷い込んだ感じだ。一瞬にして、俺の中の警戒レベルが上がった。
「エリス。いつでも剣が抜けるようにしておいてください」
「……どうして?」
「念のためですよ。あと、すれ違う相手と背後に気をつけて」
「う、うん、わかった……!」
エリスにそう言っておく。
ルイジェルドもいるし滅多なことはないと思うけど、他人任せでミスをしたら目も当てられない。
自分の身は自分で守らなければいけない。
そう思って、俺は懐の金の入った袋をぎゅっと握り締める。大した金が入っているわけじゃないが、スられるわけにもいかない。
「……チッ」
時折、荒くれ者がルイジェルドに睨みをくれるが、ルイジェルドがわりと本気で睨み返すと、すぐに舌打ちをして目を逸らした。
こういった町だと、むしろ冒険者より、強者に対する警戒は上なのかもしれない。
「本当にこんなところにいるんですか?」
「さてな」
ルイジェルドの返事は、なんとも頼りないものだった。迷いなく歩いていたのではなかったのだろうか。
いや、言葉少ななだけで、ルイジェルドはきっと何かを見つけているに違いない。
そう信じよう。
しばらく歩いていくと、ルイジェルドはある建物の前で足を止めた。
「ここだ」
視線の先には下へと下る階段があり、その先には扉。
ビジュアル系の人たちが集まる地下酒場って感じだ。
もちろん、ロックでポップなミュージックも聞こえてこないし、スキンヘッドのサングラスの門番が出入り客を見張っているわけでもない。
代わりに漂うのは、獣臭さ。ペットショップの近くを通った時のような、なんとも言えない獣の臭いがする。
それとあれだ。犯罪の匂いもする。
「中には何人います?」
「人は一人もいない。生き物は多いがな」
「じゃあ入りましょう」
誰もいないなら、特に迷うことはなかった。俺は階段を下りて、扉に手を掛けた。
鍵が掛かっているが、土魔術で解錠。
一応、周囲を確認し、誰にも見られていないことを確認して、さっと中に入り、念のため内側から鍵を掛け直す。まるで泥棒みたいだな。
中は暗い廊下が続いていた。
「エリスは背後を警戒してください」
「わかったわ」
誰か入ってくればルイジェルドが気づくだろうが、一応。
俺たちはルイジェルドを先頭に、奥へと入っていく。
廊下の奥には扉が一つ。その扉の奥には、小部屋があり、さらに扉が一つ。扉を二つ抜けると、けたたましい動物の鳴き声が耳朶を叩いた。
最奥の部屋には、ケージが並んでいた。
所狭しと並べてあるケージ。その中には、大量の動物が閉じ込められていた。
犬や猫、見たこともない動物まで。学校の教室の大きさの部屋に、ぎっしりと。
「……なによ、これ」
エリスが慄いた声を上げる。
俺はというと、なんだ、この部屋はと、疑問に思うと同時に、ここに動物が集められているなら、目当てのペットもいるかもしれない、とも思っていた。
「ルイジェルドさん。目的の猫はいますか?」
「いる。あいつだ」
即答だった。指さす先を見ると……黒豹みたいな奴が入っていた。
でかい。マジででかい。少女が両手を拡げたサイズの二倍ぐらいはある。
「ほ、ほんとにコイツなんですか?」
「間違いない、首輪を見てみろ」
黒豹の首輪には、確かに「ミーちゃん」という単語が書いてあった。
「確かにミーちゃんですね」
……とりあえず、依頼は達成だ。この黒豹をケージから出し、少女の所に持っていけば終わる。
だが、さて。他の動物はどうしたものか。
見たところ、首輪やら足輪やらを付けている個体も多い。中には、『ミーちゃん』のように、名前が書いてあるのもいる。どうみても、ペットだ。
部屋の隅にはロープや轡のようなものが乱雑に落ちている。
ロープで連想できる言葉と言えば『捕まえる』だ。
他人の高級ペットを攫ってきて、他に高く売りつける。そんな商売もありそうだ。
この世界に、そのへんの法律があるとは思えないが。良いことではないのは確かだろう。
言ってみりゃ、泥棒だからな。
「むっ」
ルイジェルドが入り口の方へと顔を向けた。エリスも気づいた。
「誰か入ってきたわ」
俺は動物の声がうるさくてわからない。
ルイジェルドはともかく、エリスはよくわかるものだ。
さて、どうしようか。入り口からここまで、時間はあまりない。逃げるか。いや、逃げ道などない。一本道だ。
「とりあえず、捕まえましょう」
話し合いという選択肢は捨てておいた。
俺たちは不法侵入者だ。ここは犯罪の現場だと思うが、正当な理由がある可能性も捨て切れない。
とりあえず拘束してみて、いい奴なら話し合いによって口止めをして、悪い奴なら殴り合いによって口止めをしよう。
★ ★ ★
数分後。
俺は部屋の隅に転がる三人の男女を見下ろしていた。男二人に女一人。
俺は全員に土魔術で手枷をつけ、水をぶっかけて目を覚まさせた。男の一人がギャーギャーと喚いていたので、近くに落ちていた布で猿轡をかませた。
残り二人は静かなものだった。だが一応、全員に猿轡だ。平等ってやつだな。
「……ふむ」
唐突に湧き上がった疑問。
さて、どうしてこうなった? 俺たちはEランクの仕事を受けていたはずだ。
迷子の猫探し。
ルイジェルドが任せろというので任せていたら、いつのまにかスラムに迷い込んでいた。
そのスラムにある建物に入ったら動物がたくさん捕まえられていて、気づいたら、なぜか人を拘束していた。捕まえるべきは人ではないというのにだ。
こうなったのも、みんな人神のせいだろう。あいつは、こうなることを見越していたのだ。
面倒なことになった。ペット探しなんて受けなければよかった。
──ひとまず、拘束した三人を観察してみよう。
男A
オレンジ色の肌をしている。目に白い部分がなくて、複眼。ちょっと気持ち悪い。ギャーギャーと蝉のようにうるさかった男だ。野卑な感じというか、喧嘩がうまそうなイメージがある。
ロキシー辞典で見た気がしたが、どうにも種族名が思い出せない。
唾液が毒性を持っているので、キスする時はどうするんだろうと疑問に思ったのは覚えている。
男B
トカゲっぽい顔だ。門番とはやや形や模様が違う。トカゲの顔は、どうにも表情とかがわかりにくい。でも目から溢れる知性の色は、俺を警戒させた。
女A
これも複眼、蜂のような顔で、なんとなく怯えているのがわかる。
やはり気持ち悪いが、体つきがエロいので差し引きゼロ。
さて、彼らをこうして見下ろしていても、何も始まらない。
お話を……いや、ボカすまい。『尋問』をするなら、誰がいいだろうか。気持ちよく情報を吐いてくれそうなのは、誰だろうか。男か、女か。
女は怯えている。ちょっと脅してやれば、案外何もかもを喋ってくれるかもしれない。
いや、女ってのは嘘をつくからな。自分が助かるために、支離滅裂で前後の繋がりのない嘘をつく。世の中全ての女がそうではないと思うが、少なくとも、姉貴はそういう奴だった。俺はそんな嘘を聞くと、憤りが先に出て、話の真実がわからなくなるタイプだ。
だから、女は除外しよう。
では、男のどちらか。男Aはどうだろうか。三人の中で一番ガッシリとした体で、顔には傷があり、喧嘩が一番得意ですって感じの彼は興奮している。あまり頭はよくないだろう。さっきから「なんだてめえら」とか「この手枷をはずしやがれ」とか、そんなことを言っている。
男Bはどうだろうか。顔色はよくわからないが、彼は俺たちをよく観察している。決して馬鹿ではあるまい。馬鹿でないのなら、こういう状況になった時の嘘も考えているだろう。
俺は男Aを選んだ。
興奮して冷静さを失っている彼ならば、ちょっと挑発したり、誘導したりすれば、必要なことは全部喋ってくれるような気がした。
ま、ダメでもあと二人残っているからな。
「いくつか聞きたいことがあります」
「……」
男Aの猿轡を外すと、彼は俺を睨みつけてきた──が、何も言わない。
「おとなしく喋ってくれれば手荒なげぶぅはぁ!?」
いきなり蹴り飛ばされた。しゃがんでいた俺は踏ん張ることもできず、そのまま後ろに吹っ飛ぶ。
ごろんと一回転。後頭部が壁に打ちつけられて、目の前に星が散った。
痛い。くそう。しかし、本当に頭の悪い奴だな。こんな状況で捕まえている相手を蹴るとは。
相手を怒らせたらどうなるか、とか考えないんだろうか。
「え!? ちょ、ちょっと! やめなさいよ!」
エリスの叫び。俺は跳ね起きた。男Aがエリスに何かをしたのかと思った。
俺が考えている間に手枷を外し、ルイジェルドの目を盗んでエリスを人質に……。
「なっ……!?」
俺の目に飛び込んできたのは、男Aの喉に突き刺さった槍だった。
ルイジェルドが、男Aを突き刺したのだ。エリスは、それを見て目を丸くしている。
槍が横に捻るように引き抜かれ、血が飛んだ。
ピッと壁に赤い斑点がついた。男Aは反動でぐるりと回転し、うつ伏せになる。その喉からは、だくだくと血が流れている。背中にじわりと血が滲んでいく。地面に広がる、赤い水溜まり。むわりと香る、血の臭い。
男はビクンと一瞬だけ体を痙攣させて、動かなくなった。
死んだ。男は一言も喋ることなく、死んだ。ルイジェルドに、殺された。
「な、なん……なんで殺したんですか?」
俺の声は震えていた。人死にを見るのは初めてじゃない。ギレーヌだって、俺を助けるために人殺しをした。けど、あれとは何かが違った。
なぜか身体が震えている。なぜか心は怯えている。
(なんだ、俺は何に怯えているんだ?)
人が死んだことか?
馬鹿な。この世界では、誰かが死ぬなんて、日常茶飯事だ。そんなことはわかっていたはずだ。
頭でわかっていても、実際に見るのは初めてだから違う?
なら、なぜギレーヌが誘拐犯を殺した時にはなんでもなかったんだ?
「子供を蹴ったからだ」
ルイジェルドは淡々と言った。当然だと言わんばかりの口調だった。
ああ、そうか。わかった。俺は人が死んだことに怯えているんじゃない。
俺が蹴られたという、それだけのことで、息をするように、相手を殺した、ルイジェルドに、怯えているのだ。
ロキシーも言っていたじゃないか。
『人族と魔族では常識が違う部分も多いので、どんな言葉がキッカケで爆発するかわかりません』
そうだ。もし、ルイジェルドの矛先が俺に向いたら、どうする?
この男は強い。ギレーヌか、それ以上に強い。
俺の魔術で勝てるのか? 対抗はできるはずだ。近接戦闘を得意とする相手へのシミュレーションは何度も繰り返した。パウロ、ギレーヌ、エリス。俺の周囲にいた人物は、誰もが近接戦闘のスペシャリストだった。ルイジェルドは、その中でも、恐らく一番強い。
だから、自信を持って「勝てる」と言えるわけではない。けれど、殺すつもりでやれば、いくらでも手はある。けど、もし、エリスに向いたら? 俺は守りきることができるのか?
無理だ。
「こ、殺しちゃダメだ!」
「なぜだ? 悪人だぞ?」
俺が慌てて言うと、ルイジェルドは目を丸くしていた。心底意味がわからないって顔だ。
「それは……」
どう説明すればいい、俺はルイジェルドにどうしてほしい?
そもそも、なんで殺しちゃいけないんだ?
一般的な道徳心は、俺にはない。ニートだった頃は「人を殺しちゃいけない」なんて言葉を鼻で笑っていた。親が死んだ時もそうだった。これから大変だとは思いつつも、知るか馬鹿、そんなことよりオ○ニーだ、と水晶小僧していた。
そんな俺が言ったところで、上辺だけの軽い言葉になるだろう。
「殺しちゃダメな理由は、あるんです」
俺は、動揺している。自覚しろ。俺は今、テンパッている。
自覚した上で考えろ。まず、なぜ俺は震えている? 怖いからだ。今まで優しい男だと思っていたルイジェルドが、あっさり人を殺した。スペルド族は誤解されているだけの心穏やかな種族だと思いこんでいたが、違った。
種族がどうかはわからないが、少なくともルイジェルドは違う。ラプラス戦役の時代から、ずっと敵を殺し続けてきたのだ。今回も、そんなケースの一種だろう。そして、俺やエリスにその矛先が向く可能性が、まったくない、とは言い切れない。
俺はルイジェルドが認めるような、清廉潔白な人間ではない。いつか、どこかで、彼の逆鱗に触れてしまう日が来るだろう。それで彼が怒るのはいい。考え方が違うのだから、意見を違えるのも仕方がない。喧嘩の一つもするだろう。
けど、殺し合いまでするつもりはない。どんな状況でも、命のやり取りにだけは発展しないように、今、この段階で、きっちりとルイジェルドに言っておかなければならないのではないだろうか。
「いいですか、ルイジェルドさん、よく聞いてください」
しかし、言葉はまだ見つかっていない。どう言う?
なんていえば説明できる? 俺たちだけは殺さないでくださいと懇願するのか?
馬鹿な。
俺は先日、彼に一緒に戦う戦士だと言ったばかりだ。彼の庇護下にいるのではなく、仲間内にいるのだ。懇願はダメだ。
頭ごなしにダメだと言うのもよくない。ルイジェルド自身が納得しなければ、意味がない。
考えろ。俺は何のためにルイジェルドと一緒にいる? スペルド族の悪名をなんとかするためだ。ルイジェルドが人を殺せば、スペルド族の印象は悪くなる。これは間違いないはずだ。だから、他の冒険者と喧嘩しないようにと言い含めたのだ。スペルド族の印象は最悪だ。
どれだけ良いことをして認識を改めても、目の前でスペルド族が殺人を犯せば、きっと今までのことは水に流され、ルイジェルドの印象は地に落ちる。
だから殺しちゃいけない。スペルド族が怖いという認識を、他の人々が持ってはいけないのだ。
「ルイジェルドさんが人を殺すと、スペルド族の悪名が広まります」
「…………それは、悪人でもか?」
「誰を殺したかではありません。誰が殺したかです」
考えながら、言葉を選びながら、慎重に言う。
「わからんな」
「スペルド族が人を殺すというのは、他とは意味が違います。魔物に殺されるようなものです」
ルイジェルドは、ちょっとだけムッとした顔をした。種族の悪口に聞こえたのかもしれない。
「…………わからんな。どうしてそうなる」
「スペルド族は恐ろしい種族と思われています。少しでも気に食わなければ、すぐに他者を殺す悪魔だと」
言いすぎかと思ったが、世間の認識はそんなものだ。
それを変えようとしているのだ。
「スペルド族は世間に言われているような悪魔ではないと、そう口で言うのは簡単です。行動で示せば、大多数の人が認識を改めてくれるでしょう」
「……」
「けど人を殺せば、全ては台無しです。やっぱりスペルド族は悪魔だったと思われるでしょう」
「馬鹿な」
「心当たりはありませんか? 今まで、人助けをしてきて、仲良くなったあとに手のひらを返されたことは?」
「………………ある」
言いながら、俺の中でもまとまってきた。
「しかし、人を一切殺さなければ……」
「どうなる?」
「スペルド族にも、理性があると思われます」
本当にそうなのか? この世界で、人を殺さなかったぐらいで、理性があると思われるのか?
いや、今は考えるな。俺は間違っちゃいないはずだ。ルイジェルドは人を殺しすぎた。スペルド族は、人を殺して当然の種族だと思われている。殺さなくなれば、認識を改められるはず。
辻褄は合っているはずだ。
「殺さないでください。スペルド族のことを思うなら、誰も」
殺していい時、悪い時。普通はそれを判断しなければいけない。けれど、この世界の判断基準は俺にはわからず、ルイジェルドの判断基準は恐らく過激。
両極端でラインが見極めにくい。
なら、いっそのこと、全部禁止したほうが手っ取り早い。
「誰も見ていないなら、いいんじゃないのか?」
ルイジェルドの言葉に、俺は頭を抱えそうになった。誰も見ていないなら犯罪を犯してもいいなんて、どこの小学生だ。こいつ、本当に五〇〇年も生きてきたのか?
「見ていないと思っても、人の目はあるんですよ?」
「周囲にはいないぞ?」
ああ、くそ、そうか。額の目のおかげか。
「見ている人は、いますよ」
「どこにだ?」
ここにだ。
「僕とエリスが、見てるじゃないですか」
「む……」
「誰も殺さないでください。僕らだって、ルイジェルドさんを怖がりたくはないんです」
「……わかった」
最後は結局、泣き落としのような形になった。自分の言葉に自信なんてない。
だが、ルイジェルドは頷いてくれた。
「よろしくお願いします」
俺は、ルイジェルドに頭を下げた。見れば、手が震えていた。
落ち着け。こんなのは普通だ。はい、深呼吸。
「すぅ……はぁ…………すぅ……はぁ……」
なかなか落ち着けない。動悸が収まらない。エリスはどうしている? 怯えているんじゃないのか、見てみると、エリスは平然としていた。
いきなりでびっくりしたけどゴミは死んで当然ね、って顔をしている。いや、さすがにそんな酷いことを考えてはいないと思うけど、腕を組んで、足を開いて、顎を上げてのいつものポーズだ。
内心はどうであれ、いつも通りであろうとしてくれている。
だというのに、俺が動揺していてどうするよ。
手の震えは止まっていた。
「じゃあ、尋問を続けましょうか」
血なまぐさい匂いの充満した部屋で、俺は無理矢理に笑みを作った。
第十話 「初仕事終了」
さて、尋問の時間だ。
男と女、どちらを先に尋問しようか。
虫っぽい目をした女の方は、見るからに怯えている。もう必死にンーンー唸りながら、俺たちから逃げようとしている。この怯える様が実にそそる……のは、さておいて。
猿轡を外すと、どうにも支離滅裂な言葉を叫びだしそうだ。
尋問をするなら、もう少し落ち着いてからの方がいいかもしれない。
トカゲの男の方。
ちょっと表情は窺い知れない。トカゲの顔の変化なんて俺にはわからないからな。心なしか青ざめているようにも見えるが、周囲をよく観察しているようにも見える。
俺の顔色、ルイジェルドの顔色、エリスの顔色。
きっと、彼の頭の中では、この場をどうやって生き残るかで一杯だろう。
こうなってくると、ルイジェルドが一人殺してしまったのが悔やまれる。短絡的な奴が喋ってくれるのが一番楽だった。
いっそ、二人共猿轡を外して、両方から聞いたほうがいいだろうか。片方を別室に移動させて、別々に尋問をする。そして、後で情報をすり合わせる。
よし、それで行こう。
「エリス、そっちの女の方を見張っていてください」
「わかった」
エリスは力強く頷いた。
俺は男の方を連れて、廊下へと移動した。一人では持てないので、ルイジェルドに手伝ってもらった。廊下に出て、声が届かないぐらいの位置まで移動して、噛み付かれないように、丁寧に猿轡を外す。
「質問に答えてください」
「こ、答える、答えるから、殺さないでくれ」
「いいですよ。喋ってくださるなら、助けてあげます」
「ひ、ひい!」
安心させるようににっこり笑ったつもりだが、怯えられた。
意外と冷静な奴だと思ったが、そうでもないのか。
「この建物にいる動物たちは、なに?」
「ひ、拾ってきたんだ」
「へぇ~それはすごいや! で……どこから拾ってきたんですか?」
「いや、それは……」
チラチラと目線が動き、俺とルイジェルドの顔色を見ている。
まだ嘘でもつこうというのか。
「そ、そのへんで……」
嘘にもなっていなかった。顔は賢そうに見えるが、それほど賢くないのかもしれない。
「なるほど! この町では動物がたくさん落ちてますからね! …………お前、俺が子供だからってバカにしてるだろ?」
ちょっと凄んで見せる。
「そ、そんなことはない」
ダメだな。どうもこの体では、脅そうとしてもマヌケな感じになってしまうらしい。
十歳だしな。仕方ない。ちょっと脅すか。
「爆発」
パチンと指を一発鳴らし、男の目の前に小さな爆発を起こした。
「うわちっ!」
男の鼻先が焦げる。
「な、なん、何やったんだ!?」
と、聞いてくるが、無視。
「お前さ、もうちょっと頭を捻って答えろよ。死にたくないんだろ?」
死んでしまった男のことを思い出したのか、男がぶるりと身を震わせた。
そして俺は思い出す。先ほどの会話は魔神語だったな、と。散々こいつらに聞こえる言語で、スペルド族だのなんだのと言ってしまった。
まあ、いいか。知ってしまったのなら、利用するだけだ。
「なあ。わかるだろ。そっちの男は、髪を青く染めてるけど、正真正銘、本物の『デッドエンド』だ。俺だって、見た目通りの年齢じゃねえ」
「ほ、本物……?」
「俺らはお前らと同類なんだよ。正直に話してみろ。もしかしたら、手伝ってやれるかもしれない」
という方向で話を進めてみることにする。
「でも……ヒッ!」
男はチラリとルイジェルドを見て、すぐに目線を逸らした。
睨まれたのかもしれない。
「教えろよ。ここで、何を、してたんだ?」
「ぺ、ペットを攫ってきて……」
「ほう、攫ってきて?」
「捜索願いの出たペットを、探し出したフリをして返すんだ」
「なるほどなあ」
これはきっと本当だろう。確証はないが、やっていることは辻褄が合っていて、納得できる。
今回はいたいけな少女の捜索願いだったが、中には「金持ちマダムのクリスチーヌちゃんを探せ」とかいう依頼もあるのだろう。
ギルドの報酬はランクごとで上限下限が決まっているようだが、それとは別に、依頼主が特別報酬を出すこともあるかもしれない。
運が良ければ、ペット探しでも儲けられるのだろう。
「で、捜索願いが出なかったらどうしてるんだ?」
「しばらくしたら、普通に放してるよ……」
「へえ、ペットショップに売ったほうが得なんじゃねえの?」
「ハッ! んなことしたら、足がつくだろうが」
男がふてぶてしく鼻で笑った瞬間、ルイジェルドが槍の石突きで地面をドンと突いた。
男がビクンと震える。
さすがルイジェルドだ。調子に乗った瞬間、立場を思い出させるお前の脅しのタイミング、イエスだね!
「随分と細々とやってるんだな」
「そ、そうだよ」
「俺だったら、捕まえた動物は売るけどな。バラバラにして、肉屋に。それなら足もつかないだろ?」
魔物の肉を美味しそうに食べるこの世界なら、家畜じゃなくても売れそうだし。
あ、トカゲ男がなんか「信じられない」って顔をしている。
なんでや! 大王陸亀の肉も、ペットの亀の肉も変わらんやろ!
「ルーデウス、お前、こいつらもそうやって肉屋に売るつもりなのか?」
振り返ると、ルイジェルドが恐ろしいことを言ってきた。
なるほど、このトカゲ男も、そんな想像をしたわけか。
「それもいいかもしれませんねぇ……」
ちょっと脅してみると、トカゲ男の顔がひきつった。
ああ、この表情はわかる。懐かしい。生前ではよくそういう顔をされたもんだ。
「ルーデウス……」
ルイジェルドさん、後ろから睨むのはやめてください。
視線を感じます。冗談です。やりませんから。
「ま、俺らは猫を一匹探しに来ただけだ。別に正義の味方ってわけじゃない。だから、何も見なかったことにして、立ち去ってもいい」
「ほ、本当か?」
「でも、お前ら、ルイジェルドが本物のスペルド族だって知ってしまったからなぁ。どうしようかなぁ?」
「だ、誰にも言わねえよ! それに町中にデッドエンドがいるなんて、言っても信じねえだろ?」
「いいや、信じるさ。悪い噂ってのは、広まるもんだ」
都合の悪い噂は、特にな。そう思っておいて損はない。
「俺としては、お前ら全員を殺して埋めるのが一番てっとり早いんだがね?」
「か、勘弁してくれよ……。なんだってするから、命だけは……!」
なんだってする、頂きました。脅すのはこれぐらいでいいか。
しかし、さて、どうしたもんか。彼らはペット誘拐犯、つまり悪者である。とはいえ、聞いた感じバックのいない小悪党という感じだ。放っておいても、大したことはないだろう。
が、ルイジェルドが人を殺す場面を見られてしまった。これにより、ルイジェルド人気者作戦の障害になる可能性が芽生えた。後顧の憂いは絶っておきたい。
しかし、殺すのはダメだ。ルイジェルドに殺すなと言ったばかりだしな。
町の衛兵に突き出すという案はどうだろうか。
いや、彼らは所詮、ペット誘拐犯だ。警察に突き出しても、大した罪には問われないかもしれない。中途半端な罰金とかだと、逆恨みされる可能性もある。今は殊勝な態度だが、喉元過ぎれば熱さを忘れるものだ。
できれば、目の届く所にいてもらって、定期的に脅していきたい。
少なくとも、こいつらが安全だとわかるまでは。
しかし、それにもリスクが伴う。脅し続けることで、逆恨みが、ただの恨みに変わる可能性もある。ただでさえ、こっちは向こうを一人殺しているのだ。今は恐怖の材料だが、いずれ恨みの材料になるに違いない。
殺すのも、警察に突き出すのも、どちらもダメ。
なら、取り込むか。手元において、金稼ぎとランクアップを手伝ってもらう。町中での情報収集や、各種小間使い。なんなら、ペット誘拐のビジネスを引き継ぐのもいい。
だが、これはルイジェルドがあまりいい顔をしないだろう。
ルイジェルドの中では、彼らは殺してもいいレベルの悪党だし、一緒に行動したくはないだろう。
ふーむ。
それぞれのリスクリターンを整理してみるか。
一.殺害する
リスク:ルイジェルドが混乱する+問題が起きたら何でも殺して終了という悪い癖が付きそう
リターン:後顧の憂いは絶てる+彼らの金銭を奪える
二.衛兵に突き出す
リスク:逆恨みされる可能性が残る
リターン:もしかすると、ちょっとした名声が得られるかもしれない
三.放置する
リスク:逆恨みされる可能性が残る
リターン:特になし
四.取り込む
リスク:仲間がいい顔をしない+他人に悪事の片棒を担いでいると思われる可能性
リターン:彼らを身近で監視できる+人手が増える
一は、今後のためにも、あまりよくない気がする。
別に俺は正義の味方というわけではないが、なんでもかんでも殺しちゃえ、なんてのは思考停止だ。いずれ、大きなしっぺ返しを食らう気がする。
二と三は、ローリスクローリターンだ。
逆恨みされても、ルイジェルドがいれば見つけ出すのは容易だが、結局は殺すことになってしまう。二度手間だ。
やはり四か。
ルイジェルドの心象は悪くなるだろうが、俺たちには早急に金が欲しいという、切実な問題もある。
そう、金だ。俺たちは今、金が欲しいのだ。金を稼ぐのに、人手があるのはいい。
彼らのペット誘拐ビジネスを手伝うのもいいし、彼らにパーティに入ってもらえば、Fランクの仕事も手分けしてできる。ランクアップは重要だ。せめてCランク以上の依頼を受けられれば、俺たちも安定してくるだろう。
…………ん?
「そういや、依頼でペットを渡しているってことは、お前ら冒険者なのか?」
「そ、そうだ」
なんと、彼らは冒険者だったらしい。
「ランクは?」
「D、Dだ」
しかも、ランクは俺たちよりも上らしい。
「DなのにEの仕事を受けてるのか?」
「ああ、もうCには上がれるが、Eランクのペット探しで安定して稼げるんだ」
Cランクに上がると、Eランクの仕事は受けられないので、Dランクにとどまったまま、Eランクで安定して稼ぐ、という奴もいるのか。
彼らの場合は詐欺も同然だが。
俺たちなら、さっさとCに上がって、Bランクの討伐依頼を受けていくだろうが、戦闘系が苦手という冒険者もいるのだろう。ふむ、いっそのこと、彼らにCランクの仕事を受けてもらって、それを手伝うのもいいな。報酬は山分け、金の問題は解決できる。
いや、それだと、俺たちのギルドランクが上がらないな。
「あ……」
その時、俺の脳裏に電流走る。
そうだ。いいことを思いついた。
「お前ら……さっきの奴なしで、この仕事、続けられるのか?」
「い、いや、もうこんな仕事はやめてまっとうに……」
「正直に答えろよ」
「続けられる! あいつは、俺たちが二人でやってるところを見つけて、分前が欲しいってんで脅してきたんだ!」
マジか。そりゃ運が良かったな……。
三分の一を正解だったってことだ。これも人神の思し召しかね。
「よし、じゃあ俺たちと手を組もう」
そう言うと、ルイジェルドが背後で叫んだ。
「手を組むだと!? 何を言っている!」
「ルイジェルドさん、ちょっと黙っていてくれませんか?」
「なに!」
「悪いようにはしませんから」
「……」
振り返る。ルイジェルドは、やはり良くない顔をしている。いい思いつきだと思ったが、やはりやめておくか?
だが、この案は完璧だ。金は貯まる、ランクも上がる、ルイジェルドの評判も上がる。
全てを満たした完璧な策……のはずだ。
俺はトカゲ男に向き直った。
「さっき、なんでもするって言ったよな」
「い、命を助けてくれるなら、か、金だって払うよ」
「金はいらない。その代わり、ランクを一つ上げてくれ」
「は?」
俺は説明する。
「いいか、俺たちは見ての通り、全員が戦闘系だ。ペット探しも苦手じゃないが、できれば討伐系の方が効率がいい」
「だ、だろうな……と、いうより、なんでこんな仕事を?」
「事情があって冒険者になったばかりなんだよ」
「は、はあ……」
「まあそんなことは置いとけ」
話が逸れそうだったので戻す。
「でだ。俺たちは戦闘系の依頼を受けたいが、ランクが低くて受けられない。逆に、お前たちは戦闘系の依頼は受けられない。ここまではいいな?」
「え、ええ」
「そこで、仕事を交換するんだ」
仕事を取り替えると聞いて、トカゲが首をちょっとかしげた。
「ど、どういうことでしょうか」
「お前たちはCかBランクの戦闘系の仕事を受ける。俺たちはランクを上げるために、ペット探し系の依頼を受ける。そして、俺たちはお前たちの仕事を、お前たちは俺たちの仕事を行う」
「ちょ、ちょっとまってください。受けた仕事を別のパーティが報告したって……」
「バカ! 報告はそれぞれ受けたほうでするんだよ」
「あ」
男Bもようやく気づいたようだ。
俺たち:Eランクの仕事を受け、Bランクの仕事を行う。Eランクを報告し、報酬をもらう。
ヤツラ:Bランクの仕事を受け、Eランクの仕事を行う。Bランクを報告し、報酬をもらう。
こういう形だ。最後に、報酬を交換するのだ。
ギルド規約的に問題もあるかもしれないが、低ランクの依頼を高ランクが手伝うこともあると聞く。それの逆をするだけだ。不正はしていない。
「俺たちは金もランクも欲しい。お前らは安定した生活が欲しい。ギブアンドテイクってヤツだ。なんだったら、Bランク依頼の報酬のうち、いくらかをお前らの分け前としてやってもいい」
「び、Bランク依頼の分け前……」
トカゲ男が、ゴクリと喉を鳴らした。
Bランクの報酬は、高い。
アメとムチ。叩いてばかりでは裏切られる。こいつらにも利益を与えるのだ。
俺たちと組めばいい思いをできると思わせなければ。
「だが、一つ条件がある」
「じょ、条件?」
「ああ、『デッドエンド』の名前を広めるんだ」
「広めるって……知らないヤツはいないだろ?」
だろうね。
「良い者風にだよ。俺たちの素行の良さを、嘘でもなんでもいいから宣伝しろ。なんだったら、お前らがFランクの仕事とかやって、『デッドエンド』だって名乗ってもいい」
「な、なんでそんなことを……?」
なんで、か。ルイジェルドの過去を長々と話せば、信じるだろうか。
いや、無理だろうな。こいつは、今さっき目の前でルイジェルドに仲間を殺されたばかりだ。
あまりいい仲間ではなかったようだが、こいつの中には、スペルド族が恐ろしいという感情が刻まれているはずだ。
「知らないほうが良いこともあるんだぜ?」
「……わ、わかったよ」
適当に言っただけだが、わかってくれたらしい。
「オレたちは、あんたらの名前を、売り込めばいいんだな?」
「そういうことだ、もちろん都合が悪い時には名乗るなよ? うちには地の底まで追いかけていくヤツがいるからな」
男はルイジェルドの方を見て、こくこくと頷いた。
「せいぜい俺たちのランクが上がるまで。仲良くやろうや」
「ああ、ああ」
「明日の朝、冒険者ギルドに集合な。サボるなよ」
俺は彼の背中をポンと叩いた。
一応、女の方も尋問して、話の裏を取った。
彼らはペット探しの専門家で、昔からそういう仕事を生業にしてきたらしい。
ある時、明らかに迷子なペットを保護したところ、もしかすると、先に捕まえておけば手間が省けるんじゃないか、と考えた。
それがエスカレートして、ペット誘拐という方向になったのだという。
最初は二人で細々とやっていたが、ある日、ペットを捕まえているところを男Aに見つかる。
男Aは用心棒をすると言って無理矢理パーティに入り、そのままリーダー面して、事業を拡大させたらしい。用心棒代と称して女を抱き、分け前も多く取っていたそうだ。
だから、あいつを殺したことは、あまり恨んでいないらしい。少なくとも、女の方は。
本当に、運がよかった。
ちなみに、トカゲ男は名前をジャリル。ムシ女の方は名前をヴェスケルというらしい。
俺は彼らと簡単な打ち合わせを終え、手錠を外してやった。
★ ★ ★
猫を連れて建物から出ると、ルイジェルドが睨んできた。
「おい、なんだあれは!」
「なんだって、なんですか?」
ルイジェルドに胸ぐらを掴まれた。足が浮く。
「とぼけるな! あいつらは悪党だぞ! それと手を組むだと!?」
ルイジェルドが本気で怒っていた。
マジで怖い顔だ。その顔で、こいつが先ほど、人を殺したばかりだと思い出す。
「た、確かに悪党ですけど、小悪党です。彼らは、そんな悪いことはしていません」
「悪事の大小ではない、悪党は悪党だ!」
こうなることはわかっていたはずだ。なのに、なぜか、足が震える。
声が震える。目の端に涙が溜まる。
「だ、だって、この策は、一石二鳥で……」
「……だからなんだというのだ!」
ルイジェルドは納得がいっていないらしい。
まずい。恐怖で頭が働かない。ガチガチを鳴る歯の音だけが俺の頭を支配する。
「悪党は、裏切るぞ!」
ルイジェルドが睨み、叫んでくる。
裏切り。その可能性は考慮に入れてある。
だが、奴らにも益のある話だ。結構脅したし、しばらくは大丈夫なはずだ。
「あんな奴らと手を組むなど、何を考えている!」
言われて、迷う。
そうだ。別に、手なんて組まなくてもいいのだ。
もっと時間を掛けていけばいいのだ。金が足りなくなれば平原に行って魔物を狩り、少しずつ依頼を受けて、じっくりランクを上げていく。
それでもいいのだ。別に、あんな奴らを使わなくても、なんとかなるのだ。
ちょっと遠回りになるだけ。それだけだ。
やっぱり、やめるか? 今すぐとって返してあいつらぶっ殺すか?
血の海でレッツ海水浴か?
迷う。俺は正しいのか?
「ルイジェルド!」
迷いを中断したのは、大音声だった。
耳朶を叩く音と共にドンとルイジェルドの体が揺れた。
「ルーデウスから手を離しなさいよ!」
エリスがルイジェルドの尻に蹴りを入れていた。何度も、何度も。
「何が不満なのよ!」
エリスの大音声がビリビリと鼓膜を震わせる。
何事かと周囲の人々が目を向けてくる。
「悪党と組むのは好かん」
「好きじゃないってだけで文句を言うの!? 全部、私とあんたのためにやってくれてることなのよ!」
ルイジェルドが目を見開いた。俺の体がストンと、地面に降りる。
すると、エリスも蹴るのをやめたが、大音声は鳴り止まない。
「大体、動物を攫ったぐらいなんだっていうのよ!」
「そうじゃない、子供を蹴るような奴は」
「蹴るぐらい、私だってするわよ!」
「……だが、悪は悪だ」
「あんただって昔は悪いことしたんじゃないの!?」
ルイジェルドが絶句した。
エリスさん。味方をしてくれるのは嬉しいんですが、あんまりそういう核心的な部分をえぐるのはよくないですよ?
「ルーデウスは凄いんだから! 任せておけば全部うまくいくんだから! だから黙って従いなさいよ!」
「……」
「ちょっと嫌なことがあったからって、文句言わないでよ!」
「いや」
「文句言うぐらいなら帰りなさいよ! 私とルーデウスだけでやっていけるんだから!」
エリスの必死な顔に、ルイジェルドは明らかにたじろいでいた。
「……わかった。すまん」
結局、ルイジェルドは俺に謝った。
エリスの気迫に押し切られた感じだ。
決して納得してはいないだろう。
「い、いえ、いいんです……」
それにしても、随分とハードルが上がった気がする。
迷っているなんて言えない空気だ。あいつらと組むのは軽率だったかもしれない。
けど、こうなっては、意見は変えられない。不安だらけだが、もう、やるしかない。
最初に名案だと思った自分を信じてやるしかない。
自分ほど信じられないものはないんだが……。
★ ★ ★
猫を送り届けると、依頼主のメイセルには大層喜ばれた。
彼女は猫を見た瞬間に駆け寄り、ぎゅっと抱きしめて涙を流した。
よほど大切にしていたのだろう。猫もおとなしくしている。猫といっても黒豹だが。
「ありがとう! あのね! はい、これ!」
と、ルイジェルドに手渡したのは、鉄か何かでできたカードだ。表面には、依頼ナンバーのようなものと『完了』の文字が書かれていた。
「これは?」
「冒険者なのに知らないの!?」
少女に、信じられない、という顔をされた。
お、教えてやることを許可してやってもいいんだからね。
「よ、よろしければ教えてください」
「あのね、これを冒険者ギルドに持っていくと、お金を交換してくれるんだよ。最初はかんりょーってなってないの! でもね、何もないところに指を載せて、かんりょーって言えば、そうなるの!」
意訳「カードに指を載せて完了と唱えると、カードが完了状態になる」
なるほど。盗難対策か。いや、でも例えば俺とかがやれば完了になるんでねえの?
カードだけ盗んで、完了にして金をもらう……。
いや、すぐバレるか。対策もしてあるだろう。
「でも、最初から完了ってなってたような?」
普通は、依頼を完了すると同時に、カードを完了状態にするのではないだろうか。
「うん! ルイジェルドならきっと何とかしてくれるから。先に完了にしといたの!」
あらやだ。この子可愛い。信じる少女は美しい!
ルイジェルドは少女の頭を撫でた。
「そうか……信じてくれたのだな。ありがとう」
「ううん! 悪魔さんにもいい人がいるってわかったから!」
悪魔と聞いて、ルイジェルドの顔が一瞬凍りついたように思えた。
気持ちはわかるけど、そんなもんだよ、あなたの今の認識は。
「それではお嬢さん、『デッドエンド』のルイジェルドを、ぜひ、お忘れなく」
「うん! またいなくなったらお願いね!」
少女の言葉に、俺はちょっとだけ胸が痛くなった。
★ ★ ★
冒険者ギルドに戻る頃、時刻はすっかり夕暮れだった。毎回これなら、すぐに破産だ。
「なんだ、おい! あいつら戻ってきたぜ!」
「おいおい、迷子のペットちゃんは見つけられたのかぁ!?」
建物に入ると、馬の頭をした奴が煽ってきた。ミノタウロスっぽいけど頭は馬。とても特徴的なので覚えていた。
てか、こいつずっとギルド内にいたのか?
「あれ? 今朝の馬面の人……。今日はお仕事はおやすみですか?」
この人、ちょっと苦手なんだよなあ。昔、俺をイジメてた奴に感じが似てて。
なんていうか、今からこいつイジメるから皆もノってねー、みたいな。
「な、なんだ? いきなり丁寧な話し方しやがって、気味がわるいな……」
おっとしまった、演技を忘れていた。ごまかそう。
「アドバイスをくれた先輩に敬意を払うのは当然じゃないですか」
「お、おう、そうか?」
馬面は照れていた。こいつ、チョロいな。
「おかげで、依頼も無事達成できましたよ」
「なに?」
完了と書かれたカードをピラピラと見せると、馬面は素直に感心してみせた。
「すげえな、この町じゃ、ペットってなかなか見つからねえんだぜ?」
そりゃそうだろう。行方不明になる理由が人の手によるものなんだからな。
「ま、『デッドエンド』のルイジェルドなら、軽いですよ」
「マジかよ……偽者のくせにやるじゃねえか」
「ホンモノだっつってんだろ!」
最後に演技をして、カウンターへと向かった。職員に完了カードと三人分の冒険者カードを差し出すと、しばらくして冒険者カードと、安っぽい百円玉のような硬貨が一枚返ってきた。
戻ってくると、ルイジェルドに馬面が話しかけていた。
「よー、どうやって見つけたんだ? 参考までに教えてくれよ」
「狩りの追跡術を使っただけだ」
「狩り! お前の部族ってなんてところだっけ?」
「……スペルド族だ」
「なんてな。わかってるって。そのペンダントを見りゃあな」
馬面の男の目は、ルイジェルドの胸元、ロキシーのペンダントへと注がれていた。
「おれぁノコパラ。Cランクだ」
「ルイジェルドだ。Fランクだな」
「Fなのは知ってるっつの! ま、わからないことがあったらなんでも聞けよ。先輩としてなんでも教えてやるからよ! ガハハハ!」
ルイジェルドと馬面は、楽しそうに会話をしている。あの嫌われ者のルイジェルドが人と喋っているというのはいいことだが、余計なことを喋ったり、突然キレて襲いかかったりしないか心配だ。特に、子供関係のことは触れないでやってほしい。
心配と言えば、隣に座るエリスも心配だ。彼女にもたまに話しかけてくる奴がいるようだが、言葉がわからないので返事をしない。
「ねえ、あんた、その剣いいわね。どこで手に入れたの?」
『…………』
「ちょっと! なんとか言いなさいよ」
一人の女戦士が、彼女の無視にムッとしたのが見て取れた。
「どうしました?」
慌てて間に入ると女戦士は「ケッ、なんでもないよ」と言って立ち去った。
代わりに、ノコパラが話しかけてきた。
「ボウズか、ちゃんと報酬は受け取れたのか?」
「ええ、屑鉄銭一枚。僕らの初めての稼ぎです」
「ハハッ、さすがにやっすいなあ」
「小さな少女のなけなしのお小遣いをそんな風に言っちゃいけませんよ」
「安いのは安いだろうが」
「金額はね」
あの幼い少女が猫を探すために貯金箱を割った。そんな光景を思い浮かべてみれば、屑鉄銭一枚という金額が安くないことはわかるだろう。
「あんたにはこの価値はわかりませんよ。あっち行ってください、シッシッ」
「んだよ、ツレねーなー。ま、頑張れよー」
ノコパラは手を振りながら、ギルドをうろつき始めた。こいつは何の仕事をしてるんだろう……。
ともあれ、こうして俺たちは初めての依頼を終えた。
第十一話 「順調な滑り出し」
翌日。冒険者ギルドに顔を出すと、トカゲ男が声を掛けてきた。
「あ、どうも。ランクアップは済ませておきました」
誰だこいつと一瞬思ったが、隣に虫っぽい目をした女が立っていて、ようやく昨日のペット誘拐犯だと気づいた。
確か、ジャリルとヴェスケルだったか。どうにも、顔の区別がつきにくい。トカゲ顔はこの町に結構多いし、昨日は何の変哲もない布の服を着ていたが、今は冒険者っぽい皮の鎧を着ているのもあるだろう。
どちらも何の変哲もない普通の服装なわけだが、受ける印象はガラリと変わった。
「ああ、ジャリルさん。ご苦労様です」
「な、なんだ、その喋り方、気持ち悪いな……」
「敬語です。いけませんか?」
「い、いや」
ひと睨みすると、ジャリルは視線を逸らした。
「ヴェスケルさんも、今日からよろしくお願いします」
「あ……はい」
ヴェスケルは、相変わらずルイジェルドに怯えていた。ルイジェルドは、相変わらず彼らを睨んでいる。ま、仕方あるまい。
「じゃあ、中に入りましょうか」
「あ、ああ」
ジャリルは不安そうにしつつも、俺の言葉に頷いた。
冒険者ギルドに入ると、目ざとく俺たちを見つけた馬面が寄ってきた。
「よう!」
「…………うっす」
こいつ、今日もギルドにいるのか……。ほんと、何の仕事をしているんだろう。
「おっと、今日は『ピーハンター』と一緒なのか」
「よ、よう、ノコパラ。久しぶりだな」
どうやら、馬面とトカゲ頭は知り合いらしい。
「おう久しぶり。聞いたぜジャリル。ランクをCに上げたんだってな。大丈夫かぁ? Cランクじゃペット探しはできねえぞ?」
ノコパラはそこまで言ってから、俺たちと、ジャリルを見比べる。そしてヒヒンといなないた。
「なるほどな。どおりでペット探しがはええと思ったぜ。昨日の依頼、『ピーハンター』に手伝ってもらったんだろ?」
ピーハンターはジャリルたちのパーティ名らしい。なるほど、丁度いい。
「そうなんですよ! 昨日、ペットを探していたら知り合いまして! ノウハウを教えてくれるっていうんです!」
そんな嘘を適当にぶちあげる、
「ハッハー、臆病者のジャリルもついに弟子を持ったか! しかも偽のスペルド族、ぷくく……!」
いい具合に勘違いしてくれた。チョロいな。馬面はひとしきり笑った後、ジャリルの後ろを見た。
「そういや、ロウマンの姿が見えねえな。どうしたんだ?」
「あ、ああ……ロウマンは……死んじまった」
「そっか。そりゃ残念だったな」
ロウマンというのは、昨日ルイジェルドが殺した人の名前だろう。
そいつの死を聞いても、ノコパラはあっさりとしたものだった。
冒険者の中では、人が死ぬのはそれほど大した事件ではないのかもしれない。気にしていたのは俺だけなんだろうか。そういえば、ジャリルとヴェスケルも、ロウマンとやらを殺したことに関しては、別段気にしていない感じだった。
「でも、ロウマンが死んだのに、なんでランク上げたんだ? おまえらのパーティだと、あいつが一番強かっただろ?」
「そ、それは」
ジャリルが俺をチラ見したのを見て、ノコパラはヒヒーンと、いやハハーンと頷いた。
「あーあー。わかった。言わなくてもいい。そうだなー。弟子の前なら、ちょっとでもでかい顔してえよな!」
ノコパラは一人で勝手に納得すると、ジャリルの背中をぽんぽんと叩いて、ギルド内へと戻っていった。ジャリルはほっと一息。
しかし、なんなんだろうなアイツ。いっつも絡んできやがって。もしかして、俺のこと好きなのか。いや、あいつの目はどちらかというとルイジェルドを見ている。つまりホモ……なわけないか。
「さて、依頼を見てみましょうか」
ギルドに入ると、俺たちに奇異の目線を向けてくるヤツもいる。
今のところは無視だ。一応、弟子っぽく振る舞ったほうがいいかと思い、あれこれと聞きながら、ジャリルと共にD~Bにかけての依頼を見ていく。
「採取と収集というのはどう違うんですか?」
「え? あ、ああ。採取は植物が相手で、収集というのは魔物相手が多いかな……」
ジャリル先輩の曖昧な答え。でも確かに、そんな感じだ。
生物相手なら収集、そうでないなら採取……ね。
「あ、そうだルイジェルドさん」
「なんだ?」
「申し訳ありませんが、しばらくは金を貯めながらランクを上げようと思います」
「……なぜ俺に言う?」
「例の件が後回しになるからです」
ジャリルとヴェスケルには名前を売れと言い含んであるが、あまり期待はしていない。
慇懃な態度で依頼を受けさせるという案も思いついたが、基本的に奴らの行動についてはノータッチで行くつもりだ。
ノータッチなら、彼らが何をしても知らぬ存ぜぬで通せる。もし仮に奴らの犯罪行為が見つかったとして、もし仮に奴らがそれをルイジェルドにやらせられたと主張しても、冒険者ランクは彼らのほうが圧倒的に上だし、ルイジェルドはすでに偽者だと知れ渡っている。奴らが笑われるだけだ。
「なるほど、わかった」
ルイジェルドの了承を得てから、俺はジャリルと相談しつつ、いくつかの依頼を受けた。
★ ★ ★
門番に挨拶をして、町の外へと出ていく。
この町の周辺では、パクスコヨーテ、アシッドウルフ、大王陸亀、巨岩石亀あたりが、狙い目だそうだ。
パクスコヨーテは毛皮、アシッドウルフは牙と尻尾。大王陸亀は肉で、巨岩石亀からは魔石が取れる。
とりあえず、大王陸亀は今回は無視。肉は重いしな。
一番の狙いは巨岩石亀だ。魔石は小さくてもそこそこの値段で買い取ってもらえる。大きさに対する値段の効率がいいのだ──が、巨岩石亀の数は少なく、人里に近い所にもいない。
結果として群れていて一回の戦闘で数を稼ぎやすい、パクスコヨーテが中心となるというわけで、今回、俺が受けた依頼もパクスコヨーテの毛皮収集だ。
もっとも、一回で数匹分を稼げるというだけだ。索敵と剥ぎ取りの時間を考えれば、アシッドウルフも大差はないので、アシッドウルフも見かけたら狩っておくつもりだ。
こっちは依頼を受けてはいないが、収集は依頼を受けるより先に現物を集めてもいい。
依頼が受けられてしまったのなら、買取カウンターに持っていくだけだ。
パクスコヨーテの群れは、多くても精々一〇匹。
索敵と剥ぎ取りの時間を考えると、一日に狩れる数はそう多くはないと、最初は思っていた。
最初のパクスコヨーテの一群を倒し、その毛皮を剥ぎ取ると、ルイジェルドは死体を一ヶ所に集めだした。何をしているんだと疑問に思っていたが、
「風の魔術で、血の匂いを飛ばせるか?」
という言葉で納得いった。血の匂いでおびき寄せるわけだ。言われるがまま、風魔術で風向きをあちこちへと変える。
「巨岩石亀は狩れんが、周囲のパクスコヨーテが集まってくるぞ」
言う通りになった。
その日、俺たちは一〇〇匹以上のパクスコヨーテを狩った。この周辺のパクスコヨーテは狩り尽くしたかもしれないと思えるほどだ。
しかし、大変だった。
寄ってくるパクスコヨーテ、それらを狩り続けるルイジェルドとエリス。
そして、ひたすら死体から皮を剥ぎ取り続ける俺。
重労働だ。三〇匹を超えたあたりから、俺の腕は鉛のように重くなった。肩は痛くなり、血の匂いで吐きそうになった。倒せば宝石に変身するようになれば楽なのにと思いながらも、何とか頑張ったが、七〇匹ぐらいで限界がきた。
エリスと交代。
パクスコヨーテを魔術で殺す作業は、剥ぎ取りよりずっと楽だった。爆散させたり、毛皮に必要以上の傷を付けないように、少しずつ魔術の威力を調整しながら、一匹ずつ丁寧に殺していく。
やはり俺はこういう頭脳労働の方がいいと思っていた矢先、三〇匹ぐらいでエリスが音を上げた。
やはり、彼女は肩の凝る作業は苦手らしい。次はルイジェルドが剥ぎ取りか、と思ったが、すでに十分すぎるほどの毛皮が手に入っていた。一度では運びきれないので、往復して運ぶことにする。
「待て。その前に、死体は焼いておけ」
と、運ぶ前に、ルイジェルドはそう言った。
「焼く? 食べるんですか?」
「いや、パクスコヨーテは不味い。焼いて埋めるだけでいい」
死体を放置しておくと、別の魔物が食って増える。焼くだけでも、他の魔物が食ってしまうし、死体をそのまま地中深くに埋めるとゾンビコヨーテとして復活するらしい。
それらを阻止するために焼いて埋めるという手順を踏む必要があるのだとか。
毛皮だけを綺麗に剥ぎ取る→あえてゾンビコヨーテを作る→ギルドで討伐依頼が出る→討伐。
という黄金連携を思いついたが、ルイジェルドに止められた。わざと魔物を増やすような行為は禁忌であるとされているらしい。そういうローカルルールはどこかに書いておいてほしいものだ。
「でも、旅の途中ではそんなことしていませんでしたよね?」
「数匹程度なら問題ない」
ということらしい。どれぐらいがボーダーになるかはわからないが、この量の死体は疫病の元とかにもなるからな。特に断る理由もない。俺は死体をキッチリ消し炭にしておいた。
全てを運び終えた頃には、日が落ち始めていた。
今日の狩りはこれで終了だ。よく働いた。はやく宿に帰って休みたい。
だが、あの延々と続く剥ぎ取り作業を明日もやるのか。明日あたりはゆっくり休みたいところだが……。
「今日は一杯儲かったわね! 明日もこの調子でいくわよ!」
エリスは元気一杯だ。そんなエリスの手前、弱音を吐くわけにもいかない。
★ ★ ★
三日後。『デッドエンド』は早くもEランクに上がった。
「お疲れ様です」
ジャリルにねぎらいの声を掛けつつ、本日狩ってきた分の金銭の一割を彼らに渡す。
「あ、ありがとうよ」
一割。決して多くはない金額だと思う。こんな金額で彼らは暮らしていけているのだろうかと聞いてみると、彼は冒険者とは別に、この町で仕事を持っているらしい。
「どんな仕事を?」
「ペット屋だ」
なるほど、売りつけたペットを攫うわけか。まさに悪徳商人だな。
「あんまり悪いことはするなよ」
「わかっているよ」
そもそも、彼の営むペットショップというのは、町中にいる野良の動物を捕まえ、多少の訓練を施してペット化する仕事らしい。彼の種族、ルゴニア族は獣を調教するのが得意な種族で、その調教術は、それはもう古来より伝統として受け継がれており、そこらの野良犬から、果ては誇り高き獣族の女戦士まで、どんな相手でも屈服させることができるのだとか。
いやはや、まったくしょうがない種族だと思う。
もし、エリスとルイジェルドがその場にいなければ、俺も黙ってはいないところだった。
ぜひともご教授ください、と頭を擦りつけて弟子入りしただろう。
それはさておき、ペット屋というのは、害獣駆除を兼ね備えた素晴らしい仕事だそうだ。
「そんな素晴らしい仕事をしてるのに、なんでペットを攫っちゃうんですか……」
「最初は保護してただけなんだ。けど、魔が差してな」
魔が差して、味をしめて、ああなったというわけか。
「しかし、ペットショップと冒険者の両立は大変でしょう?」
「そうでもないさ。ペットのストックはまだあるからな」
店を開けているのは昼下がりまでで、そこから夜にかけて依頼を行うのが、彼のスタイルらしい。
「まあ、僕らとしては、きちんと依頼さえこなしてくれれば文句はありませんがね」
「そっちはまかせてくれ、俺たちも冒険者の端くれだからな。デッドエンドの名前も、ちゃんと売っている」
本当かねえ。
★ ★ ★
金に多少の余裕ができたので、普段着と防具を買うことにした。
まず、適当にそこらの行商から服を購入。
エリスの買い物は早かった。彼女は、軽くて動きやすくて丈夫なもの、を基準にしているため、あまりオシャレな感じじゃないズボンをささっと購入してしまった。
状況がよくわかっているチョイスだと思うが、もっと女の子らしいものを一着ぐらい、と思ってしまったので、店の端の方にあったピンク色のヒラヒラしたワンピースを薦めてみると、彼女はあからさまに嫌そうな顔をした。
「……私にそんなの着てほしいの?」
「一着ぐらいはあってもいいんじゃないですか?」
「じゃあルーデウスも男らしいのを買いなさいよ」
と、山賊の着るような毛皮のベストを押し付けられそうになった。
俺がこれを着ると、エリスがひらひらのワンピースを着る。それならそれでもいいかな、と一瞬思ったが、二人が並んだ姿を想像して、諦めた。
服を購入後、防具屋へと赴いた。
今のところ、エリスも大した怪我をしたことはなく、俺が治癒魔術を使えるから、多少の怪我ならすぐ治る。だから防具はいらないんじゃないかと思ったのだが、ルイジェルド曰く「お前の治癒魔術では、致命傷や部位欠損は治せず、エリスはまだ実戦経験が浅い。慣れや油断から致命傷を受けることもある」とのことなので、防具は必要であるらしい。
防具屋は、なかなか立派な店構えをしていた。
といっても、アスラで見た店よりずっと無骨な感じだ。
店に入ると、行商より若干高い品物が並んでいた。行商の方が値段は安く、たまに掘り出し物もあるのだが、店を構えているところの方が品質が安定し、品揃えもいい。サイズが揃っているのも大きいな。俺たちは子供サイズだから。
「心臓を守る防具ですから、なるべくいいのを……」
現在、エリスの胸当てを選んでいる。女性用の胸当ては、バストサイズに応じた種類があった。
「これでいいわ」
エリスは自分にぴったりサイズの皮の胸当てを試着して「どう?」と聞いてきた。
胸を凝視できる機会を逃す俺ではない……ふむ。成長は順調な感じだ。
「もうワンサイズ大きいほうがいいですね」
「なんでよ」
なんでって?
「僕らは成長期なので、ピッタリだとすぐ合わなくなります」
そう言いながら、次のサイズをエリスに渡す。
「ぶかぶかじゃない」
「大丈夫、大丈夫」
エリスはブツブツ言いながら、各部位を守る装備を買っていく。最近の戦いで、怪我しやすい場所は彼女もわかっている。各種関節と急所は守るとして、頭はどうするべきか。重くなりすぎるとスピードが殺される。とはいえ、頭も急所だ。何か身に着けておいたほうがいいだろう。
「こういう兜はどうでしょう」
世紀末覇王の弟のようなフルフェイスメットを提示すると、エリスは露骨に嫌そうな顔をした。
「カッコ悪い」
一蹴。最近の若者にこのセンスはわからんらしい。
その後、いくつかの兜を被せてみたが、重い、ダサい、臭い、視界が狭い等の理由で、結局は鉢巻のようなものに落ち着いた。鉄板が縫い込まれているものだ。鉢金というんだったか。
ちなみに、フードは目立つ赤髪を隠すために被っているだけで、防具としての意味はない。
「こんなものね。どうルーデウス! 冒険者に見える?」
ロインにもらったカトラス風の剣を腰に、軽装の冒険者の格好をしてエリスはくるりと回る。
正直、コスプレみたいだ。胸当てのサイズが合ってないのが特に。
「よくお似合いですよ。お嬢様。どこからどう見ても歴戦の戦士です」
「そう? むふふ」
エリスは腰に手を当てて、自分を見下ろしながら、にまにまと笑った。俺はエリスがニマっている間に、装備を一式、鉄銭一枚まで値切って購入。さすがに、一式となると高いな。
「次はルーデウスね!」
「僕はいらないんじゃないですか?」
「ダメよ! ローブ買いましょう! ローブ! 魔法使いっぽいの!」
自分は剣士で、幼馴染の魔法使いと一緒に冒険。エリスはそういう冒険者に憧れていたようだ。
夜は眠れない日もあるみたいだが、昼間のエリスは実に図太い。
まあいいか。付き合ってやろう。
「おじさん、僕の体に合うローブってありますか?」
と聞くと、防具屋のオヤジは無言で棚の一つを開けてくれた。
「小人族用だ」
そこには、色とりどりのローブがあった。どれも微妙にデザインが違う。色は五色。赤、黄、青、緑、灰。かなり淡い色だ。
「色が違うと何か違うんですか?」
「布に魔物の毛が織り込んである。耐性もちょっと付いてる」
「赤は火、黄は土……灰色は?」
「ただの布だ」
なるほど。だから灰色だけ半額なのか。他の色もちょっとずつ値段が違う。材料の問題だろうか。
「ルーデウスは青色よね!」
「どうでしょうね……」
近距離戦だと爆風で自分を吹っ飛ばすとかやるしな。
赤か緑の方がいいかもしれない。きつねか、たぬきか。
「坊主、どんな魔術使うんだ?」
「攻撃魔術を全種類使えますよ」
「へぇ。すげえな。若そうに見えるのに……じゃあ、ちょっと値は張るが」
と、オヤジが取り出したのは、ちょっと濃い目の灰色、ねずみ色という感じ。
「マッキーラットの皮で作ってある」
「○ッキーマウス?」
「マウスじゃねえ、ラットだ」
俺の脳裏には、赤い半ズボンをはいた黒いアイツが浮かんでいたがぶんぶんと振り払う。
手にした感じは布のようだが、そういう生き物なのだろうか。
「これにはどんな効果が?」
「魔力耐性はねえが、丈夫だ」
試着してみる。
「ブカブカですね。もっと小さいのはないんですか?」
「それが一番小さい」
「子供用のがあるでしょう?」
「そんなものはない」
なんて、ノーマルスーツを初めて着用した柔道家みたいな会話をしつつ。まあ、体の方は成長期だから、これでいいのかもしれない。生地もいい。丈夫という言葉通り、防刃性もちょっとはありそうだ。それに、ネズミ色ってのもいいな。名は体を表すって言うし。
「ま、これにしときましょうか」
「気に入ったか? 屑鉄銭八枚だ」
「じゃあそれを……」
可能な限り値切って、屑鉄銭六枚で購入した。
ついでに、エリスと色違いの鉢金をもう二つ購入。俺とルイジェルド用である。いざという時に、ルイジェルドの額の宝石を隠せるように……なんで俺の分も買ったのかって?
仲間ハズレは嫌じゃん。
★ ★ ★
俺たちが買い物をしている間、ルイジェルドはヴェスケルを監視しに行ってもらっていた。
彼らには期待しているわけではないが、彼らの働き次第では、俺たちの評判は地に落ちる可能性もある。ゆえにルイジェルドを偵察に送り込んだのだが、そんなに心配なら、最初からあんな奴らと手を組まなければいい、と言われた。
仰る通りだ。しかし、そのお陰で、金銭的に余裕ができた。今のところはどっこいだろう。
結論から言うと、彼らはしっかり働いていたらしい。Fランクの仕事を嫌がらずに、献身的に。
ヴェスケルは本日、害虫駆除の依頼を受けていた。
台所に生息する憎きあいつを退治する依頼だ。
彼女の種族はズメバ族といって、唾液に毒性がある。その唾液には誘引力があり。唾液を摂取した虫は死亡、あるいは麻痺で動けなくなって、ズメバ族の餌となる。
つまり、害虫駆除は彼女の十八番である。
依頼主は老婆だった。
実に偏屈そうで、口をへの字に結んでいる老婆だ。ルイジェルドはちょっとでも気に食わないことがあれば叩き出すという気概を老婆から感じ取ったらしい。
だが、ヴェスケルは特に衝突することもなく、迅速に害虫を全滅させたらしい。ルイジェルドが確認したところ、本当に家の中から一匹もいなくなったのだとか。その後、彼女は家中の隙間を何やら糸のようなもので埋め、侵入経路を塞いだ。
「ありがとうよヴェスケル。困ってたんだ」
「いいえ。何かあればまた『デッドエンドのルイジェルド』にお任せください」
「『デッドエンドのルイジェルド』? それが今のパーティ名かい?」
「そのようなものです」
ヴェスケルは、そんな会話をし、最後に唾液から作った餌を数個渡して、老婆と別れた。
依頼完了。冒険者ギルドで俺たちと落ち合い、報酬を受け取ったのだ。
「聞く限り、しっかり働いていますね」
「……ああ」
俺が思っていた以上に、彼女の仕事は完璧だ。老婆とも知り合いのようだし、アフターケアもできている。行き当たりばったりで猿真似をした俺より、よほど心象がいいだろう。
「彼らは根っからの悪党ってわけじゃないみたいですね」
「そうだな」
まあ、俺も疑っていたわけだが……いつもやっていることに加えてデッドエンドを名乗るだけなら、彼らの負担もないだろう。楽して金を儲けている、という意識を持ってもらえるのは悪くない。
裏切る可能性も低くなるからな。
「悪事を働いたという事実は消せん」
「でも、今は頑張っています。ルイジェルドさんと同じようにね」
「む……」
犯罪者だって悪いことばっかりやってるわけじゃないのさ。彼ら然り、俺然り、ルイジェルド然りだ。別にやるなと言ったわけじゃないのに、あれからペット誘拐もしてないしな。
もっとも、まだ三日だ。悪事がバレて死にそうな目にあった記憶が薄れるには早い。
「殊勝なのは今のうちだけかもしれません。今後も事あるごとに監視したほうがいいでしょうね」
そう言うと、ルイジェルドは眉を顰めた。
「お前は……手を組んだ相手を信用していないのか?」
「当たり前です。僕がこの町で信用してるのは、エリスとルイジェルドさんの二人だけですよ」
「……そうか」
ルイジェルドが俺の頭に手を伸ばそうとして、やめた。俺はルイジェルドを信用しているが、ルイジェルドからの信用は、なくなっているように感じる。
まあ、今はそれでもいいさ。俺の目的はエリスと一緒にアスラ王国に帰ることだ。ついでにスペルド族の名誉回復もするが、ルイジェルドに信用されることは目的にはない。
「行きましょうか」
俺たちは魔照石の光の中を、ゆっくりと宿に向かって歩き出した。
冒険者生活の滑り出しは順調であったと言える。
第十二話 「子供と戦士」
三週間が経過し、俺たちはDランクに上がった。
上がるのが随分早い、そう思って調べてみると、昇格の条件は以下の通りであると判明した。
F→Eには、F級の仕事を一〇回こなすか、E級の仕事を五回連続でこなす。
E→Dには、F級の仕事を五〇回こなすか。E級の仕事を二五回こなすか、D級の仕事を一〇回連続でこなす。
それ以降も、回数的にはかなり掛かるが、似たような感じだ。
また、失敗が続くと降格がある。自分より低いランクの仕事は五回連続失敗で降格。同ランクなら一〇回連続失敗で降格。自分よりランクが上の仕事なら失敗しても降格はないが、五回連続失敗で受けることができなくなる。
ジャリルとヴェスケルが二人掛かりで、毎日F、Eランクの仕事をやってくれたからこそ、ここまであっさりと上がれたというわけだ。
現在はDランク。つまりCランクの仕事を受けることができる。Cランクの依頼は余裕だから、すぐにでもCランクには上がれる。
そろそろ、ジャリルたちとの契約を切ってもいいかもしれない。奴らはもうペット誘拐はやらないようだが、依頼交換がどんな悪影響を及ぼすかわからない。
金も貯まってきているし、彼らと決別し、この町を発つのにはいい頃合いかもしれない。
だが、Cランクに上がるまでは利用させてもらうことにした。今のところは問題ないようだし、安定して稼げている状態を手放すのは、惜しい。金はあればあるだけ、いいからな。
現在の所持金は緑鉱銭一枚、鉄銭七枚、屑鉄銭一四枚、石銭三五。石銭換算で一八七五枚。
一八七五円。全財産をはたいても、アスラ大銅貨二枚にも満たないのだ。
いや、よその大陸の物価を考えるのはよそう。Cランクに上がり次第、ジャリルたちと決別し、この町を発つ。その方向でいくとしよう。
そんな中、こんな依頼を見つけた。
B
・仕事:謎の魔物の捜索・討伐
・報酬:屑鉄銭五枚(討伐で鉄銭二枚)
・仕事内容:魔物の捜索・討伐 ・場所:南の森(石化の森)
・期間:次の月末 ・期限:早急に
・依頼主の名前:行商のベルベーロ
・備考:森の奥でうごめく影を見つけた。正体を突き止め、危険であるなら排除してほしい。
俺はジャリルと共に、顎に手を当てて悩んだ。
謎の魔物。なんとも曖昧な依頼である。実はいないのかもしれないし、仮にいたとしても、どうやってその魔物だと証明すればいいのか。しかし、鉄銭二枚と報酬はいい。倒さなくても屑鉄銭五枚は悪くない。
「気になるのか?」
「報酬がいいので。でも怪しい」
ジャリルもそれに頷く。
「こういう依頼は報酬をもらえないこともあるからな。やめておいたほうがいい」
そういうことは、以前に一度あった。
あれは二週間前。アシッドウルフを収集してくれ、という依頼を受けて、いつも通りアシッドウルフの牙と尻尾を規定通り集めてきたのだが、必要なのはアシッドウルフの全身でした、と言われた。依頼内容にはそのへんが詳しく書いていなかったが、俺たちは違約金を払うことになった。
思い返すも屈辱的な出来事だ。
そうならないためにも、受けないのがいいのだが……俺は金に目が眩んでいた。
「ああ、でも、鉄銭二枚……もう一度ぐらい『勉強』しておくのもいいかも」
「あんたもこりないな」
「こういう場合、違約金は屑鉄銭五枚分の方が適用されるんでしょう?」
「そうだ。カッコの方は特別報酬みたいなもんだからな」
ちなみに、ノコパラがルイジェルドに絡んできたり、他冒険者がエリスに絡んできたりとうるさいので、二人は外に待たせてある。ヴェスケルも冒険者ギルドには顔を出さない。
止める者はいなかった。
「まあ、石化の森なら、何もいなくても売れるモノは手に入るだろうし、あんたらなら違約金分も回収できるだろう。いいんじゃないか?」
「よし。じゃあ、そっちも頑張って」
後で思い返すも、どうにも、この頃の俺は判断力が鈍っていた。
慣れが慢心を生んでいた。順調に行っているがゆえ、リスクを軽視し、焦りが利益を追求させた。もっとうまくやれたはずだと思う反面、あの時はあれ以上のことはできなかったと思う俺がいた。
★ ★ ★
石化の森。
距離はリカリスの町から丸一日。街道の脇にある森で、先の尖った骨のような木が大量に生えており、まるで森が石化してしまったように見える。
森を突っ切れば、次の町までの近道となるが、アーモンドアナコンダやエクスキューショナーといったBランクに類する危険な魔物も生息しているため、通るのは腕に覚えのある護衛を何人も雇った急ぎの行商人ぐらいだ。
この世界において森は例外なく危険であるが、魔大陸の森は、格別に危険である。
そんな森の入り口。
そこには、三つのパーティが集まっていた。
Bランクパーティ『スーパーブレイズ』。
Dランクパーティ『トクラブ村愚連隊』。
そして、Dランクパーティ『デッドエンド』。
現在、各パーティのリーダーが顔を付きあわせている。
森等の前でパーティが鉢合わせしたら、一応の顔合わせをしておくのが冒険者の常識、だそうだ。
無視したいところだったが、森の中で鉢合わせしても厄介だし、顔を出しておくことにした。
「おい、で、なんだてめえらは」
開口一番。イライラした顔で言ったのは、『スーパーブレイズ』のリーダーのブレイズだ。
顔に覚えがある。確か、初日に俺たちを笑った豚野郎だ。おっと、悪口じゃないよ。
顔が豚なのだ。エリスにゲスい目線を向けていた門番と同じ種族だろう。種族名はなんと言ったか……俺の脳内では、豚頭族と呼んでいる。
彼らは多種多様な種族で構成されている六人パーティだ。魔大陸でCランクに上がるためには、周囲の魔物を狩れる実力が必要だから、全員が実力の裏打ちされたベテランだろう。
「オレたちは依頼で来たんだよ!」
『トクラブ村愚連隊』リーダーのクルトはムッとした顔で言った。
「僕らもそうです」
『デッドエンド』のリーダーも右に同じと頷いた。ま、俺だけど。
Dランク二人の言葉を聞いて、ブレイズはチッと舌打ち。
「ブッキングしちまったか。なんか嫌な予感してたんだがなあ……」
ブレイズがイライラと首筋を掻いた。
「ぶ、ブッキングってなんですか?」
「あ!?」
クルトがおずおずと聞くと、ブタがいきなりキレた。
「まぁまぁ、抑えて抑えて。何卒、ここは初心者の俺らに一つ、ご教授してください」
俺が揉み手でスリよると、ブレイズはペッと地面に唾を吐いた。
「同時期に違うヤツが依頼を出しちまって、それをギルドが管理できずに一緒に出しちまったってことだよ」
なるほど。ダブルブッキングか。依頼者が三人、依頼が三つ。それぞれ違うものだと思っていたら、実は同じものだったという感じか。ありそうな出来事だ。
一応、他の面々の依頼内容を聞いてみる。
ブレイズの依頼『石化の森に出現した、白牙大蛇の討伐』。
クルトの依頼『石化の森で目撃された謎の卵の採取』。
ルーデウスの依頼『謎の魔物の捜索』。
「捜索? あれ? Dランクにそんな依頼あったっけ?」
クルトの疑問には、もちろん、ちゃんと考えてある。
「Cランク依頼です。クルトがギルドから出た後に貼り出されたんですよ」
「そっか……そっちの方が良かったな……」
ブツブツ言うクルトを尻目に、俺は考える。依頼内容だが、ちょっとずつ被ってる感じはする。
まず、この森には白牙大蛇はいないが、討伐依頼が出ているということは、発見されたということだ。つまり、謎の魔物も、白牙大蛇であり、謎の卵も白牙大蛇の卵という可能性もある。
もちろん、謎シリーズが白牙大蛇ではない可能性もある。
ダブルブッキングと断じたブレイズは早計だ。
「それにしても、どうしてこんなことが?」
「しらねえよ。たまにあるんだよ」
まあ、それもしょうがないか。コンピューター管理じゃないしな。
「で? こういう場合はどうすれば?」
「どうもしねえよ、早い者勝ちだ」
ブレイズが言うと、クルトが驚愕の声を上げた。
「なっ! あんたらが先に魔物を倒したら、オレたちの依頼はどうなるんだよ!」
「あん? 卵の採取だったか? そりゃ見つけたら割るさ。白牙大蛇が繁殖でもしたら大変だ」
ブレイズはヘラヘラとクルトをあざ笑った。
「なあ、ルーデウス。あんたからも言ってくれよ! こいつらに先に倒されたら、オレたちの依頼が……!」
クルトは俺に矛先を向けた。確かに、彼らが先に魔物を倒せば、俺たちの捜索依頼も失敗……。
いや、俺たちは捜索が任務だ。白牙大蛇がいましたと報告すれば、それで完了になりそうな空気はある。それでダメでも森で魔物を狩って帰れば、違約金分は払えそうだ。
「まだダブルブッキングと決まったわけじゃありません。白牙大蛇ではない、別の魔物もいるかもしれません」
俺がそう言うと、ブレイズは嫌そうな顔をした。
「だから、いっしょに探しましょうってか? 俺らに子守をしろって言うのか?」
その言葉に、クルトがカッとなった。
「誰がお前らの世話になりたいって言ったよ!」
「とかいって、俺らに守ってもらいてえんだろ? Dランクじゃこの森はキツイからなぁ」
ああ、なるほど。俺とクルトの二パーティが、Bランクのブレイズたちに金魚の糞みたくくっついて楽に依頼を達成するのが嫌なのか。ブレイズたちの負担が増えるだけだからな。
無論、俺も一緒に行動したくない。ルイジェルドが槍で戦うところは見られたくない。彼は強すぎるから、本当のスペルド族だとバレる可能性もある。……ここはクルトに便乗させてもらうか。
「そうですね。実に不愉快です。子守は必要ありません。『デッドエンド』は単独で行動させてもらいます」
俺は一方的にそう言って、リーダーの輪から出た。
★ ★ ★
ルイジェルドとエリスの所に戻る。
「なんだったの?」
待ちかねたと言わんばかりに、エリスが聞いてくる。
「依頼内容が被っていたんです」
「それはどうなるの? 譲っちゃったりするの?」
「まさか、早い者勝ちですよ」
「そう、腕が鳴るわね」
エリスはやる気満々だった。彼女は最近の冒険者らしくない狩りにはうんざりしているようだった。完全に『作業』だからな。
そうこうしているうちに、ブレイズとクルトも話が終わったようだ。クルトは残り二人に短く話かけ、森へと入っていった。『スーパーブレイズ』も、彼らとは違う方向へと入っていく。
「ねえ、私たちはどうするの?」
「そうですね。いつもどおりルイジェルドに索敵をしてもらって、例の謎の魔物とやらを探す方向で行きましょうか」
そう提案したが、ルイジェルドが首を振った。
「まて」
「どうしました?」
「あの三人の子供が心配だ」
三人の子供。愚連隊のことだろう。
「彼らの実力では、この森では生きていけん」
「つまり?」
「手伝ってやろう」
ということらしい。
「……でも、あまり一緒に行動すると、スペルド族だってバレますよ」
「構わん」
俺が構うっちゅーねん。
「スペルド族だとバレたら、色々厄介なことになります」
「ならば、彼らを見殺しにしろというのか?」
「そうは言っていません。後ろから追尾して、いざという時に助けてあげましょう」
仕方がない。作戦変更だ。鉄銭二枚は諦め、恩を売ることにしよう。
しかし、安易に手助けをしても大丈夫なのだろうか。魔物に襲われているところを助けるとなると、スペルド族だとバレる可能性が高くなる。さすがに命を助けてもらってまで、偏見を持ち出すことはないと思いたいが……しかし、デッドエンドという存在は魔大陸では特別だ。
どうなるかわからない。
いざとなれば、ジャリルたちのように仲間に引き入れる方向でいくか……。
というわけで。クルトたちを尾行することにした。
意気揚々と森の奥へと入っていくクルトたちを見て、ルイジェルドは眉を顰めていた。
「どうしました?」
「奴ら、森に入るのは初めてなのか?」
「さあ、僕は知りませんが」
「迂闊すぎる」
と、その心配の通り、クルトたちは索敵に失敗し、エクスキューショナーと遭遇した。
エクスキューショナーは人型をした魔物で、中身は生前に冒険者だった者のゾンビである。
そのゾンビが、なぜか巨大な剣と分厚い全身鎧で武装している。
鎧が重いため動きはそれほど速くはないが、ひたすらにタフで剣に技術がある。
基本的に単体であり、それほど大きいサイズでもないのにランクB。強敵である。
しかし剣と鎧は死ぬと消滅するため、金にならない。
そんな魔物に遭遇したクルトたちは、出会って早々に全力逃走。
「助けに入るぞ!」
「いえ、まだです」
飛び出そうとしたルイジェルドを、俺は止めた。
「なぜだ!」
「まだピンチじゃありません」
エクスキューショナーは鎧姿に似合わず素早いが、しかし、全力で逃げているクルトたちに追いつけるほどではない。
次第に距離が離れ、このままいけば逃げ切れるというところで、クルトたちの運が尽きた。
彼らの逃げた先にいたのは、アーモンドアナコンダ。
三~五匹程度で群れる魔物で、体にアーモンドのような紋様がある。体長は三メートル程度。牙には強力な毒があり、動きも俊敏。タフで数も多いゆえにB。強敵である。
石化の森を代表する、出会いたくない魔物トップツーに挟まれたクルトたちは半泣き半笑いの顔をしていた。
大方、どちらかに出会っても逃げればいいや、ぐらいに思っていたのだろう。実際、エクスキューショナーからは逃げきれそうな感じだった。
こうなったのは、彼らが考え足らずだからだ。実力的に見合った場所でないのだから、やめておけばいいのに。でも、ちょっと背伸びをしたい気持ちはわかる。
「助けるぞ!」
「いや、もうちょっと待って」
すぐに助けようとするルイジェルドを制する。
ギリギリのピンチを演出するのだ。ピンチになればなるほど、売れる恩も大きくなる。
傷だらけになったところで、治癒魔術で直せばいい。ククク。俺の策は完璧だ。
「あ!」
エリスの叫び。体を両断されて宙を舞う、鳥少年。
一撃だった。
彼はエクスキューショナーの攻撃をいなすことができず、一撃で即死した。
俺の悪い笑みが引きつった。そして自分の考え違いに気づいた。彼らは、すでに、ギリギリのピンチだったのだ。浅はかなのは、俺だった。
「だから言った!」
ルイジェルドの苛立ちの混じった声。
俺が即座に『岩砲弾』をエクスキューショナーに放つと同時にルイジェルドとエリスも飛び出した。
俺の魔術を食らって、エクスキューショナーは生きていた。ストーントゥレントを一撃で倒した岩砲弾を受けて立っていた。
硬すぎる、と思ったが、よく見ると右手だけが吹っ飛んでいた。慌てすぎて狙いを外したのだ。ヤツは左手で剣を拾うと、こちらに向かって走ってきた。
遠目に見れば遅いと思ったが、こうして向かってくると、その鈍重そうな見た目からは想像もできないスピードに思えた。
俺は冷静に、ヤツの足元に柔らかい泥沼を設置した。ズボッと片足をツッコミ、前のめりに倒れるエクスキューショナー。
その真上に巨大な岩石を生成し、勢いよく叩き潰した。
その頃、ルイジェルドたちもアーモンドアナコンダを全滅させていた。
その後、クルトは真っ青な顔でガクガクと震えながらも、しっかりと礼を言ってきた。
「……はぁはぁ……まじ……はぁはぁ……助かったよ、お、おまえら、つ……強いんだな……」
岩の下敷きになったエクスキューショナー。首を綺麗に断ち切られて死んでいるアーモンドアナコンダ。このぐらいなら楽勝だ。楽勝なのに、助けられなかったのだ。
「いや、助けるのが遅れて……悪かったよ」
クルトの目には、憧憬の色がつき始めていた。
俺は胸が痛くなり、視線を逸らした。逸らした先には、体を半分に割られて死んだ少年がいた。嘴のついた顔。たしかガブリンとかいう名前だったか。俺が余計なことを考えなければ、死ぬことはなかっただろう。
そう考えていると、ルイジェルドに胸ぐらを掴まれた。彼は顎で死体を指し、言う。
「あれはお前のせいだ」
容赦なく心が抉られた。
「はい……」
「三人とも、助けられたんだぞ!」
わかってる。わかってるさ。俺だって、こんなつもりじゃなかったんだ。
やるせない気持ちでいっぱいだ。こんな結果を望んだわけじゃない。
反省だってしている。後悔だってしている。なのに、なんで責められなければいけないんだ。
「俺だって一生懸命なんだよ! ここ一番で最大の成果が出るように狙ったんだよ! なんでそれを責められなきゃいけないんだよ!」
「死んだからだ!」
的確に言い返された。
「ぐっ……」
言い返せない。俺が殺したようなものだ。
「……」
エリスも今日は黙っている。
彼女も思うところがあったんだろうか。ガブリンの死体をじっと見ていた。
もはや俺に言葉はなかった。俺は失敗したのだ。人の生死が関わる場面で、自分の利益を優先して、手遅れになったのだ。
「お、おい、仲間割れはやめてくれよ」
結局、止めてくれたのはクルトだった。
「お前は関係ない。コイツの問題だ」
ルイジェルドは取り合わないが、クルトも引き下がらない。
「関係ないけどわかるさ。オレたちが戦っているところを見て、助けるか見捨てるかで意見が割れたんだろ!?」
いいえ。実際には割れるどころか、俺が独断で見捨てる形になりました。
「確かにあんたらは強いかもしれないけど、万が一だってある。それに、オレたちを助ける義理もない!」
ルイジェルドの髪が逆立ったかと思った。
「義理などではない! 子供を助けるのは大人の責任だ!」
その言葉に、クルトがカッとなったのがわかる。
「オレたちは子供じゃない! 冒険者だ! ルーデウスのリーダーとしての判断は正しい!」
「むっ……」
ルイジェルドが黙ったが、俺は自分の判断を正しいとは思っていない。
「だが、仲間が死んだのだぞ?」
「見りゃわかるよ! 確かにオレたちも、このままずっと三人でって思ってたさ! けど、死ぬことだってちゃんと覚悟してきたつもりだ! 冒険者なら、若くたって、年寄りだって、みんな覚悟してる!」
ズキンと胸が痛んだ。俺にそんな覚悟はない。冒険者という職業は、あくまで金儲けの手段としてしか見ていない。
「助けてくれたのには感謝してる! けど、ウチのメンバーのことはウチの問題……。いや、依頼の難易度を見極められなかったオレの責任だ」
クルトの言葉を青臭い、若い正義感とでもいうんだろうか。
それとも社会に揉まれていないガキっぽさがあるとでもいうんだろうか。
しかし、そこには必死さがあった。
最近の俺に、明らかに足りなかったものだ。所持金とギルドのランクばかりを気にして、依頼をゲーム感覚で捉えていた俺には、なかった必死さだ。
「そっちのお前……クルトとか言ったか。子供扱いして悪かった。お前たちは一人前の戦士だ」
彼はクルトの言葉で、何かを納得したようだった。
「そして、ルーデウス。すまなかった」
俺を地面に降ろし謝罪した。今回の件について、ルイジェルドが謝ることは、ない。
「謝らないでください。俺がミスした事実は、帳消しにはならないんですから」
「いや。ミスではない。お前は奴らの戦士としての矜持を守ろうとしたのだ。すぐに助けようとした俺は浅はかだった」
「いや……」
そんなことは、一切考えてなかった。
「あの小悪党の二人組の時もそうだったな……」
ルイジェルドは一人で勝手に納得している。
俺は納得していない。今回の件は反省しなければならない事柄の一つだ。すぐにでも悪かった点を洗いだし、次回、似たようなミスを犯さないように整理すべきだ。
と、思う反面、勝手にそう勘違いしてもらえてラッキー、結果よければ全部オッケーじゃんという、浅ましい考えもあった。
自分が嫌になりそうだった。
★ ★ ★
クルトたちはそのまま死体を抱えて町に帰るという。
俺たちは、せめてと森の入り口まで護衛してやった。ルイジェルドなら、「町まで送ろう」と言い出すかと思ったが、そうはならなかった。彼は、クルトたちを戦士として認めたのだ。
「一人欠けては町に戻れないかもしれない。けど、死ぬ覚悟はしている」
そう言った彼の背中は物哀しく、思わずエリスが駆け寄り、
『頑張りなさいよ!』
と、声を掛けるほどだった。
言葉は通じていないが、エリスの表情からクルトも言いたいことがわかったらしい。
「ありがとう……えっと、こうだっけ?」
『えっ!』
と、エリスの手を取ると、その親指の付け根あたりにキスをした。
そして、にこやかに笑って去っていった。
エリスは固まっていた。俺もどうしていいかわからなかった。エリスはバッと振り返り、俺を見た。そして、キスされたあたりをゴシゴシと鎧の裾でこすった。
『ち、違うんだから!』
エリスは何やら必死な顔をしていた。キスといっても、皮の手袋ごしだ。そんなに必死にならなくてもいいと思うんだが。
『こ、これ、もう使わないから!』
エリスは手袋をはずすと、ぽいと森の奥へと放り投げた。おいこら、手袋もタダじゃないんだぞ。
『装備品を投げるな!』
『新しいのを買う金が勿体ないでしょう!』
ルイジェルドと俺の叱責が重なった。反射的な言葉だったが、こんな時にまで金の話を持ち出してしまうとは。ううむ……。
『うるさい!』
エリスは涙目になって地団駄を踏んだ。こんなエリスは久しぶりに見る。なんだろう。
手の甲にキスをするというのは、どんな意味があるんだろう。
『ルーデウス! はい!』
と、彼女は、俺の眼前に手を差し出したので、反射的に舐めた。
『!』
エリスの顔が真っ赤に染まり、俺はグーで殴られた。
意識が刈り取られそうになるほどの本気パンチだった。首の骨が折れるかと思った。このパンチなら世界が取れると思いつつ、俺は無様に地面に転がった。
何をすればよかったんだ?
殴られて地面に倒れていると、エリスが俺に舐められたところをじっと見て、ペロっと舌で舐めたのが見えた。そして、見る間に真っ赤になると、ごしごしと服の裾で手を拭った。
『ご、ごめんルーデウス。でも舐めちゃだめよ!』
その仕草が可愛かったので、俺は全てを許した。ついでに、失敗して鬱だった気分も少し晴れた。
★ ★ ★
森を歩きながら、ルイジェルドについて考える。
子供好きの正義漢。俺の認識におけるルイジェルドはそんな感じだったが、本日『戦士』というキーワードが浮上した。
「ルイジェルドさんにとって、戦士って、なんですか?」
「戦士は子供を守り、仲間を大切にする者のことだ」
即答だった。しかし、そのことから、俺はようやく、今までルイジェルドが怒っていた理由を察することができた。彼は、考えなしの正義感ではない。戦士に矜持を求めていただけなのだ。
『戦士は子供を害してはならない。
戦士は子供を守らなければならない。
戦士は仲間を見捨ててはならない。
戦士は仲間を守らなければならない』
彼の中には、こんな感じの考えがあるのだ。だから、俺を蹴り飛ばしたペット誘拐犯は悪党と断定された。そして、その敵を討とうともせず命乞いをした二人も、戦士の風上にも置けない悪党と断定された。
クルトたちもそうだ。最初は彼らを子供として見ていた。
子供を見捨てた俺は、悪党というわけだ。
しかし、先ほどの啖呵で、考えを改めた。子供から戦士へと認識を変えた。そうすることで、俺の行動が許された。むしろ、彼らを戦士として見ていなかったと、彼は反省した。
彼の中における、子供と戦士の線引きがどうにもわからない。
エリスはどうやら子供として見ているようだが。俺はどっちなのだろうか。
聞くべきか、聞かざるべきか。
「戦っているな」
悩んでいると、ルイジェルドが警戒の声を上げた。
「さっきの……ブレイズたちですか?」
「そうだ」
ブレイズたちであるらしい。
ルイジェルドの第三眼がどういう見え方をしているのかわからないが、鉢巻で塞がれていても見えており、個体の識別もできるらしい。
便利だ。俺も欲しい。
「助けますか?」
「必要なかろう」
さすがBランクともなると、ルイジェルドに戦士として見てもらえるらしい。
森の先には、一匹の大蛇がとぐろを巻いていた。そして、その周囲には四つの死体があった。
「……え?」
死んでるんですけど……。
必要ないって、そういう意味か。でも、ブレイズの死体はない。逃げたんだろうか。
「確か六人パーティでしたよね……残り二人は?」
「死んでいる」
全滅したらしい。合掌。
「しかし、あの魔物は?」
ブレイズたちを全滅させた魔物は、デカかった。
「あれは赤喰大蛇だな」
その赤い蛇は俺とエリスが両手を繋いでも抱えきれない胴体、一〇メートルはあろうかという長さ、そして、威嚇するように広げられている頚部を持っていた。
胴体の途中が、ポコリと大きくなっていた。あの片方は恐らく豚肉だろう。ていうか、白蛇って話じゃなかったっけ?
「この森に赤喰大蛇がいるとはな。しかもでかい」
「普通はいないんですか?」
「普通はな。だが、稀に発生する」
赤喰大蛇とは、白牙大蛇の上位種である。白牙大蛇よりも巨大な体を持ちながら、敏捷性は大幅に上回る。火に耐性を持つ硬い鱗で全身を覆い、鋭い牙には猛毒がある。何を摂取して変異するのかはわかっていないらしいが、白牙大蛇のいる所に、ごく稀に発生する。
白牙大蛇はBランクだが、赤喰大蛇はAランクに相当する強敵である。
Bランクのパーティでは、瞬殺だっただろう──ということらしい。
彼は食事に夢中で、どうやらこちらには気づいていない。今にも、三つめの餌に取り掛かろうとしている。
「やれるわよね?」
エリスが自信満々に剣を抜く。
「やるのか?」
ルイジェルドが俺に聞いてくる。
「……僕が決めてもいいんですか?」
「任せる」
「他に誰が決めるのよ」
任せられた。ちょっと考えてみよう。依頼内容は、謎の魔物の発見か討伐。
とりあえず、白牙大蛇か赤喰大蛇が謎の魔物で間違いなさそうだ。
この森にはいないらしいし、ソレっぽいのを発見した現在、帰っても依頼は成功だ。でも、倒せば鉄銭二枚の報酬。できることなら、倒したいところだ。もっとも命あっての物種、という言葉もある。
今さっき、目の前で一人が死んだばかりだ。
負けたら死ぬ。危険な橋は渡りたくない。
「なんなら、俺が一人で倒してきてもいい」
悩んでいると、ルイジェルドがそう提案した。
「ルイジェルドさん。一人で倒せるんですか?」
「ああ。俺ひとりで十分だ」
頼もしいセリフ。なんとかダッシュさんみたいだ。
「じゃあ、エリスを守りながらでもいけますか?」
「いつもどおりだ。問題ない」
Aランク相手にこの余裕。まあ、ルイジェルドがこう言うのなら、大丈夫だろう。よし。
「じゃあやりましょうか」
決定した。
★ ★ ★
俺が魔術で遠距離攻撃し、近距離で二人が戦う。
いつも通りの連携なので、いつも通り岩で砲弾を作る。
今回は、Aランクが相手ということで、ちょっと威力を上げる。
形状を楔状に。着弾後に爆発するように、内部に火の魔術を内蔵。発射。砲弾は超高速で飛んでいき、赤蛇へと突き刺さり、そのまま大爆発を起こす──はずだった。
「なっ!?」
赤喰大蛇は、クッと体をひねり、砲弾を避けた。
回避されたのだ。偶然ではない。赤喰大蛇は飛んでくる砲弾を、明らかに見てから避けた。遠くの方で、砲弾が爆発した。
「うそだろ……」
先制攻撃に失敗したが、うちの特攻隊は止まらない。ルイジェルドを先頭に、斜め後ろからエリスが追随する。いつもと陣形が違う。いつもはエリスが前のはずだ。
「シャァ!」
「…………ふん!!」
ルイジェルドが頭へと襲いかかる。短槍を使った、いつも通りの打突。赤喰大蛇はその攻撃をスウェーの動作で避け、反動を利用してルイジェルドに噛み付く。噛まれれば一発で大穴が開きそうな牙を、ルイジェルドは軽く槍で弾いた。
同時に、赤喰大蛇の後ろに回り込んだエリスが、尻尾に向かって剣を振るう。
エリスの斬撃は切断には至らない。赤蛇の肉か鱗、あるいは両方が硬いのだ。
「シャアアァ!」
赤喰大蛇の気がエリスへと向いた瞬間、エリスとルイジェルドがパッと離れる。
一瞬の間隙を突いた俺の魔術が赤喰大蛇へと飛んでいく。
流れは事前に決めておいた、いつも通りの連携パターン。
「また外した!?」
しかし、赤喰大蛇はまたも避ける。先端を尖らせることで速度を増した砲弾は、赤喰大蛇の脇をすり抜け、背後の木を数本まとめて叩き折った。また見てから回避されたのだ。
当たらなくても問題はない。脳と心臓を執拗に狙うルイジェルドと、尻尾から徐々に切り刻んで注意を逸らすエリスの波状攻撃に、当たれば痛いで済まない魔術。
こちらのパターンは単調だが、そうそう対処できるものでもない。
エリスを執拗に狙えば突破口も開けるだろうが、ルイジェルドのヘイト管理は完璧だ。赤喰大蛇は俺とエリスを放置せざるを得ない状況になっている。
ルイジェルドと俺の攻撃は当たらないが赤喰大蛇は次第に疲労し、動きを鈍らせていく。
そして、ついに岩砲弾が蛇の胴体を捉えた。
★ ★ ★
赤喰大蛇の剥ぎ取りを終えた頃には、すっかり日が暮れていた。
その日は、赤喰大蛇の肉で晩餐。どこが売れるのかわからなかったが、とりあえず牙を引っこ抜き、皮を剥いで絨毯のように丸めてある。
クルトたちが探していたであろう卵も見つかったが、でかすぎて運べる要素がない。
色々考えたが、割っておくことにした。魔物を増やす行為は厳禁だそうだからな。
ブレイズたちの死体は、売れそうなものを剥ぎとった後、焼いて埋葬しておいた。これをそのままにしておくと、エクスキューショナーになるんだろうか。
ゾンビとしてよみがえる、という現象がイチマチ理解できない。
(それにしても、赤蛇は強かったな)
俺は先ほどの戦闘──赤蛇に魔術を回避されたことを思い出す。
回避だ。何度も回避された。
最後に直撃弾を得るまでは、かすることさえほとんどなかった。
考えてみれば、エクスキューショナーもそうだった。直撃だと思ったら避けられて、片腕だけを吹っ飛ばす結果になった。Bランク以上の魔物ともなると、魔術を回避するぐらいはできるのか。
赤蛇はAランクという話だ。ルイジェルドの槍も避けていた……が、あれは手加減していたからだろう。本気を出せば、一撃で仕留められたに違いない。
赤蛇がエリスの剣を避けなかったのは、脅威度が低いから避ける必要もないと踏んだからか。
しかし、この世界の生物は化け物揃いだな。人族だって、魔術を受け流すことはできるようだし、魔物は銃弾を見てから回避する。Sランクの魔物となったら、岩砲弾が直撃しても無傷、なんてことも有り得るかもしれない。
恐ろしいことだ……危険な場所にはなるべく近寄らないようにしよう。
ともあれ、こうして、俺たちは依頼を達成した。
──そして、この依頼がリカリスの町における最後の依頼となった。
第十三話 「失敗と混乱と決意」
赤喰大蛇を討伐し、ギルドに帰ってきた。
いつも通り、ジャリルと冒険者ギルドの外で待ち合わせし、完了カードを交換する。
そして赤蛇の牙と皮を渡し、口裏合わせ。
量が多かったので、今回はヴェスケルを含めた全員で冒険者ギルドに入る。すると、案の定ノコパラが寄ってきた。この男は、本当にいつもギルドにいて、いつも寄ってくる。
「ようよう、随分面白そうなのを狩ってきたじゃねえか。それ、赤喰大蛇の鱗じゃねえのか? あ?」
俺はジャリルに目線を送り、打ち合わせ通りに言葉を吐かせる。
「あ、ああ。運よくな、弱っているところに出くわしたんだ」
「へぇ~。お前らがねえ~」
ニヤニヤと、何か面白いことでもあったかのように、ノコパラはジャリルを見下ろしている。
なんだ。何か、いつもと違う気がする。
「と、途中で『スーパーブレイズ』の連中が死んでたんだ。あいつらが弱らせたんだろう」
「なに? ブレイズ……死んだのか?」
「ああ」
「ま、赤蛇じゃしょうがねえか……」
ノコパラは、ふぅんとつまらなさそうに息を吐いた。
「だが、いくら弱ってたからってお前ら二人で赤蛇はなぁ……」
「弱ってたというか、死にかけていたんだ。いや、もう死んでいたと言っても過言ではない。正確には死んでいなかったが、死んだも同然だったんだ」
早口にそう言って、ジャリルは足早にそこを去る。ノコパラも納得していない顔で、標的を俺たちに切り替えた。
「お前らは、今日もペット探しか?」
「ええ、ジャリル師匠のペット捜索術は素晴らしいので、今日も小銭をゲットです」
「へぇ~」
俺もまた足早に去ろうとする。何か、よくない感じがした。
しかし、ノコパラは馴れ馴れしくも、俺の肩に手を回し、小声でボソリと言った。
「で、町の外で、どうやってペットを探すんだ」
一瞬だけ、無意識的に、俺の動きが止まったが、ポーカーフェイスは作れていたと思う。
まだ、想定内だ。俺たちが町の外に行くのを見られただけ。
「今回はたまたま外にいたんですよ」
「へぇ~。というと何か?」
ごまかす方向で話を進める。ノコパラはジャリルの肩をガシリと掴んだ。
「赤喰大蛇も、たまたま町の中にいたってことかよ?」
なるほど。ジャリルたちは町中で姿を見られている。つまり、バレてるってことだ。
「さぁて、不思議なこともあるもんですねぇ」
このパターンは、想定していた。切り抜けるパターンはいくつかある。例えば、ジャリルを尻尾切りにすれば、この場は逃れられる。俺たちは低ランクで、高難度依頼を押し付けられて困っているのだ、と。
だが、これはやらない。これをやると、俺がルイジェルドに切られる可能性がある。
戦士の行いじゃないからな。
「おいおい、今更しらばっくれんなよ」
「しらばっくれるも何も、さて、僕らが何かしましたかね」
「あ?」
「僕らは『ピーハンター』に依頼を手伝ってもらい、『ピーハンター』の依頼を手伝っていた。それだけのことですよ?」
しらばっくれる方向から、開き直る方向へとシフト。
ギルドの規約は見なおしたが、俺たちに非はないはずだ。
もっとも、規約に書いてなければオッケーというわけではない。世の中、ルールを守れば何してもいいわけではないのだ……とはいえ、その正確な線引きは俺にはわからない。だから、俺たちは正しいという方向でごまかす。
「ふざけんじゃねえぞ。てめえらのやり方を真似する阿呆が出てきたらどうなる?」
「どう、とは?」
「依頼が金で買えることになっちまう。冒険者ギルドの存在意義がなくなるんだよ」
ふむ。金銭取引はしていない……と言い張ってもダメそうだな。
でも、そうか、依頼の売買に分類されるのか。なるほど、こいつ頭がいいな。確かに、俺たちみたいなやり方が横行すれば、依頼を金で売買するヤツラも出てくるかもしれない。
例えば、Dランクの依頼を全て受領し、他のDランクの連中に売るのだ。
売ったヤツラは金も入り、ランクも上がる。何もしていないのに、だ。
もっとも、そのやり方だと、売れなければ依頼失敗となるが。
「なんでノコパラさんがそんなことを気にするんですか? あんたには、迷惑かけてないでしょう?」
「いいのか? そんな態度を取って。お前らの取れる道は二つだぜ……ジャリル、てめえも聞け」
俺は胸ぐらを掴んで持ち上げられた。後ろでルイジェルドとエリスが気色ばむ。
とりあえず、今はハウス。まだ話は終わっていない。
「ヘヘヘ……」
馬面の表情は馬なのでわからない。だが、そこに下卑た笑いが張り付けられてるのは、わかった。
「冒険者資格が大事なら、毎月、鉄銭二枚、俺んところに持ってこい」
あらやだ清々しい。この世界に来て、初めてこういう人に会った気がする。最近はどいつもこいつも中途半端にいい面と悪い面があるからな。こういう風に、悪い面だけを見せてくれる相手は楽でいい。余計な気遣いをしないで済むからな。
しかし、ノコパラめ、どうりでずっとギルドにいるわけだ。
コイツはギルド内で不正をしそうなヤツを見張っているのだ。そして、見つけるとこうして強請ってくる。楽な商売だ。コイツを通報すれば一発で終了なんじゃないだろうか……いや、そうすると通報したほうの不正も発覚するわけか。
「おめーら。かなり稼ぐみたいだから、ヘヘ、余裕だろう?」
「い、いくつか、質問いいですか?」
動揺しているフリをしつつ、俺は冷静に話を進める。
「あん?」
「やっぱ、今回のコレは、依頼の売買に分類されるんですよ……ね?」
「おう、バレりゃあ、罰金と冒険者資格の剥奪だ。困るだろ?」
「困ります、困ります」
落ち着け、まだ慌てるような事態じゃない。こういう状況も、想定していた。
大丈夫、まだ、大丈夫だ。
「と、とりあえず今は持ちあわせがないので、ジャリルさんと、依頼の報告をしてきていいですか?」
「構わねえよ。だが、逃げんなよ?」
「もちろんですよ、旦那ぁ~」
やっぱこいつ、あんまり頭良くないなと思いつつ、俺はカウンターへと向かう。
「お、おい……どうすんだ、どうすんだよ!」
「落ち着いて。平然としてください」
動揺するジャリルを適当に相手しつつ、ヴェスケルを手招き。完了カードを受け渡し、報酬を受取る。それと同時に『ピーハンター』を解散させ、ジャリルとヴェスケルを『デッドエンド』へと加入させた。
意味のない措置かもしれない。冒険者ギルドがどこまで細かく帳簿をつけているのかわからないからな。
背後を見ると、ルイジェルドが憤怒の形相だった。その視線の先には、ノコパラがいる。
今回、ルール違反をしたのは俺たちなわけだが、それを嵩にきて脅すような行為は戦士的にダメらしい。とりあえず、ルイジェルドをジェスチャで制しておく。
エリスは状況がわかっていないようだ。言葉がわかれば、最初にノコパラに襲いかかるのは、恐らく彼女だ。その時は、拳ではなく剣で襲いかかるだろう。
「ほら、とりあえず今月の分、払っとけよ」
戻ってくると、ノコパラはなれなれしく、俺たちに肩に腕を回してきた。ジャリルは愛想笑いで受け取ったばかりの鉄銭二枚を渡そうとするが、俺はその手を掴んで止めた。
「その前に一つ」
「んだよ。早くしろよ、俺ぁ気が短ぇんだ」
心の中で深呼吸を一つ。うまくいくことを祈ろう。
「俺たちが不正をしたって証拠、あるんだろうな?」
ノコパラの忌々しそうな舌打ちが、ギルド内に響いた。
★ ★ ★
ギルドの帳簿から、『デッドエンド』が行った依頼がピックアップされる。
ギルド職員は、何のために、などと聞かなかった。ノコパラがこれを聞くのは、今日で初めてではないのだろう。それらを元に、依頼者の所へと向かうことにする。
「路地裏で襲おうとか考えんなよ?」
ノコパラはルイジェルドとジャリルを見ながら、そう言った。ルイジェルドの殺気はかなりのものだと思うが、彼は怖くないのだろうか。
案外、そういう殺気を受けるのは慣れているのかもしれない。
「俺が死ねば、仲間がギルドに報告するし、それに、なんちゃってCランクのお前らと違って、俺はBに上がれるCだからよ」
最後の一言は、さすがに虚勢だろう。ノコパラも五対一で勝てるとは思っていまい。
いくら俺たちを追い込んでいるとはいえ、彼だって死にたくはないのだ。
とはいえ浅はかだな。俺なら護衛の一人も付ける。
「さぁて、ついたぜ」
最初の一軒。見たことのない民家だ。
ノックすると、中から出てきたのは、偏屈そうな婆さんだった。
ワシのような鼻で、黒いローブを着ている。
家の中からは、甘ったるいにおいが漂ってきた。
恐らくあの中で、ね○ねるねるねを作っているのだ……。
彼女は俺たちを見て訝しげな顔をしたが、ヴェスケルの顔を見ると、顔をほころばせた。
「おや、ヴェスケルじゃないか。今日はどうしたんだい? 大勢ひきつれて。ああ、それが『デッドエンドのルイジェルド』のメンバーかい?」
ノコパラはぎょっとした顔で俺たちを見渡し、婆さんの視線がヴェスケルの顔に注がれているのを見て「ハン!」と、にやけた笑いを張り付かせた。
「婆さん。こいつらは、『デッドエンド』じゃねえんだ。アンタ、だまされてたんだよ」
「あん?」
婆さんはノコパラを一瞥すると鼻で笑った。
「ハッ、どう騙したっていうんだい?」
「どうって、そりゃ」
「ヴェスケルはきちんと害虫駆除をしてくれたよ。さすがはズメバ族だね。あれ以来、一匹も見かけないよ」
どうやら、この老婆はヴェスケルが回った家の一つらしい。
そういえば、ルイジェルドが監視した話の一つに、そんなこともあったか。
「きちんと仕事をしてくれるなら、あたしゃ本物の『デッドエンド』でも構わんよ」
その言葉に衝撃を受けたのはノコパラだけではなかった。
ルイジェルド本人も驚いた顔をしていた。
「け、けどな!」
「老い先短い身だしね。最後にそんなのと出会えるなら、会ってみたいものさ」
ノコパラは目を白黒させながら、苛立ちの表情でヴェスケルに振り向く。
「ヴェスケル! てめえ冒険者カード出してみろ!」
ヴェスケルはハッとした顔で、しかし、ニヤリと笑い、冒険者カードを取り出した。
そこには、パーティ名『デッドエンド』と書かれたカードがあった。
「なっ! ち、畜生、てめえらやりやがったな……!」
すでに、『ピーハンター』は存在しない。調べれば、ギルドの帳簿には残っているだろう。
さらに調べれば、規約のどこかに引っかかるかもしれない。
だが、ノコパラはそこまで頭が回らなかったらしい。
「クソが! 次だ!」
ギルドに戻ることはせず、俺はニヤニヤと笑いながら、ノコパラについていく。
数十件の依頼人を回り、ノコパラは赤を通り越して青い顔になっていた。
「ちくしょう、どうなってやがる」
どの依頼者も、ジャリルとヴェスケルを『デッドエンド』として認識していた。
そして、冒険者カードも『デッドエンド』。
挙句の果てに、最初の依頼である少女の元を訪れると、少女が歓喜の声をあげてルイジェルドの足に抱きつくという、嬉しいハプニングもあった。
「ノコパラさん。悪いんですが証拠がないんじゃあ、僕らもあんたに金を払うことはできませんよ」
「くそがあ」
ていうか、逆に彼をギルドに訴えることもできよう。依頼の邪魔をしたとかでっち上げて。
「くっくっく」
思わず、悪い笑いが溢れる。そうしているうちに、最後の依頼者の場所が見えてきた。
というか、狼の足爪亭だった。ジャリルたちは俺たちの泊まる宿屋でも働いていたらしい。
さすがに顔を知る者がいるとごまかすのは難しいかもしれないが、宿屋の主人とはそれほど仲良くしていた記憶もない。ま、今まで通りだ。なんとかなるだろう。
「最後は、あいつらだ」
足爪亭の入り口から出てきた二人。
それを見て、俺は凍りついた。
ヤバイと、俺の頭が警鐘を鳴らす。エマージェンシー。突然の空襲。敵機襲来。不測の事態。
俺の考えの足りなさが、頭の悪さが、ここにきて浮き彫りになる。
「あ、ルーデウス、帰ってきたのか……お疲れさん。って、なんだ、ぞろぞろ引き連れて」
クルトは疲れきった顔で、俺たちを出迎えてくれた。
ノコパラは俺の焦りを悟ったのか、あるいは最初からこうするつもりだったのか。
「よう、前の石化の森で助けてもらったのは、『デッドエンド』で間違いねえよな?」
現在の『デッドエンド』のパーティランクはD。『ピーハンター』が受けたあの依頼はB。
つまり、受けることができない。つまり、調べればボロが出る。
「そりゃあ……」
クルトは俺とルイジェルドの顔を見る。俺は必死で、黙っていてくれと首を振る。
(虚勢を張れ、お前は誰の手も借りてなんかいない。窮地を切り抜けたのは仲間うちだけだ、そうだろ?)
と、せめて、クルトたちが虚勢を張って、「そんなの知らねえよ! オレたちは誰にも助けられてなんかいない!」と抗弁してくれることを祈る。クルトはそれを見て、力強く頷いた。
「当たり前だろ、こいつらぐらい強い奴は見たことねえよ」
アラヤダ正直者!
クルトは、俺たちがいかに強く、エクスキューショナーとアーモンドアナコンダを葬ったかを語った。かなり脚色と擬音の入った説明だった。
『ルーデウスさんはマジパネェよ。エク公とかマジ調子で、おっかねえけど、デッドエンドに上等キれるほどじゃなかったわ。エク公とルーデウスさんがタイマン張ってどうだったか、わかる? ワンパン。マジ。ワンパンでエク公ブチン。ぺちゃんこ。ルイジェルドさんもマジヤバ。こっちにフッ、あっちにフッと動いただけで、アナコンダボン! スッゲーことやってんのにヨユーって顔してんの! いや、マジ痺れたわー』
と、そんな感じの解説をノコパラは、そうかそうかほうほうそらすげー、とニヤニヤしながら聞いていた。
そうして、俺たちへと振り返る。
「おかしいなぁおい、町で依頼を受けてた奴が、石化の森で人助けなんかしてんだろうな」
「いや、あの、それは、僕らがジャリルと一緒に……」
「ジャリルもヴェスケルも、ずーっと町にいたぜ?」
もう、ごまかすのは無理だった。すでにノコパラの頭の中では俺たちを追い込む算段がついているに違いない。落ち着け、まだ手はあるはずだ。
考えろ。まずは三つ。選択肢を思いつけ。よし、思いついた。
一.ノコパラを殺す
仲間がいるという話を信じるなら、決していい方向には進まない。
だが、案外いい方向に転がるかもしれない。全ては運次第。下策。
二.ジャリルに全ての罪を被せる
俺たちは新人、彼らは古参だ。騙されていた、食い物にされていたと叫べば、通るかもしれない。
だが、ルイジェルドの信頼は失われる。仲間を裏切ってはいけない。下策。
三.今は金を払っておき、時期を見てなんとかする
これも全てが運次第。すぐに解決策が見つかるかもしれないが、ノコパラに俺たちの戦闘力を知られれば、逃がさないために二重三重の策を仕掛けられるかもしれない。町から逃げ出さないように、自分たちから逃げられないように。下策。
だめだ、全部下策だ。下手の考え休むに似たり。
どうする。一番楽なのは二だが、これは、恐らく、最悪の手だ。
その場しのぎで、決して未来につながらない手。彼らを裏切るということは、ルイジェルドとの信頼関係が切れるということだ。ルイジェルドは、俺の言葉を二度と信用すまい。
だから、二はダメだ。絶対にダメだ。
一もダメだ。意味がない。今日までやってきたことが無駄になる。
いくらここが、人死にに大して寛容な魔大陸でも関係ない。
一度やれば、同じことを同じ方法で解決しようとしてしまう。血塗られた道を歩くつもりはない。俺に、そんな覚悟はない。
三はもっとダメだ。こいつらに金を渡すということは、不正を認めるということ。一番やっちゃいけない。飼い殺しにされているうちに、二つ、三つと罪状を重ねられるかもしれない。その罪をどうにかするために、さらに無理な要求をされるかもしれない。もし俺だったら、エリスの体とかを要求するだろう。そうなれば、結局はノコパラを殺すハメになる。
いや、それでも三か。
いやいや、三を選ぶなら最初から一だ。ノコパラと、その仲間を、殺すしかない。
殺すしかないのか? やるのか……。やるしかないのか……?
俺は、人を殺せるのか? どこかにいる他の奴らはどうする?
ルイジェルドに探させるのか?
どうやって?
ルイジェルドでも、誰を探せばいいのかわかっていなければ、見つけられないはずだ。
いっそ、冒険者を諦めるか? 資格なんてなくても、生きていける。
この大陸で金を貯める方法はなんとなくわかっている。だが、そうやって割り切ったとして、ジャリルたちはどうなる? 調べれば、ペット誘拐のことだって明るみに出るかもしれない。
俺たちは金もできたし、この町から出ていけばいい。
けど、彼らは違う。彼らはこの町に住んでいる。ペット誘拐なんてしていたと知られれば、この町を追い出されるんじゃないのか?
彼らに平原を生き延びる術はない。結局は裏切ることになるんじゃないのか?
それとも、町から追い出された彼らの世話を焼くのか?
無理だ。自分たちだけでもギリギリだっていうのに。できるわけがない。
……いや、ここまできたら覚悟を決めよう。
血塗られた道を歩く覚悟だ。俺の目的を思い出せ。エリスを無事に家に返すことだ。
そのためなら、ルイジェルドも、ジャリルたちも、裏切っていい。
その結果、エリスに軽蔑されたとしてもいい。パウロやロキシーに顔向けできなくなったとしてもいい!
水聖級魔術を使ってこの町を水没させ、混乱に乗じて、エリスを連れて逃げる。
冒険者資格は諦める。どんな悪事に手を染めてでも、目的を達成する。
やってやるよ……。
★ ★ ★
覚悟を決め、手に魔力を集めた時、ふと気づいた。
ノコパラの顔が、豹変していた。
「お……あ……」
馬面が真っ青になり、ガクガクと膝が震えている。その視線の先は俺ではなく、俺の後ろ。
振り返る。
そこには、ルイジェルドの姿があった。水に濡れたルイジェルド。
すぐ脇には、宿屋の裏にあるはずの水瓶が転がっていた。
「る、ルイジェルドさん?」
目に入るのは、輝くエメラルドグリーン。
エメラルドグリーンの髪が、しっとりと濡れて、輝いていた。
水を浴びたことで、青色の染料が、落ちたのだ。
さらに彼は、額を隠す鉢金の結び目を解いた。額の赤い宝石が、露わになる。
憤怒の形相で立つ、悪魔の戦士がそこにいた。
「す、す、す、スペルド……」
ノコパラが尻餅を付いた。
「俺が『デッドエンド』のルイジェルド・スペルディアだ。バレてしまっては仕方がない。お前たちを皆殺しにしてやろう」
棒読みの、ヘタクソな演技だった。しかし殺気だけが本物だった。
「キャアアアァァァァァ!」
誰かが叫んだ。街角を歩いていた少女が、青年が、老人が、手に持ったものを放り投げて叫び声を上げ、逃げていく。そんな中、まずジャリルが裏切った。
「俺は脅されていただけだ! 知らねぇ! 仲間じゃねぇんだ!」
大声で叫んで、ヴェスケルと共に逃げていく。
クルトは腰を抜かしていた。つい先日、ルイジェルドに啖呵を切ったことを思い出したのか。青い顔で、小便を漏らしていた。髪の色が変わったぐらいで、こいつらは何をそんなに恐れているのか。俺には到底理解できない。だって、お前ら、今まで普通だったじゃないか。
クルトさあ。お前とか、さっき、ルイジェルドを猛プッシュしてたじゃないか。将来はルイジェルドみたいになりたいとか言ってたじゃないか。尊敬の目で見てたじゃないか。
なのに、なんて髪の色を見ただけで、そんなに怯えるんだ?
エリスを見ろ、何が起こったのかわからないのに、平然としているじゃないか。
いつも通り、腕を組み、足を肩幅に広げ、顎をクッと上げて。静かに目を見開いて。平然としているじゃないか。
周囲には逃げる人々と、震えながらへたり込む人。剣を抜いてはみたものの、足をガクガク震えさせている人。
いろんな者がいたが、みんな震えていた。
これほどか。
『デッドエンド』の姿は、ただ髪が緑であるということの意味は、これほどなのか。
これほど、人々の中に恐怖として浸透しているのか。
ハッ、なんだか笑えてくるな。俺がやろうとしていたことは何だったんだ。髪を見せただけでこんな状況になるのを、俺ひとりが頑張って、どうにかなると思っていたのか。
馬鹿馬鹿しい。エリスが大丈夫だったから、ミグルド族が大丈夫だったから、他の人も大丈夫だと思ったか? 無駄だったんだ。
スペルド族の悪評は、評判じゃない。
恐怖の象徴なのだ。
それを正す? 無駄だ。できっこない。
「…………」
ルイジェルドは阿鼻叫喚の中、ゆっくりとノコパラに歩み寄る。
「貴様……ノコパラとか言ったな」
胸ぐらを掴んで、持ち上げた。ノコパラの重そうな体が、簡単に持ち上がる。
「ルイジェルドさん! 殺しちゃだめですよ!」
この期に及んで、俺はまだそんなことを叫んだ。
殺しちゃいけない、こんな状況で殺したら、デッドエンドの名前に、一生消えない傷がつく。
いや、もう無理か、今更か。
今更そんなことをしても遅い。もういいよ。やっちゃえ、○ーサーカー!
「す、すまん、ま、まさか本物だとは思ってなかったんだ! ゆ、許して、許してくれ! 頼む!」
「……」
ルイジェルドの憤怒の形相。震えるノコパラ。
『ねえ、何が起こっているのよ!』
唐突に、エリスが話しかけてきた。俺はゆっくりと答える。
『最悪の事態が起こっています』
『どうにかしなさいよ!』
『できませんでした。すいません』
『ルーデウスにできないなら、どうしようもないわね!』
エリスはあっさり諦めた。俺もとっくに諦めた。もうどうにもならん。全ては俺の責任だ。
見つかっても、どうにかなると思っていた。浅はかな考えで、事態がどうにかなっても大丈夫な気でいた。結果、ダメだった。
こうなってしまえば、俺にできることといえば、当初の予定通り、全てを水に流すことぐらいだ。
水聖級魔術で。なんちゃってね。ハハハ。
「た、助けてくれ。お、おれには、腹をすかせた三つのガキが七人いるんだ!」
支離滅裂な命乞いのセリフを吐くノコパラ。
どう考えてもでまかせだ。俺だって、もうちょっとマシな命乞いをする。
「……町からは出ていく。だからお前も忘れろ」
が、ルイジェルドはあっさりと許した。
やはり子供という単語が効いたのか。
「へ、へへ、へ、あ、ありがてえ」
助かった、というノコパラの顔は、次の言葉で引きつる。
「しかし、もし、次の町にたどり着いたときに、俺たちの冒険者資格が剥奪でもされていてみろ」
ルイジェルドは、槍の先で、ノコパラの頬にスッと一筋の傷をつけた。
ノコパラの股間がぐっしょりと濡れ、ケツのあたりがモリモリと膨らんだ。
「俺が町中に侵入できんとは思うなよ……?」
ノコパラはこくこくと頷いた。
ルイジェルドが手を離すと、ノコパラは落ち、ビチャリと嫌な音を立てた。
★ ★ ★
そして、ルイジェルドは町を追われた。
全ての罪を自分で被って逃げ出した。
ひどいもんだった。
ルイジェルドは一人で走りだし、俺たちは取り残された。
衛兵たちが走ってきて、事情を聞かれ、俺はルイジェルドは悪くないと抗弁した。
しかし、子供の言うことだ。
そう言えと脅されたのだなと、勝手に判断された。
ルイジェルドは悪事を企んでいた。俺たちはそれに利用された。悪事の内容はわからないが、運よく最悪の事態を避けることができた。彼らの中ではそうなったのだ。
周囲の人々は、俺とエリスをかわいそうな目で見ていた。何も知らない、利用された子供として見ていた。
はらわたが煮えくり返りそうだった。
ルイジェルドが何をやったというのだ。全部、俺がやったことじゃないか。
俺の甘い考えが引き起こした事態じゃないか。
俺たちは宿に戻り、すぐに荷物をまとめた。大して量の多くない荷物をまとめ、宿を出る。
早くしなければ、ルイジェルドがどこかに行ってしまうかもしれない。
どのみち、俺たちだってこの町にはいられない。ノコパラは生きている。仲間もいると言っていた。俺たちの不正もそのままだ。ほとぼりが冷めれば、次はルイジェルドの助けはない。
「なあ、ルーデウス……」
宿を出たところで、クルトが話しかけてきた。なんと言っていいかわからない。
困惑の表情だ。
「お前、なんであんなのと一緒にいたんだ?」
「あんなのって言うなよ。お前を助けたのは誰だよ。それを小便漏らすほど怯えやがって、何が成り上がるだよ」
「いや……それは……ごめん……」
いや、クルトには当たってはいけないな。こいつは助けてくれようとした側だ。
「すまんクルト、言いすぎた」
「いや、いいんだ。本当のことだし」
クルトはいい奴だな。エリスは両手を後ろにして彼を睨んでいるが。
「クルト、頼みがある。命の恩を返してくれ」
「ああ、なんだ?」
クルトは、まじめな顔で頷いた。
「ルイジェルドは悪い奴じゃない。昔の出来事のせいで怖がられているけど、いい奴なんだ。俺たちがこの町を出ていった後も、そういう噂を流してくれ」
「あ、ああ。わかってるよ。命の恩人、だもんな」
本当にわかっているのやら。
まあ、口約束だが、もしかするとやってくれるかもしれない。
冒険者ギルドに寄り、ジャリルとヴェスケルを『デッドエンド』から脱退させる。
ついでに職員に言伝を頼む。
「こんなことになったけど、助かった。ありがとう。『彼』も感謝しているって、伝えてください」
あいつらは最後に裏切った。けど、それも仕方がないのかもしれない。
結局のところ、彼らが助かるには、その道しかなかった。
最後にだけ目をつぶれば、世話になったのは確かだ。
町の入り口へ向かう途中、運搬用に飼育されたトカゲのような爬虫類を一匹購入する。足が六本あり、ギョロっとした目がチャーミングなトカゲだ。こいつは魔大陸において、馬車のような役割を持っている。大の大人がゆうに二人乗れる種で、鉄銭一〇枚。全財産の約半分。
旅に出る時には、これだけは買おうと決めていたものだ。魔大陸を移動する際には、このトカゲがいるといないのとでは、大きな違いがあると聞いた。
店主から操り方を聞き、荷物を積んで、町の外へと向かう。
門にはたくさんの兵士がいた。これから、ルイジェルド退治にでも出かけるのかもしれない。
その中に、見た顔があった。トカゲ頭と豚頭だ。彼らは青ざめつつも、興奮した表情だった。
話しかけると、先ほど『デッドエンド』が出ていったから気をつけろ、と忠告をもらう。
そこから、やれデッドエンドは悪魔だの、町中で一体なにをやらかそうとしていたのかだの、ルイジェルドを見たこともないくせに憶測だけで悪と決めつける発言が続いた。
「あの人は、二ヶ月近く町中にいましたけど、何一つ問題なんか起こしていませんよ」
耐え切れず、そう言った。門番は「はぁ?」という顔をしていた。
俺は二人を睨み、舌打ちを一つ、町の外へと出た。
心がささくれ立っていた。
ルイジェルドと再会しなければいけない。
彼はまだ近くにいるだろうか。いや、いるはずだ。
彼の戦士としての誇りが本物であるなら。俺たちを……いや、エリスを見捨てるはずがない。
「このぐらいでいいか」
町が見えなくなったぐらいで、空に向かって魔術で花火を上げた。
轟音が響く。熱が降り注ぎ、光が散る。しばらく待つも、ルイジェルドは現れない。
「エリスも、ルイジェルドを呼んでください」
エリスが大音声でルイジェルドを呼ぶ。大きな声だ。
しばらくして現れたのは、パクスコヨーテだった。虫の居所が悪い俺は、そいつらに八つ当たりした。周辺の岩場はキレイな広場に、パクスコヨーテは肉片になった。
こうやってバラバラにしてもゾンビとして復活するのだろうか。
ふん、知ったこっちゃないな。あんな町の連中なんて。
「見て、ルイジェルドよ」
戦闘が終わった頃、ルイジェルドが姿を見せた。
彼はバツの悪そうな顔をしていた。そんな顔はしないでほしい。
「なんで呼んですぐに現れなかったんですか? 黙っていなくなるつもりだったんですか?」
けど、なぜか俺の口から出てきたのは、彼を責めるような詰問口調だった。
そんなつもりじゃなかったのに。
「すまん」
開口一番、謝られた。居心地が悪い。
どう考えても、俺が悪いのだ。
調子に乗って、ジャリルたちを仲間に引き入れて、安易な方法で先に進もうとして、悪事がバレてつけこまれて、でも何とかなると簡単に考えて、八方塞がりになって……。
そして、ルイジェルドに尻拭いをしてもらったのだ。彼が泥をかぶってくれなければ、俺たちはあの町に縛られ続けることになったかもしれない。
いや、ノコパラは、あの道のプロだ。クルトたちがいなくても、俺たちを追い詰めただろう。
「なんで謝るんですか。謝るのは、こっちの方ですよ」
いたたまれなかった。
「いや、お前は、やれるだけのことをやっていた」
「でも」
「作戦に失敗はつきものだ。俺はお前が、日夜神経を磨り減らして、あれこれと考えていたのを知っている」
ルイジェルドはふっと笑い、俺の頭に手を載せた。
「まあ、お前は何を考えているのかわからなかったし、今日まではそれが、良からぬ企みだと思っていた。ゆえに、我慢できないことも多かったが」
ルイジェルドはエリスを見て、うんと頷いた。
「お前はあるものを守ろうと必死なだけだったのだな。先ほど、お前がヤツを殺そうとした時、その覚悟を見せてもらった」
先ほどって、ああ、町を水没させようとした時か。
「守るべきものがあるお前は戦士だ」
戦士だと言われて──涙が出そうになった。
俺はそんな立派じゃない。浅ましく金儲けを考えて、損得だけを考えて、ルイジェルドを切り捨てようとまでしたのだ。
最後の最後に頼れる相手を捨てようとしたのだ。
「ルイジェルドさん、僕……いや、俺は……」
真摯な言葉で、自分の言葉で。敬語なんて鎧を付けない、俺自身の言葉で、しかし、何を言おうとしたのかは、わからない。
「言うな」
ルイジェルドは俺の言葉を、遮った。
「これからは、俺のことは後回しにしろ」
「え?」
「安心しろ。悪評の回復をせずとも、俺はお前たちを守る。信用しろ。いや、信用してくれ」
信用はしている。信頼もしている。やらなくてもいい。
なるほど、確かにルイジェルドの名前を売るという行為は骨だ。
目的を二つ持てば、行動も曖昧になる。無理も出てくる。最近の俺の精神的なストレスは相当なものだった。考えられることも考えられず、思いつくことも思いつかなかった。結果として、今回のような失敗を引き起こす。
だからやらなくてもいい。
だが、納得できるものでもない。あんな光景を目の当たりにして。町中から石を投げられるような光景を見て。はいそうですかと、じゃあ次からは町の外で待っていてくださいねなどと、言えるわけがない。
「いえ、ルイジェルドさんの悪評は、必ず消します」
むしろ、俺は決意を新たにした。
これはせめてもの恩返しだ。次はうまくやってみせる。
自分に無理をさせず、できる範囲でやってみせる。
「懲りないヤツだな。そんなに俺が信用できないか?」
「信用していますよ。だから報いたいんじゃないですか」
俺だって、昔はイジメられていたのだ。
一度貼られたレッテルに苦しみ、何十年も人のいない世界にいた。ロキシーに連れ出してもらわなければ、シルフィやエリスに会うこともなかった。
ルイジェルドと俺とでは、ケースが違う。規模も全然違う。そんなことはわかっている。でも、だからといって。俺がルイジェルドを見捨てる理由にはならない。
ロキシーのように、無自覚的にできるわけではない。俺にできるのは、失敗を続けながら、泥の中を這って進んでいくことだけだ。
ルイジェルドにとってはいい迷惑かもしれない。また今回みたいに失敗して、ルイジェルドに尻拭いさせることになるかもしれない。でもいい。
何もやらないよりはいい。
「……頑固なヤツだな」
「ルイジェルドさんほどじゃありません」
「フッ。じゃあ、よろしく頼む」
ルイジェルドは苦笑し、静かに頷いた。
なぜだろうか。俺はその時、ルイジェルドと、本当の意味で、信頼関係を結んだと思った。
★ ★ ★
翌朝、目を覚ますとルイジェルドがスキンヘッドになっていた。
唖然というか、怖い。
顔の傷も相まって、ヤクザみたいだ。
「今回のことで、人が俺の髪を恐れているとわかったからな」
凄い覚悟だと思ってしまった。俺の常識だと、坊主頭にするということには、決意と反省の意味がある。この世界には、そんな常識はない。ないのだが……。
この行動を見ると、俺も頭を丸めないといけない気がしてきた。
反省には、行動を。
ルイジェルドがやったのなら、俺も坊主にすべきではないのか。いや、でも、しかし……。
「え、エリス、俺もああいう風にしたほうがいいかな?」
「ダメよ。私、ルーデウスの髪、結構好きだもん」
エリスを逃げ場に使った不甲斐ない俺を、笑え。
第十四話 「旅の始まり」
魔大陸という言葉を聞くと、ド○クエ世代の俺としては、魔界という単語を思い浮かべる。
魔王が統治し、魔物たちの小さな村があり、人々の忘れられた祠があり、強力な魔物がそこらを闊歩する場所だ。
しかし、この世界では違う。まず、魔王が統治していない。
魔王がいないわけではない。現在、魔王はアバウトに三〇名ぐらいいて、それぞれがそれぞれで適当に君臨している。
しかし、統治はしていない。あくまで魔王と名乗り、偉そうにしているだけだ。
一応、魔王はそれぞれ親衛隊だか騎士団だか、かっこいい名前のついた軍事力を持っている。リカリスの町を守っていた衛兵もそれに当たる。彼らは冒険者とは別に、周囲の魔物を退治したり、町中にいる犯罪者を逮捕したりと、独自に自分たちの住む町を守っている。軍隊というよりは、自警団という意味合いが強いようだ。
そのへんの魔王と自警団の関係についてはよくわからない。
魔王が任命しているのか、それとも自警団が勝手に魔王の配下を名乗っているのか。魔王が戦争をすると決めれば、彼らが魔王軍となるわけだから、何らかの契約はなされているのだろう。
現在は互いに戦争するということもなく平和であるが、あくまで平和なのは魔王の周辺だけであり、魔大陸の大半が無法地帯となっている。サザ○クロスと聖○十字陵の周辺は平和でも、その間の道のりでは無所属のモヒカンが跋扈しているというわけだ。
ちなみに、リカリスの町周辺は、『バーディガーディ』という魔王が君臨している。
六本腕で黒い肌、筋肉ムキムキマッチョマンの大魔王らしい。もっとも、現在は放浪の旅に出ていて、行方不明なのだとか。実にフリーダムだ。
魔大陸には強力な魔物が出没する。冒険者ギルドにおいて、最もランクの低い討伐依頼はCランクである。逆に言えば、この大陸にはCランク以上の敵しかいない。ストーントゥレントで、ギリギリDランクか。
とはいえ、魔族は種族的に人族よりも強い。その上、種族ごとの特性もあるため、集団戦も非常にうまい。Bランクに上がるのに壁はあるが、魔大陸のBランク冒険者は他の大陸の冒険者より質が上だ。
上がれないヤツはノコパラやジャリルみたいになる。そう考えると、ルイジェルドは異常だ。
彼はAランクの魔物なら、一人で倒せると豪語する。質の高いBランク冒険者六~七人より強いのだから。『デッドエンド』の二つ名は伊達じゃない。
そんな人物の信頼を得られたことを、純粋に嬉しく思う。
★ ★ ★
リカリスの町を出立して三日が経過した。
ルイジェルドと信頼関係を結べて安心したせいか、最近、俺の食欲が旺盛になり始めた。
食材はよろしくない。俺たちの主食は大王陸亀の肉だ。美味しくない。不味い。
なので、俺はちょいと工夫することにした。
焼くのがダメならば調理法を変えるのだ。
魔術で作り出した土鍋、魔術で作り出したグレイラット家の美味しい水、魔術で作り出した火力の強いコンロ(人力)。この三つを使い、煮ることにした。
水は貴重だが、俺ならば無限に作り出せる。本当は圧力鍋で柔らかく調理したいと思ったが、試してみたところ、爆発しそうになったのでやめた。
時間は掛かるが、ガス代も水道代も無料だ。じっくりコトコト愛情を込めて煮込めばいいのだ。
土魔術を使った調理器具は、使い捨てできるため、便利だ。
そのうち、燻製も試してみたいが、ストーントゥレントのチップでは美味しくならなさそうだ。
ともあれ、これで大王陸亀の肉は、マシになった。
硬くて不味い肉が、柔らかくて不味い肉に変化した。
うん、不味い。煮たところで、やはり特有の臭みは残っているし、不味いものは不味い。
おかしな話だ。ミグルドの里で食べた時はもうちょっと美味しかった。
何が足りないのだろうかと、そこで俺は思い出した。
ミグルドの里で栽培されていた植物だ。最初に見た時は、枯れかけの作物だ、と思ったのだが、違う。あれは恐らく、香草の一種だ。肉の臭みを取り、より美味しくするための彼らの知恵なのだ。
ロキシーの「苦くて美味しくない」という言葉にすっかり騙されてしまった。
あれは野菜だが、そのまま食べるものではないのだ。
まったく、うちの師匠はドジっ娘で困る。
次の町に赴いたのなら、そうした香辛料を買い込もう。他にも、使えそうな食材があったら色々試してみたい……無駄遣いになるだろうか。
魔大陸では、基本的に食料が高額だ。植物がほとんど育たない地域であるせいか、特に野菜類が高い。細い高麗人蔘みたいなのが、肉五キロと物々交換されたりする。
大王陸亀は安い。主食であるといえよう。五トントラック以上の大きさを持つあの亀は、一匹狩るだけでかなりの世帯が何日も食っていける。
かといって、それで町中の全世帯がまかなえるはずもない。時にはパクスコヨーテを食ったり、トゥレントに寄生する虫の幼虫を食ったりする。
さすがに、虫ともなるとエリスも遠慮気味だった。
俺だってゴメンだ。
この大陸の食文化は、俺には合わない。
大王陸亀の肉は、調理次第ではまだ食える。低い食文化の水準の中では、まぁ、美味しい部類だ。焼くだけで美味いというルイジェルドの言葉にも、ギリギリ頷ける。
だが、やはり香辛料は必要だ。
二人はあまり必要としていないようだが、俺には必要だ。つまり俺の独断で買うことになる。だが、独断はよくない。俺たちは、チームだからな。
チームなら、何事も相談する習慣をつけたほうがいいだろう。
★ ★ ★
「全員集合!」
さぁ寝るぞと、枕代わりになる布の塊をどこに置くか迷っていたエリスと、目をつぶり、周囲の索敵をしていたルイジェルドを呼び寄せる。
「いまから会議をしたいと思います」
「……会議?」
エリスは首をかしげた。
「はい、これから旅をするにあたって、色々問題が起きると思います。その時になって、三人が意見を違えて喧嘩しないように、大まかな事柄を先に話し合って決めておくんです」
「それって……」
エリスは訝しげな表情を作った。やはり、彼女はそうした細かいことに参加するのは嫌だろうか。いっそのこと、ルイジェルドと二人で話し合ってもいいのだが、仲間ハズレはよくない。
彼女は荷物ではないし、やはりこうした相談事には参加させなければ。
「それって、あれよね。いつもルーデウスたちが月に一回やってたやつよね?」
月一回? ああ、フィットア領で家庭教師をしていた時に他の家庭教師連中とやっていた職員会議のことか。
そういえば、そんなのもやってたな。
「そうです。それの冒険者バージョンです」
エリスは口元をキュっと閉じると、すとんと俺の前に座った。真面目な顔をしようとしているが、口元にニマニマ笑いが張り付いている。
なんだろう。さして面白いものでもないんだが……まぁ、嫌がられるよりいいか。
「それは、俺も参加するのか?」
ルイジェルドの疑問。むしろ、お前が参加しないでどうするとツッコミたい。
「もちろんです。こういう話し合いは、戦士団の頃にはしなかったんですか?」
「していない。俺が全て一人で決めていた」
普通はそういうものらしい。リーダーのいうことを聞きなさい、ってヤツだ。
でも、俺は民主主義の国の出身だ。
「今日からは、三人で話し合い、三人で決めていきましょう」
「了解した」
ルイジェルドは素直に頷き、座った。焚き火の脇で、俺たち三人は車座になった。
「よし。では第一回『デッドエンド作戦会議』を始めます。拍手」
パチパチパチと、三人でそれぞれ拍手をする。
「ルーデウス、なんで拍手するの?」
「そういうものです」
「ギレーヌたちとの時はやってなかったじゃない」
なんで知ってるんだ? まあ、いいけどさ。
「記念すべき一回目だから拍手するんです」
職員会議ではしなかったけど、今は冒険者だ。盛り上げていかないとな。
「こほん。さて、前回、僕は盛大な失敗をしました」
「いや、お前のは失敗ではなく」
「シャラップ! ルイジェルドさん、発言をする時は、話が終わった後、挙手でお願いします」
ヒステリックな三角メガネっぽく、そう言った。
「わかった」
「よろしい」
ルイジェルドが気圧されたように黙ったのを見て、俺は続ける。
「失敗の原因は、いくつか思い当たります」
情報収集を怠ったこと、金儲けばかりを考えたこと、一石二鳥を狙いすぎたこと、エトセトラ。
ま、ソレらはそれぞれ気をつけるとして。
「予防策として、これからは報告・連絡・相談を密にしていこうと思います。この三つは『ほうれんそう』といって、実に重要なものです」
「ほうれんそう……か」
ほうれんそう。とても重要だ。一缶飲むだけで、屈強な大男を星の彼方までぶっとばせる。
「はい。ほうれんそうです。何かをする時は、まず相談!」
「ふむ。具体的にはどうすればいい?」
「やりたいことや困ったことがあったら、その都度聞いてください」
実際、社会で相談というのがどういうことをするのかは知らないが……。
まあ、難しいことは置いておこう。俺たちにやれることをやればいいのだ。
「僕も二人に聞きます。聞かれたほうは、考えてください。やるべきか、やらざるべきか、そうすれば、案外相手の気づいていない名案が出てくるかもしれません」
思えば、俺はルイジェルドに相談せずに決めることが多かった。俺は口では彼を信用していると言っていたが、心の底では彼を信用していなかったのかもしれない。
「そして、連絡。何か気づいたり何かわかったら口に出し、周囲のもう一人に伝えてください」
エリスがうんうんと難しそうに頷いている。わかっているんだろうか。
「最後に、報告。途中経過も重要ですが、失敗したか、成功したかだけでもいいです。これは、僕に伝えてください」
一応リーダーだからな。自覚を持っていこう。
「ここまでで質問は?」
「ない、続けてくれ」
「はい!」
ルイジェルドが首を振り、エリスが手を上げた。
「はい、エリス」
「三人で相談はするけど、ルーデウスが決めるのよね?」
「まあ、最終的には、そうなりますね」
「じゃあ、最初からルーデウスが全部決めればいいんじゃないの?」
「僕ひとりじゃ考えられる範囲に限界があります」
「でも、私じゃルーデウスの考えられなかったことなんて思いつけないわ!」
そう言ってもらえるのはありがたいが、ハッキリ言わせてもらうと、俺だって安心が欲しいのだ。
相談して、大丈夫よ、あなたならできるわ、と言ってもらいたいのだ。
「思いつけなくても、エリスの言葉がヒントになって、何かいい考えが浮かぶかもしれません」
「そうかしら……」
エリスはよくわかっていないという顔だ。まあ、最初のうちはしょうがないだろう。
頭を使うのが重要なのだ。
「さて、とりあえず、今後のことについて決めていきたいと思います」
今後のこと。十分な準備はできなかったが、旅は始まった。
行き当たりばったりになるが、やっていくしかない。
「まず目的地ですが、最終目的地はアスラ王国になります。中央大陸西部です。これはいいですね」
二人は頷く。しかし魔大陸から中央大陸には渡れない。
航路がないからだ。この世界では、海は海族が支配している。決められた航路以外は通れない。
「ルイジェルドさん、ミリス大陸には、どこから渡れますか?」
「魔大陸最南端の港町、ウェンポートから船が出ている」
ゆえに中央大陸に行きたければ、魔大陸の南端→ミリス大陸。ミリス大陸を縦断。ミリス大陸の西端→中央大陸の東南端というルートを通る必要がある。
もっとも、裏ワザのようなルートもある。
魔大陸の北西から、天大陸へと渡る道だ。このルートを通れば、ミリス大陸を経由しなくとも中央大陸に至れる。中央大陸に至りたいだけなら、理論上は数ヶ月は短縮できる。
だが、このルートは口で言うほど容易くはない。
天大陸は断崖絶壁の上にある大陸である。翼でもなければ上に上がることはできないから、岸壁を伝っていくことになる。足場はなく、道はなく、魔物も大量にいる。生存率五%とか言われている過酷なルートだ。
しかも、そこを抜けても、待っているのは中央大陸で最も過酷な北方大地であるため、賞金稼ぎに追われる犯罪者ぐらいしか通らない。
あくまでも、理論上の話だ。実際には、もっと時間が掛かるだろう。
結果として旅程日数にそれほど差が出るわけでもなく、わざわざ危険を犯す必要はない。
というわけで、俺たちが向かう先は、南だ。
「船賃はいくら掛かるかわかりますか?」
「わからん」
「そこまでの道のりは、どれぐらい掛かりますか?」
「かなり掛かるな。休みなく移動して……半年ぐらいではないか?」
休みなく移動して半年、遠いな。
「何か移動手段はありませんかね、転移魔法陣とか」
「転移魔法陣は、第二次人魔大戦の折に禁術として指定されたと聞く。探せばどこかに残っているかもしれんが、使うのは難しいだろう」
適当に言ってみたのだが、あるのか、旅○扉。
「結局、地面を歩いて移動するしかないってことですか?」
「そうだな」
高速で移動する手段はないらしい。半年も移動し続ける……うーむ。いや、半年、移動し続けると考えるからいけないのだ。少しずつ移動する。町から町へ。そう考えればいい。
千里の道も一歩から、ってやつだ。
「とりあえず、最南端の港町ウェンポートを目指すとして、次の町まではどれぐらい掛かりますか?」
「二週間ほどで、大きな町に着くはずだ」
二週間。そんなもんか、町から町の距離は。
「冒険者ギルドはありますかね」
「あるだろうな」
ルイジェルド曰く、昔は種族ごとに集落を作り、彼らの情報交換、物々交換の場として、町がある。
ゆえに、小さい町というものは存在せず、種族の戦士たちが寄り集まる冒険者ギルドも、当然のように存在する。
また、昔は冒険者ギルドはなく、町を守るのは、各種族から代表して選ばれた戦士たちだったそうだ。戦うことの少ない種族のために、戦える者の多い種族が戦士を出向させることもあったのだとか。
スペルド族とミグルド族の関係がそんな感じだったらしい。
そんな種族間の関係の繋がりを強めるために、別種族同士で結婚する、ということもあったという。
どうりで、魔族は雑多な種族が多いわけだ。ハーフやクォーターだらけなのだろう。
っと、話が逸れたな。
「では、僕らは冒険者ギルドのある町を転々と移動することにしたいと思います」
そこに一週間から二週間ほど滞在。冒険者資格が剥奪されていなければ、冒険者としての依頼を受けつつ、『デッドエンド』の名前を売っていく。
そして、次の町までの旅費が貯まり次第、町を出立する。
「というのが、一連の流れですが、何か質問、あるいは意見はありますか?」
ルイジェルドが挙手。
「別に、俺の名前は売らなくてもいい。そのために髪も切った。今の俺は、スペルド族ではない」
「ま、名前を売るのは依頼のついでですよ、ついで」
ヴェスケルたちの働きでわかった。特別なことをする必要はないのだ。
誠心誠意仕事をして、うまくいけば、『デッドエンドのルイジェルド』と名乗る。
ダメなら、ルーデウスと名乗る、それだけだ。次から、『デッドエンド』の汚名は、俺が被るのだ。
でも、そのことはルイジェルドにはナイショだよ。
え? 相談が大事って決めた後で勝手に決めるなって?
細けぇこたぁいいんだよ。
「あと、滞在中にすることで、何か質問はありますか?」
「はいっ!」
「はいどうぞ、エリス君」
このノリ、懐かしいな。授業中みたいだ。
「昔やっていたみたいに、お店の値段を調べたりはしないの?」
「市場調査ですか?」
ふむ。そういえば、リカリスの町ではサボっていたな。
あの町では、本当に行き当たりバッタリだった。運搬用のトカゲだって、相場を知っていれば、もう少し安く手に入ったかもしれない。
「やっていきましょう。値段を知ることは、金をうまく使うことの第一歩ですからね。他には何かありますか?」
ルイジェルドとエリスは無言で顔を見合わせた。
ないようだ。まあ、とりあえずはこんなものだろう。先に進むにつれて、問題も出てくるだろう。その時は、喧嘩せずにゆっくり話し合えばいいのだ。
「では、明日から、よろしくお願いします」
そう言って、俺は二人に頭を下げた。
こうして、俺たちの旅は始まった。
★ ★ ★
次の町で、ルイジェルドがスペルド族と認識されることはなかった。
眉毛まで剃ったせいだろうか、魔大陸では、髪型をガッチリ整えるといった文化もないらしい。種族ごとの外見を大切にしているのだろう。
門番には快く迎えいれてもらえた。
ルイジェルドの見た目は茶坊主というか、どう見てもマフィアか右翼にしか見えないのだが、町中にはもっと物騒な顔をした奴らもいるからだろう。
それと、やはり、冒険者らしい格好をしていると違うらしく、本当によく来たと歓迎された。
ルイジェルドも、こんな快く迎えられたのは初めてだと嬉しそうに言った。
外見は大丈夫でも、パーティ名が『デッドエンド』であるとギルドにいうと、周囲から「大丈夫か?」なんて疑問が飛んでくる。本物なので大丈夫というと、大抵は笑い声が上がった。
この方法は相変わらず有効らしい。
知らない場所でも簡単に受け入れられる。デッドエンドという存在のネームバリューは、今となってはありがたかった。
町に来て、宿に泊まれば作戦会議。
今回の議題は、エリスから。「洗濯中にルーデウスが私のパンツの匂いを嗅いでいる、やめてほしい」と、真顔で言われ、俺はエリスのパンツに触ることを禁止された。
しかし、そうなると洗濯ができるのはルイジェルドだけとなる。
こんな子供と見れば頭を撫でずにはいられないようなロリコン野郎に可愛いエリスのパンツを渡すわけにはいかないというわけで、エリスに洗濯を覚えてもらった。
本日から、洗濯はエリスの担当である。
と、思ったら、彼女はコッソリ、俺のパンツの匂いを嗅いでいた。
でも、俺は決してやめてほしいなんて言わない。それが男の度量ってもんだろ?
情報収集はそう難しくなかった。
冒険者ギルドを利用すれば、大抵のことはわかった。子供のフリをして、他の冒険者に聞くだけだ。ホント、楽だった。このまま子供でいたいと思ったぐらい、なんでも教えてくれた。
調子に乗って、グラマラスな女冒険者にスリーサイズを聞こうとしたら、エリスにマウントを取られた。
この世界には、タップという概念がない。
そんな感じで町から町へと渡り歩きながら、俺たちはどんどん南へと移動していく。
一ヶ月、二ヶ月と。
ある日を境に、エリスは魔神語を習いだした。
ロキシーの教科書がないので詳しいことは教えられないが、俺とルイジェルド、二人の教師がいるため、彼女もすぐに覚えられそうだ。アスラ王国にいた頃は読み書きなんてちっとも覚えられなかったのに……やはり、環境は人を変えるようだ。
自分だけ会話が通じないと、ストレスも半端ないしな。
「わ、わたし、は、エリス・ボレアス・グレイラット……です」
「はい、できていますよ、お嬢様」
『ほんと!?』
まあ、まだまだ会話には程遠いが……。
山本五十六も言っている。
『やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず』
なので、俺は褒めて伸ばす。
『さすがお嬢様ですぅ! さすがですぅ! シビレますぅ!』
『……なんかバカにしてない?』
『いえいえいえいえそんなまさか』
ちょっと調子に乗りすぎたか……褒めればいいってもんじゃないな、うん。
『ねえ、でももうすぐ魔大陸から出るんでしょう?』
『その予定です。次はミリス大陸ですね』
もうすぐといっても、まだまだ先は長いがね。
『じゃあ、もしかして、魔神語を覚えても意味ないんじゃ……?』
『また来るかもしれないじゃないですか』
必要にかられてやる気になったとはいえ、エリスは相変わらず勉強嫌いのようだ。
そんな彼女は俺に魔神語を教わりつつ、ルイジェルドに戦い方を教わっていた。
最初の頃は、俺もそれに参加していたのだが、正直ついていけなかった。
ルイジェルドの指導は、ただひたすら、無言で打ち合いをするだけだ。最終的には、指導を受ける側は地面に転がされ、あるいは喉元に槍を突きつけられる。
そして、ルイジェルドが「わかったか?」と聞く。
俺にはわからない。何度やってもわからない。
だが、エリスには理解できるらしく、たまに、ハッとした顔で「わかったわ」と、言う。
何がわかるというのだろうかと聞かれれば、俺もなんとなくはわかる。
恐らく、ルイジェルドはこちらの悪い部分を、戦いの中で突いているのだ。
戦いとは流動的で、動かせる部分は多い。だからこそ、口ではなく実際にやっているのだ。
けど、だからといって、理解できるものではない。それがわかるのなら、俺はもっと強くなっていたはずだ。
多分、エリスは天才だ。きっと、戦いに関しては、俺の及ばないところにいる。
正直なところ、俺はルイジェルドの戦いの理論がチンプンカンプンだった。
だが、エリスにはわかる。
「わかったわ」というのは口だけじゃなく、何かを理解しているのだ。
そして、事実、エリスは強くなっている。彼女の戦闘力は飛躍的に向上している。
まだまだギレーヌには及ばないだろうが、もしかすると、パウロはそろそろ超えているかもしれない……もしかすると、魔術を使った俺より強いんじゃないだろうか。
俺も、色々考えないといけない。
エリスが成長しているのに、俺が今のままでは、立つ瀬がない。
なんとかして、強くなりたいと思い、エリスの目を盗んで、ルイジェルドに本気で挑んでみたことがある。
本気といっても、パウロを想定していた時のような、接近戦での戦い方でだが……。
結論から言うと、負けた。
完敗だった。
ルイジェルドには、俺の考えてきた接近戦用の魔術が、何一つ通じなかった。
「悪くはない。お前は魔術師としては完成の域にある」
負けたはずなのに、そう言われた。昔、ギレーヌにも似たようなことを言われた気がする。
「だが、考え方は良くない。俺に接近戦で勝とうとする必要はない」
近すぎるのだと言われた。相手の土俵に上がるから苦戦するのだ、と。
そんなことはわかっているが、だからといって、いつも遠距離から戦いを始められるとは限らないじゃないか。
「じゃあ、どうすればいいんですか?」
「さてな。俺も魔術は専門外だからな……。魔術を交えての接近戦といえば、龍族が得意としているらしいが、俺はペルギウスの戦いを少しだけ見たことがあるだけだ、参考にはならん」
「ペルギウスって、あの空中城塞の人ですよね? どんな戦い方だったんですか?」
「ああ、ヤツは前龍門と後龍門を召喚し、自分は魔力爪を使って戦っていた」
召喚。召喚魔術は知らないんだよな……。
「その、前龍門と後龍門というのは、どういう召喚魔術なんですか?」
「詳しくは知らんが、前龍門は相手の魔力を常に吸収し、後龍門は吸収した魔力を自分のものにする、という感じだった」
ゆえに、ペルギウス相手には長期戦になればなるほど不利になる。
ラプラスは圧倒的な魔力総量を誇ったがゆえに、あまり効果がなかったらしいが……。
並の戦士なら、五分もたたないうちに体中の魔力を吸収されて気絶するらしい。
「卑怯な戦い方ですね」
「…………そうか?」
ルイジェルドなら、それを卑怯だと言うかと思ったが、そうでもないらしい。
やはり、宿敵ラプラスに一矢報いた仲間意識でもあるのだろうか。
「そう焦るな。お前の年齢を考えれば、本格的に強くなれるのはこれからだ」
最終的に、ルイジェルドはそう言って、俺の頭を撫でた。
戦士として見てはくれているようだが、ルイジェルドは俺の頭を撫でる。
単純に、子供の頭を撫でるのが好きなのだ、この男は。
しかし、でも、どうすれば強くなれるんだろうか……。
なんて悩みつつも、南へ、南へ。
町に着き、依頼を受けて、名前を売り、金を貯めて、次の町へ。
同じことを繰り返しながら、ただひたすら、南へ。
五ヶ月、六ヶ月。
旅の途中、ルイジェルドに勝負を挑んでくる者がいた。
「我こそは北神カールマンが直弟子『孔雀剣のオーベール』! の、三番弟子のロドリゲス!」
最初は賞金稼ぎかと思った。
知らん間にルイジェルドに賞金が懸けられたのかと思ったのだ。
「その物腰、さぞ名のある御仁とお見受けした! 立ち合いを所望したい!」
しかし、どうやら違うらしい。
彼は武者修行のために魔大陸を旅している者だと名乗った。
「ルイジェルドさん、どうします?」
「こういう手合いは久しぶりだな」
ルイジェルド曰く、魔大陸には武者修行者も多いらしい。魔大陸は魔物も強く、その魔物を退治する冒険者たちも強い。修行しようなんて考えている輩にはうってつけの場所なのだとか。
意味もなく強くなってどうすんだろうな。
「俺は受けてもいいが、どうすればいい?」
「僕は断ってもいいと思いますけど、どうしたいです?」
「俺は戦士だ。手合わせしたいというのなら、相手をしたい」
受けたいなら最初からそう言えよということで、ルールを決めることにした。
一.殺し合いはなし、止めは刺さないこと
二.こちらが名乗るのは、勝負の後であること
三.勝っても負けても禍根を残さないこと
相手は快く承諾してくれて、決闘開始。
ルイジェルドは勝った。相手の全力を受けきるような動きで、勝った。手加減をしている、という感じではなく、ローリスクに動き、相手の動きを完全に制したのだ。
「完敗だ。こんな強い者がいるとは……世界はまだまだ広いな! で、名前はなんと言うのだ?」
「ルイジェルド・スペルディアだ。『デッドエンド』と呼ばれている」
「なに、あの『デッドエンド』か!? 魔大陸で何度も噂を聞いたぞ。恐ろしいスペルド族の男がいるとな!」
戦いが終わると、彼は驚いた。
意外と、人族はスペルド族の特徴を知らないのだ。スペルド族が槍を使っているだとか、額に赤い宝石があるだとか、そういうことを知らない者が多い。
人族の常識では、スペルド族の特徴は髪がエメラルドグリーンって部分だけなのだ。
エメラルドグリーンの髪。戦争から四〇〇年も経った今では、ただそれだけが迫害の理由なのだ。
髪が緑なだけでイジメられる、俺には到底理解できない。
「しかし髪がないようだが?」
「故あって、剃った」
「り、理由は聞かないほうがよさそうだな……」
明らかに強い相手、恐怖の象徴スペルド族、中でも最も凶悪とされる人物。
恐れて当然の相手だが、そこはやはり、武人同士。何か通じるものがあるらしい。
強さを基準で生きる人々にとって、ルイジェルドは尊敬に値する人物なのだ。
「まさか、歴史上の人物と手合わせしてもらえるとは……! これは故郷で自慢できるな!」
大抵の相手は、嬉しそうにしていた。
まるで、道端でハリウッドスターにでも会ったかのような、しかも、気難しいと思われていたそのスターが、意外とフレンドリーだった時のような、そんな喜び方だった。
「我こそは────」
そいつを皮切りに、ルイジェルドは挑まれ続けた。
南に行けば行くほど、そういう手合いが増えた。武者修行者の中には学のあるやつもいて、ルイジェルドが四〇〇年前の戦争時のスペルド族の戦士団のリーダーと同じ名前だと指摘する者もいた。
同一人物だと言うと、大層驚いていた。
その人物には、ルイジェルドの戦争話が一昼夜を掛けて語られることとなった。
ルイジェルドおじいちゃんの昔話は長いが、誇張なしで語られるその実話は、武人にとって興奮するものであるらしい。特に、一〇〇〇人の包囲を抜け、長い時間潜伏し、ラプラスに一矢報いるくだりには、武人も男泣きに涙を流した。
この話を本にして流通させれば、案外スペルド族の見方も変わるかもしれない。
『実録! 正義なき戦い 魔大陸死闘篇!』とか『誰も知らない歴史の真実 スペルド族編』とか、そんな感じで。
土魔術を使えば印刷はできるからな。
さらに、俺は四ヶ大陸語を扱える。ま、国の法律に抵触して捕まる可能性もあるが……。
頭の片隅には置いておくことにしよう。
「じゃあな、ありがとう! 勉強になった」
武者修行者たちは、誰もが嬉しそうに別れた。喧嘩別れをすることは一切なかった。それもこれも、みんな髪を剃ったおかげだろう。
もう、スペルド族は全員スキンヘッドにすればいいんじゃないかな?
そうして、南へ、南へ。
俺たちは旅をする。
八ヶ月、九ヶ月。
もちろん、順調なだけじゃない。
問題は何度も起きた。
言葉を理解したことで、嘲笑にブチ切れたエリスが喧嘩することもあった。ルイジェルドがスペルド族だとバレて、追い出されることもあった。また、俺がエリスの水浴びを覗こうとして、ルイジェルドに首根っこを掴まれて引き戻されることも多々あった。
似たような問題は何度も起きた。
最初の頃は、問題が起きるたびにヤキモキしたものだ。
直さなきゃ、どうにかしなきゃ、と思った。
けれど、考えてみれば、だ。
エリスは喧嘩をする時には絶対に剣を抜かなかった。ルイジェルドも、追い出される時は最初の時のような騒乱は起きなかった。
町で仲良くなった衛兵から「すまんな、スペルド族だと、やっぱり怖がるヤツがいるからな」と申し訳なさそうに言われることもあった。
そして俺は、結局一回もエリスの水浴びを覗くことはできなかった。
どれも小さな問題だった。
大問題には発展していない。
だからか、そのうち気にしなくなった。エリスは乱暴者だし、ルイジェルドはスペルド族だし、俺はスケベだ。生まれた時からそうだったのだ、今更直そうと思ったって、直るもんじゃない。
ま、やれることはやっているのだ。
失敗しても後からフォローすればいい。
気楽にいこう、気楽に。
途中からは、そう思えるようになっていった。
決して、失敗を軽くみているつもりはない。
ただ、肩の力を抜くという、当たり前のことを実践できるようになっただけだ。
簡単で当たり前のこと。
そんなことを、俺はこの旅で、ルイジェルドと共に行動することで、学ぶことができたのだ。
そうやって、旅を続けて約一年が経過。
俺たちはいつしかAランクの冒険者になり──。
魔大陸最南端、港町ウェンポートへとたどり着くこととなる。
番外編 「アスラ王女と奇跡の天使」
アスラ王国王都アルスは全世界で最も人口が多く、そして最も巨大な都である。
その巨大な都の中央にあるのは、やはり世界で最も大きく美しいと言われる白亜の城。
王城シルバーパレス。
だが、その城の内部にあるのは、外見とは似ても似つかぬドロドロとした汚い政争である。
貴族同士の騙し合い、化かし合い。
夜討ち、朝駆け。
この城の中は、誰も信用できないと言われるほどの魔境であった。
フィットア領消滅事件は、そんな政争にも大きな影響を与えることとなる。
今回は、その発端となった事件を語ろう。
★ ★ ★
シルバーパレス内部には、王族貴族の住居の他に、数々の庭園が存在している。
赤い花を持つ植物を集めた、薔薇の園。
黒い花を持つ植物を集めた、牡丹の園。
青い花を持つ植物を集めた、紫陽花の園。
そして、白い花を咲かせる植物を集めた庭園。
通称、白百合の園。
その白百合の園は、ある人物のお気に入りであった。
その人物とは、アリエル・アネモイ・アスラ。
アスラ王国第二王女。
絶世の美女と呼ばれた第一王妃の美貌と輝く金髪、歴代最高と呼ばれた国王の美声を受け継いだ彼女は、まだ成人前だというのに溢れんばかりのカリスマを持ち、王都にいる大半の民衆より歴代最高の美姫として人気があった。
そんな彼女には三日に一度、この白百合の園で紅茶を飲む習慣がある。
白百合の園に備え付けられた白のテーブルに座り、己の護衛騎士、守護術師を従えて、一人で静かにお茶を飲む。
その姿は、同性であってもため息をつくほど可憐で、異性であれば見とれてしまうほどの儚さをもっていた。
お伽話に出てくる妖精のような姿は、近づくことすら無粋であると思わせるに十分であった。
ゆえに、彼女が白百合の園にいる時に、話しかけてくる者はいない。
一緒にお茶を飲もうとする者すら、一切存在しない。
彼女はただ一人椅子に座り、護衛騎士や守護術師と短い言葉を交わしながら、短いティータイムを楽しむのである。
その護衛騎士もまた、美姫に似合いの美男子であった。
護衛騎士は明るい栗色の髪を持ち、高い鼻と尖った顎、彫りの深い顔立ちを持つ美男子。
ルーク・ノトス・グレイラット。
四大地方領主であるグレイラット家の次男坊で、剣神流中級の腕を持つ若き騎士である。
城内で彼のことを知らぬ子女はいない。
齢にして十代前半。年齢に似つかわぬ巧みな話術は女性を飽きさせるということを知らず、彼と話した女子は必ず彼の虜になるとすら言われるほどの、伊達男であった。
同年代の女子にとって最も人気のある男である。
守護術師は二人に比べ、やや年上の人物である。
年上と言っても、成人して間もない、十六か十七といった年齢だろう。
ルークと比べ絶世の美男子というほどではないが、平均から見れば十分すぎるほどの美男子で、やや線の細い、人好きのする顔立ちをしている。
コケティッシュな印象を受ける彼の姿は、美男美女の二人をよく引き立て、三人の姿をより一層近づきがたいものへと変えていた。彼の名はデリック・レッドバット。
名高きレッドバット家の三男で、由緒正しきアスラ魔法学院を卒業した上級魔術師である。
一体彼らがどんな会話をしているのか。
それは城内に住む年若い者たちが最も興味を持つ事柄であったが、誰も知ることはない。
三人は、今日も白百合の園にて、静かに会話をしている。
「……それで、色は何色でしたか?」
アリエルの声が、静かな庭園に響く。
彼女の声は非常に美しく、まさに鈴を転がすようなという形容詞がぴったりであった。
「綺麗なピンク……いえ、ややオレンジ掛かっておりました」
アリエルの前、テーブルの向こう側に立つルークが朗々とした声で答えた。
まだ喉仏が出ていない彼の声はやや高いが、美男子の声はこうであるという予想を裏切らぬ格好のいい声であった。
「……」
そんな二人の会話を、守護術師デリックが静かに聞いている。
その表情は物憂げであり、二人の会話を聞きつつ、その内容を吟味しているかのように思えた。
「私はやはり、白磁のような白に、綺麗な桜色がツンと上を向いているのが好きですね」
「アリエル様、しかしながら、内側にたたまれたものも、それはそれでよろしいものでございます」
「まぁ、ルークは陥没しているものも良いというの?」
アリエルの驚いたような声に、ルークが平然と答える。
「自分は大きければ、それでよいと思っている人間ですゆえ、それ以外の部分にはこだわりませぬ」
「はぁ……ルークは風情がありませんね」
アリエルはため息をつき、ルークは肩を竦めた。
さて、この二人が何の話をしているかというと。
「それで、新しく入ったメイドのサリーシャの具合はどうだったのですか?」
「初々しく、感度も宜しくて、なかなかに良い感じでした」
なんのことはない。
ルークが先日落とした女の子の乳首の色の話をしているだけである。
「そうですか……では、どうにかして私の寝所にも連れ込みたいところですね」
「そういったことならお手伝いしましょう」
「あら、一度抱いた子を、さっさと捨ててしまうのですか?」
「サリーシャの胸は、自分には少々小さすぎますゆえ」
アリエルとルーク。
この二人は、その外見からは似ても似つかぬほど好色であり、下品であった。
二人して宮中のメイドや、中級貴族の娘を食いまくっているのである。
「やはり、可愛い女の子をイジメるというのは、非常に興奮しますからね。サリーシャは良い声で鳴いてくれそうです」
宮中で知る人ぞ知る事実であるが、アリエルは同性もイケる性質であり、極度のサドであった。
アスラの貴族王族は行きすぎた性癖を持つ者が多いが、アリエルもまた例にもれない存在である。
ルークはそこまで極端ではないが、巨乳好きの好色な人物であった。
彼らはその見た目と噂の陰に隠れ、陰謀渦巻くアスラ王宮にて、好き勝手に生きているのだ。
もっとも、アスラの王族貴族の中において、彼らが特別におかしいというわけではない。
大半の貴族は、彼らと同様、いや、それ以上に変態的な趣味趣向を持っていることが多い。
四〇〇年以上の歴史を持ち、戦争や飢餓と無縁なこのアスラ王国では、他者よりも逸脱した行為を好むことをステータスとする人間も多いのだ。
アリエルやルークはまだ若いが、そうした貴族の嗜みにどっぷりと浸かっているのである。
しかし──。
「アリエル様。ルーク。あまり、そのように好き勝手振る舞うのは……よろしくないのではないでしょうか」
デリックはというと、彼は常識人であった。
レッドバット家は元々は地方の中級貴族であり、アスラ王国の退廃的な世界とは無縁の貴族であったためである。
そんな彼が、なぜ第二王女の守護術師などという大役を仰せつかったかというと、単純に魔術学校での成績が良かったからである。貴族の上級魔術師は貴重なのだ。
「デリック……あなたは、もう少しアスラ貴族のことを学んだほうがいいですね」
「そうだデリック。お前はいつもそうだ。場の空気を読むということを覚えたほうがいい。そうでなければ、女の子にモテないからね」
二人に肩を竦められ、デリックはため息をつく。
「そうではありません、アリエル様。あなた様はこれからアスラ王国の国王となられるかもしれないお方。つまらぬ風聞や下らぬ色情で敵を作るのは、好ましくないと申しておるのです」
デリックの言葉に、ため息をついたのはアリエルであった。
「あのねぇデリック。あなた、いつもそう言うけれど、私は第二王女ですよ?」
「そうです。あなたは高い王位継承権を持つ、次期国王候補の一人です」
「上には兄上が二人。姉上が一人いるのです。姉上はすでに嫁ぎ先も決まってしまったようですが、兄上様方は今も国王を目指してしのぎを削っていらっしゃいます。あの方々がいる限り、私が女王になることなど、ありえませんよ」
「いえ、あなたは、正妃様のお子です。正統なるアスラ王家の血を引く、唯一のお方です」
「やめなさいデリック」
デリックの言葉を、アリエルは遮った。
「そんな言葉がお兄さま方の耳に入って、私のところに暗殺者が送られでもしたら、どうするのですか。私に付いて甘い汁を吸おうとする貴族も増えているというのに……」
「アリエル様が自覚を持って戦おうとなされば、暗殺者と戦い、命を失ったとしても、自分はかまいません」
「デリック。物騒なことを言わないで頂戴。それに、私は知っているんですよ。あなたが私たちのことをどう思っているか……そんなことを言ってその気にさせて、いざ戦いとなれば私を見捨てて逃げてしまうのでしょう?」
「なっ……!」
デリックは目を見開いた。
彼はワナワナと体を震わせ、表情を険しく変化させ、ギュッと拳を握りしめた。
「あのね、デリック。私は女王になどならずとも十分なのです。こうして庭園でお茶を飲み、好きなように生きていくだけで十分なのです。どうせ兄上方と戦っても勝ち目はありませんし、なのに積極的に政争に参加するのは、馬鹿馬鹿しい話ですよ?」
アリエルの悟ったような物言いは、的を射ていた。
いくらアリエルの王位継承権の順位が高くても、年齢的にも、味方の数でも負けており、勝ち目は薄い。ならば王などと分不相応なものは早々に諦め、享楽的に生きるのが賢いやり方である。たとえ王にならなかったとしても、アリエルは世界最大の国であるアスラ王国の王女なのだから、それが許されるのだ。
「もう、いいです……」
デリックは、心にモヤモヤとしたものを抱えながら、しかし言葉を見つけることができず、一言そう言って、その場から離れた。
その後ろ姿をアリエルとルークが肩を竦めて見送り、そしてまた、宮中の女子の乳首の色についての談義に戻ったのである。
★ ★ ★
デリックは守護術師としての任務を放棄したわけではない。
向かった先はトイレである。
デリックとルークの任務はアリエルの護衛であるが、人間である以上、生理的なものは付きまとう。どちらかが催した時はもう片方に告げ、素早く済ませるのが彼らの常である。排泄中というのは人が最も無防備になる瞬間であり、襲われやすいというのは異世界であっても変わらない。
デリックは白百合の園の甘ったるい空気に慣れず、最初は催す度にルークに告げてトイレへと赴いていた。だが、慣れというものは恐ろしいもの。何度も何度もトイレへと足を運ぶ度に「デリックは白百合の園では途中でトイレに行く」という常識がアリエルとルークの中に作られ、いつしかいちいちトイレと言わなくてもよい、と命じられるに至った。
アリエルは性的な意味で変態だが、優雅にお茶を楽しんでいるところに厠という無粋な単語を聞きたくないのだ。
そんなデリックは、厠の中に篭り、一人考える。
「はぁ……」
思い出すのは先ほどの会話である。
アリエルは、国王になるつもりなど、まったくないのだと言う。
しかし、デリックはアリエルに王になってほしかった。
決して、アリエルの兄二人、第一王子と第二王子が王に相応しくないと思っているわけではない。彼らが王位を継げば、歴代のアスラ国王に勝らずとも劣らぬ、立派な王となるだろう。
しかしそれではダメなのだ、とデリックは思う。
彼らが王になれば、アスラ王国は今まで通りに腐敗したまま大きくなるだろう。貴族と貴族の醜い争いは続き、その分だけ国の進歩は遅れ、いずれは他国の介入を許してしまうかもしれない。
アスラ王国は飢えとは無縁の土地柄だ。
貴族がどれだけ腐敗し、民から税を搾り取ったとしても、なお民衆は飢えることがないとすら言われている。ゆえに不満はたまりにくく、現状をどうにかしようと思う者も出てこず、大きな反乱や内戦は起きなかった。
それがゆえに、停滞している。
無論、魔術や技術の研究は進んでいるが、それでも技術的なものでは南の王竜王国に、魔術的なものでは北の魔法三大国に、追い抜かれている。まだまだ他の分野ではアスラ王国が圧倒してはいるものの、このまま百年、いや五十年も停滞が進めばどうなるか。
南の王竜王国は、肥沃な土地であるアスラ王国を虎視眈々と狙っている。
山に守られ、他国からの侵略はないと決め込んでいる今のアスラ王国が、五十年後、技術的に進歩した王竜王国に攻め入られればどうなってしまうのか。その時に、魔術的に進歩した魔法三大国が連動して北から攻めてくれば……。
「アリエル様なら、できるのに……」
デリックは、そんな停滞をアリエルなら打破できると考えていた。
デリックはアリエルと初めて出会った時のことを思い出す。
ほんの数年前。王国主催の成人パーティでの出来事だ。
当時のデリックは魔法学院を卒業したばかりだった。デリックは首席でこそなかったものの、優秀な成績で卒業し、数ヶ月後にアスラ王国の魔術師団に入ることが決まっていた。
デリックは自分自身を、優秀ではあるが、珍しくないレベルの魔術師だと認識していた。
そんなデリックの前に現れた、可憐な少女。
アリエルは、当時まだ未成年であったが、来賓としてパーティに来ていた。
幼くも、ハッキリとした口調で祝辞を述べるアリエル。デリックの目には、学院を首席卒業した者よりも聡明に見えた。
その後、魔術師団で働いていたデリックの元に、父親から「王女の守護術師の座が空いているのでダメモトで推挙しようか?」という提案があった際には、一も二もなく飛びついたものだ。
アリエルは行動力のある女性である。今でこそ、昼間はお茶を飲み、夜になったらメイドをお手つきにするだけの毎日を送っているが、実は勤勉で社交的で、自己の発展のための努力を惜しまない性格である。
アリエルが王となり、国力向上のために尽力すれば、アスラ王国はより一層の発展を遂げ、あるいは中央大陸全土を征服することすら、不可能ではないだろう。
なにしろ、アリエルは卓越したカリスマの持ち主であるから。
魔術学院や魔術師団は反社会的な思考を持つ者の巣窟で、現在の政権を牛耳る大臣や、王族貴族を陰ながら批判する者が多かった。
だが、そんな場所にあっても、アリエルを批判する者は一人もいない。
そんな彼女なら、ラプラス戦役の後期に人族のリーダーとなり、終戦後に国王となったガウニス・フリーアン・アスラのように民衆に好かれる王となるに違いない。
アリエルのためなら命を捨てても惜しくない、という者が大勢いる。
デリックもその一人だ。
その覚悟をあのように言われては、デリックとて憤りもする。
「確かに、こんな生活を送っていれば、命の危険はないかもしれないが……これでは、まるでそこらの腐った貴族と変わらないじゃないか……」
それとも、アリエルは、大勢の期待を背負うのが嫌なのだろうか。
自分は、重責を押し付けないと思われたからこそ、守護術師として選ばれたのだろうか。
普段は何も言わないが、実は自分はアリエルに嫌われているのだろうか……。
「はぁ……」
と、そんなことを考えてブルーになっていたデリックの耳に、ふと小さな声が届いた。
「ん?」
厠の裏手で、何者かが話をしているらしい。
「アリエル王女──」
「──殺害──」
小声の中から、不穏な単語を聞き取ったデリックは、即座に息を潜め、壁に耳を当てた。
「やはり、グラーヴェル殿下はアリエル殿下を危険視なさっていると?」
「ああ。あの民衆の人気はただごとではない。さして公共の場に姿を現しているわけでもないのに、自分よりも知名度が高いと嘆かれていた」
「そう考えると、確かにおかしいですな……今はあんな態度を取ってはいるが、裏では王になるための根回しをしているのやもしれませんぞ」
「正面から戦って勝てぬのなら後ろから……というわけですか」
デリックはそれを聞いて、眉を顰めた。
アリエルの民衆人気が高いのは、カリスマのお陰もあるが、第一王子グラーヴェルより、民衆の前に姿を現すことが多いからだ。王宮内での催し物を重視し、王宮外の催し物を欠席するグラーヴェルとは逆に、アリエルは王宮外での催し物に参加することが多い。
例えば王都の脇を通るアルテイル川にかかる大橋の落成式に参加し、橋を渡る最初の一人となったり、魔術学院の開催する大魔術舞闘会に貴賓として参加し、優勝者に花束と賞品を手渡し、手の甲に口づけをする栄誉を与えたり、と。
政争にはなんの関わりもない催し物に参加するからこそ知名度も高く、人気も高いのだ。
「しかし、そうなってくると……」
「ええ、邪魔ですな」
「……後顧の憂いは、絶っておくべきでしょうなぁ」
「それがグラーヴェル殿下の、ひいてはアスラ王国のためになりましょう、そう思って、とっくに手配をしておきました」
「ハッハッハッ。相変わらずお人が悪い」
デリックは、今すぐ出ていき、この二人を殺害しようと考え、即座にその考えを打ち消した。
恐らく、外で会話をしているのは第一王子派の貴族だろう。自分たちの思い通りに事を進めるためには金に糸目を掛けず、どんな汚いことでも平気でやり、いざ自分たちが追い詰められると見苦しく言い逃れをしようとする連中だ。そんな連中は、この王宮内には大勢いる。
ここでデリックが魔術を使い、二人を殺したとしても、意味はない。
アリエルが守護術師に命じ、第一王子派の貴族を殺害した。これはグラーヴェルに敵対する意志があると取られ、第一王子派から執拗な攻撃を受けるだけである。
なし崩し的にでもアリエルが王を目指すのであらば、とも思うデリックであったが、アリエル自身にやる気がなければ、結局は後手後手に回り、追い詰められ、ネズミのようになぶられて殺されるだけである。
デリックは彼らの殺害を諦め、厠を出た。
ともあれ、降りかかる火の粉は払わねばならない。
あの貴族たちは、すでに何者かを手配したと言っていた。となれば、近日中にでもアリエルか、あるいはその守護をするルークかデリックを狙い、何かが起きるだろう。
暗殺者か、もしくは毒か。
この一件をアリエルに伝え、警戒すると共に、改めて、戦いへの意志を促そう。
そう思い、デリックは足早に白百合の園へと戻り始める。いつ何時襲われてもいいように、ローブの懐から杖を取り出しながら。
「……戦いなんて、いつぶりだ」
魔術学院にいた頃には、定期的に模擬戦が行われた。同じ魔術学院の生徒とやったり、騎士学校に通う生徒と戦ったり、三人や五人でチームをつくり、チーム同士で戦ったこともある。
年に何度かは教員や冒険者に引率されて森に入り、魔物との実戦経験を積んだ。
人を殺したことがないわけではない、模擬戦では魔術のあたりどころが悪く、相手を即死させてしまったこともあるし、王女の護衛選別の試験の時には、いざという時に使い物になるかどうかと、死刑囚と戦わされ、相手を殺害した。
だが、そんなデリックやルークに対して暗殺者を送り込むというのなら、手練れを送り込んでくることだろう。
本格的な殺し合いになる。そう考えると、デリックの腕に若干の震えが走った。
「守りきれるだろうか、いや……」
そんな不安を口に出し、即座に打ち払った。
彼らのあずかり知らぬことであるが……。
フィットア領にて転移事件が起こったのは、まさに、この瞬間であった。
★ ★ ★
「アリエルさ……えっ!?」
白百合の園へと戻ってきたデリックの目に、とんでもないものが飛び込んできた。
白百合の園の奥。ハイビスカスの森といわれる区画から、のっそりと姿を現す、巨大な二足歩行の猪の姿。
ターミネートボア。
単体ではDクラスだが、多くのアサルトドッグを引き連れることで、CクラスにもBクラスにもなる凶悪な魔物。本来は森の奥でしか遭遇しないが生息数は多く、時折森の外に出てきて村を襲い、家畜や人間の子供を攫って食べる。
大昔に、二〇匹以上のアサルトドッグを従えたターミネートボアに襲われた小村が皆殺しにあったということで、アスラ王国内では最も知名度の高い魔物であるといわれている。
森近くにある村では、子供が悪いことをすると「夜遅くまでおきていると大きな猪がやってきて食べて」しまうぞ、とスペルド族と並んで教えられる。
デリックもまた、恐ろしい魔物として、ターミネートボアの名前と姿はよく知っていた。
「馬鹿な……」
だが、なぜ魔物がここに。
ここは王宮。世界最大の国家たるアスラ王国の王族が住む場所。
決して安全ではないが、世界で最も魔物と無縁な場所。
なのに、なぜ、こんな所に魔物がいるのか。
そうか、先ほどの会話。奴ら貴族が手配していたというのは……いや、そんな馬鹿な、いくらなんでも、貴族風情に魔物を王宮に入れる手配などできようはずもない。そんなものは、上級大臣ですら不可能だ。
デリックは知らぬことであるが、このターミネートボアは、フィットア領消滅事件に巻き込まれ、まさに今、この場に転移してきたのである。
「はっ」
思考の渦の中にいたデリックの目に映ったのは、アリエルだった。アリエルとルークは相変わらず楽しそうに下品な話題に花を咲かせているようで、ターミネートボアの存在には気づいていない。ターミネートボアはアリエルをその視界に収め、狩人のように爛々とした目で睨んでいるというのに。
デリックは、走った。
走りながら魔術を詠唱しようとした。
しかし、それと同時にターミネートボアが動いた。デリックに気づいたのか、それとも何かを察したのか、草木を掻き分け、アリエルに向かって一直線に突進した。
(間に合わん!)
デリックは詠唱をやめた。
「アリエル様、お逃げください!」
「えっ?」
デリックの叫びに、アリエルは疑問の声を上げつつも、しかし即座に立ち上がり、横合いから急速に突っ込んでくる巨大な塊を発見、横に跳び、転がった。
ターミネートボアは庭園内にある木に突っ込んで叩き折りつつ、こちらを振り返る。
デリックはその間に、アリエルとターミネートボアの間に割り込んだ。
彼の目の前に巨大な猪が立ちふさがる。
口元からダラダラとよだれをたらし、爛々と輝く目でデリックを見据える。
魔術師が何をしようというのか。こんな距離で、こんな巨大な魔物相手に。目と鼻の先まで接近されれば、詠唱など間に合うはずもない。
デリックは詠唱などしなかった。
ただ両手を大きく広げ、声高に叫んだのだ。
「ルーク! あとは、任せた!」
次の瞬間、デリックはターミネートボアの拳を受けて、吹っ飛んだ。
肋骨が全て叩き折れ、内臓はぐちゃぐちゃになり、血反吐を吐きながら中空を吹っ飛んだ。
ゆうに五メートルは離れた内壁へとぶち当たり、背骨が砕けた。
「うげふっ……」
意識を失わなかったのは、不幸中の幸いだったろうか。
それとも、ただの不幸だろうか。
(あ……死ぬのか)
デリックは、はっきりとした意識の中、己の死を悟った。
同時に、死の匂いを感じ取った。
これは、致命傷だと確信していた。
(こんな傷受けて死んだ奴、前にいたよな……)
恐怖はなかった。唐突すぎて、脳が状況に追いついていなかったのかもしれない。
そんなデリックの視界に、ルークが剣を抜き、ターミネートボアへと向かっていくのが映った。
(馬鹿だなルーク……お前一人で勝てるわけがないだろう……ああ、そうか、扉が向こうにあるから、ただ逃げるわけにはいかないのか……)
デリックは目線だけを動かして、周囲を見る。
(アリエル様は、アリエル様は無事なのか?)
見ると、アリエルはやや混乱した様子だったが、しかし怯えた様子もなく、デリックの方へと駆け寄ってくるところだった。
「デリック……! ああ、なんてことを……今すぐ、治癒術師を呼ばなくては」
心配そうに叫ぶアリエルに、デリックは最後の力を振り絞って声を出す。
「うげっふ……そんな、ことより、はやく、お逃げくださ、ごぼっ……」
「デリック! 喋らないで! 誰か! 誰かいないのですか!」
「ごぼっ……無駄です……、アリエル様……自分はもう……助かりません……」
「そんな……気を確かにもちなさい!」
泣きそうなアリエルを、デリックは意外な気持ちで見ていた。
てっきり自分は、アリエルとルークから煙たがられていると思ったのに、と。
すると、なぜか、小さなお茶目心が湧いてきた。こんなときだというのに。
「み、見捨てて、逃げたりは……しなかった……でしょう?」
その言葉で、アリエルはハッとした。
そして、目の前に横たわる、忠義に厚い守護術師を、今までとは違った目で見た。
「……デリック」
「アリエル様……最後のお願いです……どうか、どうか、王に、王になられてください。そして、アスラを、より良い国へと……げふっ」
肺に折れた肋骨が刺さり、デリックの口から大量の血が噴出した。
アリエルはその様子を見て、静かに。
静かに頷き、振り返る。
アリエルの前に、巨大な猪が立っていた。
ルークは吹き飛ばされ、絶望的な表情でアリエルを見ている。
「……」
アリエルは、猪を睨みつけた。
「あなたがどこから来たのかは知りませんが、私はアスラ王国の王となる女です。このような場でやすやすと殺されるわけには参りません、お下がりなさい!」
そう叫ぶが、当然ながらターミネートボアに言葉など通じるはずもない。
魔物はこの場でもっとも美味しそうな食べ物を前にして、ふごふごと興奮した鼻息を吐き出しながら、一歩、また一歩とアリエルに近づいていく。
デリックはそれを見て、祈った。
ミリス教徒であるデリックは、天に祈った。
(どうか、神よ、どうかこの場をお救いください。自分の命と引き換えに、アリエルというこの世になくてはならない存在をお助けください)
祈りは届かない。
そんなことはデリックにもわかっていた。聖ミリスは偉大なお方であり、人々を救済した救世主である……が、しかし、この場においてそのような祈りが何の役にも立たないことは、デリックにも理解できていた。
しかし、祈らざるをえなかった。
そしてターミネートボアの手の届く位置に、アリエルが入った。
魔物の拳が振りあがり。
祈りが届いた。
「──ぁぁぁぁああああ!」
叫び声と共に、空から天使が降ってきた。
みすぼらしい格好をした、幼い、白髪の、天使が。
「う、うわぁぁぁ!」
彼女は、半狂乱ともいえるような可憐な雄たけびを上げながらターミネートボアへと両手を向けて、その上半身を消し飛ばした。
(ああ、神よ、感謝いたします)
デリックはその光景を見ながら、最後に涙した。
(今後も、アリエル様をお守りください)
デリックは安らかな気持ちで、その生涯を終えた。
★ ★ ★
転移事件は一人の魔術師を殺し、アリエル・アネモイ・アスラの意識に改革を与えた。
この後、アリエルがどのような道を歩んだのか、ルークがどう変わったのか。
また、空から降ってきた天使がどうなったか──。
それらは、次の機会にするとしよう。
作者闲话
『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 3』
理不尽な孫の手先生 こぼれ話
3巻からの方は(さすがにいないと思いますが)はじめまして。
1巻からの方はありがとうございます。
WEB版の方から読んでいただいている方は、いつもありがとうございます。
理不尽な孫の手です。
このコーナーはこぼれ話という事で、1巻の時は物語自体の誕生秘話、2巻の時にはヒロインの誕生秘話について書きました。
なので、3巻でもやっぱり誕生秘話について書こうかと思います。
今回は、主人公の師匠役の人物について書いていきましょう。
・師匠という存在
1巻、2巻を読んだ方はわかるかと思いますが、主人公には常に師匠役の人物がいます。
すでに無詠唱魔術を扱い、魔力もたっぷり、一般人より明らかに強い主人公ですが、彼を肉体的、あるいは精神的に導く存在がいます。
ロキシー・ミグルディアしかり、パウロ・グレイラットしかり、ギレーヌ・デドルディアしかりです。
そして、3巻で登場したルイジェルド・スペルディアというキャラクターもまた、師匠役の人物の一人となります。
・師匠役の必要性
なぜこうした師匠が必要なのか。
一つは「異世界」という世界に現実味を持たせるためです。
「異世界転生」というジャンルでは、と言葉にあらわしてみると、非現実的なことこの上ありません。
それも、主人公は魔術の才能があり、一人でどんどん強くなってしまう。
こんな簡単に物語が進むのか、ご都合主義すぎませんか、と思った時に必要なのが主人公を押さえつける存在です。
ゲームの世界であるならば、主人公より強い存在はいません。
格闘ゲームやFPS、MMORPGといったゲームならまだしも、一人でプレイするRPGでは最終的には主人公が一番強くなってしまいます。
しかしながら、現実ではそうなる事はほとんどありません。
常に上がいて、その上にはさらに上がいる。
そして、目に見える上というのは「目標」となります。
そのためにも、「主人公より上の存在」は必要なのです。
・ナビゲート役としての役割
また、異世界ものを一人称、ということで、いわゆるナビゲート役というものも必要となってきます。
ナビゲート役は主人公が見たものを説明してくれる係であり、読者を安心させるための保護者ともなります。
一部のRPGにおいて、序盤から仲間に入るわりにやたら強いけど、途中でパーティから離脱してしまうタイプのキャラを思い出していただければわかるかと思います。
守られている間に強くなる。
しかし、ずっとそんなキャラが交代で出てきて守られてばかりでは、面白くはありませんよね。
というわけで、無職転生の師匠役の人物には、ひと味加えてあります。
・師匠役の変化
一巻ではロキシーとパウロ。二巻ではギレーヌ。
そして三巻ではルイジェルド・スペルディアというキャラが師匠役として登場します。
本作を読んだ方はわかると思うのですが、師匠役の人々はそれぞれ弱みを持っています。
やや鼻持ちならない自信家であったロキシー。
父親だけど人間的にまだまだ未熟なパウロ。
剣術の達人だけど頭の回転は鈍いギレーヌ。
彼等は主人公と触れ合うことで、変化していきます。
パウロは主人公と触れ合う事で人間的に成長し、ギレーヌは勉強ができるようになり、ロキシーは神となりました。
ルイジェルド・スペルディアが今後、どのように変化していくのか。
また、彼と触れ合う事で、主人公がどう変化していくのか。
主人公は、彼等を超えることはできるのか。
という部分に焦点を当てて読むと、書籍版の読者さんもWEB版の読者さんも楽しめるかもしれません。
では、以上です。
文库版 无职转生~到了异世界就拿出真本事~