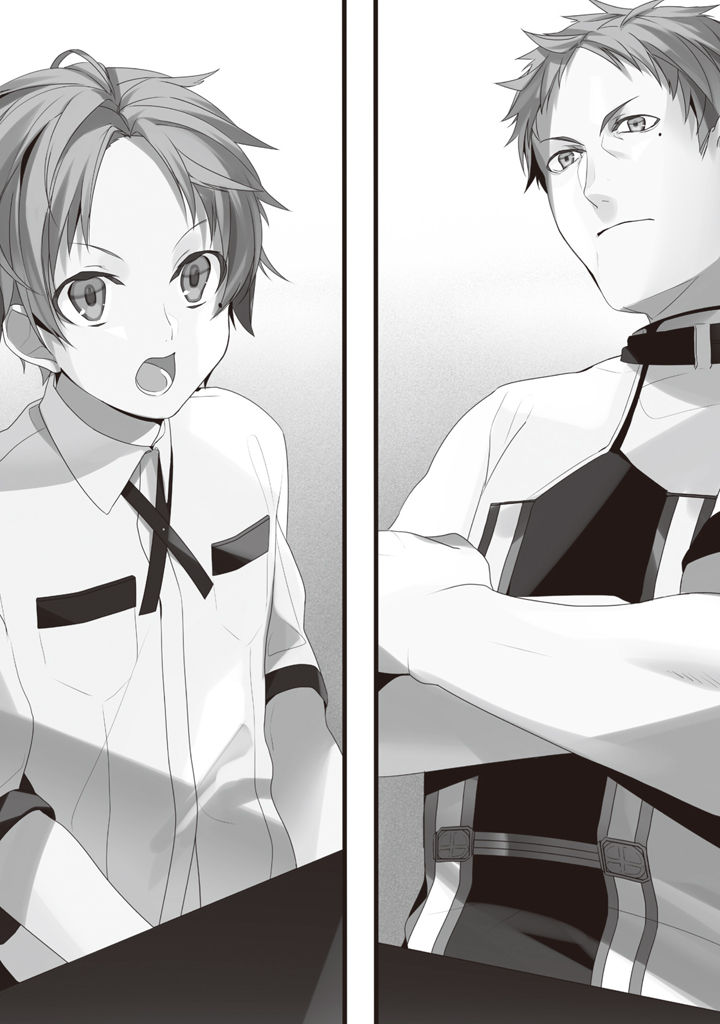無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
第一巻
著者:理不尽な孫の手 角色原案:シロタカ
发售时间:2014年01月24日
特装版发售时间:2020年12月16日
本馆一并提供Epub电子书下载 请自行前往 洛琪希图书馆借书柜台 借阅
制作信息
简介
人生やり直し。王道の大河転生ファンタジー始動す!
34歳無職童貞のニートは無一文で家を追い出され、自分の人生が完全に詰んでいたと気付く。己を後悔していた矢先、彼はトラックに轢かれ呆気なく死んでしまう。ついで目を覚ました場所は――なんと剣と魔法の異世界だった!!
ルーデウスと名付けられた赤ん坊として生まれ変わった彼は、「今度こそ本気で生きて行くんだ……!」と後悔しない人生を送ると決意する。
前世の知能を活かしたルーデウスは瞬く間に魔術の才能を開花させ、小さな女の子の家庭教師をつけてもらうことに。さらにはエメラルドグリーンの髪を持つ美しいクォーターエルフとの出会い。彼の新たな人生が動き始める。
――憧れの人生やり直し型転生ファンタジー、ここに始動!
目录
CONTENTS

第一章 幼年期
「目の前に崖がある。踏み出して地面に叩きつけられるか、
その場に留まって罵声を浴びせ続けるかは君の自由だ」
── I do not want to work, whatever it may be said by whom.
著:ルーデウス・グレイラット
译:ジーン・RF・マゴット
プロローグ
俺は三十四歳住所不定無職。
人生を後悔している真っ最中の小太りブサメンのナイスガイだ。
つい三時間ほど前までは住所不定ではない、ただの引きこもりベテランニートだった。
だが、気づいたら親が死んでいた。
引きこもっていた俺は、葬式はもちろん、親族会議にも出席しなかった。
結果、見事に家を追い出されることとなった。
床ドンと壁ドンをマスターし、家で傍若無人に振る舞っていた俺に味方はいなかった。
葬式当日、ブリッヂオ○ニー中にいきなり喪服姿の兄弟姉妹たちに部屋に乱入され、絶縁状を突きつけられた。
無視すると、命よりも大切なパソコンを弟が木製バットで破壊しやがった。
半狂乱で暴れてみたものの、兄は空手の有段者で、逆にこっちがぼっこぼこにされた。
無様に泣きじゃくって事なきをえようとしたら、着の身着のまま家から叩き出された。
ズキズキと痛む脇腹(多分肋骨が折れてる)を押さえながら、とぼとぼと町を歩く。
家を後にした時の、兄弟たちの罵詈雑言が未だ耳に残っている。
聞くに堪えない暴言だ。
心は完璧に折れていた。
俺が一体なにをしたっていうんだ。
親の葬式をブッチして無修正ロリ画像でオ○ってただけじゃないか……。
これからどうしよう。
いや、頭ではわかっている。
バイトか定職を探して、住む場所を見つけて、食べ物を買うのだ。
どうやって?
仕事を探す方法がわからない。
いや、なんとなくだが、ハロワにいけばいいということはわかる。
だが、伊達に十年以上引きこもっていたわけじゃない。ハロワの場所なんかわかるわけもないし、それにハロワに行っても仕事を紹介されるだけだと聞いたことがある。
紹介された所に履歴書を持っていき、面接を受けるわけだ。この、所々に染みや汗や血の付いた汚いスウェットで面接を。
受かるわけがない。俺だったらこんなクレイジーな格好した奴は絶対に採用しない。共感は覚えるかもしれないが、絶対に採用はしない。
そもそも履歴書の売っている店もわからない。
文房具屋か? コンビニか?
コンビニぐらいは歩いていればあるかもしれないが、金は持っていない。
もし、それらがクリアできたとしよう。
運よく金融機関か何かで金を借りることができて、服を新調して、履歴書と筆記用具を買ったとしよう。
履歴書というものは住所が無いと書けない、と聞いたことがある。
詰んだ。ここにきて、俺は人生が完全に詰んだのを自覚した。
「……はぁ」
雨が降ってきた。
もう夏も終わり、肌寒くなってくる時期だ。冷たい雨は何年も着古したスウェットに難なく染みこみ、容赦なく体温を奪った。
「………やりなおせればな」
思わずそんな言葉が溢れる。
俺だって、生まれた時からクズ人間だったわけじゃない。
そこそこ裕福な家庭の三男として生まれた。兄兄姉弟。五人兄弟の四番目。小学生の頃は、この歳にしては頭がいいと褒められて育った。勉強は得意じゃなかったが、ゲームがうまくて、運動もできるお調子者。クラスの中心だった。
中学時代にはパソコン部に入り、雑誌を参考に、お小遣いを貯めて自作PCを作成。パソコンのパの字も知らなかった家族からは、一目も二目も置かれていた。
人生が狂ったのは高校……いや、中学三年からだ。パソコンにかまける余りに、勉強をおろそかにした。今考えれば、これがきっかけだったのかもしれない。
勉強なんか、将来に必要ないと思っていた。役に立たないと思っていた。
その結果、県内でも最底辺と噂の超絶バカ高校に入学するハメになった。
そこでも、俺はイケる気でいた。
やればできる俺は、他の馬鹿どもとは出来がちがうんだと思っていた。思っていたんだ。
あの時のことは、今でも覚えている。
購買で昼食を買おうとして並んでいた時、いきなり横入りしてきた奴がいた。
俺は正義漢ぶってそいつに文句を言った。当時、変な自尊心と、中二病心溢れる性格をしていたためにやってしまった暴挙だ。
しかし、最悪なことに相手は先輩で、この学校でも一、二を争うほど危ない奴だった。
結果として、俺は奴らに顔が腫れ上がるまで殴られ、全裸で校門に磔にされた。
写真もいっぱい撮られ、いとも容易く、面白半分で学校中にバラまかれた。
俺のヒエラルキーは一瞬にして最下層に落ちて、ホーケーという仇名を付けられてからかわれた。
一ヶ月も学校に通わないうちに不登校になって引きこもった。父や兄はそんな俺を見て、勇気を出せだの、頑張れだのと無責任な言葉を投げつけた。俺はその言葉を全て無視した。
俺は悪くない。
あんな状況で、誰が学校に行けるというんだ。
誰だって、あんな状況になったら学校になんて行けない。行けるわけがない。
だから、誰に何を言われても、断固として引きこもった。
同年代の知り合いが、みんな俺の写真を見て笑っていると思っていた。
家から出ずとも、パソコンとネットがあれば、時間はいくらでも潰せた。ネットで影響を受けて、色んなことに興味を持ち、色んなことをやった。プラモを作ったり、フィギュアを塗装してみたり、ブログをやってみたり。母はそんな俺を応援するがごとく、ねだればいくらでも金を出してくれた。
が、どれも一年以内には飽きた。
自分より上の人間を見て、やる気が失せたのだ。
傍から見れば、ただ遊んでいるだけに見えただろうけど、一人だけ時間に取り残され、暗い殻に閉じこもってしまった俺には、他にできることがなかった。
いいや、今にして思えば、そんなのは言い訳だ。
まだ、漫画家になると言い出してヘタクソなWEB漫画を連載してみたり、ラノベ作家になると言い出して小説を投稿してみたりするほうがマシだったろう。
俺と似たような境遇でそうしている奴はたくさんいた。
そんな奴らを、俺は馬鹿にしていた。
彼らの創作物を見て鼻で笑って、「クソ以下だな」と評論家気取りで批判していた。
自分は何もやっていないのに……。
戻りたい。
できれば最高だった小学か、中学時代に。いや、一、二年前でもいい。ちょっとでも時間があれば、俺には何かができたはずなんだ。どれも中途半端でやめたから、どれも途中から始められる。
本気を出せば、一番にはなれなくても、それなりのプロにはなれたかもしれない。
「……」
なんで俺は今まで、何もやってこなかったのだろうか。
時間はあったのだ。その時間、俺はずっと部屋に引きこもっていたが、パソコンの前に座りながらでもできることはいくらでもあったはずだ。一番になれなくても、何かの道の中堅として頑張っていくことは、いくらでもできたはずなのだ。
漫画でもいい、小説でもいい。ゲームでも、プログラミングでも。何かしら、本気で取り組んでいれば、何か成果を残せたはずなのだ。それが金銭につながるかどうかはさておき……。
いや、よそう。無駄だ。
俺は頑張れなかった。きっと過去に戻っても似たようなことで躓いて、似たようなことで立ち止まったに違いない。普通の人間が無意識に乗り越えられるべき所を乗り越えられなかったから、俺は今ここにいるのだ。
「ん?」
ふと、激しい雨の中、俺は誰かの言い争う声を聞いた。
喧嘩だろうか。
嫌だな、かかわり合いになりたくない。そう思いつつも、足はまっすぐにそちらに向かっていた。
「──だから、あんたが──」
「おまえこそ──」
見つけたのは、痴話喧嘩の真っ最中らしき三人の高校生だ。
男二人に女が一人。いまどき珍しいことに、詰襟とセーラー服。
どうやら修羅場らしく、ひときわ背の高い少年と少女が何かを言い争っていた。もう一人の少年が、二人を落ち着かせようと間に入っているが、喧嘩中の二人は聞く耳を持たない。
(ああ、俺にもあったな、あんなの)
それを見て、俺は昔のことを思い出す。
中学時代には、俺にも可愛い幼馴染がいた。可愛いといっても、クラスで四番目か五番目ぐらい。陸上部だったので髪型はベリィショート。町を歩いて十人とすれ違ったら、二人か三人ぐらいは振り返る、そんな容貌だ。もっとも、あるアニメにハマり、陸上部といえばポニテと言って憚らなかった俺にとって、彼女はブスもいいところだった。
けれど、家も近く、小中と同じクラスになることも多かったので、中学になっても、何度か一緒に帰ったりもした。会話をする機会は多かったし、口喧嘩をしたりした。惜しいことをしたもんだ。今の俺なら、中学生・幼馴染・陸上部、それらの単語だけで三発はイケる。
ちなみに、その幼馴染は七年前に結婚したらしいと風の噂で聞いた。
風の噂といっても、リビングから聞こえてきた兄弟の会話だが。
決して悪い関係じゃなかった。お互いを小さい頃から知っていたから、気兼ねなく話せていた。
彼女が俺に惚れていたとかは無かったと思うが、もっと勉強してあの子と同じ高校に入っていれば、あるいは、同じ陸上部に入って推薦入学でもしていれば、フラグの一つも立ったかもしれない。 本気で告白すれば、付き合うことぐらいはできたかもしれない。
そして、彼らのように、帰り道で喧嘩したりするのだ。あわよくば、放課後に誰もいない教室でエロいことも。
ハッ、どこのエロゲーだ。
(そう考えるとあいつらマジリア充だな。爆発しろ……ん?)
と、俺はその瞬間に気づいた。
一台のトラックが三人に向かって猛スピードで突っ込んできているのを。
そして、トラックの運転手がハンドルに突っ伏しているのを。
居眠り運転。
三人はまだ気づいていない。
「ぁ、ぁ、ぶ、危ねぇ、ぞぉ」
咄嗟に叫んだつもりだったが、十年以上もロクに声を出していなかった俺の声帯は、肋骨の痛みと雨の冷たさでさらに縮こまり、情けなくも震えた声しか発せず、雨音にかき消された。
助けなきゃ、と思った。同時に、俺がなんでそんなことを、とも思った。
だが、もし助けなければ、五分後にきっと後悔するんだろうと直感した。凄まじい速度で突っ込んでくるトラックにハネられ、ぐちゃぐちゃに潰れる三人を見て、後悔するんだろうと直感した。
助けておけばよかった、と。
だから助けなきゃ、と思った。
俺はもうすぐ、きっとどこかそのへんで野垂れ死ぬだろうけど、その瞬間ぐらいは、せめてささやかな満足感を得ていたいと思っていた。
最後の瞬間まで後悔していたくないと思った。
──転げるように走った。
十数年以上もロクに動いていなかった俺の足はいうことを聞かない。もっと運動をしておけばと、生まれて初めて思った。折れた肋骨が凄まじい痛みを発し、俺の足を止めようとする。もっとカルシウムを取っておけばと、生まれて初めて思った。
痛い。痛くてうまく走れない。
けれども走った。走った。
走れた。
トラックが目の前に迫っているのに気づいて、喧嘩していた少年が少女を抱き寄せた。もう一人の少年は、後ろを向いていたため、まだトラックに気づいていない。唐突にそんな行動にでたことに、きょとんとしている。俺は迷わず、まだ気づいていない少年の襟首を掴んで、渾身の力で後ろに引っ張った。少年は俺に引っ張られ、トラックの進路の外へと転がった。
よし、あと二人。
そう思った瞬間、俺の目の前にトラックがいた。安全な所から、腕だけ伸ばして引っ張ろうと思ったのだが、人を引っ張れば、反作用で自分が前に出る。
当然のことだ。俺の体重が一〇〇キロを超えていようと関係ない。全力疾走でガクガクしていた足は、簡単に前に出てしまった。
トラックに接触する瞬間、何かが後ろで光った気がした。
あれが噂の走馬灯だろうか。一瞬すぎてわからなかった。早すぎる。
中身の薄い人生だったということか。
俺は自分の五十倍以上の重量を持つトラックに跳ね飛ばされ、コンクリートの外壁に体を打ち付けた。
「かッハ……!!」
肺の中の空気が一瞬で吐き出される。全力疾走で酸素を求める肺が痙攣する。
声も出ない。だが、死んではいない。たっぷりと蓄えた脂肪のおかげで助かった……。
と思ったが、トラックはまだ迫ってきていた。
俺はトラックとコンクリートに挟まれて、トマトみたいに潰れて死んだ。
第一話 「もしかして:異世界」
目が覚めた時、最初に感じたのは眩しさだった。
視界一杯に光が広がり、俺は不快な気分で目を細めた。
次第に目が慣れてくると、金髪の若い女性が俺を覗き込んでいるのがわかった。
美少女……いや美女と言っていいだろう。
(誰だ?)
隣には、同じくまだ年若い茶髪の男性がいて、ぎこちない笑みを俺に向けている。
強そうでワガママそうな男だ。筋肉が凄い。
茶髪でワガママそうとか……こういうDQNっぽい奴は見た瞬間に拒否反応が出るはずなのだが、不思議と嫌悪感がなかった。
恐らく、彼の髪が染めたものではないからだろう。綺麗な茶髪だった。
「──××──××××」
女性が俺を見て、にっこり笑って何かを言った。
何を言っているのだろうか。なんだかボンヤリして聞き取りにくいし、全然わからない。
もしかして、日本語じゃないのか?
「────×××××───×××……」
男の方も、ゆるい顔で返事をする。いやほんと、何を言ってるのかわからない。
「──××──×××」
どこからか、三人目の声が聞こえる。
姿は見えない。
体を起こして、ここはどこで、あなた方は誰かを聞こうとした。
俺は引きこもってたとはいえ、別にコミュ障ってわけじゃない。
それぐらいはできる。
「あー、うあー」
と思ったのだが、口から出てきたのは、うめき声ともあえぎ声とも判別のつかない音だった。
体も動かない。
指先や腕が動く感触はあるのだが、上半身が起こせない。
「×××───××××××」
と、思ったら男に抱き上げられた。
マジかよ、体重百キロ超の俺をこうも簡単に……。
いや、何十日も寝たきりだったのなら、体重は落ちているか。
あれだけの事故だ。手足が欠損してる可能性も高い。
(生き地獄だなぁ……)
あの日。
俺はそんなことを考えていたのだった。
★ ★ ★
一ヶ月の月日が流れた。
どうやら俺は生まれ変わったらしい。その事実が、ようやく飲み込めた。
俺は赤ん坊だった。
抱き上げられて、頭を支えてもらい自分の体が視界にはいることで、ようやくそれを確認した。
どうして前世の記憶が残っているのかわからないが、残っていて困ることもない。
記憶を残しての生まれ変わり──誰もが一度はそういう妄想をする。
まさか、その妄想が現実になるとは思わなかったが……。
目が覚めてから最初に見た男女が、俺の両親であるらしい。
年齢は二十代前半といったところだろうか。
前世の俺よりも明らかに年下だ。
三十四歳の俺から見れば、若造といってもいい。
そんな歳で子供を作るとは、まったく妬ましい。
初日から気づいてはいたが、どうやらここは日本ではないらしい。
言語も違うし、両親の顔立ちも日本人ではない、服装もなんだか民族衣装っぽい。
家電製品らしきものも見当たらない(メイド服着た人が雑巾で掃除してた)し、食器や家具なんかも粗末な木製だ。先進国でないだろう。
明かりも電球ではなく、ロウソクやランプを使っている。
もっとも、彼らが特別に貧乏で電気代も払えないという可能性もある。
……もしかして、その可能性は高いのか?
メイドっぽい人がいるから、てっきりそれなりに金があるのかと思ったが、
彼女が、父か母の姉妹と考えれば、なにもおかしいことはない。家の掃除ぐらいするだろう。
確かにやり直したいとは思ったが、電気代も支払えないほど貧乏な家に生まれるとは、これから先が思いやられる。
★ ★ ★
さらに半年の月日が流れた。
半年も両親の会話を聞いていると、言語もそれなりに理解できるようになってきた。
英語の成績はあまりよくなかったのだが、やはり自国語に埋もれていると習得が遅れるというのは本当らしい。それとも、この身体の頭の出来がいいのだろうか。まだ年齢が若いせいか、物覚えが異常にいい気がする。
この頃になると、俺もハイハイぐらいはできるようになった。
移動できるというのは素晴らしいことだ。
身体が動くということにこれほど感謝したことはない。
「眼を放すとすぐにどこかに行っちゃうの」
「元気でいいじゃないか。生まれてすぐの頃は全然泣かなくて心配したもんだ」
「今も泣かないのよねぇ」
動きまわる俺を見て、両親はそんな風に言っていた。
さすがに腹が減った程度でビービー泣くような歳じゃない。
もっとも、シモの方は我慢してもいずれ漏らすので、遠慮せずぶっ放させてもらっているが。
ハイハイとはいえ、移動できるようになると、色んなことがわかってきた。
まず、この家は、裕福だ。
建物は木造の二階建てで、部屋数は五つ以上。メイドさんを一人雇っている。
メイドさんは、最初は俺の叔母さんかとも思ったが、父親と母親に対する態度がかしこまったものだったので、家族ではないだろう。
立地条件は、田舎だ。
窓から見える景色は、のどかな田園風景である。
他の家はまばらで、一面の小麦畑の中に、二~三軒見える程度。
かなりの田舎だ。電柱や街灯の類は見えない。近くに発電所が無いのかもしれない。
外国では地面の下に電線を埋めると聞いたことがあるが、ならこの家で電気を使っていないのはおかしい。
さすがに田舎すぎる。文明の波に揉まれてきた俺にはちょっときついかもしれない。
生まれ変わってもパソコンぐらい触りたいのだ。
などと思っていたのは、ある日の昼下がりまでだ。
することが無いのでのどかな田園風景でも見ようと思った俺は、いつもどおり椅子によじ登り、窓の外を見てギョッとした。
父親が庭で剣を振り回していたからだ。
(ちょ、え? 何やってんの?)
いい年してそんなの振り回しちゃうようなのが俺の親父なわけ? 中二病なわけ?
(あ、やべ……)
驚いた拍子に椅子から滑った。
未熟な手は椅子を掴んでも身体を支えることができず、重い後頭部から地面へと落ちていく。
「キャア!!」
どしんと落ちた瞬間、悲鳴が聞こえた。
見れば、母親が洗濯物を取り落とし、口に手を当てて真っ青な顔で俺を見下ろしていた。
「ルディ!! 大丈夫なの!?」
母親は慌てて駆け寄ってきて、俺を抱き上げた。
視線が絡むと、安堵した顔になって胸を撫でおろした。
「……ほっ、大丈夫そうね」
(頭を打った時は、あんまり動かさないほうがいいんだぜ、奥さん)
と、心の中で注意してやる。
あの慌てようを見るに、危ない落ち方をしたのだろう。
後頭部からいったしな、アホになったかもしれん。あんま変わらんか。
頭がズキズキする。一応は椅子に掴まろうとしたし、勢いは無かった。
母親があまり慌てていないところを見ると、血は出ていないようだ。たんこぶ程度だろう。
母親は注意深く俺の頭を見ていた。
傷でもあったら一大事だと言わんばかりの表情をしている。
そして最後に、俺の頭に手を当てて、
「念のため……。神なる力は芳醇なる糧、力失いしかの者に再び立ち上がる力を与えん『ヒーリング』」
吹きそうになった。
おいおい、これがこの国の「イタイのイタイのとんでけ」かよ。
それとも、剣を振り回す父親に続いて母親の方も中二病か?
戦士と僧侶で結婚しましたってか?
と、思ったのもつかの間。
母親の手が淡く光ったと思った瞬間、一瞬で痛みが消えた。
(……え?)
「さ、これで大丈夫よ。母さん、これでも昔は名の知れた冒険者だったんだから」
自慢気に言う母親。
俺は混乱していた。
剣、戦士、冒険者、ヒーリング、詠唱、僧侶。そんな単語がぐるぐると俺の中を回っていた。
なんだ、いまの。何したの?
「どうした?」
母親の悲鳴を聞きつけて、窓の外から父親が顔をのぞかせた。
剣を振り回していたせいか、汗をかいている。
「聞いてあなた、ルディったら、椅子の上になんかよじ登って……危うく大怪我するところだったのよ」
「ま、男の子はそれぐらい元気でなくちゃな」
ちょっとばかしヒステリックな母親と、それを鷹揚に流す父親。
よく見る光景だ。
だが、今回は後頭部から落ちたせいだろう、母親も譲らなかった。
「あのねあなた、この子はまだ生まれてから一年も経ってないんですよ。もっと心配してあげて!!」
「そうは言ったってな。子供は落ちたり転んだりして丈夫になっていくものじゃないか。それに、怪我をしたなら、そのたびにおまえが治せばいい」
「でも、あんまり大怪我をされて治せなかったらと考えると心配で……」
「大丈夫だよ」
父親はそう言って、母親と俺を一緒に抱きしめた。
母親の顔が赤く染まる。
「最初は泣かなくて心配だったけど、こんなにヤンチャなら、大丈夫……」
父親は母親にチュっとキスをした。
おうおう、見せつけてくれるねお二人さん、ヒューヒュー。
その後、二人は俺を隣の部屋で寝かせると、上の階へ移動して、俺の弟か妹を作る作業へと入っていった。
二階に行ってもギシギシアンアン聞こえるからわかるんだよ、リア充め……。
(しかし、魔法か……)
★ ★ ★
それからというもの、俺は両親やお手伝いさんの会話に注意深く耳を傾けるようになった。
すると、聞きなれない単語が多いことに気づいた。
特に、国の名前や領土の名前、地方の名前。固有名詞は聞いたことのないものしかなかった。
もしかするとここは………。
いや、もう断定していいだろう。
ここは地球ではなく、別の世界だ。
剣と魔法の異世界だ。
そこで、ふと思った。
……この世界なら、俺もできるんじゃないだろうか、と。
剣と魔法の世界なら、生前と常識の違う世界なら、俺にだってできるんじゃないだろうか。
人並みに生きて、人並みに努力して。躓いても立ち上がって、なお前を向いて生きていくことが。
生前は死ぬ間際に後悔した。
自分の無力さと、何もしてこなかったことへの苛立ちを持ちながら、死んだ。
けど、それを知っている俺なら。
生前の知識と経験を持つ今の俺なら、できるんじゃないだろうか。
──本気で生きていくことが。
第二話 「ドン引きのメイドさん」
リーリャはアスラ後宮の近衛侍女だった。
近衛侍女とは、近衛兵の性質を併せ持つ侍女のことである。
普段は侍女の仕事をしているが、有事の際には剣を取って主を守るのだ。
リーリャは職務には忠実であり、侍女としての仕事もそつなくこなした。
しかし、剣士としては十把一絡げの才能しか持ち合わせていなかった。
ゆえに、生まれたばかりの王女を狙う暗殺者と戦って不覚を取り、短剣を足に受けてしまうこととなった。
短剣には毒が塗ってあった。王族を殺そうとするような毒である。
解除できる解毒魔術の無い、厄介な毒である。
すぐに傷を治療魔術で治し、医者が解毒を試みたおかげで一命は取り留めたものの、後遺症が残ってしまった。
日常生活を送る分には支障は無いが、全速力で走ることも、鋭く踏み込むこともできなくなった。
リーリャの剣士生命はその日、終わりを告げた。
王宮はリーリャをあっさりと解雇した。
珍しいことではない。リーリャも納得している。
能力がなくなれば解雇されるのは当然だ。
当面の生活資金すらもらえなかったが、後宮務めを理由に、秘密裏に処刑されなかっただけでも儲けものだと思わなければいけない。
リーリャは王都を離れた。
王女暗殺の黒幕はまだ見つかっていない。
後宮の間取りを知っているリーリャは、自身が狙われる可能性があると深く理解していた。
あるいは王宮はリーリャを泳がせて、黒幕を釣ろうとしていたのかもしれない。
昔、なんで家柄もよくない自分が後宮に入れたのかと疑問に思ったが、今にして思えば、使い捨てになるメイドを雇いたかったのかもしれない。
何にせよ、自衛のためにも、なるべく王都から離れる必要があった。
王宮が餌として自分を放流したのだとしても、何も命じられていない以上、拘束力はない。
義理立てする気もなかった。
リーリャは乗合馬車を乗り継いで、広大な農業地域が続く辺境、フィットア領へとやってきた。
領主の住む城塞都市ロア以外は、一面に麦畑が広がるのどかな場所だ。
リーリャはそこで仕事を探すことにした。
とはいえ、足を怪我した自分には荒事はできない。
剣術ぐらいなら教えられるかもしれないが、できれば侍女として雇ってもらいたかった。
そっちのほうが、給料がいいからである。
この辺境では剣術を使える者、教える者は数多くいるが、家の仕事を完璧にできる教育された侍女は少ないのだ。
供給が少なければ、賃金も上がる。
だが、フィットア領主や、それに準じた上級貴族の侍女として雇われるのは危険だった。
そうした人物は、当然ながら王都ともパイプを持っている。
後宮付きの近衛侍女だったと知られると、政治的なカードとして使われる可能性もあった。
そんなのはゴメンだ。
あんな死にそうな目には、二度と遭いたくない。
姫様には悪いが、王族の後継者争いは自分の知らない所で勝手にやってほしいものである。
といったものの、賃金の安すぎる所では、家族へ仕送りもままならない。
賃金と安全の二つを両立できる条件はなかなか見つからなかった。
★ ★ ★
一ヶ月かけて、各地を回ったところ、一つの募集が目についた。
フィットア領のブエナ村にて、下級騎士が侍女を募集中。
子育ての経験があり、助産婦の知識を持つ者を優遇する、と書いてある。
ブエナ村はフィットア領の端にある、小さな村である。
田舎中の田舎、ド田舎だ。
不便な場所ではあるが、まさにそういう立地こそ自分は求めていたのだ。
それに、雇い主が下級騎士とは思えないほど条件が良かった。
何より、募集者の名前に見覚えがあった。
『パウロ・グレイラット』
彼はリーリャの弟弟子である。
リーリャが剣を習っていた道場に、ある日突然転がり込んできた貴族のドラ息子だ。
なんでも父親と喧嘩して勘当されたとかで、道場に寝泊まりしながら剣を習いだした。
流派は違えども、剣術を家で習っていたこともあり、彼はあっという間にリーリャを追い越した。
リーリャとしては面白くなかったが、今となっては自分に才能がなかっただけだと諦めている。
才能溢れるパウロはある日、問題を起こして道場を飛び出していった。
リーリャには一言「冒険者になる」と言い残して。
嵐のような男だった。
別れたのは七年ぐらい前になるか。
あの時の彼が、まさか騎士になって結婚までしているとは……。
彼がどんな波瀾万丈の人生を送ってきたかは知らないが、リーリャの記憶にあるパウロは決して悪いヤツではなかった。
困っているといえば助けてくれるだろう。
ダメなら昔のことを持ちだそう。
交渉材料となる逸話はいくつかある。
リーリャは打算的にそう考えて、ブエナ村へと赴いた。
パウロはリーリャを快く迎えてくれた。
奥方のゼニスがもうすぐ出産ということで、焦っていたらしい。
リーリャは王女の出産と育成に備えてあらゆる知識と技術を叩きこまれたし、顔見知りかつ出自もハッキリしているということで、身元も安全。
歓迎された。
賃金も予定より多く払ってくれるというので、リーリャとしても願ったり叶ったりだった。
★ ★ ★
子供が生まれた。
難産でもなんでもない、後宮でした練習どおりの出産だ。
何も問題はなかった。スムーズにいった。
なのに、生まれた子供は泣かなかった。
リーリャは冷や汗をかいた。
生まれてすぐに鼻と口を吸引して羊水を吸い出したものの、赤子は感情のない顔で見上げているだけで、一声も発しない。
もしや、死産なのか、そう思うほどの無表情だ。
触ってみると、温かく脈打っていた。息もしている。
しかし、泣かない。
リーリャの心中に、先輩の近衛侍女から聞いた話がよぎる。
生まれてすぐに泣かない赤子は、異常を抱えていることが多い。
まさかと思った次の瞬間、
「あー、うあー」
赤子がこちらを見て、ぼんやりした表情で何かを呟いた。
それを聞いて、リーリャは安心した。
何の根拠もないが、なんとなく大丈夫そうだ、と。
★ ★ ★
子供はルーデウスと名付けられた。
不気味な子供だった。一切泣かないし、騒がない。もしかしたら身体が弱いのかもしれないが、手間がかからなくていい。
などと、思っていられたのは、最初だけだった。
ルーデウスはハイハイができるようになると、家中のどこにでも移動した。
家中の、どこにでも、だ。炊事場や裏口、物置、掃除道具入れ、暖炉の中……などなど。
どうやって登ったのか、二階にまで入り込んだこともあった。
とにかく眼を離すと、すぐにいなくなった。
だが、なぜか必ず家の中で見つかった。
ルーデウスは、決して家の外に出ることはなかった。
窓から外を見ている時はあるが、まだまだ外は怖いのか。
リーリャがこの赤ん坊に本能的な恐怖を感じるようになったのは、いつからだろうか。
眼を離していなくなり、探して見つけ出した時だろうか。
大抵の場合、ルーデウスは笑っていた。
ある時は台所で野菜を見つめて、ある時は燭台のろうそくに揺れる火を見つめて、また、ある時は洗濯前のパンツを見つめて。
ルーデウスは口の中で何かをブツブツと呟いては、気持ち悪い笑みを浮かべて笑うのだ。
──それは生理的嫌悪感を覚える笑みだった。
リーリャは後宮に務めていた頃、任務で何度か王宮まで足を運んだのだが、その時に出会った大臣が浮かべる笑みによく似ていた。
禿頭をテカらせて、デップリと太った腹を揺らしながら、リーリャの胸を見て浮かべる笑みに似ているのだ。生まれたばかりの赤ん坊が浮かべる笑みが。
特に、恐ろしいのはルーデウスを抱き上げた時だ。
ルーデウスは鼻の穴を膨らませて、口の端を持ち上げて、鼻息も荒く、胸に顔を押し付けてくる。
そして喉をひくつかせ、「フヒッ」と「オホッ」の中間くらいの奇妙な声で笑うのだ。
その瞬間、ゾッとする悪寒が全身を支配する。
胸に抱く赤ん坊を、思わず地面に叩きつけたくなるほどの悪寒が。
赤ん坊の愛らしさなど欠片もない。この笑みは、ただひたすらにおぞましい。
若い女の奴隷をたくさん買い入れているという噂の大臣と同じ笑み。
それを生まれたばかりの赤ん坊がするのだ。
比べ物にならないぐらい不快で、赤ん坊相手に身の危険すら感じてしまう。
リーリャは考えた。
この赤ん坊は何かがおかしい。もしかすると、何か悪いモノでも憑いているのかもしれない。あるいは、呪われているのかもしれない、と。
そう思い立ったリーリャは、居てもたってもいられない気持ちになった。
道具屋へ走り、なけなしの金を使って必要なものを購入。
グレイラット家が寝静まった頃、故郷に伝わる魔除けを行った。
もちろん、パウロには無断でだ。
翌日、ルーデウスを抱き上げて、リーリャは悟る。
無駄だった、と。
相変わらずの気持ち悪さだった。赤ん坊がこんな顔をしているというだけで不気味だった。
ゼニスも「あの子ってお乳を上げる時に、舐めるのよねぇ……」などと言っていた。
とんでもないことだと思う。
パウロも女に目がない節操無しだが、こんなに気持ち悪くはない。
遺伝としてもさすがにおかしい。
リーリャは思い出す。ああ、そういえば、後宮でこんな話を聞いたことがある、と。
『かつて、アスラの王子が、夜な夜な四つん這いで後宮を動きまわるという事件があった。王子は悪魔に憑かれていたのだ。そうと知らずに、迂闊にも王子を抱き上げてしまうと、王子はその侍女を後ろ手に隠したナイフで、心臓を一突きにして殺してしまうのだ』
なんて恐ろしい。
ルーデウスはソレだ。
間違いない。絶対そういう悪魔だ。
今はおとなしくしているが、いずれ覚醒し、家全体が寝静まった頃に一人、また一人と……。
ああ……早まった。明らかに早まった。こんな所に雇われるんじゃなかった。
いつか絶対襲われる。
…………リーリャは迷信を本気で信じるタイプだった。
★ ★ ★
最初の一年ぐらいは、そんな風に怯えていた。
しかし、いつからだろうか。予測できなかったルーデウスの行動がパターン化された。
神出鬼没ではなくなり、二階の片隅にあるパウロの書斎に篭るようになった。
書斎といっても、何冊か本があるだけの簡素な部屋だ。
ルーデウスは、そこに篭って出てこない。ちらりと覗いてみると、本を眺めてブツブツと何かを呟いている。
意味のある言葉ではない。
ないはずだ。少なくとも、中央大陸で一般的に使われている言語ではない。
言葉を喋るのもまだ早い。文字なんてもちろん教えていない。
だから 赤ん坊が本を見て、適当に声を出しているだけだ。
そうでなければおかしい。
だが、リーリャには、それがどうしても、意味のある言葉の羅列に聞こえて仕方がなかった。
ルーデウスが本の内容を理解しているように見えて仕方がなかった。
恐ろしい……。と、ドアの隙間からルーデウスを見ながら、リーリャは思う。
しかし、不思議と嫌悪感はなかった。
思えば、書斎に篭るようになってから、正体不明の不気味さや気持ち悪さは次第になりを潜めていった。
たまに気持ち悪く笑うのは変わらないが、抱き上げても不快感を覚えなくなった。
胸に顔も埋めないし、鼻息も荒くならない。
どうして自分はこの子をおぞましいなどと思っていたのだろうか。
最近はむしろ、邪魔してはいけないと思うような真摯さや勤勉さを感じるようになった。
ゼニスに話してみると、同じように感じたらしい。
それ以来、放っておいたほうがいいのでは、と思うようになった。
異常な感覚だと思った。
生まれて間もない赤子を放っておくなど、人としてあるまじき行為だ。
しかし、最近のルーデウスの瞳には知性の色が見えるようになった。
数ヶ月前までは痴性しか感じられなかった瞳にだ。
確固たる意志と、輝かんばかりの知性がだ。
どうすればいいのか。知識はあれども経験の薄いリーリャには、判断が難しい。
子育てに正解などない、と言っていたのは、近衛侍女の先輩だったか、それとも故郷の母親だったか。
少なくとも今は気持ち悪くないし、不快にもならない。怖気も走らない。
ならば、邪魔をして元に戻すこともない。
──放っておこう。
リーリャは最終的に、そう判断したのだった。
第三話 「魔術教本」
俺が転生して、約二年の歳月が流れた。
足腰もしっかりしてきて、一人で二足歩行ができるようになった。
この世界の言葉も喋れるようになってきた。
★ ★ ★
本気で生きると決めて、まずどうしようかと考えた。
生前では何が必要だったか。
勉強、運動、技術。
赤ん坊にできることは少ない。せいぜい抱き上げられた拍子に胸に顔を埋めるぐらいだ。
メイドにそれをやるとはあからさまに嫌そうな顔をする。
きっとあのメイドは子供嫌いに違いない。
運動はもう少し後でいいだろうと考えた俺は、文字を覚えるため、家の本を読み始めた。
語学は大切だ。
日本人は自国語の識字率はほぼ一〇〇%に近いが、英語を苦手とする者は多く、外国に出ていくとなると尻込みする者も多い。外国の言葉を習得しているということが、一つの技能と数えられるぐらいに。よって、この世界の文字を覚えることを、最初の課題とした。
家にあったのはたった五冊だ。
この世界では本は高価であるのか、パウロやゼニスが読書家ではないのか。
恐らく両方だろう。数千冊の蔵書を持っていた俺には信じられないレベルだ。
もっとも、全部ラノベだったが。
五冊とはいえ、文字を読めるようになるのには十分だった。
この世界の言語は日本語に近かったため、すぐに覚えることができた。
文字の形は全然違うのだが、文法的なものはすんなりと入ってきた。
単語を覚えるだけでよかった。言葉を先に覚えていたのも大きい。
父親が何度か本の内容を読み聞かせてくれたから、単語をスムーズに覚えることができたのだ。
この身体の物覚えの良さも関係しているのかもしれない。
文字がわかれば、本の内容は面白い。
かつては勉強を面白いと思うことなど、一生涯ないと思っていたが、よくよく考えてみれば、ネトゲの情報を覚えるようなものだ。面白くないわけがない。
それにしても、あの父親は乳幼児に本の内容が理解できるとでも思っているのだろうか。
俺だったからよかったものの、普通の幼児なら大顰蹙ものだ。大声で泣き叫ぶぞ。
家にあった本は次の五冊だ。
『世界を歩く』
世界各国の名前と特徴が載ったガイド本。
『フィットアの魔物の生態・弱点』
フィットアという地域に出てくる魔物の生態と、その対処法。
『魔術教本』
初級から上級までの攻撃魔術が載った魔術師の教科書。
『ペルギウスの伝説』
ペルギウスという召喚魔術師が、仲間たちと一緒に魔神と戦い世界を救う勧善懲悪のお伽話。
『三剣士と迷宮』
流派の違う三人の天才剣士が出会い、深い迷宮へと潜っていく冒険活劇。
最後の二つのバトル小説はさておき、他三つは勉強になった。
特に魔術教本は面白い。
魔術の無い世界からきた俺にとって、魔術に関する記述は実に興味深いものである。
読み進めていくと、いくつか基本的なことがわかった。
一.まず、魔術は大きく分けて三種類しかない。
『攻撃魔術』──相手を攻撃する。
『治癒魔術』──相手を癒す。
『召喚魔術』──何かを呼び出す。
この三つ。そのまんまだ。
もっと色々なことができそうなものだが、教本によると魔術というものは戦いの中で生まれ育ってきたものだから、戦いや狩猟に関係のない所ではあまり使われていないらしい。
二.魔術を使うには、魔力が必要である。
逆に言えば、魔力さえあれば、誰でも使うことができるらしい。
魔力を使用する方法は二種類だ。
『自分の体内にある魔力を使う』
『魔力の篭った物質から引き出して使う』
このどちらかだ。
うまい例えが見つからないが、前者は自家発電、後者は電池みたいな感じだろう。
大昔は自分の体内にある魔力だけで魔術を使っていたらしいが、世代が進むにつれて魔術も研究され、高難度になり、それに伴って消費する魔力が爆発的に増えていったそうだ。
魔力の多い者はそれでもいいが、魔力の少ない者はロクな魔術が使えなかった。
なので、昔の魔術師は自分以外のものから魔力を吸い出し、魔術に充てるという方法を思いついたのだ。
三.魔術の発動方法には二つの方法がある。
『詠唱』
『魔法陣』
詳しい説明はいらないだろう。口で言って魔術を発動させるか、魔法陣を描いて魔術を発動させるか、だ。
大昔は魔法陣の方が主力だったらしいが、今では詠唱が主流だ。
というのも、大昔の詠唱は一番簡単なものでも一分~二分ぐらい掛かったらしい。
とてもじゃないが戦闘で使えるものではない。
逆に魔法陣は一度書いてしまえば、何度か繰り返し使用できた。
詠唱が主流になったのは、ある魔術師が詠唱の大幅な短縮に成功したからだ。
一番簡単なもので五秒程度まで短縮し、攻撃魔術は詠唱でしか使われなくなった。
もっとも、即効性を求められない上、複雑な術式を必要とする召喚魔術は、未だに魔法陣が主流だそうだ。
四.個人の魔力は生まれた時からほぼ決まっている。
普通のRPGだとレベルアップするごとにMPが増えていくものだ。
しかし、この世界では増えないらしい。
ほぼ全員が職業戦士だという。ほぼ、というからには多少は変動するようだが……。
俺はどうなんだろうか。
魔術教本には魔力の量は遺伝すると書いてある。
一応、母親は治癒魔術を使えるみたいだし、ある程度は期待していいんだろうか。
不安だ。両親が優秀でも、俺自身の遺伝子は仕事をしなさそうだし。
★ ★ ★
とりあえず俺は、最も簡単な魔術を使ってみることにする。
基本的に魔術教本には魔法陣と詠唱の両方が載っていたが、詠唱が主流らしいし、魔法陣を書くものもなかったので、そっちで練習することにする。
術としての規模が大きくなると詠唱が長くなり、魔法陣を併用したりしなければいけないらしいが、最初は大丈夫だろう。
ちなみに、熟練した魔術師は、詠唱がなくても魔術が使えるらしい。
無詠唱とか、詠唱短縮ってやつだ。
しかし、なぜ熟練すると詠唱なしで使えるようになるのだろうか。
魔力の総量が変わらないということは、レベルアップしてもMPが増えるわけじゃないだろうし。
逆に、熟練度が上がると消費MPが減るんだろうか。
いや、仮に消費MPが減ったところで、手順が減る理由にはならないか。
……まぁいいか。とりあえず使ってみよう。
俺は魔術教本を片手に、右手を前に突き出して、文字を読み上げる。
「汝の求める所に大いなる水の加護あらん、清涼なるせせらぎの流れを今ここに『ウォーターボール』」
血液が右手に集まっていくような感触があった。
その血液が押し出されるようにして、右手の先にこぶし大の水弾ができる。
「おおっ!!」
と、感動した次の瞬間、水弾はバチャリと落ちて、床を濡らした。
教本には、水の弾が飛んでいく魔術と書いてあるが、その場で落ちた。
集中力が切れると、魔術は持続しないのかもしれない。
集中、集中……。
血液を右手に集める感じだ。こう、こう、こんな感じ……うん。
俺は再度右手を構え、先ほどの感覚を思い出しながら、頭でイメージする。
魔力総量がどんだけあるかわからないが、そう何度も使えないと考えたほうがいい。
一回一回の練習を全て成功させるつもりで集中するんだ。
まず頭でイメージして、何度も何度も頭の中で繰り返して、それから実際やってみる。
躓いたら、そこをまた頭でイメージする。脳内で完璧に成功するまで。
生前、格ゲーでコンボ練習する時はそうしていた。
おかげで俺は、対戦でもコンボをほとんど落としたことがない。
だからこの練習法は間違っていない………と思いたい。
「すぅ……ふぅ……」
深呼吸を一つ。
足の先、頭の先から、右手へと血液を送るような感じで力を溜めていく。
そしてそれを、手のひらからポンと吐き出すような感じで……。
慎重に慎重に、心臓の鼓動に合わせて、少しずつ。少しずつ……。
水、水、水、水弾、水の弾、水の玉、水玉、水玉パンツ……。
邪念が混じった、もう一回。
ギュッと集めてひねり出して水水水水…………。
「ハァッ!!」
と、思わず寺生まれの人みたいな掛け声を上げた瞬間、水弾ができた。
「おっ、え……?」
ばちゃ。
驚いた瞬間、水弾はあっけなく落ちてしまった。
「…………あ」
あれ……今、詠唱しなかったよな?
なんでだ……?
俺がやったことと言えば、さっき魔術を使った時の感覚を、そのまま真似しただけだ。
もしかして、魔力の流れを再現できれば、別に詠唱しなくてもいいのか?
無詠唱ってそんな簡単にできるもんなのか?
普通は上位スキルだろ?
「簡単にできるんなら、詠唱ってのはなんの意味があるんだ?」
俺のような初心者でも、無詠唱で魔術を発動させることができた。
身体の魔力を手の先に集めて、頭の中で形を決める。
それだけで、だ。
なら、詠唱なんて必要ないだろう。みんなこうすればいい。
(……ふむ)
もしかすると、詠唱というのは魔術を自動化してくれるのではないだろうか。
いちいち集中して全身から血液を集めるように念じなくても、言葉を発するだけで全てやってくれる。
それだけのことなのではないだろうか。
車のマニュアルとオートマのようなもので、実は手動でやろうと思えばできるものなのではないだろうか。
『詠唱すれば自動的に魔術を使ってくれる』。
これの利点は大きい。
まず第一に、教えやすい。
体中の血管から血液を集めるような感じでー……と、説明するより、詠唱すれば誰でも一発でできるほうが、教えるほうも教えられるほうも楽だ。
そうして教えている間に段々と、『詠唱は必要不可欠なもの』となっていったのではないだろうか。
第二に、使いやすい。
言うまでもないことだが、攻撃魔術を使うのは戦闘中だ。
戦闘中に目をつぶって、うぬぬー、と集中するより、早口で詠唱したほうが手っ取り早い。
全力疾走しながら精緻な絵を描くのと、全力疾走しながら早口言葉を言うの、どっちが楽かということだ。
「人によっては前者の方が楽かもしれんが……」
パラパラと魔術教本をめくってみたが、無詠唱の記述はなかった。
おかしな話だ。俺がやった感じでは、そう難しくはなかった。
俺に特別才能があるのかもしれないが、他の人がまったく使えないってことはないだろう。
こう考えるのはどうだろう。
魔術師は普通、初心者から熟練者まで、みんな詠唱で魔術を使い続けているのだ。
何千回、何万回と使い続けるうちに身体が詠唱に慣れきってしまう。
なので、いざ無詠唱でやろうとしても、どうやればいいのかわからない。
ゆえに、一般的ではないとされ、教本には書かれていない。
「おお、辻褄があってる!!」
てことは、今の俺は一般的ではないってことだ。
すごくね?
うまいこと裏ワザを使えた感じじゃなくね?
『まさか くらいむ の かたりすと を おらとりお なしで?』
『ただ ふつうに この かたりすと を つかって ちゃねる を ひらかせただけなのに』
って感じじゃね?
うっは、興奮してきた!!
おっと、いかんいかん。ちょっと落ち着け、クールになれ。
生前の俺はこの感覚に騙されてあんなことになった。
パソコンが人並み以上にできることで選民意識を持ってしまったがゆえに、調子こいて失敗した。
自重しよう自重。大切なのは、自分が他人より上だと思わないことだ。
俺は初心者。初心者だ。
ボウリング初心者が初投で運よくストライクをとれただけ。
ビギナーズラックだ。才能があるとか勘違いしないで、ひたすら練習に励むべきだ。
よし。最初に魔術を詠唱して唱えて、その感覚を真似して、ひたすら無詠唱で練習する。
これでいこう。
「それじゃあもう一発」
と、右手を前に出してみると、妙にだるい。
しかし、なんか肩のあたりにズッシリと重いものが載っている感じがする。
疲労感だ。
集中したせいだろうか。
いや、俺もネトゲプロ(自称)の端くれ、必要とあらば不眠で六日間狩りをし続けることもできた男だ。
このぐらいで切れる集中力は持ちあわせていないはず。
「てことは、MPが切れたか……?」
なんてこった……。魔力総量が生まれた時に決まるのなら、俺の魔力は水弾二発分ということになる。
さすがに少なすぎね? それとも、最初だから魔力をロスしてるとか、そういうのなんかね?
いや、そんな馬鹿な。
念のためもう一発出してみたら、気絶してしまった。
★ ★ ★
「もう、ルディったら、眠くなったらちゃんとトイレにいってベッドに入らなきゃダメでしょ」
起きた時には、読書中に居眠りして、そのままおねしょをしたことになっていた。
ちくしょう。この歳で寝小便したと思われるとは……。
ちくしょう……ちくしょう……。って、まだ二歳か。寝小便ぐらい許されるか。
てか、魔力少なすぎだろ。
はぁ……萎えるわ……。まぁ、水弾二発でも、使い方次第か。
精々、咄嗟に出せるように練習だけしておくか……。
はぁ……。
★ ★ ★
次の日は、水弾を四つ作っても平気だった。
五つ目で疲れを感じた。
「あっれぇ……?」
昨日の経験から、次の一発で気絶するとわかっていたので、ここでやめておく。
で、考える。
最大六つ。昨日の二倍だ。
俺は桶に入った水弾五発分の水を見ながら、考える。
昨日の今日で回数が二倍に増えた理由を。
昨日は最初から疲れていたとか、初めてだから消費MPが大きかったとか。
今日は全部無詠唱でやったから、詠唱をする、しないで変わることはないはず。
わからん。
明日になったら、また増えているかもしれない。
★ ★ ★
翌日。
水弾を作れる回数が増えた。
十一個だ。
なんだか、使った回数分だけ増えている気がする。
もしそうなら、明日は二十一個になっているはずだ。
さらに翌日。
念のため、五個だけ使ってその日はやめておく。
さらにさらに翌日。
二十六個になっていた。
やっぱり、使った分だけ増えていく。
(嘘こきやがって……!!)
何が人の魔力総量は生まれた時に決まっている、だ。
才能なんて眼に見えないものを勝手に決め付けやがって。
子供の才能ってのは大人が勝手に見極めていいものじゃねえんだよ!!
「ま、本に書いてあることを鵜呑みにするなってことだな」
この本に書いてあるのは「人の幸せには限界がある」とかそういうレベルの話なのかもしれない。
あるいは、鍛えた結果の話なのだろうか。
頑張って鍛えても、魔力総量には限界値があるという話なのだろうか。
いやまて、そう結論付けるのはまだ早い。まだ仮説は立てられる。
例えば……。そう、例えば、成長に応じて増えていく、とか。
幼児の時期に魔力を使うと飛躍的に最大値が増える、とか。
あ、俺だけの特殊体質ってのも捨てがたいな。
……いや、だから自分を特別だと思うなって。
元の世界でも、成長期に運動すれば能力が飛躍的に伸びるとか言われていた。
逆に成長期を過ぎてから、頑張っても伸び率が悪いとも。
この世界だって、魔力とかなんとか言ってるけど、人間の体の構造は変わらないはずだ。
基本は一緒。
なら、やることは一つだ。
成長期が終わる前に鍛えられるだけ、鍛える。
★ ★ ★
翌日から、限界まで魔力を使っていくことにした。
同時に、使える魔術の数を増やしていく。
感覚さえ覚えれば、無詠唱で再現することは簡単だ。
とりあえず、近日中に全系統の初級魔術は完全にマスターしたいと思う。
初級魔術というのは、文字通り攻撃魔術の中で最も低いランクに位置する。
水弾や火弾はその中でも、特に入門的な位置づけにある初級魔術だ。
魔術の難易度は七段階に分かれている。
『初級、中級、上級、聖級、王級、帝級、神級』
一般的に教育を受けた魔術師は自分の得意な系統の魔術を上級まで使えるが、他の魔術は初級か中級までしか使えないらしい。
上級より上のランクを使えるようになると、系統に応じて火聖級とか水聖級とか呼ばれて一目置かれるのだとか。
聖級。
ちょっと憧れる。
しかし魔術教本には、火・水・風・土系統の上級魔術までしか載っていなかった。
聖級以上はどこで覚えればいいのだろうか……。
いや、あまり考えないようにしよう。
RPGツ○ールでも、最強のモンスターから作ると、高確率で挫折する。
まずは最初のスライムからだ。
もっとも、俺はスライムから作っても完成させたことがないがね。
★ ★ ★
さて、教本に書かれている水系統の初級魔術は以下の通りだ。
水弾:水の弾を飛ばす。ウォーターボール。
水盾:地面から水を噴出させて壁を作る。ウォーターシールド。
水矢:二十㎝ほどの水の矢を飛ばす。ウォーターアロー。
氷撃:氷の塊を相手にぶつける。アイススマッシュ。
氷刃:氷の剣を作り出す。アイスブレード。
ひと通り使ってみた。
初級と一口に言っても、使う魔力はまちまちだった。
水弾を一とすれば、大体二~二十ぐらいか。
基本的には水系だ。
火を使って火事にでもなったら危ないからな。
火事と言えば、消費魔力は温度も関係しているのか、上級になればなるほど氷が増えていくようだ。
しかし、水弾にしろ水矢にしろ、飛ばすとか書いてあるのに飛んでいかなかった。
なんだろう、どこかで何かを間違えているのだろうか……。
うーむ。わからん。
魔術教本には、魔術の大きさや速度についても書いてある。
もしかすると、弾を作り出した後に、さらに魔力で操作するのだろうか。
やってみる。
「お?」
水弾が大きくなった。
「おお!!」
ばちゃん。
「おぉ……」
しかし、やはり落ちてしまう。
その後、色々やって水弾を大きくしたり小さくしたり。
違う水弾を二つ同時に作ったり。
それぞれの大きさを変えてみたり。
と、新たな発見はあったが、一向に飛んでいかなかった。
火と風は重力に影響を受けないせいか空中に浮いているのだが、結局は一定時間で消えてしまう。
ふよふよと浮いた火の玉を風で飛ばしてみたりもしたが、何かが違う気がする。
うーむ……。
★ ★ ★
二ヶ月後。
試行錯誤の末、ようやく水弾を飛ばすことができた。
それが切っ掛けとなり、詠唱の仕組みが大体解明できた。
詠唱は、ある一定のプロセスを辿っている。
生成→サイズ設定→射出速度設定→発動。
このうち、サイズ設定と射出速度設定を術者自身が設定することで、術が完成する。
つまり詠唱をすると。
一.まず自動的に使いたい魔術の形が作り出される。
二.その後、一定時間以内に魔力を追加して、サイズを調整。
三.サイズ調節後、さらに一定時間以内に魔力を追加することで、射出速度を調整。
四.準備時間が終わると、術者の手を離れ、自動的に発射される。
という流れになるわけだ。
多分間違っていない……と思う。
詠唱の後、二回に分けて魔力を追加するのがコツだったのだ。
サイズ調節をしなければ、射出速度の調節に行かない。
道理で飛ばそうとしても大きくなるだけで何も起こらないわけだ。
ちなみに無詠唱でやる場合は、それら全てのプロセスを自分でやる必要がある。
面倒に思えるが、サイズと射出速度の入力待ち時間を短縮できる。
詠唱するよりも数段早く発射することが可能だ。
また、無詠唱なら生成の部分もいじることができた。
例えば教本には書いていないが、水弾を凍らせて、氷弾にするとかだ。
これを練習していけば、カイザーフェニックス(ドヤ顔)とかもできるだろう。
アイデア次第でいくらでも応用が効くのだ。
面白くなってきた!!
……けど、基本は大事だ。
色々と実験するのは、魔力総量がもっと増えてからにしよう。
『魔力総量を上げる』
『息をするように無詠唱で魔術を使えるようになる』
次の課題はこの二つだ。
いきなり大きな目標を立てると挫折しちゃうからな。
小さなことからコツコツだ。
よーし、頑張るぞ。
そうして、俺は毎日、気絶寸前まで初級魔術を使い続けて過ごした。
第四話 「師匠」
三歳になった。
最近になって、ようやく両親の名前を知った。
父親はパウロ・グレイラット。
母親はゼニス・グレイラット。
俺の名前はルーデウス・グレイラット。
グレイラット家の長男というわけだ。
ルーデウスと名付けられたわけだが、父親も母親も互いに名前を呼び合わないし、俺のことはルディと略すので、正式名称を覚えるのに時間が掛かったのだ。
★ ★ ★
「あらあら、ルディは本が好きなのね」
本を常に持って歩いていると、ゼニスはそういって笑った。
彼らは俺が本を持っていることを咎めなかった。
食事中も脇に置いているし。だが、魔術教本は家族の前では読まないようにしていた。
能ある鷹は爪を隠す、というわけではないが、この世界における魔術の立ち位置がわからない。
生前の世界では、中世に魔女狩りというものがあった。
魔法を使う者は異端で火あぶりというアレだ。
さすがにこんな本が実用書として存在しているこの世界で、魔術が異端ということはないだろうが、あまりいい顔はされないかもしれない。
魔術は大人になってから、とかいう常識があるのかもしれない。
なにせ、使いすぎると気絶するような危ないものなのだ。
成長を阻害させるとか思われているかもしれない。
そう思ったので、家族の前では魔術のことは隠している。
もっとも、窓の外に向かって魔術をぶっ放したこともあるので、もうバレてるかもしれない。
しょうがないじゃないか、射出速度がどれだけ出るのか試したかったんだから。
メイド(リーリャさんというらしい)は、たまに険しい顔で俺を見てくるが、両親は相変わらずのほほんとしているので、大丈夫だと思いたい。
止められるのならそれでもいいが、成長期があるとして、それを逃したくはない。
才能は伸びる時に伸ばしておかないと錆び付いてしまう。
今のうちに使えるだけ使っておかなければ。
★ ★ ★
そんな魔術の秘密特訓に終止符が打たれた。
ある日の午後だった。
そろそろ魔力量も増えてきたし、中級の魔法を試そうと、軽い気持ちで水砲の術を詠唱した。
サイズ:一 速度:〇。
いつもどおり、桶に水が溜まるだけだと思っていた。
ちょっと溢れるかもね、ぐらいには考えていた。
そうしたら、凄まじい量の水が放出されて、壁に大穴が開いた。
穴の縁から、ポタポタと水滴が地面に落ちるのを、俺は呆然と見ていた。
呆然としながらも、どうにかしようとは思わなかった。
壁には穴が開き、間違いなく魔術を使ったとバレる。
それはもうしょうがないことだった。
俺は諦めが早いのだ。
「何事だ!! うおあっ……」
最初にパウロが飛び込んできた。
そして、壁に開いた大穴を見てあんぐりと口を開けた。
「ちょ、おい、なんだこりゃ……ルディ、大丈夫なのか……?」
パウロはいい奴だ。
どう見ても俺がやったようにしか見えないのに、俺の身を案じているのだから。
今も「魔物……か? いやこのへんには……」などと呟いて、注意深く周囲を警戒している。
「あらあら……」
続いてゼニスが部屋に入ってくる。
彼女は父親より冷静だった。
壊れた壁と、床の水たまりなどを順番に見ていき、
「あら……?」
目ざとく、俺の開いていた魔術教本のページに目を留めた。
そして俺と魔術教本を見比べると、俺の目の前でしゃがみこんで、優しげな顔で目線を合わせる。
怖い。
目の奥が笑ってない。
泳ぎそうになる目線を、必死にゼニスに向ける。
俺はニート時代に学んだのだ、悪いことをして開き直って不貞腐れても、事態は悪化する一方だと。
だから、決して目を逸らしてはいけない。
こういう時に必要なのは、真摯な態度だ。
目を合わせて逸らさない、というのはそれだけで真摯に見える。
内心でどう思っていても、少なくとも見た目は。
「ルディ、もしかして、この本に書いてあるのを声に出して読んじゃった?」
「ごめんなさい」
俺はこくりと頷き、謝罪を口にする。
悪いことをした時は、潔く謝ったほうがいい。
俺以外にやれる奴はいない。
すぐバレる嘘は信用を落とす。
生前はそうやって軽い嘘を重ねて信用を落としていったものだ。
同じ失敗はすまい。
「いや、だっておまえ、これは中級の……」
「きゃー! あなた聞いた!! やっぱりウチの子は天才だったんだわ!!」
パウロの言葉を、ゼニスが悲鳴で遮った。
両手を握って、嬉しそうにぴょんぴょんと跳んだ。
元気だね。
俺の謝罪はスルーですかい?
「いや、おまえ、あのな、だって、まだ文字を教えてな……」
「今すぐ家庭教師を雇いましょう!! 将来はきっとすごい魔術師になるわよ!!」
パウロは戸惑い、ゼニスは歓喜している。
どうやら、ゼニスは俺が魔術が使えたのが嬉しくてしょうがないらしい。
子供が魔術を使っちゃいけないとかは、俺の杞憂に過ぎなかったらしい。
リーリャは平然と無言で片付けを始めている。
恐らく、このメイドは俺が魔術を使えることを知っていたか、薄々感づいていたのだろう。
別に悪いことじゃないから特に気にも留めなかっただけで。
あるいは、この両親が歓喜するところを見たかったのかもしれない。
「ねえあなた、明日にもロアの街で募集を出しましょう!! 才能は伸ばしてあげなくっちゃ!!」
ゼニスは一人で興奮し、天才だの才能だのと騒いでいる。
いきなり魔術をぶっぱなしたぐらいで天才ときた。
親馬鹿ってやつなのか、中級魔術を使えるのがすごいことなのか、判別がつかない。
いや、やはり親馬鹿だろう。
俺はゼニスの前では魔術を使う素振りは一切見せなかった。
なのに「やっぱり」なんて言葉が出てくるということは、以前から俺が天才かもしれないと思っていたのだ。
根拠も無く……。
ああ、いや。
心当たりがあった。
俺はひとりごとが多い。
本を読んでいる時でも、気に入った単語やフレーズをボソボソと呟いてしまうことがある。
この世界に来てからも、本を読みながらボソボソとひとりごとを口にしていた。
最初は日本語だったが、言葉を覚えてからは無意識にこの世界の言葉を使うようになった。
そして、ひとりごとを聞いたゼニスは「ルディ、それはね──」と、単語の意味を教えてくれるのだ。
おかげで、この世界の固有名詞も結構憶えることができたのだが、ま、それはおいておこう。
誰も何も言わなかったが、俺はこの世界の文字を独学で覚えた。
言葉も教えてもらっていない。
両親からしてみれば、我が子は教えてもいないのに文字を読み、本の内容を口に出して喋れる、という認識をされていたのだろう。
天才だろう。
俺だって自分の子供がそんなんだったら天才と思う。
生前、弟が生まれた時もそうだった。
弟は成長が早く、何をするのも俺や兄より早かった。
言葉を喋るのも、二本の足で歩くのも。
親というのはのんきなもので、何かを子供がする度に、「あの子は天才じゃないかしら」とのたまうのだ。それが大したことではなくとも。
まぁ、高校中退のクズニートだったとはいえ、精神年齢は三十歳以上だ。
それぐらいには思われないとやるせない。
十倍だぞ十倍!!
「あなた、家庭教師よ!! ロアの街ならきっといい魔術の先生が見つかるわ!!」
そして、才能がありそうと見るや英才教育を施そうとするのは、どこの親も一緒らしい。
生前の俺の親も弟を天才だと持て囃して、習い事をたくさんさせていた。
というわけでゼニスは魔術師の家庭教師を付けることを提案したのだが。
これをパウロが反対した。
「いやまて、男の子だったら剣士にするという約束だったろう」
男だったら剣を持たせ、女だったら魔術を教える。
生まれる前にそういう取り決めをしていたらしい。
「けれど、この歳で中級の魔術を発動できるのよ!! 鍛えればすごい魔術師になれるわ!!」
「約束は約束だろうが!!」
「なによ約束って!! あなたいつも約束破るじゃない!!」
「俺のことは今は関係ないだろうが!!」
その場で夫婦喧嘩を始める二人。
平然と掃除するリーリャ。
「午前中は魔術を学んで、午後から剣を学べばいいのでは?」
口論はしばらく続いたが、掃除を終えたリーリャがため息混じりにそう提案することで、口論はやんだ。
そして、馬鹿親は子供の気持ちを考えず、習い事を押し付ける。
ま、本気で生きるって決めたし、いいんだけどね。
★ ★ ★
そんなワケで、ウチは家庭教師を一人雇うことになった。
貴族の子弟の家庭教師という仕事は、それなりに実入りがいいらしい。
パウロはこのへんでは数少ない騎士で、一応は下級貴族という位置づけになるらしいから、給金も相場と同じぐらいのものを出せるのだとか。
しかし、何しろここは国の中でも端の方の田舎。
つまり辺境らしく、優秀な人材はもちろん、魔術師すらほとんどいない。
魔術ギルドと冒険者ギルドに依頼を出したところで、はたして応じる者がいるかどうか……。
という心配があったらしいが、あっさりと見つかったらしく、明日から来てくれることになった。
この村には宿屋が無いので、住み込みになるらしい。
両親の予想によると、来るのは恐らくすでに引退した冒険者だ。
若者ならこんな田舎には来たがらないし、宮廷魔術師なら王都の方にいくらでも仕事がある。
この世界では、魔術の教師ができるのは上級以上の魔術師と決まっている。
ゆえに冒険者のランクとしては中の上か、それ以上。
長年魔術師として研鑽を積んだ中年か老人で、
ヒゲをたくわえたまさに魔術師って感じのが来るだろう、という話だった。
「ロキシーです。よろしくお願いします」
しかし、予想を裏切って、やってきたのはまだ年若い少女だった。
中学生ぐらいか。
魔術師っぽい茶色のローブに身を包み、水色の髪を三つ編みにして、ちんまりというのが正しい感じの佇まい。
日焼けしていない白い肌に、少し眠そうジトっとした目。無愛想な感じの口元。眼鏡こそかけていないものの、図書館に引きこもっている文学系少女という印象を受ける。
手にしているのは鞄一つと、いかにも魔術師が持っていそうな杖だけだ。
そんな彼女を、家族三人でお出迎え。
「……」
「……」
彼女の姿を見て、両親はびっくりして声も出ないようだった。
そりゃそうだろう。
予想とあまりに違いすぎる。
家庭教師として雇うのだから、それなりに歳を重ねた人物を想像していたのだろう。
それが、こんなちんまいのだ。
もっとも、数多くのゲームをこなしてきた俺にしてみれば、ロリっこ魔術師の存在は別段不思議ではない。
ロリ・ジト目・無愛想。
三つ揃った彼女はパーフェクトだ。
ぜひ俺の嫁に欲しい。
「あ、あ、君が、その、家庭教師の?」
「あのー、ず、随分とそのー」
両親が言いにくそうにしているので俺がズバリ言ってやることにした。
「小さいんですね」
「あなたに言われたくありません」
ピシャリと言い返された。
コンプレックスなのだろうか。
胸の話じゃないんだけどな。
ロキシーはため息を一つ。
「はぁ。それで、わたしが教える生徒はどちらに?」
周囲を見渡して聞いてくる。
「あ、それはこの子です」
ゼニスの腕の中にいる俺が紹介される。
俺はキャピっとウインク。
すると、ロキシーは目を見開いたのち、ため息を吐いた。
「はぁ、たまにいるんですよねぇ、ちょっと成長が早いだけで自分の子供に才能があると思い込んじゃうバカ親……」
ぼそりと呟く。
聞こえてますよ!! ロキシーさん!!
ま、俺もそれには激しく同意だけどね。
「何か」
「いえ。しかし、そちらのお子様には魔術の理論が理解できるとは思いませんが?」
「大丈夫よ、うちのルディちゃんはとっても優秀なんだから!!」
ゼニスの親馬鹿発言。
再度、ロキシーはため息を吐いた。
「はぁ。わかりました。やれるだけのことはやってみましょう」
これは言っても無駄だろうと判断したらしい。
こうして、午前はロキシーの授業を、午後はパウロに剣術を習うこととなった。
★ ★ ★
「では、この魔術教本を……いえ、そのまえに、ルディがどれほど魔術を使えるか試してみましょう」
最初の授業で、ロキシーは俺を庭に連れ出した。
魔術の授業は主に外でやるらしい。
家の中で魔法をぶっぱなせばどうなるか、ちゃんとわかっているのだ。
俺のように、壁をぶっ壊したりはしないのだ。
「まずはお手本です。汝の求める所に大いなる水の加護あらん、清涼なるせせらぎの流れを今ここに『ウォーターボール』」
ロキシーの詠唱と同時に、彼女の手のひらにバスケットボールぐらいの水弾ができた。
そして、庭木の一つに向かって高速で飛んでいき、
ベキィ。
と、木の幹を簡単にへし折ると、柵を水浸しにした。
サイズ:三、速度:四ぐらいだろうか。
「どうですか?」
「はい。その木は母様が大事に育ててきたものですので、母様が怒ると思います」
「え? そうなんですか!?」
「間違いないでしょう」
一度、パウロが剣を振り回して木の枝を叩き折ったことがあるが、その時のゼニスの怒りようは半端ではなかった。
「それはまずいですね、なんとかしないと……!!」
ロキシーは慌てて木に近づくと、倒れた幹をうんしょと立てた。
そして顔を真っ赤にして幹を支えたまま、
「うぐぐ……、神なる力は芳醇なる糧、力失いしかの者に再び立ち上がる力を与えん『ヒーリング』」
詠唱。
木の幹はじわじわと折れる前へと戻っていった。
おー、すげー。
とりあえず褒めとこう。
「ふう」
「先生は回復魔術も使えるのですね!!」
「え? ええ。中級までは問題なく使えます」
「すごい!! すごいですぅ!!」
「いいえ、きちんと訓練すればこのぐらいは誰にでもできますよ」
言い方はややぶっきらぼうだったが、口元はにまにまとだらしなく緩んでおり、ちょっと得意げに鼻がひくひくと動いていた。嬉しそうだ。
特に捻りもなくすごいすごいと連呼しただけでこれか、チョロそうだ。
「では、ルディ。やってみてください」
「はい」
俺は手を構えて……。
ヤバイ、一年近く水弾の詠唱なんてしてなかったから思い出せない。
今ロキシーが言ったばっかだよな。えっと、えっと。
「えっと、なんて言うんでしたっけ?」
「汝の求める所に大いなる水の加護あらん、清涼なるせせらぎの流れを今ここに、です」
ロキシーは淡々と言った。この程度は想定内らしい。
しかし、そんな淡々と言われても一度では覚えられん。
「汝の求める所に……ウォーターボール」
思い出せないので端折った。
先ほどのロキシーの作った水弾よりもちょっとだけ小さく、ちょっとだけ遅く。
彼女より大きいのを作ったら拗ねるかもしれないしな。
俺は年下の女の子には寛容なのだ。
バスケットボールの水弾は、バシュンという音を立てて勢いよく射出された。
バキバキッと木が倒れる。
ロキシーは難しい顔をしてそれを見ていた。
「詠唱を端折りましたね?」
「はい」
何かヤバかっただろうか。
そういえば、無詠唱は魔術教本にも載っていない。
何気なく使っていたが、実は何か禁忌に触れたりするんだろうか。
それとも、俺のようなのが詠唱を端折るとか十年早いとか怒られるんだろうか……。
その場合、いいじゃねえかよ、あんなダセェ詠唱していられっかよ、って反発したほうがいいんだろうか。
「いつも詠唱を端折っているのですか?」
「いつもは……無しで」
どう答えるか迷ったが、正直に答えておく。
これから勉強を教わるのだし、いずれはバレる。
「無し!?」
ロキシーは目をむいて、マジで、という顔で俺を見おろした。
「……そう。いつもは無し。なるほどね。疲れは感じていますか?」
しかし、すぐにすまし顔で取り繕った。
「はい、大丈夫です」
「そう。水弾の大きさ、威力共に申し分ないです」
「ありがとうございます」
ロキシーは、ここでようやく微笑んだ。
ニヤリと。
そして呟く。
「……これは鍛えがいがありそうですね」
だから聞こえてるって。
「さあ、さっそく次の魔術を……」
ロキシーが興奮した様子で、魔術教本を開こうとした時。
「ああぁー!!」
背後で叫び声が上がった。
様子を見にきたゼニスだった。
飲み物を載せたお盆を取り落とし、両手で口を押さえて、ボッキリ折れた木を見ている。
悲しげな表情。
次の瞬間、その表情に怒りの色が篭っていく。
あ、やべぇ。
ゼニスはツカツカと歩いてくると、ロキシーに詰め寄った。
「ロキシーさん!! あなたね!! ウチの木を実験台にしないで頂戴!!」
「えっ!! しかしこれはルディがやったもので……」
「ルディがやったのだとしても、やらせたのはあなたでしょう!!」
ロキシーは背景にイナズマが奔ったようなショックを受け、白目になってがっくりと項垂れた。
まぁ、三歳児に責任をなすりつけちゃいかんだろ。
「はい……そのとおりです」
「こういうことは二度としないで頂戴ね!!」
「はい、申し訳ありません、奥様……」
その後、ゼニスは庭の木をヒーリングで華麗に修復すると、家の中へと戻っていった。
「早速失敗してしまいました……」
「先生……」
「ハハッ、明日には解雇ですかね……」
地面に座り込んで『の』の字を書き始めそうなロキシー。
打たれよわいなぁ……。
俺は彼女の肩をぽんぽんと叩いた。
「……」
「ルディ?」
叩いてみたが、二十年近く人と話してこなかった俺には、慰めの言葉が見つからない。
ごめんなさい。こういう時、なんて言っていいのかわからないの……。
いや、落ち着け。
考えろ考えろ、エロゲーの主人公ならこんな時にどうやって慰めてた?
そう、確か、こんな感じだ。
「先生は今、失敗したんじゃありません」
「ル、ルディ……?」
「経験を積んだんです」
ロキシーはハッと俺を見た。
「そ、そうですね。ありがとうございます」
「はい。では授業の続きをお願いします」
こうして、初日からロキシーとちょっと仲良くなれた。
★ ★ ★
午後はパウロと鍛錬だ。
俺の体格にあった木剣がないため、基本的には体作りが中心となってくる。
ランニング、腕立て伏せ、腹筋、などなど。
パウロは、とりあえず最初は体を動かす、ということを中心にやらせるつもりらしい。
パウロが仕事で指導ができない日も、基礎体力訓練だけは毎日欠かさずやるように言いつけられた。
そのへんは、どこの世界でも変わらないらしい。
頑張ろう。
子供の体力では午後全部を使って鍛錬をするわけにもいかないので、剣術は昼下がりまでには終了する。
そのため、俺は夕飯までの間に、魔力を使い果たすまで使う。
魔術というものは『大きさを変化させる』と使用する魔力量が変わる。
詠唱した時に何も意識しない時を一とすると、大きくすればするほど加速度的に消費魔力が増えていく。
質量保存の法則ってやつだ。
しかし、なぜか逆に小さくすることでも消費魔力が増えるのだ。
この理論はよくわからない。
こぶし大の水弾を作り出すより、一滴の水を生み出すほうがはるかに魔力を消費する。
おかしな話だ。
前々から疑問に思ってみたのでロキシーに聞いてみたら、「そういうものだ」と返された。
解明されていないらしい。
仕組みはわからない。
しかし、訓練を行うに関しては、その仕様も悪くはない。
最近は魔力総量が結構増えてきたので、大きな魔術を使わなければ消費しきれないのだ。
魔力を使うだけなら、力尽きるまで最大出力でぶっぱなせばいい。
だが、そろそろ応用力をつけていっても良いだろう。
なので、できる限り細かい作業を練習することにした。
魔術で小さく、細かく、複雑な作業をするのだ。
例えば、氷で彫像を作ったり、指先に火を灯して板に文字を書いたり。
庭から土を持ってきて成分を選り分けたり……。
錠前の鍵を掛けたり外したり、なんてのもやってみた。
土の魔術は金属や鉱物にもある程度作用するようだ。
ただし、金属の種類が硬くなればなるほど、消費される魔力が大きくなった。
やはり硬いものを変化させるのは、難しいらしい。
操作する対象が小さくなればなるほど、細かく複雑に、かつ正確に素早く動かそうとすればするほど、消費する魔力の量が莫大になっていく。
野球ボールを全力投球する。
針の穴にゆっくりと糸を通す。
この二つで同じぐらいの魔力を消耗するといった感じだ。
また、違う系統の魔術を同時に使用するということもやってみた。
同じ系統を同時に使うのに比べ、三倍以上の魔力を消費するようだ。
つまり、二種類の系統の魔術を同時に発動し、小さく細かく素早く正確に動かせば、簡単に魔力を全消費することができた。
そんな毎日を続けていたら──
半日以上、魔術を使い続けても、まったく底が見えなくなってきた。
もうこれくらいで十分か、そんな気持ちが芽生える。
俺の怠け者の部分が、そろそろいんじゃね? と囁いてくる。
その度に、俺は自分を叱りつけた。
筋トレだってちょっとサボったら体が鈍る。
魔力だってそうかもしれない。一時的に増えたからって訓練を欠かしてはいけないのだ。
★ ★ ★
夜中に魔術を使っていると、どこからかギシギシアンアンと悩ましい音が聞こえだした。
どこからかもなにも、パウロとゼニスの寝室に決まっている。
お盛んだ。
そう遠くない未来に、俺の弟か妹が生まれることだろう。
できれば妹がいいな。
うん。弟はいやだ。
俺の脳裏には、俺の愛機パソコンにバットをフルスイングする弟の姿が残っている。
弟はいらない。
可愛い妹がいい。
「やれやれだぜ……」
生前なら、こんな悩ましい音を聞いたら、即座で壁ドンか床ドンして黙らせたものだ。
おかげで姉は家に男を連れてこなくなった。
懐かしい。
当時、ああいうことをする奴らは、俺の世界を黒く塗りつぶす巨悪に思えた。
俺をイジメてた奴らが、俺の決して手の届かない領域からアホ面して見下ろしてるような気がして、やり場のない怒りが襲った。
暗く不快な場所に落とした張本人が、お前、まだそんな所にいるの? と、見下してくるのだ。
これほど悔しいことはない。
しかし、最近は違う。
身体が子供になったせいか、ヤっているのが両親なせいか、あるいは自分自身で未来に向かって努力しているせいか。
二人の営みを、すげー微笑ましい気分で聞いている俺がいる。
フッ、俺も大人になったもんだぜ……。
音だけ聞いていると、なんとなく内容もわかる。
どうやら、パウロはかなりお上手らしい。
ゼニスの方はあっという間に息も絶え絶えノックダウン状態になっているのに、パウロは「まだまだこれからだぞぅ」とか言って攻めつづけている。
陵辱系エロゲの主人公みたいな男だ。
底知れぬ精力……。
ハッ、もしかしてパウロの息子である俺のムスコにもそんなパワーが秘められているのでは!?
覚醒はよ。
ヒロインはよ!!
俺にもピンク色の展開を!!
と、最初の頃は興奮していたが、最近では枯れたもので、ギシギシと軋む廊下を通り抜けて、平然とトイレに行くようになった。
ちなみに、部屋の前を歩くとギシアンがぴたっと止まるので、結構面白い。
その日も、歩けるようになった息子がいるということを知らしめてやるべく、トイレへと向かった。
どれ、今日は一つ、声でも掛けてやるか。
おとーさん、おかーさん、裸でなにしてるの? とか聞いてみるか。
言い訳が楽しみだぜ。ククク……。
そんなことを考えながら、音を殺して部屋を出た。
そこには先客がいた。
青髪の少女が、暗い廊下に座り込んで、ドアの隙間から寝室を覗いていた。
頬は紅潮し、やや荒い息を潜めるように、しかし視線は部屋の奥に釘付け。
その手は、ローブの下へと潜り込んで何やら悩ましげな動きを見せていた。
俺はそっと自室へと戻った。
ロキシーとて年頃の娘である。
彼女がこのようなアレにふけるのを、見てみぬふりをする情が俺にも存在した。
……なんちゃって。
いやぁ、いいものを見た。
★ ★ ★
四ヶ月ほど経った。
中級までの魔術は使えるようになった。
ということで、ロキシーと夜の座学をすることになった。
おっと、夜のって付いてるからってエロいことをするわけじゃないぞ。
勉強するのは、主に雑学だ。
ロキシーはいい教師だ。
決してカリキュラムにこだわりを持たない。
俺の理解度に合わせて、授業の内容をエスカレートさせる。
生徒への対応力が高いのだ。
教科書用に用意した本から質問を出して、俺が答えられれば次に行く。
わからなければ丁寧に教えてくれる。
それだけのことだが、俺は世界が広がるのを感じた。
生前、兄が受験の時、家庭教師を雇っていた時期があった。
俺も、一度だけ気まぐれでその内容を聞いたことがある。
だが、学校の授業の内容とそう変わるものではなかった。
それに比べて、ロキシーの授業はわかりやすく、面白い。
打てば響く授業だ。
ていうか、性に芽生え始めた中学生ぐらいの先生に勉強を教えてもらう。
そのシチュエーションが最高だ。
生前の俺なら、そんな妄想だけで三発はイケたね。
★ ★ ★
「先生、どうして魔術には戦闘用のものしかないんですか?」
「別に戦闘用しかないわけではないのですが……」
俺の唐突の質問にもロキシーはきちんと答えてくれる。
「そうですね、何から説明しましょうか……。まず魔術というのは、古代長耳族が創りだしたものだと言われています」
おお、エルフ!!
やはりいるのか!!
金髪で緑っぽい服を着ていて弓を持っていて触手に絡め取られる人たち!!
おっと、落ち着け。
俺の認識と違うかもしれない。
字面を見るに、耳は長いようだが……。
「長耳族というのは?」
「はい。長耳族とは、現在はミリス大陸の北の方に住んでいる種族です」
ロキシーの話によると。
大昔、まだ人魔大戦が起きる前、世界がまだ混沌として戦いが絶えなかった頃、古代長耳族たちは外敵と闘うため、森の精霊たちと対話し風や土を操ったそうだ。そして、それが史上最古の魔術と言われているのだとか。
「へえ、ちゃんと歴史があるんですね」
「当然です」
ロキシーは、茶化すなと言わんばかりに頷いた。
「今の魔術というのは、人族が戦争の中で長耳族の魔術を真似し、形態化させていったものです。人族はそういうのが得意ですからね」
「人族はそういうのが得意なんですか?」
「ええ、新しいものを生み出すのは、いつも人族です」
人族は発明大好きな人種らしい。
「戦闘用しかないのは、主に戦いの中でしか使われてこなかったというのもありますが……。魔術に頼らなくても、身近なものを使えば実現できるという理由もあります」
「身近なもの、というと?」
「例えば明かりが必要なら、ロウソクやカンテラを使えばいいでしょう?」
なるほど、よくある設定、ってやつか。
魔術を使うより、道具を使ったほうが簡単だから。
理にかなってるぜ。
もっとも、無詠唱なら道具を使うより簡単なんだがね。
「それに、全ての魔術が戦闘用というわけではありません。召喚魔術を使えば、必要に応じた力を持つ魔獣や精霊を召喚することもできますし」
「召喚魔術!! そのうち教えてもらえるんですか?」
「いえ、わたしには使えませんので。それに、道具というのなら、魔道具というものも存在します」
魔道具か。
字面からなんとなく想像がつくな。
「魔道具というのは?」
「特殊な効果を持つ道具です。内部に魔法陣を刻んであるので、魔術師でなくとも扱うことができます。もっとも、ものによっては大量の魔力を使いますが」
「なるほど」
大体想像どおりだ。
それにしても、ロキシーが召喚魔術を使えないのは残念だ。
攻撃魔術や治癒魔術はなんとなく原理がわかるが、召喚魔術は何をどうすればいいのかわからない。
それにしても、知らない単語が一気に増えたな。
人魔大戦、魔獣、精霊……。
大体わかるけど。一応聞いておくか。
「先生、魔獣と魔物はどう違うんですか?」
「魔獣と魔物は大きくは違いません」
基本的に魔物というのは従来の動物から突然変異で生まれる。
それが運よく数を増やして、種として定着し、世代を重ねて知恵をつけたのが魔獣だ。
もっとも、知恵をつけても人を襲うようなのは魔物と呼ばれることも多いらしい。
逆に、魔獣が世代を重ねて凶暴になり、魔物に戻るケースもあるとか。
具体的な線引きはないそうだ。
魔物・人を襲う。
魔獣・人を襲わない。
という認識でいいのか。
「というと、魔族は魔獣が進化したものなんですか?」
「全然違います。魔族という単語は、大昔に人族と魔族が戦争をしていた頃につけられた名称です」
「さっき言ってた、人魔大戦ってヤツですか?」
「そうです。最初の戦争があったのは七〇〇〇年ぐらい前ですね」
「それはまた、気が遠くなるぐらい昔ですね」
この世界は、わりと長い歴史を持っているようだ。
「そう昔でもないですよ。つい四〇〇年前にも、人族と魔族の間で戦争をしていましたからね。七〇〇〇年前に始めてから、休み休みずっと戦争してるんですよ、人族と魔族は」
四〇〇年でも十分昔だと思うが、しかし七〇〇〇年以上も争い続けているのか。
仲悪いねえ。
「はぁ、なるほど。それで結局、魔族というのは?」
「魔族というのは、結構定義が難しいのですが……」
曰く『一番新しい戦争で魔族側についていた種族』というのが一番わかりやすいらしい。
もっとも、例外もあるそうだが。
「あ、ちなみに私も魔族です」
「おぉ、そうだったんですか」
魔族がここで家庭教師をやっている。
てことは、今は戦争してないってことかな?
平和が一番。
「はい。正式には魔大陸ビエゴヤ地方のミグルド族です。ルディの両親も、わたしの姿をみて驚いていたでしょう?」
「あれは先生がちっちゃいからだと思っていました」
「小っちゃくありません」
ロキシーはムスッした顔で即座に言い返した。小さいことを気にしているらしい。
「あれはわたしの髪を見て驚いていたんです」
「髪?」
青くて綺麗な髪だと思うが。
「魔族は一般的に、緑に近い髪色を持つ種族ほど凶暴で危険だと言われています。特にわたしの髪は、光の加減では緑に見えなくもないですから……」
緑色。
この世界の警戒色なのだろうか。
ロキシーの髪は目が醒めるような水色だ。
彼女は自分の前髪をくるくるといじりながら説明してくれている。
仕草が可愛い。
日本で水色の髪といえば、パンク系かオバちゃんと相場は決まっているものだ。
そういう人らを見ても、俺は不自然さと嫌悪感しか抱かない。
だが、ロキシーの青髪は不自然さが全然なく、嫌悪感を抱かない。
むしろ、ロキシーのちょっと眠そうな目によく似合っている。
エロゲーのヒロインにいたら、最初に攻略するぐらいには似合ってる。
「先生の髪は綺麗ですよ」
「……ありがとうございます。でも、そういうことは将来好きな子ができた時に言ってあげてください」
「僕、先生のこと、好きですよ」
迷わず言った。
俺は迷ったりしない。
可愛い子には全員に粉をかけるのだ。
「そうですか。あと十数年した時に考えが変わらなかったらもう一度言ってください」
「はい、先生」
あっさりスルーされたが、ロキシーがちょっと嬉しそうな顔をしていたのは見逃さない。
エロゲーで鍛えたナイスガイスキルが異世界でどれだけ通用するかはわからない。
けど、まったく無意味というわけではないらしい。
日本では使い古されて冗談のように聞こえる小っ恥ずかしいセリフも、この世界なら情熱的でユニークな恋の導火線だ。
うん、何言ってんのか自分でもワカンネ。
ロキシーは可愛くてエッチだからフラグ立てときたいな。
でも年齢差が結構あるよね。
将来的にどうなるかな……。
「それでは話を戻しますが、派手な色ほど危険というのは、まったくの迷信です」
「あ、迷信なんですか」
警戒色とか真面目に考えて損したぜ。
「はい。バビノス地方にスペルド族という、髪が緑の魔族がいたのですが、彼らが四〇〇年前の戦争で暴れまわったため、そういう風に言われるようになったんです。なので、髪の色は関係ありません」
「暴れまわったんですか」
「はい。たった十数年ほどの戦争で敵味方あらゆる種族に恐れられ、忌み嫌われるほどに暴れました。戦争が終わった後、迫害を受けて魔大陸を追われるぐらい危ない種族でした」
戦争が終わってから、味方に追い出されたってことか。
すげえな。
「そんなに嫌われてるんですか……」
「そんなにです」
「何をやったんですか?」
「さぁ、それはわたしにも……ただ、味方の魔族の集落を襲って女子供を皆殺しにしたりとか、戦場で敵を全滅させた後に、味方も全滅させたりだとか、そういう逸話は子供の頃に何度も聞きました。夜遅くまで起きていると、スペルド族がやってきて食べてしまうぞ、と」
しまっ○ゃうオジさんかよ。
「ミグルド族もスペルド族に近い種族なので、かつては風当たりも強かったと聞きます。そのうち、ご両親にも言われるかと思いますが……」
いいですか、とロキシーは前置きした。
「エメラルドグリーンの髪を持っていて、額に赤い宝石のようなのがついた種族には、絶対に近づかないでください。やむを得ず会話しなければならない場合も、決して相手を怒らせてはいけません」
エメラルドグリーンの髪、額に赤い宝石。
それがスペルド族の特徴らしい。
「怒らせるとどうなるんですか?」
「家族を皆殺しにされるかもしれません」
「エメラルドグリーンと、額に赤い宝石、ですね?」
「そうです。彼らは額のそれで魔力の流れを見ます。第三の眼ですね」
「スペルド族って、実は女しかいないとかあります?」
「え? ありませんよ? 普通に男もいます」
「額の宝石が何かすると青色になったりとかしますか?」
「え? いえ、なりませんよ? 少なくとも私の知る限りでは」
なんなんですか、とロキシーは首をかしげた。
俺も聞きたいことが聞けて満足だ。
「でも、それだけ目立つなら見分けるのは簡単ですね」
「はい。見かけたら何気なく用事があるフリをして逃げてください。いきなり駆け出すと刺激する恐れがありますので」
不良の顔を見て即座に逃げ出したら、なんとなく追いかけられて絡まれるようなものか。
経験がある。
「話をするといっても、相手を尊重して喋れば問題ないですよね?」
「あからさまに侮蔑したりしなければ問題ないと思います。けれども、人間族と魔族では常識が違う部分も多いので、どんな言葉がキッカケで爆発するかわかりません。遠まわしな皮肉とかもやめておいたほうがいいですね」
ふむ。
すごい癇癪持ちなのだろうか。
しかし、迫害を受けているという話だが、どちらかというと恐れられているという感じだ。
あいつらを怒らせるとヤバイから近くにいないでほしい、といった感じか。
怖い怖い。
殺されて二度も三度も人生をやり直せるとは思えない。
極力近づかないようにしよう。
スペルド族、ヤバイ。
俺はそう心に刻んだ。
★ ★ ★
一年ほど経った。
魔術の授業は順調だ。
最近は、全ての系統で上級の魔術まで扱えるようになった。
もちろん無詠唱でだ。
普段している練習に比べれば、上級魔術なんて鼻くそをほじるようなもんだった。
ていうか、上級魔術は範囲攻撃が多くて、いまいち使い勝手が悪いように感じる。
広範囲に雨を降らせるとか、何に使うんだ?
と、思ったら、日照りの続いた日にロキシーが麦畑に向かって雨を降らせて、村人から大絶賛を受けたらしい。
俺は家にいたので、パウロから聞いた話だが。
ロキシーは他にも、村の人に依頼を受けて、魔術を使って問題を解決しているらしい。
『土を起こしていたら大きな岩が埋まっていたんだ、助けてロキシえもん!!』
『まかせて、ドン○ラコー』
『なぁにその魔術?』
『これはね、岩の周囲の土を水魔術で湿らせて、土の魔術で泥にする混合魔術なんだ』
『うわっ、すごい、岩がどんどん地下に沈んでいく!!』
『うーふーふー』
そんな感じだ!!(多分)
「さすが先生。人助けにも余念がありませんね」
「人助け? 違いますよ。これは小銭稼ぎです」
「金を取っていたんですか?」
「当然です」
なんて守銭奴だ。
と、思ったが、村の人もそれは承知だそうだ。
村にはそういうことができる人がいなかったから、ロキシーは大絶賛されているらしい。
ギブアンドテイクってやつか。
俺の感覚が間違っているのだ。
困っている人を無償で助けるのは当然。
それは日本人の感覚だ。
普通は金を取る。
それが普通だ。常識だ。
まぁ、生前の俺は引きこもってたから困ってる人を助けるどころか、家族全員から困った奴として扱われていたがね。
ハッハッハー。
★ ★ ★
ある日、ふと聞いてみた。
「先生のことは先生ではなく師匠と呼んだほうがいいのではないでしょうか」
すると、ロキシーはあからさまに嫌な顔をした。
「いいえ、恐らくあなたはわたしを簡単に超えてしまうので、やめたほうがいいでしょう」
俺はロキシーを超えてしまう逸材らしい。
評価されると照れるな。
「自分より力の劣る者を師匠と呼ぶのは嫌でしょう?」
「別に嫌じゃないですよ」
「わたしが嫌なんです。自分より優秀な人に師匠と呼ばれるなんて、生き恥じゃないですか」
そういうものなんだろうか。
「先生は、先生の師匠より強くなっちゃったから、そう言ってるんですか?」
「いいですかルディ。師匠というのはですね、もう自分に教えられることは無いと言いながらも、事あるごとにアレコレと口出ししてくるような厄介な存在なんです」
「でも、ロキシーはそんなことしないでしょう?」
「するかもしれません」
「もしそうなったとしても、俺は敬いますよ?」
事あるごとに偉そうにドヤ顔で忠告してくるロキシー。
きっと俺はニコニコしてしながら敬ってしまうだろう。
「いいえ、わたしも弟子の才能に嫉妬したら何を口走るかわかりません」
「例えば?」
「薄汚い魔族の分際で、とか、田舎者のくせに、とか」
言われたのか。
可哀想に。
差別はよくないよな。
でも、上下関係なんてそんなもんだ。
「いいじゃないですか、威張ってれば」
「年齢が上というだけで威張ってはだめなんです!! 実力が伴わない師弟関係は不快なだけなんです!!」
断言された。
よほど師匠との仲が悪かったらしい。
ともあれ、そういうわけで、俺はロキシーを師匠とは呼ばないことにした。
けれど、心の中では師匠と呼び続けることに決めた。
この幼さの残る少女は、本を読むだけでは理解しえないことを、きちんと教えてくれるのだから。
第五話 「剣術と魔術」
五歳になった。
誕生日にはささやかなパーティが開かれた。
この国には、誕生日を毎年祝うという習慣は無いらしい。だが、一定の年齢になると、家族が何かを贈るのが通例なのだそうだ。
一定の年令とは五歳、十歳、十五歳。
十五歳で成人であるから、非常にわかりやすい。
パウロはお祝いに剣を贈ってくれた。
二本だ。
五歳児が持つにしては長く重い実剣と、短めの木剣。
実剣はきちんと鍛造されたもので、刃もついていた。
子供が持つようなものではない。
「男は心の中に一本の剣を持っておかねばならん、大切な者を守るには──」
この薫陶は長かったのでニコニコしながら聞き流した。
パウロは機嫌良さそうに話していたが、最終的にはゼニスが「長い」と、窘めた。
パウロは苦笑し「ついては、必要な時以外はしまっておくように」と締めくくった。
恐らく、パウロが与えたかったのは、剣を持つことへの自覚と覚悟なのだろう。
ゼニスからは一冊の本をもらった。
「ルディは本が好きだから」
と、手渡されたのは、植物辞典だった。
思わず、「おぉ」と声を上げてしまった。
この世界では、本は高価なのだ。製紙技術はあっても印刷技術は無いらしく、全部手書きだし。
植物辞典は分厚く、挿絵でわかりやすく丁寧に説明してある。
一体どれだけの値段がするものやら。
「ありがとうございます。母様。こういうのが欲しかったんです」
そう言うと、ぎゅっと抱きしめられた。
ロキシーからはロッドをもらった。
三〇センチほどのスティックの先に小さな赤い石のついた、質素なものだ。
「先日制作したものです。ルディは最初から魔術を使っていたため失念していましたが、師匠は初級魔術が使える弟子に杖を作るものでした。申し訳ありません」
そういうものだったらしい。
師匠と呼ばれることを嫌がっていたロキシーだったが、慣習を無視するのは気が引けたらしい。
「はい、師匠。大切にします」
そう言うと、ロキシーは苦笑いをした。
★ ★ ★
翌日から、本格的な剣術の鍛錬が開始された。
基本的には素振りや型を中心に。
庭に作成された木人相手に、型や打ち込みの具合を見たり、父親相手に打ち合いをして足運びや体重移動の訓練をしたり、といった具合だ。
基礎的な感じで、実にいい。
この世界において、剣術はかなり重要視されている。
本に出てくる英雄たちも、ほとんどが剣で武装している。たまに斧や槌を持っている者はいるものの少数派だ。
槍を持っている奴はいないが、これは例の嫌われ者のスペルド族が三叉の槍を使っていたからだ。槍は悪魔の武器。そういう常識があるのだ。一応、本にもそんな悪魔が何匹か登場した。敵も味方も食い殺す、無差別殺人鬼みたいな役割でだ。
そういう背景もあるからか、こちらの剣術は元いた世界より優れている。
達人になると、岩を一刀両断したり、剣閃を飛ばして遠くの相手を攻撃できたりする。
現にパウロも、岩ぐらいなら両断できる。
原理が知りたかったので、褒めて讃えておだてたら何度も実演してくれた。幼くして上級魔術をも操れる息子が喜んで手を叩くのだから、パウロもさぞ気分がよかっただろう。
まあ、何度見ても原理がよくわからなかったが。
見てもわからなかったので、説明を要求してみたのだが……。
「クっと踏み込んでザンッ!! って感じだ」
「こうですか!?」
「馬鹿! それじゃぐぅっと踏み込んでドンだろうが!! クッと踏み込んでザンだよ! もっと軽やかにだ!」
こんな感じだった。
これは推測だが、この世界の剣術というのは魔力が絡んでいる。
魔術が見た目どおりに魔法っぽく発現するのと違い、剣術の方は肉体強化や、剣などの金属の強化といった方面に特化している。そうでなければ、超高速で動きまわり岩を両断するなど、できるものか。
もっともパウロに魔力を使っている意識はない。
ゆえに、説明もできない。
しかし、再現できるようになれば、身体強化ブーストの魔術が使えるようになるようなものだ。
頑張ろう。
★ ★ ★
この世界では、主流となる流派が三つある。
──一つは剣神流。
攻撃こそが最大の防御と言わんばかりの攻撃的な剣術で、とにかく相手に先に剣を当てるのを目的としたような速度重視の流派。
先の先を取って一撃必殺。
倒しきれなければヒットアンドアウェイを倒せるまで続ける。
元の世界に当てはめて言うなれば、薩摩示現流といったところか。
──一つは水神流。
こちらは剣神流とは真逆。
受け流しとカウンターを中心とした防御の剣術だ。
専守防衛をモットーとしているため、こちらから打って出る手は少ない。
だが達人になると、あらゆる攻撃に対してカウンターを放てるようになるらしい。
あらゆる攻撃──魔術や飛び道具に対しても、だ。
宮廷騎士や貴族といった、守ることが中心となるような人物が習う剣である。
──一つは北神流。
これは剣術というより、兵法であるようだ。
特徴的な技は無く、状況に応じた臨機応変さがウリらしい。
パウロ曰く、臨機応変といっても、小手先で小賢しいことをするのが多いらしい。
しかし、極めればまさに奇想天外。
ジャ○キー・チェンの剣術版といった感じになるようだ。
怪我の治療や、身体部位の欠損があっても戦える流派であるため、傭兵や冒険者といった者たちに好まれる剣術ではある。
これらは三大流派と呼ばれ、世界中に使い手がいる。
剣士として極限に達したいと思う者は、各門派の扉を叩き、死ぬまで剣を振り続けるらしい。
が、そうした者は少数だ。
手っ取り早くそれなりに強くなりたければ、いくつかの流派をかじって良いところ取りをしていくのが基本らしい。
現にパウロも剣神流を主としつつも、水神流と北神流の両方をかじっている。
剣神流にしろ水神流にしろ、それだけで世に出るにはピーキーすぎる剣術なのだろう。
ちなみにこれら剣術も、次のようにランク分けされている。
初級、中級、上級、聖級、王級、帝級、神級。
また各流派の名前に神とついているのは、流派の始祖の通称からだ。
水神流の初代剣士は、同時に水神級の魔術を扱える魔術師でもあったのだとか。
剣も神級、魔術も神級、そらもうベラボウに強かったらしい。
ちなみに、剣士を呼ぶ時は『水神』『水聖』と呼ぶが、魔術師を呼ぶ時は『水神級』『水聖級』と、『級』を付けるのが一般的だそうだ。
例えば、ロキシーは『水聖級魔術師』である。
★ ★ ★
俺は剣神流と水神流の二種類を学んでいくことになった。
攻撃の剣神、防御の水神というわけだ。
「しかし父様。話を聞く限り、北神流が一番バランスがいいように思えますが」
「バカを言うな。あれは剣を使って戦っているだけで、剣術じゃない」
「なるほど」
北神流は三つの流派のうちでも、差別されているようだ。
あるいは、パウロが個人的に嫌っているだけか。
嫌っているわりに、パウロは北神流も上級らしいが。
「ルディは魔法の才能があるようだが、剣術を習っておいて損はない。剣神流の斬撃をしのげるような魔術師になれ」
「魔法剣士……というやつですか?」
「ん? 魔法剣士は剣士が魔法を使えるというものだ。お前の場合は逆だろう?」
どう違うというのだろう。
戦士から転職しようが、魔法使いから転職しようが、魔法剣士は魔法剣士だと思うのだが。
どちらにせよ、剣術を鍛えれば、魔術にも応用できる。
問題は、パウロは身体強化ブーストを無意識でやっているので教えてはくれない、ということだ。
自分でなんとか習得する必要があるが、ただ身体を鍛えてできるようになるものなのだろうか。
どうにかして原理を究明しないとな……。
「…………やっぱり、剣術は嫌か?」
考え込んでいると、パウロが不安そうな顔で聞いてきた。
俺には魔術の才能がある、なんて言われているからか。
パウロは俺が剣術の稽古を望んでいないのでは、と悩んでいるようだ。
だが勘違いしないでほしい。俺は剣術の稽古が嫌なわけじゃない。むさ苦しい男と庭でさわやかな汗を流すより、ロキシーと二人っきりでお勉強するほうが好きなだけだ。
インドア派なのだ。
もっとも、それは好き嫌いの問題だ。
この世界で本気で生きると決めたからには、剣も魔術も頑張ってみせるさ。
「いえ、魔術と同じぐらい剣術も上手になりたいです」
パウロはその言葉にジーンと感動したようで、嬉しそうに頷くと、木剣を構えた。
「よし、じゃあ打ち込みを始めるぞ。掛かってこい!!」
単純な男だ。
魔術と剣術。最終的にどちらに頼ることになるのかはわからない。
ぶっちゃけどっちでもいい。
「はい!! 父様!!」
だが、親孝行は早いうちからしておくべきだ。
生前、両親には死ぬまで苦労を掛けた。
もし俺が両親にもっと優しくしていれば、兄弟たちも俺をいきなり家から叩き出すような真似はしなかったかもしれない。
なので、親は大切にしなければな。
★ ★ ★
そうして剣術の初歩に足を踏み入れた頃、魔術の授業はというと、かなり技術的、かつ実践的な部門へと進んでいた。
「水滝、地熱、氷結領域を順に発生させるとどうなりますか?」
「霧が発生します」
「そうです。ならば、その霧を晴らすには?」
「ええと、もう一度地熱を使って地面を温めます」
「そのとおりです。やってみせてください」
複数の系統を順番に使うことで現象を発生させる。
これは『混合魔術』と呼ばれている。
魔術教本には、雨を降らせる魔術は載っていても、霧を発生させる術はなぜか載っていない。
そこで、魔術師は違う系統の魔術を順番に使う。そうすることで、自然現象を再現するのだ。
顕微鏡のないこの世界。
自然現象の原理まで解明されているわけではないだろう。
混合魔術には、昔の魔術師の創意工夫が詰まっている。
まぁ、俺にそんな面倒なことをする必要はない。
雲を作り出し、雨を降らせる魔術を、地面スレスレで発動するだけでいい。
だが、自然現象を意図的に発生させる、というのは理解しやすい。
頭をひねれば、色々できそうだ。
俺の頭では、少々難しいがな。
「魔術はなんでもできるんですね」
「なんでもはできません、過信してはいけません。ただ冷静に、自分のできること、やるべきことを淡々とこなしてください」
と、ロキシーには窘められたが、俺の頭の中は超電磁砲やら光学迷彩といった単語が躍っていた。
「それに、なんでもできるなんて吹聴して回れば、できないことも押し付けられます」
「先生の経験談ですか?」
「そうです」
なるほど、それは気をつけなければいけない。
押し付けられるのは面倒だしな。
「しかし、魔術師にそんなに仕事を押し付けてくる人がいるんですか?」
「ええ、上級魔術師というものは数が多いわけではありませんから」
戦うことのできる人間が二〇人に一人。
その中でも魔術師はさらに二〇人に一人。
そんな感じらしい。
魔術師は四〇〇人に一人といったところか。
魔術師自体は別に珍しくもないが、
「魔術学校を卒業するまできちんと学んだ人間……。つまり上級魔術師となると、魔術師一〇〇人に一人といったところでしょう」
上級魔術師は、四万人に一人。
中級・上級魔術に加えて混合魔術を操れれば、できることが飛躍的に増える。
ゆえに、引っ張りだこなんだそうだ。
この国の家庭教師も上級以上という資格が必要だ。
資格としての効果も強い。
「魔術学校なんてあるんですか?」
「はい。魔術学校は大国ならどこにでもあります」
それにしても、あるとは思っていたが魔術学校か。
始まっちゃうか? 学園編。
「が、やはりいちばん大きいのはラノア魔法大学でしょう」
ほう、大学もあるのか。
「その大学は他の学校とはどう違うんですか?」
「いい設備と教師が揃っています。他の学校で習うより近代的で高度な講義を受けることができるでしょう」
「先生も大学の出身なんですか?」
「そうです。もっとも、魔術学校というのは格式が高いものなので、魔族であるわたしは魔法大学にしか入れなかったのですが……」
貴族の子弟が通うようなラノア王国の魔術学校は、種族が人間でないというだけで審査で弾かれるのだそうだ。
魔族への差別も少なくなりつつあるが、やはりまだまだ風当たりは強いらしい。
「ラノア魔法大学には変な格式やプライドがありません。正しい理論なら、奇抜でも一蹴されることはありませんし、様々な種族を受け入れることで、各種族の独自魔術の研究もすすんでいます。もしルディが魔術の道を進みたいというのなら、魔法大学に進む道をオススメします」
自分の出身校というのもあるだろうが、ベタ褒めだ。
まあ、もうちょっと先の話だろう。
五歳で入学したらイジメられちゃうかもしれないし。
「そのあたりを決めるのはまだ早いんじゃないかと……」
「そうですね。パウロ様の意向に従い、剣士か騎士の道を進むのもいいと思います。騎士の肩書きを手に入れた上で、魔術大学に留学していた者もいました。剣か魔術、どちらか片方の道しかない、とは思わないでください。魔法剣士という道もありますから」
「はい」
それにしても。
パウロとは逆に、ロキシーは俺が魔術嫌いなのでは、と不安に思っているようだ。
最近は魔力量も増え、法則もわかってきた。
ゆえに、授業を気もそぞろで受けることが多くなってしまった。
もともと、三歳の時にムリヤリ始められた魔術の授業。
この二年で嫌気がさしてきた。
そう思われたのかもしれない。
パウロは俺の魔術の才能を見て。
ロキシーは俺の剣術の熱心さを見て。
それぞれ違う理由から、中間の道もあるのだと示しているのだろう。
「でも、まだまだ先の話でしょう?」
「ルディにとってはそうですね」
ロキシーは寂しそうに笑った。
「ですが、そろそろわたしの教えられることも少なくなりました。卒業も近いですから、こういう話をしてもいいでしょう」
…………卒業?
第六話 「尊敬の理由」
この世界に来てから、俺は家の外に出たことはない。
意図的に、出ないようにしてきた。
怖いからだ。
庭に出て、外を見れば、すぐにでも記憶が蘇る。
あの日の記憶。脇腹の痛み。雨の冷たさ。無念。絶望感。トラックにハネられた時の痛み。
それらが昨日のことのように蘇ってくる。
足が震える。
窓から外を見ることはできた。自分の足で庭までは出ることができた。
だが、それ以上は出られない。
俺は知っている。
目の前に広がるのどかな田園風景は、一瞬で地獄に変わるのだ。いかにも平和ですという風景は、決して俺を受け入れてはくれないのだ。
生前。家の中で悶々としながら何度妄想しただろうか。
日本がいきなり戦争に巻き込まれたら。ある日突然美少女の居候ができたら。
そしたら、きっと俺は頑張れる。
そんな妄想をして、現実逃避をしていた。
何度も夢に見た。
夢の中の俺は超人ではなかったが、人並みだった。人並みに、自分のできることをやっていた。一人で生きていくことができていた。
けれど、夢は覚めた。
もし、一歩でも家の外に踏み出せば、この夢も覚めてしまうかもしれない。
夢が覚め、あの絶望の瞬間に戻ってしまうかもしれない。
後悔の波に押しつぶされそうな、あの瞬間に………。
いや、これは夢じゃない。
こんなリアルな夢があってたまるものか。
VRMMORPGだと言われたほうがまだ納得できる。
これは現実だ。
そう、自分に言い聞かせる。
わかっている。
この現実は夢じゃない。
わかっているのに、俺は一歩も踏み出せない。
心の中ではどれだけやる気になっても。
本気になると口で誓っても。
身体は決して付いてこない。
泣きそうだ。
★ ★ ★
卒業試験は村の外でやる。
そう言ったロキシーに、俺は小さく抵抗した。
「外ですか?」
「はい、村の外です。もう馬も用意してあります」
「家の中でやることはできませんか?」
「できません」
「できませんか……」
俺は迷っていた。
頭の中ではわかっている。いつかは外に出なければならない。
この世界でも引きこもりであってたまるものか、と。
しかし、身体は拒否する。覚えているのだ。あの時のことを。
生前、不良どもにボコボコにされて、ゲラゲラと笑われ、心に大きな傷を負った時のことを。
どうしようもなくて、引きこもってしまった時のことを。
「どうしました?」
「いえ………その………、外には魔物とかいるかもしれませんし」
「このあたりは森に近づかなければ滅多に遭いませんよ。それに、遭っても弱いですから、わたし一人でも倒せます。ていうか、ルディでもいけると思いますよ」
この期に及んであれこれと理由をつけて外に出たがらない俺を見て、ロキシーは怪訝そうな顔をしている。
「あ、そういえば聞きました。ルディ、あなた外に出たことがないんでしたっけ?」
「う……はい」
「さては、怖いんですね? 馬が」
「う、馬は別に怖くないですよ?」
馬はむしろ好きだよ?
ダビ○タとかやってたし。
「ふふ。安心しました。意外に歳相応なところもあるんですね」
ロキシーは勘違いしていた。
しかし、外に出るのが怖いとは言えなかった。
それはきっと、馬が怖いというより情けないことだからだ。
俺にはプライドがあった。
内実を伴わない、ちゃちなプライドだ。
この小さな少女に馬鹿にされたくないという、ただそれだけの。
「仕方ありませんね。よっこらしょ」
俺が動かないでいると、ロキシーはいきなり俺を肩に担いだ。
「なぁ!?」
「乗ってしまえば、すぐにでも怖くなくなりますよ」
俺は暴れなかった。
心の中に葛藤があったせいもあるが、持ち運ばれて流されるまま任せておけばいいか、とそんな気持ちもあった。
ロキシーにポンと放り投げられるように馬の上に乗せられた。
ロキシーはそのまま後ろに飛び乗り、手綱をぽんと一つ打つ。
馬はカッポカッポと歩き出した。
俺はあっさりと家を出た。
★ ★ ★
この世界に来てから庭の外に出るのは初めてだ。
ロキシーは村の中をゆっくりと進んでいく。
時折、俺たちを見て、村人が無遠慮な視線を送ってくる。
まさか、と思う。
身体が緊張する。
視線はいまでも怖い。
無遠慮で、格下を見る目は、特に。
明らかに馬鹿にする口調で話しかけられたりはしないだろうか。
ないはずだ。
知らないはずだ。
この世界で俺を知っている人は、あの狭い家の中だけだ。
なんで見ている。
見るなよ。仕事してろよ……。
いや……。
俺ではない。
ロキシーを見ているのだ。
中にはロキシーに向けて会釈をする者もいる。
ああ、そうか。
彼女は、村の中に立場を築いたのだ。
この国では、まだ魔族への風当たりが強いというのに。
田舎ともなれば、その傾向はより顕著だろうに。
たった二年で、彼女はこの村で会釈をされる存在になったのだ。
そう考えた瞬間、背中のロキシーがとたんに頼もしく感じられた。
彼女は道を知り、人々と知り合っている。
もし人々が俺に何か言ったとしても、なんとかしてくれるだろう。
ああ、まさか、寝室を覗いてあんなことしてた少女がこんなに頼もしく感じられるとは。
次第に、俺の身体から緊張が抜けていくのが感じられた。
「カラヴァッジョが上機嫌です。彼、ルディを乗せられて嬉しいみたいですよ」
カラヴァッジョとは、馬の名前である。
当然ながら、俺には馬の機嫌などわからない。
「そうですか」
適当に返事をしつつもたれかかると、ロキシーの控えめな胸が首裏に当たった。
いい感じだ。
俺は何を恐れていたのだろうか。
こんなのどかな村で、誰が俺を馬鹿にするというのか。
「まだ怖いですか?」
そう聞かれ、俺は首を振った。
人の視線はもう怖くなくなっていた。
「いえ、もう大丈夫です」
「ほら、大丈夫だったでしょう?」
心に余裕ができていた。
すると、周囲の風景が目に入ってきた。
一面見渡す限りの畑で、間に家がちょこちょこと建っている。
まさに農村という感じだ。
かなり広い範囲に結構な数の家が見える。もっと密集していれば、町と思ったかもしれない。
風車が立っていればスイスと思ったかもしれない。
あ、水車小屋もあるのか。
リラックスできると、沈黙が気になった。今までロキシーといる時は、こんな沈黙は無かった。
こんな風に、二人で密着しているなんてこともなかった。沈黙は苦ではなかったが、こそばゆかった。
なので俺は口を開く。
「先生、この畑では何が取れるんですか?」
「主にはアスラン麦です。パンの原料ですね。それに、バティルスの花と野菜を少々といったところでしょうか。バティルスの花は王都で加工されて香料になります。あとはいつも食卓に上がるものばかりですね」
「あ、あそこのはピーマンですよね。先生が食べられない」
「べ、別に食べられないわけじゃありません。ちょっと苦手なだけです」
俺はあれこれと質問を続ける。
今日、ロキシーは最終試験だと言った。
つまり、家庭教師が終わりだということだ。
せっかちなロキシーのことだ。明日にはウチを出ていくかもしれない。
そうなれば、今日が最後だ。もっと話をしておこう。
しかし、気の利いた話題は見つからず、俺は村のことをただひたすらに聴き続けた。
ロキシーの話によると、この村はアスラ王国の北東にあるフィットア領の一部で、ブエナ村という名前らしい。
現在は三〇世帯余りが農業をして暮らしているらしい。
俺の父親であるパウロは、この村に派遣されている騎士だ。
村人がきちんと仕事をしているか監視をすると同時に、村内で喧嘩を仲裁したり、魔物などが攻めてきた際には村を守ったり、といった仕事を受け持っている。
ようするに国公認の用心棒だ。
とはいえ、この村では若い衆が持ち回りで自警をしている。
だから、パウロも午前中で見回りを終えたら、午後は大体家にいるわけだ。
基本的に平和な村だから、仕事が無いのだ。
そんな話をしていると、次第に畑もなくなってきた。
聞くこともなくなり、しばらくまた沈黙する。
それからさらに一時間ほどだろうか。
周囲からは完全に畑が消え、何もない草原を移動していた。
★ ★ ★
地平線の果てまでずっと草原だ。
いや、遠くの方にうっすらと山が見える。
少なくとも、日本では見られない光景だろう。
地理の教科書か何かで見たモンゴルの光景がこんな感じだったろうか。
「このあたりでいいでしょう」
ロキシーはポツンと一本だけ立っている木の側で馬を止めると、降りて手綱を木に結んだ。
そして、俺を抱いて下ろしてくれる。
ついで俺と向かい合った。
「これからわたしは水聖級攻撃魔術『豪雷積層雲』を使います。この術は、広範囲に雷を伴う豪雨を降らせる術です」
「はい」
「真似して使ってみてください」
水聖級の魔術を使う。
なるほど、それが最終試験の内容か。
これから使うのが、ロキシーの最大の魔術であり、俺が使えるようになれば、ロキシーに教えられることはないということだ。
「わたしは実演するために一分ほどで散らしますが、そうですね……。一時間以上降らせ続けることができたら合格としましょう」
「秘伝だから人のいない所でやるんですか?」
「違います。人や農作物に被害が出るかもしれないからです」
ほう。
農作物に被害が出るレベルの雨を降らせるのか。
こりゃ凄そうだ。
「では」
ロキシーは天に向かって両手を上げた。
「雄大なる水の精霊にして、天に上がりし雷帝の王子よ!!
我が願いを叶え、凶暴なる恵みをもたらし、矮小なる存在に力を見せつけよ!!
神なる金槌を金床に打ち付けて畏怖を示し、大地を水で埋め尽くせ!!
ああ、雨よ!! 全てを押し流し、あらゆるものを駆逐せよ!!
『キュムロニンバス』!!」
一つ一つの単語を、噛み締めるようにゆっくりと詠唱する。
時間にして一分以上。
唱え終わった瞬間、一瞬にして周囲が暗くなった。
数秒のタイムラグ──そして叩きつけるように雨が落ち始める。
凄まじい暴風が吹き荒れ、真っ黒な雲が稲光を伴いだす。
ザーザーと滝のような雨の中、ゴロゴロと音を立て、紫色の光が雲の中に走る。
雲の中の稲光が次第に力を増していく。
まるで光が重さを伴っているかのように次第に膨れ上がっていき──。
──落ちた。
バガァァン!!
木に落ちた。
鼓膜がジンジンし、目がチカチカした。
気絶するかと思った。
「あっ!!」
ロキシーがうっかりミスをした時の声を上げる。
雲が一瞬で散っていく。
雨も雷もすぐに収まった。
「あわわ……」
ロキシーが真っ青な顔で木の方に駆け寄っていく。
見てみると、馬が煙を上げて倒れていた。
ロキシーは馬に手を当てると、即座に詠唱。
「母なる慈愛の女神よ、彼の者の傷を塞ぎ、健やかなる体を取り戻さん『エクスヒーリング』!!」
ロキシーがわたわたと中級の治癒魔術を施し、程なくして馬は蘇った。
即死ではなかったらしい。
中級の治癒魔術では、死者は蘇らないからな。
馬は怯えた顔をしていて、ロキシーの額には脂汗がびっしりついていた。
「ふ、ふぅ……危ないところでした」
確かに危ないところだった。
あの馬はうちに一頭しかいない馬だ。
パウロが毎日丁寧に手入れをして、たまににこやかな顔で遠乗りに出かけていく。
別に名馬でもなんでもないらしいが、長年苦楽を共にしてきた友で、ゼニスの次に愛していると言って憚らない。そんな大切な馬だ。
もちろん、二年間一緒に暮らしてきたロキシーだってそのことはよく知っている。
ロキシーが恍惚とした表情で馬にべったり張り付いているパウロを目撃して、若干引いていたのを、俺は知っている。
「こ、このことはナイショでお願いしますね?」
ロキシーは涙目になって言った。
彼女はドジだ。
よく、うっかりミスでこんなことをしてしまう。
だが、頑張り屋だ。毎晩、夜遅くまで俺への授業の予習をしていたのも知っている。
まだまだ若いってことでナメられないように、精一杯威厳を出そうとしていたことも知っている。
俺はそんな彼女を好ましく思う。
年齢が離れてさえいなければ嫁に欲しいぐらいに。
「安心してください。父様には言いませんので」
「うう……お願いします」
なるべくなら、同年代で知り合いたかったな。
「うぅ……」
ロキシーは半泣きだったが、すぐに顔をブルブルと振り、パンパンと頬を叩くと、キリッとした顔で俺を見た。
「さぁ、やってみなさい。カラヴァッジョはわたしが守っておきますので」
馬は今にも怯えて逃げ出しそうな様子だが、ロキシーが小さな身体でガッシリと止めている。
ロキシーの小さな体で馬を抑えられるとは思えないのだが、馬はそわそわしつつもおとなしくしている。ロキシーはその体勢のまま、むにゃむにゃと何かを詠唱し始めた。
と、見るまに彼女と馬を土の壁が覆っていく。
あっという間に、土製のカマクラが出来上がる。
土の上級魔術『土砦』だ。
あれなら、雷雨を受けても大丈夫だろう。
よし、やるか。
いっちょすごいのを見せて、ロキシーの度肝を抜いてやろう。
えーと、たしか詠唱は……。
「雄大なる水の精霊にして、天に上がりし雷帝の王子よ!!
我が願いを叶え、凶暴なる恵みをもたらし、矮小なる存在に力を見せつけよ!!
神なる金槌を金床に打ち付けて畏怖を示し、大地を水で埋め尽くせ!!
ああ、雨よ!! 全てを押し流し、あらゆるものを駆逐せよ!!
『キュムロニンバス』!!」
一発で言えた。
モクモクと雲ができていく。
と同時に、俺は『豪雷積層雲』を理解した。
中空に雲を作り出すと同時に、複雑に動かして雷雲にする。そんな感じだ。
常時魔力を注ぎ込まなければ雲の動きが止まり、すぐに雲が散ってしまう。
(魔力はともかく、両手を一時間も上に上げ続けるのはしんどいな……)
いや、まて。
魔術師は創意工夫だ。
こんな元気を集めるようなポーズで一時間も耐える必要はないんじゃないか?
そうだ。これは試験だ。
一時間も同じ姿勢でいるのではなく、雲を作ったら混合魔術であれを維持するのだ。
危ないところだった。習ったことを使わねば。
「えーっと。確か昔テレビ見たな。雲ができるまでの過程は───」
さっきロキシーが作った雲がまだ残っている。
こう横向きに竜巻を発生させるような感じで、上昇気流を作るのに下の方を暖めたほうがいいんだっけか。
ついでに上の方も冷やして上昇気流の速度を上げて──。
なんてやっていたら、半分ぐらい魔力を消費してしまった。
まぁでも、これだけやれば一時間以上は持つだろう。
俺は満足して、雷の鳴る豪雨の中、ロキシーの作ったドームの中へと入った。
ロキシーは暗いドームの端の方で、馬の手綱を握って座っていた。
彼女は俺を見ると、こくりと頷いた。
「このドームは一時間ほどで消えますので、それまで消えなければ大丈夫です」
「はい」
「安心してください。カラヴァッジョは大丈夫です」
「はい」
「はいはい言ってないで、一時間、外できっちり雷雲を制御するんです」
ん?
「制御ですか?」
「ん? 何かおかしなことを言いましたか?」
「いえその、制御って必要なんですか?」
「そりゃあもちろん、水聖級の魔術だって、魔術なのですから、きちんと魔力を使って維持をしないと、風に散らされてしまいます」
「散らされないようにはしておきましたけど……?」
「は? ぁ……!?」
ロキシーは何かに気づいたようにドームの外へと飛び出していった。
同時に、ドームがボロボロと崩れ始める。
こらこら、ちゃんと制御しないか。
馬が生き埋めになるだろう。
「おっととと」
と、慌てて制御を引き継ぎ、外に出る。
ロキシーは呆然とした顔で空を見上げていた。
「……そうか、斜めに上がっていく竜巻が雲を押し上げて……!!」
そこには、俺の創りだした、際限なく大きくなっていく積乱雲があった。
我ながらいい出来だ。
昔、何かの特番でスーパーセルができるまで、というのを科学的に検証していた。
詳しい内容はよく覚えていない。
確かこんな感じというビジョンを持って作っていたら、それっぽいのができたのだ。
「ルディ。合格です」
「え? でも、また一時間経ってませんよ?」
「必要ありません。あれだけできれば十分でしょう。ていうか消せますか?」
「あ、はい。ちょっと時間掛かりますけど」
俺は地面の方を広域で冷やしたり、上の方を温めたり、下に向かって気流を作ったりして、最終的に風魔術の力技で、なんとかして雲を散らした。
終わる頃には、俺とロキシーはびしょ濡れになっていた。
「おめでとうございます。これであなたは水聖級です」
水もしたたるいい女は、濡れた前髪をかき上げつつ、普段あまり見せない晴れやかな笑みでそう宣言した。
生前、何もできなかった俺が、一つのことを成し遂げた。
そう思った途端、腹の底から何かが湧きあがってくるような奇妙な感覚があった。
この感覚は知っている。
達成感だ。
俺はこの瞬間、この世界に来て初めて『第一歩』を踏み出したのだと実感した。
★ ★ ★
翌日。
ロキシーは旅装を整え、二年前に来た時と寸分変わらない格好で玄関にいた。
父も母もロキシーが来た時と、あまり変わらない。
俺の背だけが伸びていた。
「ロキシーちゃん、まだウチにいてもいいのよ? 教えてないお料理も一杯あるし……」
「そうだぞ。家庭教師が終わったとはいえ、君には去年の干ばつの時にも世話になったしな。村の奴らだって歓迎するだろう」
両親はそう言ってロキシーを引きとめようとする。
俺の知らないところで、ロキシーは両親と仲良くなっていたらしい。
まぁ、彼女は午後から夜まで丸々暇だったわけだし、毎日何かしらしてれば、顔も広くなるか。
主人公が行動を起こさない限り能力に変動のないゲームのヒロインとは違うってことだ。
「いいえ。ありがたい申し出ですが、今回のことで自分の無力さを思い知りました。しばらくは世界を旅しながら、魔術の腕を磨くつもりです」
どうやら、俺にランクで追いつかれてしまったのがショックらしい。
前に、弟子に追いつかれるのは嫌だと言ってたしな。
「そうか。まぁ、なんだ。悪かったな。うちの息子が自信を失わせてしまったようで」
パウロよ。そういう言い方はよくないぞ。
「いえ、思い上がりを正していただいたことを感謝すべきはこちらです」
「水聖級の魔術が使えて思い上がりってことはないだろう」
「そんなものが使えなくとも、工夫しだいでそれ以上の魔術が使えることを知りました」
ロキシーは苦笑しながらそう言うと、俺の頭に手を置いた。
「ルディ。精一杯頑張ったつもりですが、わたしではあなたを教えるのに力不足でした」
「そんなことはありません。先生は色んなことを教えてくれました」
「そう言ってもらえると助かります……ああそうだ」
ロキシーは、ローブの内側に手を入れると、ゴソゴソと中を探り、革紐についたペンダントを取り出した。
緑の光沢を持つ金属でできていて、三つの槍が組み合わさったような形をしている。
「卒業祝いです。用意する時間が無かったので、これで我慢してください」
「これは……?」
「ミグルド族のお守りです。気難しい魔族と出会った時にこれを見せてわたしの名前を出せば、少しぐらいは融通してくれる……かもしれません」
「大切にします」
「かもですからね。あんまり過信してはいけませんよ」
ロキシーは最後の最後に小さく微笑んで、旅立っていった。
俺はいつしか泣いていた。
彼女には、本当にいろんなものをもらった。
知識、経験、技術……。
彼女と出会わなければ、俺は今もなお、一人で魔術教本を片手に効率の悪いことをやっていただろう。
そして何より、彼女は俺を外に連れ出してくれた。
外に出た。
それだけのこと。
ただ、それだけのことだ。
ロキシーに連れ出してもらった。
そのことに意味がある。
この村に来て、まだ二年しか経っていないロキシーが。
決して他人との付き合いがうまいとは思えないように見えるロキシーが。
魔族ということで、村人から決していい目を向けてもらえなかったはずのロキシーが。
パウロでもゼニスでもなく、ロキシーが連れ出してくれたことに、意味がある。
連れ出したといっても、ただ村を横切っただけ。
しかし、外に出るという行動は、俺にとって間違いなく心的外傷だった。
彼女はそれを治してくれた。
ただ村を横切っただけで。
俺の心を晴れやかにさせてくれた。
彼女は俺を更生させるのが目的ではなかった。
だが、俺の中で何かが吹っ切れたのは間違いない。
昨日、びしょ濡れで帰ってきた俺は、門を振り返り、一歩だけ外に出てみた。
ただそこには、地面があった。
ただの地面だ。
震えはなかった。
俺はもう、外を歩けるのだ。
彼女は、誰にもできないことを、やってのけたのだ。
生前、両親も兄弟もできなかったことを。
彼女はしてくれたのだ。
無責任な言葉でなく、責任ある勇気を与えてくれたのだ。
狙ってやったことじゃない。
それはわかっている。
自分のためにやったことだ。
それもわかっている。
けれど尊敬しよう。
あの小さな少女を、尊敬しよう。
そう心に誓い、俺はロキシーの背中が見えなくなるまで見送った。
手元には、ロキシーにもらった杖とペンダント。
そして数々の知識だけが残った。
と、思ったら。
数ヶ月前に盗んだロキシーの染み付きパンツが自室にありました。
ごめんなさい。
第七話 「友達」
俺は外に出てみることにした。
せっかくロキシーが外に出るようにしてくれたのだ。無駄にはすまい。
「父様。外で遊んできてもいいですか?」
ある日、植物辞典を片手にパウロにそう聞いてみた。
この年頃の子供というものは、目を放すとすぐにどこかに行ってしまう。
近所とはいえ、黙って出ては親も心配するだろうとの配慮だ。
「外? 遊びに? 庭じゃなくてか?」
「はい」
「お、おお。もちろんだ」
あっさりと許可が出た。
「思えば、お前には自由な時間を与えていなかったな。親の勝手で魔術と剣術を同時に習わせたが、子供には遊ぶことも必要だ」
「いい先生と巡り合わせていただいて感謝しています」
厳格な教育パパだと思っていたが、わりと柔軟な思考をしているらしい。
一日中剣術をしろと言われる可能性まで考慮していたのだが、拍子抜けだ。
感覚派だが、根性論は持っていないらしい。
「それにしても、お前が外に、か。身体の弱い子だと思っていたが、時が経つのはあっという間だな」
「身体が弱いなんて思ってたんですか?」
初耳だ。病気なんてしたことないのに……。
「全然泣かなかったからな」
「そうですか。まぁ、今が大丈夫ならいいじゃないですか。丈夫で愛嬌のある息子に育っていますよ。びろーん」
と、ほっぺたを引っ張って変顔をしてみせると、パウロは苦笑した。
「そういう、子供らしくないところが逆に心配なんだがな」
「長男がしっかりしていることの何が不満なんですか」
「いや、不満は無いんだが」
「不満たらたらの顔で、もっとグレイラット家の跡継ぎとして相応しい人間になれ、とか言ってもいいんですよ?」
「自慢じゃないが、父さんがお前ぐらいの頃は女の子のスカートをめくることに夢中な悪ガキだった」
「スカートめくりですか」
この世界にもあるのか。
しかし自分で悪ガキつったな、この男。
「グレイラット家に相応しい人間になりたいなら、ガールフレンドの一人でも連れてきなさい」
なに? ウチってそういう家柄なの?
辺境を守る騎士で下級貴族って話じゃなかったの?
格式とか無いの? いや、所詮は下級。そんなもんか。
「わかりました。では、めくるスカートを見つけに村に行ってまいります」
「あ、女の子には優しくするんだぞ。それに、自分の方が力が強くて魔術が使えるからって威張っちゃだめだ。男の強さは威張るためにあるんじゃないからな」
お、今いいこと言った。
いいねいいね、生前のうちの兄弟にも聞かせてやりたいよ。
そうだな、力ってのはただ振るっても意味がない。
パウロの言うことはもっともだよ。俺も理解者さ。
「わかっていますよ父様。強さとは、女の子にいい格好を見せる時のためにあるんですよね」
「……いや、そうじゃなくてな」
あれ? そういう話の流れじゃなかったのか?
失敗失敗。てへぺろ。
「冗談です。弱い者を守るためにあるんですよね?」
「うむ、そのとおりだ」
そんな会話の後、植物辞典を小脇に抱え、ロキシーにもらった杖を腰に差し、さぁ出かけようかと思ったところでふと気づいて振り返った。
「ああそうだ、父様。これからもちょくちょく外出すると思いますが、出かける時は必ず家の誰かに言いますし、剣術と魔術の鍛錬は毎日欠かさずやります。日が落ちて暗くなる前には帰りますし、危ない所には近づきません」
「あ……ああ」
念のため、そう言い残しておく。
パウロはなぜか唖然としていた。
本当なら、お前が言わなきゃいけないことだぜ?
「では、行ってきます」
「…………行ってらっしゃい」
こうして、俺は家を出た。
★ ★ ★
数日が経過した。
外は怖くない。順調だ。すれ違う人と爽やかな挨拶をかわせるようにまでなった。
人々は俺のことを知っていた。パウロとゼニスの子供、ロキシーの弟子として。
初対面の相手には挨拶と自己紹介。二度目の人にはこんにちは。誰もがにこやかな顔で挨拶を返してくれる。
こんな晴れやかな気分は久しぶりだ。
半分以上がパウロとロキシーの知名度のおかげ。残りは全てロキシーのおかげだ。
つまり大体ロキシーのおかげだな。
御神体を大切にしよう。
★ ★ ★
さて。
外に出た主な目的は、主に自分の足で歩き、地理を覚えることだ。
地理さえ覚えておけば、突然家から叩き出されても、迷ったりしないからな。
同時に、植物系の調査も行いたい。
ちょうど植物辞典もあることだし、食べられるもの、食べられないもの、薬になるもの、毒になるもの……。それぞれ見分けられるようにしておいたほうがいい。
そうすれば、突然家から叩き出されても、飯に困ることはないからな。
ロキシーはさわりしか教えてくれなかったが、この村では麦と野菜と香水の材料を栽培しているらしい。
香水の材料、バティルスの花というのはラベンダーによく似た植物だ。
薄紫色をしており、食べることもできるのだとか。
そういった目立つものを中心に、俺は目についた植物を片っ端から植物辞典で照合していった。
といっても、村はそれほど広くないし、大した植物があるわけじゃない。
何日もしないうちに、俺の行動半径は広がり、森の方へと向くようになっていた。
森には植物が多いからだ。
「確か、森は魔力溜まりができやすいから、危ないんだったな」
魔力溜まりができやすい環境は、魔物の発生率が高い。
魔力による突然変異で生まれてくるのが魔物だからな。
なぜ森に魔力溜まりができやすいのかは知らんが。
もっとも、このあたりはそもそも魔物が出にくい上に、定期的に魔物狩りが行われているので比較的安全だ。
魔物狩りとは文字通り。
月に一度、騎士、狩人、自警団たちといった男衆が、総出で森に入って魔物を一掃するらしい。
とはいえ、森の奥で凶悪な魔物がいきなり出現することもあるらしい。
俺は魔術を憶えて多少は戦える力を手に入れたかもしれない。
だが、元は喧嘩もロクにしたことのない引きこもりだ。
増長してはいけない。
実戦経験も無いし、調子に乗ってヘマしたら目も当てられない。
そうして死んでいった奴を何人も見てきた……漫画でな。
そもそも、俺は血の気の多いほうじゃない。戦いは極力避けるのが一番だと思っている。
魔物に遭遇したら逃げ帰ってパウロに報告しよう。
そうしよう。
そんなことを考えつつ、俺は小高い丘を登っていた。
丘の上には、大きな木が一本だけ立っている。
この辺りで一番大きな木だ。
自分で歩いた村の地理を確かめるのには高い所がいい。
ついでに、このへんで一番大きなあの木が何の木なのかを確かめるつもりだった。
と、その時。
「魔族は村にはいんなよなー!」
風にのってそんな声が聞こえてきた。
この声音で、嫌な記憶が蘇った。
引きこもりの原因となった高校生活。
ホーケーと仇名された頃の悪夢。
丁度、俺の仇名を呼ぶ時の声音と今の声音が似ていた。
あからさまに格下の相手を数で虐げる時の声音だ。
「あっちいけよなー!」
「くらえー!」
「よっしゃめいちゅーぅ!」
見れば、そこには先日の雨で泥沼みたいになっている畑。
その中で体中泥だらけにしている三人の子供たちが、道を歩いている一人の少年に向かって泥を投げつけていた。
「頭に当てたら十点な!」
「っしゃー!」
「俺あたった! あたったって!」
うわー。いやだいやだ。イジメの現場だ。ああいう奴らは、相手が格下なら何をやってもいいと思ってるんだ。エアガンを買ったら、そいつに向けて撃ってもいいと考えているんだ。人に向けて撃つなと書いてあるのにだ。相手を人として見てないからだ。人として許せんね。
少年はというと、足早にそこを去ればいいのに、なぜか遅々として進んでいかない。
よく見ると、バスケットのようなものを胸元に抱えており、それに泥玉が当たらないように身を縮こまらせているからだ。
そのため、イジメっ子たちの攻撃から逃げ切れないでいた。
「なんか持ってるぜ!!」
「魔族の宝か!!」
「どこで盗んできたんだー!!」
「あれにぶつけたら百点な!!」
「宝を奪いとろうぜ!!」
俺は少年の方に向かって走っていく。走りながら、魔術で泥玉を作る。そして射程距離に入った瞬間、全力投球。
「わっぶ」
「なんだぁ!?」
リーダー格っぽい、ひときわ体の大きい奴の顔面に命中。
「ってぇ、目に入った」
「なんだよお前!!」
「関係ねーやつが入ってくんなよ!!」
「魔族の味方すんのかよ!!」
標的が一瞬で俺の方に向いた。こういうのはどこの世界でも一緒だな。
「魔族の味方じゃありません。弱い者の味方なんです」
俺はドヤ顔で言ったが、少年たちは自分たちこそが正義という顔で糾弾してきた。
「かっこつけてんじゃねえよ!!」
「おまえ、騎士んところのヤツだな!!」
「お坊ちゃんかよ!!」
あらやだ。身元がバレてら。
「いーのかー!! 騎士の子供がこんなことして!!」
「騎士が魔族の味方だって言ってやろー!!」
「てか、兄ちゃんたち呼んでこようぜ!!」
「兄ちゃーん!! 変なのがいるぅー!!」
子供たちは仲間を呼んだ!
しかし誰も現れなかった。
しかし、俺の足は竦んだ!
ぐぬぬ、三人もいるとはいえ、子供に叫ばれて足が竦むとは情けない。
これがイジメられて引きこもった者のサガか……。
「う、うるさい! 三人で寄ってたかって一人を攻撃するとかお前ら最低だ!」
はぁ? って顔された。
む、むかつく。
「てめぇこそ大声だしてんじゃねえよ、バァーカ!!」
むかついたので、泥玉をもう一発投げる。はずれた。
「てめっ!!」
「あいつどこに泥持ってんだよ!!」
「いいからやり返せ!!」
三倍になって返ってきた。パウロに教えてもらった足捌きと魔術を駆使して華麗に回避。
「あ、あたんねぇ!!」
「よけんじゃねえよ!!」
ふはは、当たらなければどうということはない!
しばらく三人は泥玉を投げ続けていたが、俺に当たらないとわかると、急につまんなくなったとでも言わんばかりに、手を止めた。
「あーあ!! つまんねぇの!!」
「もう行こうぜ!!」
「騎士んとこのが魔族と仲良くしてたって言いふらそーぜ!!」
別に俺ら負けてないから。飽きたからやめただけだから。
そんな口調で言い残して、三人のクソガキは畑の向こうへと去っていった。
やった! 生まれて初めてイジメっ子を倒したぞ!
じ、自慢にはならねえな。
ふぅ。それにしても、やっぱ喧嘩は得意になれないな。殴り合いにならなくてよかった。
「君、大丈夫? 荷物は無事?」
とりあえず、泥を投げつけられていた少年に振り返ってみると……。
(わーぉ……)
同じぐらいの歳とは思えないほどの美少年がそこにいた。
子供にしては随分と長いまつ毛に、すっと通った鼻筋に、薄い唇、ぞくりとするような顎のライン。白磁のような肌──それらに怯えたウサギのような表情が相まって、なんとも言えない美しさを醸し出していた。
くそう、パウロがもっと美男子系だったら俺も……。
いや、パウロは悪くない。ゼニスも優秀だ。
だからこの顔は大丈夫だ。
生前のあのニキビと皮下脂肪だらけの顔に比べれば大丈夫だ。
十分いけるって、うん。
「う……うん……だ、大丈夫……」
少年は怯えた顔を向けてきた。
まるで小動物のようで保護欲を誘う。
ショタコンのお姉さんがいたら、一発でジュンってなるだろう。
が、今はそれもこびりついた泥のせいで台無しだ。
服は泥だらけ。顔の半分に泥が付着し、頭にいたっては泥一色。
バスケットを守れたのは奇跡的といってもいい。
しょうがないな。
「ちょっと、そこに荷物置いて、そっちの用水路の前でひざまずいて」
「え……? え……?」
少年は目を白黒させながらも、なぜか言われたままにしてくれる。
あまり人の言うことに逆らわない子らしい。
まあ、逆らう子ならさっきのイジメにも反撃してるか。
少年は四つん這いで用水路を覗きこむような姿勢になっている。
ショタコンのお兄さんがいたら、一発でズグンってなるだろう。
「目をつぶってろ」
俺は水の温度を火の魔術で適当に調整する。
熱すぎず冷たすぎず、四十度ほどのお湯を作り出す。
そいつを少年の頭にぶっかける。
「わぁっ!!」
慌てて逃げようとする少年の首根っこを掴んで、泥を綺麗に洗い落とす。
最初は暴れていたけど、お湯の温度になれてくると、またおとなしくなった。
服の方は……家で洗濯したほうがいいだろう。
「よし、こんなもんかな」
泥が落ちたので、俺は風を火の魔術で適当に調整してドライヤーのように温風を送りつつ、ハンカチで少年の顔を丁寧に拭ってやった。
すると、エルフのようにとんがった耳と、日光に輝く、綺麗なエメラルドグリーンの髪が現れた。
その色を見た瞬間、ロキシーの言葉が思い出される。
『エメラルドグリーンの髪を持つ種族には、絶対に近寄ってはいけません』
ん?
いや、ちょっと違ったな。
確か……。
『エメラルドグリーンの髪を持っていて、額に赤い宝石のようなのがついた種族には、絶対に近づかないでください』
そうだ。確かこうだ。
額に赤い宝石のようなのがついた種族、だ。
少年の額はというと、白い綺麗なおでこちゃん。
オッケー、セーフ。
彼は危ないスペルド族ではない。
「あ、ありがとう……」
お礼を言われて、ハッと我に返った。
おうおう、ビビらせてくれやがって。
腹いせにちょっとばかし、偉そうにアドバイスを開始する。
「君ね。ああいう奴らはちゃんとやり返さないと付け上がるよ」
「勝てないよ……」
「抵抗する意思が大事なんだ」
「だって、いつもはもっとおっきな子もいるんだもん……。痛いのは嫌だよ……」
なるほど。
抵抗すると仲間を呼んで徹底的に痛めつけるわけか。
こういうのはどこの世界も一緒だな。
ロキシーが頑張ったから大人の方は魔族を受け入れるようになったみたいだけど、子供の方はそうは行かないか。
子供ってやつは残酷だ。
ちょっと違うだけで爪弾きにしやがる。
「君も大変だね。髪の色がスペルド族に似てるってだけでイジメられて」
「き、きみは、平気……なの?」
「先生が魔族だったからね。君はなんていう種族なの?」
ロキシーのミグルド族はスペルド族と近しいと言っていた。
もしかすると、彼もそんな種族なのかもしれない。
そう思って聞いたのだが、少年は首を振った。
「……わかんない」
わからないか。
この歳なら、そういうもんなのかな?
「お父さんの種族は?」
「……半分だけ長耳族。もう半分は人間だって」
「お母さんは?」
「人間だけど、ちょっとだけ獣人族が混じってるって……」
半長耳族と、クォーターの獣人?
それでこんな髪になるのか……?
と思っていたら、少年は両目に涙を浮かべていた。
「……だから、魔族じゃないって……お父さん、いうけど……髪の色、お父さんとも、お母さんとも、違う……」
めそめそと泣きだす少年の頭をよしよしと撫でておく。
しかし、髪の色が違うとは大問題だな。
お母さんが浮気していた可能性が出てくる。
「違うのは髪の色だけ?」
「……耳も、お父さんより長い……」
「そっか……」
耳が長くて髪が緑の魔族……どこかにはいそうだな。
うーん、他人の家庭の事情にまではあんまり踏み入りたくないんだが、俺もかつてはイジメられっ子だったし、どうにかしてやりたい。髪の色が緑色ってだけでイジメられるのは可哀想だしな。
俺の遭っていたイジメは身から出た錆の部分もある。
けど、少年は違うだろう。生まれを変えるのは、自分の努力では不可能だ。
生まれた時から、髪の色がちょっと緑色だっただけで道端で泥玉を投げつけられる……。
うう……考えるだけで尿が出そうだ。
「お父さんは優しくしてくれてる?」
「……うん。怒ると怖いけど、ちゃんとしてれば怒られない」
「そっか。お母さんは?」
「優しい」
ふむ。声音から察するに、父親も母親もきちんと愛情を注いでいるようだ。
いや、実際に見てみなければわからないか。
「よし、じゃあ行こうか」
「……ど、どこに?」
「君についていくよ」
子供についていけば親が現れる。自然の摂理だ。
「……な、なんで、ついてくるの?」
「いや、さっきの奴らが戻ってくるかもしれないし。送るよ。家に帰るの? それとも、それをどこかに届けに?」
「お弁当……お父さんに、届けに……」
お父さんはハーフエルフだったか。
物語に出てくるエルフといえば、長寿で閉鎖的な暮らしをしていて、傲慢な性格で他の種族を見下している。弓と魔法が得意で、水と風の魔法を得意とする。あとは名前のとおり耳が長いことぐらいだ。
ロキシーの話によると、「大体それで合ってるが、別に閉鎖的ではない」らしい。
やっぱこの世界のエルフも美男美女が多いのだろうか。いや、エルフに美男美女が多いというのは日本人の勝手な思い込みだ。洋ゲーに出てくるエルフは過度にトンがった顔をしていてとても美男美女には見えなかった。日本人のオタクと外国人のパンピーの感性の違いかね。
もっとも、この少年の両親は美男美女のコンビで確定っぽいが。
「あの………なんで、守って、くれたの?」
少年は保護欲をかきたてる仕草で、おずおずと聞いてくる。
「弱い者の味方をしろと父様に言われてるんだ」
「でも……他の子に、仲間はずれにされるかも……」
そうだろうとも。
イジメられっこを助けたらイジメられました──なんてのは、よくある話だ。
「その時は君が遊んでくれよ。今日から友達さ」
「えっ!?」
だから、二人で徒党を組むのだ。
イジメの連鎖は、助けられたほうが裏切ることで起きる。助けられたほうが責任を持って、助けてくれた恩を返すのだ。もっとも、少年の場合はイジメの原因がもっと根の深い部分にあるので、裏切ってイジメっこの側にまわるとは思わないが。
「あ、家の手伝いとか忙しい?」
「う、ううん」
向こうの都合も聞いていなかったなと思ったが、弱気な顔でぶんぶんと首を振られた。
いいね、その表情。ショタコンのお姉さんがいたら一発でホイホイ釣れるだろう。
ふむ、これはいいかもしれない。
この顔なら、将来的に女の子にモテモテになるだろう。そして、つるんでいれば、そのおこぼれが俺の方にくるかもしれない。俺の顔は大したレベルじゃないだろうけど、男二人が並んでいた時、片方のレベルが高ければもう片方もそれなりに見えるものなのだ。
ちょっと自分に自信がない子は、きっと俺を狙うはず。
自信満々でぐいぐい来られるより、ちょっと自信なさそうな子の方が俺の好みだ。
いける。美少女が自分の近くにブスを置いて引き立て役にする。その逆をやるのだ。
「そういや、名前を聞いてなかったな。俺はルーデウス」
「シル…フ──」
小声でぼそぼそと言うので後半がやや聞き取りにくかったが、シルフか。
「いい名前じゃないか。まるで風の精霊のようだ」
そう言うと、シルフは顔を赤くして「うん」と頷いた。
★ ★ ★
シルフの父親は美形だった。
尖った耳に、輝くような金髪、線は細いが筋肉が無いわけではない。ハーフエルフの名に恥じぬ、エルフと人間のいいところ取りをしたような男性だった。
彼は森の脇にある櫓で、弓を片手に森を監視していた。
「お父さん、これ、お弁当……」
「お、いつもすまないなルフィ。今日はイジメられなかったかい?」
「大丈夫、助けてもらった」
目線で紹介されて、俺は軽く会釈をする。
ルフィというのは愛称か。手とかが伸びそうな感じである。
シルフもあれぐらい能天気で傍若無人ならイジメられたりしなかったろうに。
「初めまして。ルーデウス・グレイラットです」
「グレイラット……もしかして、パウロさんの所の?」
「はい。パウロは父です」
「おお、話には聞いていたが、礼儀正しい子だ。おっと、申し遅れた。ロールズです。普段は森で狩りをしています」
聞くところによると、ここは森から魔物が出てこないように見張る櫓で、二四時間体制で村の男衆が持ち回りで見張りをしているらしい。当然ながらパウロにも当番があり、ロールズはそこでパウロと知り合い、互いに生まれた子供のことであれこれと相談しあったのだとか。
「ウチの子はこんな見た目だが、ちょっと先祖返りをしてしまっただけなんだ。仲良くしてやってほしい」
「もちろんです。仮にシルフがスペルド族だったとしても、僕は態度を変えたりはしませんよ。父様の名誉に掛けてもね」
そう言うと、ロールズは感嘆の声を上げた。
「その歳で名誉かぁ……優秀な子でパウロさんがうらやましいなぁ」
「小さい頃に優秀だった子供が、大人になっても優秀とは限りません。羨ましく思うのは、シルフが大人になってからでも遅くはありませんよ」
シルフのフォローを入れておいてやる。
「なるほど……パウロさんの言っていたとおりだ」
「……父はなんと?」
「君と話していると親として自信を失うらしい」
「そうですか。では、これからはもう少し悪さをして説教をさせてあげることにしますかね」
などと話していると、服の裾を引っ張られた。見れば、シルフがうつむきながら俺の裾を引いていた。大人同士の話は子供にはつまらんか。
「ロールズさん。ちょっと二人で遊んできてもいいですか?」
「ああ、もちろんだとも。ただし、森の方には近づかないように」
それは言われるまでもないが……。
ちょっと足りないんじゃないかね?
「ここに来る途中に大樹のある丘がありましたので、あの辺りで遊んでいると思います。暗くなる前に責任を持ってシルフを送り帰します。帰りに丘の方を見て、家に帰ってもいなければ、なんらかの事件に巻き込まれた可能性が高いので、捜索をお願いします」
「あ……ああ」
なにせ、携帯電話もない世界だ。ほうれんそうはキッチリ守るのが大事だ。
トラブルを全て避けることはできない。すぐにリカバリーするのが大切なのだ。
この国はかなり治安がいいみたいだが、どこに危険が潜んでいるかわかったもんじゃない。
唖然としているロールズを尻目に、俺たちは丘の木へと戻った。
「さて、何をして遊ぼうか」
「わかんない……と、友達と、遊んだことないから……」
友達、という部分でシルフは少し躊躇った。きっと今まで友達がいなかったのだろう。
可哀想に……。いや、俺もいなかったけどな。
「うん。とはいえ、俺も最近になるまで家に引きこもってたからな。さて、どんな遊びをしていいのか」
シルフはもじもじと手を合わせて、上目遣いにこっちを見てくる。
背丈は同じぐらいなのだが、背中をまるめているので、俺を見上げてしまうのだ。
「ねえ、なんで、ぼく、とか、おれ、とか言い方を変えるの?」
「え? ああ。相手によって変えないと失礼になるからな。目上の相手には敬語だよ」
「けいご?」
「さっき、俺が使ってたような言葉のこと」
「ふぅん?」
よくわからなかったらしいが、誰でもおいおいわかっていくことさ。
それが大人になるってことだよ。
「それより、さっきの、あれ。教えて」
「さっきのあれ?」
シルフは目をキラキラさせながら、身振り手振りで説明してくれる。
「手から、あったかいお水がざばーって出るのと、暖かい風が、ぶわーって出るの」
「あー。あれね」
泥を洗い流した時に使った魔術のことだ。
「難しい?」
「難しいけど、練習すれば誰にでもできるよ……多分ね」
最近は魔力量が上がりすぎてどれぐらい魔力を消費してるのかわからないし、そもそもこっちの人らの魔力量が基本的にどれぐらいあるのかわからない。
とはいえ、水を火で温めているだけ。無詠唱でいきなりお湯、とまではいかないだろうが、混合魔術として使えば、誰にでも再現できる。だから多分大丈夫だ。多分。
「ようし。じゃあ今日から特訓だ!!」
こんな感じで、俺はシルフと日が暮れるまで遊んだ。
★ ★ ★
家に帰ると、パウロが怒っていた。
怒っていますという感じに腰に手をやって、玄関の前で仁王立ちしていた。
さて、何をやらかしたっけか。心当たりといえば、大切に保管してある御神体を発見されたことぐらいだが……。
「父様。只今帰りました」
「なんで怒っているかわかっているか?」
「わかりません」
まずはシラを切る。もしパン……御神体を発見されていなかった場合、やぶ蛇になるからな。
「さっき、エトの所の奥さんが来てな、お前、エトの所のソマル坊を殴ったそうじゃないか」
エト、ソマル。誰だそいつ?
聞き覚えのない名前が出てきて、俺は考える。
基本的に、俺は村では挨拶ぐらいしかしていない。
名前を言えば、向こうも名乗ってくれるが、その中にさて、エトという名前がいたような、いなかったような……。
ん、まてよ。
「今日の話ですか?」
「そうだ」
今日出会ったのは、シルフとロールズと、三人のクソガキだけだ。
てことは、ソマルってのは三人のクソガキの一人か。
「殴ってはいません。泥を投げつけただけです」
「この間、父さんが言ったことを覚えているか?」
「男の強さは威張るためにあるんじゃない?」
「そうだ」
ははーん。
なるほど、そういえば、去り際に魔族と仲良くしてるのを言いふらしてやるとか言ってたな。
どういう嘘を吐いて殴ったことになったかわからないが、とりあえず俺のネガキャンをしたというところか。
「父様がどういう話を聞いたのかはわかりませんが……」
「違う!! 悪いことをしたら、まずはごめんなさいだ!!」
ぴしゃりと言われた。
どういう話を聞いたのかはわからないが、鵜呑みにしているらしい。
参ったな。こういう状況だと、シルフがイジメられているところを助けたと言っても、ウソくさい。
とはいえ、一から説明するしかないか。
「実は道を歩いていたら……」
「言い訳をするな!!」
段々イライラしてきた。ウソ以前に、俺の言い分を聞いてくれる気すらないようだ。
とりあえずごめんなさいしてしまってもいいのだが、それはパウロのためにもよくない気がする。
いずれ作られるであろう弟か妹に理不尽な思いをしてほしくはない。
この叱り方は、ダメだ。
「………」
「どうした、なぜ何も言わない?」
「口を開けば言い訳をするなと怒鳴られるからです」
「なに!?」
パウロの眦が釣り上がる。
「子供が何か言う前に怒鳴りつけて謝らせる。大人のやることは手っ取り早くて簡単で、羨ましいですね」
「ルディ!!」
バシッ、と頬に熱い衝撃が走った。
殴られた。
が、予測していた。挑発をしたら殴られる、当然だ。
だからぐっと踏みとどまった。殴られるのなんて二十年ぶりぐらいか……。
いや、家を出る時にぼっこぼこにされたから、五年ぶりか。
「父様。僕は今まで、できる限り良い子でいるように努力してきました。父様や母様の言いつけに背いたことは一度もありませんし、やれと言われたことも全力で取り組んできたつもりです」
「そ、それは関係ないだろう」
パウロも殴るつもりはなかったらしい。
目に見えて狼狽していた。
まあいい。好都合だ。
「いいえ、あります。僕は父様を安心させるように、信頼してもらえるようにと頑張ってきたんです。父様はそんな僕の言い分は一切聞かず、僕が知らない相手からの言葉を鵜呑みにして怒鳴りつけ、あまつさえ手まで上げたんです」
「しかし、ソマル坊は確かに怪我をして……」
怪我?
それは知らないな。自分で付けたのか?
だとしたら当たり屋みたいな奴だな……。
だが残念だったな。俺には大義名分がある。
怪我なんていうちんけな嘘じゃなくてな。
「仮にその怪我が僕のせいだったとしても、僕が謝ることはありません。僕は父様の言いつけには背いていませんし、胸を張って僕がやったと言いましょう」
「………ちょっとまて、何があったんだ?」
おっと、気になってきたな? でも、聞かないと決めたのはお前だぜ。
「言い訳は聞きたくないのでは?」
そう言うと、パウロはグッと苦い顔をした。もうひと息か。
「安心してください父様。次回からは三人掛かりで無抵抗の相手一人を攻撃しているのを見ても無視します。あまつさえ四対一になるように僕の方から動きましょう。弱い者を寄ってたかってイジメることこそがグレイラット家の誇りであり家訓なのだと周囲に喧伝しましょう。そして大きくなったら家を出て、二度とグレイラットとは名乗らないことにします。実際の暴力は無視して、言葉の暴力を許すような、そんなゴミクズの家の人間だと名乗るのは恥ずかしいので」
パウロは絶句していた。
顔を赤くし、青くし、葛藤がかいま見える。
怒るかな。それとも、もうひと息必要かな?
やめておいたほうがいいぞパウロよ。俺はこれでも、二十年以上勝てるわけのない口論で言い逃れ続けてきた男。たった一つでも切り口があれば、最低でも引き分けにもっていけるのだ。
まして今回は完全なる正義。
お前に勝ち目はない。
「……すまなかった。父さんが悪かった。話してくれ」
パウロが頭を下げた。
そうだな。変な意地を張ってもお互い不幸になるだけだ。
悪ければ謝る。それが一番だよ。
俺も溜飲を下げ、事の詳細をできる限り客観的に話した。
丘の上に登ろうとしていると声が聞こえた。三人の子供が休畑の中から、道を歩く一人の子供に泥を投げつけていた。泥を一~二発投げつけてから説き伏せると、彼らは悪態をついてどこかへ行ってしまった。泥を投げつけられていた子を魔術で洗ってやり、一緒に遊んだ。
といった感じに。
「ですので、謝るのでしたら、そのソマル君とやらがシルフに謝るのが先です。体の傷はすぐ消えますが、心の傷はすぐには消えませんので」
「……そうだな、父さんの勘違いだった。すまん」
パウロはしょんぼりと肩を落としていた。
それを見て、俺は昼間にロールズから聞いた話を思い出す。
『君と話していると親としての自信を失うらしい』
もしかすると、パウロは叱ることで父親らしい部分を見せたかったのかもしれない。
まぁ、今回は失敗したようだが。
「謝る必要はありません。今後も僕が間違っていると思ったら、容赦なく叱ってください。ただ、言い分も聞いてくれると助かります。言葉足らずだったり、言い訳にしか聞こえなかったりする時もありますが、言いたいことはありますので、意を汲んでいただければと思います」
「ああ、気をつけるよ。もっとも、お前は間違ったりしなさそうだが……」
「でしたら、そのうちできる僕の弟か妹を叱る時の教訓にしてください」
「………そうするよ」
パウロはハッキリと落ち込んだ様子で自嘲げに言った。
言い過ぎただろうか。五歳の息子に言い負ける。うん。俺だったら凹む。
父親としてはまだ若いもんなコイツ。
「そういえば、父様は、いま何歳でしたっけ?」
「ん? 二十四だが?」
「そうですか」
十九で結婚して俺を作ったのか。
この世界の平均結婚年齢が何歳ぐらいかはわからないが、魔物とか戦争とかも日常的に起こっているようだし、結婚年齢としては妥当な線なのか。
一回りも下の年齢の男が結婚して子供を生んで子育てで悩んでいる。それだけで、三十四歳住所不定無職職歴無しだった俺が勝てる部分は無いと思うのだが……。
まぁ、いっか。
「父様、今度シルフを家に連れてきてもいいですか?」
「え? ああ、もちろんだ」
俺はその返答に満足すると、父親と一緒に家の中へと入っていった。
パウロが魔族に偏見を持っていなくてよかったと思う。
★ パウロ視点 ★
息子が怒っていた。
今まで、さして感情らしい感情を見せてこなかった息子が、静かに激怒していた。
どうしてこうなったのだろうか。
事の起こりは昼下がり、凄い剣幕でエトの奥方が屋敷に怒鳴りこんできたことからだ。
近所で悪ガキとして評判の子供ソマルを連れており、ソマルの目尻には青い痣ができていた。剣士としてそれなりに修羅場をくぐってきたオレには、それが殴られてついたものだとわかった。
奥方の話は要領を得なかったが、要約するに、うちの息子がソマル坊を殴ったらしい。
それを聞いて、オレは内心でほっとした。
大方、外で遊んでいたら、ソマルたちが遊んでいるところを見かけて、仲間に入れてもらおうとしたのだろう。
しかし、息子は他の子供たちと違う。あの歳で水聖級魔術師だ。
きっと偉そうに何かを言って、反発を受けて喧嘩になったのだ。
息子はなんだかやけに聡くて大人びているが、子供らしいところもあるのだ。
エトの奥方は顔を赤くしたり青くしたりしながら大事にしようとしているが、所詮は子供の喧嘩だ。見たところ、怪我の方も痕になったりはしないだろう。
オレが叱って終わりだ。
子供なら殴り合いの喧嘩の一つもするだろうが、ルーデウスは他の子供より力を持っている。若くして水聖級の魔術師となったロキシーの弟子であり、三歳の頃からオレの指導で訓練してきた身体だ。
きっと喧嘩も一方的になったはずだ。
今回は大丈夫だったようだが、頭に血がのぼってカッとなれば、やりすぎてしまうかもしれない。
大体、頭のいいルーデウスになら、ソマル坊を殴らずに済ませる方法はあったはずなのだ。
殴るというのは短絡的で、もっと考えなければならない行動だと教える必要がある。
ちょいとキツめに叱ってやらないとな。
なんて思っていたのに、どうしてこうなった……。
息子は全然謝るつもりはないらしい。
それどころか、虫を見るような目でオレを見てくる。
確かに、息子にしてみれば、対等な立場で喧嘩をしたつもりなのかもしれないが、しかし力の強い者はその強さを自覚しなければならない。
まして、怪我をさせたのだ。とにかく謝らせよう。賢い息子のことだ。今は納得できないかもしれないが、必ず自分で答えにたどり着いてくれるだろう。
そう思い、強い口調で言い聞かせようとしたら、皮肉げに嫌味を言われた。
オレはその嫌味に、ついカッとなって殴ってしまった。
力の強い者はその力を自覚して、自分より弱い者に軽々しく暴力を振るうな、と説教しようとしていたのに。
オレは殴ってしまったのだ。
今のは自分が悪かったと思ったが、説教をしている立場で口にするわけにもいかない。
今しがた自分のした行動をするなと言っても説得力がない。しどろもどろになっているうちに、息子は遠まわしに自分は悪いことをしていないと言い出し、それがダメなら家を出るとまで言い出した。
売り言葉に買い言葉で、出ていけと言いそうになったが、ぐっと我慢する。
我慢しなければならないところだった。
そもそも、オレ自身も、堅苦しい家で厳格な父が頭ごなしに叱ってくるのに嫌気がさし、大喧嘩の末に家を飛び出したのだ。
オレは、父の血を継いでいる。頑固で融通のきかない父の血を、継いでいる。
そしてルーデウスもだ。
この頑固なところを見ろ。ルーデウスも自分の子供だ。
オレはあの日、今すぐ出ていけと言われ、売り言葉に買い言葉で家を出ていった。ルーデウスは出ていくだろう。大人になったら出ていくと言っていたが、いますぐ出ていけと言われれば、すぐに出ていくだろう。そういうところがあるはずだ。
父はオレが旅に出てしばらくして病に倒れ、死んだと聞く。風の噂では、今際の際まであの日の喧嘩のことを後悔していたらしい。
そのことに関しては、オレにだって負い目はある。
いや、ハッキリ言おう、後悔している。
それに照らしあわせて考えるに、ここでルーデウスに出ていけと言って本当に出ていかれたら、間違いなく後悔するだろう。
オレはもちろん、ルーデウスも後悔する。
我慢だ。経験から学んだじゃないか。
それに、子供が生まれた時に決めたじゃないか。あの父のようにはならないと。
「……すまなかった。父さんが悪かった。話してくれ」
謝罪は自然と口に出た。
すると、ルーデウスはスッと表情を和らげ、淡々と説明してくれた。
なんでも、ロールズの子がイジメられていたところに通りがかって、助けに入ったのだという。
殴るどころか、泥玉を投げあっただけで、喧嘩すらしていないという。
その話が本当なら、ルーデウスは胸を張って誇れることをしている。だというのに、褒められるどころか言い分も聞いてもらえずに殴られたことになる。
ああ、思い出す。
自分が幼い頃にも、そういうことは何度もあった。父は一切聞いてくれず、オレの至らない部分ばかりを責めた。その度にやるせない気持ちになったものだ。
失敗した。何が説教しなければ、だ。
はぁ……。
ルーデウスは、そんな自分を責めることなく、最後には慰めてすらくれた。できた息子だ。できすぎだ。本当に自分の息子なのだろうか。……いや、ゼニスが浮気しそうな相手の中に、あんな優秀な子供の父親はいない。うう、自分の種がこんなに優秀だったとは……。
誇らしいと思うより、胃が痛い。
「父様、今度シルフを家に連れてきてもいいですか?」
「え? ああ、もちろんだ」
しかし、今は息子に初の友達ができたことを喜んでおこう。
第八話 「鈍感」
六歳になった。
生活はあまり変わっていない。
午前中は剣術の鍛錬。午後は暇があればフィールドワークと、丘の木の下で魔術の練習。
最近は、魔術を使って剣術の補助的な動きができないかと色々試している。
風を噴出して剣速を上げたり、衝撃波を起こして自分の身体を急反転させたり、相手の足元に泥沼を発生させて足を止めたり……。
そんな小手先の技ばかり考えているから、剣術の方が成長しないと思う奴もいるだろう。
だが、俺はそうは思わない。
格闘ゲームで強くなる方法は二種類だ。
一つ目は、相手より弱い能力で勝つ方法を考える。
二つ目は、自分の能力を高くするために練習する。
今現在、俺が考えているのは一つ目だ。
課題としては、パウロに勝つこと。
パウロは強い。父親としてはまだまだだが、剣士としては一流だ。
二つ目だけを重視し、馬鹿正直に身体を鍛えていけば、確かにいつかは勝てるだろう。
俺は六歳だ。十年経てば十六歳、対するパウロは三十五歳。
さらに五年経てば二十一歳、対するパウロは四十歳。
いつかは勝てるが、それでは意味がない。
年老いた相手に勝ったところで、「いやー、現役の頃だったらなー」と言い訳されるだけだ。
脂の乗っている時期に倒してこそ、意味がある。
パウロは現在二十五歳。
第一線は退いたようだが、肉体的には一番いい時期だ。あと五年以内には一度ぐらい勝ちたい。
できれば剣術で。でもそれは無理そうだから、魔術を織り交ぜた接近戦で。
そう思いながら、俺は今日も脳内パウロ相手にイメトレをする。
★ ★ ★
丘の上の木の下にいると、高確率でシルフがやってくる。
「ごめん、待った?」
「ううん、いまきたとこ」
と、待ち合わせのカップルみたいなことをいって遊び始める。
最初の頃は遊んでいると例のソマル坊、他クソガキ共がよってきた。途中から小学生高学年ぐらいの子供も混ざったが、全て撃退した。その度に、ソマルの母親がウチに怒鳴りこんできた。
それでわかったのだが、ソマルの母親は子供のこと云々というより、どうやらパウロのことが好きらしい。子供の喧嘩をダシに会いにきていたというわけだ。馬鹿馬鹿しい。
かすり傷一つでウチまで歩かされるソマル君もうんざりしているようだった。彼は当たり屋ではなかったのだ。疑ってすまんね。
襲撃があったのは五回ぐらいか。
ある日を境にパッタリと来なくなった。たまに遠くの方で遊んでいるのを見かけるし、すれ違うこともあるが、互いに話しかけることはない。
無視することに決めたらしい。
こうして、あの一件は一応の解決をし、丘の上の木は俺たちの縄張りとなった。
★ ★ ★
さて、クソガキよりもシルフのことだ。
彼には遊びと称して、魔術の訓練を施している。
魔術を覚えれば、クソガキを一人で撃退することもできるからだ。
最初の頃、シルフは入門的な魔術を五~六回で息切れしていたが、この一年で魔力総量もかなり増えてきた。半日ぐらいなら、ずっと魔術の練習をしていても問題ない。
『魔力総量には限界がある』
この言葉の信憑性は実に薄い。
もっとも、魔術の方はまだまだだ。
特に彼は火が苦手だった。シルフは風と水の魔術を実に器用に操ったが、火だけはうまくできなかった。
なぜか。長耳族の血が混じっているから?
違う。
ロキシーの授業で習った、『得意系統・苦手系統』というヤツだ。
文字どおり、人にはそれぞれ、得意な系統と苦手な系統が存在しているのだ。
一度、「シルフ、火が怖いか」と、聞いてみたことがある。
すると、彼は「ううん」と首を振ったが、手のひらを見せてくれた。そこには醜い火傷の痕。
三歳ぐらいの時、親が目を離した隙に暖炉の鉄串を掴んでしまったのだという。
「でも、今は怖くないよ」
と、彼は言うけれど、やはり本能的に怯えているのだろう。
そういう経験が、苦手系統に影響するのだ。
例えば炭鉱族は、水が苦手系統になることが多い。
彼ら炭鉱族は山の近くで暮らしており、子供の頃から土をいじって遊び、成長と共に父親について鍛冶を学んだり鉱石を掘り出したりして過ごすため、火と土は得意になりやすい。しかし、山で活動している時に、いきなり温泉が湧いて火傷をしたり、大雨で洪水になって溺れたりすることが多く、水が苦手になりやすい。
といった感じで、直接的には種族は関係ないのだ。
ちなみに俺に苦手系統は無い。
ぬくぬく育ったからな。
別に火が使えなくても温風と温水は作れる。
だが概念を教えるのが面倒だったので、火の魔術も練習させた。火はどんな時でも使えておいて損はない。サルモネラ菌は熱すれば死滅するのだ。食中毒で死にたくなければ、火は通さねば。
もっとも、初級の解毒魔術で大抵の毒は中和できるようだがね。
シルフは苦戦しながらも、文句を言わずに練習していた。
自分の言い出したことだからだろう。
俺の杖(ロキシーからもらったやつ)と、俺の魔術教本(家から持ってきたやつ)を手に、難しい顔で詠唱するシルフは美しい。
男の俺ですらこう思うのだから、将来モテるんだろう。
(嫉妬の心は父ごころ……)
どこからかそんな声が聞こえたような気がして、慌てて首を振る。
いやいや。嫉妬しても意味はない。そもそも、そういう作戦じゃないか。
イケメン友釣り作戦。
シルフイケメン、オレフツメン、オンナヤマワケ♪
「ねぇ、ルディ。これなんて読むの?」
脳内で歌っていると、シルフが魔術書のページを指さして、上目遣いで見つめていた。
この上目遣いも強力だ。思わず抱きしめてキスしてしまいたくなる。
ぐっと我慢。
「これはな、『雪崩』だ」
「どういう意味なの?」
「ものすごい量の雪が山に溜まった時、重さに耐え切れずに崩れ落ちてくるんだ。ほら、冬に屋根の上に雪が溜まった時に、たまにドサッと落ちてくるだろ? あれの凄いやつ」
「そうなんだ……すごいね。見たことあるの?」
「雪崩をか? そりゃあもちろん…………ないよ」
テレビでしかね。
シルフに魔術教本を読ませる。それは読み書きを教えるということにもつながっていた。文字も学んでおいて損はない。
この世界の識字率がどれぐらいか知らないが、現代日本のように識字率が約一〇〇%というわけではないだろう。
この世界には文字を読めるようになる魔術はない。
識字率が低ければ低いほど、文字が読めるということは有利になる。
「できた!!」
シルフが歓喜の声を上げた。見れば、見事に中級の水魔術『氷柱』に成功していた。地面からぶっとい氷の柱が生え、陽の光を浴びてキラキラと光っている。
「大分上達してきたな」
「うん!! ……でも、この本にルディが使ってたの、書いてないよね?」
シルフが首をかしげながら聞いてくる。
「ん?」
使ってたの、と言われてお湯のことだと思い至る。
俺は魔術教本をペラペラとめくり、二点を指で示す。
「書いてあるじゃん。水滝と灼熱手」
「……?」
「同時に使うんだ」
「…………??」
首をかしげられた。
「どうやって二つ一緒に詠唱するの?」
しまった。自分の感覚で話してしまっていた。そうだね、口で二つ同時は無理だよね……。
これではパウロを感覚派だと笑えないな。
「えっと。呪文を詠唱しないで水滝を出して、それを灼熱手で温めるんだ。片方は詠唱してもいいと思うし、桶に水を溜めて、あとから温めるのでもいい」
無詠唱で同時にやるのを実演してみる。
シルフは目を丸くして見ていた。無詠唱での魔術というのは、やはりこの世界では高等技術に入るらしい。ロキシーはできなかったし、魔法大学の教師にもできる人は一人しかいなかったらしい。
だから、シルフも無詠唱ではなく混合魔術を使っていくべきだろう。
難しいことをやらなくても、似たような結果は出せるのだからと、俺は思ったのだが。
「それ、教えて」
「それって?」
「口で言わないやつ」
シルフはそうは思わなかったらしい。
そりゃあ、二つの魔術を交互にやるより、一発で出せたほうがよさそうに見えるか。
うーむ……ま、教えてみて無理そうなら、自分で混合魔術を使っていくだろう。
「んー。そうだな。じゃあ、いつも詠唱中に感じる、体中から魔力が指先に集まっていく感じ。あれを詠唱しないでやってみるんだ。魔力が集まってきたな、と思ったら、使おうと思っていた魔術を思い浮かべて、手の先から絞り出す、そんな感じでやってみろよ。最初は水弾あたりからね」
伝わったかな?
うまく説明できん。
シルフは目をつぶってむーむー唸ったり、くねくねと変な踊りを踊ったりしだした。
感覚でやっていることを伝えるのは難しい。
無詠唱なんて頭の中でやることだ。人それぞれ、やりやすい方法も違うだろう。
最初は基礎が大事だと思って、シルフィにはこの一年、ずっと詠唱させてきた。
やはり詠唱すればするほど、無詠唱は難しくなるのだろうか。今まで右手でやっていたことを左手でやるのと同じように、今更変えろというのは難しいのだろうか。
「できた! できたよルディ!!」
と、思ったがそうでもないらしい。
シルフは嬉しそうな声を上げて、水弾を連発しだした。
詠唱してたと言っても、所詮は一年。自転車の補助輪を外す程度の感覚でできてしまうものらしい。若さゆえの感性か。あるいはシルフの才能か。
「よし、じゃあ。今までに憶えた魔術を無詠唱でやってみろよ」
「うん!!」
なんにせよ無詠唱でやれるのなら、俺も教えやすい。
自分でやってることを教えていくだけだからな。
「ん?」
と、そこでポツポツを雨が降り始めた。
空を見ると、いつのまにか真っ黒な雨雲が空を覆っていた。
一瞬の間を開けて、叩きつけるような雨が降ってきた。
いつもは空の様子を見て、帰るまでは降らないように調整していたが、今日はシルフが無詠唱で魔術を使えたということで、油断してしまったらしい。
「あーあー、酷い雨だな」
「ルディ。雨降らせられるのに、やませられないの?」
「できるけど、もう濡れちゃったし、作物は雨が降らないと育たないからね。天気が悪くて困ってるって言われない限りはやらないよ」
そんな話をしながら、俺たちは走ってグレイラット邸へと戻った。
シルフの家は遠いからだ。
★ ★ ★
「ただいま」
「お、おじゃま、します……」
家に入ると、メイドのリーリャが大きめの布を持って立っていた。
「おかえりなさい。ルーデウス坊ちゃま……と、お友達の方。お湯の準備ができています。風邪を引かないうちにお二階で体をお拭きください。もうすぐ旦那様と奥様が帰ってらっしゃいますので、わたくしはそちらの用意をしています。お一人でできますか?」
「大丈夫です」
リーリャはどしゃ降りを見て、俺が濡れて戻ってくると予測していたらしい。彼女は口数が少なく、あまり話しかけてもこないが、有能なメイドだ。特に説明せずとも、シルフの顔を見ると家の中に取って返し、大きめの布をもう一枚持ってきてくれた。
俺たちは靴を脱いで裸足になり、頭と足元を拭いてから二階へと上がった。
自室に入ると、大きな桶にお湯が張ってあった。この世界には、シャワーというものはもちろん、湯船にお湯を張るという文化もないから、これで体を洗うのだ。
ロキシーの話によると、温泉はあるらしいが。
ま、風呂嫌いの俺としては、こんなもんでいい。
「ん?」
俺が服を脱いで全裸になった時、シルフは顔を赤くしてもじもじとしていた。
「どうした? 脱がないと風邪引いちゃうぜ?」
「え? う、うん……」
しかし、シルフは動かない。人前で脱ぐのが恥ずかしいのか……。
それとも、まだ一人で脱げないのだろうか。しょうがないな、六歳にもなって。
「ほら、両手上げて」
「えと……うん……」
シルフに両手を上げさせて、ぐっしょりと濡れた上着をずぼっと引きぬく。
筋肉のついていない真っ白い肌が露わになる。そのまま下も脱がそうとすると、腕を掴まれた。
「や、やだぁ……」
見られるのが恥ずかしいのか。
俺も小さい頃はそうだった。幼稚園の頃だ。プールの時間になると全裸になってシャワーを浴びるのだが、同年代に見られるのが妙に恥ずかしかった。
とはいえ、シルフの手は冷たい。早くしないと本当に風邪を引いてしまう。
俺は強引にズボンを引きずり下ろした。
「や……やめてよぉ……」
子供用のカボチャパンツに手をかけると、ぽかりと頭を殴られた。
見上げると、シルフが涙目になって睨みつけていた。
「笑ったりしないから」
「そ、そうじゃな……や、やぁ……!!」
わりと本気の拒絶だった。シルフと知り合ってから、こんなに激しく拒絶されたのは初めてだ。
ちょっとショック。
あれか。長耳族には裸を見せてはいけないという掟でもあるのか?
だとすると、無理やり脱がすのも悪いか……。
「わかった、わかったよ。そのかわり、後でちゃんと履き替えろよ。濡れたパンツって結構気持ち悪いし、冷やすとお腹壊すからな」
「うー……」
俺が手を離すと、シルフは涙目になりながら、こくこくと頷いた。
可愛い。この可愛らしい少年と、もっと仲良くなりたい。
そう思ったら、唐突に俺の中にイタズラ心が芽生えた。
俺だけ全裸って、不公平じゃん。
「隙あり!」
パンツに手を掛けて、一気にずり下ろした。
いでよ!! ゼン○ーペンデュラム!
「ぇ……ぃ、ぃゃあーっ!!」
「…………え?」
シルフの悲鳴。一瞬でしゃがみこんで体を隠す。
その一瞬、俺の目に映ったのは、最近見慣れたピュアなショートソードではなかった。
もちろん、禍々しい紋様の浮かぶダークブレードでもなかった。
そこにあったものは、いや、なかったものは──。
そう………なかったのだ。
ないはずのものがあったのだ。
生前に、パソコンのモニターの中で何度も見てきたものだ。
時にはモザイクがかかっていたり、時には無修正だったり。俺はそれを見ながら、いつかはホンモノを舐めたい入れたいと思いながら、ブラックラストをホワイティキャノンしてペーパーハンケチーフにミートさせていたもの──それがあった。
シルフは。
彼は……彼女だったのだ。
頭が真っ白になる。
俺は今、シャレにならないことをやったのでは……?
「ルーデウス、何をやっているんだ……」
ハッと振り返れば、パウロが立っていた。いつ帰ってきたのか。叫び声を聞きつけてこの部屋に来たのか。
俺は硬直していた。パウロも硬直した。
泣きながらしゃがみこんでいる全裸のシルフがいる。
全裸の俺の手には彼女のパンツが握られている。
そして、俺のキュートなベイビーボーイ。彼は若々しくも猛々しく、その存在を主張していた。何も言い逃れができない状況だった。
俺の手からパンツが落ちた。
外は雨だというのに、パサリという音がやけに響いた気がした。
★ パウロ視点 ★
仕事を終えて家に返ってくると、息子が幼馴染の少女を襲っていた。
頭ごなしに叱ろうとして、しかしオレは慎重になる。今回も何か事情があったのかもしれない。前回の失敗は繰り返すまい。とりあえず、泣きじゃくる少女を妻とメイドに任せて、息子をお湯で拭いてやることにした。
「どうしてあんなことをしたんだ?」
「ごめんなさい」
一年前に叱った時には、絶対に謝らないという意思が見えたものだが、今回はあっさりと謝罪の言葉が出てきた。態度もしおらしい。塩で揉んだ青菜のようだ。
「理由を聞いているんだ」
「濡れたままだから。脱がそうと思ったんです……」
「でも、嫌がってたんだろう?」
「はい……」
「女の子には優しくしなさいって、父さん言ったよな」
「はい…………ごめんなさい」
ルーデウスは何も言い訳をしない。オレがこいつぐらいの時はどうだっただろうか。
〝だって〟と〝でも〟ばっかり言ってた気がする。
言い訳小僧だった。息子は立派だ。
「まぁ、お前ぐらいの歳なら、興味を持つものなのかもしれないがな。ムリヤリはだめだぞ」
「…………はい、ごめんなさい。二度としません」
なんだか打ちひしがれた様子の息子を見ていると、申し訳ない気分になってくる。
女好きはオレの血筋だ。オレは若い頃から血気盛んで精力が強く、可愛い子と見ればひっきりなしに手を出してきた。今はある程度落ち着いたものの、昔は本当に我慢というものができなかった。
遺伝したのだろう。
理知的な息子にとって、そんな本能は悩んで当然のものだろう。
どうして気づいてやれなかったのか……いや、ここは共感すべきところではない。
経験からどうするべきかを示してやるのだ。
「父さんじゃなくて、シルフィエットに謝るんだ。いいね」
「シルフィ、エット……許してくれるでしょうか……」
「最初から許してもらえると思って謝っちゃダメだ」
そう言うと、息子はさらに落ち込んだ。
思えば、最初から息子はあの子に執心していた。一年前の騒動だって、あの子を守るためにしたことだ。その結果、父親に殴られることにすらなった。
その後も、毎日のように一緒に遊んで、他の子から守っていた。剣術も魔術を頑張りながら、彼女のためにマメに時間を作っていた。自分が一番大事にしていた杖や魔術教本を彼女にプレゼントしてしまうぐらい、アプローチしていた。
そんな子に嫌われたかもしれないと思えば、落ち込むのもわかる。
オレだって昔はそうだった。嫌われては落ち込んだものだ。
だが、安心しろ息子よ。オレの経験で言えば、まだまだ余裕で挽回できる。
「なに、大丈夫だ。今までイジワルしてこなかったのなら、心から謝れば、ちゃんと許してくれるさ」
そう言うと、息子はちょっとだけ晴れやかな顔になった。
頭のいい息子だ。今回はちょっと失敗してしまったらしいが、すぐにリカバリーするだろう。
それどころか、今回の失敗をうまいこと利用して、彼女の心を虜にするかもしれない。
頼もしくも末恐ろしい。
風呂から上がった息子は、シルフィエットに向かい開口一番こう言った。
「ごめんシルフィ。髪も短かったし、今までずっと男だと思ってたんだ!!」
ウチの息子は完璧だと思っていたが、意外とバカなのかもしれない。
オレは初めてそう思った。
★ ルーデウス視点 ★
謝ったり褒めたり宥めたりして、なんとか許してもらった。
シルフは女の子だったので、今後はシルフィと呼ぶことにした。
本名はシルフィエットというらしい。
パウロには、あんな可愛い子を男と見間違うとか、どういう目をしているんだと呆れられた。
俺だって、「お前、実は女だったのかー!!」をマジでやると思わなかったさ。
仕方ないじゃないか。初めて会った時は俺よりも髪が短かった。ベリーショートというほどオシャレな感じではないけど、坊主というほど短くもない、そんな感じだった。服装だって女の子っぽい格好は一度もしたことがなかった。浅い色の上着にズボン。それだけだ。スカートでも履いてれば、俺だって間違わなかったさ。
いや……落ち着いて考えてみれば、だ。
髪の色でイジメられていた。だから、髪を短く切って目立たなくするだろう。イジメられれば走って逃げなければいけない。だから、スカートよりズボンを履くだろう。シルフィの家はそれほど裕福ではない。だから、ズボンを一着作れば、スカートを作る余裕は無い。
知り合ったのが三年後だったら、俺だって間違えなかった。
先入観で可愛い男の子だと思っていただけで、中性的というわけでもないのだ。
もし彼女が……いや、もうよそう。
何を言っても言い訳だ。
女の子だとわかると俺の態度も変わってしまう。
男っぽい格好をしているシルフィを見ていると、変な気分になる。
「し、シルフィは可愛いんだから、もっと髪を伸ばしたほうがいいんじゃないですか?」
「え……?」
どうせなら見た目から変わってくれれば仕切り直しもしやすい。
そう思い、そう提案する。
シルフィは自分の髪が嫌いだが、エメラルドグリーンの髪は、陽の光を浴びると透けるように輝く。ぜひとも伸ばしてほしい。そしてできればツインテかポニテにしてほしい。
「やだ……」
しかし、あの日以来、シルフィは俺に対して警戒心を抱くようになった。
特に身体的な接触は露骨に避けられるようになった。
今までハイハイと何でも言うことを聞いていたので、ちょっとショックだ。
「そっか。じゃあ今日も無詠唱での魔術の練習をしましょうか」
「うん」
内心を隠すように、表情を取り繕う。シルフィには俺しか友達がいないので、結局は二人で遊ぶことになる。まだわだかまりは残っているようだが、一応は遊んでくれる。
なので、今はそれでよしとしよう。
★ ★ ★
現在の俺のスキルをこの世界での基準で表すと以下の通りである。
『剣術』
剣神流:初級 水神流:初級
『攻撃魔術』
火系:上級 水系:聖級 風系:上級 土系:上級
『治癒魔術』
治療系:中級 解毒系:初級
治癒魔術は、やはり七段階のランクに分けられており、治療・結界・解毒・神撃の四つの系統から成り立っている。
といっても、攻撃魔術と違い、火聖とか水聖とかカッコイイ呼び名はない。
聖級治療術師、聖級解毒術師、といった呼ばれ方をする。
治療は文字通り、傷を直す魔術。最初は切り傷を直すのが精一杯だが、帝級まで上がれば失った腕を生やすとかもできるらしい。ただし、神級になっても死んだ生物は生き返らない。
解毒は文字どおり。毒や病気を直す術だ。階級が上がれば、毒を作り出したり、解毒薬を作ることもできるのだとか。状態異常の魔術は聖級以上で、難しいらしい。
結界は防御力を上げたり、障壁を作り出す術だ。わかりやすく言えば補助魔法だろう。詳しいことはわからないが、新陳代謝を上げて、軽いキズを治したり、脳内物質を発生させることで、痛みを麻痺させたりしてるんだと思う。ロキシーは使えなかった。
神撃系はゴースト系の魔物や邪悪な魔族に有効的なダメージを与える魔術らしいが、神撃系は人族の神官戦士が秘匿している魔術であるらしく、魔法大学でも教えていないのだとか、ロキシーも知らなかった。
ゴーストなんて見たこともないが、この世界にはデるらしい。
原理がわからないと無詠唱で使えないので、不便である。
そもそも、攻撃魔術に理科っぽい原理があるというだけで、他の魔術にも原理があるのかどうかがわからないのだ。魔力というものが万能の元素っぽいのはわかる。だが、どういう変化をさせれば何ができるのかはわかっていない。
例えば、遠くのものを浮かせたり手元に引き寄せたりするサイコキネシス。
これなんかも再現できそうではあるが、超能力者でなかった俺にはどうやれば再現できるのか見当もつかない。
ちなみに、俺は傷が治るプロセスをふわっとしか憶えていない。ゆえに、ヒーリングを無詠唱でできないのだと思う。医者としての知識を持っていれば、治癒魔術も無詠唱で使えたかもしれない。
他にだって、何かしらしていれば、魔術で再現できただろう。
あるいは、スポーツでもやっていれば、剣術も上達したかもしれない。
そう思えば、生前はなんと無駄な時間を過ごしてきたのだろうか。
いいや。無駄などではない。
確かに俺は仕事もしなかったし学校にも行かなかった。だが、ずっと冬眠していたわけではない。あらゆるゲームやホビーに手を染めてきた。他の奴らが勉強や仕事なんぞにかまけている間に、だ。
そのゲームの知識、経験、考え方は、この世界でも役立つ。
はずだ……!!
まあ、今は役立ってないんだけどね。
★ ★ ★
それは、パウロとの剣術の鍛練中のことだ。
「はぁ……」
思わずため息が漏れた。
露骨なため息をついては怒られるかと思ったが、パウロはニヤニヤと笑った。
「ははーん。ルディ、さてはお前。シルフィエットに嫌われて落ち込んでるな?」
今のため息はそのことではない。
ではないが、確かにシルフィのことも悩みの一つだ。
「ええ、まあ。剣術もうまくならないし、シルフィには嫌われるし、ため息も吐きますよ」
パウロはニヤニヤと笑って、木剣を地面に刺した。木剣にもたれかかるように、目線を落としてくる。
まさかこいつ、笑いものにする気じゃねえだろうな……。
「父さんがアドバイスしてやってもいいぞ」
意外な言葉が出た。
俺は考える。
父、パウロはモテる。ゼニスは美女と言ってもいいし、エトの奥さんの件もある。リーリャだってパウロに尻を触られてまんざらではない顔をしていた。何かあるのだ、女の子に嫌われないための秘訣が。リア充に至る道が。まあ感覚派だろうから理解はできないだろうが、参考にはなるかもしれない。
「お願いします」
「んー、どうしようかなぁ」
「靴でも舐めましょうか?」
「いや、お前、いきなり卑屈になったな」
「教えてくれなければ、リーリャに色目を使ったことを母様に報告します」
「今度はやけに高圧的……って、うぉぃ!! 見てたのかよ!! わかった、わかったよ。もったいぶって悪かった」
リーリャに色目ってのはカマを掛けただけだったんだが……。
もしかして──浮気?
まあいいか。それだけこの男がモテるってことだ。モテ男様の講義を聞くとしよう。
「いいか、ルディ、女ってのはな」
「はい」
「男の強い部分も好きだが、弱い部分も好きなんだ」
「ほう」
聞いたことがあるな。母性本能がどうとかって話か?
「お前、シルフィエットの前で強い部分しか見せてこなかったんじゃねえか?」
「どうでしょう、自覚はありませんが」
「考えてみろ。自分より明らかに強い奴が、欲望をむき出しにして迫ってきたら、どう思う?」
「怖い、でしょうね」
「だろう?」
あの日のことを話しているのだろう。彼が彼女になった日のことを。
「だから弱い部分を見せてやるんだ。強い部分で守ってやり、弱い部分を守ってもらう。そういう関係に持っていくんだ」
「ほう!!」
わかりやすい! 感覚派のパウロとは思えない!
強いだけではダメ、弱いだけでもダメ。しかし両方を兼ね備えればモテる!!
「でも、どうやって弱い部分を見せれば」
「そんなのは簡単だ。お前、今悩んでるだろ?」
「ええ」
「ひた隠しにしているそいつを、シルフィエットの前であからさまな態度に表すんだ。オレは悩んでいます、あなたに避けられて落ち込んでいますってな」
「す、するとどうなります?」
パウロはニヤリと笑う。悪い顔だ。
「うまくいけば、向こうから寄ってくる。慰めてくれるかもしれん。そしたら、元気になれ。仲良くしたら相手が元気になった。それが嬉しくない奴はいない」
「!!」
なるほど。自分の態度で相手の感情をコントロールする……。
さすがだ。でも計画どおりにいくとは限らないのでは?
「そ、それでダメだったらどうします?」
「そん時はまた聞け。次の手を教えてやる」
二手目があるのか。策士、策士だよこの男!!
「な、なるほど、じゃあ今すぐ行ってきます!!」
「行ってこい、行ってこい」
パウロはひらひらと手を振った。俺は居てもたってもいられず、駈け出した。
「六歳の息子になに教えてんだか……」
後ろから、そんな声が聞こえた気がした。
★ ★ ★
木の下についたが時間が早すぎたので、シルフィは来ていない。
木剣を持ってきたのはいつもどおりだが、いつもは身体を拭いてから来るので、汗びっしょりだ。どうしよう。どうしようもない。こういう時は脳内練習だ。俺は木剣を振ってシミュレートする。強さは見せてきた、次は弱さを見せる。弱さ。どうやってだっけか。そう、落ち込んでいるところを見せるのだ。どうやって。タイミングは。いきなりやるのか。それはおかしいだろう。話の流れで、だ。できるのか、いや、やってみせるさ。
そんなことを考えて木剣を振っていたら、いつのまにか握力が無くなっていたのか、木剣がすっとんでいった。
「うっ……」
剣が転がった先に、シルフィがいた。俺は頭の中が真っ白になった。
ど、どうしよう。なんて言えばいい?
「ど、どうしたのルディ……?」
シルフィは、俺を見ると目を丸くした。なんだろう、どうしたって、早く来すぎたせいか?
「んー、ふぅ……んふー、シルフィの可愛い姿が、見れなくて、ざ、残念だなーって」
「そ、そうじゃなくて、その汗」
「はぁ……はぁ……あ、汗? なにが……?」
はぁはぁと息を荒く近寄ったら、怯えた顔で引かれた。いつもどおり一定以内の距離には近づかせてくれないのだ。
俺はこんなに惹かれているのに、君はこんなに引いている。なんちゃって。
「……」
汗が額から落ちてくる。息も整ってきた。よし。
俺は打ちひしがれた様子で木に手を当てて、反省のポーズ。しょんぼりと肩を落とし、大きくため息。
「はぁ……最近のシルフィ、冷たいよね……」
しばらく沈黙が流れた。
これでいいのか? これでいいのかパウロ。もっと弱々しい感じを見せたほうがいいのか。それともワザとらしすぎたか?
「!!」
俺の手が後ろからぎゅっと握られた。温かくも柔らかい感触に振り返ると、シルフィがいた。
お、おおお!
こんなに近い。久しぶりにシルフィが近い。パウロさん! 俺、やりましたよ!!
「だって、最近のルディ、なんかちょっと変だもん……」
シルフィは少しだけ寂しそうな顔で言った。我に返る。
うん。自覚はあった。
言われるまでもなく、俺は今までと同じ態度では接していない。
シルフィから見れば、それはまさに豹変だったろう。相手が小金持ちだと知った瞬間の婚活女子の如き豹変だ。
気分がいいわけがない。でも、じゃあどうやって接すればよかったんだ?
今までと同じように、なんてのはさすがに無理だ。こんなに可愛い子と一緒にいて緊張しないわけがない。
幼く、同年代、可愛い女の子。こんなのと仲良くなる方法を俺は知らない。
俺が大人の立場なら、あるいはシルフィがもっと育っていれば、エロゲー等で得てきた知識を総動員してなんとかした。男なら、弟が幼かった頃の経験を生かした。けれども彼女は同年代の幼女で、女の子だ。無論、それぐらいの年齢の女の子と性的に仲良くなるゲームもやったことはあるが、あんなものは幻想だ。それに、そういう関係になりたいわけじゃない。シルフィはまだ幼すぎる。俺の守備範囲じゃない。
とりあえず、今のところはね。将来的には期待してるけどね!!
それはさておき、彼女はイジメられっ子だった。俺がイジメられていた時、味方はいなかった。だから、俺は彼女の味方でいてやりたい。男だろうと女だろうとだ。その部分だけは変わらない。でも、やっぱり今までと同じように接するのは難しいのだ。俺だって男だし、可愛い女の子とはいい関係を築いていきたい。
今後のために!!
ぬう……わからない。どうすればいいんだ。そこもパウロに聞いておけばよかった……。
「……ごめんね、でも私、ルディのこと、嫌いじゃないよ」
「し、シルフィ……」
俺が情けない顔をしていると、シルフィは俺の頭を撫でてくれた。
そして、シルフィはほやっとしたはにかみ笑いを見せた。柔らかい笑みだった。
じーんときた。
明らかに俺が悪いのに、彼女は謝ってくれたのだ。
俺は彼女の手を掴んで、ぎゅっと握った。
シルフィはちょっと驚いて顔を赤くしつつ、上目遣いで言った。
「だから、普通にしてて?」
上目遣いのその言葉は強力だった。
俺に決断させるに十分な威力を秘めていた。
俺は決意した。
そうだ。彼女は普通を望んでいる。
今までどおりの関係だ。だからできる限り普通に接するのだ。
彼女が怯えないように、狼狽えないように、男としての部分をひた隠しにして接するのだ。
つまり、アレだ。俺はアレになればいいのだ。
なってやろうじゃないか。
鈍感系主人公に。
第九話 「緊急家族会議」
ゼニスの妊娠がわかった。弟か妹が生まれるらしい。
家族が増えるよ。やったねルディちゃん!!
ゼニスはここ数年悩んでいた。
彼女は俺以降に子供ができないことを気に病んでいた。
もう自分は子供が産めないんじゃないかと、ため息混じりに漏らしていたのだが、一ヶ月前ぐらいから味覚の変化に始まり、吐き気、嘔吐、倦怠感。いわゆるつわりの症状が出始めた。憶えのある感覚だったため、医者に行った結果、ほぼ間違いないだろうと言われたらしい。
グレイラット家はその報告に沸いた。
男の子だったら名前はどうしよう、女の子だったら名前はどうしよう。部屋はまだあったよな。子供服はルディのお下がりを使おう。
話題は尽きなかった。
その日はずっと賑やかで、笑いの絶えない日だった。俺も素直に喜び、できれば妹がいいと主張した。弟は俺の大切なものを壊していくからな(バットで)。
そして。
問題はそのさらに一ヶ月後に浮上した。
★ ★ ★
メイドのリーリャの妊娠が発覚した。
「申し訳ありません、妊娠致しました」
家族の揃った席で、リーリャが淡々と妊娠を報告した。
その瞬間、グレイラット家は凍りついた。
(相手は誰……?)
なんてことを聞ける空気ではなかった。
全員が薄々感づいていた。リーリャは勤勉なメイドだ。給金もほとんど実家へと送っていた。村の問題を解決するためにちょくちょく出かけるパウロや、定期的に村の診療所に手伝いにいくゼニスと違い、業務以外での外出もほとんどしなかった。リーリャが誰かと特別親しくしているという噂も聞かない。
あるいは行きずりの誰かと、とも思ったが……。
俺は知っている。
ゼニスが妊娠してから禁欲生活を強いられたパウロのことを。性欲を持て余したヤツが、夜中にこっそりとリーリャの部屋に向かったのを。
俺が本当に子供だったら、二人でトランプでもしてるだろうと思っただろう。
だが残念ながら、俺は知っている。ババ抜きではなく、母抜きで何が行われていたのかを。
だが、もう少し気をつけてほしかった。例のあの二人も言っているじゃないか。
『良い子の諸君!! 「やればできる」実にいい言葉だな。我々に避妊の大切さを教えてくれる!!』
この言葉を、顔を真っ青にしているパウロにも聞かせてやりたい。
ま、この世界に避妊という概念があるかどうかは知らないが。
もちろん。事実を暴露して家庭崩壊を招くつもりはない。
メイドに手出しとか、いつもなら許せんと思う。
だが、パウロにはシルフィの件で世話になった。今回だけは許してやろう。
モテる男は辛いのだ。なので、もし疑われてたら庇ってやろう。偽のアリバイをでっち上げてやってもいい。そう決めて、安心してくれ、という視線でパウロに目配せしておいた。
と、同時にゼニスが、まさかという顔でパウロを見た。
奇しくも、俺とゼニスの視線が一斉にパウロに注がれることとなった。
「す、すまん。た、多分、俺の子だ……」
奴はあっさりとゲロった。
情けない……。いや、正直な男だと褒めるべきか。もっとも日頃から家族の揃った席で俺に向かって、「正直に」とか「男らしく」とか「女の子を守れ」とか「不誠実なことはするな」と偉そうに薫陶をたれていた手前、嘘を吐けなかっただけなのかもしれないが。
いいじゃないか。嫌いじゃないよ、お前のそういうところ。
(状況は最悪だけどな……)
ゼニスが仁王のような顔で立ち上がり手を振り上げるのを見て、俺はそう思った。
こうして、リーリャを交えて、緊急の家族会議が勃発した。
★ ★ ★
沈黙を最初に破ったのはゼニスだった。
会議の主導権は彼女に握られている。
「それで、どうするつもり?」
俺の目から見るに、ゼニスは極めて冷静だった。
浮気した夫に対してヒステリーも起こしておらず、ただ一発頬を張っただけだ。
パウロのほっぺちゃんには赤いもみじ模様がついている。
「奥様の出産をご助力した後、お屋敷をお暇させていただこうかと」
答えたのはリーリャだ。彼女も極めて冷静だった。この世界では、こういうことがよくあるのかもしれない。雇い主にお手付きにされるメイド。問題になり、屋敷から出ていく。
うん。
いつもならそんな不憫なストーリーには興奮する。けど、さすがにこの空気ではピクリともしない。俺にだって節操はあるのだ。パウロと違ってな。
ちなみにパウロは端の方で縮こまっている。
父親の威厳? んなもんねーよ。
「子供はどうするの?」
「フィットア領内で産んだ後に、故郷で育てようかと思います」
「あなたの故郷は南の方だったわね」
「はい」
「子供を産んで体力の衰えたあなたでは、長旅には耐えられないわね」
「……かもしれませんが、他に頼れるところもないので」
フィットア領はアスラ王国の北東だ。
俺の知識によると、アスラ王国で『南』とされる地域へは、乗合馬車を乗り継いでも一ヶ月近くかかる。一ヶ月とはいえ、アスラ王国は治安も気候もいい。乗合馬車を使えば、過酷というほどではない。
だが、それは普通の旅人の場合だ。
リーリャには金がない。乗合馬車には乗れないし、旅路は徒歩になるだろう。
もし、グレイラット家が旅費を出し、乗合馬車を使えたとしても、危険性は変わらない。
子供を産んだばかりの母親の一人旅。俺が悪い奴だとして、それを見かけたらどうする?
そりゃ襲うさ。格好のカモだ。狙ってくれと言っているようなものだ。子供を人質にでも取って、適当な口約束で母親を拘束。とりあえず金銭は奪い、身ぐるみを剥ぐ。この世界には奴隷制度があるらしいので、子供と母親、両方とも売り払って終了だ。
いくらアスラ王国はこの世界でも一番治安のいい国だと言っても、悪い輩がゼロというわけではないはずだ。高確率で襲われるだろう。
ゼニスの言うとおり、体力的な面もある。リーリャの体力がもったとしても、子供はどうだ。
生まれたばかりの子供が一ヶ月の旅に耐えられるか?
無理だろう。
もちろん、リーリャが倒れれば、子供だって道連れだ。病気になっても、医者に見せる金が無いのなら、共倒れになる。
赤子を抱いたリーリャが大雪の中で倒れている光景が目に浮かんだ。
俺としては、リーリャにそんな死に方はしてほしくない。
「あの、母さん、さすがにそれは……」
「あなたは黙っていなさい!!」
パウロがおずおずと口を開いたが、ゼニスにピシャリと言われて、子供のように縮こまった。
この一件に関して、彼に発言権は無い。パウロは役に立たない。
「…………」
ゼニスは難しい顔で爪を噛んだ。どうやら彼女も迷っているらしい。
彼女はリーリャを殺したいほど憎んでいるわけではない。
それどころか、二人は仲がいい。六年も一緒に家事をしてきたのだ、親友と言ってもいいだろう。
リーリャが宿したのがパウロの子供でなかったら。
例えば路地裏でレイプされた結果にできた子供であったとしたら、ゼニスは迷うことなくリーリャを保護し、我が家で子供を育てることを許可……いや強制しただろう。話の流れから察するに、この世界には堕胎という概念はないようだし。
今、ゼニスの中で二つの感情がせめぎ合っているのだと思う。
好きだという気持ち、裏切られたという気持ち。
この状況で後者に感情が偏っていないゼニスはすごいと思う。俺なら嫉妬で今すぐ叩き出す。
ゼニスが冷静でいられるのは、リーリャの態度も関係しているだろう。リーリャは言い逃れを一切せずに、責任を取ろうとしている。仕えてきた家を裏切った責任を。
だが、俺に言わせれば、責任を取るべきなのはパウロだ。リーリャが一人で責任を取るのは、おかしい。
絶対におかしい。
こんなおかしな別れ方をしてはいけない。
俺はリーリャを助けることに決めた。リーリャには世話になっている。あまり関わりあいにはなっていないし、話しかけられたこともほとんどない。
けれど彼女はきちんと世話を焼いてくれている。剣術で汗をかいたら布を用意してくれる。雨に濡れたらお湯を用意してくれる。冷え込む夜には毛布を用意してくれる。本を棚にしまい忘れたら、きちんと整頓してくれる。
そして何より。
何より……何より、だ。
彼女は御神体の存在を知りつつ、黙っていてくれている。
そうリーリャは知っているのだ。
あれはシルフィをまだ男だと思っていた頃だ。
雨が降っていた。俺は復習も兼ね、自室で植物辞典を読んでいた。すると、リーリャが来て、掃除を始めた。辞典に夢中になっていた俺は、リーリャが神棚付近を掃除しているのに気づかなかった。気づいた時には手遅れで、リーリャの手には御神体が摘まれていた。
バカなと思った。確かに俺は二十年近く引きこもっていた。誰はばかることなく、オープンに散らかしていた。デスクトップには「えろ絵」なんてフォルダすらあった。だから、隠蔽スキルは錆び付いてしまっていたのかもしれない。だがまさか、こうもあっさりと見つかるとは。結構マジに隠したのに……。これがメイドという生き物なのか。
俺の中で何かが崩れると同時に、頭のてっぺんから血液が落ちる音を聞いた。
尋問が始まった。
リーリャは言った「これはなんですか?」と。
俺は答えた「なななんでしょうね、それわはははははは」と。
リーリャは言った「匂いますね」と。
俺は答えた「ご、ゴマラーユの香りかなんかなんじゃないんじゃないですかね」と。
リーリャは言った「誰のですか?」と。
俺は答えた「…………すいません、ロキシーのです」と。
リーリャは言った「洗濯をしたほうがいいのでは?」と。
俺は答えた「それを洗うなんてとんでもない!!」と。
リーリャは無言で御神体を神棚へと戻した。
そして、戦慄する俺を背に、部屋から出ていった。
その晩、俺は家族会議を覚悟した。
しかし、何もなかった。
深夜、布団の中でガタガタ震えて過ごした。翌朝になっても、何もなかった。
彼女は誰にも言わなかったのだ。
この恩を、今返そう。
「母様。一度に二人も兄弟ができたというのに、なんでこんなに重い雰囲気なのですか?」
なるべく子供らしく。
リーリャも妊娠したんだ。やったね、家族がたくさんだ。なのにどうして怒ってるの?
という感じを出しながら、俺は切り出した。
「お父さんたちがやっちゃいけないことをしたからよ」
ゼニスはため息混じりに言う。その声音には、底知れぬ怒りが混じっている。けれど、怒りの矛先はリーリャではない。ゼニスだってわかっているのだ。
一番悪いのは、誰か。
「そうですか。しかしリーリャは父様に逆らえるのでしょうか?」
「どういうこと?」
なら、パウロには悪いが、今回は自業自得だ。罪を一手に被ってもらうとしよう。
すまんね、シルフィの件でのことは次回だ。
「僕は知っています。父様はリーリャの弱みを握っています」
「え? 本当なの!?」
俺のでまかせを信じ、ゼニスは驚いてリーリャを見る。
リーリャはいつもどおり無表情だが、心当たりがあったらしく、眉をぴくりと動かした。ホントに弱みを握られているのだろうか。普段の言動を見る限り、むしろリーリャがパウロの弱みを握っているように見えたが……。
いいや。好都合だ。
「この間、夜中にトイレに行こうと思ってリーリャの部屋の前を通ったら、父様が……なんとかを言いふらされたくなかったらおとなしく股を開けって言っていました」
「なっ!! ルディ、なにをバカな……」
「あなたは黙っていなさい!!」
ゼニスが金切り声を上げて、パウロを制した。
「リーリャ、今の話は本当?」
「いえ、そんな事実は……」
リーリャは言いかけてから、視線を彷徨わせた。
本当に心当たりがあるのか。あるいはそういうプレイでもしたのかもしれない。
「そうね、あなたの口からはあったとは言えないわね……」
ゼニスはその態度に、勝手に納得した。
パウロは目を白黒させて口を開き、しかし言葉は出せずにパクパクと金魚のようになっている。
よし。畳み掛けよう。
「母様。リーリャは悪くないと思います」
「そうね」
「悪いのは父様です」
「……そうね」
「父様が悪いのにリーリャが大変な目に遭うのは間違っています」
「…………そうね」
手応えが薄い……あと一息。
「僕はシルフィと一緒にいて毎日が楽しいのですが、生まれてくる僕の弟か妹にも、同じぐらいの年齢の友達がいたほうが良いのではないでしょうか」
「……そう、ね」
「それに母様。僕にとっては両方とも兄弟です」
「…………わかったわよ。もう、ルディには敵わないわね」
ゼニスは大きくため息をついた。
苦労を掛けるね、ママン。
「リーリャ、うちにいなさい。あなたはもう家族よ!! 勝手に出ていくのは許さないわ!!」
鶴の一声。
パウロは目を見開き、リーリャは口に手を当てて涙ぐんでいた。
これにて、一件落着。
★ ★ ★
こうして、全ての責任をパウロになすりつけることで、事態は事なきを得た。
最後に、ゼニスは無機質で冷徹な目をパウロに送った。
業界ではご褒美かもしれないが、俺のボールはキュンってなった。
そんな目をして、ゼニスは一人で寝室へと戻っていった。
リーリャは泣いていた。無表情な顔はそのままに、目からポロポロと涙を流していた。
パウロがその肩を抱こうとして、迷っている。
とりあえず、この場はプレイボーイに任せるとしよう。
俺はゼニスの後を追い、寝室へと向かう。この一件で、パウロとゼニスが離婚するなんてことになったら、それはそれで問題だからな。
寝室の扉をノックすると、ゼニスがすぐに顔を出した。
「母様。先ほど言ったのは僕の考えた嘘です。父様のことを嫌いにならないでください」
間髪入れず、前置きは一切なく、そう言った。
ゼニスは一瞬呆気に取られたようだが、苦笑し、優しい顔で俺の頭を撫でた。
「わかってるわよ。私だって、そんな悪い男に恋をしたつもりはないもの。馬鹿で女に目がないから、いつかはこういうことがあると覚悟もしてたの。いきなりだったからびっくりしただけよ」
「……父様は女に目がないのですか?」
なんとなく、知らないフリをして聞いてみる。
「そうね。最近はあまりだけど、昔は見境がなかったわね。もしかしたら、知らないだけでルディのお兄さんかお姉さんがどこかにいるかもしれないわよ」
と、俺の頭を撫でる手に力がこもった。
「ルディはそんな大人になっちゃダメよ?」
ギリギリと頭を撫でる、否、掴む手に力が篭っていく……。
「シルフィちゃんを大事にしなきゃダメよ?」
「いた、痛い、もちろんです、母様、痛いです」
今後の行動に関して、大きな釘を刺された気分だ。
でも、この調子なら大丈夫だろう。今後どうなっていくのかは、パウロの努力次第だ。
それにしても、まったく、ウチの父親はヤンチャで困るよ。
二度目はないぜ、セニョール。
翌日。
剣術の稽古がすんげー厳しかった。
ちゃんとフォローまでしたんだから、八つ当たりはやめてほしい。
★ リーリャ視点 ★
ハッキリ言おう。
妊娠は、自分が悪い。パウロを誘ったのは自分だ。
この家に来た頃は、そのつもりはなかった。けれど、毎夜毎晩二人の喘ぎ声を聞き、男女の匂いの充満する部屋を掃除していれば、自分とて女だ、性欲は溜まる。
最初は自分で済ませていた。
けれども、毎日庭で剣術の稽古をするパウロを見ていると、消化しきれなかった残り火が身体の奥底で大きくなるのだ。
剣術の稽古をするパウロを見ていると、初めての時を思い出す。
あれは、まだずっと若かった頃、剣道の道場で寝泊まりしていた頃。相手はパウロで、無理矢理の夜這いだった。嫌いではなかったが、愛し合っていたわけではない。ロマンチックとは言いがたかったので、当初は涙したものだ。
けれど、次に自分に色目を使ってきたのは脂ぎった大臣だった。
アレよりマシかと思えば、気にも留まらなくなった。
パウロがメイドを募集していると聞いた時も、あの時のことを交渉材料にすればいいか、ぐらいに思っていた。
久しぶりに出会ったパウロはあの頃よりもずっと男らしかった。
少年らしさは消え、厳しさと屈強さを兼ね備えた男になっていた。
自分はそんな男を前にして、六年間もよく耐えたと思う。
最初、パウロも自分に色目は使わなかった。
そのままならば、次第に火照りも消えただろう。
だが、たまにされるセクハラで情欲の火は燃え盛った。
我慢はできたが、絶妙なバランスで立っているのを自覚していた。
ゼニスの妊娠で、それが決壊した。
パウロが性欲を持て余しているのを、自分は好機と考えてしまった。好機と考えて、パウロを部屋へと誘いこんでしまったのだ……。
だから、自分が悪いのだ。妊娠は罰だと思った。情欲に負け、ゼニスを裏切った罰だと。
しかし、許された。
ルーデウスが許してくれた。
あの賢い子供は、何が起こったのかを正確に理解し、的確に会話を誘導し、落としどころまで綺麗に持っていった。
まるで過去に似たようなことがあったかの如き冷静さだ。
不気味……いや、そう言うのはもうよそう。
自分はルーデウスを不気味に思い、散々避けてきた。
ルーデウスは聡い。避けられていることに気づいていただろう。そんな自分を、ルーデウスは救ってくれたのだ。決していい気分ではなかっただろうに。
己の感情より、自分とこの子を救うことを選んでくれたのだ。
不気味だと言って避けてきた自分が恥ずかしい。
彼は命の恩人である。尊敬すべき人物である。
敬うべきだ。最大限の敬意を払い、死ぬまで仕えるべき人物だ。いや……自分は今まで、彼をないがしろにしてきた。自分だけでは返しきれないだろう。
そうだ。
もし、お腹の子が無事に生まれ、育ったのなら。
この子を、ルーデウスに……。
ルーデウス様に仕えさせるのだ。
★ ルーデウス視点 ★
それから数ヶ月は、特に何事もなく過ごした。
シルフィの成長は著しい。無詠唱の魔術を中級まで使えるようになった。徐々に細かいこともできるようになってきている。
対して、俺の剣の腕はあんまり変わらない。
良くはなってきているようだが、未だにパウロから一本も取れないので実感が湧かない。
あと、リーリャの態度が軟化した。彼女は今まで、俺を警戒していたらしい。まあ、そりゃ小さい頃から魔術をバカバカ使ってたから、当然だろう。
基本的に無表情なのは変わらないが、言葉や行動の端々に、やたら仰々しい敬意のようなものを感じるようになった。敬われるのは気分がいいが、パウロの立場がないので程々にしてほしい。
ともあれ、あの一件以来、リーリャとは少しずつ話をするようになった。
主に、パウロとの昔話だ。
なんでもリーリャは昔、パウロと一緒の道場で剣を習っていたことがあるらしい。
当時のパウロは才能はあったが、練習嫌いだったとか。練習をサボって町に繰り出しては遊び歩いていたのだとか。リーリャは当時のパウロに寝込みを襲われて純潔を散らしたのだとか。パウロはそれが発覚することを恐れて道場を逃げ出したのだとか。
そのあたりのことを淡々と話してくれた。
リーリャの昔話を聞けば聞くほど、俺の中のパウロ株はどんどん下落していった。
レイプに浮気。パウロはクズだな。
けど、パウロも根は悪いヤツじゃない。自由奔放で子供っぽくて、母性本能をくすぐるタイプみたいだし。俺の前では父親らしくしようと努力してるし。ちょっと我慢が効かなくて、思い立ったら直情系なだけで、決して悪いヤツではないんだ。
「なんだ、まじまじと見て。父さんのようなカッコイイ男になりたいか?」
剣術の最中にパウロを見ていたら、そんなことを聞かれた。
ふざけた奴だ。
「浮気して家庭崩壊の危機を作り出すような男が、カッコイイのですか?」
「ぐぬぅ……」
パウロは苦い顔をした。その表情を見て、俺も気をつけようと心に決める。
もっとも俺は鈍感系だ。浮気なんてしない。女の子が勝手に俺を取り合うだけ。そうするように仕向けるだけだ。
「ま、あれに懲りたら、母様以外に手を出すのは控えてください」
「り、リーリャはいいだろう?」
この男、懲りていないらしい。
「次は母様が無言で実家に帰るかもしれませんねぇ……」
「ぐ、ぐぬぅ……」
女を二人囲って、ハーレムでも作ったつもりだろうか。美人の嫁さんを手に入れ、いつでも手が出せるメイドを囲い、息子に剣を教えつつ田舎で爛れた隠居暮らし。
おいおい、羨ましいぞ。最高のエンディングの一つじゃないのか?
某ラノベで言うなら、ル○ズとシ○スタの両方に手を出して無事でいるようなもんだ。
俺も鈍感系とか言ってないで、見習うべきじゃないのか……?
いや、だめだ。落ち着け。あの家族会議の時の、最後のゼニスの目を。
あんな目をされたいのか?
嫁は一人で十分だ。
「お、お前も男ならわかるだろう?」
パウロはなおも食い下がってきた。わかるけど、同意しない。
「六歳の息子に何がわかるというんですか?」
「ほら、お前だってシルフィちゃんに唾つけてるじゃないか。あの子は将来美人になるぞぉ」
そこには同意せざるを得ません。
「そうでしょうね。今のままでも十分可愛いとは思いますが」
「わかってるじゃないか」
「まあね」
パウロはクズ野郎だけど、なんだかんだ言って話が合う。
俺は見た目は子供だが、精神は四十を超えたニート。正真正銘のクズだ。
ゲーム内に限るが、女の子も好きだし、ハーレムも大好きだった。本質的な部分では女誑しのパウロと一緒なのかもしれない。
というか、話が合うと思い始めたのは、シルフィを剥いた事件からだ。
あの事件の後、パウロの方から歩み寄り、打ち解けてくれた気がする。自分の弱い部分を見られたせいか、無理に厳格な父親であろうともしなくなった。彼も成長しているのだ。
「んふふ……」
ふと見ると、パウロがニヤニヤと笑っていた。
その視線は俺ではなく、俺の後ろへ注がれている。振り返るとシルフィが立っていた。ウチまで来るとは珍しい。
よく見ると、若干、頬を赤く染めて、もじもじとしている。
聞いていたらしい。
「ほら、今の言葉、もう一度言ってあげなさい」
パウロの古典的なからかい。
俺はフッと鼻で笑う。まったく、わかってない。
パウロもまだまだだな。
心地いい言葉でも、何度も聞いていれば慣れ、刺激が薄くなってしまう。鈍感に見せかけて、たまにポロリと本心をこぼすように言うのが効果的なのだ。
たまにだ。二度も言ってはダメなのだ。
なので、俺はにっこりと笑って、無言でシルフィに手を振っておいた。
大体、シルフィはまだ六歳だ。そういう話をするのは、十年は早い。
今の時期から可愛い可愛いと言われて甘やかしても、ロクな女にならない。
生前の俺の姉貴がいい例だ。
「あ、あのね。ルディも、その……カッコイイ、よ?」
「そうかい、ありがとうシルフィ」
白い歯をキラッと光らせ(たつもりで)、ニコッと笑う。
さすが、シルフィは社交辞令が上手だね。その上目遣いに、危うく本気だと勘違いするところだったよ。シルフィを可愛いといったのは本心だけど、そこに恋愛感情は無いのだ。
今のところはね。
「では父様。出掛けて参ります」
「草むらで押し倒したりするんじゃないぞ」
やるかよ。お前じゃあるまいし。
「母様!! 父様が──」
「わー、やめろやめろ……!!」
今日も我が家は平和だった。
★ ★ ★
それからしばらくして、ゼニスの出産が行われた。
大変だった。なにせ逆子だったのだ。
リーリャも身重ということで、ヘルプとして村の産婆さんを呼んできていたのだが、その婆さんが、お手上げだと言いだした。それほどの難産だった。
出産には時間は掛かり、母子ともに危険な状況に陥った。
リーリャは持てる知識を総動員して必死に動いた。俺も微力ながら、治癒魔術をかけ続けることで援護した。
その甲斐あって、なんとか出産に成功した。
赤子は無事にこの世界に誕生し、元気な産声を上げた。
女の子だった。妹だ。弟じゃなくてよかった。
ほっとしたのもつかの間、リーリャが産気づいた。
誰もが疲れ果て、気が緩んだ瞬間の出来事だ。
早産という単語が俺の中で躍る。
しかし、今度は産婆さんが役に立った。逆子の対処はヘタクソでも、早産の方は経験があるらしい。さすがは年の功。
俺は即座に婆さんの指示に従った。呆けているパウロの尻にケリを入れ、リーリャを俺の部屋へと運ばせる。その間に魔術を使って産湯を作り直し、綺麗な布をありったけかき集めて、婆さんの元へと戻ってくる。
あとは、婆さんに任せた。
子供が生まれる瞬間、リーリャは健気にパウロの名前を呼んだ。
パウロは汗だくになりながら、リーリャの手を強く握っていた。
生まれた子は、ゼニスの娘よりは小さかったが、それでも元気な産声を上げた。
こちらも女の子だった。
二人とも女児。妹だ。
両方とも女の子かー、なんて言いながら、パウロがでへでへと笑ってる。
バカ親丸出しの顔。この顔を見るのは今日で二度目だ。
それにしても、パウロが不憫でならない。なにせ、我が家の女の勢力が二倍になってしまったのだ。そんな状況で一番下の立場になるのは、誰か。
メイドに浮気して子供を産ませた父親だろう。
俺は尊敬されるカッチョイイ兄貴を目指すが、パウロはきっと尊敬されまい。
ゼニスの娘は、ノルン。
リーリャの娘は、アイシャ。
そう名付けられた。
第十話 「伸び悩み」
七歳になった。
二人の妹、ノルンとアイシャはすくすくと育っている。
おしっこを漏らしては泣き、うんこを漏らしては泣き、お腹がすけば泣き、なんとなく気に食わなかったら泣き、気に食わなくなくても泣いた。
夜泣きは当然、朝泣きも当然。昼はなおさら元気にビャービャー。
パウロとゼニスはあっという間にノイローゼになってしまった。
ただ、リーリャだけは元気で、
「これですよ、これこそが子育てなんですよ! ルーデウス坊ちゃんの時はイージー過ぎました! あんなのは本当の子育てじゃありません!」
と、手際よく二人の世話をしている。
ちなみに、夜泣きは弟で慣れているので、俺は大して気にならなかった。
自慢じゃないが、赤ん坊の世話は弟でやったことがある。テキパキとおしめを交換し、洗濯や掃除を手伝う。そんな俺を見て、パウロがとても情けない顔をしていた。
この男は戦前の日本男児の如く、家のことがまったくできないのだ。
剣の腕は確かだし、村の連中からの信頼もブがつくほど厚いのだが、パパとしては半人前も良いところだ。
二人目だというのに……まったく。
★ ★ ★
ここらでパウロの名誉を回復させるためにも、彼の凄いところを話しておこう。
俺はこの欠点だらけ、人としてどう見てもクズなパウロを、認めている。
なぜか。強いからだ。
まず、パウロの剣術の階級。
剣神流・上級
水神流・上級
北神流・上級
と、三つとも上級である。
この上級というのは、才能ある者が一つの流派に打ち込んで十年ぐらいかかると言われている。
上級は、剣道で言うところの、四段か五段ぐらいに相当すると思う。中級が初段から三段ぐらいであり、一般的な騎士なら中級で一人前、と言われている。聖級となると高段位と呼ばれる六段以上の腕前が必要となってくるが、これは置いておこう。
つまり、パウロは剣道・柔道・空手でそれぞれ四段の腕前を持っている。
それも、全部途中で投げ出して、である。
ロクな大人じゃないと思うが、強さに関しては折り紙つきだ。しかも、まだ二十代中盤だというのに、恐ろしく実戦経験が豊富だ。
経験に基づいた言葉は、実に狡猾で実践的。
感覚的なので半分も理解できていないが、しかしもっともなことを言っているのだとわかる。
俺は二年間パウロから剣術を習っているが、未だ初級の域を出ない。あと数年経って体力がついてくればわからないが、現状ではどれだけ脳内でイメトレしても、パウロに勝てるビジョンが浮かばない。魔術を駆使し、策を弄しても、まるで勝てる気がしない。
パウロが魔物と戦うところを見たことがある。
正確には、見せられた。魔物が出たという知らせを受けた時、「戦いを見るのも経験になる」と、ムリヤリ連れ出されて、遠くから見物させられた。
はっきり言おう。
ムチャクチャカッコよかった。
相手にした魔物は四匹。
訓練されたドーベルマン並みに動く犬のような魔物《アサルトドッグ》が三匹。
二足歩行で腕が四本あるイノシシの魔物《ターミネートボア》が一匹。
イノシシが犬を引き連れるように、森の奥から現れた。
パウロはそいつら軽くあしらって、一発で首を切り落とした。
もう一度言おう、ムチャクチャカッコ良かった。
なんというか、戦い方に華があるのだ。ハラハラドキドキというか、不思議なリズム感があって、見ていて心地良い。
言葉ではうまく表現できない。あえて単語を挙げるとするなら、カリスマだ。
パウロの戦い方にはカリスマがある。男衆に絶大な信頼を受け、ゼニスが惚れてリーリャが体を許し、エトの奥さんが熱を上げるのも納得できるぐらいだ。
村で抱かれたい男ナンバーワンなのだ。
いや、抱かれたいとかそういうのはさて置いて。
俺は、彼の存在をありがたく思う。自分より強い存在が身近にいることを。
もし、パウロの存在がなければ、俺はこの世界で簡単に増長してしまっていたことだろう。
ちょっと魔術がうまいからといって魔物に戦いを挑んだりして、アサルトドッグを捉えきれず、無残に噛み殺されただろう。
あるいは、魔物ではなく、人。
増長した挙句、勝てない相手に喧嘩を売ってしまう。
ありがちな話だ。
外道だと思って成敗しようと思ったら、返り討ちにあうとかは。
この世界の剣士は規格外に強い。
本気を出せば最高時速五〇㎞ぐらいで走れて、動体視力や反射神経だって半端ない。
治癒魔術のお陰で簡単には死なないから、一撃で殺しに来る。
魔物というものが存在する世界では、人はかくも強くなければいけないのかと思うほどに強い。
しかも、そんなパウロですら、まだ上級なのだ。剣士という枠組みだけでも、まだまだ上がいるのだ。この世界で有名とされる人々や魔物の中には、パウロが束になっても勝てない相手が多数存在しているのだ。
上には上がいる。
パウロはそんな当たり前のことを教えてくれたありがたい存在である。
もっとも、どれだけいいところがあろうとも、家ではただのダメなパパだ。
オリンピック金メダリストだって法を犯せば犯罪者なのと一緒で。
★ ★ ★
ある日、俺はいつもどおりパウロから剣術の稽古を受けていた。
パウロには今日も勝てない。きっと明日も勝てないだろう。
最近、上達している実感が湧かない。けれども、やらなければ上達はしない。
実感が湧かずとも、己の血肉にはなっているはずなのだ。
多分。
そうだよね? なってるよね?
などと考えていると、ふと、パウロが思いついたように声を上げた。
「そうだルディ。お前学校って……」
言いかけて、やめた。
「……必要ないか。なんでもない、再開」
何事もなかったかのように木剣を構えようとするパウロ。
俺は聞き逃さない。
「なんですか、学校って……?」
「学校というのは、フィットア領の都市ロアにある教育機関だ。読み書き、算術、歴史、礼儀作法なんかを教えてくれる」
「聞いたことはあります」
「普通、お前ぐらいの歳になると通い始めるもんだが……。必要ないだろ? お前、読み書きも算術もできたよな?」
「ええ、まあ」
算術はロキシーに教えてもらった、ということにしている。
娘が二人生まれたことで財政的にやや難しくなり、帳簿とにらめっこしているゼニスを手伝ったところ、大層驚かれたのだ。また天才だなんだと騒ぎ出しそうだったので、咄嗟にロキシーの名前を出した。
結果として、ロキシーの評価が上がったので、よしとする。
「しかし学校には興味はあります。同じぐらいの年代の子が集まるんでしょう? 友達ができるかもしれません」
と、いうとパウロはペッと唾を吐いた。
「そんな良い所じゃないぞ? 礼儀作法とか堅っ苦しいだけで役に立たないし、歴史なんて知ってても意味ないし、それにお前絶対イジメられる。近所の貴族のクソガキ共が集まってくるんだが、自分が一番じゃねえと気に食わないのばっかりだ。お前みたいのがいると徒党組んでイジメてくるだろうな。なんたら侯爵を父に持つ私よりもどうちゃらで身分の低いお前は生意気だーっとな」
実体験っぽい話だ。
パウロは厳しい父親と貴族の汚さに嫌気がさして家を飛び出したという話だ。
その礼儀作法や歴史とやらも、アスラ貴族の見栄がこびりついた、非常に見苦しいものなのだろう。
パウロと息の合う俺としても、きっと息苦しいに違いない。
「そうなんですか。貴族のお嬢様に可愛い子がいるかと思ったのですが」
「やめとけやめとけ。貴族の娘ってのはな、ゴッテゴテに化粧して、ガッチガチに髪型キメて、甘ったるい匂いプンプンさせてて、いざベッドで脱がしてみると、運動なんて全くしてないから、コレまただらしない身体してるんだぞ。ま、中には剣術とかを嗜んでいて、結構いい身体してる子もいるけどな、大体はコルセットで誤魔化してるから脱がしてみるまでわからないんだ。父さんも何度か騙されたもんだ……」
遠い目をして言うパウロの言葉には妙な信憑性があった。
言ってる内容はクズ同然だが、そういう経験を経て、ゼニスという良妻を得たのだと思えば、含蓄のある言葉かもしれない。
「じゃあ、学校に行くのはやめておきましょう」
シルフィにもまだ教えたいことがある。
大体、イジメられるとわかっているのに行くなんて正気の沙汰じゃない。
伊達にイジメられたせいで二十年近く引きこもってねえぞ。
「そうだな。学校に行くぐらいなら、冒険者にでもなって迷宮にでも潜ったほうがいい」
「冒険者ですか……?」
「そうだ。迷宮はいいぞ。化粧をする女なんていないから、綺麗かどうかが一目でわかる。剣士も戦士も魔術師も、みんな引き締まったいい身体をしているしな」
クズの発言は置いておくとして。
本によると、迷宮というものは、一種の魔物であるらしい。
元はただの洞窟だったものが、魔力が溜まることで変異していき、迷宮へと変貌を遂げる。
迷宮の最深部には力の源とも言える魔力結晶があり、それを守るための守護者がいる。
魔力結晶は餌でもあり、強力な誘引力を発している。
魔物はそれに吸い寄せられて迷宮に入り込み、罠に掛かったり、餓死したり、魔力結晶を守る守護者にやられたりして死ぬ。
迷宮は死んだ魔物の魔力を吸収する。
もっとも、できたばかりの迷宮は逆に魔物に魔力結晶を食われてしまったり、たまに崩落して潰れてしまうのだとか。
そういうマヌケな部分を聞くと生物っぽい。
また、魔力結晶に吸い寄せられるのは、魔物だけではない。
人間もワラワラと寄ってくる。
魔力結晶は魔術の触媒として使われるため、大変高値で取引されるからだ。大きさにもよるが、小さくても一年以上は遊んで暮らせる金額になる。魔物にとっての財宝は魔力結晶だけだが、人間にとっての財宝はそれだけではない。
迷宮は時間が経つと、それまで食ってきた魔物や冒険者の装備に、何年も掛けて魔力を注ぎ込む。
そうすることで、新たな餌を作る。
それが魔力付与品だ。
魔力付与品は魔道具と違い、使用者が魔力を用いなくても使える魔法の道具だそうだ。ただ、魔力付与品は、大抵はろくな能力がついていない。
ゴミ能力が大半だそうだ。
だが、中にはたまに神級の人らも真っ青なチート能力がついているものがあるらしい。
そうしたものは、売れば大金になるということで、一攫千金を夢見た人々は迷宮へと潜る。
大概は、途中で力尽きて倒れてしまい、迷宮は魔力を得て深く広くなっていく。
そして、長いこと存在している迷宮の奥地に、莫大な量の財宝が眠ることとなる。
確認されている中で最も古く深いのは、中央大陸の赤竜山脈が霊峰、龍鳴山の麓にある『龍神孔』だ。文献によると一万年前からあるらしい。推定される最下層は二五〇〇階。その迷宮は龍鳴山の頂上にある孔ともつながっているらしく、頂上から孔に向かって飛び降りれば、一瞬で最下層近くまで行けるらしいが、その方法で降りて上がってこられた者はいない。
ちなみにその頂上の孔は噴火口ではない。
『龍神孔』が赤竜を捕らえて捕食するために開けたものだ。
上を竜が通過すると吸い込むらしい。
真偽の程は定かではないが、一万年も生きた魔物なら、それぐらいしてもおかしくはない。
ちなみに最も難易度が高いと言われている迷宮は、天大陸にある『地獄』と、リングス海の中央にある『魔神窟』だ。両方とも、入り口にたどり着くことすら困難で、満足に補給もできない場所にある。深い上、腰を落ち着けて探索することができないので最高難易度、というわけだ。
以上が、俺の迷宮に関する知識である。
「迷宮の話は、本で読みました」
「『三剣士と迷宮』か。あんな風に伝説の迷宮を探索できたら歴史に名を残せるぞ。頑張ってみたらどうだ?」
──『三剣士と迷宮』。
後に剣神・水神・北神と呼ばれるようになる若い天才剣士たちが出会い、紆余曲折の末に三人で巨大迷宮に挑み、喧嘩あり笑いあり友情あり別れありの展開で、見事に踏破する話だ。
そこで潜った迷宮だって、せいぜい地下一〇〇階だ。
「あれって、作り話なんじゃないんですか?」
「そんなことないぞ。現に各流派に代々伝わる剣は、その迷宮で手に入れたものだって話だ」
「へえ。でも、神級になれるほどの人が苦労してるのに、僕が頑張ったところでたかが知れてますよ」
「父さんだって潜れたんだ。ルディにだってできるさ」
パウロは、それから、鬼族の青年が海魚族の巣窟となっている迷宮に人間の剣士たちと一緒に入り、仲間を失いながらも海魚族を倒す話だとか、落ちこぼれと呼ばれていた魔法使いが偶然迷宮に落ちてしまったところ、ちょうど魔法使いを失ったばかりのパーティに拾われて、その潜在能力を覚醒させながらも強くなっていく話だとか、そういう話をざっと聞かせてくれた。
話す機会を待っていたかのような話し方だった。
そういえば、パウロは俺を剣士にしたかったと言っていた。
大方、そういう話を聞かせたり、『三剣士と迷宮』を読み聞かせたりして、迷宮・冒険者・剣士といったキーワードに憧れさせる算段だったのだろう。
迷宮。興味はある。
面白そうだとも思うが、危険すぎるとも思う。
なんせ、あの本に書いてある登場人物は、唐突に死ぬのだ。
『三剣士と迷宮』には、三剣士以外の登場人物も出てくる。
が、三剣士以外は全滅する。
会話をしてる最中に真横から飛んできた火球に当たって黒焦げになったり。いきなり落とし穴に落ちてグチャグチャになったり。ちょっと頭を上げた瞬間、真っ二つになったりして、魔物との戦いで傷一つ負う要素のない奴らが、ちょっと気が抜いた瞬間に罠にかかって全滅するのだ。
三剣士は主人公らしく華麗に罠を切り抜けるが、うっかり屋の俺が罠を全部避けられるとは思えない。鈍感系だしな。
「どうだ? 冒険者も面白そうだろう?」
「冗談じゃありませんよ」
なんでわざわざスリルを求めてハイリスクなことをしなきゃならんのだ。
できれば将来はパウロのように女の子に囲まれてまったりと暮らすのだ。
「僕は女の子の尻を追いかけているほうが性に合っていますよ」
「おお、さすが俺の息子だ」
「父様みたく、何人も囲うのが理想ですね」
「そうかそうか。けど、追いかける尻はひとつにしておいたほうがいいぞ」
ちょいちょいと後ろを指さされて振り返ると、むくれたシルフィがいた。
間が悪い。
★ ★ ★
最近は俺の部屋でシルフィに勉強を教えることが多くなった。
無詠唱の細かい理論を説明するのに、数学や理科の基礎的なことを教えておいたほうが手っ取り早いからだ。
もっとも、俺は中学時代では落ちこぼれ。なんとか入ったバカ高校もあっさり中退している。
なので、俺が教えられることなんてたかが知れている。
学校での勉強が全てというわけではないが、もっと勉強しておけば、と悔しく思う。
シルフィは簡単な読み書きと、二桁の掛け算までできるようになった。九九を教えるのにちょっと難儀したが、頭の悪い子ではない。すぐに割り算も覚えるだろう。
さらに魔術と並行して、理科も教えていく。
「どうして水を温めると水蒸……気? になるの?」
「えっとね、空気は水を溶かすんだ。でも、溶かすためには温度が必要になる。だから、温かくなればなるほど、溶けやすくなるんだ」
今は蒸発、凝固、昇華とそのプロセスについて教えている。
「…………?」
よくわかっていない、という顔をしている。
とはいえ素直な子だからか、吸収が早い。
「ま、まあ、どんなものでも熱すれば溶ける、冷やせば固まるって考えておけばいいよ」
教師ではないのでこんなもんだ。
シルフィは俺より賢い。自分で色々試して納得してくれるだろう。魔術を使えば、実験道具には事欠かないわけだしな。
「石とかも溶けるの?」
「すっごく高い温度が必要だけどね」
「ルディは溶かせる?」
「もちろんさ」
とは言ったものの、試したことはない。
最近は頑張れば大気成分を大雑把に選り分けることもできるようになってきた。それを利用して、酸素と水素をガンガン投入すれば石ぐらいはいけるだろう。それをすると自分も火傷しそうになるのでやりたくないが。
ちなみに、『溶岩』という溶岩を発生させる上級魔術もある。
どう見ても土と火の合成魔術なのだが、火系統の上級に位置している。一口に系統といったところで、全てのものは関係しあっている。火力を上げるにはより魔力を込めればいいが、可燃性の気体を利用すれば、より効率よく高い火力を実現させることができる。
そこまではわかっている。
けれど、そこまでだ。
俺の魔術の腕前は、ロキシーと別れた頃と比べても、大差がない。
既存の魔術を組み合わせたり、使い方を応用したり、理科の知識を使って単純に威力を上げたり。
一見すると、それなりにレベルアップしたようにも見えるだろう。
けど、俺は行き詰まりを感じている。俺の知識では、これ以上難しいことはできないのかもしれない。生前では困ったらネットで調べていたが、この世界にそんな便利なものはない。
誰かに習うか……。
「学校か……」
魔術学校というものもあるらしい。ロキシーは魔術学校の格式はどうのと言っていたが、俺でも入れるのだろうか。
「ルディ、学校に行くの?」
ふと呟くと、シルフィが不安げな表情で覗きこむようにこちらを見ていた。
彼女が小首をかしげると、緑の髪がふわりと揺れた。
俺が一ヶ月に一回ぐらいの割合で「髪伸ばしたほうがいいんじゃないかなぁ」と、チラチラ言っていた甲斐があってか、最近シルフィはちょっとだけ髪を伸ばし始めた。
現在の長さはショートボブになった程度だが、ちょっと癖のあるエメラルドグリーンの髪はちょっとした動作でふわりと揺れる。
いい感じだ。
ポニーテールまであと少し。
「行くつもりはないよ。父様も学校に行ってもイジメられるだけで、何も学べないって言ってたし」
「でもルディ、このごろ、また変だよ」
マジで?
変という自覚がない。何かやらかしただろうか。
シルフィの前では細心の注意を払って鈍感を演じているつもりだが。
「俺は生まれた時から変だったらしいよ」
探りを入れるつもりで聞いてみると、シルフィは眉根を寄せて首を振る。
「そうじゃなくて、なんか、元気ない……」
ああ、そういう意味か。
焦った。また何かボロを出したかと思った。
心配されてたのね。
「最近、行き詰まってるからね。魔術も剣術もちっとも上達しない」
「でも……ルディは凄いよ?」
「この年齢にしては、そうかもね」
確かに、この世界、この年齢にしては、凄いかもしれない。
けれど、まだ俺は何もやってない。魔術だって、生前の記憶と、最初に無詠唱というものに気づいたおかげで、ちょっと他人よりうまく使えるだけだ。
でも、生前の記憶のレベルが低いから、行き詰まって先に進めないでいる。勉強しておけば、と何度悔やんだところで、今更習い直すことはできない。それに前の世界での常識が、この世界でも通用するとは限らない。この世界には、俺の知らない法則がまだまだあるかもしれない。いつまでも、生前の記憶に頼っていてはダメだろう。
魔術はこの世界の理論。
なら、この世界のことを知らなくては。
「そろそろ、何か次のステップに進まないといけない、と思ってさ」
シルフィはどんどん魔術が上達し、賢くなっている。
そんな彼女を見ていると、焦りも生まれる。俺だけ足踏みしているのは情けない。
今は上から目線で鈍感系主人公などと言っているが、成長がなければ、シルフィに見限られるかもしれない。
「どこか行っちゃうの?」
シルフィは眉を顰めつつ、聞いてきた。
「そうだな。父様には冒険者になって迷宮にでも入ったほうがいいって言われたし、この村でできることも少ないのかもしれないな……。学校に行くか、冒険者か、どっちになろうかな」
軽い気持ちで言った。
「や……やだぁ!」
シルフィが唐突に叫び、抱きつかれた。
あふん。なになになんなの?
愛の告白?
と思ったら、シルフィは小刻みにふるえていた。
「し、シルフィエットさん?」
「い、や、いや……いや!!」
シルフィは、苦しいほどの力で俺を抱きしめてきた。
戸惑い、沈黙した俺に、シルフィは何を感じたのか……。
「い、いか、行かないで……うぇ、う、えぇぇ~ん」
泣いてしまった。
小さな肩を大きく震わせつつ、俺の胸に顔を押し付けるように抱きついてくる。
……なんだ、なんでだ。何これ、どういうこと?
とりあえずシルフィの頭をなでなで、背中をさすりさすり。
ついでにお尻をちょこっと……いやいやパウロじゃないんだから。
尻は自制。
背中をギュっと抱きしめて、身体の全面でシルフィの感触を味わう。
温かくて柔らかい。髪に顔を埋めると、いい匂いがする。
ああ、いいなぁ、コレ。いいなぁ……欲しいなぁ……。
「ひっく、やだよぉ、どこにも、いかないでよぉ……」
っと、我に返る。
「あ、ああ……」
そうか。そうだな。
最近、シルフィは午前中からウチに来ることも多くなった。
午前中に来て、嬉しそうな顔で俺の剣術の稽古を見て、二人で魔術の練習をしたり、勉強をする。
そんな生活を送ってきた。
俺がある日いなくなったら、シルフィはまた一人ぼっちになる。魔術でワルガキを退治できたとしても、友達ができるわけじゃない。
そう思うと同時に、俺の中で急速に愛おしさが大きくなった。
俺だけが、彼女に好かれている。
これは俺だけのものだ。
「わかったわかった。どこにも行かないよ」
こんな子をほっぽり出して、どこに行こうというのかね?
魔術の上達?
いいじゃねえか、もう聖級も上級も使えるんだから。いざとなれば、ロキシーみたいに家庭教師でもすればいい。一人立ちする年齢になるまでは、シルフィと二人でいよう。
そうしよう。
二人で一緒に育って、ちょっとずつ俺好みの女に育ててやろう。
光源氏計画だぁ。
ぐへへへへ。
…………ハッ!
いやいや!! 落ち着け落ち着け。
鈍感系になるって決めただろうが。
なーにをその気になってるんだ……。
いや、でも。
別に、鈍感だからって、幼馴染を育てちゃいけないって理由には、ならない……よね?
待て! 何を言ってるんだ!!
しかし……ぐぬぅ。俺は一体いつまで、この子の気持ちに気づかないでいればいいんだ。
この子はまだ六歳。
俺に懐いてくれてはいる。好意も感じる。
けど、本当の意味での恋愛感情ではないはずだ。
なら、お、お預けだ。
でも、一体いつまで預けておけばいい?
十歳か、十五歳か……もっと先か……?
その結果、シルフィに嫌われたらどうする?
今は好感度マックスだが、今後落ちていかないとは限らない。
その時、俺は耐えられるのか……?
俺には…………無理だ!!
人間、できることとできないことがある!!
だって、こんな柔らかくて。温かくて。ふわふわして。ほんわりしていい匂いがするんだ。
こんなのが自分の思いを必死にぶつけてくれているのに、俺は気づかない振りをするつもりなのか!!
おかしいだろ。そんなの。
互いに自覚してるなら、次に行くべきだろう。
俺だけが我慢して立ち止まるんじゃなくて、一緒に進んでいくべきだろう!!
間違った努力をして時間を浪費するつもりか?
間違ってるとわかっているのに、直さないつもりか?
決めたぞ!!
俺はシルフィを俺好みの女に育てる!!
お、俺は鈍感系をやめるぞ!! シルフィ──ッ!!
「おいルディ……お前に手紙が来てるぞ」
パウロが入ってきたので、俺は自分の『世界』から帰ってきた。
パッとシルフィを離す。
危ないところだった。あやうく小物臭の漂うラスボスになるところだった。
パウロに感謝しよう。
しかし、本心を我慢するのには、限界もある。
今回は耐えられたが、次は耐えられるか……。
★ ★ ★
手紙はロキシーからのものだった。
『ルーデウスへ。
いかがお過ごしでしょうか。
早いもので、あなたと別れてから二年が経ちました。
少し腰を落ち着けることができたので手紙を書いています。
わたしは現在、シーローン王国の王都に滞在しています。冒険者として迷宮に潜っていたらいつの間にか名前が売れてしまったらしく、王子様の家庭教師として雇われました。
王子様に勉強を教えているとグレイラット家での日々を思い出します。
王子様はルーデウスによく似ています。ルーデウスほどではありませんが、魔術の才能は抜群だし、頭もいいです。また、わたしの着替えを覗いてくるところや、パンツを盗んだりするところもそっくりです。ルーデウスと違い、元気一杯で尊大ですが、行動は本当によく似ています。
英雄は色を好むというのでしょうか。
雇用期間中に押し倒されないか心配です。
こんな貧相な身体のどこがいいんでしょうね……。
っと、こんなことを書いてるのが見つかると不敬罪になるでしょうか……?
その時はその時ですね。悪口のつもりではないので言い逃れられるでしょう。
期間限定なのですが、王宮はわたしを宮廷魔術師に任命するつもりのようです。
わたしはまだまだ魔術の研究を行っていきたいと考えており、好都合です。
そうそう、ようやくわたしにも水王級の魔術が使えるようになりました。
シーローン王国の書庫に、水王級の魔術に関する書籍があったのです。
聖級を使えるようになった時にはコレ以上は無理だと思っていたのですが、頑張ればできるものですね。
ルーデウスは水帝級ぐらい使えるようになっているでしょうか。それとも、他の系統を聖級まで使えるようになってたりするのでしょうか。熱心なあなたのことだから、治癒魔術や召喚魔術にも手を出しているのかもしれませんね。
それとも、剣の道を歩き始めたのでしょうか。
それはそれで残念ですが、ルーデウスならそっちの道でもうまくやるんでしょう。
わたしは水神級の魔術師を目指します。
前にも言いましたが、魔術のことで行き詰まったのなら、ラノア魔法大学の門を叩いてください。
紹介状が無い場合は入学試験がありますが、ルーデウスなら楽勝でしょう。
それでは、また。
ロキシーより。
追伸 もしかすると手紙が返ってくる頃に、わたしは王宮にいないかもしれないので、返信は結構です』
現状に釘を刺すような内容だった。
俺はくそうと思いつつ、シーローンとやらを地図で見てみる。
中央大陸・南部の東の方にある小国だった。
直線距離ではそれほど離れていない。だが、この中央大陸の山脈には赤竜が住み着いていて通行できないので、山を迂回して南の方から大回りしなければたどり着けない。
遠い国だ。
そして、魔法大学のあるラノアは北西へと大回りしなければたどり着けない。
「ふむ……」
ロキシーは王級以上の魔術については一切教えてくれなかったが……。
そうか、知らなかったのか。
手紙は当たり障りのない内容で返信しておくことにする。
情けない現状を、ロキシーに知られたくなかった。
彼女の中で俺がどんな凄い人物になっているのかわからないが、落胆だけはされたくない。
それにしても、魔法大学か。
ロキシーは以前にもあそこは素晴らしい、と言っていた。
しかし、遠い。
シルフィを置いてはいけない。
どうするか……。
とりあえず、俺は手紙の最後に、
『追伸 パンツを盗んでごめんなさい』
と書き加えておいた。
★ ★ ★
手紙が来た日の翌日、家族が揃った時に、俺は切り出した。
「父様。一つワガママを言ってもいいですか?」
「ダメだ」
一蹴された。
と思ったら、隣に座っていたゼニスがパウロの頭をパシンと叩いた。逆隣に座るリーリャも追撃を入れた。
件の妊娠騒動から、リーリャも一緒の食卓に座るようになった。それまでは、メイドっぽく食事中は給仕に徹していたのだが、家族として認められたということだろう。
この国は一夫多妻でも大丈夫なのだろうか。
まあいいか。
「ルディ。なんでも言いなさい。お父さんがなんとかしてくれるわ」
頭を押さえるパウロを尻目に、ゼニスが優しそうな声を上げる。
「ルーデウス坊ちゃまは今までワガママらしいことを言ってはきませんでした。ここは旦那様の威厳と甲斐性が試される瞬間だと思います」
リーリャも援護をくれた。
パウロは椅子に座り直すと、腕を組み、顎をクイっと傾けて、偉そうなポーズを作った。
「ルディが前置きを置いてまでワガママを言うんだ、とても俺の手には負えないような凄いことに違いない」
もう一度二連撃を食らい、パウロはテーブルに突っ伏した。
いつもの他愛ない家族の冗談だ。
では、切り出そう。
「実は、最近魔術の習得が行き詰まっていまして。そのためにラノアの魔法大学に入学したいのですが……」
「……ほう」
「シルフィにそんな話を匂わせたら、離れたくないと泣かれました」
「ほう、この色男め、誰に似たんだ? えぇ?」
パウロが三度目の二連撃をくらう。
「せっかくなので一緒に通いたいのですが、彼女の家は我が家ほど裕福ではありません。つきましては二人分の学費を払っていただければ、とお願いします」
「ほう……」
パウロがテーブルに肘を付いて、どこぞの司令のような鋭い眼光で俺を睨んだ。
この目は、剣を持っている時の目だ。
パウロの中で唯一尊敬できる瞬間の時の目だ。
「ダメだ」
パウロは先ほどと同じ言葉を吐いた。
今度は真剣だ。
ゼニスもリーリャも黙っている。
「理由は三つある。
一つ目は、剣術が途中だ。今投げ出せば、二度と剣が習えないレベルで中途半端になる。お前の剣術の師匠として、ここで放り出すわけにはいかない。
二つ目は、金の問題だ。お前だけならなんとかなるが、シルフィも一緒となると無理だ。魔法大学の学費は安くないし、ウチも金が湯水のようにあるわけではない。
三つ目は、年齢の問題だ。お前たちはまだ七歳だ。お前は賢い子だが、まだ知らないことも多い。経験も圧倒的に足りていない。親としての責任を放棄して放り出すわけにはいかない」
やっぱ無理か。
が、俺は諦めない。
パウロも昔と違い、きちんと頭を使って理由を言ってくれている。つまり、三つの条件をクリアすればオッケーということだ。焦らなくてもいい。俺だって、今すぐに、というわけではないのだ。
「わかりました父様。では、剣術の稽古は今までどおりつけていただくとして、年齢の方は何歳ぐらいまで我慢すればいいでしょうか」
「そうだな……十五、いや、十二歳まではウチにいろ」
十二歳か。
確か、この国の成人は十五歳だったか。
「なぜ十二歳なのかを聞いても?」
「俺が家を飛び出したのが十二だからだ」
「なるほど、わかりました」
十二歳というのは、パウロにとって譲れないところなのだろう。
男のプライドを刺激しないためにも、俺は黙って頷いておく。
「では最後に」
「おう」
「仕事を斡旋してください。読み書き算術はできるので家庭教師か、魔術師としてのものでもいいです。なるべく給金の高いものがいいです」
「仕事? なぜだ?」
パウロは真剣な目のまま、恫喝するように聞いてくる。
「シルフィの分の学費を僕が稼ぎます」
「……それはシルフィのためにはならないぞ」
「はい。でも、僕のためにはなるかと」
「……」
沈黙が流れた。
俺にとっては心地よくない空気だ。
「そうか……なるほどな……」
パウロは何かを納得したように、うんと頷いた。
「わかった。そういうことなら心当たりを当ってみよう」
ゼニスとリーリャの不安そうな顔とは裏腹に、パウロは信頼できる時の顔で、そう言った。
「ありがとうございます」
俺が礼を言って頭を下げると、夕食が再開された。
★ パウロ視点 ★
まさか、ルーデウスがあんなことを言い出すとは思っていなかった。
ウチの息子は成長が早い。
とはいえ、普通はああいうことを言い出すのは早くても十四、五を超えてからだ。
自分だって十一歳で、剣神流上級になった頃からだ。
言い出さないヤツは一生言い出さない。
「あまり生き急ぐと、早死にしちまうぜ……か……」
昔、オレにそんなことを言った戦士がいた。
当時、オレはそんな言葉を聞いて鼻で笑ったものだ。
周囲の奴らの生き方はゆっくりすぎる。人族が力のある時期は短いというのに、誰も走ろうとしていない。できる時にできる事を全部やる。やったことを咎められたら、その時は、後は野となれ山となれ、なんて思っていた。
まぁ、できる事をしたら結果としてデキてしまったので、生活を安定させるため、冒険者を引退し、貴族時代の親戚のツテを頼って騎士になったのだが。
それは置いておこう。
ルーデウスの生き方は、オレのよりもずっと早い。
見てて心配になるほどだ。
きっと、若い頃のオレを見てきた奴らも、そう思ったんだろう。
だが、無鉄砲で行き当たりばったりだったオレと違って、ルーデウスはきちんと計画的に物事を考えている。
このあたりはゼニスの血か。
「けど、ま、もう少し父親に縛られてもらうか」
そう思い、手紙を書く。
先日、ロールズにも相談されたのだが、シルフィはルーデウスにべったりだ。
シルフィから見れば、ルーデウスは地獄のような幼少時代を助けてくれた白馬の王子様だ。なんでも教えてくれるから兄のように慕っているし、最近では男女としても意識するようになったようだ。ロールズも、将来ルーデウスがもらってくれるのであれば、それに越したことはない、などと言っていた。
オレも、その時はあんな可愛い子が娘になるならそれもいいかと思ったが、今日のルーデウスの話を聞いて考えを改めた。
今の状況は洗脳に近い。
このまま成長すれば、シルフィはルーデウスなしでは何もできない大人になってしまう。
そういう奴は、貴族時代に何人も見てきた。
親に依存しすぎた木偶人形のような奴らだ。
それでも、依存対象がいる時はいい。
木偶でも操れば、面白い人形劇ができる。ルーデウスがシルフィを愛する限り、シルフィも大丈夫だ。
が、ルーデウスはオレの血を色濃く受け継いでいる。
女好きの血だ。
フラッと別の女になびいてしまう可能性もあるだろう。いや、オレの血を引いているのだ、間違いなくフラフラするだろう。
結果として、シルフィを選ばないかもしれない。
その時、残されたシルフィは立ち直れない。糸の切れた木偶人形は、決して立ち上がれない。
ウチの息子のせいで、あんな可愛い子の人生が潰される。
許せることではない。息子のためにもよくない。
手紙が書けた。
色よい返事が返ってくることを祈ろう。
しかし、さて。
あの口のうまい息子をどうやって説き伏せたものか……。
いっそ、力ずくでいくか。
第十一話 「離別」
バイトをしたいとパウロに言って一ヶ月が経過した。
本日、パウロの元に手紙が届いた。
そろそろ返事が来たのだろうと、心の準備をして待っていた。
剣術の稽古の後か、昼飯、いや夕飯時かもしれない。
そう思って、いつも通り剣術の稽古を真面目に受けていた。
★ ★ ★
話は剣術の稽古の最中だった。
「なあ、ルディよ」
「はい、なんでしょう父様」
できる限り、キリッとした顔を心がけ、パウロの言葉に耳を傾ける。
なにせ、生前も含めて初めての仕事だ。
頑張るぞ。
「お前……さ。シルフィと別れろって言われたら、どう思う?」
と、パウロは変なことを聞いてきた。
「は? 嫌に決まってるじゃないですか」
「だよなあ」
「なんなんですか?」
「いや、なんでもない。話をしたって、どうせ言いくるめられるだけだしな」
その言葉を言った瞬間。
パウロが豹変した。
素人の俺でもわかるほどに殺気をむき出しにした。
「えっ!?」
「……!!」
無言の圧力と共に、パウロが踏み込んだ。
死。
そんな単語が脳裏によぎった。
俺は反射的に魔力を全開にしてパウロを迎え撃つ。
風と火の魔術を同時に使い、パウロとの間に爆風を発生させる。
自ら後ろに飛び、熱に押し出されるように大きく後ろへ移動する。
今まで、何度もシミュレートした。
パウロ相手には、一度距離を取らなければ勝ち目はない。
爆風は自分にもダメージがあるが、怯ませることができれば距離が稼げる。
パウロは爆風など無いかのように前傾姿勢でなおも突っ込んできた。
(やはり効果がない!!)
想定していたこととはいえ、焦る。
次の回避行動を!
後ろじゃダメだ。踏み込みの方が速い。
反射的にそう考え、自分の真横に、叩きつけるような衝撃波を発生させた。
ぶん殴られるような衝撃と共に、俺の身体が横方向に吹っ飛ぶ。
背筋の凍るような風切り音が耳を掠めた。
ちょうど俺の首があったであろう場所に、パウロの剣が振られるのが目に入る。
よし。
一撃目を避けた。これは大きい。まだ近いが、距離も取ることができた。
俺の勝ちが見えた。
俺は今まさにこちらに向かって踏み込もうとしたヤツの足元を陥没させる。
パウロが落とし穴を踏み抜いた。
と思った瞬間、一瞬で体重を逆足に乗せ替え、ほぼタイムラグ無しで踏み込んだ。
(両足を止めないとだめなのかよ!?)
俺は足元に泥沼を作り出す。
沈み込む前に足裏から水流を出し、滑るように後退する。
(しまった、遅い……!)
と、思った時にはもう遅い。
パウロは沼の端で、地面を踏み固めるような一歩。
踏み込みで地面が凹んだ。
たった一歩で俺に肉薄した。
「う、うああああ!!」
慌てて剣で迎撃する。
型も何もない、無様な一撃だった。
力任せに振るった俺の手に、ぬるりと嫌な感覚が伝わった。
(水神流の技で受け流された……)
それだけはわかった。
水神流の技で流されたということはカウンターがくる。
知っていたが、対処はできない。
スローモーションのように、パウロの剣が俺の首筋に吸い込まれる。
(ああ、木剣でよかった……)
首筋に衝撃を覚え、意識が暗い闇へと落ちていった。
★ ★ ★
目が覚めると、小さな箱の中にいた。
ガタガタと大きく揺れる感覚から、ここが乗り物の中であることを感じ取る。
身体を起こそうと思ったら、指先ひとつ動かなかった。見下ろしてみると、縄でぐるぐる巻きにされていた。
いわゆる簀巻きだ。
(どうなってんだ……?)
首を巡らせてみると、ねーちゃんが一人座っていた。
チョコレート色の肌、露出度の高いレザーの服、ムキムキの筋肉、全身に傷。
眼帯をつけていて姉御って感じのするキリッとした顔立ち。
まさにファンタジーの女戦士という感じのねーちゃんだ。
あと、獣っぽい耳と、虎っぽい尻尾があって、ちょっと毛深い。
獣族ってやつだろうか。
俺が見ていることに気づいたのか、目が合った。
「初めましてルーデウス・グレイラットと申します。こんな格好で失礼します」
先に名乗ることにする。会話の基本は先に喋ること。
先手を取れば主導権を握れる。
「パウロの息子にしては礼儀正しいのだな」
「母様の息子でもありますから」
「そうか。ゼニスの息子だったな」
両親の知り合いらしく、ちょっとだけホッとする。
「ギレーヌだ。明日からよろしく頼む」
明日から?
何言ってるんだろうか。
「それは、どうも、よろしくお願いします」
「ああ」
俺はとりあえず、火の魔術を使って縄を焼き切った。
身体が痛い。変なところで寝ていたせいか。
ぐっと伸びをする。
解放感。
狭い部屋で指先だけを動かすのには慣れているが、ドSっぽいおねーさんの前で縛られていると変な気分になるからな。
周囲を見ると、現在の場所は、まさに小さな箱だ。
前後には腰掛ける場所が付いており、俺はギレーヌと向かい合わせに座っている。
左右には窓がついており、外の様子が見えた。外は見知らぬ草原だった。
予想どおり、乗り物だ。
揺れは大きく、長く乗っていると乗り物酔いになりそうだ。
進行方向からパカパカと音がする。馬だろうか。
だとすれば、馬車だ。
俺は、なぜか馬車にマッチョなねーちゃんと一緒に乗せられている。
……ハッ!!
も、もしかして、俺はこの筋肉ウーメンに攫われたのか!?
可愛すぎる俺を慰み者にしようってのか!?
やめろ、お、俺は確かに筋肉質な女も嫌いじゃないが、俺にはシルフィという心に決めた女性がいるんだ。
だからせめて、初めては優しくしてね……?
いやいやいや!!
おお、お、落ち着け。こういう時は落ち着くのだ。
素数を数えて落ち着くのだ……。
素数は一と自分の数でしか割ることのできない孤独な数字……わたしに勇気を与えてくれるって神父さんが言ってた。
三、五、えっと、十一? うんと、十三? えっと、えっと……。
わからん!!
素数なんてどうでもいいから落ち着こう。
冷静に、考えてみるのだ。なんでこんな状況になっているか。
はい、深呼吸。
「すぅ……はぁ……」
よし。
わかる範囲で、状況を整理していこう。
まず、パウロがいきなり襲いかかってきて、気絶させられた。
そして起きたら縛られていて、馬車の中にいた。
恐らく、何らかの理由で気絶させて、馬車の中に放り込んだのだろう。
馬車の中には、明日からよろしくとかいうマッチョウーメンが乗っていた。
パウロと言えば、そういえば襲いかかってくる前に妙なことを言っていた。
シルフィと別れろとか。シルフィはお前にはもったいないとか。シルフィはオレの物だとか。
あ、あのロリコン野郎……俺のシルフィにまで手を出すつもりか!?
いや、後半は言ってなかったか?
うーん?
シルフィのことを考えていたらよくわからなくなった。
くそっ、パウロのせいだ……!
まあ、聞いてみればいいか。
「あの」
「ギレーヌでいい」
「あ、じゃあ、僕のことはルディちゃんでいいですよ」
「わかった。ルディちゃん」
冗談が通じないタイプのようだ。
「ギレーヌさん。父様から何か聞いていませんか?」
「ギレーヌでいい。さんはいらん」
ギレーヌはそう言いながら、懐から一通の紙を取り出す。
そのまま俺に差し出す。受け取ってみるが、紙の表面には、何も書いていない。
「パウロからの手紙だ。読め。あたしは字が読めんから、口に出してな」
「はい」
俺は適当にたたまれた紙を開き、読み始める。
『我が愛する息子、ルーデウスへ。
この手紙を読んでいるということは、俺はもうこの世にはいないだろう』
「なんだと!!」
ギレーヌが驚愕の声を上げて立ち上がる。
この馬車、意外と天井高いな……。
「座ってくださいギレーヌ。まだ続きがあります」
「む、そうか」
そう言うと、ギレーヌはおとなしく座る。
続きを読む。
『──というのは、一度書いてみたかっただけで冗談だ。お前は、オレにボコボコにされて無様に這いつくばった挙句、縄でぐるぐる巻きにされて、囚われのお姫様のような情けない姿で馬車に放り込まれた。何が起こっているのかわからないと思うので、全てはそこの筋肉ダルマに聞け……と言いたいが、そいつは脳みそまで筋肉でできているので、ロクな説明ができないだろう』
「なんだと!!」
ギレーヌが怒声を上げて立ち上がる。
「座ってくださいギレーヌ。次の文で褒めてます」
「む、そうか」
そう言うと、ギレーヌはおとなしく座る。
続きを読む。
『そいつは剣王だ。
剣を習うなら、そいつ以上の適任は剣士の聖地にでも行かなければ見つからないだろう。腕前は父さんが保証する。父さんは一度も勝ったことがない……ベッドの上以外ではな』
いちいち余計なことを書くな、バカ親父。
けどギレーヌは満更でもない顔をしている。
ホントモテるのな、アイツ。
てか強いのな、ギレーヌさん。
『さて、お前の仕事だが、フィットア領で一番大きなロアという都市に住むお嬢様の家庭教師だ。算術、読み書き、あと簡単な魔術を教えてやってほしい。すっげーワガママなお嬢様で、学校から来ないでくれと頼まれたぐらい乱暴だ。今まで何人もの家庭教師を返り討ちにしている……が、お前ならなんとかできると信じている』
なんとかって、丸投げかよ……。
「ぎ、ギレーヌってワガママなんですか?」
「あたしはお嬢様じゃない」
「ですよねー」
続きを読む。
『そこにいる筋肉ダルマは、お嬢様の家に雇われている用心棒兼剣術の師範だ。お前に剣を教える代わりに、自分も算術や読み書きを習いたいとか言い出したらしい。脳みそも筋肉のくせに何を言ってるんだと、笑わないでやってくれ。こいつもきっと真剣なんだ(笑)』
「なんだとぉ……」
ギレーヌの額に青筋が浮かんだ。
この手紙は、俺に状況を説明すると同時に、ギレーヌを煽るためのものでもあるらしい。
どういう関係なんだ、二人は。
『物覚えは決してよくないだろうが、講師代が浮いたと思えば、悪い話じゃないだろう』
講師代。
そうか、俺はこの人に剣を習うのか。パウロは感覚派だからな。よりよい講師を用意したのか。
あるいは俺の上達しなさに落胆したのか。
最後まで面倒みろよな……。
「ギレーヌに剣術を習うと、普通はどれぐらいお金取られるんですか?」
「月にアスラ金貨二枚だ」
金貨二枚!!
ロキシーが俺の家庭教師を受け持つのに、月にアスラ銀貨五枚だったはずだ。
ざっと四倍か。なるほど、確かに悪い話じゃないかもしれない。
ちなみに、一人頭のひと月の生活費はアスラ銀貨二枚程度だとか。
『お前は、これから五年間、お嬢様の家に下宿して勉強を教えることになる。
五年間だ。その間、帰宅を禁じる。手紙などのやり取りも禁じる。お前がいると、シルフィが自立できないからだ。またシルフィだけでなく、お前も彼女に依存し始めているように感じたので、無理やり引き離させてもらった』
「なん……だと……?」
え、なに?
ちょ、ちょっとまって。
……え?
ナニソレ。五年間、シルフィと会えないってこと?
手紙も無しなの?
「なんだ、ルディちゃんは恋人と別れてきたのか?」
絶望的な顔をしていると、ギレーヌが愉快そうに聞いてきた。
「いいえ、大人気ない父親に叩きのめされてきたんですよ」
別れを告げる暇もなかったのだ。
やってくれたな、パウロォ……。
「そう落ち込むな、ルディちゃん」
「あの」
「なんだ?」
「やっぱり、ルーデウスって呼んでください」
「ああ、わかった」
けれど、冷静に考えればパウロの言うことももっともだ。
確かに、今のままシルフィが成長してしまったら、ヘタなエロゲに出てくる幼馴染キャラみたいになってしまったかもしれない。いつまでも主人公にべったりで、主人公を世界の中心として回っている衛星みたいな、自己の無いキャラ。
リアルな世界だと、学校で友達と付き合うなり、習い事をするなりしているうちに依存性は無くなっていくんだろうが、シルフィは髪のせいで友達ができない。
五年経っても、まだ俺にベッタリという可能性は大いにありえた。
俺としてはそれでも構わないのだが、周囲の大人はそうは思わなかったらしい。
そりゃそうか。いい判断だよ。
『報酬の件だが、お前には毎月アスラ銀貨二枚が支払われる。家庭教師の相場よりは安いが、子供の小遣いとしては多い。暇を見つけて、町中で金の使い方を覚えるように。金ってのは、普段から使っていかないと、いざという時にうまく使えないからな。もっとも、優秀な我が息子なら覚えなくともうまく使いそうだが……あ、間違っても女なんか買うなよ?』
だから余計な一言を書くなと。
それとも、これはあれか。ダ○ョウ倶楽部的なあれか?
絶対やるなよ、ってやつか?
『そして、五年間、投げ出すことなく見事にお嬢様に読み書き・算術・魔術を教えきった暁には、特別報酬として、魔法大学の学費二人分に相当する金額が支払われる契約になっている』
なるほど。
五年間、真面目に家庭教師をやれば、約束どおり好きにしていいってことか。
『まあ、五年後にシルフィがお前についていくとは限らんし、お前の熱も冷めて心変わりしているかもしれんがな。シルフィの方は、こっちでうまく言っておく』
うまくって……嫌な予感しかしないよ、パパン。
『五年間、まったく新しい場所で色々なことを学び、さらなる飛躍を遂げることを祈っている。知性溢れる偉大すぎる父親パウロより』
なにが知性だ……!!
力ずくだったじゃねえか!!
が、今回の判断には脱帽せざるをえない。
俺のためにも、シルフィのためにも。
シルフィは一人ぼっちになるかもしれないが、自分の問題は自分の力で解決しなければ、いつまで経っても成長できない。
俺に甘えていてはダメなのだ。
「パウロはお前のことを愛しているな」
ギレーヌの言葉に、俺は苦笑した。
「昔はもっと余所余所しかったんですけどね。自分に似てる部分があるとわかったら、ぐいぐいくるようになりましたね。でも、ギレーヌだって……」
「ん? あたしがどうかしたのか?」
俺は最後の一文を読む。
『追伸 お嬢様には合意の上なら手を出してもいいが、筋肉ダルマは俺の女だから手を出すな』
「ですって」
「ふむ。その手紙はゼニスに送っておけ」
「了解」
こうして、俺はフィットア領最大の都市、城塞都市ロアへと赴くこととなった。
思うところはたくさんあったが、今はこれでよし。ちょっとだけ目が覚めた。うん。これでよかったんだ。シルフィと一緒にいてはいけない。決して未練はないぞ。うん。
そう、自分に言い聞かせて。
(でも一年に一回ぐらいは会いたいなぁ……)
ちょっと心が揺れながら。
★ パウロ視点 ★
「あ、あっぶねぇ……」
気絶した我が子と、泥で汚れた靴を見下ろす。
今日で剣術を教えるのは最後だし、ちょっと本気出して怖がらせて父親の威厳ってヤツを見せつけてから気絶させようと思ったら、すっげぇ反応速度で魔術を使いやがった。
それも攻撃としてではなく、足を止めるための魔術を中心に、だ。
しかも、全部違う魔術だった。
「さすが俺の息子だな。戦いのセンスがある」
時間にしてみれば一瞬だったが、完全な奇襲であったにもかかわらず、三歩も使った。
特に最後の一歩は、少しでも躊躇すれば、足を取られて、一気にやられただろう。
魔術師相手に三歩だ。他に仲間がいれば、二歩目ぐらいで援護が入っただろう。あるいはもうちょっと距離があれば、四歩目が必要になっていた。
内容的には完璧に負けていた。
今のままどこかのパーティに放り込んで迷宮の探索をさせても、こいつは魔術師としてこの上ないぐらい役に立つだろう。
「さすが水聖級魔術師の自信を喪失させた天才か……」
我が子ながら末恐ろしい。
だが、嬉しい。
今までは、自分より才能があるヤツには嫉妬しかしなかったが、不思議と自分の息子だと、嬉しい気持ちしか湧いてこない。
「っと、こんなこと言ってる場合じゃないな。早くしないとロールズたちが来てしまう」
手早く気絶している息子を縄で縛り、縛り終えた頃にきた馬車へと放り込む。
タイミングよく、ロールズも来ていた。
シルフィも一緒である。
「ルディ!?」
シルフィは縛られたルーデウスを見て助けようとでもしたのか、いきなり中級の攻撃魔術を無詠唱でぶっぱなしてきた。難なく受け流したが、無詠唱な上に、威力も速度も申し分ない魔術だった。
オレじゃなければ死ぬところだ。
ルーデウスめ、なんてもんを教えてやがるんだ。
ギレーヌに手紙を渡し、ルーデウスを馬車に放り込み、御者に出るように伝える。
チラリと見れば、ロールズがしゃがみこんで、シルフィに何かを教えている。そうそう。教育は親の役目だ。ルーデウスにまかせていた分は、自分で取り戻さないとな。ロールズ。
ほっと息を吐いて、温かい目で見守っていてやると、しばらくして風に乗ってシルフィの声が聞こえてきた。
「わかった。ルディを助けられるぐらい強くなる……!!」
んー、愛されてるね。我が息子は。
それを見ていると、家の中から二人の妻が出てきた。
危ないので見ているなら家の中から、と言ってあったのだが、見送りに来たのだろう。
「あぁ、私の可愛いルディが行ってしまう」
「奥様。これも試練でございます!!」
「わかっているわ、リーリャ。ああ、ああぁルーデウス!! 旅立つ息子!! そして一人息子を奪われて可哀想な私!!」
「奥様。もう一人息子じゃありません」
「そうだったわね。妹が二人生まれたわね」
「二人……!! お、奥様!!」
「いいのよリーリャ。私はあなたの子供でも愛してみせるわ!! だって、私は、あなたを、愛しているのだもの!!」
「ああ!! 奥様わたくしもです!!」
やたらと芝居がかった口調で馬車を見送る。
ルーデウスは優秀だからか、この二人もそんなには心配していない。
それにしてもこの二人、仲がいいなー。オレとも仲良くしてくれると嬉しいんだけどなー。
てか、仲良くオレをイジメるのをやめてくれると嬉しいんだけどなー。
「しかし、下の子たちが物心ついた時には、ルーデウスはいないのか……」
ルーデウスも、カッコイイお兄ちゃん計画とやらを目論んでいたようだが、残念なことだ。
可愛い娘の愛情は、父親が独占することとなるのだ。
ぐへへ。
や、でも待てよ。これからルーデウスはあの剣王ギレーヌから英才教育を受ける。
五年後というと、十二歳。身体はもう立派だ。
帰ってきた時に魔術ありの模擬戦とかやったら、俺ってルーデウスに勝てないんじゃないか?
ヤバイ、五年後の父親の威厳がヤバイ。
「母さん、リーリャ。ルディもいなくなったことだし、俺も少し鍛えることにするよ」
ゼニスのシラッとした顔。リーリャがひそひそとゼニスに耳打ちする。
「ルーデウス様に負けそうになって、いまさら危機感を覚えたんですよ」
「昔からそうなのよ。負けそうにならないと努力しないの」
時すでに父親の威厳がヤバかった。
(まぁ、威厳なんてなくてもいいんだけどな)
無駄に威厳ばっかりあった父親に心当たりがあるだけに、心からそう思う。オレは、もう少し女にだらしないダメオヤジのフリをするのだ。威厳なんてない、親しみのある父親を目指すのだ。せめて、三人の子供が大人になるまでは……。
チラリとゼニスを見る。
子供を二人も産んだとは思えない、いい身体だ……。
(まぁ、四人目、五人目ができたら延長するけどな。うひひ)
ま、四人目の話はさておき。
(ルーデウス……)
こんなやり方は、オレだって好きじゃない。
けど、お前は言っても聞かないだろうし、オレも言って聞かせられる自信はない。
かといって、何もせずに見ているのも親として失格だ。力不足で他力本願だが、こういうことをさせてもらった。強引かもしれないが、賢いお前ならわかってくれるだろう……。
いや、わかってくれなくてもいい。
お前の行く先で起こる出来事は、きっとこの村では味わえないものだ。わからずとも、目の前の物事に対処していけば、きっとお前の力になる。
だから恨め。
オレを恨み、オレに逆らえなかった自分の無力さを呪え。
オレだって父親に抑えつけられて育ってきたんだ。
それを跳ねのけられなくて、飛び出した。
そのことには後悔もある、反省もある。お前に同じ思いはさせたくない。
けどな、オレは飛び出したことで力を手に入れたぞ。
父親に勝てる力かどうかはわからないが、欲しい女を手に入れて、守りたいものを守って、幼い息子を抑えつけられるぐらいの力はな。
反発したけりゃするといい。
そして力を付けて戻ってこい。
せめて父親の横暴に負けない程度の力をな。
ルーデウスの乗った馬車を見ながら、パウロはそんなことを考えていた。
(次巻へ続く)
番外編 「グレイラット家の母親」
私の名前はゼニス・グレイラット。
出身はミリス神聖国。長い歴史を持つ国で、清廉という言葉の似合う美しくも堅苦しい国だ。
私はそんな国で伯爵家の次女として生を受けた。
いわゆる良家のお嬢様である。
当時の私は箱入り娘だった。自分の見える範囲が世界の全てだと思っているような、世間知らずだった。
とはいえ、自分で言うのも何だが、いい子だったと思う。
両親の言うことには逆らわなかったし、学校での成績も良かった。
ミリス教の教えもしっかり守っていて、社交界での覚えも良かった。
一部では『ミリス令嬢の鑑』とまで言われているほどである。
両親にも、自慢の娘と思われていただろう。
あのまま育てば、いずれどこかのパーティで、両親の決めた相手と引き合わされたはずだ。
それはきっと、どこかの侯爵あたりの長男。品行方正だがプライドが高く、ミリス教の教えを絶対とする、ミリス貴族のお手本のような人物だ。そんな相手と結婚し、子供を産んで、どこに出しても恥ずかしくない侯爵夫人として、ミリス神聖国の貴族名簿に記される──。
それが、私の人生、ミリス貴族令嬢としての『道』だった。
しかし私がその『道』を歩くことはなかった。
成人した日、十五歳の誕生日。
私は両親と喧嘩をした。生まれて初めて親に逆らって、家を飛び出した。
両親の言いつけを守り続けることに嫌気が差していたのもある。
妹であるテレーズが私よりもずっと奔放で、それを羨ましく思っていたのもある。
様々な要因が、私を『道』からはずれさせた。
貴族が『道』をはずれて生きていくのは大変である。
だが、幸いなことに、私は貴族学校で治癒魔術を習っていた。しかも中級まで。
ミリス神聖国は治療魔術や結界魔術の盛んな国だが、それでも大抵の人は初級までしか治療魔術を習得しない。治療魔術の中級を習得していると、ミリス教団の経営する治療院への就職も可能となるため、学校では特別視されていた。
ゆえに私は、自分は優秀だ、どこででもやっていけると自惚れていた。
浅はかだった。
宿の取り方すら知らない私は、すぐに悪い奴らに目をつけられた。
彼らは「治療魔術師を募集しているんだ」と言って、お金の相場も何も知らない私を自分のパーティに引き入れた。提示された報酬は初級の治療魔術師に支払われるものより、ずっと低いものであったが、彼らはそれを相場より高いと言い張った。
正当な報酬を与えず、格安の回復役として使おうとしたのだ。
バカな私は、表面上は親切な彼らを見て、世の中にはいい人がいると思ったものだ。
もしあのまま彼らについていけば、もっと酷いことをされていただろう。魔物の盾にされたり、気絶するまで魔術を使わされたり、もしかすると体を要求されたかもしれない。
それを未然に防いだのは、パウロ・グレイラットという青年剣士だった。
パウロは悪い奴らを叩きのめすと、私を強引に自分の旅のパーティに連れ込んだ。
彼と同じパーティにいたエリナリーゼという人物が詳しく説明してくれなければ、私はパウロこそが悪漢だと思っただろう。
ともあれ、こうして私はパウロと出会った。
当初、私はパウロのことが嫌いだった。
元アスラ貴族というわりに言葉遣いは悪いし、約束は破るし、直情的だし、お金に汚いし、人のことを馬鹿にするし、すぐにお尻を触ってくるし、それどころか下心丸見えな態度で迫ってくることもあった。
でも、悪い人じゃないのはわかった。
彼はいつだって私を助けてくれた。
世間知らずな私を馬鹿にしつつも、しょうがねえなあと言いながら手を貸してくれた。
パウロは私と正反対だったが、頼もしくて、奔放で、そしてかっこよかった。
私が彼に惹かれたのは、それほどおかしなことではないだろう。
もっとも、彼の周りには魅力的な女性が大勢いて、そして私はミリス教徒だった。
ミリス教の教えには『男女は互いに一人だけを愛せよ』というものがある。
家を飛び出した私だが、しかし幼い頃から繰り返し聞かされ、学校でも常識とされていたミリスの教えは、しっかりと底に根付いていた。
だからあくる日、私は言った。
「他の女性に手を出さないなら、抱いてもいいわ」と。
彼は笑いながら、それを了承した。
嘘を吐かれている自覚はあった。
けれども、それでいいかという思いもあった。
騙されるなら、愛想を尽かすこともできる、と。
この時の私も、やはり浅はかで、迂闊で、愚かだった。
なにせ、その一度で子供ができてしまったのだから。
どうしようという思いがあった。不安で一杯だった。
まさか、パウロが責任を取って結婚してくれるなど思ってもみなかったのだ。
そうして生まれた子供が、ルーデウス・グレイラット。
──ルディである。
★ ★ ★
ルディは現在、自分の妹が眠る揺りかごの脇に座っている。
その表情は真剣そのものである。
パウロの面影を持つ丹精な顔をキリリと引き締めて、二人の妹を交互に見ている。
「あー、あー!」
ノルンがぐずった瞬間、ルディの表情がさらに引き締められる。
しかし、次の瞬間。
「ベロベロバー」
ルディは舌を出して変な顔をした。
「キャッ、キャ、バー、バー!」
それを見たノルンが嬉しそうに笑った。
ルディはノルンの笑みを見て満足気に頷くと、また真面目な表情に戻る。
「うー、あー!」
今度はアイシャがぐずる。
するとルディは即座にそっちを向いて。
「あっちょんぶりけ」
と、頬に手を当てて変な顔をした。
「うきゃー、あちょあー」
すると、アイシャもまた嬉しそうに笑う。
ルディはノルンの時と同じように、会心の笑みで頷く。
先ほどから、ルディはそんなことをずっと繰り返している。
「うふふ……」
ルディの笑みを見て、私の口からも小さな笑い声が漏れた。
なにせ、ルディは滅多に笑わない。
何かに満足がいくということがないようで、剣術を習う時も魔術を習う時も、いつだって真剣な表情で何かをしている。
親にすら、笑い顔を見せてくれることはない。
見せてくれたとしても、変な作り笑顔を向けてくるだけだ。
そんな彼が、妹にあんな顔をして笑うのを見て、満足げな顔で笑っている。
それを見ているだけで、なんだか楽しい気分になってくる。
昔とは大違いだ。
「ふぅ……」
ルディの小さな頃を思い出して、私はため息をついた。
かつてルディに魔術の才能があるとわかって狂喜乱舞した私だが、しばらくして、実はルディは心の底では両親を見下していて、家族に対する愛情を持っていないのかもしれない、なんて疑惑を持つようになった。
なにせ、ルディは私に懐かなかったから。
「……でも、そうじゃなかったのよね」
そんな私の思いが変わったのは、例の妊娠騒動の時だ。
リーリャが妊娠して、パウロが白状した。
その時、私は裏切られたと思った。
パウロにも、そしてリーリャにも。
特にパウロには約束を破られたということで、爆発寸前になるほどの怒りが湧いた。少しでも気を抜けば、リーリャに出ていけと叫ぶか、自分が出ていくと叫ぶか、どちらかになりかねなかった。
嘘を吐かれたら愛想をつかそう、と結婚前に思っていたのもある。
あんなことが起こるまで忘れかけていた考えだが、根の部分には残っていたらしい。
私の気持ちは、すでに一家離散を考えるまで追い込まれていた。
しかし、そんな気持ちはルディによって霧散した。
彼は子供のような態度を取って、うまく場を収めようとしたのだ。
やり方はあまりよくなかった。
ルディの言い分でも、私はパウロを許せなかった。
けれど、私はルディの言葉と表情から、その奥にある本心を感じ取った。
『家族関係が壊れることへの不安』
それに気づいた瞬間、思ったのだ。
ああ、この子もこの子なりに家族を大事に思っているのだな、と。
そんな気持ちになった瞬間、彼が家族への愛情を持っていないという疑惑は晴れた。
同時に子供を不安にさせちゃいけないという思いも湧いてきて、怒りがスっと引いた。
そして、パウロもリーリャも、すんなりと許せてしまった。
ルディがいなければ、こうはならなかっただろう。
「んー、ノルンちゃんは可愛いでちゅねー、将来はママに似た美人さんになりまちゅねー。そしたら一緒にお風呂とか入りまちょうねー」
そのルディは、ノルンの小さな手を握ってあやしている。
普段はあんなに真面目な顔をしているルディが、赤ちゃん言葉まで使って妹のご機嫌を取っている姿は、なんというか──。
(頼もしい……)
前々からルディのことは凄いと思っていたが、最近は頼もしさまで感じる。
ノルンとアイシャが生まれた時は本当に大変だった。
二人の娘は夜にもお構いなしに泣くし、母乳をあげたらゲロを吐くし、体を洗っている最中にお湯の中にウンチもする。
リーリャはコレが当然です、普通ですと言っていたけれど、私は夜も眠れずぐったりとしてしまった。
そこにルディがきて、任せてくださいとばかりに色々やってくれた。
その手際は熟練を思わせた。
まるで以前にやったことがあるかのようだった。
まさか、自分がやってもらった時のことを覚えているわけもないだろうから、リーリャがやっているのを見て覚えたのだろう。
さすがはルディといったところか。
親よりも子供のあやし方が上手なことに少し思うところはあるが、実に助かっている。
ルディぐらい頼もしくて、生まれたばかりの妹を世話できる子供を、私は知らない。
ルディを見ていると、私はミリス神聖国にいるであろう実兄のことを思い出す。ルディに似て真面目で勤勉で、才能もある人で、父からは貴族の鑑のような男だと言われていたが、しかし家族に対しては冷たい人で、妹を空気のように扱っていた。
貴族としては立派な人だと思ってはいるが、兄としては尊敬していない。
でも、ルディならそんなことはないだろう。
妹にも尊敬される、良い兄になるに違いない。
実際、本人もそのつもりのようで、パウロと二人で並んでノルンとアイシャを見ながら、「僕は尊敬されるカッコイイお兄ちゃんを目指します」などと宣言していた。
将来、ルディとノルンたちがどんな風になるのか、今から楽しみで仕方がない。
「アー! アギャー!」
などと考えていると、ノルンが大声で泣き始めた。
ルディはビクンと体を震わせると、ノルンに向かってベロベロバーと変な顔をする。
「ギャー! オギャー!」
しかしノルンは泣き止まない。
ルディは、オムツを触ってお漏らしをしていないかを確認したり、抱っこしてみたり、背中がかぶれていないか確認したりしてみたが、一向に泣き止まない。
私ならきっと慌ててしまい、リーリャを大声で呼んだだろう。そして、リーリャが買い出しに出ていることを思い出し、パニックに陥ったかもしれない。
けれどルディは慌てなかった。
一つ一つ原因を探っていき、やがてポンと手を打ってこちらを向いた。
「母様、どうやらお乳の時間のようです」
言われて見ると、もうそんな時間か。
妹たちと戯れるルディを見ていると、あっという間に時間が経ってしまう。
「はいはい」
「どうぞ、こちらです」
私はルディに言われるがまま、椅子に座る。
胸元をはだけさせて、泣き喚くノルンを抱き上げる。
ルディの予想どおりお腹が空いていたようで、ノルンはすぐに乳首を口に含み、おいしそうに母乳を飲み始めた。
こうしている時、自分が母になったのだという実感が強く湧いてくる。
「……ん?」
ふと、ルディの視線に気がつく。
ルディは私がお乳をあげようとすると、胸のあたりをじっと見てくる。
それはとても物欲しそうでエッチな目線で、七歳の子供とは思えないものだ。
パウロと並んでいると、まったく同じ目をするので親子なのだなと微笑ましい気分になるのだが、この歳からこれでは、将来が少し不安になる。パウロのように色んな女の子に手を出して泣かせてしまうのではないだろうか、と。
「なぁにルディ。あなたも欲しいの?」
「えっ!」
からかい交じりに聞いてみると、ルディはハッとした表情で目線をそらした。
そして、顔を赤くしつつ、言い訳をするように言った。
「いえ別に。ただ、よく飲むなと思って見ていただけです」
「うふふ」
その可愛らしい態度に、思わず笑い声が出てしまう。
「だめよ、これはノルンのだから。ルディはもっと小さい頃にたーくさん飲んだんだから、我慢なさい」
「……もちろんです、母様」
もちろんだと言う割には、ルディは少し残念そうな顔をしていた。
こういうルディはレアだ。むしょうに愛おしさが湧き上がってくる。
もっとからかってみよう。
「んー、どうしてもって言うなら、ルディにお嫁さんができた時に、お願いって頼んでみたらいいかもしれないわね」
「そうですね。その時は頼んでみます」
あら。てっきりムキになって言い返してくるかと思ったけど、悟ったような顔で流されてしまった。
からかわれているのに気づいたのだろうか。
ちょっとつまらないけど、ルディらしいとも言える。
「……無理強いしちゃだめよ?」
「わかっています」
こういう大人びたところを見ると、やっぱり少し寂しく思う。
「ケプッ」
食事の終わったノルンにゲップをさせ、揺りかごへと戻す。
濡れた乳首を布で拭いていると、またルディが乳首をじっと見つめてきた。
うーん。これは、この子のお嫁さんになる子は大変そうだ。
今のところ有力候補はシルフィちゃんだけど、あの子はルディの言いなりなところがあるから、自分が嫌なことでも強くは言えなさそうだし……。
よし。
もしその時が来たら、私がルディに対してガツンと言ってやらなくっちゃね。
母親として。
パウロは女の子を落とすことばっかり教えるだろうから、私はその後のことを教えるのだ。
「うむゅ……」
お腹が一杯になったノルンは満足そうな顔をしていたが、すぐにうとうととし始めた。
おネムの時間のようだ。
「たくさん飲んで、たくさん寝て、元気に育ってね」
ノルンの頭を撫でながらそう言うと、その時である。
「アー! アー!」
アイシャがやや控えめながらも、グズりだしたのだ。
ルディはすぐに私の胸から目線をはずすと、アイシャに向き直った。
「あーい、どうちまちたか、アイシャたーん。お背中かゆいかゆいでちゅかー?」
ルディは先ほどノルンにしたように、抱っこをしたり、オムツの様子を確かめたり、汗疹や虫刺されがないかを確認して……。
最後に、アイシャを抱いたまま、困った顔でこちらを見た。
珍しい、ルディがこんな顔をするなんて。
ルディの色んな表情が見れるのは嬉しいのだけれど、あまり曇った顔は見たくない。
「どうしたの?」
「あの、母様。今日はリーリャさん。帰ってくるの遅いですね」
「そういえばそうね」
いつもなら、買い出しに出たらこの時間には戻ってくるはずだ。
何かあったのだろうか。
……いや、確か今日は城塞都市ロアの方から商隊が来るという話だ。そこでいつもより多めに買い込む予定だと言っていたから、少し時間が掛かっているのかもしれない。
「その、アイシャなんですけど」
「うん」
「お腹が、空いてるみたいです」
「そうなの」
考えてみれば、ノルンと同じ時間にお乳を上げたのだから、アイシャだって同じ時間にお腹を空かせるだろう。
いつもは私がノルンに、リーリャがアイシャにそれぞれお乳を与えているが……。
と、そこで私はルディの困った顔に気づいた。
ルディはその表情のまま、おずおずと言った。
言葉を選びながら。
「えっと、その。母様。リーリャはいつ帰ってくるかわかりませんし、その、少しぐらいならアイシャに我慢してもらってもいいんでしょうが、アイシャをこのまま泣かせていたら、ノルンの方も泣いてしまうでしょうし、えっと……」
私は敬虔なミリス教徒だ。
ゆえに、いまだに一夫一妻の掟を破ったパウロやリーリャに思うところはある。彼らがミリス教徒でないのは知っているが、やはり自分の考えを曲げられるというのはちょっと嫌である。
そのことを、ルディは敏感に感じ取っているのだろう。
自分の一言で母親が不機嫌になったりしないか。
もう一人の妹をどうかしたりしないか。
そんな不安があるのだろう。
ルディにとっては、ノルンもアイシャも、そして私も、みんな家族なのだ。
そして……こうなった以上、私もそうあるべきなのだ。
しかし、本当に大丈夫だろうか。
アイシャにお乳をあげて、不快な気分になったりしないだろうか。
そして、それをルディに見られて、嫌われたり、軽蔑されたりはしないだろうか。
「んもう、ルディったら何を言ってるの。ほら、はやくアイシャを渡しなさい」
私は不安をかき消すように、できる限り優しい声でルディに呼びかけた。
「はい」
ルディはおずおずといった感じで、アイシャを私に渡してきた。
私はアイシャを抱くと、先ほどと反対側の乳房を露出させてアイシャに吸わせた。
もしここで、アイシャが嫌がったら私もムッとしたかもしれないが、アイシャは遠慮なく乳首に吸い付いて、コクコクと飲み始めた。
「……ほっ」
私はルディに聞こえないように、安堵の息を吐いた。
胸の内に湧き上がったのは、ノルンに母乳を与えた時と同じような感覚。
すなわち、母としての実感だ。
不思議だ。
なぜ、私はアイシャに乳をあげることを少しでも嫌だと思ったのだろうか。
アイシャに乳を吸われている時、なぜ不快になると思ったのだろうか。
我慢しなければ、と思ったのだろうか。
もっとも、答えは簡単だ。私だってわかっている。
私が母親だからだ。
結局。変わらないのだ。ミリス教徒だろうと何だろうと。
「美味しそうに飲んでるわね」
「えっと、母様のは美味しいですから」
「そういうお世辞はいらないの」
ルディは美味しそうにお乳を飲むアイシャを、そしてそれを嫌がらない私を、ホッとした顔で見ていた。
妹を守るのも、お兄ちゃんの仕事だと思っているのだろうか。
いい心掛けだ。
妹に尊敬されるお兄ちゃんになるという決意に、嘘偽りはないのだろう。
もっとも、アイシャを害するのが私だと思われているところは心外であるが。
「お世辞なんかじゃありません。ちゃんと味を覚えています」
「本当かしら」
くすくすと笑いながら、アイシャの頭を撫でてあげる。
しばらくすると、アイシャもお腹が一杯になったのか、乳首から口を離した。
そして、ノルンと同じように、ウトウトとし始めたので、揺りかごに戻してやる。
ルディは普段より優しそうな目で、私とアイシャを見ていた。
「ねぇ、ルディ」
「はい、なんでしょうか」
「撫でてもいいかしら?」
「……許可なんて必要ありませんよ。好きな時に撫でてください」
ルディはゆっくりと私の隣に座り、頭を差し出した。
私はさらりとそれを撫でる。
ルディは初産だったし手の掛からない子だったから、育てていてもあまり母親としての実感が湧かなかったけれど、最近は違う。
自分はこの子の母親なのだと、心の底から感じる。
「……」
ふと熱を感じてそちらを向く。
うららかな春の日差しが窓から差し込んでいた。
窓の外には、金色の麦畑がどこまでも広がっている。
穏やかな、春の午後。
静かで、満ち足りた気分。
なんだか、とっても幸せだ。
「こういう時間が、ずっと続けばいいわね」
「そうですね」
私の言葉に、ルディが頷いた。
ルディもまた、この空間を心地よいと感じてくれているのだろう。
でも、私が幸せだと感じられるのは、きっとルディのおかげだ。
もしルディがいなければ、敬虔なミリス教徒である私が、二人の妻のうちの一人という存在になってしまったら、自分の不幸を嘆いてノルンを連れて旅に出るか、アイシャとリーリャに辛く当たってしまったかもしれない。
ルディがいてくれてよかった。
彼が賢くて聡い子じゃなかったら、きっと今のこの気分は味わえなかっただろうから。
「ルディ」
「なんですか?」
「生まれてくれてありがとう」
ルディは面食らった顔をしていた。
そして、ポリポリと頭を掻いて、恥ずかしそうに言った。
「こちらこそ、ありがとうございます」
そんな可愛らしいルディの仕草を見て、私はまたクスクスと笑うのだった。
作者闲话
『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ XX』
理不尽な孫の手先生 こぼれ話
書籍版からの方ははじめまして。
WEB版のほうから読んでいただいている方は、いつもありがとうございます。
理不尽な孫の手です。
このコーナーは作品のこぼれ話という事だそうです。
こぼれ話。
というわけで、無職転生の『誕生秘話』について書いていこうと思います。
・プロトタイプ
無職転生にはプロトタイプがあります。
その構想を考えたのは約7年前。
私がまだ血気盛んなワナビ(ライトノベル作家になりたい人たちの総称)であり、プロになるという事に情熱を燃やしていた時のことです。
当時の構想メモによると、無職転生の原型は「魔術師の主人公が様々な仲間と冒険や恋をしたりする話」でした。
よくあるファンタジー系の学園ものですね。
ただ、当時の私はワナビらしく、周囲に迎合しない気高くも無意味なプライドを持っていました。
周囲に迎合したくない、似たような作品は書きたくない。
という思いもあり、この作品が書かれる事はありませんでした。
このまま行けば、ハードディスクの片隅に埋もれ、パソコンの買い替えと共に記憶の彼方へと消えてしまった事でしょう。
でも、そんな構想がある日、日の目を見ることになります。
きっかけは、『小説家になろう』というサイトです。
そのサイトとめぐり合った時、ワナビとしての私は死んでいました。
書いても書いても上達せず、応募をしても一次選考すら通らない。
すでに新作を書いて新人賞に応募する気力は無く、筆を折り、もう小説なんか書かねえぞと決意して、二年ほど経過した頃です。
当時、私はWEB小説というものを馬鹿にしていました。
文章を書き始めたばかりの中高生が的ハズレな指摘をしあう、プロのステージからは数段下にあるもの。
そんな事を思っていたのです。
そんな私でしたが、小説家になろうというサイトで作品を読み、驚きました。
文章力の有無にかかわらず、実に楽しそうに小説を書いているのです。
また「文章力の高い人の書いた作品が、必ずしも高評価を得ているわけではない」という所にも感銘を受けました。
内容にしても、異世界転生や、異世界トリップといった、言ってみれば一般人から馬鹿にされそうな類のものです。
しかし私はそういったジャンルが好きでした。
でも、ワナビ時代にはこんなのは時代遅れだし、売れないから書かない方がいい、と思っていました。
書くのを恥ずかしいとさえ思っていたように思います。
そんなジャンルをこのサイトでは書いてもいいのだと思った時、私の中で変遷が起こりました。
今まで自分の中で、小説を執筆する際にこだわっていた部分を捨てることを決意しました。
『誰も見たことの無いアイデアを重視する』とか、
『パロディは絶対に許さない』とか、
『テンプレは害悪だ』とか、
『安易なエロは滅せよ』とか、
『人気作品の真似をする風潮がウザイ』とか、
そうしたものを捨てて、新たに物語を書こうと思った時に目に付いた構想が、無職転生のプロトタイプでした。
・無職転生の誕生へ
小説家になろうの作品に感化された私は、プロトタイプの無職転生(以下、プロト無職)をもとに小説を書き始めました。
でも、
『パロディを多めに盛り込む』
『テンプレもどんどん使っていく』
『エロい展開も多く』
と、それらのことをプロト無職の構想で使うことは困難でした。
そこで主人公に一味加えることにしました。
まず、主人公をエロい事が大好きなオタクの中年男性にする。
そうする事で、自然にエロ展開にもっていき、さらにパロディも多用することができる。
彼はオタクであり、あらゆるテンプレを知り尽くしています。
そんな彼が、「テンプレ展開をテンプレ展開だと理解しつつ解決する」。
メタ的な観点を作品に盛り込んだわけです。
ただ、それだけでは、何も面白くありません。
テンプレを綺麗に解決する、それだけの話になってしまいます。
そこで、ひと味加えました。
物語は彼の思い通りに進みます。
しかし、解決した先には人との出会いがあり、触れあいがあり、彼の思っていたのとは少し違う展開になるのです。
そうした展開の中で、彼は前世の事を思い出したり、反省したりしながら、変化していく。
そういった構造を思いつきました。
おお、これは書いている自分も面白くなりそうだ!
と、思ってできたのが、無職転生となります。
あくまで趣味として書こう。
楽しんで書こう。
書きたいものを書こう。
そうして書かれた作品がWEBで人気となり、書籍化まで果たすに至りました。
私はそのことを、純粋にうれしく思っています。
文库版 无职转生~到了异世界就拿出真本事~